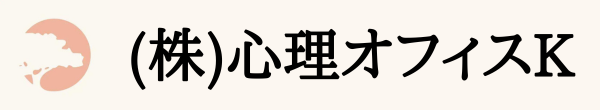(株)心理オフィスKについて
(株)心理オフィスKは横浜のカウンセリング専門機関です。対人関係、家族関係、トラウマからの回復、職場のストレス、発達の課題、心の病、人生の振り返りなど、心理的な問題について解決のお手伝いをしています。
幅広い方々のお役に立てるように、そして、多様な相談内容に対応できるように、多数のカウンセラーが在籍しています。また、仕事があっても来ていただけるように、平日は夜22時まで、土日祝も開室しています。さらに、遠方の方でも相談できるようにオンラインカウンセリングも行っています。
(株)心理オフィスKの7つの特徴
- 秘密厳守
- 夜22時まで開室
- 土日祝日も開室
- 初回の面接料が半額
- キャッシュレス決済可
- 経験豊富な多数のカウンセラーが在籍
- 対面だけではなく、オンラインでの相談も可能
(株)心理オフィスKでできること
個人向けサービス
当オフィスではクライエント様のお役に立てるようなサービスを目指しております。また、いつでも気軽にお越しいただけるように、夜は22時まで、土日祝日も開室しています。
関連コラム
この他にも関連したコラムを公開しています。
心理職・対人援助職向けサービス
心理職・対人援助職として、人の心理や感情に向き合っていると、多くの場合には苦悩し、時には疲弊してしまいます。また、心理職・対人援助職自身の問題が浮き彫りになることもあります。そうした中で、より良い援助者になるための訓練を(株)心理オフィスKでは提供しています。
関連コラム
この他にも関連したコラムを公開しています。
企業向けサービス
昨今では社員のメンタルヘルスを維持・向上させることは単に福利厚生ではない、と言われています。メンタルヘルスの維持・向上はパフォーマンスの直結する非常に重要な要因です。同様に労働環境を整えることにより、企業の総合的な利益に寄与します。心理学的な知見を通して、そうしたお手伝いをすることができます。
関連コラム
この他にも関連したコラムを公開しています。
お知らせ
- オンラインセミナー「心理検査の所見を作成するための思考プロセス」の募集を開始(2024-04-17)
- 心理職・対人援助職向けセミナーの申し込み方法を変更しました。お申し込みは各セミナーの個別のページか一覧ページからお申し込み・お支払いください(2024-03-20)
- オンラインセミナー「トーマス・オグデンの精神分析理論と臨床実践」の募集を開始(2024-03-08)
- 「見捨てられ不安を解消!臨床心理士が明かす安心の秘訣」の記事を掲載(2024-03-08)
- 「セックスレスからの脱出!臨床心理の視点から見るその心理と改善法」の記事を掲載(2024-03-07)
カウンセリングや心理検査の前の心配事などもお気軽にご相談ください