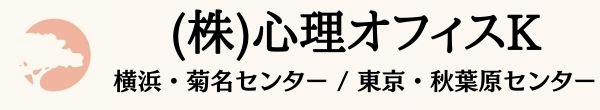ハラスメントに対する対策と相談

「上司からの理不尽な指示に苦しんでいる」「性的な差別や嫌がらせを受けてつらい…」。このような嫌がらせはハラスメントと言い、近年では多くのハラスメントが存在します。
本記事では、ハラスメントの概要や対処について解説します。
目次
ハラスメントとは

ハラスメント(Harassment)とは、他者に対する嫌がらせやいじめを指す言動の総称です。自らに「嫌がらせをしている」という自覚がなくても、他者が肉体的・精神的に苦痛を感じるのであればハラスメントに該当するといえます。
国内では1989年に上司からの女性に対する言動がセクハラであるとして初めて民事裁判が行われ、「セクシャルハラスメント(以下セクハラ)」という言葉が広まりました。また、セクハラの考えを受けて、2001年には「パワーハラスメント(以下パワハラ)」という言葉が広まっています。
厚生労働省によると、セクハラとは職場で相手の意に反する性的な言動があり、それを拒むことで解雇などの不利益を被ったり、職場環境が不快になって仕事に支障が生じたりすることを指します。また、パワハラは職場での優位関係をもとにした過剰な言動であり、労働者の心身が害され就労に支障が生じることを指します。客観的に見て必要かつ適切な指示・指導であればパワハラには該当しません。
ハラスメントは、行う側の意図はあまり重要ではありません。他者の尊厳を傷つけ、苦痛を与えてしまう言動はハラスメントとみなされるでしょう。その内容によって、加害者側は法的な責任を問われる場合もあり得ます。
ハラスメントの種類

相手の意に反する性的な嫌がらせで苦痛を与えるセクハラや、職場での優位性や権力をもって他者に精神的な嫌がらせをするパワハラのほか、時代背景や文化の変化に伴い、ハラスメントの種類は増え続けています。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| マタニティハラスメント | 妊婦に対する嫌がらせ |
| パタニティハラスメント | 職場で男性労働者が育休などで受ける嫌がらせ |
| カスタマーハラスメント | 顧客から受ける嫌がらせ |
| モラルハラスメント | モラル(道徳)の欠ける態度や言動での嫌がらせ |
| アルコールハラスメント | 飲酒に関する嫌がらせ |
| ジェンダーハラスメント | 男らしさや女らしさなど背別の固定概念による嫌がらせ |
| スクールセクシャルハラスメント | 学校内での性的な嫌がらせ |
| アカデミックハラスメント | 大学などでの優位な力関係で起こる嫌がらせ |
| ソーシャルハラスメント | SNSへの悪質な書き込みや監視行為による嫌がらせ |
また、ハラスメントは主に職場で指摘されるものでしたが、現在では職場に限らず家庭や学校、インターネット上で指摘される機会も増加しています。ハラスメントという言葉が世間的に広まり意識が高まることで個々を尊重できる反面、何でもハラスメントに捉えてしまう生きにくさが生じていることが課題でしょう。
ハラスメントが起こる原因や要因

ここ数十年でハラスメントという言葉が広まってきた原因や要因として、社会の様々な変化が考えられます。アナログからデジタル社会への変化、雇用形態の多様化、共働きの増加など社会に変化が起きることで、集団内での人間関係の希薄化やこれまで問題でなかったことが浮彫りになってきました。また、インターネットの発達により顔を合わせず文面でのコミュニケーションが増加したことで、表情や声音などの非言語的コミュニケーションが不足し、冷たく誤解されることもあります。
その他、個々を尊重する風潮となり、それぞれの価値観や偏見が衝突することや、ストレス耐性の低下などもハラスメントが起こる一要因でしょう。
また、「男は働いて女は家事育児」など性的な役割分担の思想が根強い職場・集団では、セクハラやマタハラ・パタハラが起こりやすいと言えます。
コミュニケーションや価値観の押しつけを止めて個々を尊重する社会となりつつある一方で、「何がハラスメントになるか分からない」窮屈さもまた感じやすいかもしれません。ハラスメントを防止するためには変化を柔軟に受け入れ、自分と他者の違いを認め、価値観や個性などを押しつけてしまわないよう注意が必要でしょう。
ハラスメントによって引き起こされる症状

どのようなハラスメントであっても肉体的・精神的苦痛に晒され続けることで、過度のストレスから以下のような心身の症状が出現することがあります。
- 不眠
- 食欲減退
- 過食
- 頭痛や腹痛など身体の痛み
- 吐き気
- 発熱などの身体化
- 意欲低下
- イライラ
- 落ち込み
- 集中困難
- 自己嫌悪や自信の低下
- ハラスメント言動のフラッシュバック など
ハラスメントが長引くようであれば、急性ストレス障害、長期に及ぶ場合は心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病などを発症するリスクもあります。心身に症状が現れることで、行動面では以下のような問題も生じやすくなります。
- 仕事での生産性の低下
- ケアレスミスやトラブルの増加
- 登校・出勤への抵抗
- 欠席・欠勤の増加
- 離職 など
職場であれば、ハラスメントによって雰囲気の悪化や人材維持・確保の困難さも生じるでしょう。ハラスメントは受け手に症状が出現するだけでなく、集団に対してもリスクがあるといえます。
ハラスメントを受けたときの対策

パワハラなどのハラスメントを受けた場合、どんな対策をとればいいか分からずに我慢してしまう人も一定数います。そもそも「これは本当にハラスメントなのか?」と判断に困ることが多いでしょう。ハラスメントを受ける側は、状況や心身の状態を客観的に理解できずに「自分が悪かったかもしれない」「こういうものだ」と考えてしまうケースもあります。
まずは、自分がされた言動を振り返り、それによって自分が肉体的・精神的に傷ついたのかどうか気持ちに焦点を当ててみてください。ハラスメントを受けたと感じるのであれば、以下のような対策があります。
- 何をされたのか記録する
- 話せる人に相談する
- 部署異動や退職などでハラスメント対象から離れる
- カウンセリングを受ける
可能であれば自分が受けた言動を録音などで記録しておくと、第三者への説明が容易になるほか、ハラスメントを受けた証拠材料になることもあります。友人や同僚、上司など話せる人に相談することで、1人で抱え込む苦しさを緩和し、周囲からハラスメント防止のための協力が得られることもあります。ハラスメントにより仕事が手につかないなど生活に支障が出る場合、勇気をもって逃げる選択肢も有効です。また、著しい意欲低下や気分の落ち込みなどの精神症状に苦しむようであれば、医療機関に受診し必要に応じて薬物療法やカウンセリングを受ける対策もあります。
なお、2022年4月からは全企業でパワハラ防止措置が義務化されています。ハラスメントが生じないように集団で予防する必要もありますが、万が一ハラスメントを受けた場合は上記の対策を参考にしてみてください。
ハラスメントについてのよくある質問
ハラスメントとは、相手を不快にさせたり、精神的・身体的な苦痛を与える言動や行為のことです。職場、学校、家庭など、日常のさまざまな場所で発生する可能性があります。特に職場では、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、モラルハラスメントなどが問題視されています。これらの行為は、被害者に強いストレスや不安を引き起こし、働く意欲や人間関係に大きな影響を与えることがあります。ハラスメントは、加害者の意図に関係なく、受け手が不快に感じたり、不利益を受けた場合に成立するため、社会的に大きな問題となっています。
ハラスメントの種類にはいくつかのタイプがあります。まず、セクシャルハラスメントは、性的な言動や行動により、相手を不快にさせる行為です。これには、言葉やジェスチャー、身体的な接触が含まれる場合もあります。次に、パワーハラスメントは、上司や同僚など、職場内での地位や権限を使って、他者に対して精神的または身体的な圧力をかける行為です。モラルハラスメントは、言葉や態度で相手を否定的に評価し、精神的に追い詰める行為です。この他にも、マタニティハラスメントやパタニティハラスメント、時短ハラスメントなどが存在し、これらは特定の状況において不当な扱いを受けることを指します。
セクシャルハラスメントとは、性的な言動や行動が原因で、相手が不快に感じる状況を作り出すことです。例えば、意図的な性的なコメントや、不適切なジェスチャー、身体的接触などが該当します。これにより、職場や学び舎などでの安心して働く、学べる環境が害され、被害者にとって大きな精神的な負担となります。セクシャルハラスメントは、男性から女性へのものだけでなく、女性から男性へのものや、同性間のものも含まれます。ハラスメントを防ぐためには、職場内での適切な教育や対策が重要です。また、被害に遭った場合には、早期に対応し、専門機関に相談することが大切です。
パワーハラスメントとは、上司や先輩、同僚などが職場で自らの地位や権限を利用して、他者に対して不当な圧力や精神的、肉体的な苦痛を与える行為です。具体的には、過剰な仕事の割り当てや、仕事ができないことを理由に人格を攻撃するような言葉を使うことが挙げられます。また、業務外での個人的なことに関する指摘や不適切な扱いも含まれる場合があります。パワーハラスメントの特徴は、相手がそれを受け入れることができないほどの精神的または身体的なダメージを受けることです。職場環境を快適に保つためには、上司と部下の関係が平等で、互いにリスペクトする姿勢が大切です。
モラルハラスメントとは、他者に対して言葉や態度で精神的な圧力をかける行為を指します。これは直接的な身体的暴力ではなく、精神的な苦痛を引き起こすものです。例えば、過度な批判や侮辱、無視や仲間外れ、精神的に追い詰めるような発言などが該当します。モラルハラスメントは、受け手に自信をなくさせ、ストレスや不安を引き起こすため、長期的に見ても心身に大きな悪影響を与える可能性があります。このような行為が繰り返されることで、職場や学校などの環境が悪化し、パフォーマンスの低下や人間関係の崩壊を引き起こすことがあります。
マタニティハラスメントとは、女性社員が妊娠や出産、育児を理由に不当な扱いや嫌がらせを受けることを指します。例えば、妊娠や出産を理由に仕事を減らされる、休暇を取ることを強要される、出産後に職場復帰を妨げられるなどの行為が該当します。マタニティハラスメントは、女性が家庭と仕事を両立させる過程で障害となり、精神的な負担を大きくします。妊娠や出産は自然なライフイベントであり、それに対して不当な差別を受けることは許されません。企業は、社員が安心して働ける環境を整える必要があります。
パタニティハラスメントとは、男性社員が育児に関する権利を行使しようとした際に、それを妨害されたり、育児休業の取得を拒否される、またはそれに対する差別的な扱いを受けることを指します。具体的には、育児休業を取ろうとすると上司から不当な圧力をかけられたり、育児休業を取ったことで職場内で冷遇されたりするケースがあります。育児は男女問わず共同で行うべきものであり、男性が育児に参加することを積極的にサポートする文化が企業内で求められています。パタニティハラスメントを防ぐためには、企業側が育児に対する理解を深め、社員が平等に育児の権利を享受できるようにすることが大切です。
時短ハラスメントとは、育児や介護を理由に勤務時間を短縮したり、フレックスタイム制度を利用した社員が、不当な圧力や批判を受けることを指します。例えば、短時間勤務を選択した社員が、仕事ができていない、効率が悪いなどといった批判を受けたり、過度なプレッシャーをかけられることがあります。これは、社員が家庭の事情で必要な柔軟な働き方を求めた結果、職場での不平等や差別を受けることになり、ストレスや仕事へのモチベーション低下を招くことがあります。職場が多様な働き方を受け入れ、すべての社員が平等に評価される環境を作ることが重要です。
アカデミックハラスメントとは、学問の場で、教員や学生などが、立場を利用して他者に対して不当な扱いや精神的な苦痛を与える行為を指します。例えば、教授が学生に対して不当な要求をしたり、指導を強要したり、または研究を妨害するような行為が該当します。このような行為は、学問の自由や公正な評価を害し、学びの場としての信頼を損なうものです。アカデミックハラスメントが発生すると、学業や研究活動に対するモチベーションが低下し、学生や教員の精神的な健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。
ハラスメントを受けた場合、まず最初に自分の気持ちを大切にしましょう。加害者が意図的でない場合もありますが、重要なのは自分が不快だと感じた時にその気持ちを伝えることです。相手に「やめてほしい」とはっきり伝えることが大切です。しかし、もしもそれでも改善されない場合には、上司や人事部門、労働組合などに相談することが重要です。また、証拠として記録を残しておくことも有効です。専門の相談窓口やカウンセラーに相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。ハラスメントは決して放置せず、早期に対処することが被害の拡大を防ぐために必要です。
ハラスメントに対するカウンセリング

ハラスメントは年々増えており、何がハラスメントになるか判断が難しいことも多いです。権威や価値観を押しつける関わりでは他者を不快にさせる可能性は高くトラブルの元になります。無意識のうちにハラスメントをする側になってしまうこともあるため、人がどのように感じ、考えるかは個人によって異なることを認識し、日々他者への思いやりと配慮をもって行動することを心がけましょう。
ハラスメントを受けることによって、心身に不具合が生じ、時には精神疾患になってしまうこともあります。そうした時にはカウンセリングを受けることも一つの方法です。(株)心理オフィスKではハラスメントについてのカウンセリングを行っています。
希望される方は申し込みフォームからご連絡を頂き、カウンセリングをまずは受けて見られると良いでしょう。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。