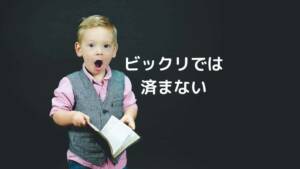場面緘黙症(正式名称は選択性緘黙)の概要、原因、診断、特徴、症状、経過、治療、カウンセリングを解説します。場面緘黙症は特定の場面で一貫して発話や行動に困難を示しますが、他の場面では支障なく話せたり、行動ができる状態です。そのため、本人は困っていても、目立つことがなく、人にも迷惑をかけないので、発見が遅くなることが多いです。
目次
場面緘黙症とは

場面緘黙症とは、公の場や人前で話すことができなくなる症状で、不安症の一種です。人前で話すことに対して異常な恐怖心や不安を感じ、声を出せなくなったり、固まってしまったりすることがあります。また、緊張や不安がピークに達すると、身体的な症状(動悸、手の震え、汗をかくなど)が現れることもあります。治療には、認知行動療法や行動療法、薬物療法などが用いられます。
特に話す能力があるにもかかわらず、幼稚園・保育園・学校・職場などの特定の社会的状況では声を出して話すことができず、家庭外での社会的な活動が増える幼児期から小学校低学年の頃に気付かれることが多い疾患です。場面緘黙症は少し前までは“elective mutism”と表現され、話さないことを自らの意思で“elect”(選択)しているという、拒否的な態度で捉えられていましたが、今は“selective mutism”と“select”(選択)された状況で話せないという不安に関連した問題としての理解が強くなりました。決して話すことを拒否しているのではなく「話せない」病態と捉える方が一般的です。
ただ、この「話せない」という状態が強いと社会的な孤立が増大することが出てきます。例えば、学校という社会的な状況では、しばしば学業または個人的に必要な事項について先生に確認をできないため、学業上の問題を起こすかもしれませんし、同級生からのいじめが起こりやすいなども含めて、学校や社会生活の機能に深刻な問題を引き起こします。
場面緘黙症に関連する症状として、過度な内気、狼狽することへの恐怖、社会的孤立と引きこもり、まといつき、強迫的傾向、否定的思考、かんしゃく、または軽度の反抗的行動が含まれることもあります。また、DSM-5では、社交不安症、全般性不安症、分離不安症、特定の恐怖症などの不安症群の一つに分類されており、他の不安症群の併存例が多いので、不安症の併存の評価を行うことが大切です。
不安症についての詳細は以下のページをご覧ください。
場面緘黙症の発症は通常5歳未満ですが、社会的交流や音読をするなどのような課題が増える学校に入るまで、この障害が臨床家の目にとまることはないかもしれません。これまでは数年、持続する場合もあるとされていましたが、DSM-5では多くの人が場面緘黙症から「脱却」することが報告されています。特に新学期のような新しい集団に入る時点での緘黙については、数ヶ月後には改善していることが多いです。最近の縦断的研究では場面緘黙症の症状は成人期までにかなり改善しますが、併存する社会恐怖などの不安障害は残存することが多いことも示されており、経過についても不安症状と関連が深いことが示唆されています。
よくある相談の例(モデルケース)
10歳未満 男性
A君は現在8歳の男の子で、小学2年生です。やや恥ずかしがり屋のところはありましたが、家庭では明るくよく話す子で、特に母親とは日常的に活発なやりとりがありました。しかし、幼稚園に入園した年少のころから園内では一言も話さず、先生や友達に対しても言葉を発することがないまま日々を過ごしていました。当初は「恥ずかしがり屋な性格だろう」と受け止められていましたが、年長に進級しても状況が変わらず、園の担任からの勧めで小児科を受診したところ、「場面緘黙症」との見立てがなされました。
小学校入学後も教室内では沈黙が続き、先生とのやりとりは筆談やジェスチャーに限られていました。周囲からの呼びかけに応じられないことで、時に誤解されたり、友達関係がうまくいかないこともありました。母親は「家では本当におしゃべりな子なんです」と語り、「どうしたら学校でも話せるようになるのか」と深い不安を抱いて、当オフィスに相談されました。
初回面接では母親のみが来談し、A君のこれまでの様子や家族関係、育ちの背景について丁寧に話されました。その中で、「外で話せないことを叱ってしまった」「がんばって声を出せた日は褒めて、出せなかった日は落ち込んでしまう」といった対応が、A君に無意識のプレッシャーを与えていた可能性にも気づかれました。カウンセリングでは、母親が「話すことを目標にしすぎず、今のA君を受け入れて見守る」姿勢を取れるよう、心理教育や支援的な面接を重ねていきました。
並行して学校との連携も行いました。担任教師との面談を通して、緘黙が「話したくない」のではなく「話せない」状態であること、無理に声を出させようとせず、筆談やジェスチャーを尊重する姿勢が大切であることを伝えました。また、クラス内でA君が安心できるような関係づくりや、決まった活動の中で小さな成功体験を積み重ねられるような支援方法を一緒に考えました。
本人には短時間の遊びを中心としたセッションを行いながらも、主に家庭と学校という「環境」に焦点を当てた介入を続けた結果、徐々にA君の表情が柔らかくなり、学校でも一部の友人に対して非言語的なやりとりを楽しむようになりました。現在もすべての場面で話せるわけではありませんが、ご家族や学校がA君のペースを尊重し、安心して過ごせる関係づくりを継続することで、ゆっくりとではありますが前向きな変化が見られています。
場面緘黙症の原因

- 行動抑制やシャイといった不安などの気質的な要因
- 心理社会的および精神力動的要因
- 社会的手掛かりを処理することができない神経心理学的要因
- 話し言葉と言語の学習障害
- 発達の遅れの既往
シャイは社会的な場面での会話を含めた社会的な相互作用が抑制されたり、回避されたりする要因となります。場面緘黙症の子どもたちはシャイで引きこもりであることが多く、乳幼児期や小児期に外界にゆっくり慣れるこや行動抑制的であったという観察も報告されています。
さらに発達障害の特性を持つ子供について、こうした場面緘黙症を発症することも考えられます。
場面緘黙症は比較的まれな障害であるため、小児期における有病率に関する調査は少なく、臨床資料や学校資料での時点有病率は0.03~1%と程度と言われています。有病率に性差はないとも言われていますが、わずかに女児が多いことが示されています。また、人種による差はありませんが、移民やバイリンガルの子どもたちでは数倍から10倍程度リスクが高くなることが報告されています。そして、場面緘黙症は青年や成人と比べて、低年齢の子どもでより現れやすいです。
A君の場合、発達の偏りは遅れは見られませんでした。ただ、性格的に恥ずかしがり屋で神経質的なところがあり、それが間接的に場面緘黙症に影響していた可能性はあります。
場面緘黙症の診断

場面緘黙症のDSM-5による診断基準
- 他の状況で話しているにもかかわらず、話すことが期待されている特定の社会的状況(例:学校)において、話すことが一貫してできない。
- その障害が、学業上、職業上の成績、または対人的コミュニケーションを妨げている。
- その障害の持続期間は、少なくとも1ヶ月(学校の最初の1ヶ月だけに限定されない)である。
- 話すことができないことは、その社会的状況で要求されている話し言葉の知識、または話すことに関する楽しさが不足していることによるものではない。
- その障害は、コミュニケーション症(例:小児期発症流暢症)ではうまく説明されず、また自閉スペクトラム症、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中にのみ起こるものではない。
引用:DSM-5
要するに明らかな発達の遅れや言語障害なく、他の状況では話すことができるにも関わらず、特定の社会的状況では一貫して話すことができない場合に場面緘黙症である可能性が出てきますが、話せないことによる実質的な困難が存在していなければ、診断基準は満たしません。
A君の場合には、これらの5つの診断基準を満たしていました。
場面緘黙症の治し方

(1)本人へのカウンセリング
現在、場面緘黙症に対する一般的な治療法は確立されてはいません。しかし、場面緘黙症を不安症として理解する流れの中で、治療についても不安に対する治療が主流になりつつあります。具体的な治療としては以下のようなものがあります。
- 随伴性マネージメント
- 系統的脱感作
- 強化
- 刺激フェーディング
- トークン法
- セルフモデリング
上記のような行動療法の技法を組み合わせたものが多いです。その他には、家族療法や薬物療法の効果を示した報告もあります。
また、子どもへの直接的なカウンセリングでは、対人交流やコミュニケーションを促しながら話すことに関連した不安を軽減することが目標となります。学校場面での介入では以下のようなことをターゲットとします。
- 不安の軽減
- 非言語的コミュニケーションの増加
- 対人交流の増加
- 言語的コミュニケーションの増加
その上で、以下のような介入を行っています。
- 話すことを強要しない
- 友達関係を促す
- 認知行動的技法を用いてリラクゼーションを試みる
- 記号やジェスチャーなどの代替コミュニケーションの仕組み作り
- 少人数の集団での活動
- 言語スキルを高めるための言語療法
このようにして具体的に介入をしていきます。
A君に対しては短時間の遊びをもちいた介入を行いました。
(2)家族や教師へのカウンセリング
小学生の場面緘黙症の場合は、保護者の不安から介入が求められることが多く、子どもの治療的ニーズと保護者への支援ニーズとを適切に理解する努力も必要になります。子どもへの直接的な治療的介入だけではなく、保護者のサポートや学校での対応など、子どもをとりまく環境への働きかけも場面緘黙症の治療では重要な要素です。
ただ、場面緘黙症は、精神科医療の対象ですが、学校場面で生じることが多いため、学校教育の対応も非常に重要になります。従来から教育現場では場面緘黙症症児への対応が行われてきており、言葉の教室や情緒障害の支援学級での指導経験が報告されています。しかし、実際には通級指導教室や支援学級で指導を受けている子どもは非常に少なく、通常学級で学校生活を送っている緘黙症児も多いと言われています。
場面緘黙症の子どもへの対応は、臨床家だけでなく、保護者や教師との協力が不可欠となります。これらは適切な臨床評価をもとに、一人一人の子どもの特性とニーズに応じた支援を実施することが重要です。
A君のケースでは、どちらかというと家族や学校に対する介入や支援を中心に行い、それが効果があったのか、A君の場面緘黙症は徐々に改善していきました。
場面緘黙症についてのよくある質問
場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)とは、特定の状況や場所で話すことができなくなる状態を指します。例えば、家庭では普通に話せるのに、学校や職場などの社会的な場面では話せなくなることがあります。これは本人の意志で話さないのではなく、強い不安や緊張から話せなくなってしまう状態です。
場面緘黙症の正確な原因は完全には解明されていませんが、一般的には以下の要因が関与していると考えられています。1. 遺伝的要因: 家族に不安障害や場面緘黙症の歴史がある場合、発症リスクが高まることがあります。2. 環境的要因: 幼少期のトラウマや過度のストレス、厳格な養育環境などが影響を与える可能性があります。3. 心理的要因: 社交不安や内向的な性格、自己評価の低さなどが関与していることがあります。これらの要因が複雑に絡み合い、特定の場面で話すことへの強い不安や恐怖を引き起こすと考えられています。
場面緘黙症の主な症状は、特定の状況や場所で話すことができなくなることです。具体的には以下のような特徴があります。1. 特定の場面での沈黙: 家庭では普通に話せるのに、学校や職場などの特定の社会的場面では全く話せなくなる。2. 非言語的コミュニケーションの制限: 話すことだけでなく、表情やジェスチャーなどの非言語的なコミュニケーションも制限されることがある。3. 持続的な症状: この状態が1ヶ月以上続く。4. 学業や社会生活への影響: 話せないことが原因で、学業成績や社会的な関係に支障をきたすことがある。これらの症状は、本人の意志で話さないのではなく、強い不安や恐怖からくるものです。
場面緘黙症の診断は、専門の医師や心理士による詳細な評価を通じて行われます。主な診断基準は以下の通りです。1. 特定の状況での話せなさ: 他の状況では話せるにもかかわらず、特定の社会的状況(例: 学校)で一貫して話せない。2. 機能への影響: この話せなさが学業や社会的な活動に支障をきたしている。3. 持続期間: 少なくとも1ヶ月以上この状態が続いている。4. 他の障害の除外: 話せないことが、言語知識の欠如や他のコミュニケーション障害によるものではない。これらの基準を満たす場合、場面緘黙症と診断されます。
場面緘黙症の治療には、主に以下の方法が用いられます。1. 認知行動療法(CBT): 不安を引き起こす考え方や行動パターンを修正し、徐々に話すことへの恐怖を克服していく方法です。2. 系統的脱感作法: 不安を感じる状況に段階的に慣れていくことで、話すことへの抵抗感を減らしていきます。3. 家族療法: 家族の協力を得て、支援的な環境を整えることで、本人の不安を軽減します。4. 薬物療法: 必要に応じて、抗不安薬や抗うつ薬が処方されることがありますが、これは主に補助的な役割を果たします。治療は個々の状況に応じて組み合わせて行われ、専門家の指導のもとで進められます。
場面緘黙症は主に子どもに見られる症状ですが、大人にも発症することがあります。子どもの頃に発症し、適切な治療やサポートを受けられなかった場合、成人期まで持ち越されることがあります。また、成人になってから新たに発症するケースも報告されています。大人の場面緘黙症は、職場や社会生活においてコミュニケーションの障害となり、日常生活に支障をきたすことがあります。したがって、子どもだけの問題ではなく、年齢を問わず適切な理解と支援が必要です。
場面緘黙症の子どもをサポートするには、以下のポイントを意識してください。1. プレッシャーをかけない: 話すことを強要せず、自然に話せる環境を整える。2. ポジティブな強化: 小さな進歩を褒めて、自己肯定感を高める。3. 不安を理解する: 子どもの不安や緊張を軽視せず、共感を示す。4. 学校との連携: 教師やスタッフと協力し、子どもが安心して過ごせる環境を作る。5. 専門家のサポート: 必要に応じて心理士やカウンセラーの助けを求める。子どもが少しずつでも自信を持ち、自分のペースで話すことができるよう、長期的な視点で見守ることが重要です。
場面緘黙症と社交不安症は似た症状を持つことがありますが、異なる点があります。場面緘黙症は、特定の場面で話すことができないという症状が中心で、話せない状況が限定的です。一方、社交不安症は、人前での行動全般に強い不安を感じる障害で、話すことだけでなく、人目につく状況全体に対する恐怖が特徴です。両者は併存することもありますが、診断と治療のアプローチが異なるため、専門家の評価が重要です。
場面緘黙症が自然に改善する場合もありますが、ほとんどの場合、適切な支援がなければ長期化する傾向があります。特に、学校生活や社会的な場面での困難が続くと、二次的な問題(自己評価の低下やさらなる不安症状)につながる可能性があります。そのため、早期の介入が推奨されます。専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに改善を図ることができます。
場面緘黙症の治療期間は個人差があります。軽度の場合は数ヶ月で改善することもありますが、症状が重い場合や長期間放置されていた場合には、数年かかることもあります。治療の進行は、子どもの特性、環境、家族や学校のサポートの度合いに大きく影響されます。焦らずに、少しずつ進歩を重ねていくことが大切です。
場面緘黙症について相談する

(株)心理オフィスKでは場面緘黙症について家族の相談やカウンセリングを実施しています。希望者は以下の申し込みフォームからご連絡ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。
- 神庭重信(編集)DSM-5を読み解く4 中山書店 2014年
- はやしみこ(著)どうして声が出ないの?: マンガでわかる場面緘黙 学苑社 2013年
- 金原洋治(著)イラストでわかる子どもの場面緘黙症サポートガイド:アセスメントと早期対応のための50の指針 合同出版 2018年
- エイミー・コトルバ(著)場面緘黙症の子どものアセスメントと支援―心理師・教師・保護者のためのガイドブック 遠見書房 2019年
- R.リンジー バーグマン(著)場面緘黙症の子どもの治療マニュアル―統合的行動アプローチ― 二瓶社 2018年
- 久田信行 金原洋治 梶正義 角田圭子 青木路人(2016). 場面緘黙症(選択性緘黙)の多様性―その臨床と教育― 不安症研究, 8(1), 31-45.