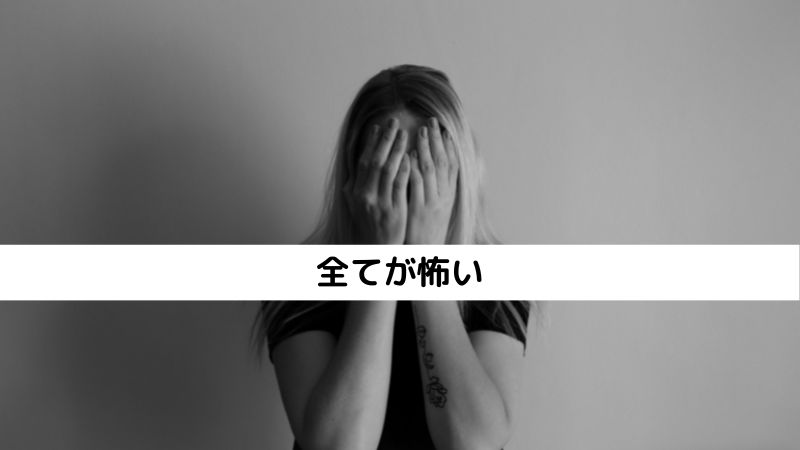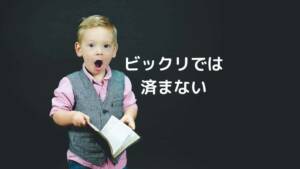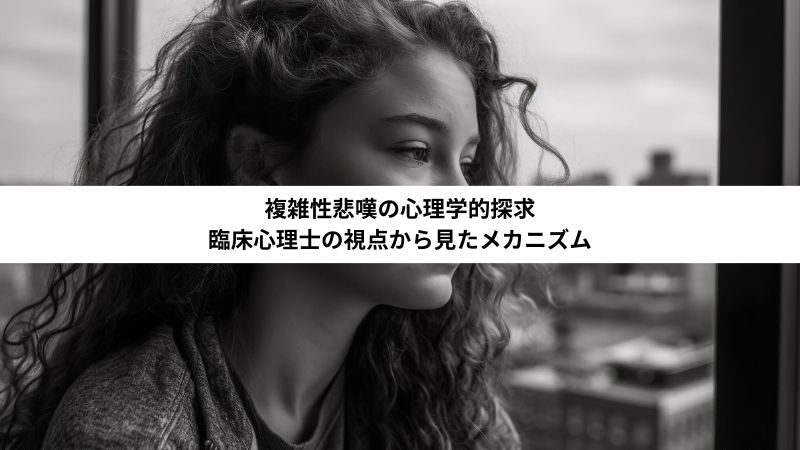全般性不安障害(全般不安症、GAD、Generalized Anxiety Disorder)とは、日常生活で制御できないほどの不安や心配を感じ、心身に支障をきたす心の病気です。
本記事では、全般性不安障害の原因、疫学、特徴、種類、診断、経過、予後、治療、カウンセリングなどについて解説していきます。
目次
全般性不安障害とは

(1)概要
全般性不安障害(全般不安症、GAD、Generalized Anxiety Disorder)は、緊張や心配、不安などが日常的に続く、不安障害のひとつです。何か特定の出来事に対する不安ではなく、日々の生活における多くのことに対して過剰な不安を感じる傾向があります。GADには身体症状も現れ、胃腸の不調や疲れ、頭痛などが起こることもあります。治療には認知行動療法や薬物療法が用いられます。
過去には不安神経症と呼ばれており、DSM-5(精神疾患の診断と統計のマニュアル 第5版)では現在、全般不安症という名称がつきました。
そもそも不安とは、あらゆる場面で誰もが感じる感覚です。不安を感じることで、心配な出来事の回避や予防行動をとることができるため、人の成長にとって大事な感覚とも言えます。不安の感じ方や強さは人それぞれであり、明確に測定することが難しい構成概念ですが、正常な不安と全般性不安障害の違いは、日常生活に支障をきたすレベルで心身の健康を損なうかどうかでしょう。
また、正常な不安であれば自然に薄らいでいく一方で、不安障害の場合は漠然とした不安が6ヶ月以上続く違いもあります。
ちなみに全般性不安障害の上位カテゴリーである不安障害については以下のページをご覧ください。
(2)よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは、長年にわたり漠然とした不安に悩まされてきました。「何か悪いことが起きるのではないか」「周囲に迷惑をかけてしまうのではないか」といった思考が常に頭から離れず、日常生活の中でも気が休まらない状態が続いていました。幼少期から几帳面で真面目な性格で、親からは「しっかりしなさい」「ミスをしてはいけない」と厳しく育てられました。学生時代は常に完璧を求め、友人関係や成績への不安で眠れない日も多くありました。
社会人になってからも、同僚や上司とのやりとりひとつひとつに強い不安を感じ、「自分の言動で相手を不快にさせたのでは」と考え続けてしまうようになりました。夜になるとその日の出来事を何度も反芻し、眠れなくなることが増えてきました。病院では「全般性不安障害」と診断され、抗不安薬を処方されましたが、薬で一時的に落ち着いても、根本的な安心にはつながりませんでした。
「このまま不安に支配された生活を続けるのはつらい」と感じたAさんは、当オフィスのカウンセリングに申し込みました。初回面接では、涙ながらに「どれだけ考えても安心できない」と語られました。カウンセリングでは、Aさんの不安に関する思考のクセを一緒に整理し、安心感のなさの背景にある幼少期の体験や人間関係の影響について丁寧に振り返っていきました。
加えて、Aさんの不安が日常の回避行動につながっていることが明らかになったため、段階的な暴露療法(エクスポージャー)も取り入れました。例えば、後で不安になりそうなメール送信をあえて避けずに行う、上司に相談したいことを勇気を出して話してみる、といった「不安が強まるが実行可能な課題」を少しずつ設定し、実際に体験していく中で「不安は高まっても、やってみれば大丈夫だった」という感覚を積み重ねていきました。
Aさんは、「最初は怖かったけれど、逃げずに行動してみることで不安が薄れることを実感できた」と語るようになり、以前よりも不安に支配されずに日々を送れるようになってきています。現在では、「不安があっても動ける自分」を大切にしながら、より安定した生活を築きつつあります。
(3)特徴
全般性不安障害ではあらゆる出来事や対象において不安や心配を感じてしまいます。自分自身のことだけでなく、他人や環境、自然災害など何にでも不安を感じ、起こる可能性が低い出来事にさえも「もしこうなったらどうしよう」と考えを止めることが難しい特徴があります。
また、不安や心配は誰にでも起こる感覚であるため、病気としての自覚をもちづらい場合が多いです。心身に支障が出ることで病気の自覚をもった場合でも、全般性不安障害の人は「何か大きな病気にかかったんじゃ」と不安が悪化したり、精神科や心療内科ではなく内科などを受診したりするため、診断までに時間がかかることもあります。
適切に受診できた場合でも、治療に用いる薬の副作用や主治医の方針などに不安を覚えることも多く、治療関係を安定させて落ち着くにはエネルギーがいる病気です。不安には1人で考えるほど悪化しやすい特徴があるため、不安を感じた場合は第三者に伝えて少しでも気持ちを緩和させてみましょう。
Aさんもこのように、どんなことに対しても不安を抱き、考えが止まらなくなってしまうという特徴がみられていました。
(4)経過や予後
全般性不安障害は、発症の具体的なタイミングが分かりにくく、一度発症すると慢性的に強い不安を感じやすい傾向があります。
治療をしない場合だと、ほかの不安障害は悪化しやすい一方で、全般性不安障害は不安が悪化することもあれば落ち着ける時期もあります。調子の良い悪い波を繰り返しながら少しずつ悪化していく病気であるため、「ただの心配性だったのかも?」と自覚しづらい病気です。
全般性不安障害は十分治療可能な病気ですが、ほかの精神疾患の合併率が高いため、二次障害の治療も含めると寛解までに時間を要するとされています。特に経過が長いとうつ病の併発が多いようです。
また、心身への支障がでることで、日常生活を楽しめず、QOL(生活の質)が下がる可能性も高いです。治療を進める最中も不安を感じやすく、通院や服薬を自己中断してしまう場合も多い病気ですが、医療機関にかかるなど治療を続けることで、全般性不安障害と上手に付き合っていくことは可能と言えます。
Aさんは幸いなことにカウンセリングを受けることにより、徐々に改善がみられ、QOLは回復していきました。
全般性不安障害の診断

(1)診断基準
全般性不安障害は、DSM-5によると以下のような診断基準があります。
全般性不安障害のDSM-5の診断基準
- 仕事や勉強、家事など様々な出来事や活動において、過度な不安や心配が6ヶ月以上続く
- 過度な不安や心配は抑えがたい
- 過度な不安や心配によって、以下6つのうち3つ以上の症状がみられる(子どもの場合は1つ以上)
- 落ち着きにくさや緊張、神経が過敏になる様子
- 疲れやすさ
- 集中のしづらさや、心が真っ白になる感覚
- 怒りっぽさ
- 筋肉の緊張など身体のこわばり
- 寝つけない、途中で覚醒する、熟睡できないなどの睡眠障害
- 過度な不安や心配、それによる症状で生活上困る
- 心身の症状は、過度な不安や心配以外では説明できない
出典:DSM-5
全般性不安障害は、とにかく漠然とした不安に日々悩まされて心身の健康を損なう病気です。不安や心配が続いていても、本人があまり困らない場合や何とか生活できている場合は、全般性不安障害とは言い難い面もあります。
(2)診断法
全般性不安障害の診断にあたって特殊な検査の実施はありませんが、診察のほか身体疾患と区別するために内科的な検査を行うことがあります。
また、ほかの精神疾患の合併症がないかを判断する必要があります。全般性不安障害はうつ病をはじめとした合併症が多いです。合併症がある場合はその治療を優先的に行うことになります。
うつ病については以下のページをご覧ください。
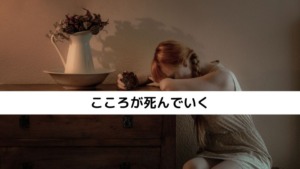
Aさんは全般性不安障害の5つの診断基準に該当していました。
全般性不安障害の症状

(1)身体症状
- 疲れやすさや倦怠感
- 頭痛や頭重感
- 不眠や中途覚醒
- 動悸
- めまい
- 肩こりなど身体のこわばり
- 発汗などの自律神経失調症状
- 便秘 など
(2)精神症状
- 慢性的な不安感
- 抑うつ気分
- 注意や集中の困難
- 予期不安
- 神経過敏さ
- 人と会いたくなくなる
- イライラしやすくなる など
これらの症状は強い不安以外の要因でも生じうるものですが、具体的な心当たりがないにも関わらず心身に不調が生じる場合は、不安やストレスとの関係があるかもしれません。
Aさんは不眠や疲労感などの身体症状と、慢性的な不安感や抑うつ気分などの精神症状がみられていました。
全般性不安障害の原因

- 神経質な性格や不安を感じやすい性格要因
- ストレスの多い生活などの環境要因
- セロトニンの取り込み量や神経症傾向などの遺伝的要因
- 男女のホルモンバランスに関する生理的要因 など
原因の特定は困難な心の病気であり、いくつもの要因が重複して発症している可能性もあります。
また、全般性不安障害は、不安障害の中でも誰もが発症する可能性のある病気で、およそ1000人のうち64人が発症すると言われています。全体的な有病率は3~8%と考えられており、発症年齢は幅広く、20~30代に多く見られますが、10代での発症例もあります。
全般性不安障害の特徴として、性差は女性に多くみられ、発症率は男性の約2倍程度です。また、西洋での生涯経験率は5.7%程度と報告されています。
決して珍しい病気ではなく、小さなストレスの積み重ねや性格から、どの年代、性別でも発症しうるといえます。
Aさんの場合、几帳面で真面目な性格であり、また厳しい躾けというストレスのある環境で生育していました。そのことが全般性不安障害に関連していることが推測されます。
全般性不安障害の治療、克服、治し方

(1)薬物療法
全般性不安障害の主症状である強い不安や、二次障害が併発している場合はその症状緩和のために薬物療法が有効とされます。
効果的とされる薬物は、セロトニンの働きを円滑にするSSRIなどの抗うつ薬や、不安や心配を緩和するベンゾジアゼピン誘導体の抗不安薬などがあります。一般的に抗うつ薬は効果が表れるまでに時間がかかりやすく、抗不安薬は即効性があるものの口の渇きや依存などの副作用がネックです。また、薬物に不安や抵抗を示す人によっては漢方薬を使用することもあります。
表1 全般性不安障害に効果のある薬剤例
| 系統 | 製品名 | 商品名 |
|---|---|---|
|
SSRI |
エスシタロプラム | レクサプロ |
| フルボキサミン | ルボックス、デプロメール | |
| パロキセチン | パキシル | |
| セルトラリン | ジェイゾロフト | |
|
ベンゾジアゼピン系 |
ジアゼパム | セルシン、ホリゾン |
| アルプラゾラム | ソラナックス、コンスタン | |
| エチゾラム | デパス | |
| ロフラゼプ酸エチル | メイラックス | |
| クロナゼパム | リボトリール、ランドセン | |
| ブロマゼパム | レキソタン | |
| ロラゼパム | ワイパックス | |
| クロチアゼパム | リーゼ |
Aさんは抗不安薬を処方されましたが、それではあまり改善は見られませんでした。
(2)カウンセリング
カウンセリングは治療の即効性を期待しづらいですが、薬物療法よりも副作用を少なく行える治療法です。不安の原因が日々の生活やストレスではなく、神経質な性格特徴や生育環境にあると思われる場合は、精神療法にて話をし、不安を扱う訓練をしていくことが望ましいと言えます。
カウンセリングを行う臨床心理士・公認心理師によって専門領域が異なるため、これらの実施が可能か事前に確認することをおすすめします。
Aさんとのカウンセリングでは、丁寧に話を聞きながら、これまでのことを整理し、地道に信頼関係を築いていきました。
(3)認知行動療法
全般性不安障害の人は不安を感じやすく、さらに不安を悪化させる自動思考をしやすいため、認知行動療法にて不安の自動思考に気づき、考え方の修正や不安への対処を試みていきます。
人によって不安に感じる出来事や不安の強さは異なるため、はじめに不安階層表を作成して不安に関する気づきを得ることが多いです。考え方や行動を変えることで、日常生活での支障を減らしていくことができます。
また、認知行動療法のスキルの一つである暴露療法(エクスポージャー)では、強い不安を克服するため徐々に不安な出来事に直面することで、不安に慣れていくことを目的とします。不安が低いものから順番に克服していくやり方が多いですが、いろいろなやり方があります。
暴露療法は勇気をもって臨む治し方なので、信頼できるカウンセラーを見つけて心身の安全を確保した上で実施しましょう。
Aさんはカウンセリングの中で認知行動療法・暴露療法(エクスポージャー)を取り入れました。そのことによって、徐々に不安が不合理なものであると体験的に理解し、改善に向かっていきました。
全般性不安障害についてのよくある質問
全般性不安障害(GAD)は、日常生活のさまざまな出来事や状況に対して過度な不安や心配が持続的に続く精神的な状態を指します。これらの不安は、6か月以上の長期間にわたり、ほぼ毎日感じられることが特徴です。具体的な症状としては、落ち着きのなさ、疲れやすさ、集中困難、筋肉の緊張、睡眠障害などが挙げられます。これらの症状により、日常生活や社会的な活動に支障をきたすことがあります。
全般性不安障害の原因は一つではなく、複数の要因が関与しています。遺伝的要因として、家族に不安障害を持つ人がいる場合、発症リスクが高まることが知られています。また、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れや、幼少期のトラウマ、長期的なストレス、性格的な傾向(例えば、完璧主義や過度の自己批判)なども影響を与えると考えられています。これらの要因が複雑に絡み合い、全般性不安障害の発症に至るとされています。
全般性不安障害の主な症状は、過度な不安や心配が長期間続くことです。これに加えて、以下のような身体的・精神的症状が現れることがあります:
– 落ち着きのなさや緊張感
– 疲れやすさ
– 集中力の低下や心が空白になる感覚
– 易怒性(怒りやすさ)
– 筋肉の緊張や痛み
– 睡眠障害(入眠困難、途中で目が覚める、熟睡感の欠如)
これらの症状により、日常生活や社会的な活動に支障をきたすことがあります。
全般性不安障害の診断は、医師や専門家による詳細な問診と評価を通じて行われます。具体的には、以下の点が考慮されます:
– 過度な不安や心配が6か月以上、ほぼ毎日続いているか
– 不安や心配をコントロールすることが難しいと感じているか
– 不安に関連する身体的・精神的症状(例:落ち着きのなさ、疲れやすさ、集中困難、筋肉の緊張、睡眠障害)が複数存在するか
また、他の精神疾患や身体的な要因による症状でないことを確認するため、必要に応じて身体検査や心理検査が行われることもあります。
全般性不安障害の治療には、主に以下の方法が用いられます:
1. 薬物療法:抗不安薬や抗うつ薬が処方されることがあります。これらの薬剤は、不安や関連する症状を軽減するのに役立ちます。
2. 心理療法:認知行動療法(CBT)は、全般性不安障害の治療に効果的とされています。CBTでは、否定的な思考パターンや行動を特定し、より適応的なものに変えることを目指します。
3. 生活習慣の改善:規則正しい生活リズムの維持、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠などが症状の緩和に寄与します。
治療は個々の状況や症状に応じて組み合わせて行われることが多く、専門家と相談しながら最適な方法を選択することが重要です。
全般性不安障害は、適切な治療とサポートを受けることで、症状の大幅な改善や完全な回復が可能です。治療には時間がかかることもありますが、薬物療法や心理療法、生活習慣の改善を組み合わせることで、日常生活における不安や心配を効果的に管理できるようになります。早期の診断と治療開始が、より良い予後につながるため、症状を感じたら専門家に相談することが推奨されます。
全般性不安障害(GAD)は、特定の状況や対象に限らず、日常生活のさまざまな出来事や活動に対する過度な不安や心配が特徴です。一方で、他の不安障害には以下のような特徴があります:
– パニック障害:予期せぬパニック発作が繰り返される。
– 社会不安障害(社交不安障害):人前での行動や評価に対する強い恐怖や回避行動。
– 特定の恐怖症:特定の物や状況(例:高所、動物)に対する強い恐怖。
– 強迫性障害(OCD):不安を軽減するために繰り返される強迫行為や思考。
これらの違いを理解することで、適切な診断と治療に役立てることができます。専門家に相談することで、自身の症状に合ったアプローチを見つけることが重要です。
全般性不安障害を完全に予防することは難しいですが、以下の方法でリスクを減らすことができます:
– ストレス管理:リラクゼーション技法(例:瞑想、ヨガ)や適度な運動を取り入れる。
– 規則正しい生活習慣:バランスの取れた食事、十分な睡眠、適切な休息を確保する。
– サポートを求める:困難な状況に直面した際、友人や家族に相談する。
– 過度の負担を避ける:無理な計画や目標を立てず、適度なペースで取り組む。
また、不安を感じたときには早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることで症状の進行を防ぐことができます。
全般性不安障害は子どもにも発症する可能性があります。子どもの場合、学校の成績や友人関係、家庭内の問題など、日常的な出来事に対して過度な不安や心配を抱えることが特徴です。また、不安に関連して身体的な症状(例:腹痛、頭痛)が現れることもあります。親や教師が子どもの様子を観察し、心配な行動が続く場合は、早めに専門家に相談することが重要です。適切な支援を受けることで、子どもの不安を軽減し、健やかな成長をサポートすることができます。
全般性不安障害を抱える人をサポートする際、以下のポイントを心がけることが役立ちます:
1. 話を聞く:批判や評価をせず、相手の気持ちを理解しようとする姿勢を持つ。
2. 安心感を提供する:無理に励ますのではなく、安心できる環境を整える。
3. 情報を共有する:専門家や信頼できるリソースから得た知識を共有し、適切な治療の必要性を理解する手助けをする。
4. サポートを求める:家族や友人だけで抱え込まず、専門家の支援を依頼する。
相手に寄り添いながら、適切なタイミングで専門的な助けを促すことが重要です。
全般性不安障害のカウンセリングや認知行動療法を受ける

(株)心理オフィスKではこうした全般性不安障害についてのカウンセリングや認知行動療法を行っています。(株)心理オフィスKでカウンセリングや認知行動療法を受けてみたいという方は以下の申し込みフォームから必要事項を記入して、送信してください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。