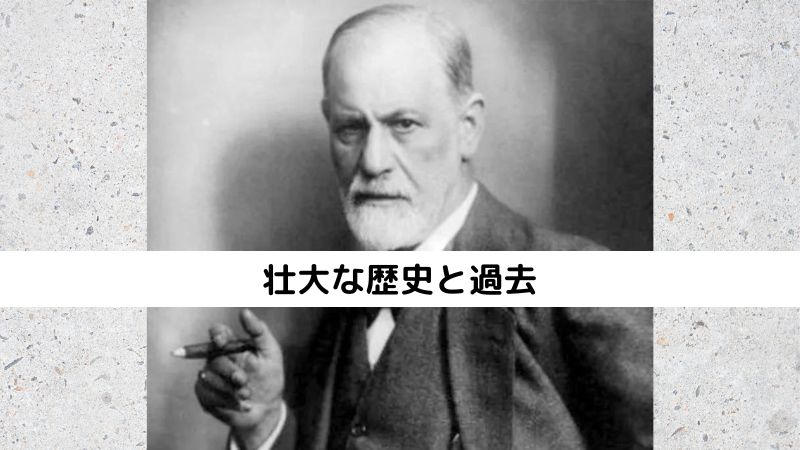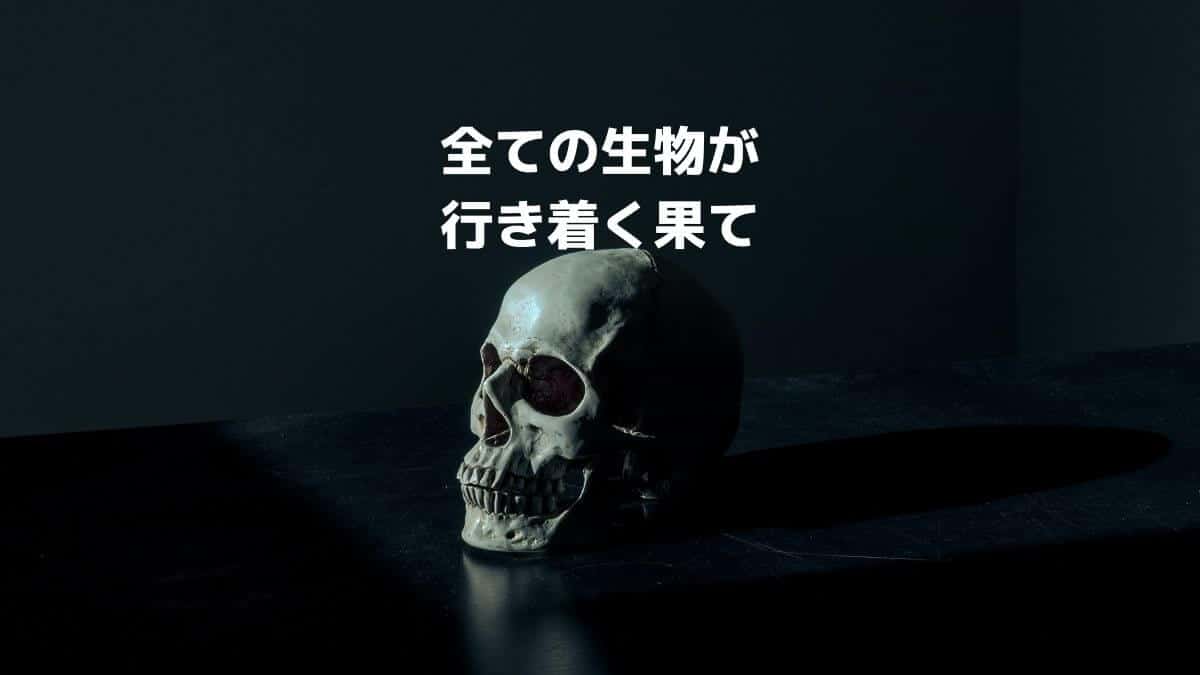現代は自己愛の時代であると言われてから久しくなりました。現代人は多かれ少なかれ自己愛の問題を抱えています。しかし、自己愛は適度にある方が健康であるとも言われています。その一方で、自己愛が過度になり、他者との関係でトラブルになるようであれば、それは自己愛性パーソナリティ障害となってしまうでしょう。
ここでは自己愛性パーソナリティ障害(自己愛性パーソナリティ症)について解説しています。
目次
自己愛性パーソナリティ障害とは
自己愛性パーソナリティ障害(自己愛性パーソナリティ症)とは、自己愛(ナルシシズム)が著しく強く、他人を利用する傾向や、自己中心的な思考や行動が見られるパーソナリティ障害のことです。自己評価が過剰であり、他人からの評価を常に求めることが特徴で、批判や否定に敏感です。また、人を支配することを好み、エキセントリックな外見や振る舞いがある場合もあります。
自己愛性パーソナリティ障害(自己愛性人格障害、Narcissistic Personality Disorder: NPD)では、歪んだ「自己愛」が形成されたことにより自尊心の調節が困難で、「自分は特別で重要な存在である」と誇大な感覚を持ってしまいます。そうした特徴から対人関係や恋愛関係ではトラブルになったりすることも多く、家庭や職場における「モラハラ」の加害者となっているケースもしばしば見られます。
親や家族から十分な愛情が得られないような不適切な養育環境が歪んだ自己愛の形成に大きく影響していると考えられています。主に個人カウンセリングや集団カウンセリングによって治療を行っていきますが、いまだに有効な治療法は確立されておらず治療が困難なケースも多いです。
自己愛性パーソナリティ障害の推定生涯有病率は、報告によって差はあるもののアメリカでは増加傾向にあり最大で6.2%にも及ぶ可能性があるという研究結果が出ています。また、女性より男性に多い傾向があることが知られています。うつ病や強迫性障害、パニック障害などの他の精神科疾患と併存していることもあり、特に神経性無食欲症(拒食症)などの摂食障害と関連が深いと報告されています。
過去には小説家の三島由紀夫、画家のサルバドール・ダリ、指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンといった有名人も自己愛性パーソナリティ障害であったと考えられています。
自己愛性パーソナリティ障害は上位カテゴリーのパーソナリティ障害の中の一つです。そのパーソナリティ障害については以下のページをご覧ください。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代の男性
Aさんは、大手企業に勤務するエリートサラリーマンです。幼い頃から両親の期待を一身に背負い、特に母親から「あなたは特別な存在だから、誰にも負けないようにしなさい」と繰り返し言われて育ちました。父親は仕事が多忙で家庭にいることは少なく、Aさんが家庭内で唯一向き合う相手は母親でした。母親の言葉は幼いAさんにとって自分の価値を確信させる一方で、期待に応えられない時の叱責や無視もまた彼に深い傷を残しました。
大学卒業後、順調にキャリアを積み重ねたAさんは、周囲からも優秀な人物として評価されていました。しかしその裏では、他者からの評価に対して異常に敏感で、少しでも批判や否定的な反応を受けると、極端に落ち込んだり、怒りを覚えたりしていました。こうした感情を隠すため、表面的には自信に満ちた振る舞いを心がけていましたが、内心では自己価値への不安と孤独感に苛まれていました。
ある日、職場で上司からの軽いフィードバックを「批判」と受け取り、感情的に反発してしまったことをきっかけに、周囲との関係がぎくしゃくし始めます。同僚との間にも壁を感じるようになり、Aさん自身も「誰も自分を理解してくれない」「このままでは職場に居場所がなくなる」と強い孤独感を抱くようになりました。仕事以外でも、親しい友人や恋人との関係が長続きせず、次第に「自分は誰とも本当の意味で繋がることができないのではないか」という疑念に苦しむようになります。
このような状態が続き、心身ともに疲弊したAさんは、インターネットで検索を重ね、カウンセリングを受けることを決意しました。初めてのカウンセリングでは、特に人間関係のトラブルについての相談が中心でした。Aさんは自分の感情や行動のパターンについて話す中で、次第に「自分は自分の価値を他者の評価に依存しすぎているのではないか」と気づき始めます。
カウンセリングを重ねる中で、Aさんは幼少期の体験が現在の行動や感情にどのように影響しているかを深く掘り下げる機会を得ました。また、自分の内面的な不安や恐れを他者との関係に持ち込むことで、無意識に相手を遠ざけていたことにも気づきます。こうした気づきをもとに、Aさんは他者との関係性を再構築するための具体的なコミュニケーション方法や、自己肯定感を育むためのスキルを少しずつ学んでいきました。
1年が経過する頃には、Aさんは職場での対人関係において以前よりも柔軟に対応できるようになり、些細な批判を受けても過剰に反応することが減っていきました。さらに、友人や恋人との関係にも変化が生まれ、初めて「他者との繋がり」を実感できるようになったと語りました。
現在、Aさんはカウンセリングを継続しながら、自分の内面を探求し続けています。彼は、「完璧でなくても良い」という感覚を少しずつ受け入れられるようになり、自己価値を他者の評価に頼らずに感じられる日が増えてきました。
自己愛性パーソナリティ障害の特徴

このような思考により、自己愛性パーソナリティ障害の人物は傲慢さを示して、周囲に優越性を誇示して、権力を求め続ける傾向があります。周囲の人に称賛を求め、時に人を利用して手柄を横取りしようとすることもあり、他者に対する共感能力にかけているため、多くの人間関係においてトラブルを抱えています。
逆に、歪んだ「自己愛」により正常な自己像が確立されていないため、臆病で非常に傷つきやすい側面も持っています。損得や利害関係に神経質で周囲からの評価を常に気にしており、時に抑うつ状態や引きこもりになったりすることも自己愛性パーソナリティ障害の特徴の一つです。
家庭や職場で他者を精神的に傷つけて支配する「モラハラ」が近年社会問題となっていますが、自己愛性パーソナリティ障害と深い関連があると考えられています。自己愛性パーソナリティ障害の人物が歪んだ自尊心を保つため、家族や職場の同僚、恋人を貶め、見下して優越感を得ることで、「モラハラ」が引き起こされるケースが多くなっています。
Aさんは傲慢さのタイプよりも、臆病で傷つきやすく評価を常に気にしているタイプに近いようです。
自己愛性パーソナリティ障害の原因

環境的な要因としては、幼少期に親や家族から過度に批判的に扱われたり、心理的虐待を受けたり、逆に甘やかされたりするなど、成長の過程で適切に扱われないことが大きく影響しています。特に両親から十分な愛情を受けられないような不適切な養育環境で育ち、自分の価値が認められない状態が続くと、正常な「自己愛」の発達が阻害され、歪んだ「自己愛」が形成されてしまうのです。
Aさんは両親からの虐待などはなかったようですが、母親からの過度な期待や父親不在などが関連しているのかもしれません。
自己愛性パーソナリティ障害の診断

DSM-5で示されている具体的な自己愛性パーソナリティ障害の診断基準は以下のとおりです。
自己愛性パーソナリティ障害の診断基準
誇大性(空想または行動における)、賛美されたい欲求、共感の欠如の広範な様式で、成人期早期までに始まり、種々の状況で明らかになります。以下のうち5つ(またはそれ以上)によって示されます。
- 自分が重要であるという誇大な感覚
- 例:業績や才能を誇張したり、十分な業績がないにもかかわらず優れていると思い込んだりします。
- 限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。
- 自分が “特別” であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達(または団体)だけが理解しうる、または関係があるべきだ、と信じている。
- 例:一流の人物でないと、特別である自分は理解できないと考えています。
- 過剰な賛美を求める。
例:自分は常に褒められて当然と思っていて、他者に褒めることを期待したり要求したりします。賛美が得られないときにはショックを受けます。- 特権意識
- 例:自分が特別有利な取り計らいを受けることを期待しています。
- 対人関係で相手を不当に利用する
- 例:他人の業績や部下の手柄を独り占めしたり、タダ働きさせたりして相手を不当に利用します。
- 共感の欠如
- 例:他者の気持ちを理解して共感することができず、他者の痛みがわかりません。
- 他者への嫉妬および他者が自分を嫉妬していると信じている
- 例:他者を妬んだり、実際には妬んでいなくても妬まれているという妄想に取りつかれたりします。
- 尊大で傲慢な行動、または態度
- 例:ふんぞり返るなどの偉そうな行動や態度を取ったり、人を見下した発言をしたりします。
引用:DSM-5
診断には、これらの特徴が成人期早期までに明らかになっており、薬物やストレスなどの一時的に起こる状態ではないことを確認する必要があります。
自己愛性パーソナリティ障害と鑑別を必要とする主な疾患としては、双極性障害や他のパーソナリティ障害(境界性パーソナリティ障害、反社会性パーソナリティ障害など)があり、しばしば診断に苦慮するケースもあります。
Aさんはこの診断基準に照らし合わせてみると、A、B、C、G、Hなどが該当するかもしれません。
自己愛性パーソナリティ障害との接し方と対処法

そうならないために自己愛性パーソナリティ障害との接し方を工夫し、対処法を検討すると良いでしょう。
(1)自己愛性パーソナリティ障害かどうかの見極め
まず、その人が自己愛性パーソナリティ障害かどうかを見極める必要があります。もちろん、医師や臨床心理士ではない人にはなかなか見極めるのが難しいかと思います。
ある程度のところでは、「自己愛性パーソナリティ障害の診断」で記載したいくつかの項目に該当するかどうかを確認はできるかもしれません。
Aさんは上記に記載したとおり診断基準に該当しているようでした。
(2)自己愛性パーソナリティ障害と適度な距離を取る
そして、自己愛性パーソナリティ障害の人を尊重しつつも、適切な距離を取ると良いでしょう。自己愛性パーソナリティ障害に巻き込まれず、嫌なことは嫌という、NOをきちんと言うことは大変重要です。また、できないことや不可能なことを明確にし、ダメなことはダメという線引きをしましょう。これは専門的にいうとリミット・セッティング(限界設定)と言います。
(3)専門家に相談する
その上で、自己愛性パーソナリティ障害が変わりたいという思いや考えがあるのであれば、医療機関やカウンセリング機関を紹介したり、連れていったりすることも良いかもしれません。
もしくは、自己愛性パーソナリティ障害に困っている家族や恋人がカウンセリング機関などに相談に行き、自己愛性パーソナリティ障害との接し方について相談することも良いでしょう。そこで自己愛性パーソナリティ障害に対する対処法なども身に着けることができます。
(4)自己愛性パーソナリティ障害と関係を切る
しかし、それでも改善がなかったり、お互いに疲弊したり、身近な人がうつ病などの精神障害になったりするようであれば、自己愛性パーソナリティ障害との関係を切ることも選択肢の内の一つになってきます。結婚しているパートナーであれば離婚になるかもしれませんし、恋愛関係にある恋人であればお別れということになるかもしれません。
より良く生きていくための最後の選択肢とも言えるでしょう。
自己愛性パーソナリティ障害の治療と治し方

(1)薬物療法
自己愛性パーソナリティ障害そのものを治療する薬物療法はありませんが、いくつかの症状にターゲットをあてた薬物療法はあります。
まず、自己愛性パーソナリティ障害の衝動性や易怒性に対してはリーマスなどの気分調整薬が著効することがあります。また、合併している抑うつや不安に対してはSSRIなどの抗うつ薬が効果があります。ただ、ベンゾジアゼピン系などの抗不安薬などは依存を引き起こす可能性が高いので、使用する際には注意が必要です。
いずれの薬物療法も長期的に使用せず、一時的な期間の使用にとどめることが必要です。
Aさんは薬物療法を使用せずに改善しましたが、必要であれば使用しても良かったかもしれません。
(2)カウンセリング
具体的な方法論としては、精神分析理論を背景に治療的な面接を行っていく力動的なカウンセリングや、自己や他者の複雑な心的状態について考えることができる能力であるメンタライゼーションを促進するアプローチ、治療者との面接により歪められた自己像を変容させていく転移焦点化心理療法などが行われています。
実際の臨床では、自己愛性パーソナリティ障害の繊細な傷つきに対しては共感を向けることが必要です。それは自己愛性パーソナリティ障害を甘やかしたり、依存させたりすることではありません。自己愛性パーソナリティ障害の深い傷つきに対する温かく、受容的で、共感的な態度を向けることで、治療関係が構築されるからです。
しかし、一方でそれだけでは自己愛性パーソナリティ障害の成長や変化は少ないでしょう。自己愛性パーソナリティ障害の言動が他者を傷つけていると同時に、自分自身もそれによってさまざまな社会的な損失を被ってしまっていることについて直面化したり、解釈したりする必要があります。そして、他者を見下したり、傷つけたりする背景にある自己愛性パーソナリティ障害の課題について目を向けてもらい、修正したり、変容したりすることを目指します。
こうした両方の関わりをとおして、自己愛性パーソナリティ障害の内省する力を養い、メンタライゼーションが促進されるのです。
また、その他にも、認知行動論をベースにした治療法として、スキーマ療法や弁証法的行動療法により、不快な感情や対人行動に関するスキルトレーニングを行うこともあります。
Aさんはカウンセリングで徐々に内省を深めていきました。そうしたことが改善のきっかけになったことは確かでしょう。
自己愛性パーソナリティ障害についてのよくある質問
自己愛性パーソナリティ障害についてカウンセリングを受ける

自己愛性パーソナリティ障害は他者を巻き込み、トラブルになりがちな非常に困った側面を持っています。しかし、一方では実は自己愛が脆弱で、そのために傷つきやすいという側面もあります。そこにはおそらく遺伝的な要因と幼少期の家庭内での傷つき体験もあるのではないかと言われています。そうすると、自己愛性パーソナリティ障害の人自身も大変な苦痛を背負っていると言えます。
そうすると、自己愛性パーソナリティ障害がより良い人生になるように、他者とそれなりの適度な接し方ができるようにサポートすることはとても大切なことだとも言えます。サポートには色々とありますが、その主なものはやはり臨床心理士や公認心理師によるカウンセリングになります。
当オフィスでも自己愛性パーソナリティ障害に対するカウンセリングを行っています。希望される方は以下のボタンからお申し込みいただければと思います。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。