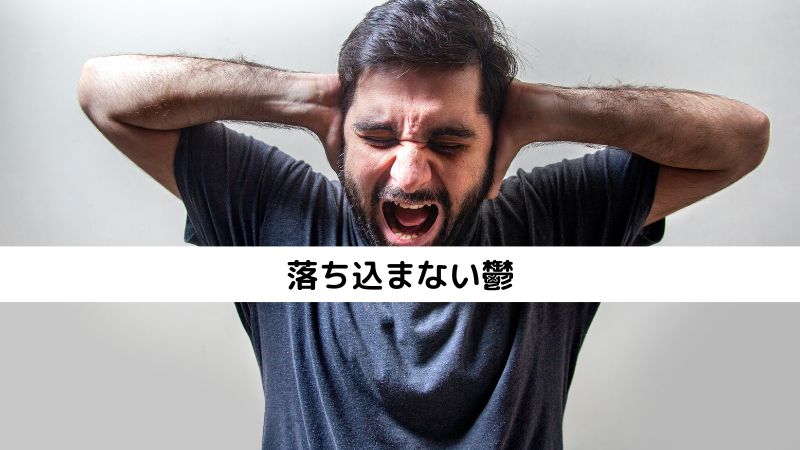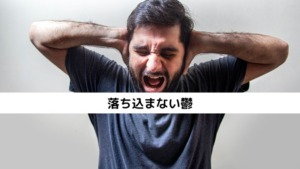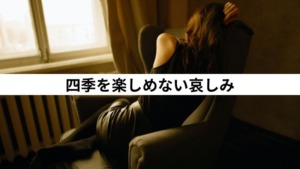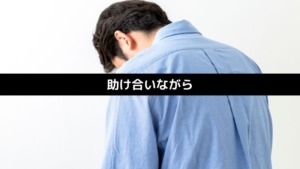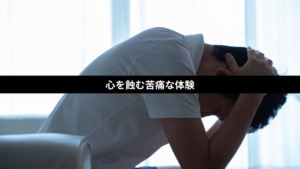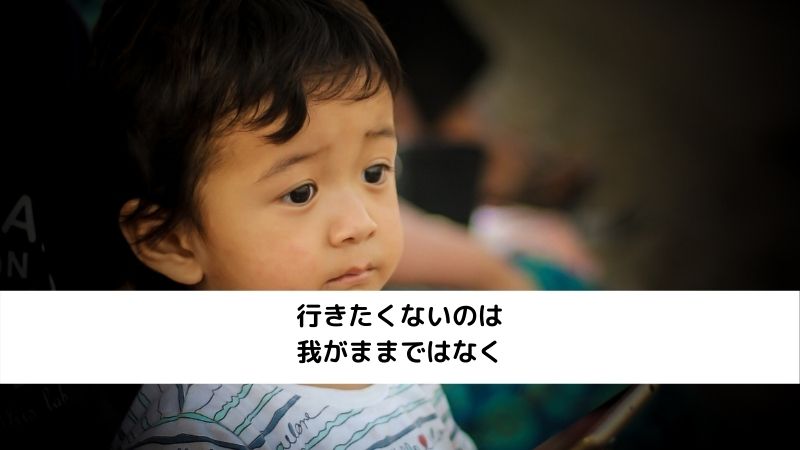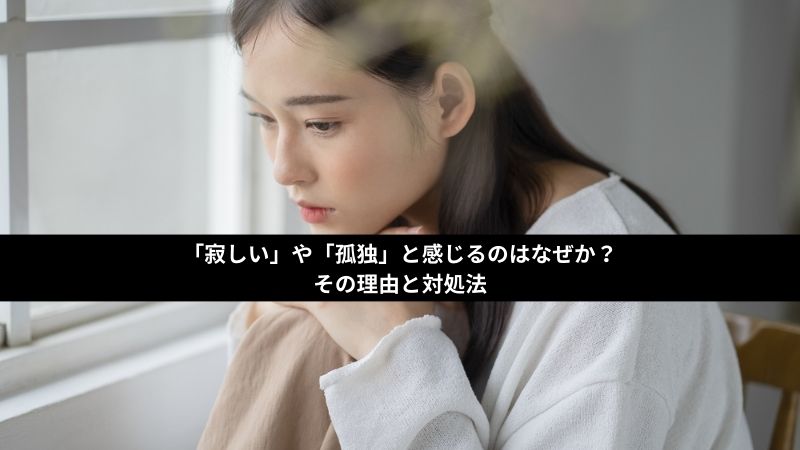「気分が沈むけれど、好きなことには反応できる」「食欲はあるし、寝すぎてしまうことが多い」――そんな状態に心当たりがある方は、もしかすると「非定型うつ病(非定型うつ)」かもしれません。典型的なうつ病とは異なり、特定の状況で気分が持ち上がったり、過眠や過食といった症状が現れるのが特徴です。
このページでは、実際に非定型うつ病の傾向を抱えていた30代女性Aさんの相談例を通して、非定型うつ病の理解や支援のヒントをお伝えします。
目次
非定型うつ病とは
非定型うつ病(新型うつ病)は、定型的なうつ病とは異なる症状を呈するうつ病の一種です。症状としては、食欲や睡眠などの生理的変化が少なく、過食や過眠などの反応過度な症状が見られることがあります。また、社交不安や過剰な敏感性、拒食症状も出ることがあります。治療は、カウンセリングや認知行動療法が一般的です。
非定型うつ病では、気分の変動が大きく、怒りや攻撃性が出ることもあったり、他責的になったりなどします。また、週末などの休日では症状が治まり、趣味や活動を楽しむことも見られます。さらに、抗うつ薬などが効きにくいという特徴もあります。このように、うつ病の症状はありつつも、従来のうつ病とは違った状態像や経過を示します。
そもそも、この非定型うつ病は正式な医学用語ではなく、現代の若者においてしばしば認められるうつ状態を報道メディアなどが命名した俗語です。非定型うつ病は、従来とは性質が異なる病状を示すだけのことであり、「非定型うつ病」という正式な病気があるわけではありません。
非定型うつ病においては、一般的な従来のうつ病より症状が軽度である気分変調症に加えて、発達障害の一部の要素が含まれている病態なのではないかと想定されています。
非定型うつ病は現代風な気分障害の状態を示唆しており、入院を必要とするほど重度ではなく、軽症であるので外来通院程度で治療が可能と考えられていますが、実際にはその診断を正確につけるのは困難であり、治療も順調にいかず慢性化しやすいと言われています。
ちなみに、従来のうつ病は、中年期から高齢期にかけて几帳面な性格、あるいは仕事熱心で完璧主義である人が発症して抗うつ薬が効果的です。しかし、近年においては抗うつ薬による治療のみでは治癒しにくい、こうした非定型うつ病が急増しています。
従来のうつ病についての詳細は以下のページをご参照ください。
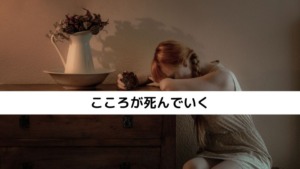
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは会社員で、接客業に就いています。幼い頃から「しっかり者」と言われることが多く、親の期待に応えるために頑張りすぎてしまう傾向がありました。自分の本音やつらさを我慢し、周囲に合わせて行動することが当たり前になっていたようです。
就職や恋愛も順調に見えていたAさんですが、30歳を過ぎた頃から、気分の波が激しくなり、特に人間関係のちょっとした出来事で強い落ち込みを感じるようになりました。恋人とのささいな言い争いや、職場での注意を受けただけでも、「見捨てられてしまうのでは」という不安が頭から離れず、急に涙が出て止まらなくなることもありました。そして、時には怒りを他者にぶつけることもありました。
また、気分が落ちている時には、甘いものを無性に食べたくなったり、長時間眠り続けたりと、身体にも変化が現れるようになりました。朝起きるのがつらくなり、仕事を休むことも増えていきました。
最初は内科を受診しましたが、うつの可能性を指摘され、心療内科に紹介されました。診察の中で「非定型うつ病」と診断され、薬による治療が始まりました。症状には波があり、薬だけでは安定しにくかったため、カウンセリングも併せて受けることになりました。
カウンセリングでは、Aさんが「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」といった気持ちから、自分の感情を抑えてきたことが少しずつ言葉になっていきました。家庭の中で感情を出すことを避けて育ってきたことや、これまでの恋愛で感じた孤独感などについても話を重ねながら、心の整理が進んでいきました。
同時に、家族支援として、Aさんのご両親との面談も数回行いました。そこで、Aさんが子どもの頃から「しっかりしなさい」「甘えるのはよくない」と言われて育ってきたことが、無意識のうちにプレッシャーになっていたことを共有しました。カウンセラーが仲介しながら、家族の中で「弱さを見せてよい関係性」についての理解を少しずつ深めていくことができました。
その結果、Aさんは自分の気持ちを表現する練習をカウンセリングで重ねると同時に、家族の前でも以前より安心して話ができるようになり、心理的な支えを実感できるようになっていきました。現在はまだ波はあるものの、調子のよい時期が増え、少しずつ安定した日常を取り戻しつつあります。
非定型うつ病の原因

ゆとり教育などを含めた現代社会を迎えて、非定型うつ病を抱えている患者さんは、自分らしく仕事業務が出来ているか、会社や上司が自分自身をきちんと評価してくれているかという課題に対して葛藤している傾向があります。
いわゆる自己愛の異常な強さと相反する自己肯定感の低下に伴って、人格形成の未熟さが、非定型うつ病の症状の本質である拒絶過敏性を始めとする様々な症状に発展していると考えられています。
Aさんの場合、恋人との関係や職場のストレスなどがきっかけとなり、症状が出現しました。また、その背景には、幼少期からの真面目で、かつ他者の期待に合うように過度に頑張る性格も関係していると推測されます。
非定型うつ病の特徴と症状

非定型うつ病は、医学的に明確な定義がある病気ではありませんが、例えば職場で気分が沈んで激しく落ち込む症状を始めとするうつ状態を呈するだけでなく、自分自身を責めずに上司や他人に責任転嫁する、休職中にもかかわらず趣味の旅行をする等の特徴が見受けられます。若年者が職場などにおいて軽度の抑うつ傾向になるが、自宅では基本的に健康的で楽しく振る舞うなど状況依存した症状様式、あるいはうつ状態に陥った責任を他者に帰するという無責任感、そして休職を深刻に捉えないという病識の希薄性を認めることが典型的です。非定型うつ病では、上司や会社が悪いと思い込んで他罰的な考え方を有する、あるいは自尊心が強くて自己中心的な性格であるとともに他者への配慮性が乏しいなどの症状が認められます。
また、仕事が休みの週末時期には基本的に元気である一方で、週明けに仕事が実際に開始されると気分が落ち込む特徴も見受けられます。非定型うつ病の亜型である「気分変調性障害」は、若年期に本人も気づかないうちに発症し、うつ病の罹病期間がとても長いために様々な病気や症状が上乗せされて認められることがあります。
また、「適応障害」とは、ある環境に本人が耐えがたさを感じて、感情や行動面で問題が分かり易く引き起こされる状態を示している一方で、非定型うつ病では対人関係に過敏に反応するなど性格の問題と誤解されやすく、病気と気づかれにくいことが特徴のひとつです。
適応障害については以下のページをご覧ください。
Aさんの場合には、不安、落涙、気分の落ち込みなどがみられました。そして、それ以外にも他者に怒りを衝動的にぶつけてしまうことなどもありました。
非定型うつ病の診断

また、ストレスフルな状況などに対する重度な心理的反応や不安発作を伴う精神障害、あるいは対人恐怖や社交不安などが認められるケースも、非定型うつ病として認識されて診断される場合が経験されます。
Aさんの場合、パーソナリティ障害などの他の精神障害の可能性は除外されました。
非定型うつ病の治療や治し方

(1)非定型うつ病の薬物療法
非定型うつ病は、受診した医療機関や専門医師によって実際に付けられる診断名や処方薬が様々であることが知られています。
非定型うつ病における薬物療法では、目先の症状に振り回されて多くの種類の薬剤を服用することで、疾患による症状を見ているのか、あるいは薬物の副作用に伴う症候を認めているのかが適切に判断できなくなることも想定されています。
従来のうつ病と非定型うつ病では薬物治療の内容を含めて治療方針が全く異なり、従来のうつ病では抗うつ薬が効果的に奏効することが多いですが、非定型うつ病においては抗うつ剤の効果が乏しい傾向があると認識されています。
Aさんに対して薬物療法を実施しましたが、それだけでは十分な効果は見られなかったようでした。
(2)非定型うつ病のカウンセリング
非定型うつ病における精神的な苦痛症状のなかには、精神医学的な異常性が認められずにパワーハラスメントや過酷な職場状況、本人の性格性などが問題の本質であるという場合も多く見受けられます。
そのような際には、問題の根本的な本質に対する解決策としては、周囲環境の改善、現実的問題に対する具体的な対処策に関して、カウンセリングを通じて学習することが重要な観点となります。
非定型うつ病と認識される病像の多くは、特有の性格傾向にくわえて心理的負担に繋がるストレッサーに心理的に反応して様々な症状が出現するという様式であるため、薬物療法だけに頼らずに、カウンセリングなど精神療法的な治療アプローチが必要です。
Aさんに対してカウンセリングを実施しましたが、その中で自分の感情を抑えてきたことなどについて整理し、さらに孤独感などについても取り組んでいきました。
(3)非定型うつ病の人への接し方や対応
いわゆる「非定型うつ病」が近年において世間一般にも広く普及して、産業保健現場でも「非定型うつ病」を抱える社員や部下にどのように対処すべきか、多くの企業で喫緊の問題として捉えられています。
非定型うつ病では気分の変動性が特徴として見受けられるため、本人にとって楽しい事項は実施できるのに辛いことはできないとともに、拒絶過敏性があるため些細なことでひどく落ち込む、あるいは周囲から自分がどう評価されているかを極度に恐れる傾向があります。
当該本人が仕事上で思わぬ挫折経験をすることに加えて、会社や上司から見捨てられる感覚を受けるなどの背景を有する場合もあり、家族や職場などを含めて周囲の人々は患者本人にどのように適切に対応するのがよいか苦慮していることが多いと考えられます。
昨今の現代社会変化の情勢によって、人格の成熟自体が遅れているケースが多く、今後は社会全体で特に若年者などの成熟度を充実させるように支援していく体制を整備することが重要なポイントです。
家族や友人、同僚、部下が非定型うつ病だった時の理想的な接し方は、当該本人が特段の問題を認識していない場合には、明らかに存在する身体的症状を指摘するなど周囲の方々のサポートによって徐々に病識を気づかせて、適切な治療に結び付けることが重要です。
Aさんとのカウンセリングの中では家族支援も行いました。そして、過度にプレッシャーを与えないように話し合ったりしました。そうしたことがAさんの回復に寄与していたようでした。
非定型うつ病のカウンセリングを受ける

非定型うつ病を疑う際には、自己診断せずに精神科や臨床心理士、公認心理師などに相談して問診を通じて丁寧な病歴を聞き取り、適切な診断を行って、カウンセリングなど精神療法を中心とした治療を実践する手順が重要です。
(株)心理オフィスKでも非定型うつ病の方に対するカウンセリングを実施しています。希望される方は以下のメールフォームからお問い合せください。
うつ病についてのトピック
よくある質問
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。