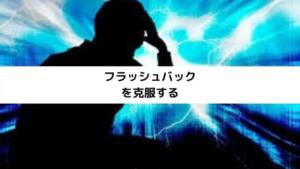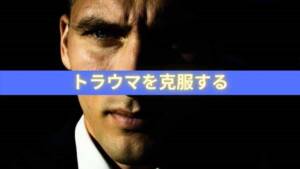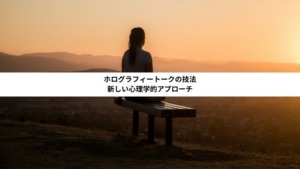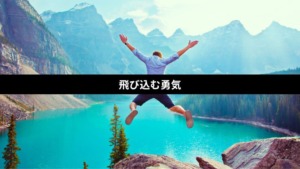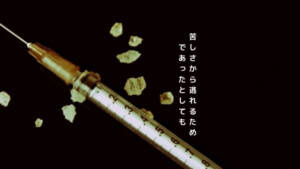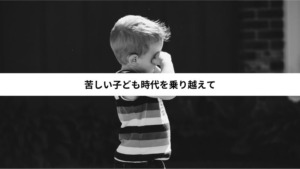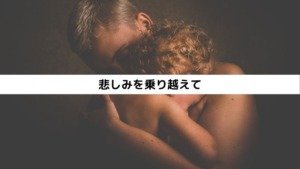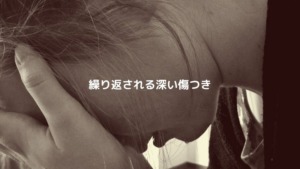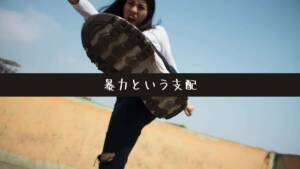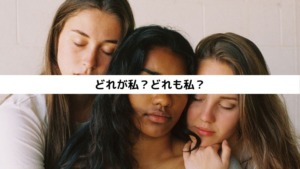トラウマとは、いわゆる「心の傷」と言われるものです。身体が傷つくことと同じように同じように心も傷ついてしまいます。そして、フラッシュバックや過覚醒、回避などのいくつかの症状が重なるとPTSD(心的外傷後ストレス障害)という診断になります。
ここではトラウマの概要、症状、特徴、克服方法、治療、カウンセリングなどについて解説します。
トラウマの概要
(1)トラウマとは
トラウマとは、心に深い傷を残す出来事や体験を指します。人によっては、自然災害や事故、虐待や暴力、戦争などの経験がトラウマになることがあります。そしてそのトラウマによって長期間にわたって脳や心、対人関係、日常生活に支障をきたします。例えば、過去の出来事が思い出されたり、トラウマを負った場所を避けたり、悪夢を見たり、感情が麻痺したりします。さらにはうつ病や不安障害などの精神疾患が引き起こされることもあります。
人間は生きていれば、様々な嫌な出来事や苦痛な事柄に出合います。しかし、そのほとんどは気ごころのしれた人に愚痴を言ったり、気分転換をしたり、趣味や仕事に没頭したりすることで乗り越えることができます。単純に時間の経過によって忘れ去られたりします。そうすることでトラウマになることはありません。しかし、苦痛な出来事が非常に大きく、心がそれらを受け入れることができなくなってしまうと、長期にわたって、トラウマとして心に残ってしまいます。
また、トラウマは、自分自身が体験することだけではなく、人が体験することを目撃したり、近親者や友人が体験したことを聞いたりすることでも生じます。例えば、家族が犯罪被害にあったり、事件事故の報道をテレビで見たり、知人が自殺をしたり、などの出来事は自分自身のことではないにも関わらず、トラウマになってしまうことがあります。
(2)よくある相談の例(モデルケース)
30歳代の女性
彼女は幼少期は裕福な家庭に育ちました。しかし、両親とも過干渉で、特に勉強に関しては厳しく、ちょっとでも点数が悪いと過度に叱責し、何時間も勉強机に向かうように強要しました。学校では勉強の成績は良いものの、大人しく、引っ込み思案だったため、いじめの対象になってしまうこともありました。この時期には原因不明の腹痛や頭痛で時折学校を休むこともありました。その後、偏差値の高い大学に入学し、ほどなく恋人ができましたが、その恋人は支配的で暴力的な男性でした。彼女が他の男性と話をしているだけでも激怒し、時には平手打ちをされることもありました。
大学卒業後は就職し、しばらくは安定して仕事をしていましたが、ある時に異動があり、職場環境がかわりました。そこは非常に忙しい部署であり、上司である部長は威圧的な性格でした。また時にハラスメントをするようなところもありました。彼女は仕事の些細なミスを上司に強く叱責されたことをきっかけに過呼吸などのパニック発作を起こし、職場で倒れてしまいました。その後も職場に行くと体調が悪くなり、出社が非常なストレスになりました。夜は眠れず、過去のいじめやDVの悪夢を見るようになりました。食欲も低下し、悲観的にばかり考えてしまい、日常生活もままならなくなりました。
そのため、精神科を受診し、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されました。そして、薬物療法と並行して、トラウマ治療を主としたカウンセリングも開始されました。カウンセリングではまずは日常生活の立て直しを行いました。生活リズムを整え、食事や睡眠が十分にとれるようにしました。日常生活が次第に落ち着いていき、トラウマの治療に徐々に入っていきました。カウンセラーと相談し、トラウマ治療の一つであるEMDRをすることになりました。EMDRで過去のトラウマを一つ一つ解消していきました。そうした治療により彼女は身体的にも精神的にも生活的にも安定していきました。
(3)トラウマの特徴と症状
トラウマ体験した後、様々な症状がみられることがあります。それが以下です。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 侵入体験 | トラウマ場面を急に思い出してしまうこと。フラッシュバックとも言います |
| 過覚醒 | 自律神経の内、交感神経が過剰に高くなること。心臓動悸、口の渇き、頭痛、腹痛、吐き気、不眠、不安、過呼吸などがあります |
| 回避 | トラウマに遭遇した場所や場面に近づかない。トラウマを想起するような出来事を避けること |
| 麻痺 | 感情が死んだように凍り付く。何も感じなくなる。意識が遠くなる |
| 否定的な思考 | 悪いことばかりを考える。過剰に自分を責める |
モデルケースでは悪夢を見たり(侵入体験)、悲観的にばかりかんがえてしまう(否定的な思考)などがそれに当てはまります。
トラウマの症状や特徴の詳細については以下のページをご覧ください。
(4)トラウマと脳と記憶
トラウマは脳と記憶に多大な影響を与えます。トラウマを受けると脳の扁桃体が活性化し、恐怖条件付けが起こってしまいます。そして、トラウマが記憶から忘却することなく、鮮明に残ってしまいます。
モデルケースではかなり古い記憶であるいじめやDVなどについても鮮明に出てくるところなどはこれらに該当するでしょう。
トラウマと脳や記憶に関することは以下のページに詳しくあります。
(5)子どものトラウマ
子どものトラウマの場合、成人とはやや違った形で症状があらわれます。分離不安、退行、身体症状などが出てくることです。これらは成人にはあまりあらわれない症状です。
モデルケースの場合には小学生の時に原因不明の腹痛や頭痛で学校を休むことがありましたが、こうしたところは子どものトラウマの特徴と言えるでしょう。
子どものトラウマについての詳細は以下をご覧ください。
(6)トラウマに関連する障害や問題
トラウマによって生じる、もしくは関連する障害や問題には様々なものがあります。以下はその一例です。
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 複雑性PTSD
- アダルトチルドレン
- ドメスティックバイオレンス
- 虐待サバイバー
- 性犯罪被害者
- 発達性トラウマ障害
- 愛着障害
- 解離性障害
モデルケースではPTSDと診断されています。
これらのことについての解説は以下のページをご覧ください。
トラウマの克服

(1)トラウマインフォームドケア
様々な問題をトラウマという視点から捉えなおし、トラウマについて気付き、理解し、対応し、再トラウマ化を防ぐという態度や姿勢、枠組みのことをトラウマインフォームドケアと言います。
モデルケースの場合、症状は職場不適応やパニック発作でしたが、その背景にトラウマがあるのではないかと見立てたところや、日常生活の立て直しから治療を進めた点などがトラウマインフォームドケアと言えるでしょう。
トラウマインフォームドケアについては以下のページに詳しく書いています。
(2)フラッシュバックへの対処
フラッシュバックなど自分自身で対処することもある程度可能です。ちなみに、モデルケースでも悪夢という形でフラッシュバックがありました。
フラッシュバックの対処の具体的な方法は以下のページをご覧ください。
(3)トラウマ治療の方法
トラウマを直接解消するいくつかの方法があります。EMDRやホログラフィートーク、認知行動療法、エクスポージャー療法などです。
モデルケースでもEMDRを行っています。それぞれの詳細は以下のページをご覧ください。
トラウマの治療やカウンセリング
(1)トラウマのカウンセリングの適切な開始時期
このようなトラウマですが、時間経過とともに自然に治っていく場合も少なからず多いようです。そのトラウマが自然に治ることを促進するためにも、そして、残念ながら慢性化してしまった状態を治すためにも適切な支援を受けることが必要です。
トラウマに対する適切な支援とは以下のように時期によって異なります。
| 時期 | 支援の方法 |
|---|---|
| 初期 | 安全の確保、身体治療、衣食住の確保 |
| 中期 | 経済支援、生活保障、生活支援、法的支援、行政サービス |
| 後期 | 自立支援、職業生活の安定、心理的支援やカウンセリング |
この順番を間違えると、クライエントのニーズに合わないことをしてしまうことになってしまいます。たとえば、初期の安全が確保できていない時にカウンセリングをしても無意味どころが害になってしまいます。
モデルケースでも最初からEMDRなどのトラウマ治療をせず、最初は日常生活の立て直しからはじめました。こうした適切な治療のタイミングというものがあります。
(2)トラウマのカウンセリングの目的
EMDRやホログラフィートーク、認知行動療法、エクスポージャー療法などのいずれのトラウマ治療でも共通点はあります。以下の3つのことを目標にすることです。
| 段階 | 説明 |
|---|---|
| 1.安全感覚の確立 | 自分自身が安全であり、身の危険を感じる心配はなく、いざとなれば誰かが助けてくれるという安全に対する信頼感の回復 |
| 2.責任の所在の変革 | 事件や事故が自分自身の責任で起こってしまったと過度に自責的、自罰的にならず、適切で妥当な範囲で起こった責任を外に向けかえること |
| 3.対処可能性の向上 | 自分自身の能力やスキルや資源を用いて、事態を制御し、危険を回避できるという自分自身に対する信頼感の回復 |
上記の軸について、3よりも2が、2よりも1が優先され、番号が若いものをある程度確立しなければ、次の番号の水準のことがなかなか達成しにくいようです。例えば、安全感覚がないのに、責任の所在を変革したり、対処可能性を向上したりすることは困難です。
モデルケースでも最初の「安全感覚の確立」などを優先した治療が行われました。
(3)トラウマのカウンセリング
適切な支援の中で臨床心理士やカウンセラーができることは様々にあります。トラウマを受けた方は罪悪感に苛まれたり、社会から孤立しがちであったり、人との関係に過敏になってしまったりすることもあるので、そうしたことを踏まえたカウンセリングをし、どのように心構えを作り、どのように行動すればよいのかを話し合っていくことは助けになるでしょう。
そして、トラウマによる生活上の支障や心の苦痛をやわらげていく心理学的な技法もいくつかあります。EMDR、ホログラフィートーク、認知行動療法、エクスポージャー療法)などです。
さらに、トラウマをきっかけにして、自身の人生の在り方や生き方の問題を見つめ、より豊かに生きていけるようになる方法として精神分析的心理療法も良い場合があります。
このようなトラウマに対する心理学的な技法の効果は高く、様々な研究データから標準的な薬物療法や医学的治療よりも効果的であると示されています。実際の支援では、心理学的な技法と医学的な治療は両方同時にしていくことが多いと思われます。
モデルケースでも、EMDRの治療も行いましたが、それだけではなく、一般的なカウンセリングを行いながら、心の安定を取り戻すための支援を行っていました。
トラウマに関するトピック
トラウマについてのよくある質問
トラウマに対するカウンセリングを受ける

そうした時には臨床心理士や公認心理師などの専門家に相談したり、カウンセリングを受けることはとても大事です。
当オフィスでもトラウマの相談やカウンセリングを行っております。カウンセリングの希望があれば、お申し込みください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。