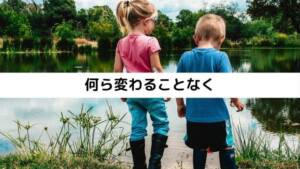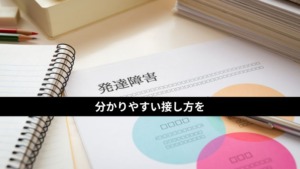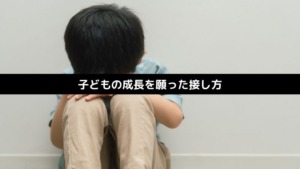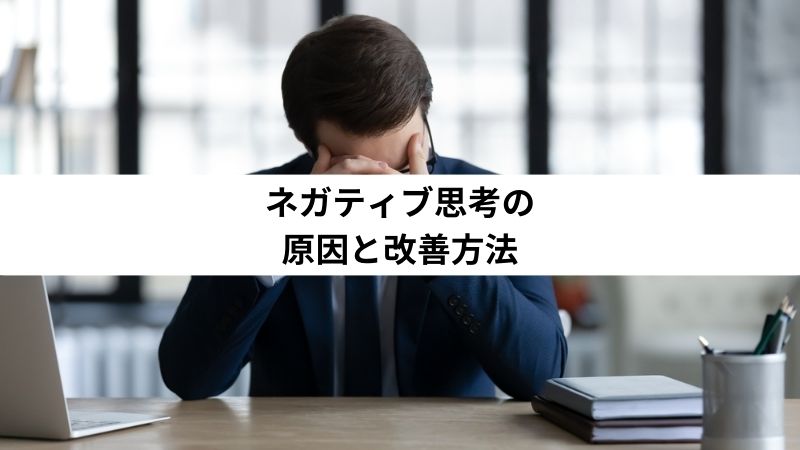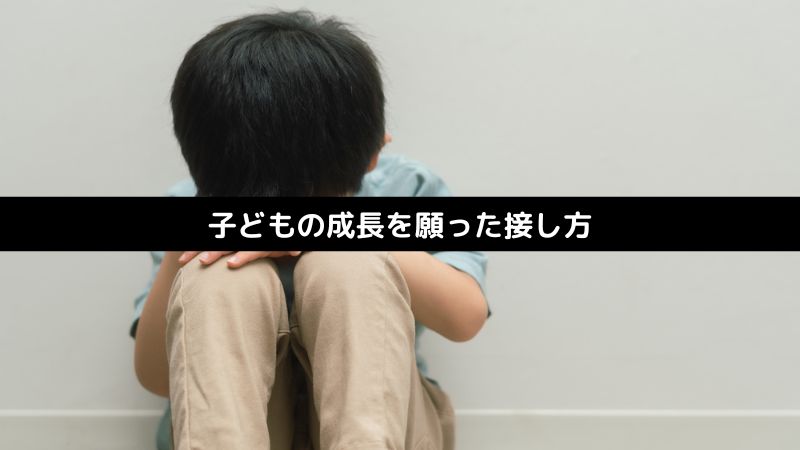皆さんの周りに、例えば「靴ひもがうまく結べない」、「キャッチボールが苦手である」、「消しゴムを使うと毎回のように紙が破れる」など、人並み外れて不器用であり、極端に運動が苦手な子どもはいませんか。
そうした症状を繰り返して認める際には、「発達性協調運動障害(発達性協調運動症)」の可能性があり、本疾患は手と手、目と手、足と手など複数の身体部位を協調させて実行する運動など日常生活において様々な操作が著しく困難になる状態を指しています。
今回は、「発達性協調運動障害」について説明していきます。
目次
発達性協調運動障害とは

統計学的には、5歳から11歳の小児期から学童期にかけての子ども事例においては、約5%程度が本疾患を発症していると考えられており、主に女児より男児のほうがその罹患率が高いことが知られています。
基本的に、簡単な運動をする際にも、それらの動作をスムーズに行うためには、誰しもが目で空間的な位置を確認し、自分自身と対象との距離を評価して、身体のあらゆる部位を連動してバランスを取ることが必要です。ところが、発達性協調運動障害の場合には、様々な場面で全身の力の入れ具合を調節する、あるいは身体を動かすタイミングを上手に調整するなどの情報統合ができずに、人並みに順調に運動することや作業動作することが難しくなります。
よくある相談の例(モデルケース)
10歳代 男性
Aさんは現在大学2年生の男性で、発達性協調運動障害(DCD)による問題を抱えていることに悩んでいます。彼は幼少期から運動が得意ではなく、同年代の子どもたちと比べて身体的な能力に大きな差がありました。例えば、運動会でのリレーや体育の授業では常に遅れを取ってしまい、チームメートに迷惑をかけることが多かったです。小学校の頃は、クラスメートから「運動音痴」とからかわれることもあり、そのたびに自信を失っていました。
中学時代には、自分の運動の苦手さをどうしても隠したいという思いから、体育の授業やスポーツ活動に参加しなくなり、友人との関係も徐々に疎遠になっていきました。高校に進学してからも、体育の授業では同じように運動ができず、部活動への参加も積極的に避けるようになりました。進学後も、身体的な協調性が求められる場面ではうまく対応できず、大学のグループワークやサークル活動でも、他のメンバーとの連携が難しく感じることが多く、焦りや不安が積もっていきました。
彼がカウンセリングを受けるきっかけは、大学での生活が続く中で精神的な疲れを感じるようになり、自分の問題を解決したいという思いからでした。ある日、友人に勧められて、発達性協調運動障害の可能性があることを知り、思い切って専門のカウンセラーに相談することを決心しました。
初めてカウンセリングに訪れたAさんは、最初は自分の症状について語ることに抵抗を感じていましたが、カウンセラーとの対話を重ねるうちに少しずつ自分の問題に向き合えるようになりました。カウンセリングの中で、Aさんは自分の運動の不器用さや協調性の欠如が、単なる「努力不足」や「根性が足りない」というものではなく、発達的な背景があることを理解しました。この認識が、Aさんにとって非常に大きな意味を持つものでした。
カウンセリングを続けるうちに、Aさんは自分の特性に合ったストレス管理方法や、日常生活での工夫を学びました。例えば、身体を使う課題に取り組む際には、無理に力を入れず、呼吸法やリズムを意識して取り組むようになりました。また、グループワークやサークル活動では、自分の得意な分野で積極的に貢献し、周囲のメンバーと協力する方法を学びました。これにより、少しずつ自信を取り戻し、日常生活での不安やストレスも軽減していきました。
現在では、Aさんは大学での生活を楽しめるようになり、他の学生と積極的に関わることができるようになりました。体育の授業やスポーツ活動でも、以前よりは自分のペースで取り組むことができ、失敗を恐れずに挑戦することができるようになっています。また、カウンセリングを通して自己理解が深まり、自分のペースで着実に成長することができるようになったことに満足しています。
発達性協調運動障害の原因

例えば、妊娠中に母親が過度のアルコールを摂取したことが影響して、早産、あるいは低出生体重児で出産した際には、その子どもが発達性協調運動障害を罹患する割合が上昇するという見解が存在します。
また、発達性協調運動障害は注意欠陥多動性障害、学習障害、アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症などを始めとする発達障害との併発が多いと言われているため、共通する遺伝的要因が関与していると疑われています。
そうした発達障害についての詳細は以下のページをご覧ください。
発達性協調運動障害の症状や特徴

学童期になれば、定型発達の小児であれば誰でも順調に実行できるような簡単な運動動作でも、その特徴的な不器用さは現れて、「床にボールを弾ませて蹴る」、「片足でバランスを取る」、「字を書く」などの簡単な協調運動においても困難さが認められます。
発達性協調運動障害の場合は、運動のぎこちなさがあり、年齢相応の身辺自立課題の遂行が難しく、手先の不器用さの代表例として箸がうまく使えないことも挙げられています。
これらの発達性協調運動障害に関連する症状そのものは、成長して大人になれば少しずつ目立たなくなっていきますが、ほとんどの場合には根底にある不器用さは成人になっても継続するとも考えられています。
知的能力が平均以上のケースでは、成人して不器用さを他の方法でサポートできることも想定されますが、上手に身体を動かせないという理由から、他者と比べて自尊心が低い、あるいは学業や業務上の問題を有する場合も多いと考えられます。
Aさんは幼少期から運動が苦手で、体育などでは常に遅れを取っていました。こうしたことは発達性協調運動障害の顕著な特徴と言えるでしょう。
発達性協調運動障害の検査や診断

ただし、年齢が低ければ低くなるほど、得意な運動や困難な動作は個々によってもともと大きく違いがありますので、発達性協調運動障害の有無は慎重に評価されなければなりません。
はさみなどの文房具を使用する、書字を行う、自転車に乗るなどの協調運動を遂行することが、生活年齢などの条件に応じて期待されるよりも明らかに劣って学業や就労活動に支障を呈している場合には、本疾患を疑うことになります。
また、これらの運動技能障害が、脳性麻痺、筋ジストロフィーなど知的能力障害や運動動作を支配している神経系の異常疾患によるものではないことも、適切な診断を付けるうえで確認しておくべき事項となります。
発達性協調運動障害のDSM-5における診断基準
以下の4つ全てに該当した時には発達性協調運動障害と診断される。
- 協調運動技能の獲得や遂行が、その人の生活年齢や技能の学習および使用の機会に応じて期待されているものよりも明らかに劣っている。その困難さは、不器用(例:物を落とす、または物にぶつかる)、運動技能(例:物を掴む、はさみや刃物を使う、書字、自転車に乗る、スポーツに参加する)の遂行における遅さと不正確さによって明らかになる。
- 診断基準Aにおける運動技能の欠如は、生活年齢にふさわしい日常生活動作(例:自己管理、自己保全)を著明および持続的に妨げており、学業または学校での生産性、就労前および就労後の活動、余暇、および遊びに影響を与えている。
- この症状の始まりは発達段階早期である。
- この運動技能の欠如は、知的能力障害(知的発達症)や視力障害によってはうまく説明されず、運動に影響を与える神経疾患(例:脳性麻痺、筋ジストロフィー、変性疾患)によるものではない。
引用:DSM-5
Aさんの場合、カウンセラーがカウンセリングの中で幼少期の聞き取りを行い、発達性協調運動障害の可能性が示唆されました。
発達性協調運動障害の支援と療育

(1)発達性協調運動障害の療育やリハビリ
発達性協調運動障害によってどんなに運動や日常動作が上手にできなくても、体を動かすことがもともと嫌いな子どもはほとんどいないことを忘れてはいけません。
発達性協調運動障害を患っている人にとっては、他者と比較されずに安心して運動などに挑戦できる目標を達成した喜びや嬉しい感情は患者さんを前向きな気持ちにさせることができます。特に、発達性協調運動障害を抱えている子どもたちは、定型発達児のように自然にあらゆる運動動作が上達していくことは期待できないので、療育やリハビリを実践するうえで大人が積極的に介入していく必要性が高いと考えられます。
基本的には、障害を有する子ども本人がやりたいことや出来るようになりたい目標を尊重して、周囲の方々は具体的なアドバイスやサポートを与えることで当該本人が自然に動作を改善できるように手助けすることが勧められます。近年では、運動プログラムを多く取り入れた療育リハビリも盛んに実施されており、例えば休日に家族で公園のアスレチックなどで色々な体の動きを経験する、あるいは共同して粘土遊びやブロックの組み立てなどを楽しみながら実践することも推奨されています。
Aさんは幼少期には運動が苦手なことについて、努力不足、運動音痴としてしか理解されておらず、発達性協調運動障害についての支援や療育はおこわなれませんでした。もしAさんは幼少期から発達性協調運動障害の可能性が周囲に疑われていれば、もう少し早くに支援を受けることができていたかもしれません。
(2)発達性協調運動障害の心理的支援やカウンセリング
発達性協調運動障害を抱えている子どもたちは、そもそも病識の理解不足などによって周囲からの支援を受けにくく、日常生活の学習場面などにおいても、本人の心に大きな負担がかかっていると言われています。
例えば、他の子どもたちのように縄跳びがうまく飛べない小児に対して、「十分に練習が足りない」、「態度がだらしない」などと誤って認識して、反復練習を強いる指導方法を行うとさらに事態を悪化させて本人の自尊心を傷つけるなど悪循環を呈する恐れがあります。
発達性協調運動障害が発達障害のひとつであることを十分に理解したうえで、本人には挫折感や屈辱感を必要以上に与えないように、その都度丁寧にサポートを行うなど合理的な心理的支援を実行することが重要な観点となります。最悪のケースでは、自尊心が傷つけられた子供は、虐待やいじめなどのターゲットになることで二次的な精神障害まで発展することが懸念されますので、適切な心理的サポートを実践することを心がけましょう。
Aさんは大学で発達性協調運動障害の可能性が疑われました。そして、発達性協調運動障害そのものを治療するというよりも、それにまつわる不便を工夫によって乗り越えたり、自尊心を取り戻したりするようなカウンセリングを行いました。
(3)発達性協調運動障害の人への接し方
家族や友人が発達性協調運動障害だった時の接し方として重要なポイントは、運動動作において上手や下手にこだわらずに苦手なことを非難的に評価しないことです。
例えば、発達性協調運動障害を有する子どもが一生懸命運動をやっているが身体が上手くついていかない状況を保護者が見て、「ふざけないできちんとやりなさい」など高圧的に批判してしまうと、子どもは積極的に身体を動かしたいと思えなくなります。「はりきって運動しているね」などと応援して頑張っていることを認めてあげれば、子どもは楽しく運動を続けられて、他の色々な遊びや動作に挑戦しようという感情が芽生えます。
発達性協調運動障害や発達障害についてのトピック
発達性協調運動障害(DCD)についてのよくある質問
発達性協調運動障害(DCD)は、運動技能の発達が通常よりも遅れ、手と手、目と手、足と手などの複数の身体部位を調和させて行う運動が困難な状態を指します。この障害を持つ人は、物を持ったり、運動したりする際に細かい動作が難しいと感じることが多いです。例えば、手先が不器用でお箸を使うのが難しい、文字を書くのが遅い、ボタンをうまく留めることができない、スキップや片足ケンケンができない、転びやすいなどの症状が現れます。運動の協調性が低いため、日常生活のさまざまな場面で困難を感じることがあります。DCDは脳の運動を制御する部分に影響を与え、感覚運動スキルに支障をきたしますが、運動能力以外には知的障害や言語能力に問題はないことが多いです。このため、早期に発見し、適切な支援を行うことが重要です。
DCDの原因は完全には解明されていませんが、遺伝的な要因や神経発達の過程における問題が関係していると考えられています。具体的には、脳の運動を担当する部分が適切に発達しない、または発達が遅れることが原因とされています。これにより、身体の動きに必要な協調性が欠け、日常的な運動技能に支障をきたすことになります。また、妊娠中の母体の健康状態や出産時のトラブルなども影響を与える可能性があるとされています。ただし、DCDの発症に至る原因は複数あり、遺伝や環境の影響も絡んでいるため、単一の原因で説明することは難しいです。研究が進んでおり、今後の医学的な発展によって、より明確な原因解明が期待されています。
DCDの診断は、専門医による問診や診察、そして発達歴の確認を基に行われます。最初に医師は、運動能力の評価を行い、子どもの発達に関する情報を収集します。また、標準化された運動テストを使って、子どもがどの程度の運動能力を持っているかを判断します。この段階で、運動の協調性やバランス、運動の精密さなどが評価され、DCDの疑いが強い場合は、さらに詳しい検査が行われることがあります。診断には、身体的な検査とともに、他の発達障害や注意欠陥障害、学習障害などの可能性も考慮しながら行います。DCDは、知能や感覚に問題がない場合でも運動能力に特化した診断が必要となるため、発達心理学や運動療法の専門家と連携することが重要です。診断を受けた後は、適切な支援と介入が求められます。
DCDは完全に治るわけではありませんが、適切な支援やトレーニングによって、症状を軽減することは可能です。治療の中心は、運動療法を取り入れて、身体の協調性を向上させることにあります。専門家による定期的なリハビリテーションや運動プログラムを通じて、手先の器用さやバランス感覚、協調的な動きの改善を目指します。具体的には、感覚運動のトレーニングや協調運動を促す活動を行い、運動能力が低いと感じている子どもや成人が自信を持てるようにします。また、個別の支援が求められるため、家庭や学校でのサポートも重要です。大人になっても、生活の中で特定の運動や作業に困難を感じることがあるかもしれませんが、支援があれば仕事や社会生活に十分に適応することができます。
DCDの子どもに対する支援は、専門家による運動療育や、発達障害に理解のある医師、カウンセラーとの連携が中心となります。まずは、医療機関での診断を受け、専門家からのアドバイスをもとに、個別の支援計画を立てることが重要です。特に、運動能力に関する課題に対応するためには、運動療法や感覚運動トレーニングを行い、子どもが日常生活をよりスムーズに送れるよう支援します。家庭でできるサポートとしては、家でできる運動やボール遊び、手先を使う作業(例:パズルや折り紙)を行い、遊びながら協調運動を鍛えることが効果的です。また、学校では、体育の授業やその他の活動において、個別の支援が求められます。教師やスクールカウンセラーと連携し、子どものペースに合わせた支援を行うことが、社会生活においての自信を高める鍵となります。
DCDの子どもは、学校生活においても特別な支援が必要です。特に、運動能力に関わる課題があるため、体育の授業での配慮や、日常生活の中での手先を使う作業に対するサポートが求められます。教師やスクールカウンセラーと連携し、子どもの個別のニーズに合わせた支援を提供することが大切です。例えば、体育の授業で体力に応じた内容に調整したり、書字や読み書きに関する困難を軽減するための特別な支援が行われます。また、学校の行事や外遊びにおいても、子どもが他の子どもたちと平等に参加できるよう配慮が必要です。学校全体で子どもの自尊心を高める環境を整え、友達関係を築くための支援を行うことが大切です。
DCDの子どもでも、適切な支援と努力を通じて、さまざまな職業に就くことが可能です。特に、運動能力よりも知識やコミュニケーション能力が重視される職業においては、大きな可能性を発揮することができます。例えば、事務職、デザイン、ライティング、IT業界など、運動能力を必要としない分野では十分に活躍できるでしょう。また、身体を使う職業でも、作業方法を工夫したり、支援を受けながら仕事を進めることが可能です。大切なのは、自分の得意分野を見つけ、それに合わせたサポートを受けながら、目標に向かって進んでいくことです。早期の支援が将来の職業選択においても有利に働きます。
DCDの症状は、必ずしも成長とともに改善するわけではありません。大人になっても、手先が不器用であったり、運動に関する困難を感じることがあります。しかし、適切な支援と努力によって、社会生活や職業生活で適応することは可能です。大人になった場合、日常的な作業においても自分なりの工夫をしながら生活していくことができます。職場での支援を受けることで、十分にパフォーマンスを発揮できる場合も多いため、必要に応じて職場環境の調整やサポートを求めることが重要です。また、運動能力が低いことに対する自信を高めるために、リハビリテーションや運動療法を続けることも有益です。
DCDの改善には個人差がありますが、支援やトレーニングを受けることで、少しずつ改善が見られることが多いです。運動療法やリハビリテーションは、長期間にわたって行うことが必要であり、早期の段階から適切なサポートを受けることで、改善のペースが早くなることがあります。具体的な改善の時間は、子どもや成人それぞれの状態により異なりますが、継続的な支援と努力を通じて、日常生活での動きや仕事に対する自信が高まることが期待されます。支援を受けながら改善を目指すことが大切です。
DCDは他の障害と併発することがあります。特に、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、不安障害などと併発することが多いとされています。これらの障害がある場合、運動障害だけでなく、学習面や社会的な適応にも課題が生じることがあります。そのため、DCDを持つ子どもや成人が他の障害を併発している場合は、総合的な支援が必要です。診断を受ける際には、運動障害だけでなく、他の障害についても評価し、適切な支援を行うことが重要です。
(株)心理オフィスKで発達性協調運動障害に対するカウンセリングを受ける

運動発達レベルは個人差が大きい分野ですが、年齢や動作内容に関係なく、個々のペースに合わせて、無理なく患者さん自身が楽しめる経験を沢山させてあげることが重要であり、繰り返して様々な経験を通じて少しずつ運動能力などが向上していくこともあります。
さらに、発達性協調運動障害の方は心理的な苦痛や自信の喪失、対人不安を抱えてしまいやすい傾向にあります。その点についてはカウンセリングなどが効果があるでしょう。
(株)心理オフィスKではこうした発達性協調運動障害の方やそのご家族に対するカウンセリングや心理支援を行っています。ご希望の方は以下の申し込みフォームからご連絡ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。
- 武田朋恵 他「箸を握り持ちしている発達性協調運動障害児 一症例に対する箸操作性向上の取り組み」 作業療法の実践と科学. 2020年 2巻2号 p.34-39
- 東恩納拓也(著)「運動の不器用さがある子どもへのアプローチ 作業療法士が考えるDCD(発達性協調運動症)」クリエイツかもがわ 2022年
- 中井昭夫(編)「イラストでわかるDCDの子どものサポートガイド: 不器用さのある子の「できた!」が増える134のヒントと45の知識」合同出版 2022年
- 辻井正次、宮原資英(監修)「発達性協調運動障害[DCD]: 不器用さのある子どもの理解と支援」金子書房 2019年
- 宮原資英(著)「発達性協調運動障害:親と専門家のためのガイド 第2版 増補版」スペクトラム出版社 2020年