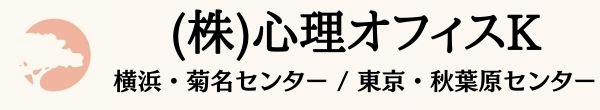仕事を辞めたい!ストレスやメンタルの不調で現れる症状や解決策とは
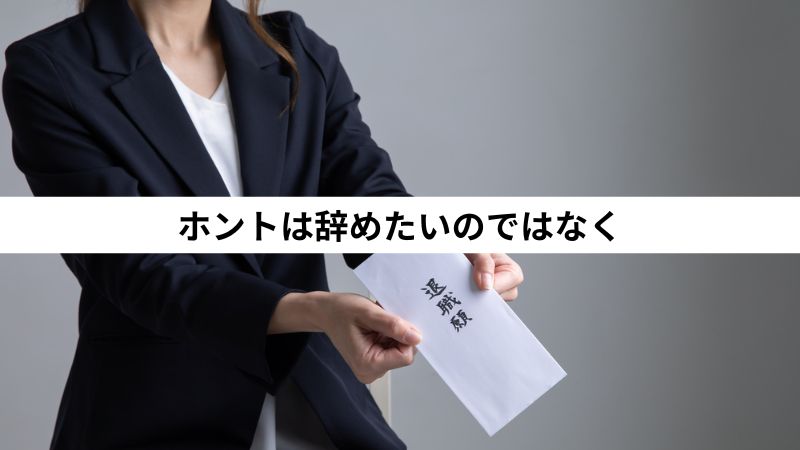
本記事では、ストレスやメンタルの不調により「仕事を辞めたい」と思った際の解決策について紹介します。
仕事では、日々さまざまな作業をこなし、後輩や上司などの同僚との人間関係も構築しなければなりません。そういった日常生活を送っていると、自分でも気付かないうちにストレスを抱え、メンタルに不調をきたすケースもあります。突発的に仕事を辞め後悔しないために、メンタルの不調でどういった症状が現れるのか、どのような解決策をとると良いのかを考えていきましょう。
目次
仕事を辞めたいと思うことについて
「仕事を辞めたい」と感じることは、現代社会で働く多くの人が一度は経験する悩みの一つです。業務量の増加や職場の人間関係、評価へのプレッシャー、仕事へのやりがいの喪失、将来への不安など、さまざまな要因が重なったとき、「辞めたい」という思いは自然に生まれてきます。しかし、実際には生活のための収入を得なければならないことや、社会的な立場、責任感、職場や家族への迷惑を考えると、なかなか簡単に辞める決断ができずに葛藤を抱える方も少なくありません。そのため、「辞めたい」という気持ちを持ちながらも我慢し続けてしまい、心身の不調やうつ状態に陥るケースも見受けられます。
このようなときは、まず自分自身の気持ちや状況を冷静に見つめ直すことが大切です。仕事を辞めたいと思う理由を整理し、今の状態で無理を続けていないか、自分の限界を超えていないか確認しましょう。また、信頼できる家族や友人、職場の同僚に相談することで、孤立感や不安が和らぐ場合もあります。さらに、心療内科やカウンセリングなど専門家に相談することで、心身の回復や新たな選択肢を見つけるきっかけになることもあります。自分の人生を大切にするために、時には「立ち止まる勇気」を持つことも重要です。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは幼少期から人間関係において気を遣うタイプでした。小学生の頃から両親は共働きで、兄妹の面倒を見たり、家の手伝いを積極的にこなしてきました。両親は厳格というよりは、子どもに自立を求める傾向が強く、Aさん自身も「周囲の期待に応えなければならない」と感じて成長してきました。社会人になってからもその姿勢は変わらず、与えられた仕事を真面目にこなし、職場の同僚や上司にも気を配りながら働いていました。
しかし、数年前から業務量の増加や人間関係の軋轢が重なり、次第に精神的な負担を強く感じるようになりました。休日も仕事のことが頭から離れず、睡眠が浅くなり、朝起きるのがつらい日が続きました。徐々に「自分はこの仕事に向いていないのではないか」「もう辞めたい」という気持ちが強くなり、出勤前になると動悸や吐き気が現れることも増えていきました。職場に行くことが苦痛となり、心療内科を受診したところ、適応障害と診断され、一定期間の休職を勧められました。
休職中は薬物療法によって気分の落ち込みや不安症状がやや軽減しましたが、「このまま社会復帰できるのだろうか」という不安も強く残りました。そんな折、職場の復帰支援として会社のEAP(従業員支援プログラム)を通じてカウンセリングを受けることになりました。初回のカウンセリングでは、Aさんはこれまでの経緯や苦しさを丁寧に語りました。カウンセラーからは、「頑張りすぎてしまう自分」や「他人の期待に応え続けることによる疲弊」について指摘され、Aさん自身もその傾向を自覚するようになりました。
カウンセリングの中では、「自分の気持ちや限界を知ること」や「職場でのコミュニケーションの取り方」「休むことへの罪悪感」について丁寧に話し合いました。少しずつ、「すべてを完璧にこなす必要はない」「自分のペースで仕事を続けていけばいい」という考え方に変化していき、気持ちの余裕が生まれてきました。精神的に落ち着きを取り戻すとともに、「辞めたい」という思いは徐々に和らぎ、「もう一度、無理のない範囲で働きたい」と感じるようになりました。
現在は段階的に職場復帰を進めており、以前よりも自分の気持ちを大切にしながら仕事に取り組めています。Aさんは「困ったときは誰かに相談すること」「自分を追い詰めすぎないこと」の重要性を学び、以前よりも前向きな気持ちで日々を過ごしています。
仕事を辞めたい!その理由は?
誰しも多かれ少なかれ、1度は「仕事を辞めたい」や「仕事に疲れた」と思ったことがあるはずです。人によって理由はさまざまですが、仕事を辞めたい理由には、どういったものがあるのでしょうか。
Aさんは、仕事量の増加や職場の人間関係のストレスが重なり、「自分はこの仕事に向いていないのでは」と悩むようになりました。その結果、精神的な負担が強まり、仕事を辞めたいと強く感じるようになりました。
(1)給与・待遇面
給与や待遇面の不満で仕事を辞めたいと感じることがあります。自分が変わることで変化するものではないため、現状を変えるのが難しいという面がネックです。
「仕事量と給与が見合っていない」や「適正な評価を受けられない」場合は、仕事へのモチベーションがどんどん下がっていくことになるでしょう。
(2)人間関係
仕事を辞めたい理由で、給与や待遇面と並んで多い理由が、人間関係です。しかし、厚生労働省が行った「第6回21世紀成年者縦断調査」によると、「仕事を辞めた者の退職理由」で人間関係をあげた方は比較的少なく、全体の13%ほどでした。
ただし、エンジャパンが行った「退職理由のホンネとタテマエ」のアンケートで、本当の退職理由としてあげたものは人間関係が最多。社内でのいじめや先輩・後輩との関係構築など、人間関係によるトラブルが退職に影響することは否めません。
(3)業務内容
業務内容が自身の性格や適正に向いていないという理由も考えられます。また、自分がイメージしていた仕事をさせてもらえないなどのギャップによって、退職を考えるケースも。
例えば、入社する前は華やかな仕事に見えたとしても、実際入社してみると同じ作業ばかりさせられるなどの理由です。理想と現実とのギャップが大きいと、モチベーションを保ちにくくなるでしょう。
(4)社風と合わない
会社によって方針や社風があります。長年にわたって築き上げたもののため、一社員が変えることはなかなか難しいでしょう。そのため、社長の考え方や職場の雰囲気に合わせられないと感じると、仕事を辞めたいと考えるようになってしまいます。
(5)キャリアアップへの迷い
仕事をしていくと「このままで良いのか」や「もっと違う分野の仕事をやりたい」などのキャリアに関する迷いが出てくることもあるでしょう。また、正当な評価がなされないことで、今後のキャリアアップが見込めない場合などは、転職の二文字が頭をよぎるはずです。
仕事を辞めたいのに辞められない…どうして?
ここでは、仕事を辞めたいのに辞められない理由について考えていきます。
仕事を辞めたい理由はたくさんあるものの、実際には行動できない方も。嫌な仕事を続けると、身体的にも精神的にも悪影響が出る可能性があるにも関わらず、どうして仕事を辞められないのでしょうか。
Aさんの場合、幼い頃から「周囲の期待に応えなければならない」という思いが強く、責任感や罪悪感からなかなか仕事を辞める決断ができませんでした。「迷惑をかけたくない」という気持ちも、辞められない理由の一つでした。
(1)引き止められる
「仕事は続けるもの」という概念から、上司から引き止められて辞められない場合があります。年配の方は、同じ会社に長く勤め、その会社で円満退社することを理想としているためです。
その概念を持ち出された場合、仕事を辞めることをなかなか理解してもらえないケースもあるでしょう。
(2)甘えだと叱責される
「仕事が辛い」「やりたい仕事ができない」と家族や上司に相談した場合、「甘え」だと叱責されることも。たしかに、実績を積むことで知識や技術を習得し、やりたい仕事ができるようになったり、仕事が辛いと思わなくなったりすることもあるでしょう。
しかし、やりたくない仕事を耐え続けると、身体に不調をきたすこともあります。
(3)収入がなくなることが気がかり
当たり前のことですが、仕事を辞めると収入がなくなります。まとまった貯蓄や退職金などがあれば、しばらくの生活は安心でしょう。しかし、貯蓄や退職金がないと、生活が行き詰まってしまいます。
そういった今後の生活を考えて、仕事を辞めたくても辞められないという方も多いでしょう。
こんな症状が出たら注意!立ち止まるタイミングかも
ここでは、立ち止まるタイミングである注意すべき症状について紹介します。
仕事を辞める理由は人の数だけあり、1つの理由ではなく、さまざまな理由が複合的に組み合わさっていることもあります。「仕事を辞めたい」と感じた場合には、理由を客観的に考えてみましょう。自身の技量や知識不足が問題であれば、その点を補うことが先です。
ただし、責任感が強い方などの場合、仕事でのストレスが原因で、不調が起きていることもあります。そういった際には、一旦立ち止まる必要があるでしょう。
Aさんは、朝になると動悸や吐き気が現れたり、夜眠れなくなるなどの身体症状が出てきました。また、気分の落ち込みや不安も強くなり、日常生活にも影響が出始めました。
(1)イライラする
些細なことでもイライラして後輩にあたったり、仕事が手につかなくなったりするケースも。イライラするだけでなく、焦りや不安にかられる方もいます。
(2)気持ちが落ち込む
やる気がなくなり気持ちが落ち込むという症状が出る方も。無関心になったり、マイナス思考になったりするケースもあります。
(3)仕事でミスが増える
集中力が低下することで、仕事でミスが増えるケースも。ぼんやりしていることが増え、話しかけても的確な返事がない場合もあります。
(4)身なりを気にしなくなる
気持ちがふさぎがちになったり、ぼんやりすることが増えたりすると、身なりを気にしなくなることもあります。
(5)体調を崩す
精神症状として現れる方もいますが、体調面に変化が現れる方も。例えば、不眠や頭痛、吐き気、肩こり、腰痛、食欲不振・過食などです。
(6)休みがちになる
心と身体のバランスが崩れてくると、遅刻や欠勤が増えてきます。気持ちが落ち込みマイナス思考になったり、意欲がなくなったりすることで、会社へ行くことが億劫になってしまうのです。
退職前にできる解決策とは
最後に、退職前にできる解決策について見ていきましょう。
「仕事を辞めたい」と思ってすぐに行動したほうが良い場合もありますが、行動に移したあとで「辞めなければ良かった」と思うこともあります。解決できる問題であれば、解決して仕事を続けるということも可能です。
退職前にどういった行動をとると良いのかを紹介します。
(1)医師に相談
体調不良や精神的な落ち込み等がある場合は、まずは医師に相談しましょう。治療によって症状が改善することも。また、受診することで、他の病気が原因だとわかることもあります。
その他には、退職後にハローワークなどで支援を受ける際に、医師の診断書が必要になることもあるためです。
Aさんは心療内科を受診し、適応障害と診断されました。医師からは休職を勧められ、薬物療法を受けることで少し気持ちが楽になりました。
(2)家族や同僚に相談
家族や同僚に相談するのもおすすめです。人に悩みを相談することで、頭の整理や気持ちの整理ができることがあります。信頼できる人が近くにいる場合には、1人で抱え込まず頼ることも大切です。
Aさんは家族や信頼できる同僚に自分の状態を打ち明け、サポートを受けました。話を聞いてもらうことで孤立感が軽減しました。
(3)休職を活用する
「体調を崩す=退職」ではなく、休職制度を活用するのも有効です。精神的に辛い場合や体調を崩している場合は、休職期間を使って療養することで、仕事復帰できるようになるかもしれません。
また、退職してすぐに次の仕事が見つかるという保証はありません。休職期間に転職の準備をするというのも一つの方法です。
Aさんは医師の指示で一定期間の休職を選択し、心身の回復に努めました。休むことで心に余裕が生まれました。
(4)カウンセリングを受ける
カウンセラーに相談することもおすすめです。うつ病が軽快したり、相談できる人がいることの安心感によって、「仕事を辞めたい」という気持ちがなくなったりすることもあるでしょう。
家族や友人に相談する方もいますが、心配するあまり「仕事を辞めるのはもったいない」や「収入は?今後はどうするの?」などと言われ、追い込まれることがあります。そのため、近しい人にこそ言えないという方も。
カウンセラーであれば、カウンセリングのプロのため、客観的に相談にのってもらえ、解決に向かうための力強いサポートを得られるという点がメリットです。
Aさんはカウンセリングを受けることで、「頑張りすぎる自分」に気づき、自己理解が深まりました。徐々に気持ちも前向きになり、仕事を続ける意欲が戻ってきました。
まとめ:まずは立ち止まって焦らず答えを出そう
「仕事を辞めたい」と感じると、すぐに行動に移す方もいますが、なかなか行動できずに心や身体を崩してしまう方もいます。勢いで退職すると、のちのち後悔するかもしれません。他方で、我慢し過ぎて、社会生活を送りづらくなっても困ります。
いずれの場合も、まずは立ち止まって現状把握することが最優先です。休職制度を活用したり、病院の受診やカウンセリングを受けたりすることで、心身のケアをしていきましょう。
当オフィスには、心身のケアを専門に行うカウンセラーが在籍しております。お気軽にご相談ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。