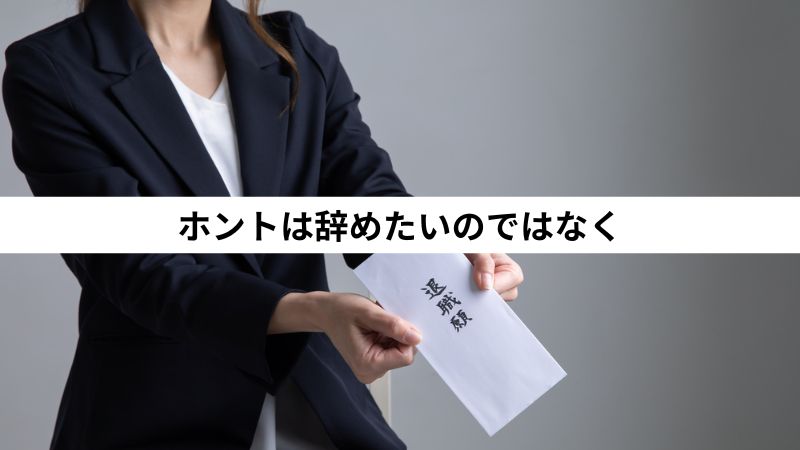メンタル不調を治すために必要なこととは?プロが教えるアプローチとは

本邦においてメンタルヘルスの不調で医療機関などに定期的に通院する方は約420万人にも上り、また人生の一生涯を通じておよそ5人に1人が心の病に罹患すると指摘されているほどにメンタルヘルス不調は誰にでも起こりうる身近な病気と考えられます。
今回は、メンタル不調を治すために必要なことなどについて説明していきます。
目次
メンタル不調とは?その種類や症状について
厚生労働省によると、メンタル不調とは「精神および行動の障害に分類される精神障害のみならず、ストレスや強い不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える精神的および行動上の問題を幅広く含むもの」と定義づけられています。
メンタル不調の主な症状は、憂鬱な気持ちが続いて焦燥感や不安感に駆られる、夜眠れなくなった、喜びや嬉しさなど表情が乏しくなる、遅刻や欠勤が増えた、今まで当たり前にできていた基本的な動作などができなくなった、仕事のミスが増えるなどが挙げられます。
メンタル不調の状態が続くと本人の生活能力や仕事の効率に重大な悪影響を及ぼしてしまう可能性がありますし、症状が重症化すると毎日の規則正しい生活や仕事を続けられず、長期的な療養が避けられない事態となりますので注意が必要です。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは幼少期から真面目で周囲の期待に応えようと努力する一方で、自分の気持ちを表現することが苦手でした。両親は共働きで忙しく、Aさんはいつも「迷惑をかけてはいけない」「自分のことは自分で何とかしなければ」と感じて育ちました。小学校では友人関係に恵まれていましたが、中学・高校と進学するにつれて、集団の中で自分の居場所を探すのが難しくなり、悩みを誰にも打ち明けられないまま過ごしていました。
社会人になってからは、責任感が強く業務もきちんとこなしていましたが、次第に仕事の量や人間関係のストレスが積み重なっていきました。上司からの期待に応えようと無理を重ね、同僚とのコミュニケーションもうまくいかなくなり、休日も仕事のことが頭から離れなくなりました。次第に眠れない日が続き、朝になると体が重く、職場に行くのが苦痛になっていきました。また、食欲の低下や頭痛、倦怠感などの身体的な不調も現れるようになり、「このままではいけない」と思いながらも誰にも相談できず、一人で抱え込んでいました。
やがてAさんは、通勤途中に動悸や息苦しさを感じたり、涙が止まらなくなったりすることが増えていきました。心配した家族に勧められて心療内科を受診したところ、「適応障害」と診断され、薬物療法とともにカウンセリングを勧められました。初めてのカウンセリングでは、自分の気持ちを言葉にすることに戸惑いがありましたが、カウンセラーとの対話を重ねるうちに、幼少期から「頑張らなければ認められない」という思い込みが強く根付いていたことに気付くようになりました。また、「弱音を吐いてもいい」「人に頼ってもいい」と少しずつ自分を許す気持ちが生まれていきました。
カウンセリングでは、ストレスとの向き合い方や自分の感情を整理する方法、仕事とプライベートのバランスのとり方などを話し合い、少しずつ自分自身を取り戻していきました。やがて、Aさんは自分の限界を認め、無理をしすぎないことを覚え、徐々に眠れるようになり、職場への復帰も果たしました。現在では、自分のペースを大切にしながら生活できるようになっています。
メンタル不調の原因とリスクファクター
主に、仕事場や職場環境では残業や早出勤務を余儀なくされて所定外労働時間が長い人がメンタル不調に陥りやすいと言われています。
それ以外にも、ひとりで多くの仕事を抱え込んでいる、周囲に相談できる人がいない、熱心に取り組むも周囲から評価してもらえない、自分のペースで勤務作業を進めることが出来ずに融通が利きにくい、職場での役割が大きく変化した場合にも心理的負担が増大すると考えられています。
メンタル不調の原因は仕事だけとは限らず、自分自身や家族の健康問題、人間関係のトラブルや経済的困窮など、労働以外の要素でメンタル不調に陥るケースも少なくありません。
仕事がいくら順調であっても私生活で様々なストレスや難題を抱えている人では、職場で状況を把握しづらいために労働環境において適切なサポートが難しい場合も多いと考えられます。
Aさんの場合、幼少期から「周囲に迷惑をかけてはいけない」という思い込みが強く、自己主張や助けを求めることが苦手でした。職場での過重な責任や人間関係のストレスが重なり、長期間にわたる無理がメンタル不調の主な原因となりました。
メンタル不調の治し方についての実践的なアドバイス
(1)メンタル不調を自宅で改善するための方法
仕事や家庭のストレスは適切に対処すればある程度緩和されて、メンタルヘルス不調を未然に防止することができ、数々のストレスに向き合うにあたって「何がストレスを引き起こしているかを知ること」が重要なポイントとなります。
個々によって感じるストレスの要因は様々あって、環境などの外的要因もあれば、人それぞれにおける内面の問題もありますので、ストレスチェックなどを利用してストレス要因を自分なりに把握することで、効果的に自宅でストレスに対処してメンタル不調を改善することが可能となります。
Aさんは、決まった時間に起床・就寝する、無理のない範囲で日常生活のリズムを整える、好きな音楽や読書でリラックスすることを心がけました。
(2)メンタル不調に効果的な食事と運動
通常、内臓や筋肉など人体をつくるタンパク質はアミノ酸で構成されています。
アミノ酸は学習や記憶につながるドーパミンや、元気を出すノルアドレナリン、気分を安定させるセロトニンといった、行動や気分に指令を与える神経伝達物質をつくるもととなるため、メンタル不調の場合にはアミノ酸を積極的に摂取することをお勧めします。
身体的な健康もメンタルの状態を左右する要素であるため、毎日の生活の中でウォーキングやランニング、ヨガなど自分に適した運動を心がけて実施するのも重要なポイントです。
また、軽いランニングやサイクリングなどの有酸素運動には、特にネガティブな気分を発散させて、心身共にリラックスさせて、睡眠リズムを整える作用があってメンタル不調に効果的であると期待されていますので、日々の生活に取り入れてみましょう。
Aさんは、栄養バランスの良い食事を意識し、朝食を欠かさず摂るようにしました。また、散歩や軽いストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす習慣も取り入れました。
(3)メンタル不調を克服するための習慣
日々のメンタルの状態を良好に維持するためには、健康的な生活習慣を送ることが欠かせません。
例えば、充分な睡眠時間を確保することは、心身の健康を維持する土台となりますし、同じ物事でも悲観的な考え方をするのではなく、ポジティブな捉え方を前向きに実践するだけでもメンタル不調をある程度緩和することができるでしょう。
Aさんは、自分の気持ちを書き出す日記をつけたり、小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を育てるように意識しました。また、必要な時は「休む」ことを自分に許すようになりました。
メンタル不調の人への接し方
(1)職場の上司や同僚が知っておくべきメンタル不調の人への接し方
職場で同僚や部下の体調不良や仕事ぶりの変化に気づいたとき、あるいは自分の同僚や部下から仕事やプライベートに関して悩みを相談されたときに、どうしたらいいか対応に困ってしまうこともあるでしょう。
メンタル不調の個別の事例性に気づきやすいのは、部下である労働者の状況を日常的に把握し、個々の職場における具体的なストレス要因を把握している管理監督者(あるいは上司)であると言われています。
基本的には、同僚や部下の不調を早期的に見つけて、仕事のストレスを少しでも解消できるように声掛けなどを行うことで本人のメンタル不調の発症を食い止めることが期待できますし、上司として部下に日頃から関心を持って接することが重要なポイントとなります。
日常の業務から同僚や部下をこまめに観察し、労働時間や労働環境の調整を行うとともに、必要に応じて相談を受けて、明らかなメンタル不調の症状が認められた際には産業保健スタッフ、専門医療機関や心理カウンセリングへつなぐなど適切な対応を実施しましょう。
Aさんは、上司や同僚が仕事量の調整や配慮をしながら、「困った時は遠慮なく相談してほしい」と温かい声かけをしてくれることが安心感につながりました。
(2)家族が知っておくべきメンタル不調の人への接し方
個人的な要因がストレスになっている場合も周囲からのサポート、生活や仕事の満足度、生きがいなどがあれば緩和される場合が多いため、ストレスに有効的に対処するには、個人による努力だけではなく、家族からの支援も重要です。
メンタル不調を抱えている本人の近しい家族が大きな責務を感じて、治療に際してついつい力が入って一つ一つの言動に気をつけるあまり、ご本人が余計に心配を感じることも懸念されますので、まずは力を抜いて、病気の理解から開始するように意識しましょう。
Aさんの家族は、本人のつらさを否定せず、焦らせることなく「いつでも話を聞くよ」と寄り添う姿勢を大切にしました。
メンタル不調の専門的なケアとは
(1)精神科や心療内科での対応
メンタル不調を来した場合には、比較的症状が軽いうちから精神科や心療内科で専門的なケアや治療を受けることで症状の回復が早まることが多く、メンタル不調の早期発見や早期対応はそれだけ重要性が高い点であるといえます。
メンタル不調は、自分でも周囲からも気づかぬうちに病状が進行している場合があり、疲れているのに眠れない、あるいは好きなことが楽しめない症状が、ほとんど1日中、毎日、1週間以上続く場合には、精神科や心療内科など医療機関の受診が急がれます。
セルフケアなどでのレベルでは対処できないメンタル不調では、時間が経っても顕著に改善されることは少なく、家や勤務先から近くてアクセスの良い通院先などで適切な処置や治療を行うことを推奨します。
Aさんは医師による診断と薬の処方を受け、症状の軽減に取り組みました。
(2)メンタル不調の人へのカウンセリングとは
「自分を責めがちであり、ストレスへの対処方法が判断できない」など、事象のとらえ方や考え方の傾向を変えることで不調を改善したいと希望する場合には、医療機関の治療と並行してカウンセリングを受けると効果が出ることが見受けられます。
メンタルヘルス不調を未然に防ぐには、まずは自分自身のストレス状況を理解し、心身共に日常的にコンディションを整えることが大切であり、悩みなどある場合は一人で抱え込まず公認心理師や臨床心理士などのカウンセラーに相談することも大切です。
カウンセリングについては以下の記事が参考になります。
Aさんの場合、カウンセリングで自分の思いや考えを整理し、ストレスへの対処法を学ぶことで、少しずつ心身の安定を取り戻しました。
メンタル不調についてのよくある質問
メンタル不調とは、精神的な健康が損なわれ、心身のバランスが崩れる状態を指します。症状としては、気分の落ち込み、過度の不安や恐怖、日常的な疲れ、集中力の低下、社会的な孤立感などがあり、これらが長期間続くことで日常生活に支障をきたすことがあります。メンタル不調は、身体的な症状と同じように深刻な問題であることを理解し、適切な対応が必要です。例えば、仕事や家庭の問題、過労、過度のストレスが原因であることが多く、その原因に合わせた対処が求められます。
メンタル不調の原因は多岐にわたりますが、主なものとしては、過度なストレス、生活環境の変化、人間関係の問題、仕事でのプレッシャー、家庭内でのトラブル、健康問題などが挙げられます。特にストレスは心身に多大な影響を与えるため、これが蓄積されるとメンタル不調を引き起こしやすくなります。また、遺伝的な要因や過去のトラウマが影響を与えることもあります。さらに、睡眠不足や不規則な生活習慣が心の健康に悪影響を及ぼすことも多いです。これらの要因が複雑に絡み合って、メンタル不調を引き起こす場合があります。
メンタル不調の症状は、気分の落ち込みや焦燥感、過度の不安、怒りやイライラ感など、心の状態に大きく関わるものです。身体的な症状としては、睡眠障害(眠れないまたは寝すぎる)、食欲の低下または増加、体調不良(頭痛や胃痛など)を感じることがあります。さらに、仕事や家事に対する興味を失い、集中力が低下し、物事に対してのモチベーションが感じられなくなることもあります。これらの症状が長期間続く場合、精神的な健康を回復するためには、早期の介入とサポートが不可欠です。精神的な症状が身体に影響を与えることもあり、精神的・肉体的に健康を回復するためには総合的なアプローチが求められます。
メンタル不調を改善するためには、まず自分の心の状態に気づき、無理せず休むことが最も重要です。ストレスを感じるときには、適度にリラックスできる時間を設け、リフレッシュすることが大切です。休息を取るだけでなく、身体を動かすことも心の健康に良い影響を与えます。定期的な運動は、気分を改善し、ストレスを軽減させる効果があります。食事も心の健康に密接に関係しているため、栄養バランスを意識して食事を取ることが効果的です。また、十分な睡眠をとることも非常に重要です。さらに、信頼できる家族や友人に話を聞いてもらうことや、専門のカウンセラーや医師に相談することが回復の助けになります。必要に応じて、心理療法や薬物療法を受けることも有効です。
メンタル不調を予防するためには、日常的にストレス管理を行うことが効果的です。自分の体調や気分に敏感になり、無理をしすぎないことが重要です。十分な休息を取り、睡眠を確保すること、また、健康的な食事と適度な運動を生活に取り入れることも心身の健康を保つために欠かせません。ストレスを感じたときには、深呼吸や瞑想などのリラクゼーション法を試してみると良いでしょう。さらに、積極的に社交的な活動に参加し、孤立しないよう心がけることも大切です。自分の限界を知り、無理をしないことが予防につながります。メンタル不調が起こる前に、日常的に心のケアを行うことが予防につながります。
メンタル不調を感じているクライエントに対して、家族や友人はまずその気持ちを理解し、寄り添うことが重要です。アドバイスや励ましをするよりも、まずはしっかりと話を聞いてあげることが効果的です。クライエントが自分の気持ちを話しやすい環境を整えることが支えになります。また、クライエントが専門的な支援を必要としている場合は、カウンセリングや医療機関への受診を勧めることも一つの方法です。家族や友人ができることは、無理に問題を解決しようとするのではなく、安心感を提供し、サポートが必要なときに適切なサポートを提案することです。クライエントにとって、家族や友人が理解を示し、支えになることが、回復への第一歩となります。
メンタル不調の治療方法には、心理療法と薬物療法の2つの主な方法があります。心理療法では、カウンセリングや認知行動療法が行われ、クライエントが自身の考え方や行動パターンを見直す手助けをします。特に認知行動療法は、思考を改善することにより、感情や行動を変えることを目的としています。薬物療法では、抗うつ薬や抗不安薬が処方されることがあります。これらの薬は、脳の化学的な不均衡を調整し、症状を軽減するのに役立ちます。また、生活習慣の改善やストレス管理技法も治療の一部として行われます。治療方法は個々の状態に合わせて選択され、長期的な回復を目指して進められます。
職場でメンタル不調のクライエントをサポートするためには、まずその人の状態を理解し、柔軟な対応をすることが求められます。勤務時間の調整や業務内容の変更、休息時間の確保などが配慮されるべきです。また、過度なプレッシャーを避け、安心して相談できる環境を提供することが重要です。特にクライエントが話しやすいように、プライバシーを尊重し、上司や同僚が過度に詮索しないことが必要です。職場でのメンタルサポートは、心理的な安全を保ちつつ、クライエントが回復するためのサポートをすることが中心となります。
メンタル不調を感じた場合、医師の受診は重要です。まず、心療内科や精神科、または一般のクリニックで相談することが一般的です。受診時には、現在の症状や自分の生活環境について詳しく説明することが重要です。また、医師に自分の状態を正直に伝えることで、最適な治療法が提案されます。初めての受診に不安を感じるかもしれませんが、専門医は理解を示し、安心して話せる環境を提供してくれます。必要に応じて、治療の継続や他の専門的なサポートを受けることも考慮されます。
メンタル不調の回復には、個人差が大きく影響します。軽度の不調であれば数週間で改善することもありますが、重度の不調や長期化している場合は、数ヶ月以上かかることがあります。回復の過程では、治療を受けながら自分のペースで進むことが大切です。また、心身の健康を回復するためには、生活習慣の改善やストレスの軽減が不可欠です。治療を継続し、無理せず自分に合ったペースで回復を目指すことが重要です。回復には時間がかかることを理解し、焦らずに自分を大切にしながら治療を続けることが大切です。
メンタル不調のカウンセリングを受けたい

職場の上司や家族がメンタル不調者から相談を受ける際には、病気の理解や本人に対する共感などを持ちながら相手の気持ちを思いやって丁寧に対応することが重要です。
(株)心理オフィスKでもメンタル不調に対するカウンセリングを行っています。専門のカウンセラーが相談にのりますので、ご希望の方は以下の申し込みフォームからご連絡ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。