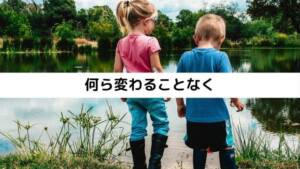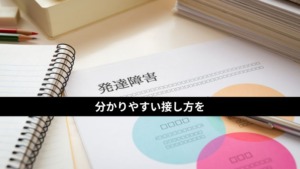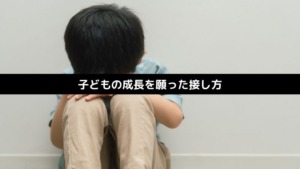発達障害の人に対する職場での接し方について
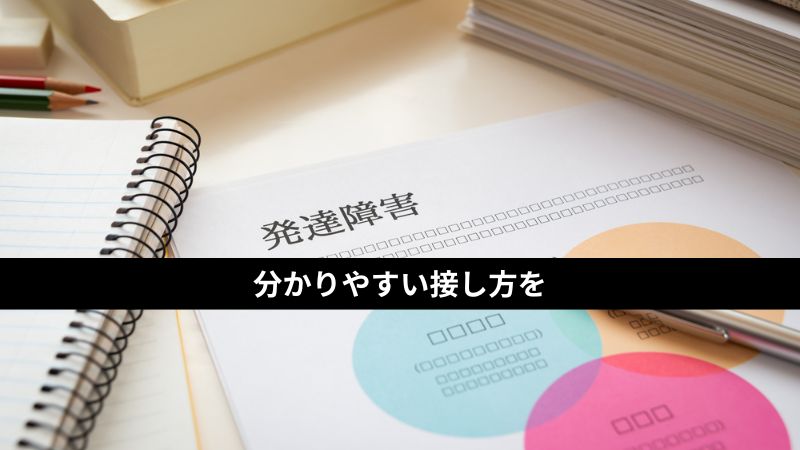
本記事では、発達障害の方と働くうえで知っておきたい接し方について紹介します。
発達障害というと、子どものうちに判明して療育を行うケースがありますが、実は大人になってから発達障害だとわかる方も。また発達障害の方は、10人に1人ほど の割合でいるとされており、職場などの身近な場所に、なんらかの発達障害の特性を持っている方がいる可能性があります。大人の発達障害の特徴を知り、どういった接し方をすると良いのかを見ていきましょう。
目次
発達障害の特性を持つ方の職場での特徴とは
ここでは、職場において大人の発達障害の方が、どういった行動をしやすいのかを紹介します。
自分が発達障害だと気づいている方もいますが、気づいていないケースもあります。また、冒頭で紹介した通り、10人に1人の割合で発達障害を抱えている場合もあるため、身近に大人の発達障害の特性を持った方がいるかもしれません。
職場での人間関係や仕事を円滑に進めるためにも、大人の発達障害の方の行動にどういった特徴があるのか理解しておきましょう。
(1)感情的になりやすい
大人の発達障害の方の場合、部下や同僚がミスをすると、ミスの原因には触れずミスしたことを感情的に怒る傾向にあります。
(2)トラブルが発生するとパニックになる
例えば、取引先との間にトラブルが発生すると、パニックになり突飛な行動に出るケースも。また、冷静さを欠き、事実とは違うことを言ってしまい、さらに混乱させてしまうということもあります。臨機応変に対応することが困難な特性が関連しています。
(3)話がうまく伝わらない
大人の発達障害の方は、人とのコミュニケーションや会話が苦手のため、丁寧に説明しても自分が思っていた内容がうまく伝わらない場合があります。また、理解してもらうためには、何度も同じ説明をしなければならないケースもあるでしょう。
(4)自分流のやり方を変えない
一日の流れや仕事への取り組み方に対して、自分流のやり方を持っている方も。大人の発達障害の方の場合、こだわりが強いため「こうすれば、仕事が早く終わるよ」と新しい方法を提案したとしても、自分流のやり方を貫く傾向にあります。
(5)ミスが多い
「聞いてメモを取る」という行為が苦手で、頼まれた仕事を忘れてしまったり、人の話をしっかり聞いていないためにミスをしたりする傾向にあります。ADHDの不注意という特性が関連していることが多いようです。
(6)電話応対が苦手
大人の発達障害の方のなかには、ワーキングメモリーの弱さから、耳から情報を得ることが苦手な方もいます。この場合、電話応対が苦手で、相手の名前や会社名を覚えられないなどのミスが起きやすいでしょう。
また、電話応対で耳から得る情報が多くなると、パニックになるケースもあります。
(7)曖昧な表現が苦手
ニュアンスをくみ取るのが苦手だったり、冗談が通じにくかったりする傾向にあるため、言われたことを勝手に解釈して思いこむ可能性が高いです。
例えば、会議に必要な資料の準備を依頼した場合、「人数分よりも少し多めで印刷を」と依頼すると、2~3部ではなく、かなり多めの必要以上の部数と思いこんで用意して、指摘されると怒ることもあるでしょう。
発達障害のある同僚への接し方
最後に、発達障害のある同僚への接し方について紹介します。特性を理解して、接し方を工夫すれば、仕事や職場でのコミュニケーションが円滑に進むようになるでしょう。
(1)具体的に説明する
発達障害のある方の場合、曖昧な表現では伝わりません。例えば、「2日後の13時までに提出してください」と具体的に伝えると良いでしょう。また、耳からの情報が認識しにくい方には、絵や図を描いて説明するのもおすすめです。
(2)優先順位をあらかじめ決める
タスク管理が苦手な方もいるため、さまざまな仕事を依頼する際には注意しましょう。
例えば、A・B・Cの仕事を依頼する場合には「まずBの仕事を終わらせてからA、その後Cに取り掛かってください」などと、あらかじめ仕事の優先順位を決めて依頼するのがおすすめです。
(3)嫌なことははっきり伝える
大人の発達障害の方のなかには、相手の表情をくみ取ることや気持ちを察することが苦手な方がいます。そのため、悪気なく失礼なことを言うケースもあるでしょう。この場合、嫌な気持ちになったことを抱え込まず、きちんと本人に伝える必要があります。
そうすれば、失言した方は「相手に失礼なことを言ったのだ」と理解することができ、次回からは言わなくなるでしょう。
(4)特性を知って他の同僚と同じように接する
大人の発達障害を持っている方だからといって、他の同僚と何か差があるわけではありません。特性を理解したうえで、接し方を工夫すれば仕事への影響は軽減できます。柔軟な関係作りを行い、他の同僚と同じように接することが大切です。
万一、気になることや仕事を円滑に進めるうえで何か支障がある場合は、職場内の指導担当者や管理者に相談すると良いでしょう。
みんなが快適に働ける職場作りを
大人の発達障害の方に限らず、職場にはさまざまな方が働いています。そのため、相手を思いやり、それぞれの特性や個性を理解して人間関係を構築していくことが大切です。ただ、職場によっては特性を理解してもらえず、辛い状況にある方もいるでしょう。辛い気持ちを抱えたままでは、心の病になる可能性もあります。
当オフィスには、大人の発達障害に精通するカウンセラーが在籍しております。身近で辛い状況にある方がいらっしゃる場合や当事者である方は、お気軽にご相談ください。