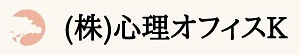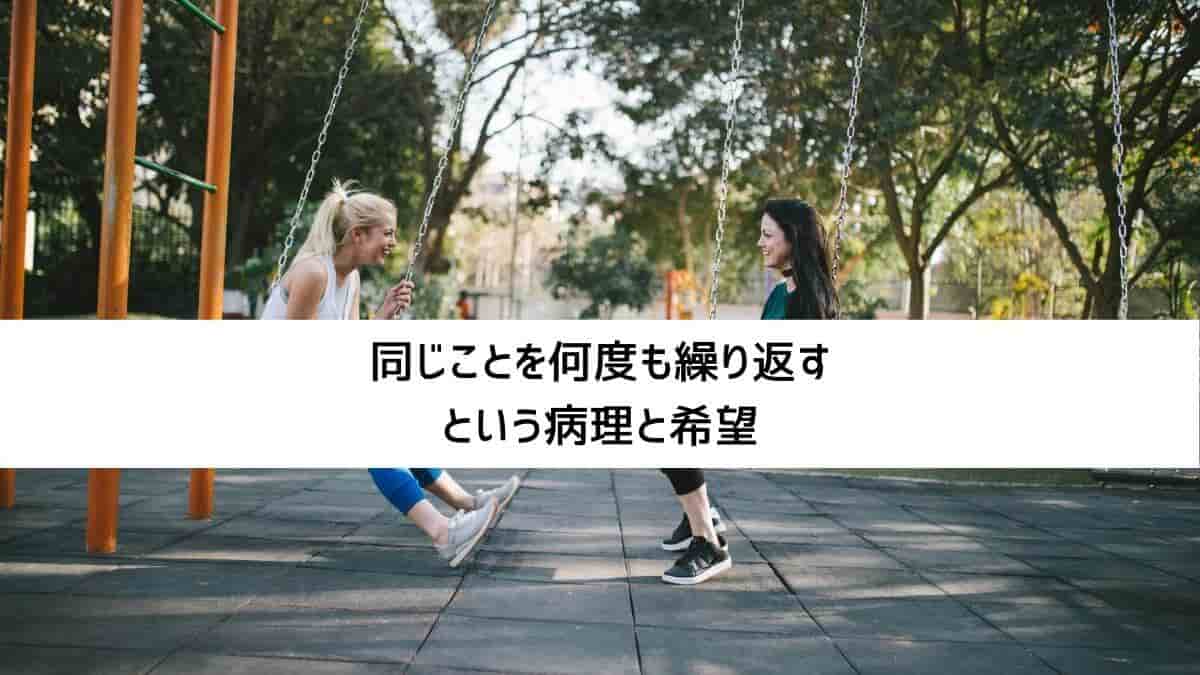ミュンヒハウゼン症候群とは、精神的・身体的には何も問題は無いにも関わらず、病気の振りをすることで、他者からの支援や慰め、関心を得ようとする人を指します。そして、それが継続的で慢性的になり、病気の振りをすることが全てのような状態になってしまいます。また、子どもや年老いた親などを病気にさせることで、献身的に尽くしている振りをする人を代理ミュンヒハウゼン症候群と言います。
現在ではこのミュンヒハウゼン症候群は虚偽性障害や作為症と呼ぶこともあります。
ここでは、そのミュンヒハウゼン症候群についての特徴や種類、治療などについて解説していきたいと思います。
目次
ミュンヒハウゼン症候群の概要
ミュンヒハウゼン症候群とは、自分自身に意図的に病気や怪我を負わせ、病院などで治療を受けることで自分を中心に周囲の人々から注意を引こうとする精神障害の一つです。多くの場合、症状を誇張したり、偽装したりすることがあります。また、病院での治療や手術を好むため、様々な手段を用いて医師や看護師を欺くことがあります。治療には、精神療法やカウンセリングが行われる場合があります。
誰しも、一度は仮病を使ったことがあるのではないでしょうか。
- 熱がある
- お腹が痛い
- 頭が割れそうだ
学校に行きたくないから、仕事を休みたいから、単に面倒だからーその理由はさまざまだと思います。しかし、病気の振りをすること自体が人生の目的になっているとしたらどうでしょうか。
- 優しくしてほしい
- 構ってほしい
- 自分の存在を認めてほしい
そういった理由で自ら進んで病気になる、自分の代わりに誰かを病気にさせる。ひいては、「病気の振り」をすることが、人生そのものになってしまう。それが、ミュンヒハウゼン症候群・代理ミュンヒハウゼン症候群です。
ミュンヒハウゼン症候群という言葉は、英国の内科医リチャード・アッシャー博士によって、1951年にはじめて用いられました。『ほら吹き男爵物語』の主人公であるミュンヒハウゼン男爵の名前に由来しています。上の写真はそのミュンヒハウゼン男爵の肖像画です。
ミュンヒハウゼン症候群は精神疾患の一つである「虚偽性障害」に分類され、その中でも重度かつ慢性のものを指します。明らかな外的原因がない状況で、身体症状がある振りをしたり、自らその症状を作り出したりします。つまり「病気の振りをする病気」です。
また、代理ミュンヒハウゼン症候群は「病気の子どもの親」としての慰めや同情を周囲から得るために、子どもが病気であると偽ったり、子どもを意図的に病気にさせたりします。
よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 女性
Aさんは、ここ数年、複数の内科や整形外科を受診し続けていました。症状はめまい、胸の圧迫感、腹痛、手足のしびれなど多岐にわたり、診察のたびに重篤な疾患を強く訴えていました。しかし、どの医療機関でも検査上の異常は見つからず、医師からは「ストレスが原因かもしれない」「心療内科の受診を検討してはどうか」と提案されてきました。Aさん自身も「自分は本当に具合が悪いのに、誰も信じてくれない」と怒りや悲しみを感じていたと語ります。
Aさんは幼少期から、家庭内で孤立感を強く抱えて育ちました。両親は共働きで忙しく、妹ばかりが可愛がられていたと感じていたそうです。自分の気持ちを表現しても聞き入れられない経験が積み重なり、次第に「身体の不調を訴えることでしか自分の存在を示せない」と思うようになったといいます。成人後も、漠然とした不安や寂しさが押し寄せてくるたびに、それを受け止めきれず、身体の異変として偽装し、医療機関を訪れるという行動を繰り返してきました。
あるクリニックの医師がAさんのこれまでの受診歴に注目し、精神科クリニックの紹介状を作成しました。当初は納得できなかったものの、「これ以上どこへ行っても変わらないかもしれない」という思いから、半信半疑でカウンセリングを受けることになりました。
カウンセリングでは、Aさんが日常的に感じている空虚感や孤独感、それをうまく他者に伝えられないつらさについて、丁寧に言葉を重ねていく作業が進められました。「本当の気持ちを出したら誰にも受け入れられない」といった根深い恐れを少しずつ扱いながら、偽装された身体症状の背景にある感情の存在をAさん自身が理解していけるよう支援されました。
通院を演じることでしかつながれなかった他者との関係を、今では「正直な気持ちで人と向き合う努力」へと少しずつ変えていくことができています。症状の訴えは以前より減り、週1回のカウンセリングがAさんにとって安心できる居場所になりつつあります。
ミュンヒハウゼン症候群の原因

例えば、幼少期に重篤な疾患のため、病院の中でしか生活できなかったとします。その後病気が回復し、外の世界で生活するようになるも、病院以外の場所での人間関係の築き方がわかりません。医師や看護師とは「病気」という道具を用いてコミュニケーションをとることができますが、一般の人はそれほどいつも病気だけを気にしている訳ではありません。なので、再び病気になって入院し、医師や看護師に構ってもらおうとする訳です。
また、パーソナリティ障害の人は、根底に不安定な自我や他者との関係構築の脆弱性があります。特に境界性パーソナリティ障害に見られる「見捨てられ不安」が代表的です。「他の人とどうやって関わればいいか分からない」「このままでは誰も自分を見てくれないのではないか」「恋人に捨てられてしまったらどうしよう」そうなった時に自ら「病気」を作り出します。
病気でいれば、恋人も優しくしてくれるでしょう。職場の同僚も心配してくれるでしょう。入院すれば病院という守られた世界で、医師や看護師が献身的に関わってくれるでしょう。そういった心の充足を得るために、身体を犠牲にする訳です。
大切な人との離別、たとえば婚約破棄が原因で病気を偽るようになった症例も見られます。裏切られた悲しさ・虚無感から逃れるために、身体を傷つけ病気を偽り周囲からの同情を得ます。
いずれにも共通して言えるのは、他者からの優しさを求めている、という点です。手段としては不健全かもしれませんが、「構ってほしい」「自分と関わってほしい」という大変シンプルな承認欲求の現れとも言えます。
Aさんは幼少期から、家庭内で孤立感を強く抱えて育ったようでした。そうしたことがミュンヒハウゼン症候群が疑われるような状態になったと推察されます。
ミュンヒハウゼン症候群の特徴

Aさんは以下のような3つの特徴がいくらか見られていました。
(1)入院するために自ら意図的に症状を引き起こす
「入院して周囲の人の同情を引きたい」その一心でさまざまな症状を自ら作り出します。
癌だと偽り自らの頭髪を抜く、貧血を演じるために自分で自分の血を抜く、中には自らの大便を用いて感染症を引き起こした症例も見られます。周囲の人の関心を手に入れ、優しく気遣ってもらう為には自らの身体を犠牲にすることはまったく厭いません。そうすることでしか、人と関わる方法がわからないのです。
(2)攻撃的だが、面倒なことが起こりそうになると姿を消す。
自分が思うような診断名がつかないと、医者に対して攻撃的になったり、ドクター・ショッピングをしたりするようになります。また、入院中もさまざまな要求をスタッフたちにぶつけます。一方で、病気が治りそうになったり嘘がばれそうになると、忽然と姿を眩まします。
他者との関係性を得る為についた嘘は、不安定な自分自身を守る鎧にもなります。その鎧がはがされることは、何にも堪え難い苦痛である為、嘘がばれる前に姿を消してしまいます。そのため、一ヶ所に定住せず、町から町へと渡り歩くような特徴も見られます。
(3)奇想天外な経歴をあたかも本当であるかのように語る
嘘の病気を演じ続けるということは、病気以外の面でも嘘をつく必要があります。嘘が嘘を呼び、どんどんエスカレートしていきます。「空想虚言症」と呼ばれる症状で、その鮮やかな語り口に周囲の人間はすっかりだまされてしまいます。
また、総じて頭の回転が早く、豊富な医療知識や巧みな演技力で周囲の人間をすっかり取り込んでしまいます。
代理ミュンヒハウゼン症候群とは

(1)代理人によるミュンヒハウゼン症候群
大人が子どもを代理人に仕立て上げるもので、自分自身ではなく、子どもの身体に病気の症状を引き起こしたり、子どもが病気であると偽ります。児童虐待の一形態としても挙げられています。大人自身の心的外傷や他者との関係構築の脆弱性、パーソナリティ障害、また配偶者との関係不良等が原因として考えられます。
子どもを病気に仕立て上げることで「病気の子どもを持つかわいそうな親」「献身的に子どもを看病する立派な親」という注目や関心を浴びることが目的です。他者との健全な関係性の構築ができないため、子ども、それも普通の子どもではなく「病気の子ども」というある種特殊な「道具」を用いないと他者と関わることができない訳です。
このように育てられた(虐待を受けた)子どもは、得てして問題を内面化します。つまり、自分が悪いことをしたから病気になるのだ、と考えるようになります。また、年齢があがると「病気でなくなったら、親に見捨てられてしまうかもしれない」と考えるようになる場合もあります。共生、ひいては共依存のような形になる訳です。そのように親との関係性を築いた子どもは、成長し自身もまたそのような親になることも少なくありません。
(2)成人の代理人によるミュンヒハウゼン症候群
病気を引き起こす相手が成人の場合もあります。「介護者」としての周囲からの同情や励ましを得ることが目的です。例えば、夫の食事に毒を盛り続け、献身的に看病を続ける妻、のような症例です。また、見捨てられ不安から妻を殺害してしまった症例も見られます。
自身の身体、子ども、妻や夫など、対象は異なりますが、そういったものを犠牲にすることでしか、他者や社会との関わり方と築くことができません。病気でなければ、病気の人間に献身的に尽くしていなければ、誰も自分など見てはくれない。そのような歪んだ認知の中で日々を過ごしている訳です。
ミュンヒハウゼン症候群の治療とカウンセリング

明確な治療法は現在確立されていませんが、心理療法的アプローチが有効とされています。身体科の医師と精神科の医師が恊働で治療に取り組む手法です。患者が装っている身体疾患への治療も必要ですが、その奥にひそむ精神的な問題を根本から治療することが必要不可欠となるため、有効な手段と考えられています。
ミュンヒハウゼン症候群のカウンセリングにおいては、症状そのものを否定したり、虚偽を直接的に非難したりすることは避け、クライエントの内的な苦しみに丁寧に寄り添う姿勢が重要です。この症候群の背景には、深い孤独感や空虚感、愛情や承認を得たいという強い欲求が存在していることが多く、それらの感情を自覚することが回復への第一歩となります。カウンセラーは、繰り返される身体症状の訴えや医療機関の利用行動の意味を、批判せずに丁寧に聞き取りながら、それがどのような心の痛みや対人関係のパターンと結びついているかを共に探っていきます。
また、Aさんのように「病気の自分」でいることが唯一の他者とのつながりの手段になっているケースでは、症状を手放すことへの恐れや不安が強くなるため、症状に依存せずに関係を築ける新たな方法を提案し、試行錯誤を重ねる必要があります。治療は長期的な支援が前提となり、時にカウンセラーへの怒りや失望といった感情がぶつけられることもありますが、それもまた関係性の一部として丁寧に扱っていきます。こうした作業を通して、症状ではなく自分自身の感情や存在を受け止めてもらえる経験が積み重なることで、少しずつ回復への道が開かれていきます。
ミュンヒハウゼン症候群についてのよくある質問
ミュンヒハウゼン症候群は、虚偽性障害の一種であり、他人の関心や同情を引くために、自ら病気やけがを装ったり、意図的に症状を作り出す精神疾患です。患者は実際には存在しない病気を訴えたり、自分自身に危害を加えて症状を引き起こすことがあります。この行動は外部からの明確な報酬を目的としていない点で詐病とは異なります。ミュンヒハウゼン症候群は、1951年にイギリスの医師リチャード・アッシャーによって命名されました。
ミュンヒハウゼン症候群の主な症状は、実際には存在しない病気やけがを装うことです。具体的には、自分で自分にけがを負わせたり、毒物を摂取して症状を引き起こす、医師や看護師に対して虚偽の病歴や症状を報告する、複数の医療機関を渡り歩き、不要な検査や治療を受けようとする、治療や検査の結果に満足せず、さらに別の症状を訴えるといった行動が挙げられます。これらの行動は他者からの関心や同情を得ることを目的としており、患者自身の健康や安全を危険にさらすことがあります。
ミュンヒハウゼン症候群の正確な原因は明らかになっていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。主な要因としては、幼少期の虐待やネグレクトなどのトラウマ体験、低い自尊心や自己評価、他者からの関心や愛情を強く求める性格傾向、人格障害(特に境界性パーソナリティ障害)との関連が挙げられます。これらの要因が組み合わさることで、患者は他者の注意や同情を引くために病気を装う行動をとると考えられています。
ミュンヒハウゼン症候群の治療は難しいとされていますが、主に精神療法が用いられます。信頼関係を築き、行動の背景にある心理的要因を探ることが重要です。認知行動療法を通じて患者の思考パターンや行動を修正し、家族療法で環境の改善を図ることも有効です。薬物療法は併存するうつ病や不安障害の治療に限られます。治療には時間がかかることが多く、専門家の継続的なサポートが必要です。
ミュンヒハウゼン症候群の診断は、患者が意図的に症状を作り出していることを確認する必要があり、非常に難しいとされています。医師は病歴や症状の医学的な整合性、複数の医療機関を訪れる行動、治療への反応、検査結果の矛盾などを総合的に評価します。他の身体疾患や精神疾患を除外し、患者との信頼関係を築きながら情報を収集することが診断の鍵となります。
ミュンヒハウゼン症候群は主に成人に多いですが、似た行動が子どもに見られる場合もあります。また、「代理によるミュンヒハウゼン症候群」(MSBP)では、養育者が子どもの病気を装う行動が報告されています。子ども自身が虚偽の症状を訴えることは少ないものの、心理的要因や環境が影響する可能性があります。専門家が子どもの安全を確保しながら適切な介入を行うことが重要です。
ミュンヒハウゼン症候群と詐病の主な違いは、動機にあります。ミュンヒハウゼン症候群では、患者は他者の関心や同情を得るために症状を捏造しますが、詐病は金銭的利益や法律上の恩恵などの外的な報酬を目的としています。このため、ミュンヒハウゼン症候群は精神疾患とされ、治療が必要ですが、詐病は医療行為を装った詐欺と見なされる場合があります。
早期発見には、医療関係者が患者の行動や症状のパターンに注目することが重要です。医学的に説明がつかない症状や多くの医療機関を訪れる行動、不必要な検査や治療を求める行為が見られる場合、専門家の評価を受けるべきです。家族や友人も患者の健康に関する過度な行動に気付いた際は、早めに医療機関に相談することを推奨します。
ミュンヒハウゼン症候群の予後は個人差がありますが、治療には時間がかかることが一般的です。患者が問題を認識し、治療を受け入れることが改善への第一歩です。精神療法や家族の支援を通じて症状の軽減や社会的機能の回復が期待できますが、再発リスクもあります。継続的な専門家の支援が重要です。
代理によるミュンヒハウゼン症候群(MSBP)は、養育者が子どもなど他者の症状を捏造し、病気であるかのように見せる状態を指します。この行為は子どもに深刻な身体的・精神的被害をもたらす可能性があり、虐待とみなされます。医療機関と児童保護機関の連携による迅速な対応が必要です。
ミュンヒハウゼン症候群の相談をするには

こうしたミュンヒハウゼン症候群や代理ミュンヒハウゼン症候群についての相談やカウンセリングを当オフィスでは行っています。希望者は以下の申し込みフォームからお申し込みください。