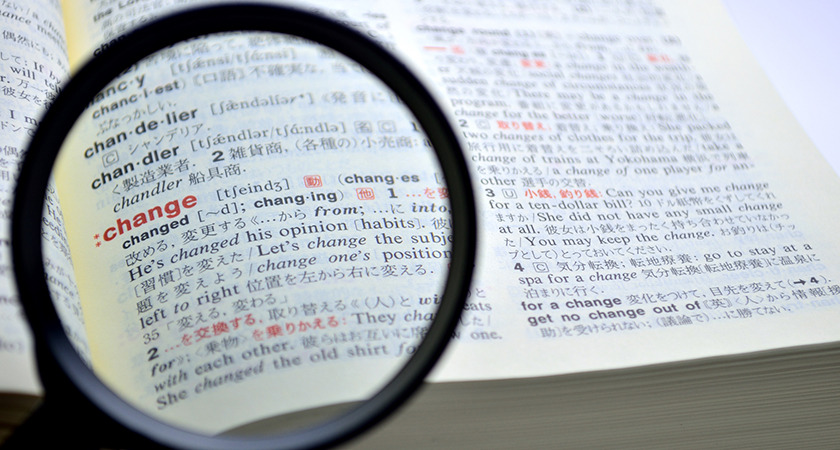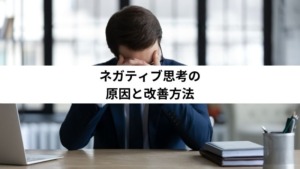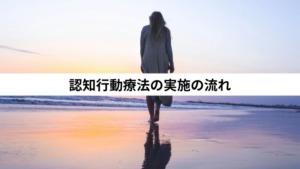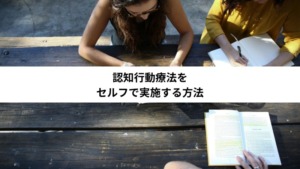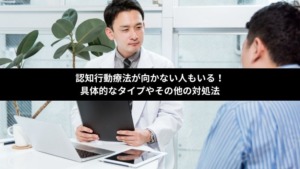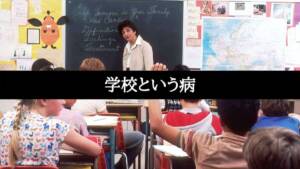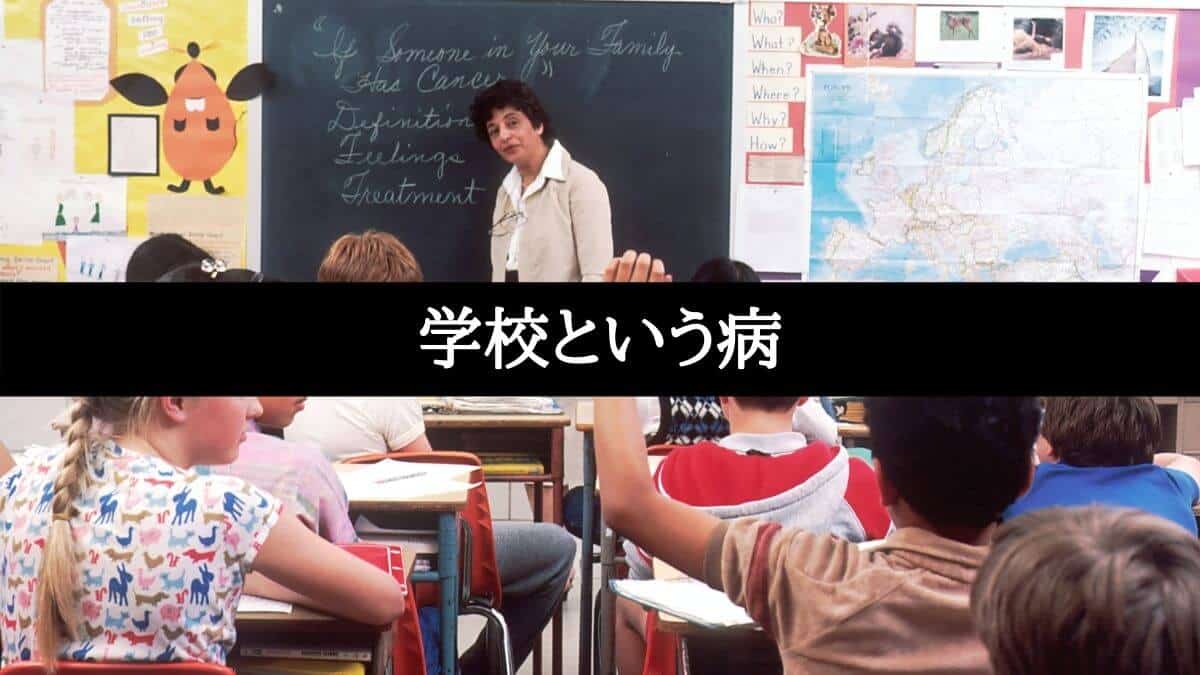本ページでは、認知再構成法について、その定義から具体的な方法まで詳しく解説しています。この治療法には枠組みがあり、どのように取り組めばよいかということが明確なので、ひとつの技法として知っていただけると幸いです。
目次
認知再構成法とは
認知再構成法とは、認知行動療法の中の一つの技法で、適応的でない認知的な行動を、適応的な行動に変容させる介入をいいます。簡単に言い換えると、ネガティブな認知をより望ましい形に変容させて実際の行動を変えていくアプローチということができます。人は、頭の中で何かを考え、評価し、計画をたてながらそれらを行動に移していますが、その頭の中で思い浮かべているものを認知的行動と呼び、ネガティブな認知的行動を減らしていくことを目的としています。
認知再構成法は、認知行動療法のひとつの技法として紹介されることが多いのですが、細かく分類すると認知療法ということができます。しばしば、行動療法と認知療法は一緒に扱われ、認知行動療法と一括りにされることが多いのですが、行動療法が「客観的に観測できる行動」を対象にしているのに対し、認知療法は「目には見えない思考・認知」を対象にしているので、認知再構成法は認知療法の技法と位置づけることができます。
認知行動療法については以下のページをご参照ください。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは30歳代の女性で、真面目で責任感の強い性格でした。幼少期から「失敗してはいけない」「周りに迷惑をかけてはいけない」という価値観を強く抱いて育ち、社会人になってからも仕事を最優先にしてきました。しかし、部署異動を機に業務量が増え、徐々に不眠や食欲低下が続き、朝起きられず欠勤が増えました。医療機関でうつ病と診断され、薬物療法を受けながら休職することになりましたが、「会社に迷惑をかける自分は価値がない」と自責感に苦しみ、カウンセリングに申し込みました。
面接では、Aさんは涙を浮かべながら「全部私のせい」と繰り返していました。そこから、認知行動療法の一つである認知再構成法を中心に取り組むこととなりました。まず、Aさんが日常で感じている不安や落ち込みがどのような「自動思考」によって引き起こされているかを丁寧に整理していきました。「一度休んだら終わり」「ミスは許されない」といった極端な思考のクセが、気分の落ち込みを強めていることが少しずつ理解できるようになりました。
カウンセリングでは、これらの自動思考が事実に基づいているのかを一緒に検討し、別の視点や根拠を探す練習を繰り返しました。「休んでも同僚に助けられたこともあった」「完璧にできた仕事もあった」といった事実を積み重ねることで、Aさんは次第に「私は何もできない」という考えを修正できるようになりました。
さらに、思考記録表を用いて気分の変動と考えの関連を客観的に振り返る作業を続けたことで、Aさんは自分の思考パターンを把握しやすくなりました。落ち込んだときには「本当にそうだろうか?」と自分に問いかけ、別の受け止め方を探す習慣が少しずつ育っていきました。
1~3年を通じて、薬物療法と併行しながら認知再構成法を継続した結果、Aさんは自分を過度に責める思考を手放し、「無理をしすぎていたのかもしれない」と自分への理解が深まりました。復職後も、以前のように限界までがんばるのではなく、適度に休息を取りながら働くスキルを身につけることができ、抑うつ気分の再燃防止にもつながりました。
認知再構成法で使うツール(コラム法のシート)
認知再構成法では多くの場合コラムというものを使用します。シートにまとめることで、ぐるぐる考えてしまっている思考を整理し視覚化します。以下にシートの例を示します。シートにはさまざまなタイプがあり、気分や確信度などを数値化して記すものや、ただ言葉で記述するだけのものもあるのですが、ここではシンプルな形のものを載せたいと思います。
表の中にある自動思考とは、認知療法の中核的な概念で、「あることが起きたときに自動的に湧きあがってくる思考」のことを指します。
| ①出来事 | 「それはどんなとき?」 |
| ②そのときの認知・考え・自動思考 | 「どのように考えた?思った?」 |
| ③気分・感情 | 「どんなきもちになった?」 |
| ④代わりとなる認知・考え(適応的な思考) | 「他にどのように考えることができる?」 |
| ⑤心の変化 | 「どう変わった?」 |
Aさんは、落ち込んだ場面を整理するためにコラム法のシートを用いました。Aさんの場合、気分の落ち込みと自動思考を切り分けて記録することで、頭の中が整理され、自分の考えのクセに気づきやすくなりました。
認知再構成法の効果
認知再構成法は特にうつ病の方に用いられます。ターゲットとしているのが、抑うつ的な気分であったり、ネガティブな感情、思考となっているので、必然的にそのような症状のあるクライエントさんに適用されることになります。効果研究も数多くされており、認知再構成法がうつや不安を軽減させるという効果が認められています。
Aさんは、事実と推測を区別する習慣が身につき、「私は迷惑をかけてばかり」という極端な思い込みが和らぎました。Aさんの場合、気分の改善だけでなく、日常のトラブルへの対処が以前より冷静にできるようになりました。
認知再構成法のデメリット
認知再構成法はある程度その人に信念や思考が備わっているということが前提になっています。そのため、まだ未成熟な子どもに対してはあまり使用しない方がいいといわれています。子どもに限らず、重篤な精神疾患で現実検討能力が低くなっているケースでは適用が難しいとされています。
また、クライエントさん本人に治療意欲が備わっているかという点も大事になります。カウンセリングルームにきてもらいお話をするだけではなく、実生活の中でコラム表を書いてきてもらうこともあるので、課題に取り組んでいくエネルギーの有無が治療の進度に関わってくる場合があります。とはいえ、クライエントさんにすべてが投げられているわけではないので、治療者は最大限クライエントさんのペースに寄り添いながら無理のない範囲でとりくんでいくことが大切です。
Aさんは、最初のうちはシートの記入に難しさを感じ、うまく思考を言語化できない場面がありました。Aさんの場合、考えを整理する時間が必要で、即効性を感じにくいというデメリットもありました。
認知再構成法のやり方
ここでは認知再構成法の大まかな流れを3つのステップで解説します。
(1)状況の同定
まず、どのような場面と望ましくない思考が紐づいているかをみていきます。クライエントさんと話をしながら場面を特定していく形と、コラム表を用いて記録してきてもらうやり方があります。前者の場合、記憶に頼った形となり、実際その場で感じた感覚や思考からずれが生じることもあるので、後者のようにその都度記録してきてもらう方が良い場合もあります。クライエントさんによっては、最初から自分で記録することが難しいケースがあるので、一緒にコラム表を作成していくこともあります。
Aさんは、落ち込みや不安が強まった具体的な場面を特定し、その状況を明確に書き出すことで、問題の「入口」を捉えやすくなりました。
(2)反応の同定
設定した状況でどのような反応をとっているかを詳しく書き出していきます。反応には、「認知・思考」と「感情・気分」「行動」があります。その出来事が起こった時、頭の中でどのように感じ、どのように考え、どのように対処しているかを振り返りながら記録します。この、反応の同定をする中で「自分はこういうときにも不快な感情になっているのかもしれない」とあらたな気づきを得ることもできるので、最初からたくさんの状況を設定しなくても進めていくことが可能です。
Aさんの場合、その場面で生じた感情・身体反応・行動を丁寧に整理することで、自分がどの瞬間に苦しくなるのか理解しやすくなりました。
(3)思考の置き換え
このステップが、認知再構成法の中で一番のポイントとなっています。どのような状況下で、自分自身が望ましくない思考をしているか、ということが見えてきた後、その望ましくない思考とは別の思考をすることはできないかというアイディアを考えていきます。しばしば、ネガティブな思考が働くとき「○○に違いない」「○○しなければならない」「絶対に○○だ」と極端で合理的でない決めつけが生じていることがあります。その思考とは別の考え方、とらえ方はないか治療者とともに話し合っていきます。
思考は、ある種の癖でもあり、そう簡単に変えられるものでもありませんし、そう考えることによって自分自身を守ってきたという場合もあるので、それを一度崩すということはとても勇気のいる行為です。最初は、無理に変えようとせず、「こうも考えられるなぁ」というところからスタートし、それを繰り返す中で思考パターンを柔軟にしていきましょう。
Aさんは、自動思考が浮かんだときに、それを別の現実的で柔らかい考え方に置き換える練習を重ねました。Aさんの場合、繰り返すうちに「本当にそうだろうか?」と立ち止まる習慣が生まれ、気分の落ち込みが軽減しました。
認知再構成法の具体例
認知再構成法でコラム法を用いたケースを2例紹介したいと思います。具体的にどのようにシートに記入するかという参考にしていただければと思います。
(1)上司から何かいわれるたびに抑うつ的になっているケース
うつ病のクライエントさんの場合、「自分は○○と思われているに違いない」と被害妄想が強くなっているケースが多くあります。はたから見れば、それらは全く根拠のない非合理的な思考とみられますが、本人にとってはそれが真実であり、現実味を帯びた感情となっています。認知再構成法では、その思考が正しいか間違っているかという点を論じ合うのではなく、「そうとも考えられるし、こうとも考えられる」と選択肢を増やすという観点で話し合いをしていきます。
| ①出来事 | 上司から報告書に不備があると指摘された |
| ②そのときの認知・考え・自動思考 | 使いものにならないと思われたに違いない |
| ③気分・感情 | 悲しい(80) |
| ④代わりとなる認知・考え(適応的な思考) | 大きな問題にならなくてよかったともいえる |
| ⑤心の変化 | 悲しみ(60) |
(2)人の前で話すことに強い不安を感じているケース
不安という感情はとても漠然としたものです。ここでは、「発表がうまくいくか心配」という例を設定しましたが、発表の何が怖いのかということを突き詰めると、「結局のところ自分は何に対して不安を感じているのだろうか」というところに行きつきます。ある意味この不安は、自分の想像した未来に抱いている不安ともいえるので、その想像自体を変換できれば不安は軽減するのではないか、と認知再構成法では考えます。
| ①出来事 | ゼミで発表がある |
| ②そのときの認知・考え・自動思考 | 失敗したらどうしよう |
| ③気分・感情 | 不安(80) |
| ④代わりとなる認知・考え(適応的な思考) | 失敗しても落とされるわけではない |
| ⑤心の変化 | 不安(50) |
認知行動療法についてのトピック
認知再構成法についてのよくある質問
認知再構成法は、私たちの思考に潜む歪みを特定し、それらを現実的でより適応的なものに修正するための心理療法の手法の一つです。この方法では、思考の癖や誤った認知を見直し、感情や行動がその思考にどのように影響を与えているかを探ります。認知再構成法の目的は、クライアントが自分自身の思考パターンを理解し、困難な状況に対してより柔軟で現実的な反応ができるようにすることです。特に、うつ病や不安症、パニック障害などの症状の改善に効果的で、認知行動療法の一部としてもよく使われます。
認知再構成法は、まず自分の思考パターンを把握することから始まります。クライアントは、日常的な出来事に対する反応として浮かぶ思考や信念を記録します。その後、これらの思考が現実的であるかどうかを再評価し、思考の歪みや偏りを見つけ出します。これらの誤った認知を現実に即した、より適応的でポジティブな考えに修正していきます。例えば、「自分は何をしても失敗する」といった考え方を「失敗しても、それは成長の一部である」といった考え方に置き換えることが求められます。認知再構成法では、思考の枠組みを変えることで、感情や行動の変化を促します。クライアントは、自分の思考がどのように感情に影響しているかを学び、感情のコントロールを改善することができます。
認知再構成法は、うつ病や不安障害、強迫性障害(OCD)、パニック障害、過剰なストレスや怒りの管理など、さまざまな精神的な問題に効果があります。特に、思考が感情や行動に強い影響を与えている場合に有効です。例えば、うつ病の患者は、自己評価が低く、自分の将来に対して否定的な見方を持ちやすいですが、認知再構成法を通じて、これらの悲観的な考え方を現実的で肯定的なものに変えることが可能です。また、不安障害やパニック障害の人々も、過度に悪い結果を想定する思考の癖を修正することで、不安を軽減し、日常生活をより快適に過ごせるようになります。
認知再構成法は、多くの人々に有効であり、誰でも実践することができます。ただし、効果を最大限に引き出すためには、専門的な指導を受けることが推奨されます。認知再構成法は自己認識を深めることを目的としており、思考の歪みを特定して修正するには一定の自己分析が必要です。自分自身で行う場合は、思考記録表やチェックリストを使って、日常的に自分の思考を見直し、現実的な視点で修正することが求められます。また、心理カウンセラーや精神科医と協力して取り組むことも有益です。専門家のサポートを受けることで、自己改善をスムーズに進めることができます。
認知再構成法の効果が現れるまでの時間は個人差がありますが、一般的には数週間から数ヶ月の継続的な取り組みで改善を実感できることが多いです。初めて取り組む場合、最初の数回で思考の変化に気づくことができるかもしれませんが、本格的な変化を感じるにはしばらく時間がかかることもあります。認知再構成法は思考の癖を改善する過程であるため、一度に全ての歪みを修正することは難しく、段階的に進めていく必要があります。クライアントが積極的に自分の思考に向き合い、継続的に実践していくことで、長期的には感情や行動にも良い変化が現れ、日常生活がより充実したものになります。
認知再構成法は、主に思考の歪みを修正することに焦点を当てた治療法です。これに対して、他の心理療法では感情や行動そのものに直接アプローチすることが多いです。たとえば、精神分析では無意識の動機や過去の経験が現在の問題にどのように影響しているかを探求します。また、感情中心の療法や行動療法では、感情や行動のパターンを改善するための技法が用いられます。認知再構成法は、クライアントが自分の思考に注目し、それをより適切なものに変えることで感情や行動の改善を図ります。したがって、認知再構成法は、思考の修正を重視する一方で、他の療法は、感情や行動の変容を重視する点で異なります。
認知再構成法を実践する際の注意点は、自己認識を深めることが重要である点です。自分の思考を正直に記録し、無理にポジティブな思考に変えようとするのではなく、現実に即した思考の修正を心がける必要があります。また、思考の修正を過度に理想化せず、柔軟なアプローチを取ることが大切です。過度に自分に厳しくしたり、否定的な思考を完全に排除しようとすることは、逆にストレスを増加させることがあります。そのため、自己肯定感を保ちながら、適切な思考の枠組みを作っていくことが求められます。専門家のサポートを受けることで、これらの注意点を上手に扱い、効果的に取り組むことができます。
認知再構成法は、さまざまな場面で有効に活用できます。仕事のストレスや人間関係のトラブル、試験の不安、プレゼンテーションの緊張など、生活の中で感じるさまざまな不安やストレスに対して、思考を修正する方法として使われます。また、うつ病や不安障害、強迫症、過食症などの精神的な疾患を抱えている場合にも、認知再構成法は効果的です。思考が感情や行動に強く影響を与えている状況で、思考の歪みを修正することによって、感情をコントロールし、日常生活をより穏やかに過ごすための手助けになります。
認知再構成法を学ぶためには、心理学の基礎知識や認知行動療法の概念を学んでおくと良いです。書籍やオンラインコースで自学することも可能ですが、実際に効果的に使うためには専門家のサポートを受けることをおすすめします。認知再構成法を提供するカウンセラーや心理療法士を訪れて、個別のカウンセリングを受けることも効果的です。セラピストと一緒に、実際に自分の思考の癖を探し、修正していく過程で、より深く学ぶことができます。また、自己分析を深めるために、日々の思考を振り返り、認知再構成法を実践してみることも有益です。
認知再構成法は、アーロン・ベックの認知療法に基づいています。ベックは、私たちの思考が感情や行動に大きな影響を与えていることを明らかにし、特にうつ病や不安障害においては、非現実的な思考が症状を悪化させると提唱しました。認知再構成法は、こうした歪んだ思考を現実的で適応的なものに変えることによって、感情や行動を改善することを目的としています。ベックの理論に基づくこのアプローチは、心理療法の分野で広く実践され、効果的な治療法とされています。
認知再構成法・認知行動療法を受けたい
今回は、認知再構成法について紹介しました。人はそれぞれ思考の癖をもって生きています。あることが起きたときに、それを何とも思わない人もいれば、それ1つで夜も眠れないほどに悩んでしまう人もいます。「捉え方を変えるだけで楽になれる」とわかってはいながらも、どうしてもネガティブに考えてしまうという人も多くおられると思います。認知再構成法はそのような方に向けられた治療法なので、ぜひ興味のある方は相談されてみてください。
また、カウンセラーと一緒に認知再構成法・認知行動療法を取り組みたいという方は以下の申し込みフォームからご連絡ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。