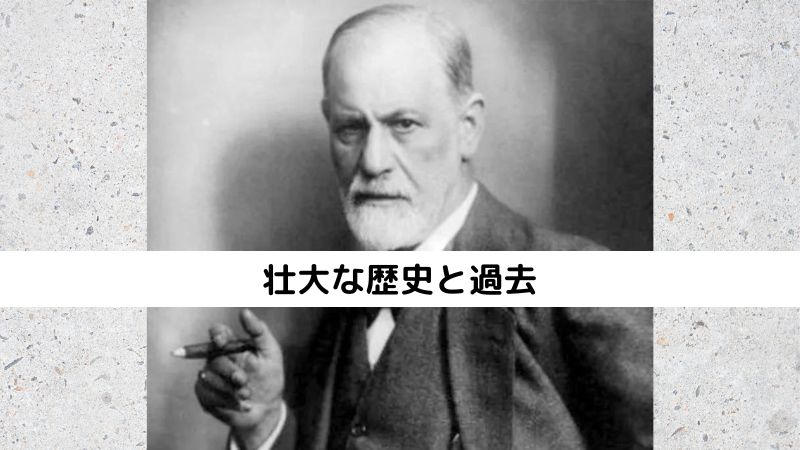本ページでは、対人関係療法について、その歴史から特徴、方法まで詳しく解説しています。対人関係療法に興味がある方、また対人関係療法を実際に受けたいと思われている方、どのような心理療法を受ければいいか迷われている方にも読んでいただければと思います。
目次
対人関係療法とは
 対人関係療法とは、対人関係を主に焦点にし、そこでの感情や行動、関係性を変化させながら、問題を解決したり、対処法を身に着けたりするカウンセリングの一つです。うつ病に対するカウンセリングとして始まりましたが、その後、摂食障害やPTSD、パーソナリティ障害など様々な精神障害にも適用できるように発展しています。対人関係療法では構造がはっきりとしており、マニュアルがあり、そのやり方に従って進めていきます。
対人関係療法とは、対人関係を主に焦点にし、そこでの感情や行動、関係性を変化させながら、問題を解決したり、対処法を身に着けたりするカウンセリングの一つです。うつ病に対するカウンセリングとして始まりましたが、その後、摂食障害やPTSD、パーソナリティ障害など様々な精神障害にも適用できるように発展しています。対人関係療法では構造がはっきりとしており、マニュアルがあり、そのやり方に従って進めていきます。
「精神医学とは対人関係の学である」という言葉があります。これは対人関係療法の源流となっている対人関係学派のサリヴァンの言葉で、精神的な不調や障害は対人関係の問題からきており、それを治療するのも対人関係であるという意味で使われています。サリヴァンは、統合失調症の研究で有名ですが、その対人関係を重視する治療のスタイルが、うつ病にも効果的ではないかと研究され、クラーマン(Klerman,G.L.)らによって開発されたものが対人関係療法となっています。
このように歴史的には、サリヴァンの対人関係学派の流れをくんでいるため、精神分析の系譜となっていますが、対人関係療法はマニュアル化された治療法で、認知行動療法と比べられるほど構造のはっきりした短期的なものとなっています。
カウンセリングや心理療法は、長い期間通い続けるというイメージをもっておられる方が多いかもしれませんが、海外では、このような短期間に解決を目指す治療法、例えば、解決志向アプローチやブリーフセラピー、認知行動療法などが盛んになっており、対人関係療法もそれらと同じように短期的な改善を目指す治療となっています。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさん(30代女性)は、職場での人間関係のストレスから抑うつ気分が続き、出勤が難しくなったことをきっかけにカウンセリングを受けることになった。以前から他人の顔色を過剰に気にし、自分の意見を言えずに我慢してしまう傾向があった。幼少期から母親の期待に応えようと努力し、失敗すると強く叱責される環境で育ったこともあり、「嫌われないようにする」ことが人との関わり方の基本になっていた。
医療機関ではうつ病と診断され、抗うつ薬を服用していたが、気分の落ち込みは改善しても人間関係の悩みは続いていた。そこで、対人関係療法(IPT)によるカウンセリングが始まった。初期には、今の抑うつ状態が「上司との対立」という具体的な対人関係の問題に結びついていることを整理し、問題領域を「対人摩擦」として設定した。Aさんは上司に意見を伝えられず、残業を引き受けて疲弊していた。
カウンセリングでは、相手との関係の中で自分の気持ちを率直に伝える練習を重ねた。治療者はAさんの発言を整理し、「その時、どんな気持ちだったか」「本当はどうしたかったか」と丁寧に確認しながら、Aさん自身の感情を言葉にする支援を行った。Aさんは少しずつ、自分の不満や希望を認識し、上司に「今のペースでは難しい」と伝えることができた。この小さな成功体験が自信につながり、次第に同僚や家族との関係にも変化が見られた。
治療が進む中で、Aさんは母親との関係を振り返るようになり、「人に嫌われないように頑張る自分」がどこから来ていたのかを理解した。治療者はこの気づきを支持しつつ、過去の理解にとどまらず、現在の人間関係の中で新しい行動を試みるよう促した。Aさんは、母親や上司との関係で身につけた「我慢して合わせる」パターンを少しずつ手放し、自分の立場を穏やかに主張する方法を学んでいった。
カウンセリングの終盤には、気分の落ち込みがほとんどなくなり、対人場面での緊張も和らいだ。Aさんは「人と意見が違っても関係は壊れない」と感じられるようになり、職場での協働もスムーズになった。IPTの過程を通じて、Aさんは自分の感情を適切に表現し、関係の中で自分を保ちながら生きる力を身につけていった。
対人関係療法の効果

また、最初はうつ病治療に特化したものでしたが、他の精神疾患にも対応できるように改訂が重ねられおり、摂食障害の治療にも対応できるとされています。摂食障害の治療では、本人のボディイメージに焦点をあてるアプローチもありますが、本人の認知が変われば完全に解決するというものでもなく、とても再発の可能性が高いとされています。そこで対人関係療法では家族など重要な他者との関係性に焦点をあて、コミュニケーションパターンの変化を促し改善を目指します。
更に、パーソナリティ障害への治療に用いられることもあります。パーソナリティ障害は、人との関係性に摩擦が生じやすく、それによって二次的な障害が生じてしまう可能性が高いので、対人関係に焦点を当てた対人関係療法は有効的であるとされています。一般的に、パーソナリティ障害へのカウンセリングの導入は難しく、カウンセリング自体が破綻してしまうようなケースもあります。その点、対人関係療法は明確な目的や筋道のある治療法なので、導入しやすいという利点があります。
Aさんは、対人関係療法を通じて、自分の感情を正直に表現しながら人と関わる力を身につけた。それまでの「嫌われないように我慢する」という関係のパターンを見直し、相手との違いを受け入れながら関係を築く方法を学んだ。結果として、抑うつ症状が軽減し、仕事や家庭でのやり取りにも自信が生まれた。
対人関係療法のやり方や方法

(1)対人関係療法の基本的な姿勢
対人関係療法は、文字通り対人関係に焦点を当てて治療していくアプローチになりますが、精神疾患やその症状などの原因を対人関係だけにみているわけではありません。クライエントがおかれている環境、遺伝、そしてパーソナリティなどを考慮し、総合的にとらえていくという特徴があります。また、その治療法はマニュアル化されており、短期間で終結する心理療法となっています。
Aさんの場合、治療者はAさんの感情や言葉を評価せずに受け止め、現在の人間関係に焦点を当てて関わった。この姿勢によって、Aさんは安心して自分の気持ちを語れるようになり、「感情を表に出しても大丈夫」という体験を重ねることができた。
(2)対人関係療法の流れ
例えば、認知行動療法(認知療法、行動療法)には、曝露療法や条件制止法、不安階層表などと様々な技法が存在しますが、対人関係療法には、それ独自の技法が存在するわけではありません。
基本的にはまず、現在の対人関係上の問題と、ライフイベント、症状の経過を聴くところからスタートし、そのあと、マニュアル化された4つのテーマをもとに治療が進められます。具体的には以下のようなテーマです。
- 身近な人の死(親、配偶者、子どもなど)
- 役割の不和(親子関係、夫婦関係、友人関係など)
- 役割の変化(昇進や退職、離婚、結婚など)
- 対人関係の欠如
この4つのテーマから1つか2つを選択して治療者との共同作業でまとめていきます。
Aさんは、初期段階でうつ症状と職場のストレスの関係を整理し、焦点を「上司との摩擦」と明確化した。中期では、自分の感情や欲求を言葉にする練習を重ね、終盤では実際に新しい関わり方を試みるようになった。治療の全体を通して、問題の理解から行動変化までが一貫して支援された。
(3)役割の重視
対人関係療法はあらゆる関係を役割としてとらえます。例えば身近な親子であっても、お互いに「親」としての役割、「子」としての役割の中で行動しているものとしてとられられます。
役割というと冷たいような印象があるかもしれませんが、役割としてとらえることで冷静に人間関係を分析できるともいえます。逆に完全に関係のない人同士でも「関係のない人」という役割をもって街中ですれ違っています。
また、人間関係療法の治療において、治療者と患者さんの関係も役割としてとらえるという特徴があります。
Aさんは職場で「頼られる部下」としての役割に縛られていた。カウンセリングでは、その役割を維持するために自分を犠牲にしていたことを理解し、より柔軟な役割の取り方を学んだ。役割の再構成により、周囲との関係も対等で健全なものへと変化した。
(4)フォーミュレーション
フォーミュレーションは定式化することを意味する対人関係療法の中核的な概念です。先ほど挙げた4つのテーマについてただ考えるだけでなく、それらを3つの因子にわけていきます。具体的には人間関係を以下の3つの因子で分析します。
- 準備因子
- 誘発因子
- 持続因子
まず、①準備因子では、患者さんの元々の愛着関係や、コミュニケーションパターン、スタイルを、次に②誘発因子では、うつ病など精神的症状のきっかけになった出来事や、対人関係、役割の変化などを、最後に③持続因子で現在の症状が慢性化している要因を考えていきます。
人間関係をひとりで考えようとしても、感情的になって「自分のせいで」と自責的になりすぎたり「相手のせいで」と他責的になってしまったり、冷静になるのは難しいものです。治療者というある意味では第3者がいる事でいろんなことを落ち着いて振り返ることができます。
また、カウンセリングでは「何から話していいのかわからない」「本当に相談したいことはこういうことではない」と思われる方がおられるかもしれませんが、対人関係療法は筋道がはっきりしているので、そういった方にもおすすめのカウンセリングといえるかもしれません。
Aさんの場合、抑うつ症状は「他者の期待に応えようとしすぎること」に根ざしていると整理された。この理解は、治療者とAさんが共有する指針となり、感情の背景や行動のパターンを冷静に見つめる助けとなった。
(5)対人関係療法のポイント
対人関係療法では、人間関係の改善を目指しているとはいえ、治療の中で焦点を当てるのはごく限られた人間関係のみです。最初からすべての人と円滑に関係を築くことを目指すのではなく、あくまでその患者さんにとっての「重要な人」との関係が重視されます。その「重要な人」との関係性がよい方向へ進むことで、結果的にいろんな人との関り方につながるという考え方をします。
このことは、人間関係療法に限ったことではありません。カウンセリングや認知行動療法においても、最初は小さな変化からスタートするということは共通しています。「うつ病を治したい」という最終的な大きな目標があったとしても、小さなところから取り組んでいく方が近道で、身近な人との関係性を改善することが有効的かもしれません。
Aさんの治療では、「現在の人間関係に焦点を当てること」「感情を正確に言語化すること」「現実的な行動を試みること」が中心となった。治療者との協働的な関係の中で、Aさんは「自分の感じ方を大切にして良い」と実感し、それが抑うつからの回復につながった。
対象関係療法を受けるには

患者さんにとって、どのようなカウンセリングがあっているかということは、患者さん本人の立場でもカウンセラーの立場でも難しい問題です。
Aさんの場合、医師の紹介で対人関係療法を知り、専門的に研修を受けた心理士に相談した。数か月の面接を経て、対人関係の問題が抑うつに関係していることが明確になり、本格的に治療が始まった。Aさんは週1回の面接を継続し、日常生活の中での変化を治療で振り返ることで、確実に改善を実感できるようになった。
対人関係療法(IPT)についてのよくある質問
対人関係療法(IPT)は、1970年代にアメリカの精神科医ジェラルド・クラインによって開発された心理療法の一種で、特にうつ病に対する治療法として有名です。この療法は、患者の精神的な問題を対人関係の中に焦点をあてて改善しようとするものです。IPTでは、過去ではなく現在の対人関係における問題や対人スキルの不足に着目します。患者は自分の感情を認識し、困難な対人関係の状況をどう扱うかを学びます。基本的には、個別またはグループで行われ、通常12〜16回のセッションが推奨されます。
対人関係療法(IPT)は、うつ病に限らず、さまざまな精神的な問題に対して有効であるとされています。特に、対人関係に起因する問題やストレスが原因となっている場合に効果的です。例えば、うつ病、社会不安障害、過食症、パニック障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、気分変調症などに対しても治療効果が見込まれています。IPTは、人々の人間関係の質を改善し、症状を軽減させることで、生活の質を向上させる手助けとなります。特に対人関係の問題がうつ病の発症や悪化に関与していると考えられる場合、IPTは非常に効果的な治療法とされています。
対人関係療法(IPT)は、患者が現在抱えている対人関係の問題に焦点をあてて治療を進めます。まず、セラピストは患者と共に問題の根源を見つけ、その問題に対するアプローチ方法を一緒に考えます。IPTでは、対人関係のスキルを向上させるために、コミュニケーション技法や感情表現の方法を学びます。また、患者が自分の感情や行動に対してどのように反応しているかを意識的に振り返り、自己理解を深めていくことが求められます。対人関係の問題が心理的な問題にどのように影響しているかを明確にし、改善策を見つけることが重要です。セラピストと患者が一緒に協力し、具体的な行動や思考パターンの変化を目指します。
対人関係療法(IPT)の治療は、通常12回から16回のセッションで行われます。これは、週に1回のペースでセッションが行われることを前提としています。個別のケースにより、治療の期間やセッション数は若干異なることがありますが、基本的には短期間での改善を目指します。治療が進むにつれて、セラピストとのセッション頻度を減らすこともあります。たとえば、治療後半では、月に1回のペースで維持療法として行われることもあります。治療期間中、患者は日常生活の中で学んだスキルを実践し、セラピストはその進捗をサポートします。
対人関係療法(IPT)は、特に対人関係に起因する問題やストレスが原因となる心理的な障害を抱えている人に適しています。うつ病の患者が最も多く利用しますが、社会不安症、パニック障害、過食症、依存症など、他の心理的な問題に悩む人にも有効です。特に、現在抱えている問題が人間関係や社会的な状況に関連している場合、IPTはその解決に有用です。また、過去のトラウマや対人関係での失敗から立ち直りたいと考えている人にも向いています。患者が自分の感情や行動に対する自己認識を深め、対人関係の改善を目指している場合に特に効果的です。
IPTは、対人関係の問題に焦点を当てた心理療法で、セラピストと患者が協力して問題解決に取り組みます。治療の過程では、まず患者の現在の対人関係や社会的な状況を明確にし、どのような問題が症状に影響を与えているのかを見つけます。その後、患者は感情や行動パターンを認識し、それに対する反応を改善するためのスキルを学びます。具体的には、感情表現の方法、コミュニケーション技法、対人関係での問題解決方法などが学ばれます。治療は通常、個別セッションとして行われますが、グループセッションも可能です。セラピストと患者が対話を通じて、感情や問題に対する理解を深め、行動の変容を促進していきます。
対人関係療法(IPT)は、特にうつ病に効果的な治療法として知られています。IPTは、うつ病がしばしば対人関係の問題やストレスによって引き起こされるという考えに基づいています。うつ病の患者は、孤立感や人間関係の困難によって症状が悪化することがあります。IPTでは、患者が現在の対人関係における問題を認識し、それに対処する方法を学びます。このアプローチにより、患者は感情的な負担を軽減し、社会的な支援を得る方法を学び、うつ病の回復を支援します。
対人関係療法(IPT)の治療は、主に4つのステージに分かれています。最初のステージでは、患者とセラピストが治療の目標を設定し、対人関係に関連する問題を明確にします。この段階では、問題を認識することが重要です。次に、患者は現在の対人関係の問題にどのように対処しているかを評価し、改善のための方法を探ります。その後、感情表現や対人スキルの強化が行われます。最後に、治療を終了する際、患者が学んだスキルを日常生活にどのように適用するかを確認し、維持するための方法を考えます。
対人関係療法(IPT)は、短期的かつ効果的な治療法とされています。治療の効果は個人差がありますが、うつ病や不安障害に関しては、多くの研究において有効性が示されています。治療を受けた多くの患者は、症状の軽減を感じ、対人関係のスキルを向上させることができたと報告しています。また、治療後もその効果が持続することが確認されています。IPTは、うつ病の再発予防にも有効であり、患者が社会的な支援を得る方法を学び、ストレスに対する対処能力を向上させるため、長期的な回復にも貢献します。
対人関係療法を受けたい

当オフィスでも対人関係療法を行っています。ご希望の方は以下の申し込みフォームからご連絡ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。