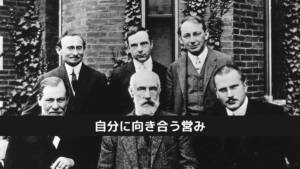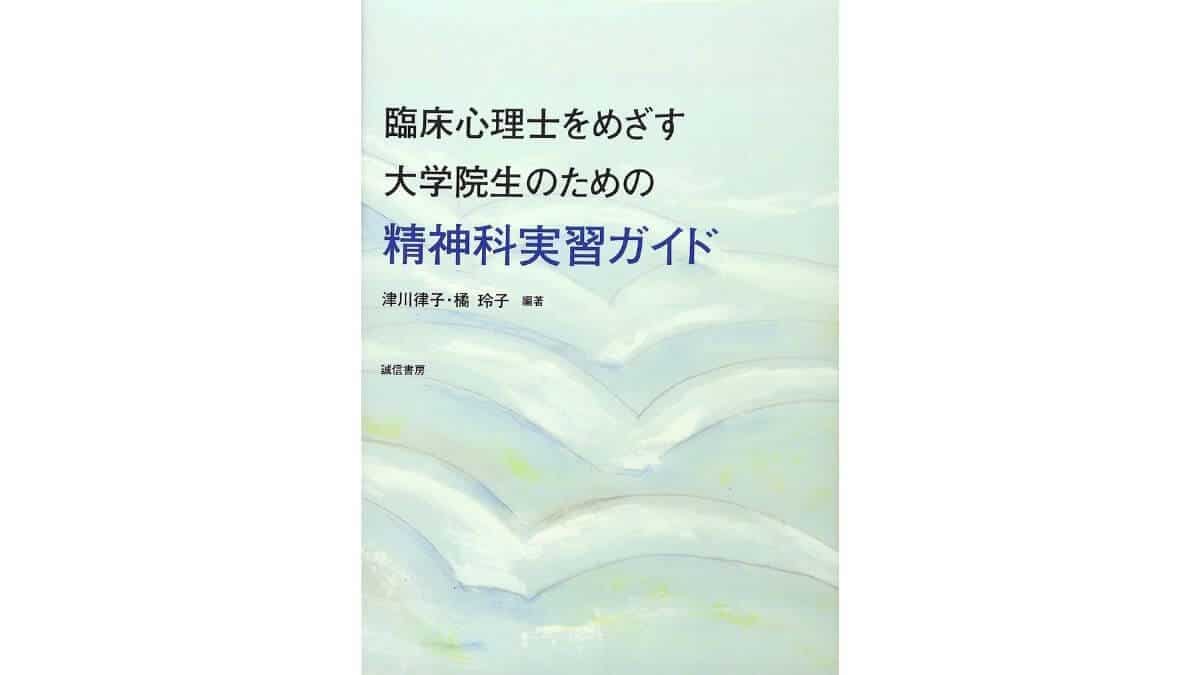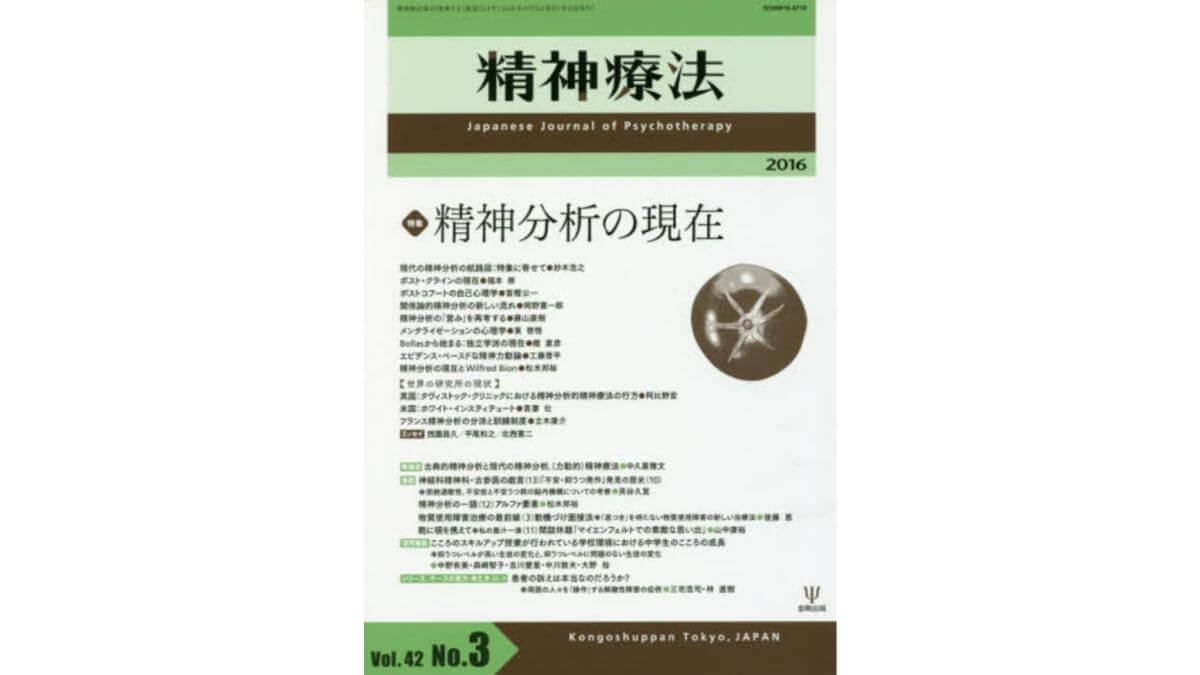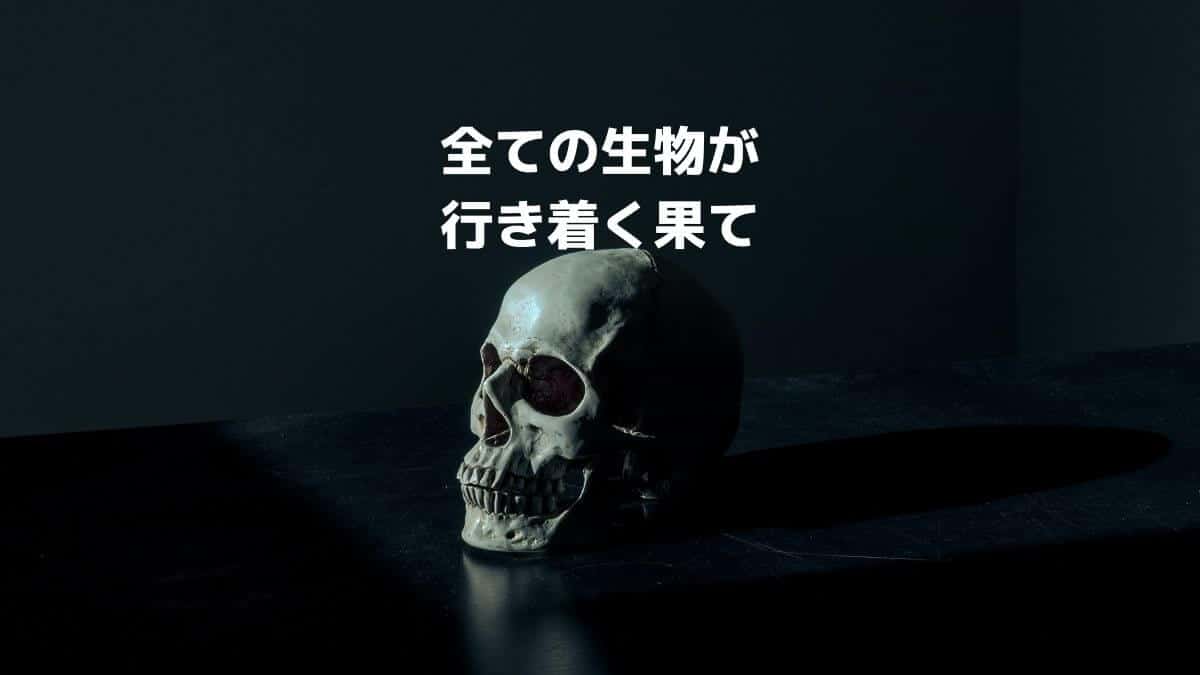移行対象と移行現象

D,W,ウィニコットの1951年の論文「移行対象と移行現象」についての要約です。子どもが一時、ぬいぐるみや毛布など柔らかいものを好むことがありますが、ウィニコットはそれらが現実世界への橋渡しをしていると指摘しました。
論文の背景
1935年~1941年にクラインのスーパービジョンを受ける。1940年初期にアンナ・フロイトとクライン大論争が起こる。ウィニコットはクライン派、アンナ・フロイトのどちらにも属さず、中間に属すようになる。
1951年に「移行対象と移行現象」を出版し、クラインとウィニコットの決別が決定的となる。アンナ・フロイトの「自我と防衛」の外的現実との適応面に注目した議論と、クラインの「母親の乳房」という内的幻想的側面の橋渡しをしようとしていた。
そして、2人の女性の橋渡しをしながら、自分のパーソナルな領域を作っていった。
基本的仮説
乳幼児が生後間もなく、指などを使い口唇快感領域を満足させることと、生後2~3ヶ月頃に人形と遊ぶのを好み、特別な対象に夢中になるということの間には相関関係がある。
(1)最初の所有物
生後間もない赤ん坊が、「最初の我(じぶん)でない所有物(Not-Me-possession)」を使う方法は様々なパターンで現れる。例えば、握りこぶしを口に入れる行動→テディベア→やわらかい玩具→固い玩具等への愛着へと移る。
親指とテディベアの間、恩を受けていることに気付かない原初的段階と受けていることに感謝する段階、などの間にある体験の中間領域(inter mediate area of experience)を移行対象・移行現象(transitional object / transitional phenomena)と呼んだ。
①最初の所有物について、②主観的なものと客観的に知覚されるものとの間の中間領域(=幻想・錯覚の領域)を重視した。
(2)個人的パターンの発達
真の「我(じぶん)ではない」対象を扱えるようになるまでの進展について。
a.移行現象
幼児側から自分以外の対象を個人パターンに織り込んでいく傾向が現れる。指しゃぶりの様な自体愛的体験と組み合わさり、機能的体験(ex1:シーツや毛布をつかみ指と一緒に口へ入れる、ex2:「mum-mum」・喃語などを伴い、口をもぐもぐさせる)が見られ、考えることや空想することが結びついてくる。
b.移行対象
毛布などの端、単語や歌、クセなどの事物や、現象等が出現する。幼児にとって、寝付くまでのための非常に重要であったり、抑うつ不安に対する防衛であったりする。ある柔らかな対象などを使用するようになり、重要性を持ち続ける。
その価値を見出し、母親はそれが汚れても洗わないように配慮するようになる。もし洗ったら幼児の体験の連続性に中断が起こり、その対象が幼児に対して持つ意味と価値を破壊してしまう中断を生じさせる。
移行現象のパターンは、生後4ヶ月、6ヶ月、8ヶ月、12ヶ月までに出現する。
(3)健全な発達の場合
移行対象は「内側に入る」こともないし、それに対する感情が抑圧される必要もない。忘れられることも、悲しまれることもなく、意味を失う。移行対象は、拡散し、「内的心的現実」と「2人の個人に共通に知覚される外的世界」の間の中間領域全体に広がっていく。子どもの関心は拡大し、抑うつ不安時でも拡大した関心の範囲は維持される。
男子は堅い対象物を使うのが上手くなり、女子は人形で1つの家族をつくっていく傾向がある。最初の「我(じぶん)でない」所有物の使い方に際立った男女差はない。
移行対象につけられる名前には、大人が使った単語が部分的に混入している。Ex)「baa」が名前の場合、大人が使った「baby」等の単語に由来している場合がある。
愛情はく奪におびやかされたりすると、最早期に始まった特定の対象や行動パターンが再び必要になることがある。
母親意外に移行対象の無い場合や、幼児の情緒発達がひどく障害され、移行的状態を享受できなかったり、使われる対象物の連続性が絶たれたりする場合もある。
(4)移行対象と象徴性(symbolism)との関係
一枚の毛布が乳房の象徴であることは確かだが、毛布の特質はその象徴的価値よりも実存性にある。毛布は現実に乳房や母親でないが、そうでないという事実は、毛布が乳房や母親を意味していることと同じくらい重要である。
幼児が象徴性を使う時、空想と現実、内的対象と外的対象、原初的創造性と知覚を明確に区別している。移行対象は、その違いと共通性を受け入れていく過程に重要である。
(5)所有物の早期の使用に関する比較の臨床例
移行対象の使用が歪曲した兄と、典型的な使用をした弟がいる。兄は生後7ヶ月まで母乳で、離乳は困難であった。母に対して非常に強い愛着を持ち、指しゃぶりをせず、哺乳瓶やおしゃぶりを受けつけず、離乳時には頼るものがなかった。同時期喘息になった。
12ヶ月時に、ウサギのぬいぐるみ→本物のウサギへ愛着(5~6歳まで)した。ウサギ=元気づけるもの(comforter)だったものの、移行対象とはならなかった。真の移行対象は、常に幼児と不可分な幼児の一部であり、母親より重要である。
一方で、弟は生後4ヶ月まで母乳で育った。生後間もなく指しゃぶりがあり、容易に離乳した。その後、毛布の端「baa」からセーターへ移行した。これは落ち着かせるもの(soother)の典型的な移行対象である。
(6)生育歴聴取の重要性
子ども全員の早期所有物と技巧について情報を得ることが重要である。聴取する時、比較すると想起しやすい。子どもは移行対象を覚えていて語ることもある。移行対象の性質や行動を述べる時、現実感覚を失っているかのように喋る。
理論的考察
(1)移行対象とクラインの内的対象(internal object)の比較
移行対象は心的概念である内的対象でも、外的対象でもなく、所有物である。移行対象を用いられるのは、内的対象が生き生きとして、現実性を持ち、good enoughな(迫害的すぎない)場合である。内的対象の質は、外的対象(乳房、母的人物、環境からのケア)の存続、活動性、態度に左右される。
しかし、一方で、外的対象の本質的な機能が不十分であると、間接的に内的対象は死の状態に陥るか迫害的な質を帯びる。この状態が長く続くと、内的対象が意味のないものになり、移行対象も無意味なものになる。
(2)幻想―幻滅(錯覚―脱錯覚)
幼児が快感原則から現実原則へ進むためには、ほどよい母親(good enough mother)が不可欠である。ほどよい母親は、幼児のニーズに対して積極的にほぼ完全に適応し、時間経過に伴い、幼児が母親の不在に対処する能力が増大するのに応じて、徐々に適応の完全さを減らしていく。
(3)幼児が母親の不在に対処する手段
母親の不在による欲求不満は時間が限られていることを体験する。時間の経過についての感覚の増大する。精神的活動性が開始する。そして、自体愛的満足を利用し、それが移行現象になる。思い出す、追体験する、空想する、夢を見るなどが、過去、現在、未来の統合を可能にしていく。
全てが順調なら、欲求への適応を不完全にすることが、対象を愛されながら同時に憎まれるものにして、対象を現実的なものにする。逆に、適応が長すぎ、自然に減らされないと、それにより幼児は障害を受ける。なぜなら、完全な適応は魔術的で、幻覚にすぎないからである。
適応は、最初は正確である必要がある。外的現実との関係を体験する能力や、外的現実についての概念を形成する能力の発達を開始できない。
(4)幻想(錯覚)とその価値
母親は初期には幼児の要求にほぼ100%適応し、乳房は幼児の一部という幻想を与える。そして、最終的に幼児を徐々に幻滅させる(断乳)が目指されるが、そのためには、初めに幻想を持たせる機会を十分に与える必要がある。幼児の中で、乳房は繰り返し創り出され、主観的現実として発達する。
中間領域とは、原初的創造性と、客観的知覚との間に持っていると認められる領域である。生まれた時からこの関係性について十分に着手されないと、その問題を解決する際に健全でなくなる。
発達の早期に、母親によって供給されたある確かな状況に置かれた幼児は、本能的緊張から拡大していく欲求を何かが必ず満たしてくれると考えることができるようになる。欲求への母親の適応がよい場合、幼児は自分の創造能力に対応する外的現実があるという幻想を持て、供給するものと、幼児の考えが重なる。
移行対象・移行現象のおかげで、個人にとって重要な意味を持つ「正当性を問われない体験の中立領域(a neutral area of experience)」との関わりを、人間は個々に始められる。
幻想を幻滅させる過程の中で、離乳により欲求不満が登場する。離乳をめぐる現象(クラインの抑うつポジション)において、幻想と、徐々に幻滅の機会が与えられている。
幻想の幻滅がうまくいかないと、幼児は離乳を達成できず、離乳へ反応することや、言及することもできなくなる。
(5)幻想―幻滅(錯覚―脱錯覚)理論の発展
現実受容という作業は完結することはなく、内的現実と外的現実を関連させる重荷から解放されることはない。体験の中間領域がその重荷を軽減する。芸術や宗教や、遊びに夢中になる子どもの遊びの領域と直結している。幼児期の中間領域は、子どもと世界との関係の習得にとって不可欠である。
中間領域は、早期の危機的な時期に、ほどよい母親の養育を受けることで存在可能になる。外的な情緒的環境と、移行対象などの物質的環境の特定の要素の時間的・連続性が重要である。
成人が、主観的現象の客観性を認めるよう求めたら、狂気として理解される。しかし、個人的中間領域を楽しみ、互いの中間領域が重なることを発見して嬉しく感じ、芸術などのグループのメンバー間の共有体験になる。
(6)理論的考察の要約
体験の中間領域は、内的現実と外的現実のどちらに属するかを問わず、幼児の体験の大部分を占める。そして、生涯を通じて、芸術、想像力に富んだ生活などに集中的体験の中に保存されていく。逆説が受け入れられることが肯定的な価値を持ちうる。逆説を解決することが、成人の中に真の自己組織と防衛組織を形成させる。
理論の応用
(1)移行現象の領域に示される精神病理
分離が移行現象に与える影響について考察する。母親が不在でも、母親の心的イメージなど、内的表象を持っていれば幼児が即座に変化することはない。しかし、記憶や内的表象が希薄化になると、移行現象は意味を失い、それを体験できなくなる。その喪失の直前、移行対象が意味を失う恐れを否認するために、移行対象を過剰に使用する例がある。
(2)臨床例「紐」
性格障害を思わせる症状がある、7歳の少年を取り上げる。母親は抑うつ的で、妹の誕生や母親の入院により3回も分離を経験した(3歳3ヶ月~4歳9ヶ月)。物や人をなめる強迫思考、排便の拒否などの症状出現した。
面接でスクイグルを実施したところ、線が全て紐に関連したものになる。現実場面では、物を紐で結ぶことに夢中で、部屋の物を紐で縛ったり、妹の首に紐を結んだりしていた。
「紐を使って、分離を否認する試みをして分離の恐怖を処理しているのでは?」と母親に問いかけたところ、母親と少年の間で分離のテーマが扱われると症状は消失した。母親は「子どもが母親を喪失し、最も重要な分離は、重篤なうつ状態になっている時。物理的に離れていることでなく、他の事柄に気を奪われ、接触が欠けてしまうこと」であると考えられる。
11歳の時に沢山のテディベアを家族のように大切にして母のように愛情を注ぎ、安心感を得ているようになった。母親との関係の不安定さに基づいた、母親同一化を持ち、同性愛や紐への倒錯的熱中への発展の可能性が考えられた。
紐はコミュニケーション技術の延長とみなすことができる。紐の過剰な使用は、不安定感の始まりや、コミュニケーションの欠如を表すと考えられる。分離の否認に変化していくという見解である。
(3)ファンタスfantasの種々の様相
両親の不在時に子どもが経験する徐々に進んでいく欠乏と関連しているケースを取り上げる。母親が次の子を産むために子どもから離れていく時、子どもに理解させることができない場合、ある一定の時間を越えると、子どもから見れば母親は死んだことを意味する。
その間に貴重な一瞬な怒りがある。消失するか、暴力への恐怖をはらみながら潜在する。死には、①母親が目の前にいるときの死、②母親が再び生き返らない時の死が存在する。再確認しなくても内的心的現実の中で人を生かしておける能力を子どもが創り上げる以前の時期に関係している。
(4)臨床例「分裂性格の女性」
分裂性格的な成人女性との1セッションを取り上げる。抑うつ的な夢を見て、空想することにおそわれる。女性は、11歳の時に疎開し、自分の幼児期と両親を完全に忘れ、世話してくれる人達をどのような呼び方もせずにすませた。それは、両親を思い出すことへの拒否だった。
彼女には、部分的な記憶喪失があり、姿も思い出せない前医師や、そこにない毛布により現実感を感じていた。そこにないものこそが現実的と考えられた。背景には、母親の献身と信頼性が非現実的で現実性に疑いがあった。そのため、移行対象よりも母親の不在の方が現実的だった。
議論
(1)総論
全体的に難解な論文であるといえる。例えば、「移行対象は内側に入ることもない」とはどういうことを意味しているのだろうか。さらに「乳房は魔術的統制下にある。…全能感とは実際の体験に近いものである」とはどういうことだろうか。
乳幼児期の経験を忘れていない人の世界は精神病の世界であると論じる人もいる。しかし、魔術的世界から抜け出せない状態が、病的な状態につながるといえるのだろうか。
最初の所有物で語られている「移行対象」や「中間領域」と幻想で語られている「移行対象」や「中立領域」は異なるのだろうか。前者は実際の物でもあり、後者はより内的なものであるかもしれない。断乳のプロセスのために移行対象が存在することが重要であるが、幻想がどのように中立領域への変化に寄与しているのだろうか。
「成人して、個人的中間領域を楽しみ、互いの中間領域が重なることを発見して嬉しく感じ、芸術などのグループのメンバー間の共有体験になる」とは、趣味は中間領域になりうるのかもしれない。特定のゲームや漫画のキャラクターなどに没頭するなどは典型例だろう。ただ、時に「趣味がない」と話す人もいるが、こうした人が病的と言えるかどうかは議論が必要だろう。
(2)臨床的あらわれ
- 快感追及ではなく安らぎを与えるもの
- 母親から与えられたモノであるにも関わらず、自分のモノになっている
- 内的な体験世界が付与されているが、単なる投影でも幻覚でもない
- 母親からの分離の際に重要となってくる
- 母親とのほどよい関係を基盤にして生じているので、母親との関係が悪化すると消失する
- 徐々に脱備給されるが抑圧ではなく文化的活動の領域に吸収される
(3)オグデン理論
母子一体化(一者性)の後に出現してくる移行現象は象徴・象徴されるもの・第三主体からなる心の世界が展開している。すなわち移行現象には象徴化能力が決定的に重要な役割を担っている。
移行現象の創造と維持に不具合が生じた時には、以下の4つの型の特異な精神病理として出現する。
- 空想と現実の区別ができない
- 情緒的象徴的意味合いが否定
- 空想と現実が解離し、フェティッシュや強迫心性が出現
- モノや対象に意味が付与されない
(4)移行現象と転移
メルツァーは移行現象や移行対象を防衛、もしくは倒錯、固着として理解できるとした。
ただ、やはり、それは移行現象や移行対象の健康的な側面を無視したものであるといえなくもない。いずれにせよ、こうしたことはセラピストとの転移のなかでも表れてくるものであり、それをどう理解するのかによって変わってくるのだろう。停滞のために使用するなら倒錯や固着だろうし、成長のために使用するなら移行現象といえるだろう。そして、セラピストをこうした使用方法で扱ってくる。
さいごに
さらに精神分析について関心のある方は以下のページをご覧ください。