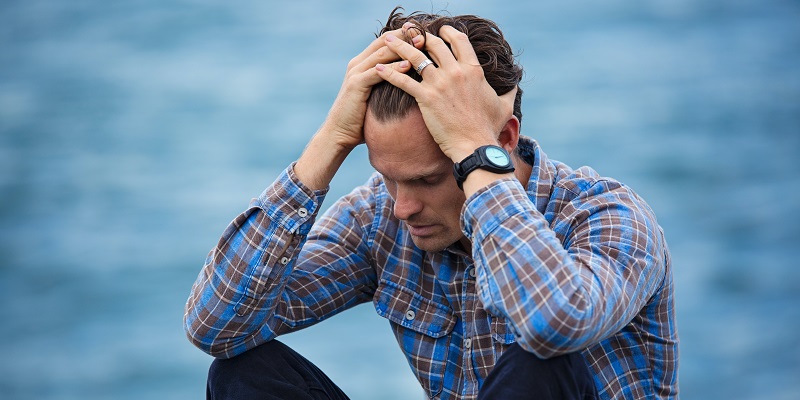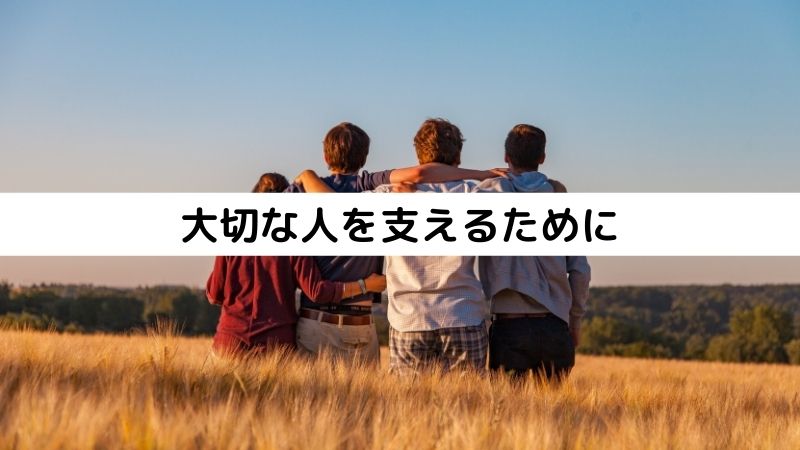統合失調症になった家族や友人への接し方

自分のご家族やご友人がもし統合失調症になってしまった際にはどのように接すれば良いのでしょうか。統合失調症の症状を回復させるためには、ご家族や周囲の方の協力が必要になりますが、ご家族自身もどのように本人に接すればいいのか分からずに過大なストレスを感じてしまうなど心身ともに消耗してしまう場合も決して少なくありません。
このコラムでは統合失調症について、分かりやすく解説し、ご家族の接し方のアドバイスをしていきます。また、ご家族がつらい場合や本人が受診したくないケースでは家族向けのカウンセリングを利用することもできます。
目次
統合失調症とは
統合失調症とは、およそ100人に1人が罹患する病気と言われている脳の病気であり、決して珍しい病気ではありません。この疾患は、脳の伝達物質のバランスが崩れることが原因となって様々な症状が現れます。
ご家族の中には、「遺伝が関係しているのではないか?」、あるいは「自分たちの接し方が悪かったから発症したのではないか?」などと自分たちを責めてしまう方も少なからずいらっしゃいますが、そういったことはありません。遺伝は原因の1つと言われていますが、あくまで原因の1つとされているにすぎません。
統合失調症の原因は現代医療では明らかになっていないのが現状です。
発症してしまった原因を追究して考えるのではなく、発症した後にどのように症状が回復できるかに重点をおいていきましょう。統合失調症はご家族や周囲の方の支援が回復の大きな助けになることが知られています。
統合失調症のさらに詳しいことは下記のページをご覧ください。
よくある相談の例(モデルケース)
50歳代 女性
Aさんは大学を卒業後に就職し結婚、二人の子どもを育ててきました。穏やかな家庭を築いてきたものの、数年前から大学生になった息子に異変が見られるようになりました。最初は夜眠れない、集中できないといった小さな不調でしたが、やがて「誰かに見られている気がする」「監視されている」といった訴えが強まり、生活全般に支障が出るようになりました。家族との会話も減り、引きこもる時間が増え、次第に妄想や幻聴が顕著となっていきました。精神科を受診した結果、統合失調症との診断が下され、薬物療法が開始されました。
薬を服用し始めてから症状は一定の改善を見せましたが、Aさんはどう息子に接したらよいのか分からず、戸惑いと不安を抱えていました。息子が混乱している時に問い詰めてしまい、かえって口論になることもありました。また、病気に対する周囲の偏見を恐れ、親戚や近所に相談できず孤立感を強めていきました。そのような中で、少しでも息子の力になりたいと考え、Aさんは臨床心理士のカウンセリングを申し込みました。
カウンセリングのプロセスでは、まずAさん自身の気持ちを整理し、無理に息子を説得したり矯正しようとするのではなく、安心感を与える関わり方を学んでいきました。心理士からは、統合失調症の症状や経過、薬物療法の意義について丁寧な説明があり、息子が感じている世界を尊重しつつ、現実検討を支えるような関わり方を少しずつ実践していきました。同時にAさん自身の疲労や不安にも焦点が当てられ、家族としてのサポート体制を整えることが大切であると強調されました。
このような取り組みを続けるうちに、息子は安心できる家庭環境を少しずつ回復し、再び外来通院に前向きな姿勢を示すようになりました。社会復帰に向けて就労支援やデイケアを利用することも視野に入れられ、Aさんも「病気を抱えながらも生活を続けていける」という実感を持つようになりました。カウンセリングは数年にわたり継続され、Aさんが孤独を抱え込まず、息子との関係を少しずつ修復していけるよう支えとなりました。最終的にAさんは、息子の症状が再燃する可能性を理解しつつも、柔軟に受け止めて対応できるようになり、家族としての安定した生活を再構築していきました。
統合失調症の症状
統合失調症では主に陽性症状・陰性症状・認知機能障害という3つの症状があります。
- 陽性症状・・・妄想や幻覚(幻聴)などの症状を指します。
- 陰性症状・・・表情が乏しい、何をするにも意欲が湧かないなどの症状です。
- 認知機能障害・・・1つの物事に集中できない、記憶の問題が生じる、あるいは物事の段取りが出来ないなどの症状を意味しています。
統合失調症の症状とステージ
統合失調症は、主に陽性症状・陰性症状・認知機能障害という主に3つの症状が見られますが、その病状は急にすべてが一気に出てくるわけではなく前兆期・急性期・消耗期・回復期という4つのステージで現れることが知られています。
では、各ステージでどのような症状が見られるのでしょうか。
(1)前兆期
一般的な言葉で言えば、統合失調症の初期段階と考えられます。症状も一般的な倦怠感や疲れの症状とも似ているため、ご本人を含めてご家族や周囲の人も気づきにくいような小さな変化であることが多いです。
例えば、寝つきが悪い、朝起きにくい、頭痛や食欲不振などの体調不良を訴えるなどが挙げられます。
その一方で、「なんとなく人に見られているような感覚」と表現されるように一般的な疲労感ではあまり認めない症状がこの時期から見られる場合もあります。
(2)急性期
このフェーズになると、「誰かに見られている」、「町中で悪口を言われている」など妄想や幻覚といった陽性症状が出ていることが多く、ご家族が変化に戸惑うことも多い時期と言えるでしょう。
(3)消耗期
急性期の症状が落ち着いた後の、「やる気が出ない」、「体がだるい」などと訴えて、無気力で、周囲の物事に無関心になり、一日中寝ているような状態が続く時期です。
(4)回復期
回復が進み、表情や気持ちに変化が現れて会話や自発性が戻ってきます。また、社会復帰に向けて意欲が出現してくる時期です。
それぞれのステージでどのような対応が出来るか?
次に、統合失調症における4つのステージで、ご家族はそれぞれどのような対応が出来るのかをよくあるお悩みをもとに解説していきます。
(1)前兆期
症状の変化に気づくことは難しいことも多いですが、休養を促したり、何か悩みはないか聞いてあげたりすることが出来るでしょう。
本人に過度な不安感や感覚過敏など一般的な疲れとは異なる症状が出ている場合には、病院の受診を検討しましょう。
Aさんの場合、息子は大学生活の中で不眠や集中力の低下を訴えるようになり、以前より引きこもりがちになっていきました。家族との会話も減り、どこか違和感のある言動が目立ち始めました。
(2)急性期
「誰かに見られている」、「電話が盗聴されている」というような妄想や幻覚が現れることも多い時期です。そして、特にこの時期には対応に悩まれるご家族もたくさんいらっしゃいます。
ご本人の状態によって適切な対応は変わるため一概には言えませんが、妄想や幻覚自体をすぐに否定してしまうとますます本人は混乱してしまうため、話を聞く姿勢を見せてあげるといいでしょう。
あくまで一例ですが、ご本人の様子と合わせて次のような返答をしてあげると良いでしょう。
- 「誰かに見られている。」→「大丈夫だよ、私が一緒にいるよ。」
- 「電話が盗聴されている。」→「それは大変だね。何かあっても私が手伝って対応するから心配しなくてもいいよ。」
- 「周りの人に悪口を言われている。」→「そうなの?私には何も聞こえないけど、それは気持ち悪いわね。でも何があっても私がいるから大丈夫よ。」
Aさんは、息子が「監視されている」「声が聞こえる」と強く訴えるようになり、妄想や幻聴が日常生活を大きく妨げる様子を目の当たりにしました。混乱が強まり、口論になることも増えていきました。
(3)消耗期
周囲からは本人がだらだらとして見えて、ご家族のストレスが溜まることも多い時期です。
患者さんの状態としては、症状が落ち着いたことで「声が聞こえてきたりしなくなったのに、体がだるくて動けない。」、あるいは「今日も思うように動けなかった。」など不安や自己嫌悪を感じやすい時期です。
そのため、本人に対しては、「大変な時期を通過するために体力を使ったので、今は休むことに専念するのが良い」といったような内容の言葉かけをすると良いでしょう。そして、消耗期に入っているということは、しばらくするとほとんどが回復期に移行し、徐々に良くなっていきます。ですので、それを希望にして本人や家族が共にお互いゆったりと構えることが重要です。
Aさんの息子は幻聴や妄想の影響から疲弊し、無気力や感情の乏しさが際立つようになりました。以前のような活力を失い、生活全体に閉塞感が漂いました。Aさん自身も対応に疲れを感じました。
(4)回復期
徐々に状態が回復してくる時期です。ただ、前兆期にまたループして再発を認めてしまう可能性もあるので、無理は禁物です。
症状が回復してくると、本人が薬を飲み忘れることも増えるためにご家族としては薬の飲み忘れがないかなど日々確認してあげましょう。
Aさんの場合、治療とカウンセリングの継続によって、息子は次第に落ち着きを取り戻しました。家庭内で安心できる時間が増え、通院や支援機関の利用に前向きになるなど、少しずつ回復の兆しが見えてきました。
統合失調症の家族に対する対応に困ったら家族向けカウンセリングの検討も
家族から見た症状や対応を読んできた中で大変だな、対応難しいな、と感じているご家族に向けて、家族向けカウンセリングを案内します。
統合失調症は、薬物療法やカウンセリングで回復が見込まれる病気です。一方で、家族のサポートが必要となりご家族の負担も多い部分があります。
例えば、ご本人が受診を拒否する、本人に対してどのように接したらいいのか分からない、様々な対応をするうえで非常にストレスを感じているといった場合には「家族向けカウンセリング」をぜひご利用ください。
(株)心理オフィスKの家族向けカウンセリングでは以下のことが可能です。
- 受診を拒否する患者さんへご家族がどのようにアプローチしたらいいのかのアドバイスをします。
- 4つのステージで症状が変化していく患者さんへの対応についての相談に乗ることができます。
- ご家族のストレスを緩和するためのサポートも提案できます。
統合失調症の家族をサポートする力になるために、このようなご家族向けのカウンセリングをご用意しています。
ご希望の方は以下のページからお申し込みください。
この記事が、家族や友人が統合失調症になって、どのように対応すればいいのか悩んでいる人にとって少しでも参考になれば幸いです。