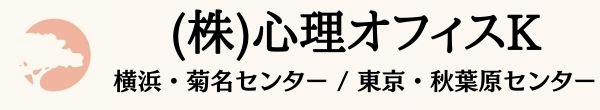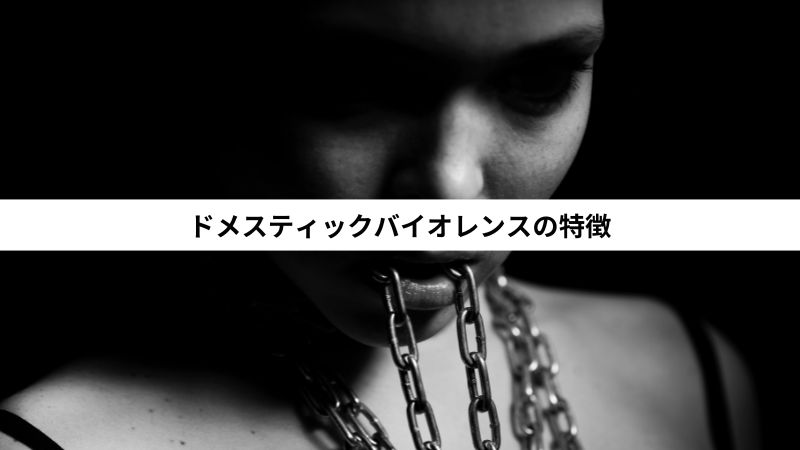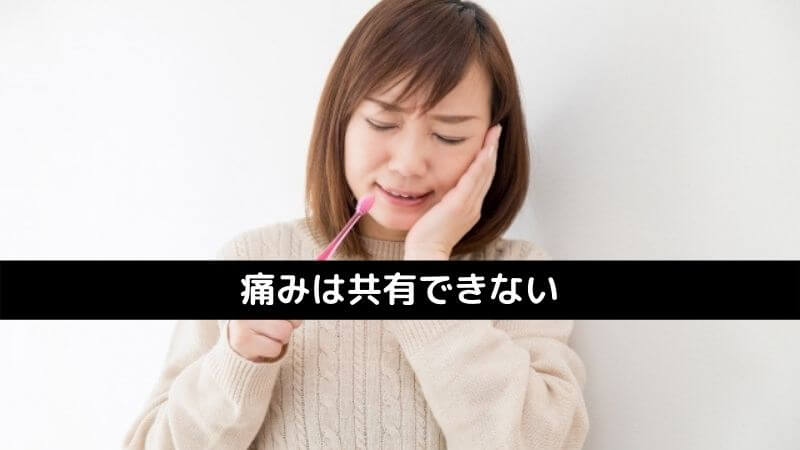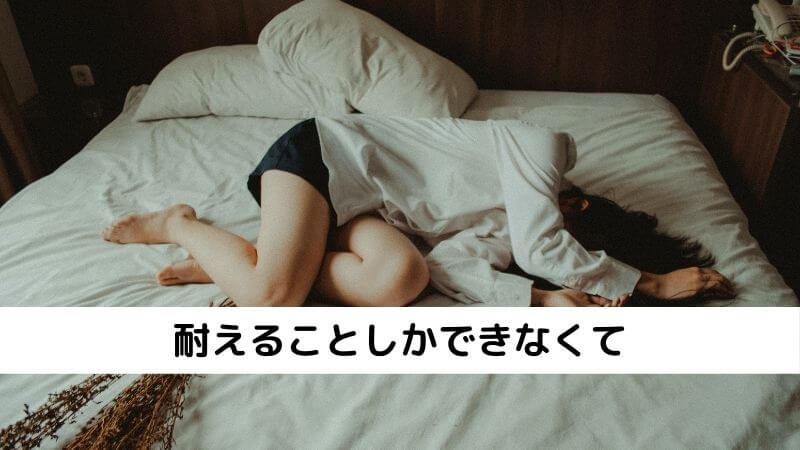夜眠れない原因とは?潜んでいる病気と解決方法について

「夜になっても毎日眠れない」「眠ってもすぐに目が覚めてしまう」という方に向けて、夜眠れない原因や潜んでいるかもしれない病気、解決方法について紹介します。
そもそも人間は、安心したら眠る、疲れたら眠る、夜だから眠るという仕組みで成り立っています。夜眠れないということは、このバランスが崩れてしまい、寝つきが悪くなったり眠れなくなったりする状態にあるというわけです。バランスが崩れるには、何か問題が潜んでいるため、その問題を解決すれば眠れるようになることも。不眠に対して、どういった問題が起こり得るのか見ていきましょう。
目次
そもそも眠れないとは?

そもそも人間は、あることをきっかけに眠れる仕組みになっています。眠れないということは、そのあることができなくなっているのです。どういった変化が起きているのでしょうか。
(1)睡眠の基本的な仕組みについて
人間が眠る行動は、基本的に「安心したら眠る」「疲れたら眠る」「夜だから眠る」というパターンで構成されています。脳を休ませるために睡眠は欠かせません。
しかし、心配ごとが多かったり不安感が強かったりすると、いろいろなことを考えすぎてしまい脳が興奮して眠れなくなるのです。
人は生まれながらに、夜になると眠くなるようになっています。昼間は活発に活動し、就寝2時間前くらいになると皮膚の温度が高くなり、体内温度が下がります。体内時計が正しく機能していれば自然に眠くなり、ベッドに横になるとスムーズに眠れるでしょう。反対に、体内時計が狂ってしまうと、眠れなくなるというわけです。
(2)よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 男性
Aさんは40歳代の男性で、会社員として営業職に従事しています。几帳面で責任感が強く、仕事の評価も高い一方で、上司や取引先との関係に常に気を配り、自分の失敗を極端に恐れる傾向がありました。幼少期には厳格な父親のもとで育ち、失敗や怠惰に対しては厳しく叱責されてきた経験があり、それが「常に完璧であらねばならない」という価値観として根づいていました。
数年前から、寝つきの悪さや夜中に何度も目が覚めるといった不眠の症状が現れ始めました。最初は仕事の繁忙期だけの一時的なものと考えていましたが、徐々に不眠が慢性化し、日中の集中力の低下や気分の落ち込みも見られるようになりました。睡眠薬を処方され一時的には眠れるようになったものの、薬に頼ることへの不安も強まり、根本的な解決には至りませんでした。
「眠れなかったらどうしよう」という考えが寝る前になると浮かび、不安が高まって余計に眠れない、という悪循環に陥っていたAさんは、心療内科の医師のすすめでカウンセリングを受けることにしました。初回面接では、生育歴や性格傾向、不眠の経緯などを丁寧に振り返り、睡眠に関する思考と行動パターンを明らかにしました。
カウンセリングでは認知行動療法(CBT)を導入し、睡眠日誌をつけながら、Aさんの「眠れない自分はダメだ」という自動思考を検討していきました。思考記録表を用いて、根拠のある現実的な見方を一緒に探し、「眠れない日があっても、自分の価値が下がるわけではない」と考えられるようになっていきました。また、ベッドに入る時間や起きる時間を整える睡眠衛生の指導や、リラクゼーション法、就寝前のルーティン見直しなど、行動面からのアプローチも並行して行いました。
数ヶ月の取り組みの中で、Aさんは徐々に睡眠に対する不安が減り、再び自然な眠りを取り戻すようになりました。不眠の背景にあった自己批判的な認知に気づき、そこに柔軟性を持たせることが、改善への鍵となりました。
(3)「夜眠れない」は睡眠障害の可能性も
「夜眠れない」という症状は、睡眠障害に陥っている可能性があります。睡眠障害とは、睡眠に対して何らかの問題がある状態のことです。具体的には、眠ろうとしても眠れない、夜中に目が覚め眠れない、昼間眠くなるなどの症状が現れます。
Aさんの場合、寝つきの悪さや中途覚醒が長期間続き、日中の活動にも支障が出ていたため、睡眠障害の一つである「慢性不眠症」の可能性が疑われました。
睡眠障害になる主な原因とは

(1)ストレス
ストレスの影響で睡眠の質が低下する可能性があるでしょう。睡眠中は、レム睡眠とノンレム睡眠の状態が起こります。レム睡眠は睡眠中も脳が働いており、夢を見るのもこの状態のときです。
ノンレム睡眠は、深い眠りで脳が休んでいる状態といえます。精神的なストレスが大きいとレム睡眠の時間が長くなってしまいます。
Aさんは仕事上のプレッシャーや対人関係のストレスを常に抱えており、それが夜間の不安や思考の過活性につながっていました。
(2)生活習慣の乱れ
残業が続く、夜勤や日勤が入り乱れるなどの不規則な生活が続くと、体内時計が崩れて睡眠障害に陥る可能性があります。
また、就寝前にパソコンやスマホを見る行為が、睡眠障害の原因になることも。ディスプレイの光によって脳が覚醒し、眠れなくなるというわけです。
Aさんの場合、夜遅くまでスマートフォンを見る習慣があり、体内時計が乱れがちで、眠気のリズムが崩れていました。
(3)飲酒やカフェインの影響
就寝前の飲酒やカフェイン摂取が、睡眠を妨げることもあります。コーヒーなどに含まれるカフェインには、目を覚ます効果があり、就寝前に飲むと眠りにくくなるでしょう。また、利尿作用もあるため、夜中に目が覚めそのまま眠れなくなるというケースも。
就寝前のアルコール摂取は、カフェインと同じく睡眠の質を低下させます。さらには、睡眠時無呼吸症候群を悪化させることもわかっています。
Aさんは眠れない夜にアルコールを摂ることが増えており、一時的な眠気は得られても睡眠の質が下がる原因となっていました。
(4)女性ホルモンの変化
特に女性の場合、女性ホルモンの分泌の変化で眠れなくなることも。閉経前後の期間には、卵胞ホルモンであるエストロゲンが減少するために、心身ともに変化が現れます。いわゆる更年期障害のことで、その症状のひとつとして不眠になるケースもあるでしょう。
「夜眠れない」には病気が潜んでいるケースも

(1)うつ病
実は、うつ病の90%に不眠症状が現れるため、うつ病の初期症状といわれています。具体的な症状としては、ベッドに入っても眠れない、途中で目が覚める、早朝に目覚めそのまま眠れないなどです。眠れなくなると、昼間に眠気に襲われて集中力が低下したり、昼寝して生活リズムが崩れたりするためさらに悪循環に陥ってしまうこともあります。
うつ病についての詳細は以下のページをご参照ください。
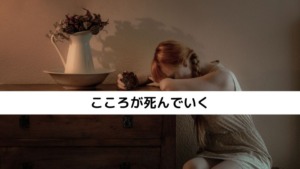
Aさんの場合、気分の落ち込みや興味の喪失も見られたため、抑うつ状態との関連が疑われ、医師による診断も並行して受けました。
(2)過眠症
過眠症は、夜眠っているつもりでも、しっかり眠れていないために日中眠気が強くなったり、起きていられなくなったりする症状のことです。主な原因には、睡眠時無呼吸症候群がありますが、なかにはがんなどの病気が起因しているケースもあります。
Aさんは入眠困難と中途覚醒が主であり、過眠症の症状は見られませんでした。
(3)むずむず脚症候群
レストレスレッグス症候群とも呼ばれるもので、寝る体勢をとると脚がむずむずしたりかゆくなったりするという疾患です。じっと座っているだけでも、同じような症状が出る人もいます。
また脚だけではなく、腰や背中、腕などにも症状が現れることがあり、夕方から夜にかけて症状が出るのも特徴です。
(4)周期性四肢運動障害
寝ているときに、脚や手といった四肢が自分の意志とは関係なく周期的に動いてしまうという障害です。身体が勝手に動くことに驚いて何度も目が覚めてしまいます。むずむず脚症候群の場合、周期性四肢運動障害を合併する可能性があることもわかっています。
自分でできる解決方法
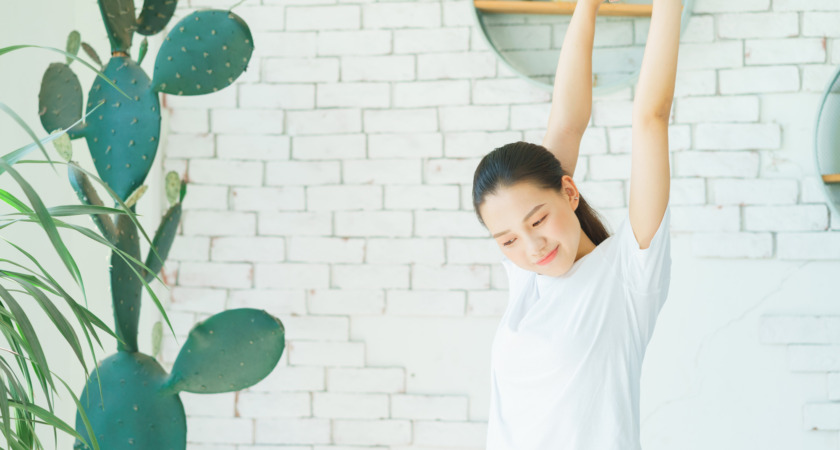
(1)生活習慣を見直す
最初に行うことは、生活習慣を見直すことです。早寝早起きや栄養バランスのとれた食事を規則正しく摂るようにしましょう。特に朝食を摂ることは、体内時計を整えるといわれているため、必ず食べるようにしてください。
さらには、朝に一定時間、太陽の光を浴びると良いでしょう。太陽の光により体内時計をリセットすることができます。
Aさんは毎日の就寝・起床時刻を一定に保つよう意識し、生活リズムの安定を図りました。
(2)就寝環境を整える
就寝環境を整えることも大切です。明るい環境だと睡眠の質が低下するといわれているため、不安を感じない程度に暗くすると良いでしょう。また、湿度や温度を調整することも大切です。
その他には、寝る前にスマホを見ない、音が気になる人は耳栓をする、寝具やパジャマにこだわるという対策をとるのも良いでしょう。
Aさんは寝室の照明を暗めにし、スマートフォンを寝室から持ち出すなど、環境調整に取り組みました。
(3)適度な運動
日中に運動をすると、寝つきや睡眠の質が良くなることがわかっています。ただし、激しい運動や就寝前の運動は、身体が興奮して眠れなくなるため注意してください。自分の身体にとってちょうど良い負荷の運動を定期的に行うことがおすすめです。
Aさんは日中に軽いウォーキングを取り入れることで、身体の自然な疲労を促し、眠気が訪れやすくなりました。
(4)入浴する
前述したように、人は皮膚の温度を上げ体内温度が下がった際に眠気を感じやすくなります。そのため、シャワーではなく入浴によって体温を上げると、体温の差が生まれやすくなり眠気が起きやすくなるでしょう。
入浴の際には、よりリラックスできるように入浴剤を入れるのもおすすめです。
Aさんは就寝の1~2時間前にぬるめのお湯で入浴し、深部体温を調整することで入眠しやすくなったと感じました。
いろいろ試しても変わらない!解決できる方法は?

(1)心療内科や精神科を受診する
ストレスの原因となる問題や悩みがある方は、心療内科や精神科を受診すると良いでしょう。医師の判断によって、抗うつ薬や睡眠薬などを用いて症状を緩和できることもあります。
Aさんは心療内科を受診し、不眠の背景にある心理的要因についても検討を始めました。
(2)睡眠外来がある病院を受診
睡眠時無呼吸症候群を疑う場合は、睡眠外来がある病院を受診すると良いです。睡眠時無呼吸症候群では、睡眠中に低酸素状態になっています。そのため、心血管疾患のリスクが高まるのです。
他の病気との合併症を防ぐためにも、睡眠時無呼吸症候群の治療を行いましょう。簡易検査や精密検査などで睡眠時無呼吸症候群と診断された場合は、CPAPという睡眠時の呼吸を助ける装置を装着して眠ったり、ダイエットや生活習慣の見直しをしたりします。
Aさんは今回は専門の睡眠外来は利用しませんでしたが、必要があれば紹介も検討する方針でした。
(3)カウンセリングに通う
どんな人でも、仕事や人間関係の悩み、家族間でのトラブルなどさまざまな問題があるでしょう。人に話すことで、心に抱えたモヤモヤを解消したり気持ちの整理ができたりすることも。それによって、安心して眠れるようになることもあるでしょう。
もちろん、身近に信頼できる人がいれば、その人に相談するのもおすすめです。しかし、「身近な人だからこそ心配をかけたくない」という気持ちから、なかなか相談できないケースもあります。そういうときには、カウンセリングに通うと良いでしょう。
カウンセリングの専門家なので、傾聴し眠れないことの原因を客観的に探ってくれます。また、自分では気づいていない問題点を見つけてくれることもあるでしょう。
Aさんは睡眠に対する不安や過剰な自己評価と向き合うため、定期的にカウンセリングを受け始めました。
(4)認知行動療法を行う
不眠症を中心とした睡眠障害には不適応的な認知と行動が関係していると言われています。認知行動療法で、そうした不適応的な認知と行動を変化させることで、睡眠の質と量を向上させることができます。
詳細は以下のページが参考になりますので、ご参照ください。
Aさんはカウンセリングの中で認知行動療法を受け、自動思考を見直しながら、睡眠に関する非現実的な信念を修正していきました。
まとめ:「夜眠れない」を放っておくと心身のバランスが崩れてしまうかも
一過性のものだと思って「夜眠れない」ということを放ってしまう人もいます。しかし、眠れないというのは、心身からの警告なのです。睡眠障害には病気が潜んでいることもあります。悪化させないためにも、解決策を試したり病院やカウンセリングを受診したりして早めの対策を行いましょう。
当オフィスには、心の疲れからくる睡眠障害などの専門知識を持ったカウンセラーが在籍しております。まずは、お気軽にご相談ください。