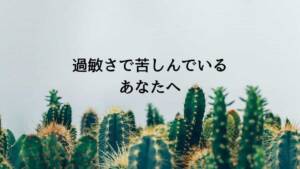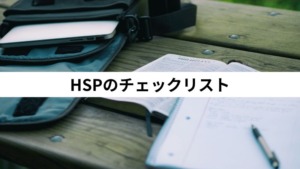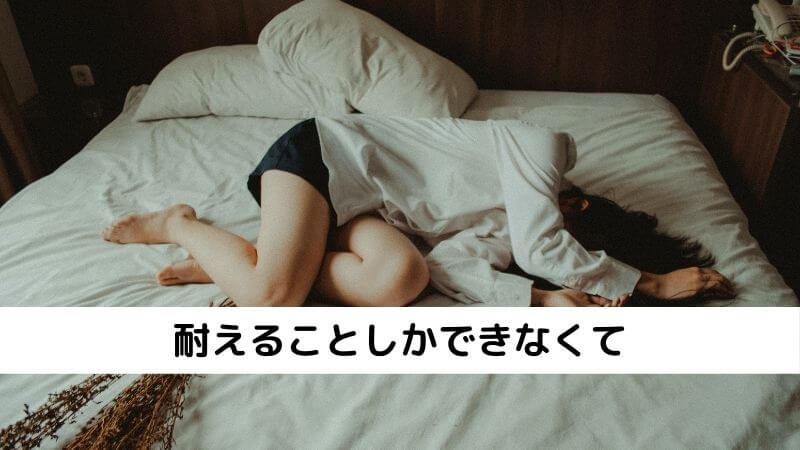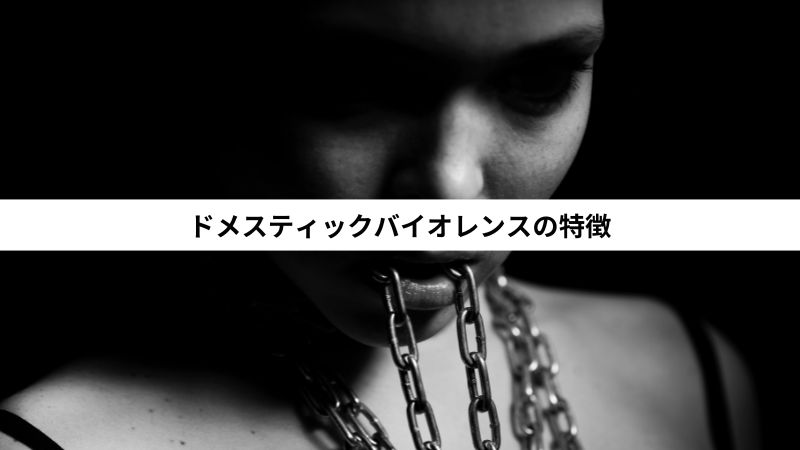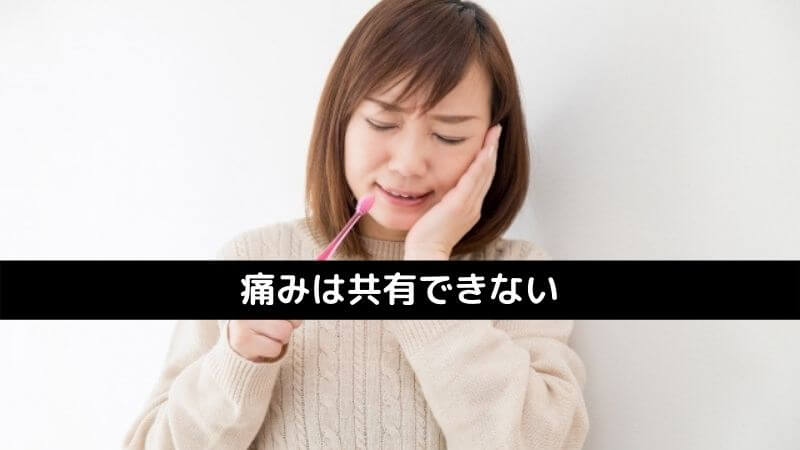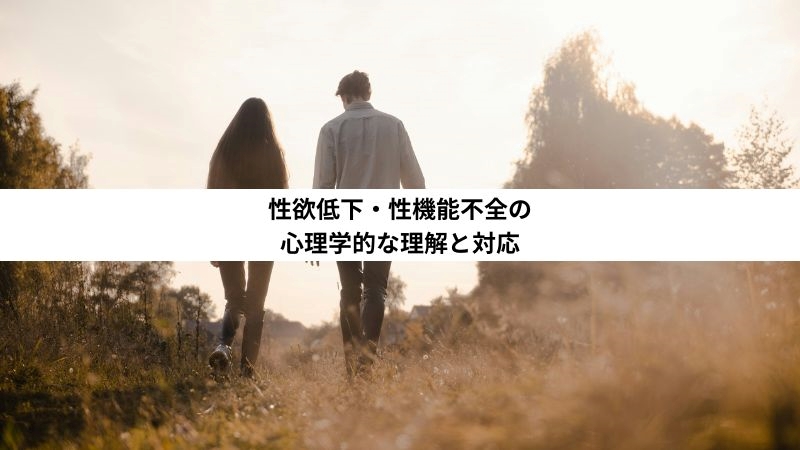すぐ泣いてしまうのはなぜ?原因や対処法を知って自分と向き合おう

泣きたいわけでもないのに、「些細なことでも泣いてしまう」「最近涙もろくなった」などと感じることはありませんか?
ストレスや感情の高ぶりによって涙を制御できなくなっているのかもしれませんが、もしかしたら他の原因が潜んでいるケースもあります。すぐ泣いてしまう原因を知り、自分を理解する時間を作ってみましょう。
目次
人が泣きたくなる理由とは?どんな人が泣きやすい?
そもそも人はどうして泣きたくなるのでしょうか?まずは、人が泣きたくなる理由について、次に些細なことでも涙が出てしまう「涙もろい人」にはどういった特徴があるのかを紹介します。
(1)なぜ泣きたくなるの?
「泣きたくなる」と聞くと、悲しいことがあったのか、または辛いことがあったのかと考えがちです。しかし実際にはどんな時に泣きたくなりますか?
たしかに、悲しいことがあった、失敗をして悔しい思いをしたなどの時に泣きたくなるでしょう。ただ、その他にも映画に感動して涙が出た、嬉しい報告を聞いて涙が出たというケースも考えられます。
人には喜怒哀楽があり、その時々に涙を流すことがあります。つまり、感情が高ぶると涙が出るのです。感情が高ぶると考えれば、さまざまな状況が思い浮かぶでしょう。人の感情が高ぶった際の例を喜怒哀楽に分けて、以下で紹介します。
- 【喜】試験に合格したことがわかった
- 【怒】何度言っても注意を聞いてくれない
- 【哀】身近な人が亡くなった
- 【楽】久しぶりに友人に会えて素敵な時間を過ごせた
具体例を見ると、泣きたくなるタイミングと感情の高ぶりとの関係に納得いただけるでしょう。しかし、感情が高ぶったからといって、大人がその度に涙を流すわけでもありません。一方で、些細なことでも泣いてしまう涙もろい人もいます。
涙もろい人とそうでない人の違いはどこにあるのでしょうか?ここからは、涙もろい人の特徴について紹介していきます。
(2)よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは30代の女性で、子どもの頃から感受性が強く、ちょっとした言葉や場面で涙が出てしまうことが多くありました。幼少期には、母親から「泣き虫だね」「弱い子だ」とからかわれることがあり、そのたびに自分でも涙を抑えられないことへの恥ずかしさや劣等感を募らせていきました。学校生活では、先生に注意されただけで涙が止まらなくなり、友人から「すぐ泣く子」と思われることがつらい経験として積み重なりました。大人になってからも、職場で上司に指摘を受けたり、ちょっとした人間関係の摩擦に直面しただけで涙が出てしまい、本人の意思に反して「感情的すぎる」と評価されてしまうことが多く、社会生活に大きな影響を与えていました。
Aさんは30代半ばに体調不良をきっかけに心療内科を受診し、医師から「特に精神疾患というより、感受性が非常に高い気質の影響が強い」と説明されました。そこでHSPの気質に関する書籍を読み、自分が人より刺激に敏感で、感情があふれやすいことに納得しましたが、それでも日常生活で涙を抑えられないことへの困りごとは続いていました。そこでより丁寧に自分の心を理解したいと考え、カウンセリングを申し込むことになりました。
カウンセリングでは、まずAさんが「泣いてしまうことを否定し、恥ずかしいものとして隠そうとする」心理に焦点が当てられました。カウンセラーとの対話を通じて、涙は弱さの表れではなく、感情の自然な反応であることを少しずつ受け入れられるようになっていきました。さらに、自分の過去を振り返る中で、幼少期に母親から繰り返し言われた言葉が「泣く自分はダメ」という自己評価を強めていたことに気付きました。この気づきは、涙を自分の一部として肯定する第一歩となりました。
長期的なプロセスの中で、Aさんは仕事や人間関係で涙が出そうになったとき、呼吸法やその場を一度離れる工夫を覚えました。また、泣いてしまったとしても自分を責めず、「私は感情を豊かに感じ取れるからこそ涙が出る」と捉え直せるようになりました。数年にわたるカウンセリングを経て、Aさんは涙を抑え込むのではなく、涙を自分の気質として受け入れながら社会生活を送れるようになり、人との関わりも以前より楽になったと実感するようになりました。
(3)涙もろい人の特徴
涙もろい人は感情が高ぶりやすいだけなのではありません。その他にも、さまざまな理由があって涙もろくなっているのです。以下では、涙もろい人の特徴をピックアップしました。
- ストレートな性格
- 感情移入しやすい
- マイナス思考
- 気分が揺れ動きやすい
すべてに該当する人もいれば、1つから2つが該当するケースもあります。ストレートな性格な人は、感情を全身で表現することもあるでしょう。人から聞いた話や実際に自分が見たことをそのまま受け取るため、敏感に反応してしまうのです。
感情移入しやすい人は、共感力が高いとも言えます。他の人が体験したことをまるで自分が体験したかのように感じ、涙を流すこともあります。
これまでの人生で、小説やドラマ、映画などで得た知識、実際の経験で得た知識なども含めて人の話を聞く傾向にあるため、話を具現化しやすく感情移入しやすくなるのでしょう。
また、マイナス思考の人は自分に自信がないために涙もろくなってしまう場合もあるでしょう。ちょっとした仕事のミスでも自己嫌悪に陥ったり、誰かが小声で話していると自分の悪口を言われているように感じたりするのです。
ネガティブにとらえ過ぎるとも言えますが、反対を言えば、他の人に気を遣い過ぎているとも言えるでしょう。
Aさんの場合、子どもの頃から人前で泣いてしまうことが多く、ちょっとした言葉や出来事にも強く反応して涙が出てしまう傾向がありました。そのため「感情的すぎる」と思われやすく、自分でも抑えられない涙に戸惑うことが多かったのです。
泣くのは我慢したほうが良いの?泣きたい時の対処法
先ほど説明したように、泣きたくなるのは感情の高ぶりによるものです。泣きたいにも関わらず我慢するということは、感情を抑え込んでしまうことになります。
感情を抑え込んでしまうと、ストレスがたまり身体に不調をきたすこともあるでしょう。ここでは、泣きたい時の対処法について紹介します。
(1)思いっきり泣く
感情に任せたごく自然な対処方法は、思いっきり泣くことです。我慢せず涙を流すことで、気持ちがスッキリして、ストレス発散になるでしょう。どうしてもその場で涙を流せるような状況でなければ、別のことを考えるなどして気持ちの整理をしてください。
そして、家に帰ったり1人になったりした際に、再び考えても泣けてくるようであれば、思いっきり泣くと良いでしょう。
Aさんは、カウンセリングの中で「涙を我慢するのではなく、思い切って泣くことで心が軽くなる」と体験的に学びました。泣いた後は気持ちが整理され、落ち着きを取り戻せることを実感するようになりました。
(2)呼吸法
高ぶった気持ちを落ち着けるために、呼吸法をすることもおすすめです。意外と知られていませんが、効果を期待できるので試してみてください。正しい呼吸法の方法を紹介します。
まずは息を吐ききってください。その後、鼻からゆっくり息を吸い込みましょう。この時、おなかが膨らむことを意識することが大事です。少し息を止め、細く長くゆっくりと口から息を吐きましょう。その際、吐く息に意識を向けます。これを3~5分ほど行うのが、正しい呼吸法です。姿勢は、座って背筋を伸ばした状態で呼吸法を行ってください。慣れてくれば立ったままの状態でも可能です。
また、呼吸法はいくつかの方法やヴァージョンがあります。以下は国立精神・神経医療研究センターの呼吸法についての動画です。こちらの方法でも効果はあるでしょう。
Aさんは、職場などで涙が出そうになったときには深呼吸をして気持ちを整える方法を取り入れました。呼吸に集中することで、感情の高ぶりを落ち着けることができました。
(3)気持ちを誰かに伝える
泣きたくなるほど感情が高ぶった際には、その気持ちを誰かに伝えるのもおすすめです。心に抱えておくのではなく、信頼できる人に気持ちを話したり、ノートに書き出したりするのも良いのでしょう。
そうすることで気持ちの整理ができ、心を落ち着かせることができます。
Aさんは、涙をきっかけに「自分がどんな気持ちだったのか」を信頼できる相手に話すようになりました。そのことで、気持ちを言葉にする習慣ができ、泣くことへの恥ずかしさが軽減していきました。
もしかしたら病気が潜んでいる場合も
そこまで涙もろいと感じたことがない人が、「最近涙もろくなった」「些細なことで涙が出てしまう」と感じるようになった場合には、うつ病が隠れている可能性があります。涙とうつ病の関係について見ていきましょう。
(1)こんな症状はない?
うつ病の初期症状として以下のようなものがあります。
- 眠れない
- イライラする
- 集中できない
- やる気が出ない
- 身体がだるい
- 人と話せなくなる
- 自己嫌悪に陥る
- 下痢になる回数が増える
最近涙もろくなって、さらに上記のような症状も出ているという方は、念のため心療内科や精神科などでカウンセリングを受けたほうが良いでしょう。
Aさんの場合、涙もろさに加えて気分の落ち込みや不眠などの症状はなかったため、大きな病気ではないと診断されました。ただ、涙もろさの背景には心理的な負担や心の敏感さが影響していることがわかりました。
(2)涙とうつ病は密接に関わっている
どうして涙とうつ病が密接に関わっているのかというと、涙は人が抱えきれない感情やストレスを有害物質としてとらえ、身体から排除する役割があるからです。
そのため、急に涙もろくなったという人は、自分が考えている以上のストレスが身体にのしかかっている可能性があります。また、うつ病の原因にセロトニンの機能低下が挙げられます。
セロトニンは脳内ホルモンの一種で、機能低下が起こると、心のバランスを取る働きが乱れてしまうのです。心のバランスが取れなくなると、感情のコントロールができなくなるため、急に涙が出たり涙もろくなったりするわけです。
うつ病については以下のページをご参照ください。
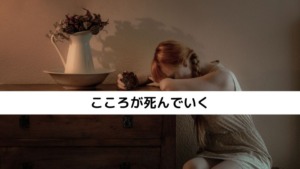
Aさんは「泣きやすいこと」が必ずしも病気ではないと理解しましたが、うつ病などで涙が増えることもあると学びました。そのため、自分の心の状態に注意を向ける大切さを意識するようになりました。
すぐ泣いてしまう人はHSPかも
昔から涙もろいという人は、もしかしたらHSPかもしれません。ここではHSPの定義や特徴、辛い時の対処法などを紹介します。
(1)HSPとはどういう人を言うの?
HSPとは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略で、とても敏感な人、または非常に感受性が強い人を意味しています。HSPは生まれ持った性質であって、病気ではありません。
HSPについては以下のページに詳しく書いていますので、ご興味があればご覧ください。
Aさんは、自分が「人より刺激に敏感で感情を深く受け止めやすい気質=HSP」であると知り、これまでの生きづらさに納得することができました。
(2)HSPの特徴とは?
HSPの特徴について見ていきましょう。
- 場や人の空気を敏感に感じ取ってしまう
- 外的刺激を受けやすい
- 共感しやすい
- 人の影響を受けやすい
- 疲れやすい
- 自己肯定感が低い
いつも他の人を気遣っているため、場や人の空気を深く読み過ぎてしまったり、人の顔色を見たりして疲れやすいのが特徴です。また、他の人のことを気にするあまり、「自分が悪いのでは…」と自己肯定感が低いケースも。
HSPの人は共感しやすい傾向にあり、すぐ他の人の影響を受けてしまうこともあるでしょう。他には、物音や光、においなどの外的刺激を敏感に受け取りやすい傾向にもあります。
Aさんは、人の表情や雰囲気を敏感に感じ取るため、相手の機嫌に影響されやすく、涙が出ることも多いと感じていました。周囲からのちょっとした言葉や出来事にも強く反応してしまう特徴がありました。
(3)HSPの方が困ること
HSPだと実生活でどういった障害があるのでしょうか?主な内容は以下の通りです。
- 外出時の人ごみで辛くなる
- 色々と考え過ぎて眠れなくなる
- 盛り上がっている飲み会の途中で帰ると迷惑かと思いズルズル長居してしまう
- 隣の家の物音が気になってリラックスできない
ここで挙げたものは一例ですが、学校での集団行動、仕事でのコミュニケーションなどさまざまなシーンでストレスがかかりやすい人と言えるでしょう。
Aさんは、仕事や人間関係で「涙を抑えられない自分」を恥ずかしいと感じ、誤解されたり、過小評価されることが困りごとでした。そのため、人前に出ることを避けてしまうこともありました。
(4)辛い時の対処法とは?
最後に、HSPの人が辛くなった時に試して欲しい対処法について紹介します。「治したい」という気持ちは理解できますが、まず大切なことは、HSPについて知ることです。
「自分がHSPかもしれない」と思った場合には、心療内科の受診やカウンセリングによって、HSPと向き合う時間を作りましょう。
「自分がHSPである」とわかるだけで、「ほっとできる」場合もあるからです。そして、自分にとってリラックスできる場所を見つけましょう。その場所に行けば、色々と考えずリセットできるという場所が理想です。それによって安心感が得られます。
また、音に敏感であるなら、イヤホンをして自分の好きな音楽を聴くなどして外的刺激をシャットダウンするのもおすすめです。
Aさんは、辛いときには自分を責めず「敏感だからこそ涙が出るのは自然」と受け止めるようになりました。また、信頼できる人に気持ちを話したり、カウンセリングでサポートを受けることで安心感を得られるようになりました。
HSPについてのトピック
HSPについてのいくつかのトピックです。HSPについてさらに詳細に知りたい方は以下をご覧ください。
すぐに泣いてしまうことに対するカウンセリング
すぐ泣いてしまう人やHSPの方に対するカウンセリングでは、まず「涙もろさ」や「敏感さ」を単なる弱さではなく、感受性の高さや共感性の豊かさとして捉え直すことから始めます。多くの場合、本人は「泣きすぎて迷惑をかけている」「大人なのに情けない」といった否定的な自己評価を持ちやすいため、その思い込みを緩めていくことが重要です。カウンセリングでは、幼少期からの経験や家族との関係の中で「泣いてはいけない」と言われ続けてきた背景を振り返り、涙に対する罪悪感や恥の感情を理解・整理していきます。
また、HSPの人は周囲の刺激に敏感で、人の表情や声のトーン、職場の人間関係の緊張感などに強く影響されやすく、涙として感情が表れやすい特徴があります。カウンセリングでは、そうした感情の反応を抑えるのではなく、呼吸法やその場を少し離れる工夫など「感情を調整する具体的な方法」を一緒に考えます。さらに、信頼できる人に自分の気持ちを言葉で伝える練習を積み重ねることで、「涙で示すしかない自分」から「言葉で自己表現できる自分」へと変化していけるよう支援します。
こうしたプロセスを通じて、本人は涙を恥ずかしいものとして隠すのではなく、「自分の感受性の一部」として受け入れられるようになります。その結果、職場や家庭での人間関係が以前よりも楽になり、涙をコントロールしようと無理をせず、自分らしい形で感情と付き合えるようになっていきます。
涙もろさについてのよくある質問
すぐ泣いてしまう原因として、いくつかの要因が考えられます。まず、ストレスや過度の疲れが影響していることが多いです。日常生活の中で抱えるストレスやプレッシャーが積み重なると、自律神経に影響を与え、感情が急激に溢れ出しやすくなります。また、感情の表現が難しい場合、自分の気持ちをうまく伝えられずに、涙として溢れてしまうこともあります。さらに、過去の経験やトラウマが影響を及ぼしている場合もあります。このような場合、感情が刺激されると、過剰に反応して涙が出ることが多いです。感情的な共感性が高い人、特に他人の苦しみに共感しやすい人も、涙が出やすい傾向にあります。
涙もろい性格自体は病気ではありません。しかし、この特徴が日常生活に支障をきたす場合、心理的な問題が隠れていることがあるため、注意が必要です。涙もろさは感情の表現方法の一つであり、強い感受性を持っている証拠とも言えますが、それが生活に影響を及ぼす場合は、うつ病や不安障害、あるいは過剰なストレスによって感情のコントロールが難しくなっている可能性も考えられます。涙が出やすい状態が続き、生活の質を低下させるようであれば、専門家に相談することをおすすめします。
泣いてしまう自分を改善するためには、まず自分の感情を無理に抑え込まないことが大切です。涙が出るのは感情が表面に出てきた証拠であり、それを否定することなく、感情に寄り添うことが重要です。感情に素直に向き合った上で、リラクゼーション技法を取り入れることも役立ちます。深呼吸や瞑想、ストレッチなどは、感情を安定させる助けになります。また、思い切り泣くこともストレス解消に繋がる場合があるため、涙を流して気持ちを整理する時間を取ることも改善策の一つです。もし、感情がうまくコントロールできないと感じる場合は、カウンセリングを受けることで、自分の感情や思考のパターンを見つめ直し、対処法を学ぶことができます。
涙もろさを改善するためには、まず自分の感情を受け入れ、無理に抑え込まないことが大切です。感情を素直に感じることができると、逆に涙を流すことでストレスが発散され、心の中がスッキリします。さらに、感情的な反応が強すぎると感じる場合、心理的なサポートを受けることも有効です。カウンセリングや心理療法では、自分の感情の原因やその反応パターンを深く理解することができます。また、生活習慣を見直すことも大切です。十分な睡眠をとること、規則正しい食事を摂ること、そして定期的に運動を行うことで、ストレスを軽減し、感情のコントロールがしやすくなります。リラクゼーション法や趣味の時間を取り入れ、心の余裕を持つことも改善策として有効です。
涙もろさは、性格の一部として現れることがあります。特に共感性が高い人や、他人の感情に敏感な人は、周囲の出来事に強く反応し、涙が出やすくなることがあります。しかし、涙もろさは単なる性格の問題だけではなく、過度なストレスや心理的な負担が影響していることもあります。感情が抑えられずに涙が出る状態が続く場合、何かしらの精神的なサインとして捉えることもでき、ストレス管理や感情のコントロールが必要になることがあります。性格や感受性と共に、生活の環境や心の状態が影響することを理解することが重要です。
涙もろさそのものは治療が必要な症状ではありませんが、日常生活に支障をきたす場合や、感情をコントロールできない場合は、心理的なサポートが有効です。涙もろさが頻繁に現れ、自己管理が難しくなる場合は、カウンセリングや心理療法を受けることで、原因となっている感情やストレスの対処法を学ぶことができます。また、心理的な問題が背景にある場合、例えばうつ病や不安障害の一部として現れることもあるため、医療機関での評価を受けることが望ましいです。自己判断せずに専門家と相談し、必要なサポートを受けることが大切です。
はい、カウンセリングは涙もろさを改善するために非常に効果的です。カウンセリングを通じて、自分の感情や思考パターンを理解し、感情をうまくコントロールする方法を学ぶことができます。専門のカウンセラーは、クライエントが感情を整理し、問題を解決するための適切な手段を提供してくれます。感情の起伏や涙もろさの原因が分かることで、無意識のうちに抱えていたストレスや過去のトラウマに向き合い、改善策を実践することが可能になります。また、カウンセリングでは、感情の解放や適切な表現方法を学ぶこともでき、感情的なバランスを取り戻す助けとなります。
はい、リラクゼーション法は涙もろさを改善するために非常に有効です。深呼吸や瞑想は、心と体をリラックスさせ、ストレスを軽減するのに役立ちます。また、軽いヨガやストレッチも効果的で、体の緊張を解きほぐし、感情を落ち着けることができます。特に、深呼吸は交感神経を抑制し、副交感神経を優位にするため、感情が穏やかになりやすいです。リラクゼーションを習慣化することで、感情的な反応を落ち着かせ、涙が出にくくなる可能性があります。心の中で余裕を持つことが、涙もろさの改善に繋がります。
はい、生活習慣を改善することも涙もろさを改善するためには非常に効果的です。まず、十分な睡眠を確保することが重要です。睡眠不足は感情の不安定を引き起こし、涙もろさを悪化させる原因となります。規則正しい食事を摂ることで体調を整えることも大切です。バランスの取れた栄養を摂取することで、体内のホルモンバランスが安定し、感情の安定にも繋がります。また、適度な運動を行うことも、ストレス解消や気分の安定に有効です。散歩や軽いジョギングなど、リズムよく体を動かすことが、涙もろさの予防や改善に役立ちます。
涙もろさが続く場合、まずは自分の感情や思考を見つめ直し、ストレスや不安が影響している可能性を考慮することが重要です。感情のコントロールが難しく感じる場合は、リラクゼーション技法を積極的に取り入れたり、カウンセリングを受けることが効果的です。また、感情を表現する方法を学び、自分自身を抑え込まずに感情を発散することも大切です。生活習慣の見直しや、心身の健康を優先することで、涙もろさの改善に繋がることが多いため、これらを実践することが重要です。
すぐ泣いてしまうことについて相談したい
泣く理由はさまざまですが、基本的にはそれだけ感情が高ぶっていることを意味し、泣くことで心のバランスと取ってくれます。ただ、すぐ泣いてしまう人のなかには、うつ病が影響している場合や、生まれ持った性質のHSPである可能性もあります。
急に涙もろくなった、昔から涙もろいことが気になっていたという方は、病院を受診したりカウンセリングを受けてみたりすると良いでしょう。
当オフィスでは、うつ病やHSPを専門にするカウンセラーが多く在籍しています。気になる症状を抱えている方は、下のボタンからお気軽にお申し込みください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。