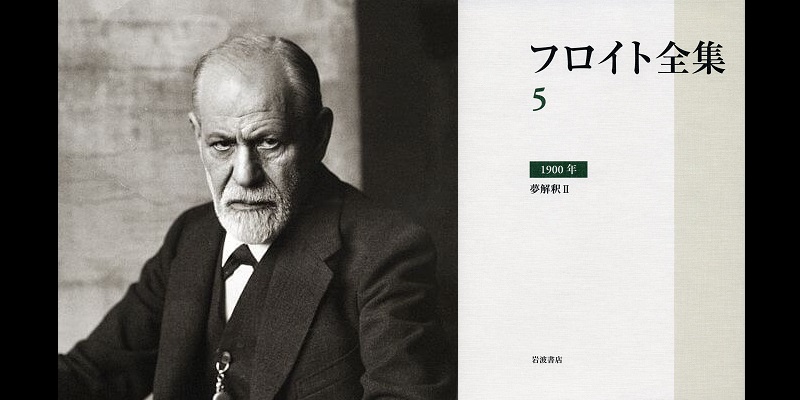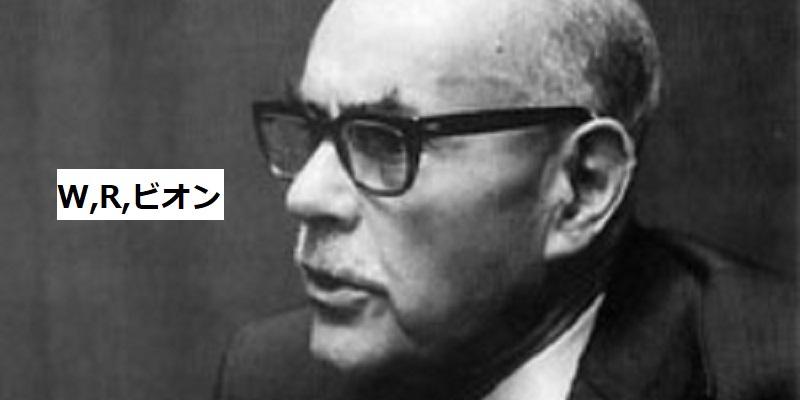精神分析の歴史

精神分析は今から約100年前にフロイトが創始した心理療法であり、人間の探求法です。当日の精神分析と現代の精神分析は相当異なっていると同時に、様々な学派に枝分かれしています。ここではその精神分析や精神分析的心理療法の歴史について述べていきます。
目次
フロイト出生と精神分析前夜
精神分析の歴史は100年以上前のオーストリア・ウィーンのフロイトまでさかのぼります。精神分析の創始者であるフロイトは1856年5月6日にフライベルクにユダヤ人として出生しました。その後10歳の時にウィーンに移り住みました。フロイトは医学部を卒業後、しばらくは生理学の研究やコカインの研究をする神経科医でした。よくフロイトを精神科医や精神医学者であると誤解している人もいますが、実際には違います。
その後、フランスのパリに留学する中で催眠療法を学び、当時の流行病であったヒステリーの治療にあたるようになりました。ヒステリーとは身体的な病因は無いにも関わらず、声が出なかったり、歩けなかったり、聞こえなくなったりする病気でした。当時は詐病(ウソをついて病気のふりをしている)とみなされて治療の対象にならないか、良くてマッサージや温熱療法、転地療法といった治療効果の怪しいことしか行われなかったようでした。その中でも一部、催眠療法が効果を上げているということもあり、フロイトは学びに行ったようです。
帰国後にフロイトは経済的な事情から大学を辞め、市井の開業医として生計をたてるようになりました。そこでヒステリー患者に対して催眠療法を行いました。しかし、フロイトは催眠があまりうまくなかったのか、なかなか成果をあげることができなかったようでした。
その折、先輩のブロイヤーという医師が有名なアンナ・Oというヒステリー患者の治療をおこなっていました。そこでは催眠を活用しつつも、過去やトラウマの想起をするごとに症状が改善していきました。フロイトはインスパイアされ、ブロイヤーと共著でアンナ・Oの症例やその他の数例を用いて「ヒステリー研究」という本を1895年に出版しました。
ヒステリー研究についての要約と解説を以下のページで書いています。
この時にはまだ精神分析という言葉はありませんでしたが、ヒステリーの病因として性的な葛藤や欲望の抑圧の結果である、という概念が形作られて行きました。
精神分析の確立
その後、1900年には「夢解釈」という本をフロイトは出版し、精神分析という名称もこれ以降頻繁にしようされることになりました。そして、治療方法も催眠療法から徐々に離れ、カウチに患者を寝かして、自由に話を語ってもらう、というスタイルに変化していきました。この時に、精神分析の方法が完成し、それ以後、現在に至るまで大きな修正を加えられることなく、伝統的なものとして存続しています。
夢解釈については以下のページを参照してください。
ただ、頻度については時代によって変化をこうむったところはあります。フロイトは週6回の精神分析を行っていました。その後、イギリスなどでは週5回がオーソドックスな頻度となり、さらに現在の訓練システムでは週4回以上という頻度になっていきました。頻度が本質的なものではないかもしれませんが、精神分析的な効力を発揮する手続きとして頻度は重要な位置を占めていると考えます。
対人関係論という学派では週3回を規定するなど学派間での違いはあったりします。現在の共通認識では、精神分析家が行う週4回以上のものを精神分析と称し、それ以下の頻度のものを精神分析的心理療法と称することが一般的になっています。
精神分析の発展
フロイトの精神分析はなんでも性的なことに結び付けるという誤解や偏見もありましたが、反対にフロイトに共鳴する人や弟子入りする人も増えていきました。その中にユングやアドラーといった有名な人も含まれていました。
1910年代にはフロイトは精神分析の技法論文と言われるものを次々と出版し、方法論を確立していきました。1920年代には第一次世界大戦の影響もあったのでしょうが、性の本能に対立するものとして死の本能という概念も精神分析に含めていくようになりました。
この時期には、ユングやアドラーといった人は次第にフロイトから離れていくということもあったようです。フロイトにとっては非常な喪失体験だったのでしょうし、哀しみもあったのかもしれません。フロイトはそうした哀しみを哀しめなかったのでしょうが、非常に迫害的に受け取り、様々な論文で彼らを痛烈に非難していました。
フロイトは元々性格に難があり、また神経症的な症状にも苦しめられていたようです。そうしたところが、患者に対する共感性や感受性となっているところもあるのでしょうが。そのため、フロイトを中心とした精神分析サークルでは様々な人間関係の葛藤が渦巻いていたと言われています。
さらには、今では考えられないことですが、近親者に対して精神分析を行うなどもあったようです。フロイトは娘のアンナ・フロイトを数ヶ月ですが精神分析をしていたこともありました。また、そのほかにも自殺や発病など悲劇的な結末に終わった例もあったようです。こうした教訓が現在における訓練システム確立の必要性として認識されていくことになったのでしょう。
話は少しそれましたが。1930年前後にはナチスドイツの影響がヨーロッパ全土に広がっていきました。それにともなって、ユダヤ人精神分析家の多くがイギリスやアメリカに移住・亡命していきました。その中でもフロイトはウィーンに居続けました。
しかし、もはやのっぴきならない状況に追いつめられた1938年にフランスのマリ・ボナパルトの手配によってウィーンを脱出し、イギリス・ロンドンにたどり着きました。ちなみにマリ・ボナパルトはフランス王女でありつつ、精神分析家でもあります。今でいうと佳子様がカウンセラーをしている、というイメージでしょうか。それはさておき。
イギリスに移住後、すぐにフロイトはガンのため死去しました。1939年9月23日のことでした。
死去の前年にフロイトはおそらくBBCのインタヴューに答えており、その肉声を以下の動画で聞くことができます。2分8秒ほどの短い映像ですが、フロイトの雰囲気は感じ取れるかと思います。
フロイトの娘、アンナ・フロイト
フロイトの子どもの中で唯一精神分析家になったのは末娘のアンナ・フロイトだけでした。精神分析のプリンセスですね。ちなみに写真を見ると、相当の美人だったようです。ジョーンズというフロイトの信頼の厚い精神分析家はアンナに求婚して断られたという逸話も残っています。ちなみに真偽のほどは分かりませんが、アンナはレズビアンであったとも言われています。偉大な父親を持つことは子どもにとっては相当の負担なのかもしれません。
アンナは元々、教師だったということもあり、子どもに対する精神分析を実践・研究していました。しかし、子どもは発達途上でもあり、親との関係が強いので、成人に対する精神分析のようなことはできないので、教育的・指導的要素を入れ、また子どもの信頼を得られるように暖かい雰囲気ですすめていくようなことをしていました。
アンナの功績は上記の児童分析のスタイルを確立させたことと、自我の防衛機制を整理したことです。自我の防衛機制とは葛藤や苦痛を感じた際、自我が傷付かないように守る方法です。抑圧、投影、同一化、昇華、など様々ありますが、アンナはこれを綺麗に整理しました。そして、これらが自我心理学という学派を形成するようになりました。
以下のページはアンナの主要な業績である「自我と防衛」という書籍についての要約と解説です。
メラニー・クラインの児童分析と対象関係論
一方でメラニー・クラインという精神分析家がいます。1882年にウィーンで出生しました。クラインは度重なる喪失を経験していました。また医師になりたかったのですが、それを諦めざるを得ない事情もありました。医師を諦めた上で結婚したのですが、その結婚生活も決して幸せなものではありませんでした。そうしたことが重なったのでしょう。クラインは重たいうつ病になってしまいました。
クラインの生涯については以下に書いています。
そのため、クラインは当時ブダペストの精神分析家であるフェレンツィに精神分析を受け始めました。それによってうつ病から回復しました。さらにはフェレンツィの勧めで精神分析家の道を志すようになりました。クラインはその後ベルリンに移住し、さらにそこでアブラハムという精神分析家から精神分析を受けましたが、ここでも不幸なことに分析を開始してまもなくアブラハムが亡くなってしまいました。
当時、クラインは子どもの精神分析を研究していました。しかし、子どもの精神分析はそもそものフロイトが否定的であったこともあり、精神分析サークルの中ではクラインは歓迎されなかったようでした。アブラハムがクラインを擁護することで何とかクラインは活動できていました。その擁護していたアブラハムが亡くなり、クラインへの風当たりはいっそう強くなっていきました。
その時に、クラインはイギリスのジョーンズという精神分析家のはからいで、イギリスで子どもの精神分析を講義する機会がありました。さらにそれを機にイギリスへと移住することになりました。1927年のことでした。当時イギリスは精神分析の首都であるウィーンから遥か遠くに離れていたので、何でも研究できる自由な風土が幸いしたのかもしれません。
クラインがイギリスに渡ってから、クラインは非常に歓迎されたようです。クラインは独自の発想で、精神分析の概念を拡大・発展させていきました。特に乳幼児の内的世界を描き出し、対象関係というジャンルを発展させました。現在の精神分析を理解する上でクラインの理論を外すことはできなくなりました。そして、それにともないクラインはイギリスでの地位を確立していき、信頼できる仲間や弟子も増えていきました。そして、クライン派と呼ばれる一派が形成されていきました。
アンナ・フロイトとクラインの論争
アンナとクラインは同じように子どもの精神分析を行っていましたが、その方法や理論背景がまるで違っていました。アンナは精神分析をそのまま適用せず、教育的な配慮をしなければならないとしました。そこには未熟な自我をサポートし、成長することを見守るという姿勢でした。子どもの外的な環境を重視するという所も重要な点です。
一方でクラインは精神分析の技法を変更せず、子どもにもそのまま適用しました。子どものプレイには自由連想と同様の意味が内包されているので、それを直接解釈していく、というものです。そこには、子どもであろうと成人と同様の葛藤や苦痛、不安があるので、それを解釈として扱うことが治療的であるという信念と理論がありました。クラインは外的な環境は無視とはいわないまでも重要視せず、ひたすら子どもの内面を扱っていく方向に特化していきました。
この両者の理論論争は悪い意味で白熱しました。時には双方が感情的な非難を繰り返したりすることもありました。しかし、このような論争によって、双方の理論が整備され、発展していったという側面もありました。例えば、クラインは外的環境の要因もやや取り入れ、アンナは子どもの内的世界を考慮するということもありました。
さらに、アンナの自我心理学派、クラインのクライン派のどちらにも属さない中間学派・独立学派というグループもありました。ウィニコットなどがその代表です。
こうした論争は数年にわたり続いていましたが、紳士淑女協定が結ばれ、一応は収束していきました。この時期に、精神分析家の訓練システムとして、臨床講義、スーパービジョン、教育分析、個人分析、訓練分析が確立していきました。またここにビックの乳幼児観察なども加わるようになりました。
ウィニコットにおける対象関係論の発展
クラインの弟子にウィニコットとビオンという精神分析家がいます。フロイトやクラインの理論を発展させ、それぞれ理論の違いはありますが、いわゆる対象関係を軸においた対象関係論を展開させました。
ウィニコットは元々、小児科医であり、その後に精神分析家となりました。精神分析家となった後も小児科医として診療を最後まで続けました。そのような経験から最早期の母子関係についての理解を深めていきました。
ウィニコットによると乳児は生まれた時には母親のホールディングに包まれ、非常に万能的な世界の中で苦痛も不安も葛藤もない中で成長します。しかし、そこでのホールディングに失敗すると、乳児は非常に迫害的で精神病的な不安を感じ、その後の発達に深刻なダメージをこうむります。そうならないために、徐々に世界は万能的でも魔術的でもないということを経験しながら成長していくことが大切であると述べています。
このことは以下のウィニコットの論文「親と幼児の関係に関する理論」に詳しく書いています。
このことはウィニコットの技法論に直結しています。通常の神経症レベルの葛藤についてはオーソドックスな精神分析を施行することで対応できます。しかし、精神病水準に病態に陥り、非常に混乱している時には、精神分析家はその退行を許容し、あたかも母親のようにホールディングしていくことが必要となります。母子関係とセラピー関係が非常に似通っているという、ウィニコットの基本理解があります。
ウィニコットの退行理論について知りたい方は以下のページをご参照ください。
ウィニコットは元々、クラインに学びましたが、上記のような理論を作っていった関係でクラインからは破門されました。そして、独立学派の中で位置づけられるようになりました。
ちなみにウィニコットはイギリスの中流階級の末っ子として生まれました。記録は定かではありませんが、母親は抑うつ的な人であったと言われています。また、第二次世界大戦では従軍医師をしており、そこで非常に過酷な体験をしたと言われています。また、1人目の妻とはあまり関係が上手く行っておらず、離婚に至っています。このようなウィニコットの傷つきが精神分析の道へと進めたのではないかと思われます。
以下の動画でウィニコットの肉声が聞けます。40秒ほどの短いものですが。
ビオンにおける対象関係論の発展
ビオンもクラインの弟子です。イギリス人ではありますが、父親が建設の仕事をしている関係でインドに生まれました。そしてインドを転々としながら、8歳になるとイギリスの寄宿学校に一人で入りました。それ以後、インドに戻ることはありませんでした。
ビオンが19歳の時には第一次世界大戦が勃発しており、ビオンは陸軍に入隊しました。配属先は戦車隊でした。そこではビオンは輝かしい功績を遺したのですが、同時に深刻なトラウマも受けました。ビオンの部隊が壊滅したり、目の前で友人が爆死したりなどあったようです。このことにより、生涯にわたってビオンは悪夢に悩まされ続けました。
除隊後、ビオンは教師をしていましたが、そこで男子生徒との性的な仲を疑われ、仕事を離れざるをえなくなりました。その後、医師になるために医学部に入り直しました。その後、医師として仕事をしていく中で精神分析に出会い、精神分析家の道を歩むこととなりました。ビオンが精神分析家になったのは50歳になった時で、当時ではかなり遅い出発でした。
しかし、その後のビオンの理論的発展は目覚ましいものでした。ビオンはウィニコットとは違う形で、最早期の母子関係についての理論を構築していきました。乳児は空腹などの耐え難い苦痛を泣声で追い払おうとします。その時、母親はその苦痛を受け取り、乳児が受け入れやすい形にして返すことにより、乳児は苦痛に耐えられるようになっていきます。これはコンテイナー理論と言われ、早期の原初的なコミュニケーションの一体です。このことがセラピー関係の中でも展開していくと考えました。
以下の動画はビオンが1978年7月3日にタビストゥックで行った講義です。
対象関係論の展開
ウィニコットとビオンの他にもたくさんの精神分析家はいますし、精神分析の基礎理論を構築していく上では重要な人も多くいます。例えば、フェアバーン、ストレイチー、スィーガル、ハイマン、ローゼンフェルド、マネ=カイル、ベティ=ジョセフ、メルツァー、等々。
いずれも、精神分析を対象関係論という観点から理論構築を行っていきました。このことは現代の精神分析に重要な影響をもたらしました。フロイトは精神分析家とは鏡のような存在になることで、クライエントを客観的に分析していくものであるとしました。そこには精神分析家とクライエントの関係はそこまで取り沙汰されるものではありませんでした。
しかし、この対象関係論の出現、展開、進歩により、セラピー関係は様々な情緒のやり取りがなされる生々しいものである、という理解ができていきました。そして、この生々しい関係が渦巻くことが悪いことではなく、そうしたことを理解し、取扱い、生き抜いていくことが人間としての成長に不可欠であるとなっていきました。精神分析はそれを扱う上での有効な装置であるのです。現在の精神分析は無意識の意識化よりも、こうした関係を取扱っていくことが主流となっていきました。
精神分析の分派
精神分析は対象関係論やクライン派だけではありません。その他にも自我心理学派、対人関係論学派、自己心理学派、間主観性学派、新フロイト派などがあります。
同じ精神分析といっても様々な理論がありますし、そうした理論構築が独自に発展しています。細部の違いを挙げればきりがありませんが、全体としての潮流として、対象関係論にはじまるような関係性に着目するという視点はいずれも備えているようです。
精神分析の衰退と発展
精神分析はフロイトの存命する初期の頃から色々と誤解と偏見にさらされてきました。何でも性欲に還元してしまう、自閉症を悪化させてしまう、誤った記憶を捏造させる、異常者の心理から正常者の心理を憶測している、エビデンスがない、等々。
確かに一部にはそういった批判が的を得ているところもありますが、そうではない誤解に基づく偏見であることもありました。
1940年〜60年代ぐらいまでは精神分析は非常に拡大していきました。一時期は米国の精神科医は全て精神分析家であったこともありますし、エリート層はほとんどが精神分析を受けていた、という時代もありました。さすがにそうした行きすぎは振り子が戻るかのように変化していきました。元々、精神分析は地味で単調でのんびりしたものです。華やかなものとは無縁であるのでしょう。
一方で、そうした華やかな発展とは裏腹に、コツコツとした地道な研究が続いてきました。例えば、自閉症研究は現在の科学的な知見をベースにし、生得的な要因を加味しつつ、精神分析的な探求が行われ、それなりの実績を積み重ねてきました。乳幼児の心の世界の探求から、愛着という観点が現在のセラピーに活用されてきています。さらには、現在のエビデンスベースドの潮流にも適応し、精神分析的なセラピーが他のセラピーに遜色ない効果をもつ、ということが実証研究の中で証明されてきています。
また、近年ではフォナギーらがメンタライゼーションという概念を創出しました。これは自分自身や他者との対人関係において、行動を内的な精神状態と結びついているものとして想像力を働かせて捉えることを指します。このようなメンタライゼーションからこれまでの精神分析を再検討され、あらたな技法論として台頭してきました。
メンタライゼーションについての詳しいブログが以下です。
もう少し視点を広げると、ロジャースの来談者中心療法やベックの認知療法、対人関係療法、一般的なカウンセリングなどは精神分析を批判検討する中で生まれてきたところもあります。そうしたセラピーの中に部分的ではありますが、精神分析が着実に活かされている側面もあります。
日本における精神分析の黎明期
我が国において、精神分析は1910〜20年頃から始まります。1910年代にフロイトの著作が大槻憲二らによって徐々に紹介され、1920年代にフロイトの論文が邦訳されていきました。このころはセラピーとしてではなく、文献上の研究にとどまっていたようです。しかし、1930年に矢部八重吉が日本人で初めて精神分析家の資格を取得し、この頃より治療としての精神分析が実践されはじめました。
古澤平作もウィーンに留学し、ステルバから教育分析を受け、フェダーンからスーパービジョンを受けました。この時期から彼らは日本の文化に精神分析を適合させるため、週5〜6回の毎日分析ではなく、週1回程度の頻度による精神分析を実践していました。また、現在では考えられないことですが、通信分析という名称で、手紙のやりとりを用いた精神分析を実践していたようでもありました。
団体としては、1930年にフロイトから許可を得た矢部が国際精神分析学会の日本支部(日本精神分析協会)を設立し、さらに戦後になり、1955年に日本精神分析学会が設立されました。
研究分野では古澤が「アジャセ・コンプレックス」を提唱し、その論文のドイツ語訳をフロイトに送ったということもありました。また土居健郎は「甘え理論」を提唱し、現在の精神分析の中の一部にも取り入れられるようになりました。以下の動画は土居健郎先生が甘え文化について話しているものです。15分00秒とやや長めですが、是非ご覧ください。
その後、小此木啓吾が日本の精神分析を牽引するようになっていきました。小此木によって精力的に海外の精神分析関連の文献が輸入・翻訳・紹介され、徐々に日本に精神分析が根付いていきました。しかし、それは毎日分析ではなく、週1回程度の頻度によるものでした。
この頻度の問題は日本の精神分析を発展させると同時に、訓練システムの問題として深刻な問題として影をおとすようにもなりました。つまり、国際精神分析学会では精神分析家になるための訓練分析を週4回以上で、数年にわたって受け続けなければならないと定められていました。しかし、日本はそうした基準を順守せず、週1回程度の訓練分析を認めてきました。
アムステルダム・ショック以降の日本の精神分析
1993年にいわゆるアムステルダム・ショックが起こりました。これは日本のそうした訓練システムの不備を国際精神分析学会が指摘し、改善命令を出してきた、というものです。このことは日本の精神分析を学ぶ者にとっては深刻なダメージをこうむりました。そして、これがもとで精神分析の訓練からおりていった人は多かったようです。その後、日本でも精神分析の訓練について国際基準に準じた形で整備をし、現在では訓練分析は週4回以上で、審査分析を合わせると3年以上を受けなければならないことになっています。
現在では、精神分析家の訓練や認定、研究、職能団体としては日本精神分析協会が担っています。日本精神分析学会は幅広く、精神分析家以外の人も受け入れ、現場実践に即した学術団体として活動をしています。両者は相互補完的な関係になっています。
また、日本では古澤や小此木の影響から長らく週1回程度の頻度で、カウチを使わない精神分析的なセラピーとして臨床の中で実践されてきました。しかし、アムステルダム・ショック以降、週4回以上のカウチを用いたものを精神分析と呼び、頻度が少なく、カウチを用いないものを精神分析的セラピー・精神分析的心理療法と区別して呼ぶようになっていきました。
さらには、毎日分析までにはならないまでも、週2回や週3回の頻度によるセラピーも徐々に実践されるようになってきました。毎年行われる日本精神分析学会の学術大会でも、そうした週複数回の設定によるセラピーが発表されるようになってきました。頻度がすべてではありませんが、高頻度になればなるほど精神分析的になっていき、そうなればなるほど変容を促せるのだろうと思います。
現在の日本における精神分析家は約40名ほどです。これは世界的に見ても極めて少ない人数となっています。このことの理由は文化や社会実情、臨床上で求められること、など色々と挙げることはできるかもしれません。
精神分析についてのトピック


終わりに
精神分析の100年にわたる歴史について解説してきました。フロイト以降、精神分析は様々に発展してきました。そして、その精神分析の実践は今でも行われています。
(株)心理オフィスKでは精神分析的な理解に基づいたカウンセリングや心理療法を行っています。希望される方は以下のボタンからご連絡ください。