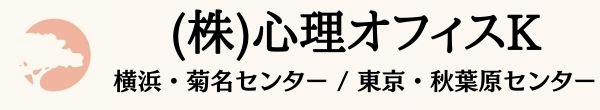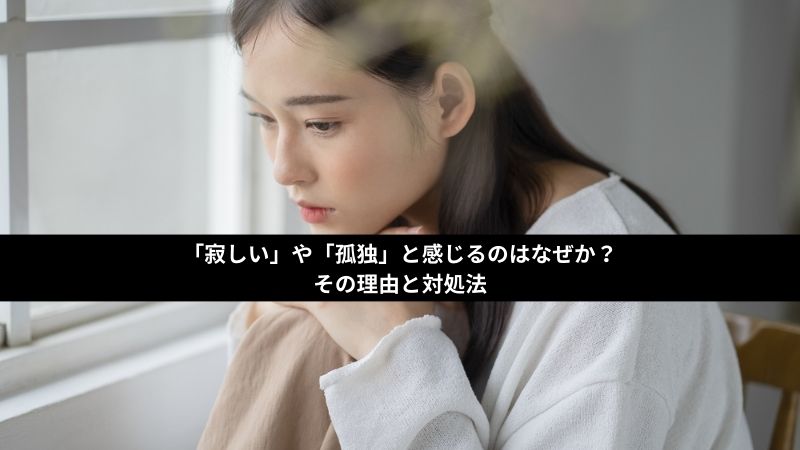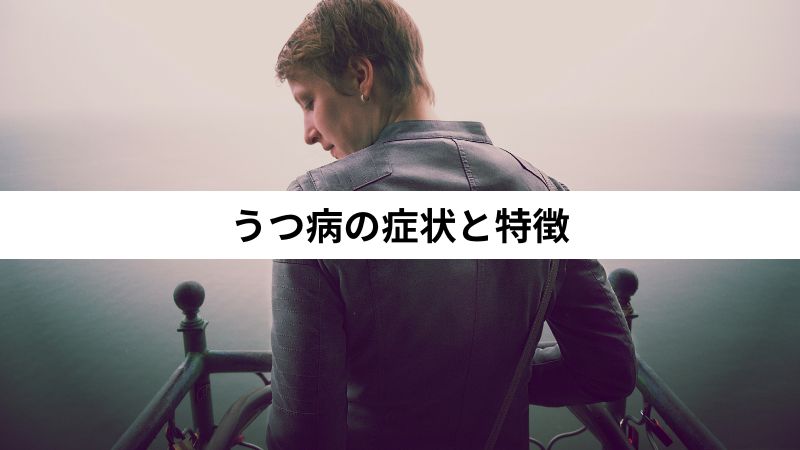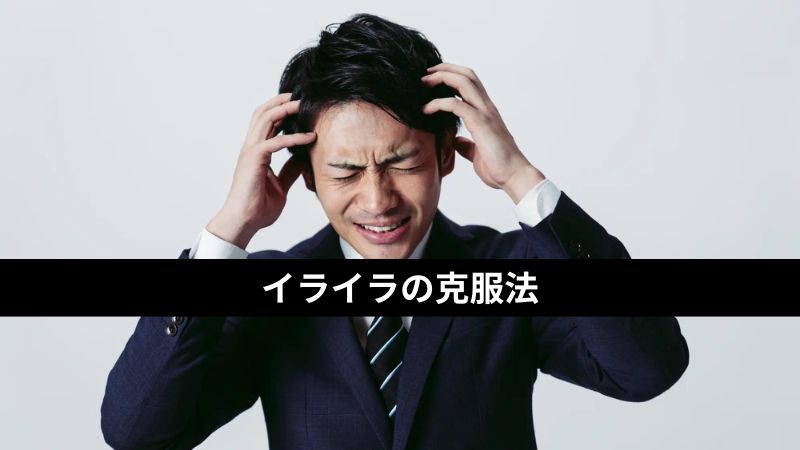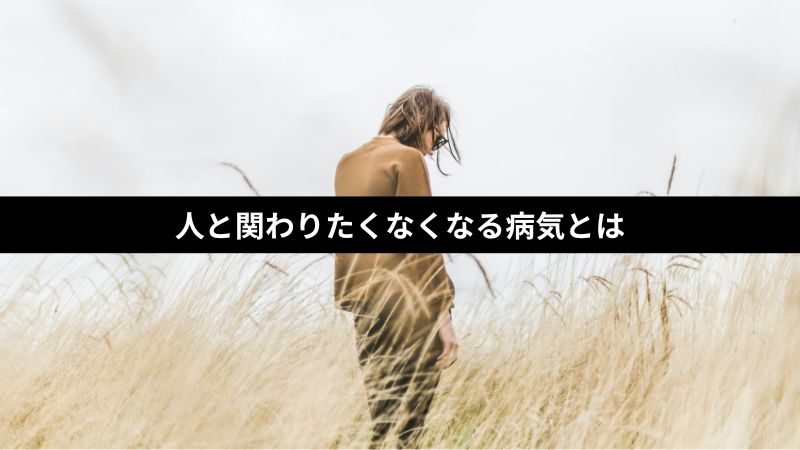感情がなくなり、麻痺してしまう病気とは

感情がなくなり、麻痺してしまう病気にはどのようなものがあるのでしょうか。この記事では、解離現象と心的外傷後ストレス障害(PTSD)を中心に取り上げて解説します。
感情がなくなり、麻痺してしまう状態が病的なものである場合は、専門的治療や支援を早めに検討しましょう。カウンセリングによる支援も活用できます。
目次
感情がなくなり、麻痺してしまうことについて
「感情がなくなり、麻痺してしまうこと」は、心理的な防衛反応のひとつとして理解されることがあります。強いストレスやトラウマ体験に直面すると、人はその苦痛に圧倒されないよう、感情を感じないように心を閉ざすことがあります。この状態は一時的であれば自己を守るために役立ちますが、長期化すると日常生活に支障をきたします。例えば、嬉しい・悲しいといった自然な感情がわからなくなり、人間関係に距離が生まれたり、生きている実感が乏しくなったりします。また、感情の麻痺は解離症状や心的外傷後ストレス障害(PTSD)、うつ病などとも関係して現れることがあり、放置すると回復が難しくなることもあります。
そのため、専門的な治療やカウンセリングにつながることが大切です。安全な関係性の中で、自分の体験を少しずつ言葉にし、感情を再び感じ取る練習を積み重ねることで、次第に感情が戻ってくる可能性があります。感情を失ったのではなく、守るために閉ざしているだけだと理解することが、回復の第一歩となります。
よくある相談の例(モデルケース)
20歳代 女性
Aさんは学生時代から感情の起伏が乏しいと感じることが多くありました。幼少期には家庭内での衝突が頻繁で、両親の間の不和や感情的な言い争いを繰り返し目にしてきました。Aさんはその中で自分の気持ちを表に出さないことで安全を保ち、波風を立てないようにすることを学んでいきました。その結果、喜びや怒りといった感情を自分でもはっきりと感じにくくなり、周囲からは「落ち着いている」と見られる一方で、内心では空虚さを抱えてきました。大学卒業後、就職をしたものの、人間関係の中で感情がうまく動かないことに苦しみ、親しい友人や恋人とも距離ができてしまいました。何が楽しいのか、何に悲しいのかが分からず、ただ淡々と日々を過ごす感覚が強まり、「自分には感情がなくなってしまったのではないか」という強い不安に襲われるようになりました。
その後、Aさんは心療内科を受診し、うつ病の可能性を指摘されました。抗うつ薬を一定期間服用しましたが、大きな改善はみられず、むしろ「薬を飲んでいるのに何も変わらない」という無力感が募っていきました。医師の勧めもあり、心理的な背景を整理するためにカウンセリングを受けることを決意しました。最初は「自分のように感情がない人間でも意味があるのか」と半信半疑でしたが、カウンセラーとの対話を通じて、感情が麻痺した背景にある幼少期の体験や、人との関係の中で繰り返し身につけてきた「感じないようにする習慣」が少しずつ理解されていきました。
カウンセリングのプロセスは数年にわたり、当初は沈黙が多く、自分の気持ちを言葉にすることが難しい時期が続きました。しかし、安心できる関係性が築かれるにつれて、Aさんは「今は何も感じていない」ということ自体を言葉にすることができるようになり、それが小さな一歩となりました。やがて、自分では気づかないうちに緊張や不安を抱えている場面があること、身体のこわばりや涙の出にくさが感情の麻痺とつながっていることが理解されていきました。長い時間をかけて、Aさんは「感情がない」のではなく「感じないようにしてきた」のだと受けとめることができるようになり、少しずつ怒りや悲しみ、そして喜びも再び体験できるようになりました。最終的に、日常の中で小さな感動や人とのつながりを実感できる場面が増え、以前よりも自分らしい感情を取り戻して生活できるようになりました。
感情がなくなり、麻痺する原因
あったはずの感情がなくなり、麻痺したように感じられる状態はなぜ起こるのでしょうか。ここでは覚醒水準の低下のあらわれと解離現象のあらわれの2つの見方を紹介します。いずれも、トラウマが関連するといわれる現象です。
(1)覚醒水準の低下のあらわれ
感情が麻痺したような状態は、覚醒水準の低下のあらわれかもしれません。
覚醒水準は外界にある刺激に対する感度や反応性の高さのことをいいます。人は通常、ほど良い覚醒水準を保って環境とかかわりますが、心身が脅かされる状況では覚醒水準をぐっと高め、注意力を研ぎ澄ませて危機に対抗します。
それでも対処しきれないほど危機が圧倒的なときは、覚醒水準を下げて対処することがあります。嵐が過ぎるのを待つように、感度や注意力を鈍らせ、反応性も下げて危機をやりすごすのです。
この覚醒水準を低下させる働きにより、感情が麻痺したように体験することがあります。
Aさんは、日常生活の中で意欲や集中力が低下し、まるで頭がぼんやりと霞がかかったような感覚を持つことが多くありました。周囲の刺激に対しても反応が鈍く、仕事や対人関係において気持ちが動かない自分に戸惑っていました。
(2)解離現象のあらわれ
感情が麻痺したような状態は、「解離」と呼ばれる現象のあらわれかもしれません。
人は通常、「自分」という一貫したまとまりやつながりのある意識世界を持っています。意識や記憶、同一性、情動、身体感覚・知覚、運動は統合されており、過去、現在、未来は連続性をもちます。
しかし、心身の安全が脅かされるほど過酷な状況に置かれた場合、「自分」が壊れるのを防ぐためにその体験を「自分」から切り離すことがあります。体験を「自分」から切り離す現象は「解離」と呼ばれ、解離により感情が麻痺したような状態となることがあります。
Aさんの場合、感情が急に遠のいたり、出来事をどこか他人事のように感じる瞬間がありました。強いストレスを感じると、記憶が部分的に抜け落ちるような体験もあり、自分の体験がつながらない不安を抱えていました。
(3)トラウマの影響
覚醒水準の低下も解離現象も、背景にトラウマが存在する可能性があります。
覚醒水準を著しく変化させることや体験を「自分」から切り離すことは、いずれも圧倒的な危機状況で身を守るための特別な働きです。この働きが危機を脱してからも生じる場合、災害や事故、長く反復された虐待などから負ったトラウマの存在が考えられます。
感情が麻痺したような状態は、心の傷によるものかもしれません。
Aさんは、幼少期の家庭内の衝突を繰り返し目にしてきたことが影響し、強い感情を表すと危険だと学習していました。そのため感情を抑え込むことが習慣化し、後に麻痺や解離として表れていきました。
解離とは
ここでは解離現象についてもう少しくわしく触れます。解離のさまざまなあらわれ方とそれぞれに関連する病気を紹介し、健康な解離と病的な解離についても説明します。
(1)解離のあらわれ方と関連する病気
解離の表れ方は、心身の安全が脅かされる体験のうちのどの部分をどのように切り離すかによってさまざまです。「自分」から解離されるものと解離の表れ方の例、それぞれに関連する主な病気は以下の通りです。
|
解離する領域 |
表れ方(例) | 関連する主な病気 |
|---|---|---|
|
感覚・知覚 |
特定の感覚・知覚のみが鈍くなる、触覚や痛みを感じない、目が見えない、声が聞こえない、など | PTSD |
|
情動 |
体験からリアルな感覚が抜ける(離人とも呼ぶ)、自分が動いている実感がない、他人事のように感じる、自分が自分でないと感じる | PTSD |
|
現実感 |
体験からリアルな感覚が抜ける(離人とも呼ぶ)、自分が動いている実感がない、他人事のように感じる、自分が自分でないと感じる | 離人感・現実感消失症、PTSD |
|
意識 |
意識全体が飛んで真っ白になる、刺激への反応が消え、ボーッとして意識障害のようになる | PTSD |
|
記憶 |
受け入れがたい体験の記憶がない、いわゆる「記憶喪失」、特定の記憶が抜けたり、過去全ての記憶が抜けたりする | PTSD、解離性健忘 |
|
運動 |
歩けない、声が出ない、立てない、などの運動機能の麻痺 | 変換症/転換性障害 |
|
行動 |
理由なく家からいなくなり放浪し、その間の記憶がない | 解離性遁走 |
|
人格 |
ひとりの中に複数の人格が共存し、交代であらわれる、いわゆる「多重人格」 | 解離性同一症/解離生同一性障害、PTSD |
上に挙げたように、感覚・知覚・情動の麻痺をはじめ、さまざまな解離のあり方と特に関連する疾患は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)です。
Aさんの場合、解離は感情の麻痺や記憶の抜け落ちとして現れました。こうした症状は解離性障害やPTSDとも関連し、長期的な心理的な負担とつながっていました。
(2)健康な解離と病的な解離
解離現象そのものは誰もが備えるありふれたもので、すべてが病的ではありません。
たとえば、我を忘れて没頭する、授業中に別のことを考えていてうわの空になる、といった健康的な体験もありますし、思春期の自我のめざめとともに一過性の離人感が体験されることもあります。
しかし、深刻なトラウマなどの脅威にさらされると、病的な解離症状に発展する可能性があります。もともとは圧倒的な脅威から心身を守るための解離が平穏な日常でも繰り返し呼び起こされる場合、不適応的な反応となってしまうのです。
Aさんは、映画や本に没頭して時間を忘れるといった健康な解離も経験していましたが、感情の麻痺や現実感の喪失は病的な解離に近い形で表れ、日常生活に支障をきたしていました。
感情がなくなり、麻痺してしまう病気とは
ここでは感情が麻痺したような状態が生じる主な疾患として、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と離人感・現実感消失症/離人感・現実感消失障害の2つを取り上げ、それぞれについて説明します。
(1)心的外傷後ストレス障害(PTSD)
心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、強いトラウマとなる出来事にさらされた後、特有の心身の症状が現れる疾患です。
代表的な症状は侵入症状(再体験・フラッシュバック)、回避症状、過覚醒症状、認知と気分の陰性の変化の4つですが、離人感・現実感消失といった解離症状を伴う場合もあります。また、覚醒水準の低下がみられる場合もあります。
感情が麻痺したような状態としては、幸福や満足、愛情を感じられなくなったり(認知と気分の陰性の変化)、自分の感情を自分のものではないように感じたり(離人感)します。さらに、注意力の鈍さやぼんやりして活気がない(覚醒水準の低下)といった様子が見られる場合もあります。
Aさんは、家庭内のトラブルを思い出すと強い不安に襲われることがありました。感情を麻痺させることで自分を守ってきましたが、それがPTSDの症状の一部として理解されるようになりました。
(2)離人感・現実感消失症(離人感・現実感消失障害)
離人感・現実感消失症は、離人感と現実感消失のいずれか、または両方を持続的、反復的に体験する疾患です。
たとえば、まわりの世界は知的にとらえられるのに感情が伴わない、何を見ても感動できない、実感がわかない、自分の感情や行動に現実感がなく、嬉しい・悲しいといった感情が感じられない、動いているのは自分ではなくロボットのよう、などと体験されます。
こうした症状はうつ病や統合失調症などに伴うこともありますが、離人感や現実感消失が単一の症状として現れ、現実検討力も保たれているのが離人感・現実感消失症の特徴です。
現実認識が失われないために体験への違和感があり、そのためにかえって強い不安を伴うといわれます。
Aさんの場合、日常の中で自分の体が自分のものではないように感じたり、周囲の世界がどこか遠くにあるように思えることがありました。こうした体験は離人感・現実感消失障害として説明されました。
感情の麻痺についての治療
感情がなくなり、麻痺してしまったら、どうすれば良いのでしょうか。ここでは専門的治療につながる目安と、回復に向けた治療や支援についてお伝えします。
(1)専門的治療につながる目安
感情が麻痺したような状態には健康的なものもありますが、病的な場合は自然治癒は難しく、専門的な治療が必要です。
感情が麻痺したような状態が一時的な体験であったり、苦痛や日常生活への支障がなかったりする場合は、治療の必要はないかもしれません。
ですが、症状が長くくり返されており、大きな苦痛や日常生活への支障が出ている場合は専門的な治療を検討しましょう。
Aさんは、自分の状態が一時的な疲れではなく、長期にわたり生活や人間関係に支障を及ぼしていると気づいたとき、専門的な治療が必要だと考えるようになりました。
(2)回復に向けた治療や支援
感情が麻痺したような状態に想定される病気の回復に向けては、以下のような治療や支援が行われます。
| 治療・支援 | 支援の詳細(例) |
|---|---|
| 安全な環境づくり | 解離を起こす刺激やストレス状況を探し、苦痛な刺激を取り除くなど調整する |
| 薬物療法 | 抗うつ薬、抗不安薬などを必要に応じて投与 |
| 心理療法 | 精神分析、認知療法、行動療法など |
カウンセリングなどの心理支援では、自分に起きていることの理解、過去の体験にまつわる感情の表現やマネジメントなどを通じて、本人が感情を含めた自己コントロール感を取り戻せる状態を目指します。
Aさんは、医師の診断と心理カウンセリングを受ける中で、自分の体験や感情を少しずつ言葉にできるようになりました。数年をかけて感情を取り戻す過程を歩み、支援者との関係の中で安心感を得ながら、次第に自分らしい生活を築けるようになりました。
解離やトラウマについて相談する
感情がなくなり、麻痺してしまう病気について、解離現象とPTSDを中心に説明しました。
感情が麻痺したような状態には、健康的なものもトラウマの影響による病的なものも考えられ、病的な場合は早めの治療や支援が望まれます。回復への支援として、カウンセリングもご検討ください。
当オフィスでもこうしたことのカウンセリングを行っております。希望者は以下のボタンからカウンセリングのお申し込みをしてください。
参考文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。