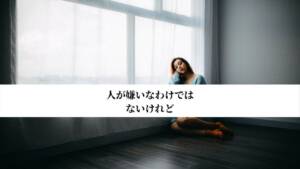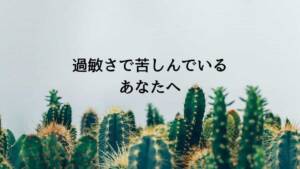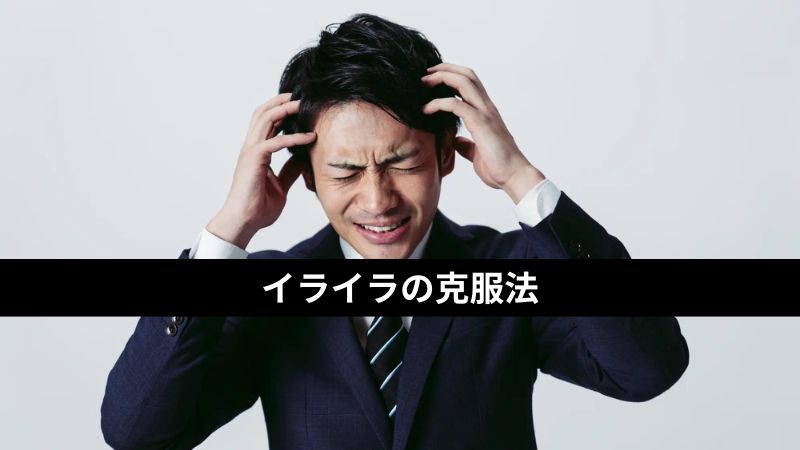人と関わりたくなくなる病気とは
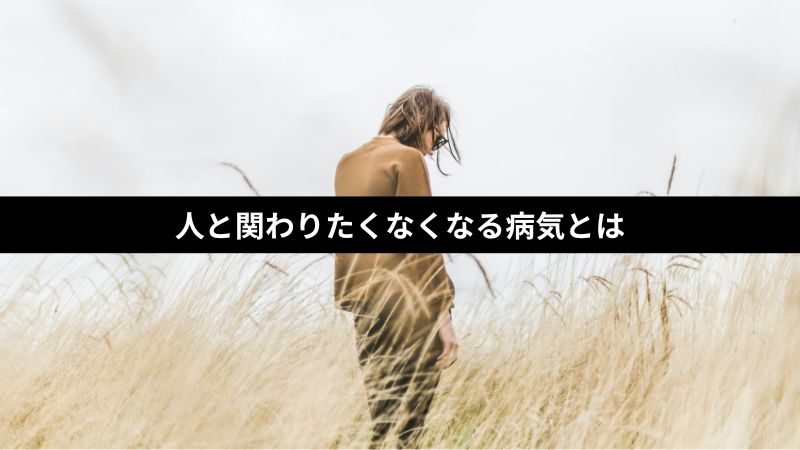
「もう誰とも関わりたくない」や「人と関わっているとどうしようもなく辛い」など、このような感情は、程度の差こそあれ、誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。こういった感情に直面しても、日常・社会生活に支障が無ければ問題はありません。
しかし、学校や職場に行くことができない・身近な人とでさえも顔を合わせることが辛くて仕方ない、死んでしまいたいとまでになってしまった時には、何か病気や障害が原因となっているのかも知れません。
ここでは、その原因として考えられる病気や障害の一例について解説したいと思います。
目次
人と関わりたくなくなる病気とは
「人と関わりたくなくなる病気」は、単なる気分や性格の問題ではなく、心身に強い負担がかかっているサインであることがあります。代表的なものとして、うつ病や適応障害が挙げられます。うつ病では気分の落ち込みや意欲の低下が続き、人と会うこと自体がつらく感じられるようになります。適応障害では、職場や家庭のストレスによって強い不安や緊張が生じ、人間関係を避けることで心を守ろうとします。また、社交不安症では人前で失敗する不安が強まり、会話や集まりを避ける傾向が出ます。
さらに、発達特性の影響で人といることに強い疲労を感じるHSPや自閉スペクトラム症もあります。これらは本人の努力だけでは改善が難しく、無理に人と関わろうとすると逆に症状が悪化することもあります。まずは心身の休養と安全な環境を整え、必要に応じて専門機関で相談し、心理療法や薬物療法を組み合わせることで少しずつ人間関係を再構築していくことが大切です。
よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 女性
Aさんは40歳代の女性で、ここ数年、人と関わることが極端に負担に感じるようになっていました。子どものころから人見知りはありましたが、大学時代には友人関係も比較的順調で、職場でも人間関係に大きな問題はありませんでした。しかし数年前、職場での人間関係のトラブルや家族内での対立が続いたことをきっかけに、人と会うと強い緊張や疲労感が残るようになり、次第に外出や連絡を避けるようになりました。人と関わったあとは頭痛や胃痛、不眠が起きるようになり、誰かに会う約束を入れるだけで動悸がするほどになっていきました。内科を受診しても明確な身体疾患は見つからず、心療内科では軽い抑うつ状態と診断され、睡眠導入剤と抗不安薬を処方されましたが、根本的な不安や孤立感は解消しませんでした。やがて職場にも行けなくなり、退職を余儀なくされたことから、さらに人を避ける生活が固定化していきました。
Aさんは自分でもこのままではまずいと感じ、インターネットで検索してカウンセリングを申し込みました。カウンセリングでは、まず「人と会うと疲れる」という感覚がどういう状況で起こるのかを丁寧に言葉にしていきました。幼少期に両親の不仲の中で常に周囲の顔色をうかがって過ごしていた経験や、相手に嫌われないように先回りして気を遣い続ける癖が、現在の人間関係でも強く働いていることが少しずつ見えてきました。セッションを重ねる中で、Aさんは無意識に「良い人でいなければならない」と自分を追い込んでいることに気づき、カウンセラーとともに安全な関係の中で本音や怒りを表現する練習を行いました。
数年かけて少しずつ、人と距離を取ることと関わることのバランスを取れるようになり、気心の知れた友人との交流から再開することで、孤立感や強い不安は和らいでいきました。現在はパートタイムの仕事にも復帰し、人と関わることへの恐怖は完全になくなったわけではないものの、自分のペースで社会生活を送れるようになっています。
考えられる病気・障害
「人と関わりたくない」となった時に考えられる病気・障害または原因として、ここでは次の3つに分けたいと思います。
| 要因 | 病気や障害の種類 |
|---|---|
| 全般的な意欲の低下に起因したもの | 気分障害(うつ)、統合失調症 |
| 社会生活・対人関係に起因したもの | 社交不安障害、回避性パーソナリティ障害 |
| ストレスや特性に起因したもの | 感情労働、HSP、アダルトチルドレン |
Aさんは、人と関わりたくない気持ちが強く、日常生活にも支障が出ていました。心療内科では軽いうつ状態と診断され、睡眠や食欲の低下、気分の落ち込みが見られました。
次にそれぞれの特徴や症状を解説します。
それぞれの特徴・症状について
(1)全般的な意欲の低下が原因
人と関わりたくないだけでなく、食欲・性欲・睡眠欲の三大欲求の減退や、「無為自閉」と呼ばれるあらゆることにおける興味・関心の低下・喪失が見られます。ただし、服薬の影響で食欲・性欲・睡眠欲に関しては、亢進する場合もあります。
Aさんの場合、朝起きるのもつらく、やる気が出ずに家事や外出を後回しにしてしまうことが多くありました。意欲の低下が続いた結果、社会活動への参加がますます難しくなりました。
a.気分障害(うつ)
多方面における興味・関心・意欲の低下・喪失が見られます。簡単にいうと「何もしたくなくなる」訳です。症状が悪化すると希死念慮と呼ばれる自殺願望が生じ、自殺企図につながる場合もあります。人と関わりたくない、のレベルを超えて生活全般ひいては命の危険の可能性もあります。
気分障害・うつ病の詳しいことは下記をご参照ください。
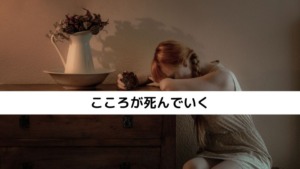
b.統合失調症
主に幻覚・妄想等の陽性症状と感覚鈍麻と呼ばれる陰性症状があります。
幻覚・妄想の種類は多岐に渡りますが「誰かに見られている」「誰かが自分の食べ物に毒を入れている」等の妄想が悪化することにより、外に出て人と会うことを避けるようになります。また陰性症状では思考力や判断力の低下・喪失が見られたり、これまで行っていた活動や社交への興味の減退・喪失が起こります。
また、二次障害としてうつを併発する場合もあります。
統合失調症の人への関わり方や接し方については以下をご参照ください。
(2)社会生活・対人関係に特化した原因
日常生活はそれほど支障なく過ごせますが、人前に出る・人と関わる場面で症状が起きます。
Aさんは、人と会ったあとに強い疲労感や頭痛が出るため、次第に人との交流自体を避けるようになりました。職場の人間関係のトラブルがきっかけで対人不安が高まり、人前で話すことにも緊張が強く出ました。
a.社交不安障害
以前は「対人恐怖症」「赤面症」等と呼ばれていたものです。
ある特定の状況や人前で何かをする際に緊張や不安が高まり、赤面・発汗・手足や声の震え等の症状が起こります。一度症状が起こった後、また同じ症状が起こるのではないかという「予期不安」が現れることで、症状が起こりそうな場面を避けるようになります。
人と関わる場面で症状が起こることが殆どなので、症状が起こりそうな場面を避ける=人と会う・人と関わるのを避けるとなり、人と関わることがどんどん億劫になっていきます。
社交不安障害についてのさらに詳しいことは下記のページをご覧ください。
b.回避性パーソナリティ障害
日常での出来事に対する反応や対人関係の築き方は人によってさまざまです。その反応の癖や築き方の特徴によって、本人がひどい苦痛を感じていたり生活に支障をきたしているものをパーソナリティ障害といいます。回避性パーソナリティ障害はその内のひとつで、否定・拒否・拒絶されることや屈辱的な場面・恥をかくことを極端に回避する特徴があります。
社会生活をしていれば誰しも人前で失敗したり、自分の意見を否定されることはあるでしょう。ですが、この障害は失敗して恥をかくことや自分の意見や考えを否定されることが何よりも辛いため、そういった場面を回避しようとします。その結果、人前に出ること・人と関わる場面がおのずと減っていきます。
(3)ストレスや特性に起因したもの
上に挙げた2つとは異なり、病気や障害ではありませんが、人と関わりたくなくなる原因の一つとして考えられます。
Aさんの場合、幼少期から周囲の顔色をうかがう傾向が強く、過度に気を遣う性格が背景にありました。ストレスが続くと動悸や不眠が悪化し、心身ともに疲弊して人と距離を取ることでしか回復できない状態になっていました。
a.感情労働
自分の感情を用いて、相手にプラスになる働きかけを行う労働をさします。肉体労働は「肉体」を、知的労働は「知識」を提供して報酬を得るように、感情労働は「感情」を提供する訳です。
仕事をしていれば多かれ少なかれ誰しも感情の提供をしていますが、特に医療・福祉従事者など直接他者と関わる対人支援職に求められる労働のあり方です。感情の提供を求められ続けることで疲弊していき、人と関わることが本来の職務であるにも関わらず、その職務であるが故に、「もう人とは関わりたくない」となってしまいます。
b.HSP
HSPとはThe Highly Sensitive Personの略で、非常に感覚が過敏で、それによって過度に疲れてしまいやすい人のことを指します。これはいわゆる病気や障害ではなく、特性の一つです。
HSPはさまざまな刺激を直接的に感じてしまいます。通常であれば気にならなかったり、無視できるぐらいのレベルであっても、HSPの人によっては針を刺されるかのような痛みを伴う感覚となってしまいます。
そして、人との関係はHSPにとっては刺激の一つです。人との関係が刺激となり、苦痛となり、それを避けようとしてしまいます。
こうしたことで人と関わりたくなる時にはHSPの可能性があります。
HSPについての詳しいことは下記をご参照ください。
c.アダルトチルドレン
アダルトチルドレンとは幼少期に養育環境がよくない家庭で育った人をさします。こうした幼少期の経験は人間関係に深刻なダメージを与え、有意義で、楽しい人間関係を作ったり、維持したりすることがとても難しくなります。
人間関係で傷つきやすかったり、些細な言動に怒りを感じてしまったり、自分を抑制して過度に相手に合わせてしまったりしてしまいます。そのため、人間関係でひどく疲れてしまいます。
こうしたことから人と関わりたくないと思ってしまいます。
こうしたアダルトチルドレンについての詳細は下記のページに書いていますので、ご覧ください。
人と関わりたくないと感じることに関するよくある質問
人と関わりたくないと感じる原因はさまざまです。過度なストレスや感情的な負担が影響していることがあります。仕事や家庭でのプレッシャー、人間関係の摩擦などが重なると、心が疲れてしまい、他人と関わりたくないと感じることがあります。また、HSP(Highly Sensitive Person)という特性を持つ人々は、周囲の刺激に敏感であるため、人との関わりを避けることが多いです。人との接触がストレスの原因になることもあります。自分の感情を守るために、無意識に人と距離を置こうとすることがあります。
HSP(Highly Sensitive Person)とは、外的な刺激や他者の感情に非常に敏感で、他の人が感じる以上に強く反応してしまう特性を持った人々を指します。HSPの人々は、音や光、感情的な雰囲気に対して過剰に反応し、疲れやすく、周囲の環境や人間関係に負担を感じやすいです。彼らにとって、人との関わりが過度な刺激となり、時に自分を守るために距離を置くことが必要と感じることがあります。HSPは病気ではなく、特性の一つです。理解と対応が重要です。
感情労働とは、仕事において自分の感情を制御し、相手に求められる感情を表現することが求められる労働のことを指します。特に医療、介護、サービス業など、他人と直接関わる職業で多く見られます。感情労働が過度に行われると、感情的な疲れが蓄積し、心身の健康に悪影響を及ぼすことがあります。これが続くと、仕事への意欲を失ったり、人との接触を避けるようになったりすることがあります。感情労働は注意深く管理する必要があり、適切なサポートが求められます。
人と関わりたくないと感じることは必ずしも病気ではありません。しかし、これはしばしば心理的な問題やストレスのサインである場合があります。例えば、うつ病や社交不安障害などが影響している可能性があります。長期間にわたり人と関わりたくないと感じ、日常生活に支障が出る場合、専門的な相談を受けることが重要です。自分の感情や行動を適切に理解し、早期に対処することが心身の健康を守るために大切です。
人と関わりたくないと感じたときは、まず自分の感情を理解し、無理に他人と接しようとするのを避けることが大切です。自分のペースで休息を取ることが心の回復に繋がります。ストレスの原因を特定し、その対処方法を考えることも重要です。例えば、日常生活で過度なプレッシャーを感じている場合、その負担を軽減する方法を考え、ストレスを減らす努力をすることが有効です。また、専門家に相談して、心の健康を保つサポートを受けることもおすすめです。
HSPの特徴は、非常に感覚が鋭く、外的な刺激や他者の感情に敏感であることです。HSPの人々は、大きな音や強い光、人混みなどに対してストレスを感じやすく、感情的な反応が強くなることがあります。また、他人の気持ちを察する能力が高いため、人間関係においても繊細に感じることがあります。このため、HSPの人は疲れやすく、静かな環境で過ごすことを好むことが多いです。自分の特性を理解することが重要で、環境を調整し、過度な刺激を避けることが有効です。
感情労働が過度に行われると、心身に大きな負担がかかり、感情的な疲労が蓄積されます。これが続くと、バーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こし、仕事への意欲を失ったり、他者との接触を避けたくなったりすることがあります。感情労働による疲れは、長期的に無視していると、精神的な健康問題に繋がる可能性もあります。感情労働を適切に管理することが求められます。必要に応じて、休息やリフレッシュの時間を取り、専門家の支援を受けることも大切です。
一時的に人と関わりたくないと感じることは、誰にでもあることです。しかし、これが長期間続く場合や日常生活に支障をきたす場合は、心理的な問題が影響している可能性があります。一般的には、ストレスや過労、感情的な疲れなどが原因となることが多いです。このような場合には、自分の感情を理解し、無理に他人と接しないようにすることが大切です。また、心理カウンセリングを受けることが有効です。
人と関わりたくない自分を受け入れることは大切です。自分の感情や体調に敏感になることで、無理に他人との接触を強要せず、自分のペースで過ごすことができます。自分の感情に対して優しく、理解を示すことが心の健康に繋がります。人と関わりたくないと感じることがあっても、それは自分を守るための自然な反応であり、無理に解決しようとするのではなく、適切に休息を取ることが重要です。自分を大切にすることが最優先です。
人と関わりたくないと感じる自分を改善するためには、まず自分の感情を理解し、無理のない範囲で人と接することが大切です。少しずつ他人との関わりを持ちながら、自分が心地よいと感じるペースを見つけていきましょう。また、ストレス管理やリラクゼーション法を積極的に取り入れることで、心の負担を軽減することができます。心理的なサポートを受けることも一つの方法で、心の健康を保ちながら、人との関わり方を見直していくことが重要です。
人と関わりたくない時には相談することも
「人と関わりたくない」冒頭でも述べましたが、この気持ちは誰しもきっと一度は経験する感情です。「自分だけがおかしいのではないか?」と思い悩む必要はありません。
心が(時には身体も)疲れているサインなので、少しリラックスする時間を作ってみてください。
いずれにしても一人で悩みすぎない・抱え込まないことが大切です。「人と関わりたくない」と矛盾するようですが、人との関わり方の悩みを助けてくれるのもまた、人です。
また、専門のカウンセラーによるカウンセリングやメンタルクリニックを受診してみるのもひとつの方法です。当オフィスでも相談やカウンセリングを行っております。ご希望の方は下記のページからお申し込みください。