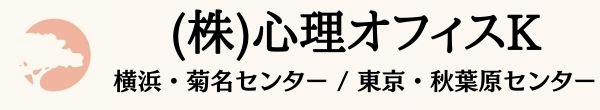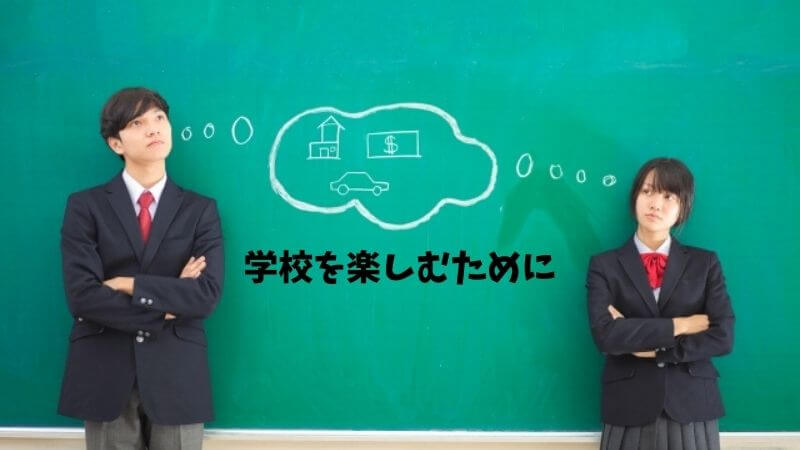子育てにイライラしてもう限界!もしかしたら病気が隠れているかも

子育て中にイライラし過ぎて、自分を制御できなくなったという経験はありませんか?育児中では、自分の時間が取れなくなり、24時間注意を払わなければならないため「終わりがない」と限界を感じることもあるでしょう。イライラが止まらないのは、何らかのストレスがかかっているためです。
そこで今回は、子育て中にイライラしてしまう原因や解消法について紹介します。
目次
子育てのイライラとは
子育てのイライラは、多くの親が抱える自然な感情ですが、背景にはいくつかの要因が重なっています。まず、子どもは成長過程で自我を主張し、親の思う通りには行動しません。その姿に直面することで、親の「こうあってほしい」という期待が裏切られ、強い苛立ちを感じることがあります。また、育児によって自分の時間が奪われ、慢性的な疲労や睡眠不足に陥ると、些細なことで感情が爆発しやすくなります。さらに、周囲からの協力が得られない状況では、孤独感や無力感が募り、イライラが増幅されてしまいます。
こうした感情は「親として失格なのでは」という罪悪感に結びつくこともあり、自己否定を強めてしまうことがあります。イライラは決して親の未熟さだけでなく、育児という大きな負荷や環境要因から生じる自然な反応であると理解することが大切です。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは、3歳になる娘の子育てに日々奮闘していました。幼少期から母親の期待に応えようと「良い子」であり続けた彼女は、感情を抑えて過ごすことが多く、自分の気持ちを素直に表現する経験が乏しいまま大人になりました。結婚・出産を経て、理想的な母親像を強く抱く一方で、子どもが思い通りに動かない場面に直面すると、抑え込んできた苛立ちが一気にあふれ出し、つい手を挙げてしまうことがありました。行為の直後には強い後悔と自己嫌悪に襲われ、「母親失格ではないか」と自分を責める日々が続きました。
次第に気分は沈み、睡眠も浅く、夫や友人に対しても余裕を持てなくなったAさんは、子育て支援センターでの相談をきっかけにカウンセリングを勧められ、心理オフィスKを訪れることになりました。初回の面接では、子どもへの愛情と同時に「感情を抑えられない恐怖」を率直に語り、涙が止まらなくなりました。カウンセリングでは、Aさんが育ってきた家庭環境における「我慢の習慣」や「母として完璧であらねばならないという思い込み」に目を向けながら、少しずつ自己理解を深めていきました。
プロセスの中で、感情が高ぶった時に深呼吸や一時的に距離を取る方法を実践するようになり、同時に「子どもの気持ちに耳を傾けることが自分を責めることにはつながらない」という実感を得ていきました。時間をかけて、自分の怒りの背景にある疲労や孤独感を認め、それを言葉で表現する力を育んでいきました。継続した面接を通じて、Aさんは「子どもと一緒に成長していく母親」であることを受け入れられるようになり、完璧でなくとも関係を修復できる安心感を持てるようになりました。
数年にわたる取り組みを経て、衝動的に手を挙げてしまうことは減り、子どもへの関わりに余裕が生まれました。イライラそのものが完全になくなったわけではありませんが、それを抱えながらも関係を保ち続けられる力を持てたことが、Aさんにとって大きな変化でした。彼女は今も子育てに悩むことはありますが、「相談できる場がある」という安心感を背景に、以前よりも穏やかに日常を過ごせるようになっています。
育児でどうしてこんなにイライラするの?
まずは育児でイライラしてしまう原因について見ていきましょう。赤ちゃんや子どもは癒やしを与えてくれて、心を穏やかにしてくれる存在だと思っている人もいるかもしれません。
しかし、実際の育児は、赤ちゃんや子どもの命を24時間体制で見守るため、常に気を張った状態にあります。つまり、自分が思っている以上にストレスがかかっているのです。このストレスに加え、以下のような原因も考えられます。
(1)子どもが自分の思う通りにならない
子どもは大人が思ったように行動してくれません。
外出しようと思ったら「外に出たくない」といい、外出先から家に帰りたくても、今度は逆に「まだ帰りたくない」と駄々をこねて大人を困らせることもあります。反抗期の子どもであればなおさらです。
Aさんは、3歳の子どもが思い通りに動かず、イヤイヤを繰り返すたびに強い苛立ちを感じていました。完璧な母親であろうとする気持ちが裏目に出て、子どもをコントロールできない自分を責めることが多くありました。
(2)自分の時間を確保できない
家事や育児を一手に背負うと、自分の時間を確保することが難しくなるでしょう。
赤ちゃんの頃は、2~3時間おきに授乳したりおむつ替えをしたりします。ハイハイや伝い歩きを始めると、ケガをしないか注意して見守らなければなりません。
しっかり歩けるようになると、いたずらをしたり勝手に外に飛び出したりしないかなど、さまざまなことに注意を払う必要があります。そうなると、自分にかけられる時間がほとんどなくなり、気づけば子どものことばかり…となってしまうのです。
Aさんの場合、子育てに追われて自分の時間をまったく持てず、休む間もなく疲労感が蓄積していました。好きだった趣味や友人との交流も減り、孤立感が強まっていました。
(3)仕事との両立ができない
仕事と育児との両立を完璧に行うことは無理です。
子どもは急に体調を崩したり、お友だちと遊んでいるときにケガをしたりなど突発的なことが起きて、仕事中でも急に保育園や幼稚園から呼び出されることがあります。
また、育休前のように「仕事を頑張りたい」と思っても、会社側の配慮から責任ある仕事を任せてもらえないこともあるでしょう。逆に、自分が仕事ばかりしていて、「子どもの世話ができていない」と自分を責めてしまう人もいるかもしれません。
Aさんは、子育てとパートの仕事を両立しようとしましたが、子どもの体調不良や突発的な要求で勤務に影響が出ることが多く、職場に迷惑をかけていると感じていました。
(4)家族の協力がない
仕事をしながら子育てをしている人はもちろん、子育てに専念している人にも子育てには家族の協力が必要です。
子どもによって性格はさまざまなため、どんなに子育てに慣れた人でも子育てに悩み、ストレスを抱えてしまいます。
これが、子育て初心者の人で、家族の協力が全くないと想定したらどうでしょうか?子どもの命を1人で背負い、育児のかたわら家事も仕事もとなると計り知れないストレスがかかります。
Aさんの場合、夫が仕事を理由に育児に積極的に関わらず、ワンオペに近い状況が続いていました。サポートがないことへの不満や孤独感が、イライラの大きな要因となっていました。
(5)子どもの発達状況が心配
育児中は子どもの発達状況も不安の要因となります。
これは自分の子どもを心配し、思っているからこそ起こるものです。しかし、他の子どもと比べて「歩き始めるのが遅い」「話し始めるのが遅い」と感じてしまうと、不安で押しつぶされそうになる人もいるでしょう。
発達のことについては以下のページが参考になります。
Aさんは、子どもが言葉の発達に遅れがあるのではと不安を抱いていました。その心配が余計に焦りや苛立ちを強め、子どもを急かしてしまう場面が増えていました。
子育てに限界を感じたらどんな症状がでる?
子育てにおけるストレスで、限界を感じた場合にでてくる症状を見ていきましょう。子育て中は忙し過ぎて、「自分に大きなストレスがかかっている」と気づかない人も多いものです。自分と似た症状がないかチェックしてみてください。
- 制御できないくらいイライラする
- マイナス思考になる
- 無気力、無関心になる
- 眠れなくなる
- 食欲がなくなる、過食になる
- 子どもに興味がなくなる
ものに当たったり、いつもだったら何とも思わないちょっとしたことで怒鳴ったりしていませんか?逆に「もうダメ」「自分が悪い」「母親失格」などマイナス思考になってしまうこともあります。
これまで好きだったものに全く関心がなくなり、やる気が起きずボーッと1日を過ごすという症状がでる人も。部屋をいつもきれいに整えていた人が、散らかったままにしているというのもチェックポイントになるでしょう。
また、体は疲れているのに全く眠れない、食欲がでない、または過食してしまうなどの症状もあります。無気力や無関心にも該当するのですが、子どもをかわいいと思えなくなったり子どもに興味がなくなったりするケースもあるでしょう。
Aさんの場合、日々の育児に追われて心身が疲弊し、子育てに限界を感じるようになると、まず強いイライラや怒りが抑えられなくなりました。その結果、子どもにきつい言葉を投げかけたり、手を挙げてしまうことがあり、その直後には強い自己嫌悪と後悔に襲われました。さらに、気持ちが落ち込みやすくなり、「母親失格ではないか」と自分を責め続ける思考が止まらなくなりました。
ストレス解消が一番!でも病気が隠れているケースも
子育てに限界を感じる前に行動することが大切ですが、限界を感じた場合にはすぐに、自分の時間を作ったり家族に協力してもらったりすることで、ストレス解消することが一番です。
ただ、ストレスだけで片付けられないケースもあります。それは、病気が潜んでいるケースです。どんな病気が考えられるのでしょうか?
(1)もしかしたら愛着障害かも
もしかしたら、母親自身か子ども自身のどちらかが愛着障害の可能性があるかもしれません。
愛着障害とは、幼少期に養育者との間に情緒的なきずなを形成できなかったことで、気持ちのコントロールが上手くできなくなったり対人関係を構築する際に問題が起きたりすることを指します。
愛着障害についての詳細は以下をご覧ください。
Aさんの場合、子どもとの関係に温かさを持ちづらく、感情が抑えきれない中で「愛着がうまく育めていないのでは」と不安を抱きました。
(2)愛着障害の特徴とは?
愛着障害の具体的な特徴は以下の通りです。
- 傷つきやすい
- 人への警戒感が大きい
- 怒ると感情的になって話し合いができない
- 白黒つけたがる
- 自分を責めてしまう
- 人への愛情の注ぎ方がわからない
- 誰にでもなれなれしい
- 人の注意を引こうとする
主に小学生までに発症することが多いのですが、愛着障害の治療をしないままだと大人になっても症状が続くことがあります。
子どもが愛着障害の場合であれば、癇癪を起しやすかったり、過度に甘えてきたり、非常に警戒的になったりするため、子育ては困難になるでしょう。
もし母親自身が愛着障害であった場合、自身の気持ちをコントロールすることができなかったり、子どもに過度に期待をもってしまったり、懐かないことに腹を立てたりしてしまいます。そのことにより子育てに限界を感じてしまったりします。
Aさんは、子どもが母親に甘えたり安心して寄り添ったりする姿が少なく、すぐに癇癪を起こす点に、愛着障害の特徴を重ね合わせて悩んでいました。
(3)愛着障害からさらに病気を引き起こすことも
愛着障害では、人の顔色を常に見ていたり自分に自信を持てなかったりと自己肯定感が低くなるケースがあります。そういった症状から過度にストレスがかかり、以下のような病気を引き起こす可能性があるのです。
- うつ病
- 不安障害
- 境界性パーソナリティ障害
- 適応障害
ここで挙げた病気は一例です。この他にも愛着障害によって引き起こされる心や体への負担はたくさんあります。気になる点がある人は、病院を受診したりカウンセリングを受けたりすると良いでしょう。
Aさんの場合、育児ストレスによる不眠や抑うつ気分が続き、放置すればうつ病や適応障害につながるのではないかという不安を強めていました。
愛着障害の診断方法や治療方法とは?
愛着障害の可能性がある人がどこの病院を受診したら良いのか、どんな治療法を行うのかについて紹介します。
(1)どの病院を受診する
愛着障害は心の病気のため、心療内科や精神科、カウンセリングの受診がおすすめです。
心理検査などを行い、どういった精神状態にあるのか、これまでの環境などをひも解いていきます。
Aさんは、子どもの発達や自身の抑うつ気分について、まずは小児科や心療内科を受診しようと考えました。必要に応じて専門機関や心理相談にもつながろうとしました。
(2)治療法は?
子どもの愛着障害を治療する際には、箱庭療法や遊戯療法などを用いたりします。また最近では応用行動分析や認知行動療法なども愛着障害に有効であると示されています。さらに、親や保護者の関わり方を指導するペアレントトレーニングなども開発されてきています。
その他に、漢方薬などの薬物治療を行ったりすることもあります。
いずれにせよ、子どものケースでも大人でも同じですが、自分にとっての安全基地を作ることが大切になります。そのため、大人の愛着障害を治療する場合には、人とのコミュニケーションによって、幼少期に不足した情緒的なきずなを形成する必要があるでしょう。もちろん親でも構いませんし、恋人や友人でもOK。
周りに相談することができなければ、心療内科やカウンセラーに相談し、自分の安全基地を確保すると良いでしょう。
Aさんの場合、カウンセリングで子どもとの関わりを見直すことが有効であり、並行して医師による診察や必要な支援を受けることで、少しずつ落ち着きを取り戻していきました。
子育て中にイライラを感じる理由についてのよくある質問
子育て中にイライラを感じる原因は多岐にわたりますが、主に過度な責任感や期待、体力的・精神的な疲労、家事や仕事との両立の難しさ、そして子どもの予測不可能な行動が影響しています。特に、育児は24時間続くものであり、その中で自分の時間や休息を取ることが難しいため、精神的に負担がかかりやすいです。また、子どもが思い通りに行動しないとき、感情が抑えきれずイライラしてしまうこともあります。加えて、家族やパートナーとの役割分担がうまくいかないと、負担感が増し、イライラが募ることもあります。このような状況は、ストレスが溜まることでさらに強く感じられることが多いのです。
イライラを減らすためにはまず、感情を認識し、コントロールすることが重要です。感情的になってしまう前に、深呼吸をする、数分間その場を離れる、そして自分の気持ちを一度整理する時間を持つことが有効です。さらに、日常生活の中で小さな休憩を取ることや、自分の趣味やリラックスできる時間を確保することも、ストレスを軽減するためには効果的です。また、家族やパートナーと協力して、育児や家事の負担を分担することが大切です。お互いにサポートし合うことで、精神的な余裕が生まれ、イライラを感じることが減ります。特に、家事や育児の負担を軽減するために協力し、具体的な役割分担を決めることは、家庭内のストレスを大きく減らす方法の一つです。
子どもにイライラをぶつけてしまう自分が嫌だと感じることは、とても理解できます。しかし、改善するためにはまず、自分の感情に対して責任を持つことが大切です。自分がイライラしていると感じた時、まずは冷静になり、一度その場から離れて深呼吸をすることが有効です。その後、自分が何に対してイライラしているのかを冷静に考え、具体的な問題点を洗い出します。そして、その問題を解決するための行動を考えることが大切です。また、子どもに対して冷静に伝える方法を学ぶことも重要です。感情的にならず、穏やかな言葉で伝えることを意識することで、親子関係の改善にもつながります。イライラを感じたときに一呼吸おくことで、自分の感情をコントロールしやすくなります。
夫に対してイライラすることが多い場合、まずはその原因を見つけることが大切です。多くの場合、コミュニケーション不足や、期待していることがうまく伝わっていないことがイライラの原因となっています。自分が感じていることや思っていることを正直に伝えることは、パートナーとの関係を改善するためには欠かせません。また、夫婦間の協力体制を築くことも重要です。家事や育児の負担を一人で背負うのではなく、共に分担することでお互いの負担を軽減できます。さらに、感情的にならずに冷静に話すことを心がけ、相手の立場や状況にも配慮するようにすることで、より良いコミュニケーションを築けるようになります。時には、自分の気持ちを一時的にリセットし、冷静に対話をすることが有効です。
子育てのイライラを解消するためには、まず自分の感情を認識し、受け入れることが重要です。自分がイライラしている理由を理解し、その原因に向き合うことが改善の第一歩です。例えば、育児が忙しすぎて疲れている、家事との両立が難しい、子どもの行動に対して過剰に反応してしまうなどの原因があるかもしれません。これらに対して、深呼吸や瞑想、短い休憩を取ることが有効です。また、家族や友人とのサポートネットワークを作ることも、イライラの解消には効果的です。時には、家族と協力して家事や育児の負担を分担し、自分の時間を作ることがストレスを軽減するためには重要です。自分の感情に敏感になり、イライラを感じた時には適切な対処法を取ることがイライラ解消には繋がります。
子どもにイライラしないための心構えとしては、まず自分の感情をコントロールすることが大切です。イライラする前に一呼吸おいて、冷静になる時間を取ることで、感情が抑えやすくなります。また、子どもの行動に過度に反応しないことも重要です。子どもは成長過程にあり、予測できない行動をすることもありますが、その行動に過剰に反応するのではなく、理解を示すことが大切です。また、子どもに対して柔軟な対応を心がけ、過度に期待しすぎないことがイライラの予防につながります。子どもの気持ちを尊重し、時には大人が譲ることも必要です。
子育て中のストレスを軽減する方法には、まず自分自身の心身の健康を大切にすることが挙げられます。適度な運動や十分な睡眠を確保することで、心身の調子が整い、ストレスに対する耐性が高まります。また、日々の生活の中で、自己ケアの時間を作ることも重要です。たとえば、リラックスできる趣味に時間を使う、友達や家族と気軽に会話をすることで心の中のストレスを軽減できます。また、育児や家事の負担を一人で抱え込まず、家族やパートナーと協力して分担することも、ストレス軽減には欠かせません。ストレスの原因を明確にし、対処する方法を見つけることが、より穏やかな心持ちを保つために必要です。
子育てのイライラを減らすためには、まず自分に対して優しくなることが大切です。完璧を求めず、ミスをしても自分を責めないことが重要です。また、育児に対して柔軟な考え方を持ち、子どもが成長していく過程を見守る気持ちを持つことで、イライラが減ります。自分の気持ちに余裕を持つために、リラックスできる時間を取ることも有効です。また、イライラした時にはその感情に気づき、無理に抑え込むのではなく、一度その感情を感じてから冷静に対応することが心の持ち方を改善するために大切です。
子育て中のイライラを解消するためには、リラクゼーション法として深呼吸や瞑想、軽いストレッチが効果的です。深呼吸をすることで、体の緊張をほぐし、心を落ち着かせることができます。瞑想も心の中の雑念を取り除き、心身のリフレッシュに役立ちます。ストレッチやヨガも、体を動かすことでリラックス効果が得られ、心の状態も落ち着きやすくなります。こうしたリラクゼーション法を日常生活に取り入れることで、イライラを感じたときに冷静さを取り戻しやすくなります。
子育て中のイライラを減らすためには、時間管理術が非常に効果的です。まずは、日々のタスクを優先順位をつけて整理することが大切です。重要なことから取り組むことで、時間に追われることなく余裕を持つことができます。また、無理なスケジュールを立てないようにし、適度な休息を取ることが肝心です。家族やパートナーと協力して役割分担を行い、お互いにサポートし合うことで、忙しい日々の中でも効率的に時間を使うことができます。このように時間管理を工夫することで、イライラすることが減り、より穏やかな気持ちで育児に取り組むことができるようになります。
子育てについて相談したい
慣れない子育てに毎日ストレスを感じている人もいるかもしれません。そんなときは1度立ち止まって、周りに助けを求める勇気も必要です。限界を迎えるまで自分1人で抱え込まず、「疲れた」「助けて」と意思表示して、他の人の協力を得てください。
「あまりにイライラが止まらない」「子どもを上手く愛せない」と感じた場合には、愛着障害が潜んでいるのかもしれません。自分の安全基地として心療内科やカウンセリングを受診してみると良いでしょう。
当オフィスでは愛着障害を専門にするカウンセラーが多く在籍しています。気になる症状を抱えている方は、以下のページからお気軽にお申し込みください。