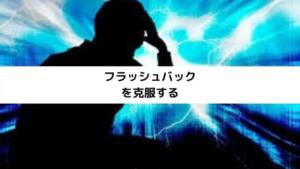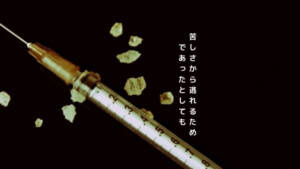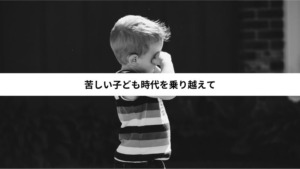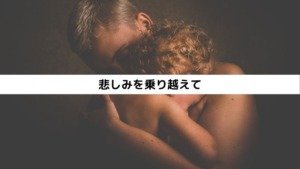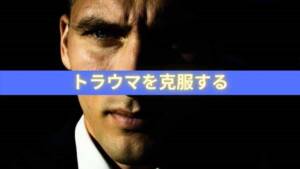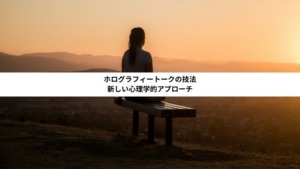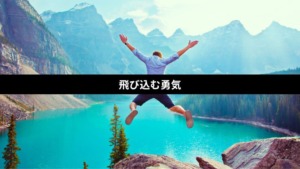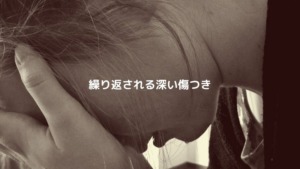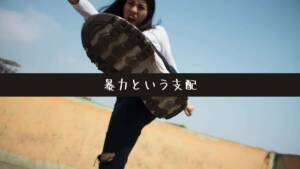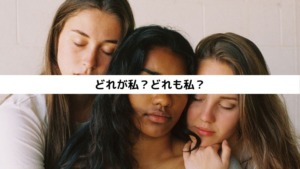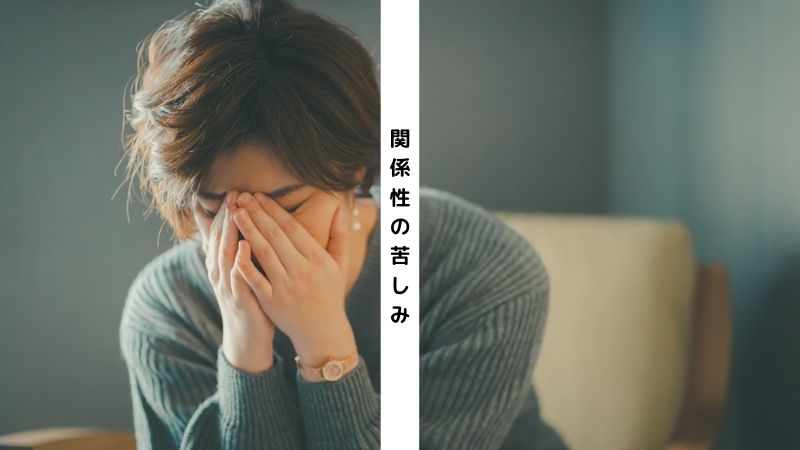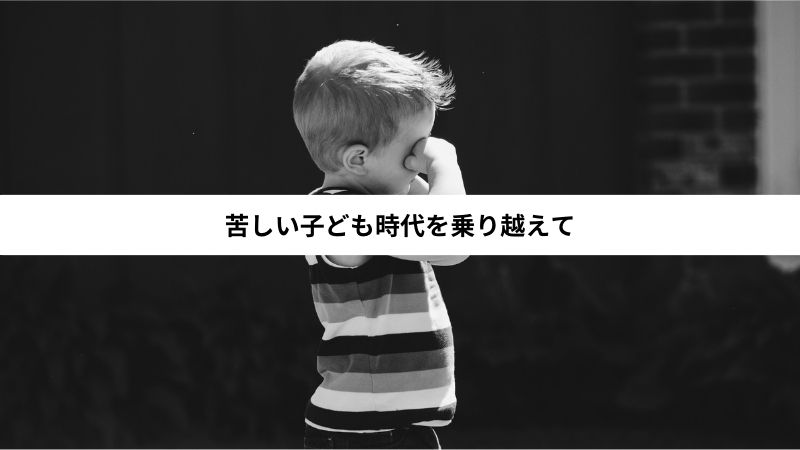子どものトラウマ

子どものトラウマとはどのようなもので、また、それを克服するにはどうしたらいいのでしょうか。この記事では、トラウマの症状やそのきっかけ、回復に向けた治療や予防に向けた支援について説明します。
トラウマの発症や回復には親子関係をはじめ、周囲の人とのかかわりが大きく影響します。カウンセリングなどの援助も活用しながら、子どもに寄り添い回復を支えましょう。
目次
子どものトラウマとは
子どものトラウマとは、いじめや虐待、事故、災害など、心身に強い衝撃や恐怖を与える出来事をきっかけに、心の中に深い傷が残る状態を指します。子どもは発達の途上にあり、ストレスに対処する力が十分に育っていないため、出来事をうまく処理できず、過度な不安や恐怖を抱え込みやすくなります。その結果、腹痛や頭痛、不眠、悪夢などの身体症状が現れるほか、集中力の低下や学業不振、友人関係の回避といった行動面の変化が見られることもあります。さらに「自分が悪いからこうなった」という否定的な自己イメージを強め、自己肯定感を損なうことも少なくありません。
トラウマ反応は脳や心に「危険がまだ続いている」という誤作動を生じさせ、安心できる環境でも過敏な警戒心が働いてしまいます。しかし、信頼できる大人の支えや安全な場での表現を通じて、少しずつ心の整理が進みます。家庭では子どもの気持ちを受け止め、安心感を育むことが回復に不可欠
よくある相談の例(モデルケース)
小学校高学年 男子Aさん、40歳代 母親Bさん
Aさんは小学校高学年の男児です。幼い頃からおとなしく几帳面で、絵を描いたり本を読んだりすることを好んでいました。ところが高学年になると、教室内でのからかいや仲間外れが続くようになり、休み時間に一人で過ごすことが増えていきました。周囲から笑われたり、遊びのグループから外されたりする体験が積み重なり、Aさんは次第に「自分は嫌われている」「教室にいるとつらい」と感じるようになりました。その頃から朝に腹痛を訴えて学校を休むことが増え、夜は不安で眠れず、悪夢で目を覚ますこともしばしばでした。小児科を受診しましたが身体的な異常は見つからず、心因性の不調として対応する必要があるとされました。
母親(40代)は面接で、「もっと早く気づいて守れなかった」と涙ながらに語りました。教師への不満や学校対応への怒りも強く、家庭では励ましが「早く行きなさい」という圧力となり、Aさんをさらに追い詰めていました。初期のカウンセリングでは、まず安全感を取り戻すことを目標にしました。家庭で安心できる時間を意識してつくり、簡単なリラクゼーションや安心の合図を母子で練習しました。学校とは保健室や別室からの部分登校を設定し、担任や養護教諭との連携を整えていきました。
カウンセリングのプロセスは1年以上にわたって継続されました。Aさんは絵や物語作りを通して、いじめられたときの不安や恐怖を少しずつ言葉に変えていきました。カウンセラーとのやり取りを重ねるなかで、「自分が悪いからいじめられた」という思い込みを見直すことができました。母親には、無理に登校を促すのではなく、Aさんの気持ちを受け止めて寄り添うことの大切さを繰り返し伝えました。また、母親が一人で学校とのやり取りを抱え込みすぎないように、相談先やサポート体制を整理しました。やがてAさんは保健室登校から一部の授業参加へと段階的に広げ、安心できる友人と過ごす時間も持てるようになりました。完全に不安が消えたわけではありませんが、腹痛や不眠は減り、学習や遊びへの意欲も戻ってきました。現在は月に一度のフォローアップで経過を見守り、再び不安が高まったときの対応を家族と共有しています。
子どものトラウマの特徴
子どものトラウマとは、どのようなものでしょうか。ここでは、トラウマの定義、子どものトラウマ反応、子どものトラウマ反応が起こるメカニズムに触れていきます。
また、そもそものトラウマやPTSDの全般的な説明は以下のページをご参照ください。
(1)子どものトラウマ反応
トラウマの特徴や症状には侵入体験、過覚醒、回避、麻痺、否定的思考があります。そのほか、小さな子どもには以下のトラウマ反応が表れやすくなります。
Aさんは教室でのからかいや仲間外れが続いた結果、朝の腹痛や頭痛、夜の不眠、悪夢といった心身の不調が現れました。また「自分は嫌われている」という否定的な自己イメージを強め、人前で話すことを恐れるようになりました。
a.分離不安
養育者などの愛着対象から離れる際に感じる不安をいい、養育者にまとわりつくといった行動がみられます。
b.退行
より早期の発達段階に戻ることをいいます。日常生活では聞き分けが悪くなる、指しゃぶりや夜尿の復活、食事や着替えなどできたはずの生活スキルが後退する、といった様子がみられることがあります。
c.身体症状
特に年少の子どもは、トラウマ反応が身体症状として表れやすくなります。食べない、体重が増えない、なんとなく元気がない、頭痛や腹痛、といった反応がみられます。
(2)子どものトラウマ反応が起こるメカニズム
トラウマ反応は元々、心身の安全が脅かされる危機的状況からこころを護るために生じるものです。一般的には危機が去ればこうした反応はなくなりますが、危機の衝撃があまりに強い場合や長く続いた場合などはこころの働きが心身に根づいてしまいます。
危機に適応するために生じたこころのはたらきが、平穏な日常でも呼び起こされてしまうと誤作動となり、不適応的な反応となってしまうのです。
Aさんの場合、繰り返されるからかいや孤立体験が、脳や心に強いストレスとして刻まれました。危険を察知する警戒心が過剰に働き、些細な出来事でも「また笑われるのでは」と感じてしまうようになりました。
子どものトラウマのきっかけ
子どものトラウマは、どのようなきっかけで起こるのでしょうか。ここでは、トラウマのきっかけになる代表的な出来事を紹介し、特に深刻なトラウマにつながる幼少期の養育不全についてくわしく説明します。
(1)子どものトラウマのきっかけとなる出来事
子どものトラウマのきっかけとなり得る出来事には、さまざまなものがあります。同じ出来事がトラウマとして残るかどうかには個人の要因も影響しますが、一般には以下のような出来事が挙げられます。いずれも心身の安全が脅かされ、逃れることができない状況です。
- 戦争や戦闘、テロ、拷問、犯罪被害、事故、災害、他人の死の目撃
- 家族との離別や死別、転居や転校、学校での体罰やいじめ
- 幼少期の養育不全(身体的虐待、心理的虐待、静的虐待、ネグレクトなどの日常的な児童虐待など)
また、大人からは些細に見えることでも小さな子どもにとっては重大な恐怖の体験となる場合があります。たとえば迷子になることは、守ってくれる人を失うという生死にかかわる体験ですし、見捨てられたと感じたときの恐怖はより強くなります。このように、幼少期の愛着(アタッチメント)対象の分離や喪失は重大なトラウマになる可能性があります。
さらに養育不全がある場合は、子どもにとって守りとなるはずの愛着(アタッチメント)自体が不安定なため、トラウマがより深刻になるおそれがあります。
Aさんは高学年になった頃から、同級生からの仲間外れやからかいを繰り返し受けました。その出来事が積み重なり、学校や教室そのものを「怖い場所」と認識するようになりました。
(2)幼少期の養育不全の影響は深刻
乳幼児期のトラウマは、それ以降に生じるトラウマよりも精神発達への影響が深刻です。特に早期から長く反復して虐待を受けた場合、脳の機能や構造に重い影響が出ることがあります。
養育不全の子どもには、以下のような様子がみられます。
Aさんの場合、母親は心配しつつも「もっと強くなってほしい」と厳しく励ますことが多く、その言葉がAさんには「自分を守ってくれない」と感じられる場面もありました。これが孤独感を強める一因になりました。
a.乳児期
抱っこや愛撫などといった養育者の母性的なかかわりが不十分な場合、自分や周りへの基本的信頼感が育ちにくくなります。また身体や情動がばらばらのままでまとまらず、情緒的に混乱しやすくなるといわれます。
b.幼児期
家族の中でしつけが不適切な場合、意志の力や自己コントロールの力が育まれず、持続力や実行力が弱かったり、わかっていてもルールを守れなかったりします。
c.児童期
言葉を大切にできなかったり、攻撃的な行動をみせたり、知的な力に見合わない学業不振が出たりします。
d.思春期以降
うつ病や双極性障害などの気分障害、不安障害、解離性障害、境界性パーソナリティ障害などの精神疾患などを発症しやすいといわれます。
(3)愛着障害として
極端な養育不全により子どもの症状が一定の基準を満たすと「反応性愛着障害」「脱抑制型対人交流障害」と診断がつく場合もあります。
Aさんは母親の愛情を十分に感じながらも、支えを求めたときに十分に受け止められない経験が重なり、不安定な愛着の傾向を示すようになりました。そのため対人関係でも信頼よりも警戒が先立つようになりました。
a.反応性愛着障害(反応性アタッチメント障害)
苦痛が生じたとき、養育者に対しめったにまたは最小限にしか安らぎを求めず、引きこもった、抑制的な反応を示します。
b.脱抑制型対人交流障害
家族以外の見知らぬ大人にもためらいなく近づいたり、過度に馴れ馴れしくしたりします。
虐待などの極端な養育不全がある場合、子どもは愛着(アタッチメント)形成の問題とトラウマが相互に関連し、複合的な問題を抱えることが指摘されています。
なお、愛着障害についてのさらに詳しい説明は以下のページをご覧ください。
子どものトラウマの回復と予防
子どもがトラウマをケアし、また予防するには、どのようなことが必要なのでしょうか。ここでは、トラウマを抱えた子どもの回復と予防に必要な対応について触れます。
(1)子どもがトラウマから回復するには?
子どものトラウマからの回復には、基本的には精神医学や心理療法による専門的な治療が必要です。トラウマ反応が疑われる子どもに気づいたら、まずは保護者に働きかけて、地域の児童相談所やPTSD治療を行っている児童精神科など、専門家の支援につなげましょう。
Aさんはカウンセリングで安心できる関係の中で自分の体験を少しずつ表現し直し、否定的な自己イメージを修正することができました。母親も子どもの気持ちを受け止める姿勢を学び、支えとなることができました。
トラウマからの回復に向けた支援には、以下のものがあります。
a.子どものトラウマ反応の理解
まず重要なのは、子どものトラウマ反応やPTSD症状を理解することです。
極度の不安や混乱など、周りからは異質に見える様子も、トラウマ反応として起こり得ると知っているだけで対応は変わります。周囲が戸惑わずに落ち着いて対応でき、誤解からの叱責によって事態を悪くすることも避けられます。
b.安心・安全な環境づくり
子どもの日々の暮らしを丁寧に観察して取れる手立てを考え、子どもに適した環境づくりをします。
たとえば暗闇が怖くて眠れない子どもには明かりを用意する、子どもが混乱を見せたらその場を苦しい状況ととらえて刺激の少ない場所に移る、といった配慮です。不安や恐怖を呼び起こす刺激や状況を取り除き、安心して生活できる場にすることが大切です。
c.大人との信頼関係
養育者や周囲の大人との信頼関係に支えられると、トラウマ反応が落ち着くことがあります。養育者に対しては、子どものなだめ方を身につける、愛着(アタッチメント)を形成する、といった、関係をつなぐための専門的援助が行われます。
また保育園や施設など、生活の場での保育者や職員による、生活を良くするためのケアや生き生きとしたかかわりも、子どもの人への信頼感を育みます。
子どもにはトラウマ反応だけでなく、安定して主体的に振る舞える場面もあります。そうした時間に周囲の大人が寄り添い、感覚を一緒に味わうことが大切です。
d.特別なトラウマ治療
今の生活への安心感や人とのかかわりへの信頼が育まれると、専門的なトラウマ治療も実を結びやすくなります。
トラウマ治療には、プレイセラピー、トラウマフォーカスト認知行動療法(TF-CBT)、集団ロールプレイなどが用いられます。また、症状への対処として呼吸法や漸進的筋弛緩法といったストレスマネジメント法の習得も有効です。
いずれも、ばらばらになったままのトラウマ体験にまとまりをもたせ、トラウマにまつわる記憶や感情に圧倒されることなく、自力でコントロールできる状態を目指します。
トラウマを抱えた子どもの症状は深刻で、回復には長い道のりが必要です。子どもにかかわる周囲の大人や支援者には、子どもと信頼関係を築き、子どもに寄り添いながら根気よく回復を支える姿勢が求められます。
(2)子どものレジリエンスを育み、トラウマを予防する
子どものトラウマの予防において、レジリエンスという概念が注目されています。レジリエンスは弾力性や柔軟な回復力を意味し、曲がっても折れない竹や柳のようなしなやかさにもたとえられます。
同じ出来事を経験しても、トラウマ反応を生じる人と生じない人がおり、そこにはレジリエンスがかかわるといわれます。不安やストレスに圧倒されずにしなやかにこなす力であるレジリエンスが発揮されれば、トラウマの深刻化を防げる可能性があります。
レジリエンスに影響し、ストレス耐性を育むといわれるのは、周囲の人との関係です。
子どもを支える関係としてまず重要なのは、親子や家族の適切な関係性です。しかし、親との関係に恵まれない場合でも、子どもを取り巻く大人たちのかかわりによって子どもの人生は大きく変わります。家族、親戚、近所の人、保育士、教師など、周囲の大人が子どもを心配し積極的にサポートしてくれることも、子どもの回復力を助けます。
自分を理解しどんな時も支えてくれると思える関係を周囲の大人と築くことが、子どもがレジリエンスを発揮し苦境を乗り切る力を支えるのです。
Aさんの場合、信頼できる大人に気持ちを話す経験や、少しずつ学校生活に再挑戦する体験を重ねることで「自分にもできる」という感覚が育ちました。これがレジリエンスを高め、再び不安に直面したときの支えになっています。
トラウマについてのトピック
子どものトラウマについてのよくある質問
子どものトラウマとは、幼少期に経験した強い心的外傷やストレスが心身に与える影響を指します。これには虐待、暴力、事故、災害、家庭の問題などが含まれます。トラウマの影響は、子どもの発達や行動に深刻な影響を与えることがあり、時には大人になってからも心に残ります。トラウマのある子どもは、感情のコントロールが難しく、対人関係や学校生活に支障をきたすこともあります。早期の介入が重要です。
子どものトラウマの主な原因は、身体的・精神的虐待、家庭内暴力、親の離婚や死別、重大な事故や災害、いじめなどです。これらの出来事は、子どもに強いストレスを与え、心理的な影響を長期的に残すことがあります。子どもはまだ感情や状況をうまく理解できないため、恐怖や不安を適切に表現することができず、その結果、内面的な傷を抱えることになります。
子どものトラウマによる症状には様々なものがありますが、主に次のような特徴が見られます:
- 情緒的な不安定さ:突然の泣き出しやイライラ、怒りの爆発など
- 不安や恐怖:夜間の怖い夢やフラッシュバック
- 社会的孤立:友達と遊ぶことができない、学校へ行きたがらない
- 身体的な不調:頭痛や腹痛、寝汗をかくなど
- 自傷行為:自分を傷つけたり、引きこもったりする場合もあります。
これらの症状が続く場合は、専門的な支援が必要です。
子どものトラウマは、心理士や精神科医、カウンセラーによる面接や観察を通じて診断されます。診断には、子どもがどのような出来事に直面したか、そしてその出来事がどのように心に影響を与えているかを評価します。さらに、標準化された心理テストや質問票を使用することで、トラウマが子どもの行動や感情にどのように影響しているのかを詳しく調べます。早期の診断が重要であり、適切な治療に繋がります。
子どものトラウマの治療方法にはいくつかのアプローチがあります。まず、心理療法が広く用いられます。特にトラウマに特化した療法として、遊戯療法や認知行動療法(CBT)があります。これらの療法は、子どもが自分の感情を表現し、過去の辛い記憶に向き合う手助けをします。また、家族療法も重要です。親や兄弟姉妹との関係を強化し、家庭内でのサポート体制を整えることが治療に大きな効果をもたらします。
子どものトラウマを予防するためには、子どもに安心感と安全な環境を提供することが最も重要です。家庭内での暴力や虐待を防ぎ、愛情と安定した育成を心掛けましょう。また、子どもが自分の感情を表現できるよう、オープンなコミュニケーションを促進することも有効です。ストレスの少ない環境を作り、子どもが心地よく過ごせるように配慮することで、トラウマを防ぐことができます。
子どもの頃のトラウマは成人後にも大きな影響を及ぼします。特に、過去のトラウマが原因でうつ病や不安障害、PTSDなどの精神的な問題が引き起こされることがあります。また、人間関係においても、信頼関係を築くことが難しくなることがあります。身体的には、慢性的な痛みや免疫系の問題などが現れる場合があります。早期に適切な治療を受けることで、これらの影響を軽減することが可能です。
子どものトラウマに対する支援は、専門のカウンセリング機関や病院で受けることができます。例えば、精神科クリニックや心理療法を提供している施設で専門的な治療を受けることができます。学校や地域の福祉機関でも支援を提供している場合があります。また、オンラインのカウンセリングサービスもあり、アクセスしやすい環境が整っています。早期に支援を受けることが回復への第一歩となります。
子どものトラウマに関する最新の研究では、トラウマが子どもの脳の発達に与える影響について多くの知見が得られています。特に、慢性的なストレスや恐怖が脳の構造や機能に変化を与え、将来的な精神的健康に悪影響を及ぼすことが明らかになっています。また、早期の介入が効果的であり、治療法としてはトラウマに特化したカウンセリングや、家族療法が重要であるという研究結果があります。
子どものトラウマに関連する法律や支援制度としては、児童虐待防止法や子ども家庭支援法があり、これらの法律は子どもを守るために制定されています。また、行政や福祉機関では、トラウマを抱える子どもへの支援プログラムが提供されており、心理的なサポートや家庭支援が行われています。地域の支援制度や専門家による支援を受けることができます。
子どものトラウマについて相談する、カウンセリングを受ける
子どものトラウマについて、トラウマ反応やきっかけとなる出来事、回復や予防に必要な対応を説明しました。
トラウマをもつ子どもの症状は深刻ですが、信頼できる支援者がおり、日々過ごす環境が安心できるところになれば、子どもの回復に向かう力は発揮されていきます。子どものトラウマの心理的な支援を検討する際は、是非カウンセリングもご検討ください。
当オフィスでも相談やカウンセリングを受け付けています。希望者は以下のページからお申し込みください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。