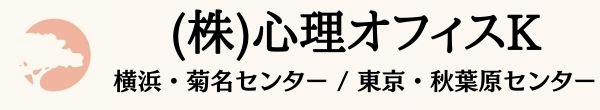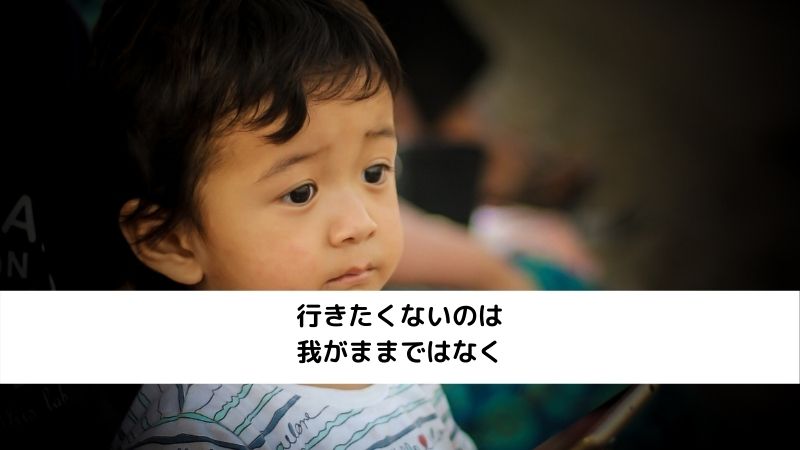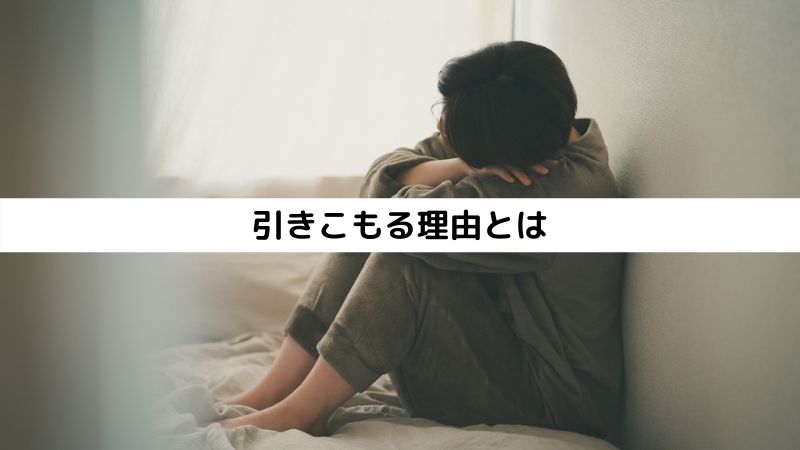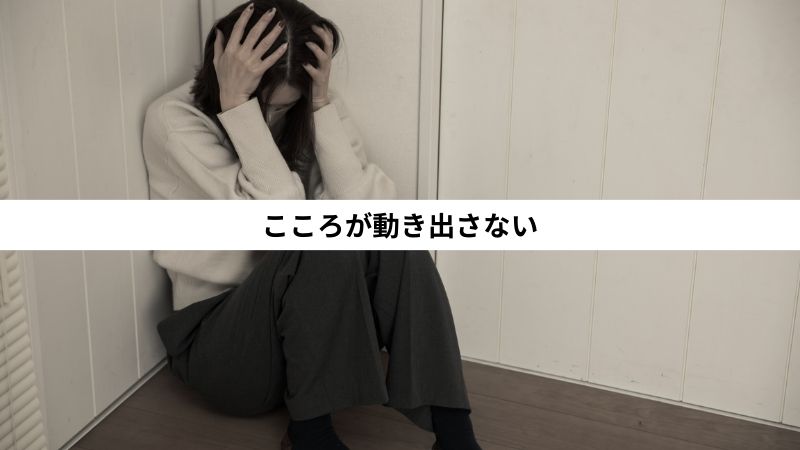不定愁訴とは一体何か?カウンセラーが解説するメカニズム
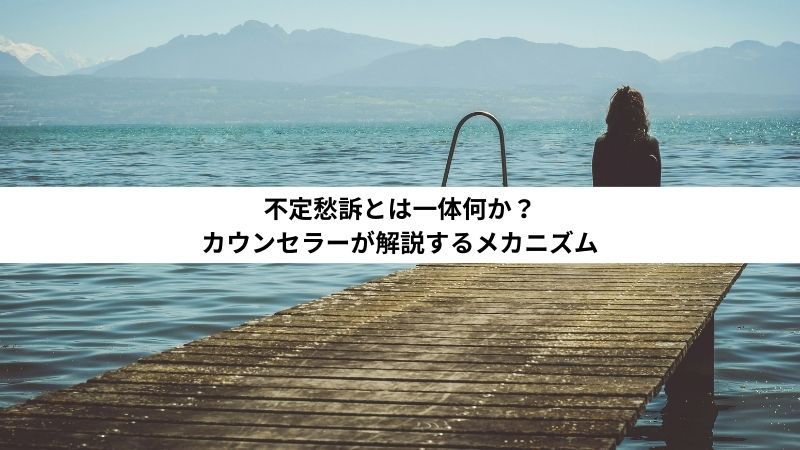
不定愁訴は、医療者が治療期間を決めてしまい作ってしまった医療者都合の用語で、ネガティブな印象がつきまといます。保険診療においては、愁訴の重症感と治療内容に応じて診断や治療の期間を決めてしまっていることが多いです。そこから外れると患者の卑屈コンプレックスも相まって、身体・精神症状が遷延化をきたし、慢性の経過をたどることが一般的です。
メカニズムを理解しそのプロセスに関してセルフチェックを行うことで、環境要因の調整など、楽になる症状は存在します。是非この記事を最後まで丁寧にご拝読いただき、楽になる訴えが少しでも減ることを願っています。
目次
不定愁訴とは
 不定愁訴とは、検査をしても明確な原因や異常が見当たらないにも医学的に説明が困難な身体的症状、精神的症状などを指します。多くの場合患者の苦しみをサポートするだけの診療が提供できないことが多く、ドクターショッピングや慢性化につながっています。身体のバランスが崩れ発生することが多いので、本邦の臓器別に細分化された現在の医療体制の苦手とされる分野ともいえ、複雑化したものへは特に心理療法や東洋医学の考え方の方が愁訴の軽快に結びつきやすいようです。
不定愁訴とは、検査をしても明確な原因や異常が見当たらないにも医学的に説明が困難な身体的症状、精神的症状などを指します。多くの場合患者の苦しみをサポートするだけの診療が提供できないことが多く、ドクターショッピングや慢性化につながっています。身体のバランスが崩れ発生することが多いので、本邦の臓器別に細分化された現在の医療体制の苦手とされる分野ともいえ、複雑化したものへは特に心理療法や東洋医学の考え方の方が愁訴の軽快に結びつきやすいようです。
不定愁訴という言葉ができた経緯としては、1963年11月に出稿の第一製薬(現在の第一三共ヘルスケア)が販売した薬剤のキャッチコピーに使用された用語が語源となり1964年に流行語となり、現代でも慢性化かつ難治性でネガティブな印象の言葉として広く知られています。
よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 女性
Aさんは40歳代の女性です。小さい頃から、家族の期待に応えようと一生懸命努力するタイプで、特に母親から「もっと頑張らないといけない」と言われることが多かったそうです。そのため、自分の気持ちよりも周囲の目や評価を優先しがちで、友人や家族との関係も「波風を立てないように」と気を使って生きてきました。社会人になってからも職場で責任感が強く、誰よりも遅くまで働き、家でも家事や育児に手を抜かずに頑張ってきました。
40歳を過ぎた頃から、Aさんは体のあちこちに不調を感じるようになりました。頭痛や肩こり、めまい、動悸、倦怠感など、さまざまな症状が日替わりで現れますが、検査をしても異常は見つかりませんでした。何度も内科や整形外科、耳鼻科を受診しましたが、「特に異常はありません」「ストレスでしょう」と言われるばかりで、Aさん自身もどうすればいいのか分からず、不安ばかりが募っていきました。やがて、朝起きることや仕事に行くことすらつらくなり、気分も落ち込みがちになっていきました。
そんなとき、職場の同僚から「カウンセリングを受けてみたら」と勧められ、半信半疑ながら申し込みを決意しました。初めてのカウンセリングでは、これまでの生い立ちや家族との関係、現在の生活状況について丁寧に話を聞いてもらいました。「ずっと自分を押し殺して頑張ってきたのかもしれない」とカウンセラーから言われ、初めて自分の気持ちに気づいたAさんは、自然と涙がこぼれました。
カウンセリングを重ねる中で、Aさんは自分がこれまで抱えてきた「自分はもっと頑張らなければならない」「弱音を吐いてはいけない」という思い込みに気づき、それを少しずつ手放すことができるようになりました。また、日常の中で自分の感情や体調に目を向け、無理をしすぎない工夫を取り入れていくことも始めました。職場や家庭でも、「できないことはできない」と言葉にできるようになり、家族にも自分の気持ちを伝えることが増えていきました。
こうした変化が積み重なり、以前のように強い不調を感じることが減っていきました。今も時折不調はありますが、「自分の体や心を大切にする」という新しい生き方を意識できるようになり、Aさんは少しずつ本来の自分を取り戻しつつあります。
不定愁訴になってしまう原因
 不定愁訴は、多くの場合ストレスによる自律神経の異常により現れる身体的症状です。その他にホルモンのバランスや生活習慣の乱れが原因と言われています。身体の弱っている部位に症状が出現することが多く、全身倦怠感、頭痛、腹痛、便秘、冷え、むくみなどが主体です。
不定愁訴は、多くの場合ストレスによる自律神経の異常により現れる身体的症状です。その他にホルモンのバランスや生活習慣の乱れが原因と言われています。身体の弱っている部位に症状が出現することが多く、全身倦怠感、頭痛、腹痛、便秘、冷え、むくみなどが主体です。
(1)幼少期からの性格
幼少期から「人に迷惑をかけてはいけない」「期待に応えなければならない」といった価値観を強く持つ人は、無意識のうちに自分の感情や欲求を抑え込みやすくなります。このような性格傾向があると、ストレスを自分の中にため込みやすく、心身に負担がかかります。結果として、心の疲れや葛藤が身体的な不調として現れやすくなり、不定愁訴につながることがあります。子どものころからの性格や家庭環境が、長期的に影響を及ぼすことも少なくありません。
Aさんの場合、幼少期から「家族の期待に応えなければならない」「弱音を吐いてはいけない」という価値観を持ち、自分の感情や欲求を抑えてきました。そのため、心の緊張や葛藤を無意識にため込む傾向があり、それが長い年月をかけて心身の負担となっていきました。
(2)日常的なストレス
職場や家庭、人間関係など、日々の生活の中で感じるストレスは不定愁訴を引き起こす大きな要因です。例えば、仕事でのプレッシャー、家事や育児の負担、夫婦関係や親子関係の悩みなどが積み重なることで、心身の緊張が続きます。こうしたストレスが長期化すると、心の疲労だけでなく、体のだるさや痛み、睡眠障害など、さまざまな身体症状となって現れることがあります。ストレスの種類や強さ、解消できる機会の有無が大きく関わります。
Aさんは社会人になってからも、仕事での責任や家庭での役割を真面目に果たそうと努力を重ねていました。人間関係や家事、育児など日常的なストレスが積み重なり、リラックスする時間がほとんど持てない生活が続いていました。こうしたストレスが心身に影響を与え、不定愁訴の症状を引き起こしていました。
(3)ホルモンバランス
特に女性の場合、月経や更年期などホルモンバランスの変動が体調や精神状態に大きく影響します。ホルモンの変動によって自律神経が乱れやすくなり、頭痛やめまい、イライラ、不安感などの症状が出やすくなります。ホルモンバランスの乱れは、年齢や体調だけでなく、ストレスや生活習慣によっても影響を受けます。そのため、原因が分かりにくい不定愁訴の背景には、ホルモンの変化が隠れていることも少なくありません。
Aさんの場合、40歳を過ぎた頃から月経の不調や更年期に関連する体調の変化を自覚するようになりました。ホルモンバランスの乱れによって、めまいや頭痛、気分の浮き沈みなどが強くなり、日常生活にも影響が出ていました。
(4)生活習慣
睡眠不足や偏った食生活、運動不足など、不規則な生活習慣は不定愁訴を悪化させる要因となります。例えば、夜更かしや不規則な睡眠リズム、過度なカフェインやアルコールの摂取、バランスの悪い食事などは、自律神経のバランスを崩しやすく、心身の不調を招きます。反対に、生活習慣を整えることで、徐々に症状が改善するケースも多いため、日々の習慣を見直すことは予防・改善の第一歩となります。
Aさんは忙しさから睡眠時間が不規則になり、食事も簡単に済ませることが多くなっていました。運動不足も重なり、健康的な生活リズムが崩れがちでした。こうした生活習慣の乱れが自律神経に負担をかけ、不定愁訴を悪化させていました。
(5)自律神経の乱れ
自律神経は、心身のバランスを保つために非常に重要な働きをしていますが、過度なストレスや生活リズムの乱れ、ホルモンの変動などによって、そのバランスが崩れることがあります。自律神経が乱れると、心臓や消化器官、呼吸などの働きにも影響が出やすく、頭痛や動悸、胃腸の不調、冷えや発汗など多様な症状が現れます。不定愁訴はこうした自律神経の不調が背景にあることが多く、バランスを整えることが症状改善のポイントになります。
Aさんの場合、慢性的なストレスやホルモンバランスの変化、不規則な生活習慣が重なり、自律神経のバランスが崩れやすくなっていました。その結果、動悸やめまい、消化不良、肩こり、頭痛など、多彩な身体症状が現れるようになりました。
不定愁訴の特徴や症状
 不定愁訴の特徴として、初発は「自覚する身体の違和感」です。症状として、身体の一部もしくは複数部位を訴え、入れ替わることもあります。周囲から理解を得にくいことから精神面にも不調をきたすことも少なくなくありません。詐病と捉えられることもありますが、自覚症状があれば、対処してくれるサポートを受けるか乗り越えるかが必要になります。
不定愁訴の特徴として、初発は「自覚する身体の違和感」です。症状として、身体の一部もしくは複数部位を訴え、入れ替わることもあります。周囲から理解を得にくいことから精神面にも不調をきたすことも少なくなくありません。詐病と捉えられることもありますが、自覚症状があれば、対処してくれるサポートを受けるか乗り越えるかが必要になります。
(1)身体症状
患者からの症状としては、「首や肩の痛み」「喉が詰まる感じ」「頭が重い」「疲労感が取れない」「胃や腸がむかむかする」「イライラして人に当たってしまう」「冷えやのぼせ」「動悸や発汗」など、主観的な訴えが多岐に渡ることが多いです。
その人の身体の弱い部位に愁訴が出ることが多く、身体の一部位の不調が、日常生活に何らかの支障につながっているケースが多く見られます。
Aさんは、頭痛や肩こり、めまい、動悸、全身のだるさなど、日によって変わる多様な身体症状を訴えていました。
(2)精神症状
「熟眠感がない」「集中力が出ない」「不安を感じて落ち込む」「なんとなく活動に意欲的になれない」「思考や感情の面で止まってしまい、行動に移せない」などストレスのせいで睡眠障害や抑うつ状態で、日中の活動などに支障が出ている方が多いです。
本人ももどかしい気持ちがあることも多いですが、抑うつ状態や気分により行動がついてこず、獲得していたものを失うことで本人や周囲から心配されて医療機関を訪れる方も多いです。
Aさんの場合、不安感や気分の落ち込み、イライラ、物事に集中できないなどの精神症状もみられました。
(3)分類の難しい不定愁訴と考え方
分類の難しい不定愁訴として、疾病利得がある場合の「詐病」があります。腰痛があるのに人が見ていないところに限り支障なく歩いている、消化器に不調があるのに消化の悪いものを好んで多量に食べるなどです。原因と結果の解釈や、症状出現のタイミング、辛さの感じ方に個人差があることなどから、判断が非常に難しいです。
しかし、原則医療者は、疾病利得や詐病という考えはしないことになっており、愁訴の長期化や複雑化の要因になっており、生活保護などの社会保障の部分も関係し社会問題となっています。
Aさんの症状は、医学的な検査では異常が見つからず、明確な診断名がつかないことが多かったため、「どこが悪いのか分からない」という不安や戸惑いが強くなっていました。
不定愁訴に対する対処と対応
 不定愁訴に対する対処は、「できるだけ話を傾聴する」「医療機関につなげること」「症状が長期化する場合には、症状があっても実現可能な行動にスポットを当て継続できるような工夫をする」ことが大切です。
不定愁訴に対する対処は、「できるだけ話を傾聴する」「医療機関につなげること」「症状が長期化する場合には、症状があっても実現可能な行動にスポットを当て継続できるような工夫をする」ことが大切です。
(1)セルフケア
セルフケアとして、自律神経のバランスを整える工夫を取り入れてみましょう。全て取り組まなくとも、自分に合った方法が見つかるでしょう。
- 食事を3食バランスの良いものを食べること。
- 睡眠と起床の時間をおおよそ決めて一定にすること。
- 適度な運動やストレッチングを日常生活に組み入れる。
- 生活環境の換気を適切に行うこと。
- ストレスを感じやすくする思考や習慣を意識して変えること。
- 過去は未来へのステップという考えを持つ。
- 人間関係の悪い人がいたとしても、相性の合う人とだけ接する。
- 飲酒や喫煙などの嗜好品を適度か、断ち切る。
- 目標を掲げ、ストレスになることを考える時間的・精神的余裕をなくすようにする。
- 吐く息を長くする呼吸法や瞑想を日常生活に取り入れる。
- ストレスの原因を探り対策をねることの習慣づけ。
不定愁訴の原因ははっきりとはわかっていないものの、多くは何らかの原因で身体や精神がストレスを感じ免疫力を低下させ、自律神経の乱れさせることにつながり起こる身体的愁訴であることが知られています。
発疹が出ているので不定愁訴ではありませんが、メカニズムが近いものとして帯状疱疹や口内炎があり、これらは免疫力が低下している一つのサインになります。症状が出るとわかりやすいので、医療機関でも対処してもらえますが、不定愁訴は症状の強さに波があり、部位も変わることもあるため介入が難しい側面があります。
どういった場面で身体に不調が出やすく、自分がストレスを感じて身体に不調をきたすかを知る一つのサインを把握する習慣づけましょう。
Aさんは、カウンセリングを通して自分の気持ちや体調に注意を向ける習慣を身につけ、無理をしすぎず休息を取ることや、リラックスできる時間を意識して過ごすよう心がけるようになりました。
(2)医学的介入(診断や治療について)
まずは、訴えのある身体部位に器質的な異常がないか、身体所見・採血・レントゲン撮影・超音波検査・C T検査・M R I撮影など、症状や訴えなどに応じて必要な検査を行います。
器質的な異常が認められない場合は、身体表現性障害や心身症やうつ病などの診断名が付くことが多いです。治療には、薬物療法・精神科的な介入が必要かの検討が行われることが多いです。自律神経失調症の場合には、漢方薬の処方などが臨床の現場では多く用いられ、頻度は低いですが、自殺企図や物質依存や過去のトラウマとの症状の関連性をさらに詳しく問診することがあります。
本来は医療者側の立場としては、不定愁訴や詐病と解釈してはいけず、解決するまで寄り添うのが正しい姿です。
Aさんは、何度も内科や整形外科などを受診しましたが、特に大きな異常は見つかりませんでした。医師からは「ストレスによるもの」と言われ、必要に応じて漢方薬や軽い安定剤が処方されることもありました。
(3)カウンセリングや心理療法
不定愁訴の一部には、介入方法と時制など医学的な治療から何らかの形でもれた方が一定の割合でいて、カウンセリングで楽になるケースもあり、両方のサポートを併用することも解決に向かう早道かもしれません。諦めない気持ち、粘り強く少しでも効果が見られたら継続することが大切になります。
2~3ヶ月のタイミングで不定愁訴は慢性化し脳の器質的な変化をきたし難治性になり、多くの医療機関では煙たがられる傾向にあります。「傾聴」と「自己の意識の核に眠っているものを引き出すアプローチ」によって少しずつではありますが、改善されてくることでしょう。
長期化することで、医療のサポートよりも心理療法の方が、効果があることも少なくありません。
Aさんの場合、カウンセリングでは、これまで抑えてきた感情や思い込みに気づき、少しずつ自分のペースで生活することを学んでいきました。その結果、徐々に症状が軽減し、前向きな気持ちを取り戻すことができました。
不定愁訴のセルフチェック
 不定愁訴のセルフチェックには、「自律神経失調症」「ストレスを溜めやすい性格」「ホルモンバランスの異常を来しやすさ」「疲労蓄積度合い」などの項目が自分に当てはまらないか確認することが大切です。
不定愁訴のセルフチェックには、「自律神経失調症」「ストレスを溜めやすい性格」「ホルモンバランスの異常を来しやすさ」「疲労蓄積度合い」などの項目が自分に当てはまらないか確認することが大切です。
簡単に述べますと食事・運動・睡眠ですが、近年「没頭できる趣味があるかどうか?」「ストレスなく付き合える仲間の存在があるか?」なども注目されており、その日から意識することによって変化させることができるものと、準備を要するものと両方揃った方が、不定愁訴を感じにくいことが注目されています。
Aさんは、カウンセラーの助言で、「自分の体調や気分の変化を記録するセルフチェック」を始めました。日々の小さな不調や心の動きを振り返ることで、自分の状態を客観的に見つめる力がついていきました。
不定愁訴についてのよくある質問
不定愁訴とは、明確な病名や検査結果が見つからないものの、体調不良を訴える症状が現れる状態のことを指します。この状態では、患者は頭痛、倦怠感、めまい、胃の不調、睡眠障害、食欲不振などを感じますが、血液検査やX線、CTスキャンなどの通常の検査でその原因が確認できない場合が多いです。これは身体的な症状が強く現れ、本人が非常に苦しいと感じることが多い一方で、医学的には直接的な異常が確認されないため、診断がつかないことが特徴です。不定愁訴が続くと、日常生活にも支障をきたし、精神的なストレスや不安感が増すことがあります。
不定愁訴の原因は様々で、身体的な疾患や外部のストレスだけでなく、心理的な要因や生活習慣など複数の要素が関与していると考えられています。例えば、過労や睡眠不足、過度のストレスが蓄積されることによって、身体が疲れを感じやすくなり、それが不定愁訴として現れることがあります。また、家庭や職場での人間関係のトラブル、過去のトラウマや感情的な未解決の問題も、心身に負担をかけ、症状として現れることがあります。さらに、内臓機能の一時的な異常やホルモンバランスの乱れ、免疫系の不調などが関与している場合もあり、そのため症状が複雑で多岐にわたるのです。
不定愁訴に伴う症状は多様で、身体的なものから精神的なものまでさまざまです。主な身体的症状には、頭痛、めまい、疲労感、胃腸の不調、筋肉や関節の痛み、食欲不振、睡眠障害などがあります。これらの症状は個人差が大きく、ある人は一部の症状を頻繁に訴える一方で、別の人は全体的に軽度であったり、時には症状が不定期に現れたりします。精神的な症状としては、不安や緊張感、集中力の低下、抑うつ気分などが報告されることもあり、これらが身体的症状と相まって、日常生活に大きな影響を及ぼします。身体的な不調が続くことによって、仕事や家庭での役割が果たせなくなることもあるため、症状が改善しない場合には生活全体に困難をきたすことがあります。
不定愁訴の診断は、まず身体的な原因があるかどうかを確認するために徹底的な検査が行われます。血液検査や画像診断(X線、CTスキャンなど)、内臓のチェックを通じて、異常が確認されない場合には、不定愁訴として診断が下されることが多いです。しかし、単に身体的な原因がないことだけでは不定愁訴と診断されません。次に、心理的な評価が行われることがあります。患者が抱える心理的なストレスや過去のトラウマ、生活環境や仕事環境の影響が症状に関連しているかを確認するためです。また、専門的なカウンセリングや心理検査を通じて、ストレス管理の方法や生活習慣の改善が必要であるかが見極められます。このように、多角的なアプローチが診断には必要です。
不定愁訴の治療方法は、症状の改善を目指してさまざまなアプローチが取られます。まずは心理的な支援が重要です。カウンセリングや認知行動療法は、患者が抱えるストレスや感情的な問題を整理し、症状の軽減を図るのに効果的です。カウンセリングを通じて、患者は自分の思考や感情に気づき、現実的な解決策を見つけることができます。また、認知行動療法では、過剰な不安や負担を軽減するために、具体的な行動変容を促す技術が提供されます。加えて、生活習慣の改善が重要です。規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動などを取り入れることで、体調が整い、不定愁訴の症状も改善することが期待されます。ストレス管理のためのリラクゼーション法や趣味を持つことも、症状を緩和する手助けとなります。
不定愁訴と心の病気は密接に関係していることが多いです。特に、うつ病や不安障害、パニック障害などの精神的な疾患は、不定愁訴の原因となることがあります。精神的なストレスや不安が、身体にさまざまな症状として現れることがあり、これらの症状が不定愁訴として認識されることもあります。例えば、過度なストレスや抑うつ状態が身体的な不調を引き起こし、その結果、頭痛、胃腸の不調、倦怠感などの症状が現れることがあります。したがって、不定愁訴の治療においては、心理的な評価と治療が非常に重要であり、場合によっては精神的な病気が隠れていることを考慮して治療が行われます。
不定愁訴の予防には、まず生活習慣を見直すことが重要です。十分な睡眠を取ること、バランスの取れた食事を摂ること、定期的に運動することなどが基本的な予防策となります。特に、ストレスを避けることが大切です。仕事や家庭でのストレスをうまく管理するためには、適度な休息や趣味を取り入れることが効果的です。また、リラクゼーション法や深呼吸、瞑想などもストレス軽減に役立ちます。定期的に健康チェックを受け、身体的な問題を早期に発見することも予防につながります。さらに、感情的な負担を感じたときには、無理せずに誰かに相談することが大切です。
不定愁訴を放置すると、症状が慢性化する可能性があります。最初は軽度な症状であっても、放置することで症状が悪化し、日常生活に支障をきたすようになることがあります。また、症状が長期間続くことで精神的な健康にも悪影響を与え、うつ病や不安障害のような精神的な問題を引き起こすことがあります。さらに、身体的な問題がある場合、それが見過ごされることによって、根本的な原因が放置されることもあります。したがって、早期に治療を始めることで、症状の改善が早く、長期的な健康維持が可能となります。
不定愁訴の診断には時間がかかることがあります。これは、まず身体的な疾患がないことを確認するために多くの検査が行われることと、患者の心理状態や生活習慣に関連する要因を詳細に評価する必要があるためです。不定愁訴の症状は、身体的な疾患と重なることが多いため、まずはそれらを排除することが重要です。その後、心理的な要因を慎重に調査するため、患者の生活環境や過去の経験を深く掘り下げて確認することが求められます。このため、診断が下されるまでには時間がかかることがありますが、精密な診断が症状の正確な原因を特定するために重要です。
不定愁訴の治療期間は、患者の症状の重さや原因に応じて異なります。軽度な症状であれば数週間から数ヶ月程度で改善することもありますが、慢性的な場合や深刻なストレスが関与している場合は、数ヶ月から半年以上かかることもあります。治療は、心理的なカウンセリングや認知行動療法、生活習慣の改善などを組み合わせて行うことが多いため、根本的な改善を目指して長期間の治療が必要となることがあります。しかし、症状が改善し始めると、治療期間を短縮することができることもありますので、早期の治療が重要です。
不定愁訴のカウンセリングを受けたい
 不定愁訴の多くの原因は、「自律神経の乱れ」「ストレス」「不規則な生活習慣」であることが多いとされています。症状についても、身体症状や精神症状様々で、愁訴もタイミングによって変わることも少なくありません。解決に向けた取り組みも日々進歩しており、過去不定愁訴として知られていたものの対処が明らかになりつつあります。しかし時代とともに、愁訴も複雑化してきており、医学的介入・心理療法を含め様々な側面からのアプローチが必要になります。
不定愁訴の多くの原因は、「自律神経の乱れ」「ストレス」「不規則な生活習慣」であることが多いとされています。症状についても、身体症状や精神症状様々で、愁訴もタイミングによって変わることも少なくありません。解決に向けた取り組みも日々進歩しており、過去不定愁訴として知られていたものの対処が明らかになりつつあります。しかし時代とともに、愁訴も複雑化してきており、医学的介入・心理療法を含め様々な側面からのアプローチが必要になります。
ストレスなどが原因であれば、カウンセリングなどが効果を発揮することがあります。もしカウンセリングを受けてみたいという方がいらっしゃいましたら、下の申し込みフォームからお問い合わせください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。