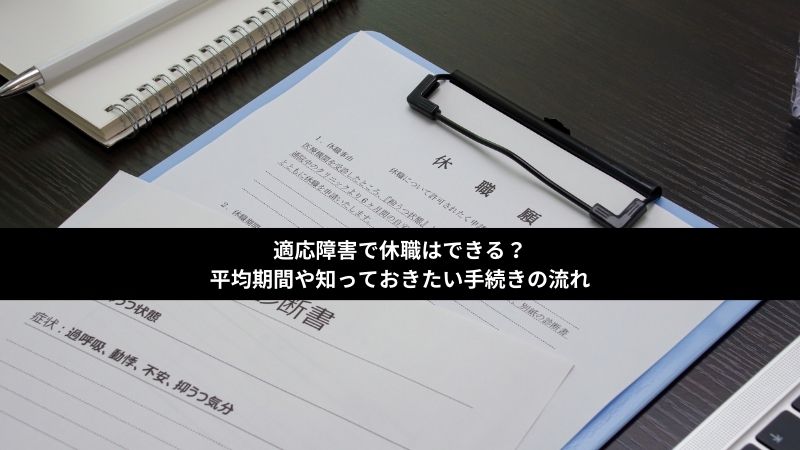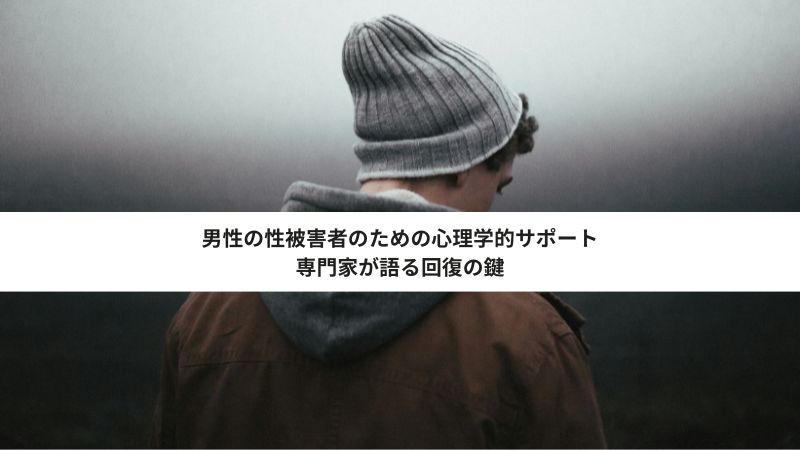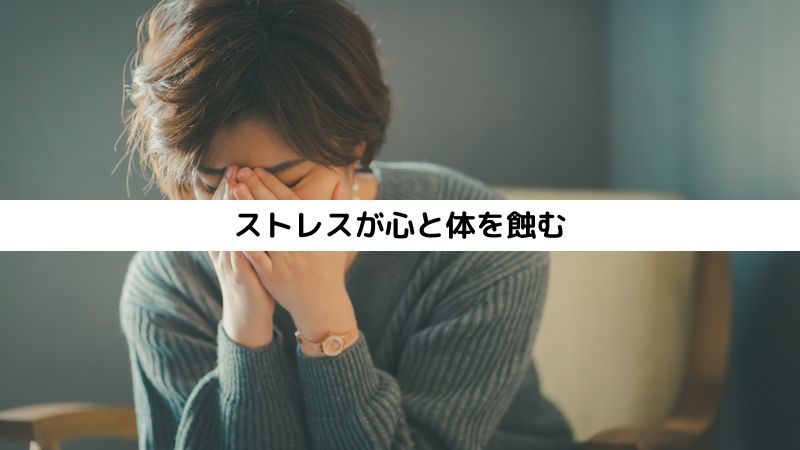複雑性悲嘆の心理学的探求:臨床心理士の視点から見たメカニズム
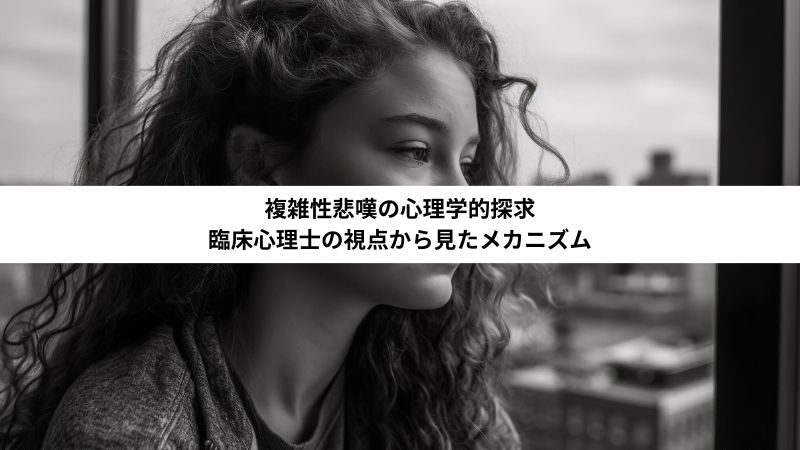
大切な人を亡くしたときには、深い悲しみを感じ、寂しさ、不安、やり場のない怒りなどさまざまな感情があらわれます。これは人間として自然な反応です。
大切な人を亡くしたときに精神面・身体面・行動面に起こる反応を「悲嘆」と呼びます。悲嘆が何らかの理由により緩和されることなく、長期にわたり継続し、生活に支障をきたす場合に「複雑性悲嘆」と区別され治療対象となるのです。
本記事では「複雑性悲嘆」の特徴や症状、治療方法について解説します。
目次
複雑性悲嘆とは
「悲嘆(grief)」とは、「強い結びつきがある誰か(あるいは何か)を『喪失』したことに伴う極めて強い感情状態」と定義づけられています。大切な人を失ったときに、悲嘆による反応が起きるのは人間として自然なことです。
ただし、悲嘆による反応が強すぎたり、反応による苦しさが持続する期間が長すぎたりする場合には「複雑性悲嘆(complicated grief)」と呼ばれ、治療の対象となります。
「複雑性悲嘆」とは、「悲嘆による反応の強さや持続期間が、文化において予想される範囲より過度であり、生活上の支障をきたしている状態」です。複雑性悲嘆の人は、大切な人を失ってから数年以上経過しても、大切な人を失った当時と同じくらいの悲嘆反応に苦しんでいる場合もあります。
よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 女性
Aさんは、幼少期から両親や兄弟と穏やかに暮らしてきました。学生時代には友人も多く、特に問題なく社会人となり、結婚を経て子どもにも恵まれました。しかし、数年前に最愛の母親を急な病気で亡くして以来、Aさんの心の状態は大きく変わりました。母親の死後、日常生活はなんとか維持できていたものの、悲しみや喪失感が強く、母親のことを考えて涙が止まらなくなったり、ふとした拍子に怒りや自責感が湧いてきたりしました。当初は「時間が経てば自然と元気になるだろう」と思っていたものの、半年以上経っても気分の落ち込みや不眠、集中力の低下が続き、家族や仕事にも支障をきたすようになっていきました。
次第にAさんは「どうして私だけがいつまでも悲しみに囚われているのだろう」と自分を責めるようになり、人付き合いも避けるようになりました。また、母親との関係が非常に密接だったため、「母の死を受け入れたら、母が本当にいなくなってしまう気がして怖い」という気持ちから、喪失を受け入れられずにいました。Aさんの状態を心配した夫や友人の勧めで心療内科を受診し、「複雑性悲嘆」と診断されました。医師からは抗うつ薬を処方され、睡眠や食事のリズムを整えることの大切さを指導されましたが、気持ちの整理にはなかなかつながらず、Aさん自身も「このままではいけない」と思い、心理カウンセリングを申し込むことになりました。
カウンセリングでは、Aさんが母親と過ごした日々や、母親に対して伝えられなかった思い、喪失後に抱えたさまざまな感情を丁寧に語り、少しずつ言葉にしていきました。カウンセラーはAさんの悲しみや罪悪感、怒りといった複雑な感情に寄り添い、「悲しみを抱えながらも自分らしい生活を取り戻していく」ことの大切さを共に考えました。回を重ねるごとに、Aさんは母親の存在を心の中に温かく感じながら、新しい日常を少しずつ受け入れられるようになっていきました。数カ月のカウンセリングを経て、Aさんは「悲しみは消えないけれど、それでも前を向いて生きていこう」と思えるようになり、徐々に生活の中に楽しみや人との交流も戻り始めています。
複雑性悲嘆の特徴や症状
ここでは、複雑性悲嘆の特徴や症状について解説します。
(1)複雑性悲嘆の特徴
複雑性悲嘆の特徴は、悲嘆の反応が強く現れる点と、持続期間が長い点です。一般的には6ヶ月以上、強い悲嘆の反応が続き日常生活に支障をきたします。
悲嘆の反応とはどういうものかも含め、複雑性悲嘆の症状について次の項で紹介します。
Aさんの場合、母親の死後も長期間にわたって強い喪失感や悲しみが続き、日常生活に大きな影響が出ていました。悲しみがなかなか癒えず、前向きな気持ちを持てなくなっていたことが特徴です。
(2)複雑性悲嘆の症状
悲嘆による反応には以下のようなものがあります。
| 反応の内容 | |
|---|---|
|
身体的反応 |
|
|
情動的反応 |
|
|
認知的反応 |
|
|
行動的反応 |
|
悲嘆による反応は、時間経過に伴い自然と回復するケースが多いです。
Kubler Rossの研究によると、悲嘆は以下のようなプロセスを経て回復するといわれています。
- 否認と孤独
- 怒り
- 交渉
- 抑うつ
- 受容
しかしすべてのケースにおいて、これらのプロセスを経て回復できるわけではありません。ある時期で停滞したり、逆戻りしたりすることもあります。一部の人は悲嘆から回復することができず、長い間苦しむことがあるのです。
複雑性悲嘆の症状は、上記のような悲嘆による反応が強く現れたり、長い期間にわたり持続したりするために、日常生活に支障をきたしている点が特徴であるといえるでしょう。
複雑性悲嘆は、QOLの低下、免疫力の低下、心疾患やがんのリスク増大、飲酒や喫煙の増加、自殺の増加の危険因子となっています。
Aさんは母親のことを考えて涙が止まらなくなることが頻繁にありました。また、眠れない日が続き、集中力も低下しました。加えて、母親を失ったことへの怒りや自責感も強く、孤独感や無力感が深まり、人間関係を避けるようになっていました。
(3)複雑性悲嘆になりやすい人の特徴
「私も複雑性悲嘆になってしまうかもしれない」と不安になる人もいらっしゃるかもしれません。複雑性悲嘆になる危険因子が明らかになっていますので、当てはまる人は長い期間1人で我慢せずに早めに専門家へ相談しましょう。
複雑性悲嘆の危険因子として、以下の内容があげられています。
| 要因 | 具体例 |
|---|---|
|
死別前の要因 |
|
|
死別関連要因 |
|
|
死別後の要因 |
|
上記に当てはまる数が多い、またはその傾向が強いなどの場合は、複雑性悲嘆になりやすい人であると考えてよいでしょう。
特に大切な人が死別関連要因にあるような亡くなり方をした場合には、それ以外の亡くなり方の場合より心に大きなダメージを受け、PTSDを併発するケースもあるほどです。死別後の要因にあるように、サポートが少ないことも危険因子の一つとなります。
上記のような危険因子がある人の場合には、専門家などによるサポートを受けるほうが安心です。
Aさんのように亡くなった方との関係が非常に密接だった人や、喪失体験を受け入れがたい状況にある人は、複雑性悲嘆になりやすい傾向があります。Aさんも「母の死を受け入れたら、本当にいなくなる気がして怖い」と感じていました。
複雑性悲嘆の診断や鑑別
複雑性悲嘆の診断や似たような病気との鑑別について解説します。特に通常の悲嘆、うつ病、PTSDとの違いについて取りあげます。
(1)複雑性悲嘆の診断基準
以前は複雑性悲嘆に相当する診断名は存在せず、研究者により「複雑性悲嘆」「遷延性悲嘆」「外傷性悲嘆」「病的悲嘆」などさまざまな名称で呼ばれていました。現在ではICD-11やDSM-5に複雑性悲嘆が精神障害として位置付けられるようになりました。
ICD-11では、複雑性悲嘆の診断基準について「遷延性悲嘆症」という診断名で以下のように記されています。
遷延性悲嘆症(Prolonged grief disorder:PDG )
- パートナーや親、子ども、その他にも親しい人を喪ったあとにあらわれる障害である
- 故人への嘆き求めと持続的な故人へのとらわれを中心とした持続的で広範な悲嘆反応を示す
- 悲嘆反応は、強い情動的苦痛(例えば:悲しみ、罪悪感、怒り、否認、非難、死を受け入れることの困難、自分の一部が失われたような感覚、肯定的感情の体験ができない、情動麻痺、社会やその他の活動に参加することの困難)を伴う
- 症状の持続期間は、死別から最低6ヶ月持続している
- 症状の持続期間や反応は明らかにその人の所属している社会や文化、宗教的背景において正常とみなされる状態より過剰である
- この症状の存在によって、その人の個人、家族、社会、学業、就労、その他の重要な側面で重篤な機能障害が引き起こされている
DSM-5では「心的外傷およびストレス因関連障害群-他の特定されるストレス因関連障害」の中に「持続性複雑死別障害(Persistent complex bereavement disorder)」として掲げられています。
「持続する悲嘆のうち死に反応した苦痛、社会性/同一性の混乱が存在し、そのような状態が12ヶ月(子どもの場合は6ヶ月)続いた病態」を「持続性複雑死別障害」としています。このように、悲嘆による反応が強くあらわれている点と大切な人を失ったあと6ヶ月以上(もしくは12ヶ月以上)持続している点が特徴です。
さらにこれらの症状により日常生活に支障をきたしている点も診断基準に盛り込まれています。
これらの基準を満たさず、日常生活に支障をきたすほどではない場合や時間経過と共に回復していく場合は、自然な悲嘆反応であると考えてよいでしょう。
Aさんの場合、半年以上にわたり強い悲しみや喪失感、社会的な機能の低下が続いていたことから、医師によって「複雑性悲嘆」と診断されました。これは、単なる一時的な悲しみや通常のグリーフとは異なります。
(2)うつ病やPTSDとの違い
複雑性悲嘆と似たような心の病気に「うつ病」と「PTSD」があります。これらとの違いについて解説します。
まず、うつ病と複雑性悲嘆との違いを以下の表に示しました。
| 具体例 | |
|---|---|
|
類似点 |
|
|
異なる点 |
|
うつ病と複雑性悲嘆は、あらわれる症状は似ています。しかし、複雑性悲嘆の場合は故人に関連して症状があらわれるのに対し、うつ病の場合は特定の出来事などに結びつかない点で異なります。
うつ病と複雑性悲嘆は別の病気です。ただし、複雑性悲嘆の人がうつ病を併発することもあるため鑑別が難しいともいわれています。
複雑性悲嘆とPTSDにおいても、複雑性悲嘆では故人への思慕や切望感と関連があるかどうかが大きな違いです。
複雑性悲嘆では故人への思慕や切望感、分離不安などが主ですが、PTSDではトラウマ場面との関連が強く故人への思慕や切望感とは無関係である点が特徴です。
ただし、事故や事件などで大切な人を亡くした場合や亡くなった場面を目撃した場合などは、複雑性悲嘆にPTSDを合併しやすいといわれています。
Aさんは抑うつ的な気分や不眠も経験していましたが、中心にあるのは「亡くなった母親への執着した思い」や「喪失の痛み」でした。うつ病やPTSDは似た症状もありますが、複雑性悲嘆は特に喪失体験に特化した症状が中心となる点が異なります。
複雑性悲嘆の治療
ここからは身近な人が複雑性悲嘆だった場合の接し方や複雑性悲嘆の治療について解説します。
(1)身近な人が複雑性悲嘆だった場合の接し方
身近な人が複雑性悲嘆だった場合、どのように接したらよいのか戸惑ってしまうかもしれません。前述の通り、複雑性悲嘆の人は悲嘆による症状に長期間苦しんでいるため、慎重に接する必要があります。
接し方のポイントは以下の通りです。
- その人が話したい内容を傾聴する(無理に死に直面させる必要はない)
- 故人が受けた治療や亡くなったときの状況を誤解している場合は心境に配慮して正しい情報を提供し誤解を解消するとよい場合がある
- 悲嘆についての説明をする
- 複雑性悲嘆が疑われる場合は専門家を紹介する
基本的にご本人の話したい内容をそのまま傾聴するスタンスがよいでしょう。故人が亡くなったときの状況などを誤解して自分を責めてしまうようなケースでは、可能な範囲で正しい情報を提供するのも大切です。
伝え方などに不安がある場合は、故人の主治医など専門家に協力してもらうのも一つの方法です。
悲嘆についての説明をする際には、以下の内容を伝えましょう。
- 大切な人を失った悲しみや悲嘆は自然な反応であること
- 悲しみを自分自身で抱えるのにはそれぞれに必要な時間がある。すぐにこの苦しみから抜け出すのは難しいこと
- 無理に感情表出を我慢することや、逆に無理に感情を表出しなくてよいこと
- 支援の場所があること
- 悲しみによる苦痛が生活に大きな影響を及ぼしている場合は支援を求める必要があること
複雑性悲嘆が疑われるような状態の場合には、医師やカウンセラーなどの専門家に相談するように促しましょう。
いきなり病院に行くのには抵抗を示す人が多いかもしれません。
まずはカウンセリングを受けてみるよう促すと、相談してみようと思ってもらいやすいものです。
Aさんの場合、夫や友人が無理に「元気を出して」と励ますのではなく、Aさんの気持ちに寄り添い、「つらいときは話していいんだよ」と受け止める姿勢で接したことが、回復の支えとなりました。
(2)複雑性悲嘆の人へのカウンセリングや認知行動療法
複雑性悲嘆の人へ有効な治療方法として、カウンセリングがあります。カウンセリングでは、主にクライエントの話をじっくりと聴きます。聴くだけなら専門家でなくてもよいのではないかと思われる人がいらっしゃるかもしれません。
しかし、専門家によるカウンセリングでは、認知行動療法などの専門的な心理療法を行ったり、複雑性悲嘆とはどういうものなのかという心理教育を行ったりする点が異なります。
複雑性悲嘆の人は、とても不安定で苦しい精神状態なのです。だからこそ、しっかりとした知識・経験のある専門家によるカウンセリングを受けたほうが安全でしょう。
複雑性悲嘆の治療方法としては、「日本版複雑性悲嘆治療:Japanese version of Complicated Grief Treatment, J-CGT」と「認知行動療法」が挙げられます。
J-CGTは武蔵野大学認知行動療法研究所における研究により開発されたもので、悲嘆反応や複雑性悲嘆の症状についてパンフレットやスライドを用いて説明する心理教育や、悲嘆のモニタリングを行う点が特徴的です。
治療のプロセスは以下の通りです。
- 導入
- 心理教育
- 個人的な目標の設定
- 重要な他者との面接
- 死の物語の再訪問
- 状況の再訪問
- スタックポイント(心のひっかかり)の同定と見直し
- 思い出フォーム
- 想像上の会話
- 治療の終結と治療後の対応についての話し合い
死に直面した状態やそのときの感情に向き合うプロセスでは、認知行動療法の手法が使われています。
認知行動療法の中でも、死に直面した状態やそのときの感情に向き合うことを意味する「曝露(ばくろ)」と呼ばれる技法が複雑性悲嘆の治療には効果的であるという研究結果が複数示されています。
研究結果は以下の通りです。
- Wagnerらの死に直面した状態やそのときの感情も含めて詳細に記載するという曝露の要素を含む認知行動療法は、複雑性悲嘆による症状の改善を示した
- Boelenらは、認知行動療法の中でも曝露と認知再構成の要素による効果の違いについて研究しており、曝露の要素が認知再構成より効果量が大きく、治療全体を通しても曝露を先に行うほうが効果的であると報告した
このように複雑性悲嘆の症状改善のためには、認知行動療法によるカウンセリングが効果的であるといってよいでしょう。
死に直面した体験に向き合うのはとても辛いことです。
直面する時期や方法については、カウンセリングを受ける人の状態に合わせて慎重に判断する必要があります。
そのため、カウンセラーを選ぶときには臨床心理士や公認心理師のような信頼できる資格を持ち、十分な経験を積んでいる人かどうかを見極める必要があるでしょう。
長期間にわたり複雑性悲嘆の症状に苦しむよりは、カウンセリングで専門的な治療に取り組んだほうが早く症状を軽くすることができるのです。
Aさんはカウンセリングを通して、母親への思いや未解決の感情を丁寧に言葉にし、少しずつ悲しみと向き合うことができるようになりました。カウンセリングでは、悲嘆のプロセスを支援し、現実的な生活の目標を持つことや、認知の偏りを修正していく取り組みも行われました。
複雑性悲嘆についてのよくある質問
複雑性悲嘆とは、大切な人を亡くした後に、その死に対する悲しみが長期間続き、普通の悲しみが癒える過程を越えて心に大きな影響を与える状態を指します。通常の悲しみは時間とともに和らぎ、日常生活に支障をきたさないことが多いですが、複雑性悲嘆ではその悲しみが長期的に続き、感情的な負担が重く、社会的な関わりや仕事、家事、日常的な活動ができなくなったり、生活全般に支障をきたすことがあります。また、亡くなった人を忘れることができず、日常的にその人のことを思い続けたり、死を受け入れることができずに何度もその死について考えてしまうことがあります。このような状態は、時間が経過しても改善せず、心的外傷を引き起こすことがあるため、適切な支援が必要です。
複雑性悲嘆の主な症状は、亡くなった人を頻繁に思い出し、そのことで情緒が不安定になり、生活全般に支障をきたすことです。具体的には、亡くなった人の死をどうしても受け入れられない、亡くなった人を強く恋しく思い、会いたいという感情が頻繁に湧き上がることがあります。また、亡くなった人の死後、その人との思い出や一緒に過ごした時間が頭から離れず、日常生活に支障をきたすこともあります。さらに、亡くなった人の死を心から信じられないという気持ちや、突然その人が戻ってくるのではないかという幻想が生まれることもあります。このような状態が長期にわたると、感情的に非常に消耗し、孤立感や無力感を感じることが多くなるため、早期に支援を受けることが重要です。
通常の悲しみと複雑性悲嘆の大きな違いは、悲しみの強さとその持続時間です。通常、悲しみは時間が経過するにつれて和らぎ、日常生活を続けることができるようになります。しかし、複雑性悲嘆では悲しみが長期間続き、その感情を解消できず、生活に支障をきたすことが多いです。通常の悲しみは、一定の期間内に感情が整理されていきますが、複雑性悲嘆の場合、喪失感が強く、心の中でその喪失を受け入れられずに長期間にわたり苦しみます。さらに、複雑性悲嘆は心身に対する負担が大きいため、心の健康や身体的な健康にも悪影響を及ぼすことがあります。通常の悲しみが過ぎ去ると新たな活動に取り組めるようになるのに対し、複雑性悲嘆は長期的な回復を必要とする場合が多いです。
複雑性悲嘆の原因は、個人の性格、過去のトラウマ的な経験、社会的なサポートの不足などが絡み合っています。特に、以前に大きな喪失経験を持っている人や、強い絆を感じていた人との別れは、悲しみを乗り越える過程をさらに難しくさせます。人々の感情的な回復力には個人差があり、悲しみをどのように処理するかは、その人の過去の経験や対処方法に大きく影響されます。また、社会的なサポートが欠如している場合、複雑性悲嘆が発生しやすく、友人や家族とのつながりが弱いと、悲しみを共有することができず、感情がこじれてしまうことがあります。さらに、複雑性悲嘆は、死後の変化や予測できない出来事に直面したことによっても引き起こされることがあります。
複雑性悲嘆の診断は、専門的な評価を受けることで行われます。精神的な問題や悲しみが長期にわたって続いている場合、精神科医や臨床心理士が、具体的な症状や症例に基づいて診断を行います。診断基準として、複雑性悲嘆質問票(ICG)などのスケールが使用されることがあります。これらのスケールは、喪失後の悲しみの強さや、その悲しみが日常生活にどれほど影響を与えているかを評価します。また、医師やカウンセラーが、悲しみの持続期間や感情のコントロール能力を詳しく聞き取る面接を行うこともあります。これにより、患者がどの程度深刻な悲しみを抱えているのか、どのような治療が適切かを見極めることができます。
複雑性悲嘆の治療方法には、認知行動療法や対人関係療法が効果的とされています。認知行動療法は、悲しみの感情や思考のパターンを見直し、現実的で適応的な考え方を促す方法です。対人関係療法は、喪失を乗り越える過程で、人間関係や社会的サポートを強化することを重視します。また、グリーフカウンセリングやグループ療法も有効な場合があります。これらの療法は、悲しみを適切に表現し、他者とのつながりを回復するための手段を提供します。さらに、薬物療法が必要とされることもあります。抗うつ薬や抗不安薬などを使って、症状を軽減し、悲しみを管理する手助けをすることがあります。ただし、薬物療法は、治療の一部として専門家の指導の下で行うことが重要です。
複雑性悲嘆の期間は、個人によって異なりますが、通常の悲しみが数ヶ月以内に回復するのに対して、複雑性悲嘆は数年にわたって続くことがあります。この長期化した悲しみのために、日常生活に支障をきたし、心身に悪影響を及ぼすことが多いです。特に、感情的な回復が進まず、亡くなった人を何度も思い出し、その死を受け入れられない場合、治療が長期にわたる可能性があります。支援を早期に受けることで、回復のスピードが早くなることがありますが、それでも完全に回復するまでには時間がかかることが一般的です。
治療しない場合、複雑性悲嘆は心理的および身体的な健康に長期的な悪影響を与える可能性があります。長期間にわたる悲しみや無力感が続くことで、うつ病や不安障害、睡眠障害が引き起こされることがあります。さらに、身体的な健康にも影響が及び、免疫力の低下や、心臓病や高血圧などの病気のリスクが高まる可能性もあります。社会的な孤立や仕事のパフォーマンス低下、家族や友人との関係の悪化も見られることがあります。最悪の場合、長期間放置されることで、自殺念慮や行動に繋がることもあるため、早期に専門的な支援を受けることが重要です。
複雑性悲嘆の予防には、まず社会的なサポートを積極的に求めることが重要です。家族や友人とのつながりを強化し、感情的な支えを得ることが助けになります。また、悲しみの感情をため込まず、表現することが予防に役立ちます。悲しみを外に出すことで、心の中に抱え込まずに済み、感情が解放されることがあります。さらに、専門的なカウンセリングやサポートグループに参加することも予防に効果的です。喪失の後に感じる感情を無理に抑えることなく、受け入れることで、悲しみの感情に向き合い、心の回復が進みます。
複雑性悲嘆のサポートを受けるには、まず専門的な心理療法を受けることが勧められます。心理カウンセラーや精神科医に相談し、自分の感情や状況に応じた治療法を見つけることが大切です。カウンセリングでは、悲しみを適切に表現し、感情を整理する方法を学ぶことができます。また、グリーフカウンセリングやグループセラピーに参加することも有効です。これらのサポートを通じて、自分の気持ちを他者と共有し、回復への道を見つけることができます。
複雑性悲嘆について相談したい
複雑性悲嘆の特徴や症状、治療方法について解説しました。
複雑性悲嘆の人は、医療機関を受診するケースが少ないといわれており、我慢している間に症状が悪化し、QOLの低下や心身の健康を損なうリスクが高まってしまいます。
大切な人を失ったあと6ヶ月以上悲嘆による反応が続いている場合は1人で我慢せずに専門家に相談しましょう。
身近な人が複雑性悲嘆かもしれないと心配な人は、まず本記事を参考にご本人の話を傾聴し、カウンセリングを勧めてみると安心です。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。