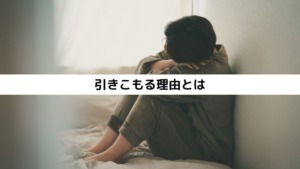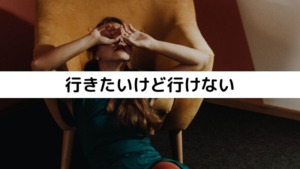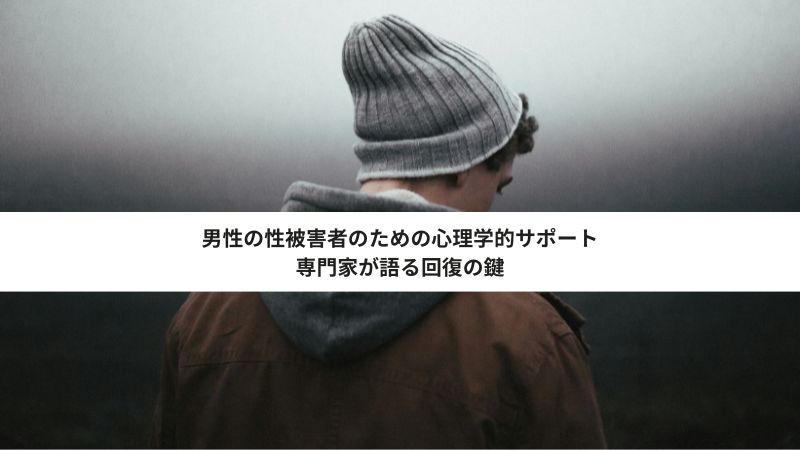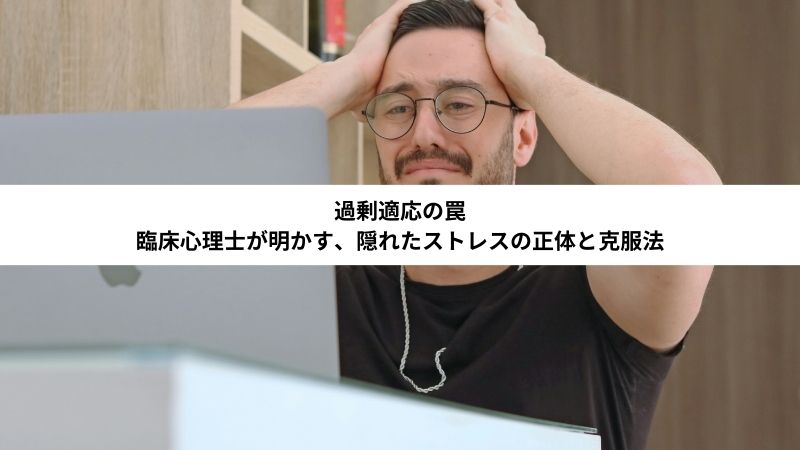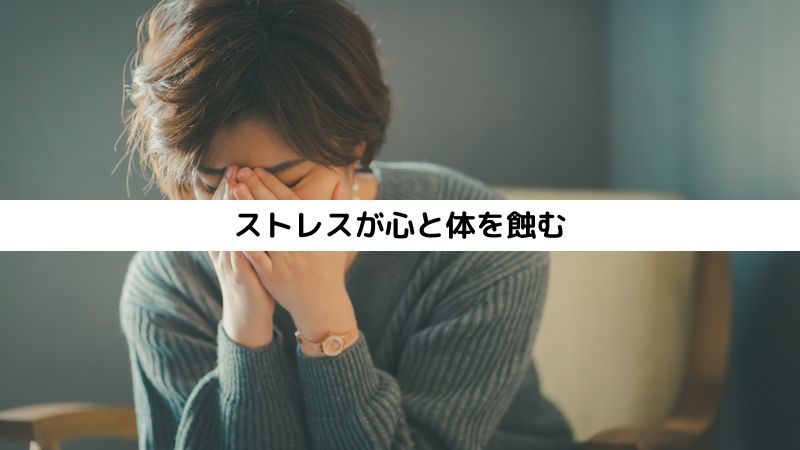引きこもりからの脱出と立ち直るきっかけ

私生活の不安や耐えがたい悩みなどにより、引きこもりになってしまう方は、全国にたくさんいます。しかし、その中には「今の状況から脱出したい」と思っている方も多いでしょう。
この記事では、引きこもりの現状を理解し、立ち直るためのきっかけや引きこもりから脱出できる方の特徴について紹介します。
引きこもりから立ち直るきっかけとは?

ここでは、引きこもりから立ち直ったきっかけについて紹介します。
(1)親との関係改善
引きこもりの状態から脱出させたい親の気持ちが大きすぎて、子どもを苦しめているケースもあります。また、親の価値観を子どもに押しつけていることで、子どもとの関係が悪化している場合もあります。
引きこもりから立ち直るためには、家族などの身近な人のサポートが必要です。子どもの引きこもりで悩んでいる場合は、子どもと話し合う時間を設け、子どもの気持ちや価値観を教えてもらうことが第一歩となるでしょう。
親の気持ちも理解できますが、子どもとの話し合いの際は、親の価値観を話したり押しつけたりしないでください。
(2)友人や周囲の変化
引きこもりをしている間に友人が結婚したり、子どもが生まれたりすることで、引きこもりから立ち直る方もいます。「周りの友人は変化しているのに自分はずっと同じ」という焦りをきっかけにしているのです。
その他にも、兄弟が一人暮らし始める、親が定年退職するなどの周囲の変化によって、引きこもりからの脱出を考える方もいます。
(3)第三者の支援
「話しかけるといつもケンカになる」「どのようにアプローチしたら良いのかわからない」という場合は、第三者に相談するのもおすすめです。家族の場合、どうしてもお互い感情的になってしまうこともあるでしょう。
カウンセラーや引きこもり支援スタッフなどの第三者であれば、家族を気にせず自分の正直な気持ちを打ち明けられるメリットがあります。引きこもりが長期化している場合や見守りを1年続けている場合は、第三者に相談してみると良いでしょう。
引きこもりについてのコラム
引きこもりについてのいくつかのトピックを紹介します。さらに詳しく引きこもりについて知りたい方はご覧ください。
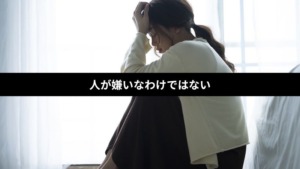
まとめ:カウンセリングを受けたい
引きこもり当事者だけの力で、立ち直るきっかけを作ることはなかなか難しいです。家族や第三者のサポートによって、引きこもりから脱出できる可能性は高まります。ただ、焦りは禁物です。まずは、引きこもり当事者が安心して話せる環境作りをするなど適切なサポートを提供するようにしましょう。
当オフィスでは、引きこもりケアの専門カウンセラーが在籍しております。ぜひお気軽にご相談ください。