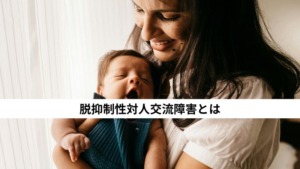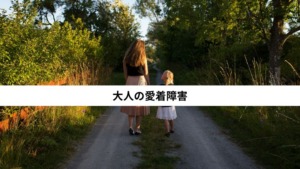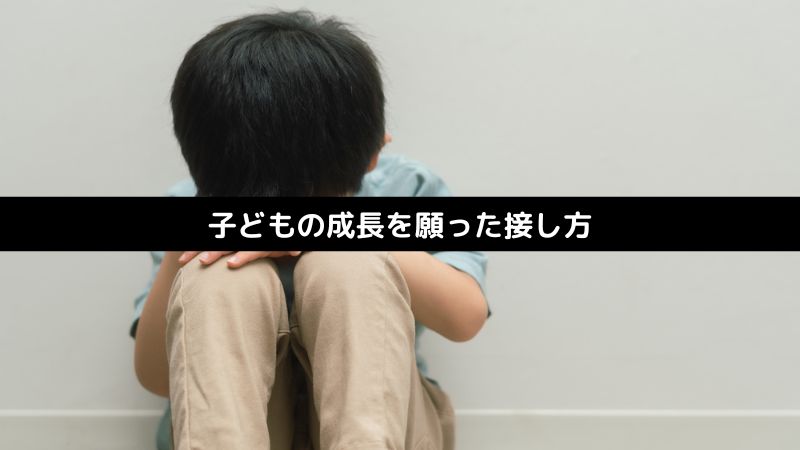愛情剥奪がもたらす不安と孤独:臨床心理士の説く克服方法とは?

愛情剥奪を受けることは、その後の人生にわたる心身の発達に影響を及ぼし、対人関係での困難や心身の不調につながりかねません。この記事では、愛情剥奪を受けた人の心理的問題や特徴とその支援について解説します。愛情剥奪についての相談には、カウンセリングもご検討ください。
目次
愛情剥奪とは
愛情剥奪は、もともと「母性的養育の喪失」「母性剥奪」などと呼ばれていた概念です。
イギリスの精神科医であるボウルビィ(Bowlby. J.)は、乳幼児と母親(あるいは、その役割を果たす人物)との親密かつ継続的で、お互いが満足と幸福感で満たされるような良好な関係がその後の人格形成や精神衛生のベースとなると考え、母子相互作用の重要性を説きました。
そして、人生早期にこの母子相互作用が欠如した状態を「母性的養育の喪失」「母性剥奪」(マターナル・デプリベーション)と呼び、長期間施設に預けられることによる早期の母性的養育の喪失は、精神発達の遅れや身体の成長の障害、非行など、心身の発達に重大な影響を及ぼすことを示唆しました。
しかし、当初は母親からの分離として用いられた「母性的養育の喪失」の用語や概念は、その後、見直されてきています。
施設で育つことは必ずしも悪いことではなく、家庭で不適切な養育を受け続けることや、先行する(喪失などの)経験、子どもの年齢や気質などの影響もあるため、さまざまな要因を検討し、個々のケースについて提供するケアの質を考える必要があると指摘されています。
こうしたことは愛着障害(アタッチメント障害)の原因になりかねません。愛着障害については以下のページをご覧ください。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは幼少期から家庭環境に恵まれず、両親は共働きで日中はほとんど家におらず、物理的にも心理的にも十分な愛情を感じることができないまま成長しました。母親は仕事と家事に追われ、Aさんとじっくり向き合う時間はほとんどありませんでした。父親も家庭内では無口で、感情的な交流が乏しかったとAさんは振り返ります。時折、両親の間で口論が絶えず、家の中に安心感や温かさを感じることが難しい環境でした。
思春期に入ると、Aさんは友人関係においてもなかなか心を開けず、自分は大切にされない存在なのではないかという孤独感を深めていきました。高校時代から不安感や抑うつ的な気分が強くなり、人間関係に極端な距離感や緊張を抱くようになりました。大学生になる頃には対人不安や自己評価の低さ、無気力感に苦しむようになり、睡眠障害や食欲不振といった身体的な不調も現れるようになりました。
社会人になってからも職場での人間関係がうまく築けず、上司や同僚との距離のとり方に悩み、何度も転職を繰り返すこととなりました。ある時期からパニック発作のような症状も現れるようになり、心療内科を受診したところ、「愛着障害」や「愛情剥奪」の影響が疑われると指摘されました。医師からは抗不安薬と抗うつ薬が処方され、一時的に症状は緩和したものの、根本的な孤独感や自己肯定感の低さは残りました。
薬物療法と並行して、Aさんはカウンセリングを受けることを決意しました。カウンセリング初期には、Aさん自身が感情をうまく表現できず、沈黙が続くことも多かったのですが、カウンセラーが根気強く受容的な態度で関わり続けたことで、次第にAさんの中に「ここでなら安心して話しても大丈夫」という感覚が芽生えました。セッションを重ねる中で、Aさんは自分が幼少期にどれほど愛情に飢えていたか、誰にも頼れないと感じていたかを少しずつ言葉にできるようになっていきました。
カウンセリングの中では、自己肯定感を育てるワークや、対人関係での新たなチャレンジを少しずつ積み重ねる練習も行いました。Aさんは徐々に「自分にも価値がある」と思える瞬間が増え、人との関係においても「距離をとりすぎなくても大丈夫」と感じられる場面が出てくるようになりました。いまだ完全な自信を持てるわけではありませんが、以前よりも日常生活が過ごしやすくなり、他者との関わりを楽しめるようになってきたと感じています。
愛情剥奪を受けた人の心理的な問題と特徴
愛情剥奪を受けた人には、どのような特徴があるのでしょうか。ここでは、愛情剥奪を受けた人にみられる心理的な問題や特徴をいくつか紹介します。
ただし、ここに挙げる心理的な問題や特徴の背景要因はさまざまであり、必ずしも愛情剥奪だけが原因とはいえないかもしれません。
自身の抱える問題や特徴について詳しく検討したい場合は、カウンセリングなどでの相談を検討してみてください。
(1)人間関係
愛情剥奪を受けた人の人間関係には、以下のような特徴が表れることがあります。こうした特徴は、人間関係の維持を困難にしがちです。
Aさんの場合、幼少期から他者との距離感がつかみにくく、人間関係で過度に警戒したり、逆に依存的になったりすることがありました。信頼関係を築くのに時間がかかり、「どうせ自分は大切にされない」と感じやすい傾向が見られました。
ほど良い距離感をとりにくく、信頼関係をもちにくい
相手との距離が近すぎるか遠すぎるかのどちらかに偏ってしまい、ほど良い距離感をとりにくくなります。
非常によそよそしく、何年たっても距離感が全く縮まらなかったり、反対に、相手を選ばずに誰とでもすぐに親密になるものの、関係が濃厚になりすぎて互いに消耗し、関係が切れやすくなったりします。
「全か無か」になりやすい
好きと嫌いがはっきりしすぎていて、同じ人にも良い面と悪い面があることを受け入れるのが難しくなります。
相手からどんなに良くしてもらっても、一度不快に思うことがあると、それまでの良い関係は帳消しになり、相手のことを全否定してしまうといったことがあります。
怒りにとらわれやすい
相手の意図を過剰に解釈して傷ついたり、相手の感情に巻き込まれたりしてしまいがちです。
相手に失望や怒りを感じると、相手を精神的、肉体的に痛めつけるような行動をとり、人間関係を壊してしまいます。
傷つきやすく、攻撃的になる
ささいなストレスにもネガティブな反応を起こしやすく、ストレスを自分への攻撃と受け止めると、暴力的になって他人に怒りを爆発させるなどの反撃行動に出ることがあります。
攻撃が自分に向かう場合、自分を傷つける行動をとることもあります。
虚言、反抗、いたずらなどの行動
ものを盗む、壊す、弱いものをいじめる、いたずら、虚言といった反社会的行動、問題行動と呼ばれる様子がみられることがあります。
これらは、自分自身の喜びや満足感といった感覚が分からないことや、そのために他人と感情を共有しにくいこと、そのための孤独感、存在感覚の希薄さ、空虚感などを補うためのものであったり、さみしさや怒りの表現でもあるといわれます。
(2)恋愛関係・夫婦関係
愛情剥奪を受けた人の恋愛関係や夫婦関係には、以下のような特徴が表れる場合があります。こうした特徴により、パートナーとの関係に困難を抱えやすくなります。
Aさんは恋愛でも相手から愛されている自信を持てず、相手の気持ちを確かめようと過剰に求めたり、逆に距離を置いたりするなど不安定な関係になりがちでした。愛情に対して素直に応じることが難しく、自己否定感や孤独感を感じることが多かったです。
信頼や愛情が保たれにくい
愛情剥奪を受けた人は、特定の人との愛情や信頼が維持されにくい場合があります。
すぐに親密な関係になるものの持続せず、すぐに冷めて分かれてしまうため、関係は不安定になりやすく、結婚や離婚を繰り返すこともあります。
性の問題を抱えやすい
基本的な対人関係だけでなく、性愛関係も愛着関係を土台として発達するため、性愛関係でもさまざまな問題を抱えやすくなります。
たとえば、母性的な愛情への憧れと性愛との混乱や、男女の役割の倒錯がみられることがあります。
(3)親子関係
愛情剥奪を受けた人の親子関係には、たとえば以下のような特徴がみられます。
子どもとしても、親になってからも、親子関係に不安定さを抱えてしまいがちです。
Aさんは自身が親になったとき、「どのように子どもと関わればよいのか」と戸惑いを感じやすくなりました。自分が経験してこなかった温かい親子関係をどう築けばよいか分からず、不安や葛藤を抱えていました。
親との確執を抱えるか、過度に従順になりやすい
親との愛着関係が不安定な人は、親への敵意や恨みなどのネガティブな感情を抱くだけでなく、親に過度に従順であったり、「いい子」として振る舞ったりする場合もあります。
関係がうまくいっているときは親を喜ばせようとする一方で、うまくいかないときは怒りなどの否定的な感情が噴き出し、急に関係が悪化することもあります。
子育てに困難を抱えやすい
愛情剥奪を受けた人にとって、子育ては大きな課題となる場合が多いです。
根っから子どもが嫌いであったり、関心がなかったりする場合もあれば、子どもが好きでもうまく愛せなかったり、接し方が分からなかったりする場合もあります。
子どもと憎しみ合う、子どもを自分の世話係にして自立を妨げてしまうなど、子どもとの関係が不安定になるケースもみられます。
(4)心身の健康
愛情剥奪の経験は、心身の健康状態にも影響する場合があります。たとえば、以下のような状態になることがあります。
Aさんの場合、慢性的な不安や抑うつ傾向が見られ、体の不調も起こりやすかったです。ストレスに弱く、緊張や不眠、食欲不振などの症状が周期的に現れていました。
ストレスに弱く、傷つきやすいため、心身の不調に陥りやすい
ささいなストレスに対してもネガティブな反応を起こしやすいといわれます。
ストレスが行動ではなく内面に向かう場合、抑うつ的になって自分を責めて落ち込む、悪い結果を予測して大きな不安を抱えるといった精神状態に陥りやすくなります。
傷つきやすく、物事を被害的に捉えたり、周囲から操作されているような感覚になったりしやすいため、さまざまな精神障害に至るリスクが高いです。
依存しやすい
安全感を持ちにくいため、ストレスに弱く、傷つきやすくなってしまいます。
そんな中で自分を支えるためには何らかの対象に依存するほかなく、それがアルコール、薬物、食べること、買い物、恋愛、セックスなどへの依存として表れることがあります。
ただ、それらは一時的な慰めや逃避となりがちで、真に回復させてくれるものとはなりにくいです。
(5)心身の発達
養育者との愛着関係は、あらゆる発達の土台となります。愛情剥奪を受けた場合、その後の人生にわたる心身の発達に問題が生じかねません。
特に、虐待という形で愛情剥奪を受けた子どもの場合、脳の広範にわたる器質的変化が生じることが指摘されており、その影響として、以下のような特徴がみられることがあります。
Aさんは自己肯定感や自信が育ちにくく、新しいことに挑戦する意欲が乏しい時期もありました。また、感情表現や他者とのコミュニケーションに苦手意識を持つなど、心理的な発達面でも課題を抱えていました。
欲求不満を和らげる力が弱い
共感などの感情の基盤は、あやされる、優しい言葉をかけられるといった養育者との交流を通じて発達します。
しかし、愛情剥奪を受けた子どもの場合、感情を調整する力の発達が不十分なため、不安や恐れに際し、緊張を和らげたりリラックスしたりすることが難しくなります。
整理整頓、見通しを立てるのが苦手
虐待を受けた子どもには、脳の前頭葉の機能障害が起こる場合があります。
前頭葉の機能障害は、整理整頓や見通しを立てることの苦手さ、そして、思考力や学習障害にもつながる場合があります。
衝動のコントロールが苦手で、多動傾向がある
前頭葉機能の障害は、衝動コントロールの未熟さや多動傾向にもつながります。
周囲からはささいに見える刺激から、大げんかになったり、フリーズしてしまったり、衝動的にものを盗んだりしてしまうことがあります。
自己肯定感や向上心が乏しい
愛情剥奪がある場合、勉強や仕事など、目標に向かって努力する意欲が湧きにくくなります。
養育者から肯定され、サポートや勇気を与えられた子どもは、自分や他者のために頑張ろうと思えますが、養育者から関心を向けられなかったり、否定され続けたりした子どもには、そうした意欲が湧きにくくなるのです。
自分を生かすのが不得意
自分の可能性を試すために踏み出すことが難しく、過度な不安を感じたり、無気力になったり、最初から諦めてしまったりします。
その結果、自らのもつ潜在的な能力を活かせていないことも多いです。
愛情剥奪を受けた人への支援
愛情剥奪を受けた人に対しては、どのような支援が行われるのでしょうか。
実際には、さまざまなアプローチがそれぞれ、あるいは組み合わせて行われますが、ここでは、医学的治療、家族支援、カウンセリングの3点に触れます。
(1)医学的治療
愛情剥奪を受けた人の心身の状態に応じ、医学的治療が行われます。愛情剥奪を受けた子どもに栄養障害がみられるときは、年齢に合った十分な食事を与えることや、栄養指導が行われ、場合によっては入院治療となることもあります。
また、衝動コントロールの困難さに対しては薬物療法が行われ、学習面の困難に対しては学習指導、運動領域には訓練療法、作業療法なども行われます。
そして、うつ病や不安障害といったさまざまな精神症状に対しては、薬物療法や心理教育、精神療法を通じた支援も行われます。
Aさんの場合、強い不安や抑うつ症状に対して心療内科で薬物療法を受けました。抗うつ薬や抗不安薬により、急性期のつらさはある程度軽減されましたが、根本的な課題の解決には至りませんでした。
(2)家族支援
愛情剥奪が生じている家族に対する支援も行われます。たとえば、子どもが親を失った場合、家族の生活全体への支援が必要です。
経済的な問題が生じることも、転居が必要となることも、離別や事件性がある場合は裁判に関わる可能性もあります。
この場合、新しい環境への適応支援に加えて、現実的な問題に対処するソーシャルワークも必要となるでしょう。虐待による愛情剥奪の場合は、親子分離も含めた安全な環境の確保が重要です。その上で、物理的・身体的・情緒的に子どもを世話し、ケアできる養育者が提供されます。
具体的には、養育不全が起きている環境から子どもを分離し、施設や里親による養育が提供されます。
また、在宅のまま親子の再統合を目指す場合もあります。
この場合、養育者とのアタッチメント関係の改善を目指す乳幼児−親治療として、乳幼児−親精神療法や、相互交渉ガイダンスなどが行われることがあります。ただ、こうしたケースはリスクが高くなるため、多元的・包括的な介入が必要とされます。
Aさんは家族との関係性を見直し、パートナーや親しい人と自分の気持ちや過去の体験を共有する取り組みを始めました。家族支援では、家族がAさんの苦しみや背景を理解し、適切な関わりを意識することが重要とされました。
(3)カウンセリング
愛情剥奪を受けた人の抱えるさまざまな困難に対しては、カウンセリングを通じた支援も行われます。たとえば、愛情剥奪によるトラウマの影響についての心理教育や、人との適切な距離の取り方の練習、衝動コントロールの練習などが行われます。低年齢の子どもの場合は、遊びの中での表現を利用します。
言語化が可能な年齢であれば、同じような体験をした子どもと感情や記憶を分かち合う集団療法が有効な場合もあるでしょう。
支援を通じて最終的に目指されるのは、自尊感情の獲得です。
愛情剥奪を受けた過去と強く結び付いた自己意識から離れ、自分を大切な存在として新たに捉え直す作業を、信頼できる支援者と一緒に行います。
その中で、愛情剥奪による傷つきが少しずつ修復されていきます。
そして、過去に愛情剥奪を受けた体験についての肯定的なことも否定的なことも、事実として自由に思い出すことができ、今現在の視点から、自分の人生の物語として意味付けられる時が来るかもしれません。そうなれば、自身の子どもと安定した愛着関係を築ける可能性も高まるでしょう。
Aさんはカウンセリングを通じて、自分の感情やニーズを少しずつ言葉にできるようになり、自己肯定感の回復や対人関係の練習を重ねてきました。安心できる対話の中で、新しい関係の築き方や自己理解を深める支援が行われました。
愛着障害のトピックについて
愛着障害についてのいくつかのトピックです。さらに詳細に知りたい方は以下をご覧ください。
愛情剥奪についてのよくある質問
愛情剥奪とは、子どもが必要とする愛情や関心を養育者から十分に受けられない状態を指します。育児放棄、無関心、または過度に厳しい育児態度が主な原因とされます。愛情は子どもの情緒的な安定にとって不可欠であり、この愛情が不足することは、情緒的な発達に深刻な影響を与える可能性があります。愛情が不足すると、子どもは不安感や孤独感を抱きやすく、社会性や自己肯定感の発達にも遅れが生じます。
愛情剥奪は、子どもに多くの深刻な影響を与えます。まず、感情的な問題が顕著になり、極端な不安や恐怖、自己評価の低さ、感情的な冷淡さなどが現れることがあります。物理的には、食欲不振や睡眠障害、発達の遅れなどの身体的な症状が出ることもあります。また、社会性の発達にも影響を及ぼし、他者との関わりにおいて問題を抱えやすくなります。子どもが愛されていると感じることが、心理的な健康や社会的なスキルの発達にとっていかに重要であるかがわかります。
愛情剥奪症候群は、子どもが必要な愛情やケアを受けられない状態が長期間続くことによって発生する、情緒的および社会的な障害です。この状態は、親の無関心、育児放棄、または過度の厳しさなど、養育環境に起因することが多いです。愛情剥奪症候群にかかる子どもは、感情のコントロールが難しく、他人との交流が不安定で、学校や家庭での行動に問題を抱えやすくなります。この症候群は、情緒的な発達や社会的な適応能力に長期的な影響を与えるため、早期の介入が重要です。
愛情剥奪症候群の症状には、身体的な発達の遅れ、感情的な問題、社会的な適応障害などが含まれます。身体的な症状としては、低体重や身長の遅れ、免疫力の低下などがあります。感情的には、極端な不安感、恐怖症、感情の起伏が激しくなることがあります。また、社会的な面では、他者とのコミュニケーションが難しく、対人関係において問題を抱えることが多いです。子どもは親からの愛情を感じることができず、その結果として情緒的な発達に支障が出ることが多いです。
愛情剥奪症候群の主な原因は、養育者の無関心や育児放棄、過度に厳しい育児態度です。これに加えて、家庭内でのストレス、親自身の精神的な問題、経済的な困難などが影響を与えることもあります。養育者が自身の感情やストレスに圧倒されている場合、子どもに対して愛情を十分に示すことができなくなります。このような育児環境では、子どもは十分な安心感やサポートを受けることができず、その結果、情緒的な問題や発達の遅れが生じます。
愛情剥奪症候群の治療は、まず子どもに適切な愛情、栄養、社会的サポートを提供することから始まります。養育者自身が心理的なサポートを受けることが重要です。養育者が自分の感情を管理できるようになることで、子どもにもより良い関係を築くことができるようになります。治療には、子どもの発達に応じた心理療法、カウンセリング、または支援プログラムへの参加も有効です。場合によっては、施設への一時的な避難が必要なこともあります。早期の介入が症状の緩和と回復につながることが多いため、早めに専門家の助けを求めることが重要です。
愛情剥奪症候群の予防には、子どもに十分な愛情を注ぎ、安定した育児環境を提供することが基本です。養育者自身が精神的に安定していることが大切で、必要に応じて心理的なサポートを受けることも予防に繋がります。また、地域の育児支援や子育てサークルに参加し、社会的なサポートを活用することも予防策となります。早期に問題に気付き、対応することが予防には最も効果的です。
愛情剥奪症候群の診断は、子どもの発達や行動を観察し、評価することで行います。具体的には、身長や体重の測定、発達段階のチェック、そして養育環境の評価が行われます。診断には、子どもと養育者との面談や、家族全体の状況を踏まえた評価が重要です。また、必要に応じて心理検査やカウンセリングが行われ、愛情不足が明らかになると診断されます。
愛情剥奪症候群の影響は、成人期にも続くことがあります。成人期においては、情緒的な不安定さ、対人関係の問題、自己肯定感の低さなどが見られることがあります。また、愛情を受けてこなかったことで、人間関係を築くのが難しくなることや、感情表現に困難を感じることが多いです。成人期になってからも、過去の愛情不足が影響している場合があるため、早期の治療とサポートが回復に繋がることが多いです。
愛情剥奪症候群とアスペルガー症候群は異なる障害ですが、愛情不足が原因でアスペルガー症候群に似た症状が現れることがあります。例えば、コミュニケーションの困難や、対人関係での問題が強調される場合があります。ただし、アスペルガー症候群は神経発達障害であり、愛情剥奪とは別の原因によって引き起こされるものです。診断には専門的な評価が必要です。
愛情剥奪について相談したい
愛情剥奪を受けることは、その後の人生にわたる心身の発達に影響を及ぼし、さまざまな対人関係の困難や心身の不調につながりかねません。
自身の抱える不安や孤独感や、愛情剥奪を受けた体験について相談したい場合は、カウンセリングもご活用ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。