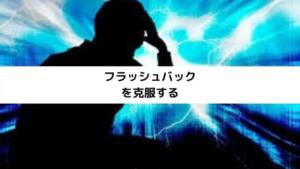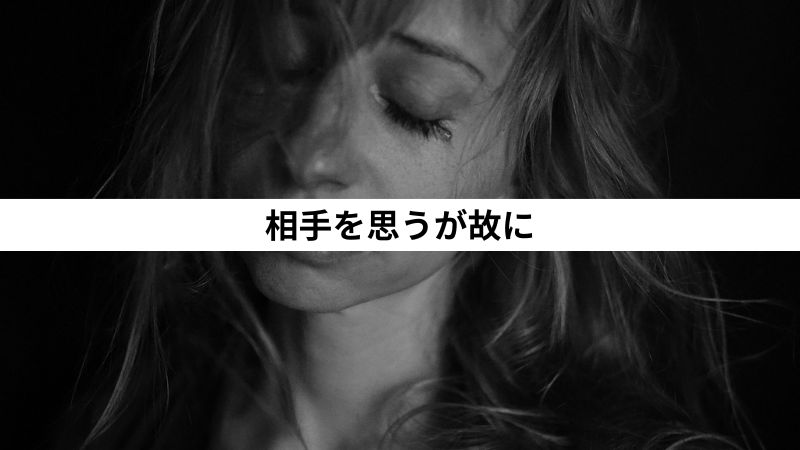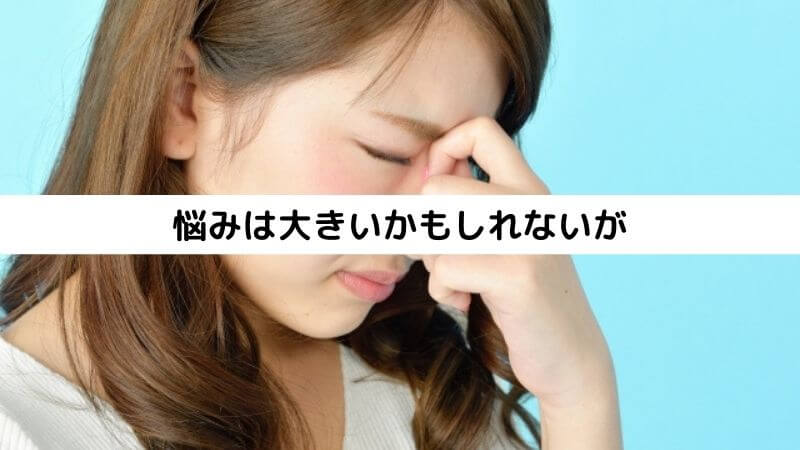ストレスが病気の原因になる!?自分では気づきにくい諸症状と対処法について
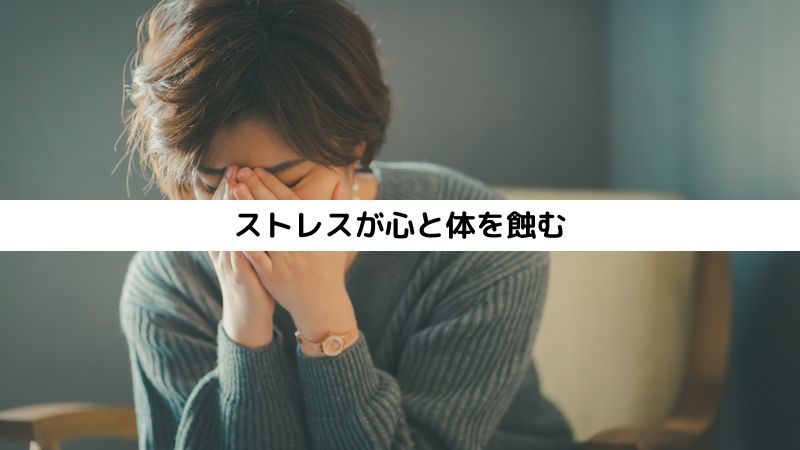
こちらの記事では、ストレスによって引き起こされる病気の症状について紹介します。
身体になんらかの不調を抱えていても、「今日は大事な仕事だから」と仕事に励んでいる人もいるでしょう。しかしその不調はストレスによるものかもしれません。自分では気づかないうちにストレスが限界に達しており、療養が必要な状態になっていることも。
今回紹介する症状が自分に当てはまらないか、また身の回りで同じような症状が出ている人がいないかチェックしてみてください。
目次
ストレスとは?みんなに起こるの?
ストレスとは何か、なぜ起こるのか、また誰にでも起こることなのかを考えていきます。
「現代はストレス社会だ」と言われることがありますが、そもそもストレスとはどういったことを指すのでしょうか?また、どんな人にでもストレスはかかるのでしょうか?
(1)そもそもストレスとはどんなもの?
ストレスという言葉は、本来は物理学で使われていました。医学界で使われるようになったのは1936年頃からで、カナダのセリエ博士がストレス学説を提唱したことで、広まりました。
医学界におけるストレスとは、外的な刺激によって身体や心に負担がかかることを言います。負担によって、さまざまな症状や反応が出ることをストレス反応、ストレスの原因をストレッサーと呼びます。
ストレス反応やストレッサーを含めてストレスと言うこともあるようです。
(2)どんな人にストレスがかかるの?
ストレスは大人も子どもも関係なくかかります。間違えられやすいことですが、実は良いことが起きても悪いことが起きても身体や心にストレスがかかります。つまり、生きていれば誰にでも何かしらのストレスがかかっているというわけです。
ただし、ストレスを溜め込むのは良くありません。ストレスに対する対応力を身につけ、コントロールする必要があります。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは、幼少期から周囲の期待に応えることを重視して育ちました。両親は教育熱心で、成績や行動に対する評価が日常的に行われ、失敗を避けるよう努めるうちに、常に緊張感を抱えて生活する習慣が身についていました。大学卒業後は希望していた企業に就職し、数年間は順調に勤務していましたが、数年前に異動となり、新しい部署での業務量や責任が急激に増加しました。特に上司からの厳しい指示や、短期間で成果を求められる環境が続き、次第に強いストレスを感じるようになりました。
最初は疲れやすさや睡眠の質の低下といった身体症状が現れ、そのうち集中力が続かず、仕事のミスが増えました。同時に「朝、会社に行きたくない」という気持ちが強まり、休日も心から休まらない状態が続きました。半年ほど経つ頃には動悸や頭痛、胃の不快感が頻発し、感情も不安定になって涙が止まらなくなることもありました。ついに通勤途中で過呼吸を起こし、救急外来を受診。精神科で「適応障害」と診断され、休職を勧められました。
休職後、主治医の紹介で当オフィスにカウンセリングを申し込みました。初回面接では、Aさんが長年「頑張らなければ認められない」という価値観に縛られてきたことや、職場での孤立感が強まっていたことが明らかになりました。カウンセリングではまず、生活リズムを整え、ストレス要因を客観的に整理することから始めました。その中で、仕事だけでなく家庭や友人関係でも「他人の期待を優先し、自分の気持ちを後回しにする」傾向が繰り返されていることに気づいていきました。
数か月の面接を通じて、Aさんは自分の感情や限界を率直に表現する練習を行い、必要なときには周囲に助けを求めるスキルを身につけました。復職に向けては、職場との連携を図り、業務量や役割の調整も行いました。その結果、以前のような過剰な緊張感や自己否定感は和らぎ、再び社会生活を送る自信を取り戻すことができました。
ストレスはどんなシーンでかかりやすい?
ストレスはどんなシーンで起こるのでしょうか?シチュエーション別に紹介します。
Aさんは、部署異動による業務量の急増と、厳しい上司からの短期間での成果要求により、大きなストレスを受けやすくなっていました。さらに、周囲に相談しづらい孤立した環境も負担を強めていました。
(1)職場のストレス
ストレスと聞くと真っ先に連想するシチュエーションが、職場でしょう。実際に、約6割の人が、職場でストレスを感じているというデータもあります。
仕事でミスをしないように慎重になったり、上司からの叱責や部下の指導に悩んだり、職場の人間関係などさまざまな要因が潜んでいる場所なのです。
(2)ホルモンバランスの変化によるストレス
女性の場合、ホルモンバランスの変化によって自律神経のバランスが崩れやすくなります。ホルモンバランスの変化は自分では気づきにくいため、知らないうちに大きな負担がかかっていることもあるでしょう。
(3)学校や受験のストレス
身体はもちろん、心も成長段階にある子どもにもストレスはかかります。むしろ、成長段階にありストレスへの抵抗力がないために、まともにストレスを受けてしまうこともあるでしょう。
勉強しても成績が伸びない、受験へ不安、友だちや親との関係性などが、学生にとってのストレスの原因になります。
(4)高齢者にかかるストレス
年齢や経験を積んだ高齢者にも例外なくストレスがかかります。これまでの蓄積したストレスや退職後の生活環境の変化、身近な人との死別、体力の低下などが原因になるでしょう。また、病気や介護などの問題にも直面しやすくなります。
ストレスによって引き起こされる症状を知っておこう
ストレスがかかったり溜まったりすると、どんな症状が出てくるのでしょうか?症状は人によって違い、1つだけ出る人もいれば複数の症状が現れる人もいます。
(1)身体に現れる症状
まずは身体に現れる症状です。
- 眠れない
- 寝過ぎる
- 食欲がない
- 食べ過ぎる
- 頭痛、胃痛
- 疲れがなかなかとれない
- 身体が重い
- 動悸、息苦しい
- 下痢、便秘
- 肩こり、腰痛 など
Aさんは、動悸、頭痛、胃の不快感、睡眠の質の低下といった症状が現れていました。
(2)病気として現れる症状
病気となって症状に出るケースもあります。
- 高血圧
- 喘息
- 心臓病
- 肥満症
- 脳卒中
- アトピー性皮膚炎
- 更年期障害
- うつ病、不安障害 など
Aさんは長期的なストレスの結果、精神科で適応障害と診断されました。
(3)気持ちの面で現れる症状
気持ちの面に変化が現れることもあるでしょう。以下の症状はありませんか?
- 悲しくなる
- 気分が落ち込む
- 何をするのも面倒
- 不安で仕方ない
- イライラする
- 楽しくない
- 何も興味がなくなる など
Aさんは、強い不安感や自己否定感、涙が止まらなくなるなどの感情の不安定さを経験していました。
(4)行動に現れる症状
行動に現れる症状もあります。
- 生活リズムが崩れる
- 外出したがらない
- 飲酒や喫煙が増える
- ギャンブルにハマる
- 運転が乱暴になる
- 浪費する など
Aさんは出勤が困難になり、通勤途中で過呼吸を起こすこともありました。
これらの症状は一時的なものだとしても、適切な対処をしなければ、解消しないまま蓄積し、病気に発展して医療的な対応が必要なケースがあります。
こういった場合では、すでにストレスへの許容範囲が限界に達しているケースがあるため注意が必要です。
強いストレスによって、こんな症状につながることも
強いストレスが急激にかかると、心や精神に強いダメージを受けてしまいます。それによってトラウマやフラッシュバック、PTSDを発症する可能性があります。どんな種類があり、どういった症状が出るのかを詳しく見てきましょう。
(1)トラウマ
トラウマはギリシャ語に由来しており、傷という意味があります。過度なストレスにさらされたことで「心の傷=トラウマ」になるのです。トラウマを原因としてフラッシュバックが起きたりPTSDと診断されたりします。
トラウマについては以下のページに詳しく書いているので、ご参照ください。
Aさんは職場での過度なプレッシャーが、再び同様の状況を思い出すだけで緊張する反応につながっていました。
(2)フラッシュバック
フラッシュバックとは、急激なストレスが原因となり、トラウマ化して出現する症状です。いつもと変わらない生活ができるものの、ストレスの原因とつながりがあるシチュエーションや行動などに出くわしたことで、恐怖心などが出てきます。
夢で見ることもあり、睡眠障害を引き起こすことも。恐怖心や不安感だけでなく、感情のコントロールができなくなる場合もあります。
フラッシュバックの詳細やその対処法については以下のページが参考になります。
Aさんは上司からの厳しい口調や職場の光景が、突然頭に蘇ることがありました。
(3)PTSD
PTSDとは、心的外傷後ストレス障害のことです。強いストレスを原因として、脳の一部に萎縮が起こったり、血流が低下したりし、身体や心の両面にさまざまな症状を引き起こします。
ただ、同じ状況を体験した人でもPTSDを発症しない人もおり、ストレスへの耐性力などによって差が起きるのも特徴です。具体的な症状としては、恐怖心や罪悪感、孤独感などが現れます。些細な音に過剰に反応したりイライラしたりすることもあるでしょう。
AさんはPTSDの診断は受けていませんが、似た反応が一時的に見られる場面がありました。
ストレスを軽減・解消するための対処法
誰にでも起こり得るストレス症状をできるだけ軽減するためには、どういった対処をすれば良いのでしょうか?対処法を紹介します。
(1)マッサージなどのリラクゼーションを利用する
マッサージやアロマテラピー、ヨガなどのリラクゼーションを行うのがおすすめです。これらは心身を癒やすことを目的にしており、リラックスすることで心身の緩和が期待できるでしょう。
Aさんは、休職期間中にマッサージやアロマを取り入れ、身体の緊張をほぐしました。
(2)軽い運動を行う
過度に疲れているときに無理に運動を行う必要はありませんが、軽い運動はストレス発散につながります。ウォーキングやジョギング、趣味のスポーツなどを行うために、外に出て太陽や風に当たることで、気分転換できるでしょう。
また運動によって適度な疲労感を得ることで、深い睡眠がとれるようになります。定期的な運動によって、うつ病を予防する効果が期待できるという研究結果もあるため、運動習慣を身につけると良いでしょう。
Aさんはウォーキングを習慣化し、気分転換と体力維持に努めました。
(3)食生活を見直す
ストレス予防のために食生活を見直すという方法も。実は、ビタミンCはストレス予防に効果があると言われています。この他にもビタミンB12を多く含む魚介類を積極的に摂ることで、うつ病予防になるでしょう。
また、肉類にも含まれているため、栄養バランスがとれた食事を摂ることが、心身の健康にもつながるのです。
Aさんは胃の不調を考慮し、消化の良い食事や規則正しい食事時間を心がけました。
(4)カウンセリングに通う
「このくらいのストレスは大丈夫」「前も同じようなことがあったけど数日で治まったし…」と、ストレスを安易に考えている人がいます。ストレスは自分が考えている以上に、心身に負担をかけている場合があることを忘れないでください。
自分なりに上手く対処できているつもりでも、問題解決には時間と労力がかかるケースもあるでしょう。病気へ発展させないためにも、早めのケアを行うことが大切です。
ストレスに対するケアは、精神科や心療内科、カウンセリングなどで行えます。定期的にケアして、悪化させないように注意しましょう。
Aさんはカウンセリングでストレス要因の整理や自己表現の練習を行い、復職に向けての準備を進めました。
ストレスについてのよくある質問
ストレスは心身に多大な影響を及ぼし、さまざまな病気の引き金となることがあります。主なものとして、以下のような疾患が挙げられます。まず、精神的な影響としては、うつ病や不安障害、パニック障害などが知られています。これらは、持続的なストレスにより脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることで発症することがあります。次に、身体的な影響としては、自律神経失調症や過敏性腸症候群、胃潰瘍、心筋梗塞などが挙げられます。これらは、ストレスによる自律神経の乱れやホルモンバランスの変化が関与しています。また、慢性的なストレスは免疫力の低下を招き、感染症にかかりやすくなるとも言われています。さらに、皮膚疾患として、アトピー性皮膚炎や蕁麻疹などもストレスが悪化要因となることがあります。これらの病気は、ストレスが直接の原因となる場合もあれば、既存の症状を悪化させる要因となることもあります。したがって、日頃からストレスを適切に管理し、心身の健康を維持することが重要です。
ストレスが原因で現れる体調不良の症状は多岐にわたります。主なものとして、以下のような症状が挙げられます。まず、頭痛やめまい、肩こりなどの身体的な不調が現れることがあります。これらは、ストレスによる筋緊張や血行不良が原因とされています。次に、消化器系の症状として、胃の不快感や食欲不振、下痢や便秘などが挙げられます。これは、ストレスが自律神経に影響を及ぼし、消化機能を乱すためです。また、睡眠障害も一般的な症状の一つです。寝つきが悪い、途中で目が覚める、熟睡感が得られないなどの問題が生じることがあります。さらに、動悸や息切れ、手足のしびれなどの症状も報告されています。これらの症状は、ストレスによる自律神経のバランスの乱れが関与しています。これらの体調不良は、個人差があり、複数の症状が同時に現れることもあります。持続的なストレスが原因でこれらの症状が続く場合は、専門家に相談することが重要です。
ストレスを軽減するためには、日常生活の中で以下のような方法を取り入れることが効果的です。まず、適度な運動を行うことが挙げられます。ウォーキングやヨガなどの軽い運動は、心身のリラックスを促し、ストレスホルモンの分泌を抑える効果があります。次に、十分な睡眠を確保することが重要です。質の良い睡眠は、脳と体の回復を助け、ストレス耐性を高めます。また、趣味やリラクゼーション法を取り入れることも有効です。読書や音楽鑑賞、瞑想など、自分がリラックスできる時間を持つことで、心の緊張を和らげることができます。さらに、バランスの取れた食事を心がけることも大切です。栄養バランスの良い食事は、体の機能を整え、ストレスに対する抵抗力を高めます。加えて、信頼できる人とのコミュニケーションを図ることも効果的です。話を聞いてもらうことで、気持ちが軽くなり、ストレスの解消につながります。これらの方法を組み合わせて、自分に合ったストレス対処法を見つけることが、心身の健康維持に役立ちます。
はい、ストレスはうつ病の発症要因の一つとされています。特に、長期間にわたる強いストレスは、脳内の神経伝達物質のバランスを崩し、気分の低下や意欲の喪失など、うつ病の症状を引き起こす可能性があります。例えば、職場での過度な業務負担や人間関係のトラブル、家庭内の問題など、持続的なストレス源が存在する場合、うつ病のリスクが高まるとされています。また、ストレスに対する個人の耐性や対処法も影響します。適切なストレスマネジメントができない場合、ストレスが蓄積し、うつ病を発症するリスクが高まります。したがって、日頃からストレスを適切に管理し、心の健康を保つことが重要です。もし、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失、睡眠障害などの症状が2週間以上続く場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。
ストレスは体にさまざまな影響を与えます。特に、自律神経系、内分泌系、免疫系の機能に大きく関与します。まず、自律神経系への影響として、ストレスを感じると交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上昇することがあります。これが持続すると、慢性的な高血圧や心血管疾患のリスクが高まる可能性があります。次に、内分泌系では、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加します。コルチゾールは短期的には体を守る役割を果たしますが、長期的に分泌が続くと血糖値の上昇や脂肪の蓄積、さらには筋肉や骨の弱化を引き起こすことがあります。また、免疫系においては、慢性的なストレスが免疫力を低下させるため、風邪や感染症にかかりやすくなることがあります。さらに、ストレスは胃腸にも影響を与え、胃酸過多や胃潰瘍、過敏性腸症候群などの消化器系の問題を引き起こすこともあります。これらの影響を軽減するためには、適切なストレスマネジメントが必要不可欠です。
ストレスが原因で胃腸の不調が現れる場合、いくつかの対処法があります。まず、ストレスの原因を特定し、可能であればその要因を取り除くか、軽減する方法を見つけることが重要です。また、食事に気をつけることも効果的です。例えば、脂っこいものや刺激の強い食べ物を避け、消化に良い食事を心がけることで胃腸への負担を軽減できます。さらに、食事の回数を増やし、少量ずつ摂ることで胃の負担を減らす方法もあります。次に、リラクゼーション法を取り入れることが有効です。深呼吸や瞑想、軽い運動などを行うことで、自律神経のバランスを整え、胃腸の機能を改善する助けになります。もしこれらの方法を試しても症状が改善しない場合は、医師や専門家に相談することをお勧めします。薬物療法や心理療法を組み合わせることで、症状が和らぐことがあります。早めの対応が重要ですので、我慢せずに適切なサポートを受けることを考えてください。
家庭で簡単にできるストレス解消法として、まず深呼吸が挙げられます。リラックスできる環境で、深くゆっくりと呼吸することで、副交感神経が活性化し、心身が落ち着きます。また、軽いストレッチやヨガを行うことも効果的です。これにより、筋肉の緊張がほぐれ、体内の血流が良くなるため、ストレス軽減につながります。さらに、音楽を聴いたり、好きな映画を観たりしてリラックスする時間を設けるのも良いでしょう。趣味に没頭することも、ストレスから意識をそらす良い方法です。また、アロマセラピーを取り入れるのもおすすめです。ラベンダーやカモミールなどのエッセンシャルオイルは、リラクゼーション効果が高いと言われています。これらの方法を取り入れることで、日常生活の中でストレスを軽減することが可能です。ただし、長期的なストレスや深刻な悩みがある場合は、専門家に相談することを忘れないようにしましょう。
ストレスは自律神経失調症の主な原因の一つとされています。自律神経は、交感神経と副交感神経のバランスを保ちながら体の機能を調整していますが、過度なストレスが続くと、このバランスが崩れることがあります。その結果、動悸や息苦しさ、頭痛、胃腸の不調、疲労感など、さまざまな症状が現れるのが自律神経失調症の特徴です。この状態が続くと、心身に大きな負担がかかり、日常生活にも支障をきたすことがあります。ストレスが原因の場合、まずはストレス源を特定し、可能な限り取り除くことが重要です。また、生活習慣を整えることや、リラクゼーション法を取り入れることで、自律神経のバランスを回復させる助けになります。症状が重い場合や改善が見られない場合は、医療機関での診察を受けることをおすすめします。
ストレスが免疫力を低下させる理由は、主にホルモンの変化にあります。ストレスを受けると、体は防御反応としてコルチゾールなどのストレスホルモンを分泌します。このホルモンは短期的には免疫機能を強化する効果がありますが、慢性的に分泌が続くと逆に免疫細胞の働きを抑制してしまいます。これにより、ウイルスや細菌への抵抗力が低下し、感染症にかかりやすくなるのです。また、ストレスは睡眠の質を低下させることが多く、これも免疫機能に悪影響を与えます。さらに、ストレス下では栄養の吸収効率が低下するため、体が必要とするエネルギーや栄養素が不足することも免疫力の低下につながります。このように、ストレスが免疫系に多角的に影響を及ぼすため、ストレス管理が健康維持には欠かせない要素となります。
ストレスがたまったときにすぐできるリラックス法として、まず深呼吸がおすすめです。腹式呼吸を意識しながら、深く息を吸い、ゆっくり吐き出すことで、体と心がリラックスします。また、短時間でできる瞑想やマインドフルネスも効果的です。静かな場所で目を閉じ、呼吸に意識を集中させるだけでも、心の緊張を和らげることができます。さらに、好きな音楽を聴いたり、お茶をゆっくり飲んだりすることも簡単にできるリラックス法です。これらの方法を試しても気持ちが落ち着かない場合は、少し外に出て散歩するのも良いでしょう。新鮮な空気を吸い、体を動かすことで、ストレスホルモンが減少し、気分がリフレッシュされます。これらのリラックス法を組み合わせて、自分に合った方法を見つけることが重要です。
ストレスを軽くするカウンセリングを受けたい
私たちは、自分の想像を超えたストレスに日々さらされています。「この前までは大丈夫だったのに…」ということが乗り越えられなくなることも。これはストレスの蓄積によるものです。
ストレスは、定期的に荷下ろしする必要があります。運動やリラクゼーション、カウンセリングなどを上手く使って、ストレスを軽減していきましょう。
当オフィスには、ストレス問題に精通するカウンセラーが多数在籍しています。悪化する前に、早めにご相談ください。ご希望の方は以下の申し込みフォームからご連絡ください。
参考文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。