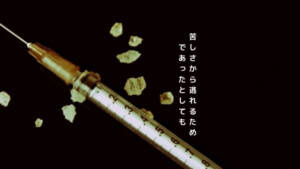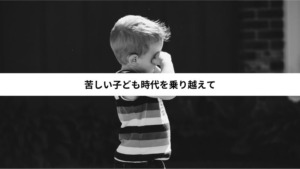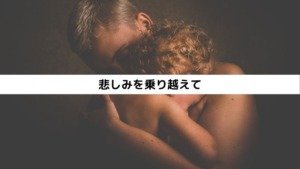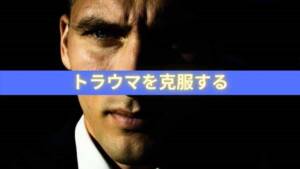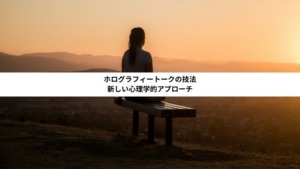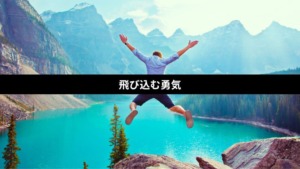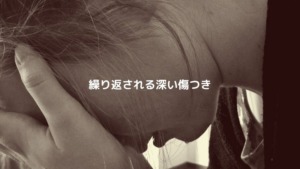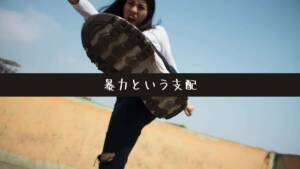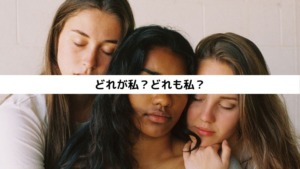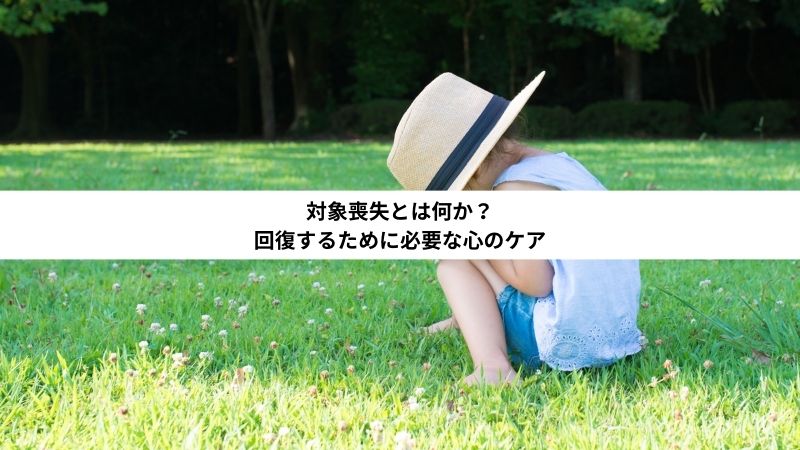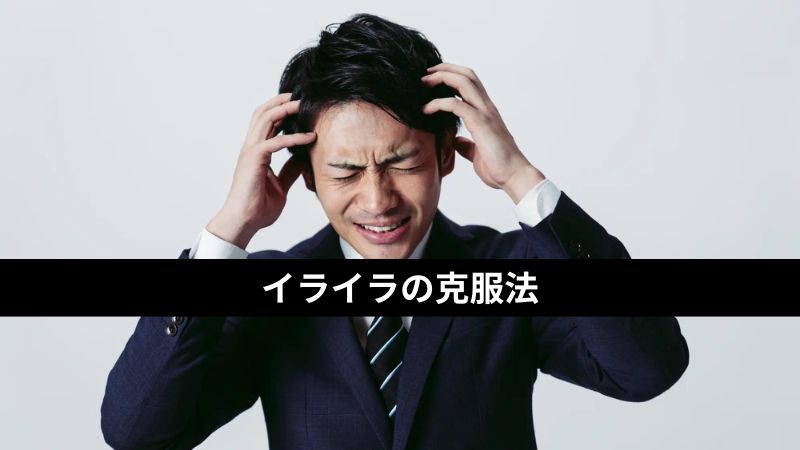フラッシュバックの対処法とトラウマからの回復
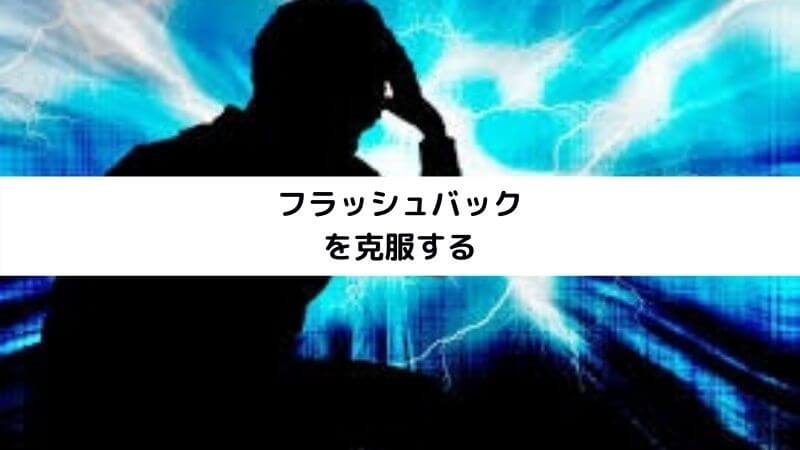
フラッシュバックとは、過去に強いトラウマ体験(心的外傷)をした場合に、その時の嫌な記憶が後々になって急激にかつ非常に鮮明に思い出されたり、同じような夢を見てしまったりする現象のことを指します。さて、果たしてこのフラッシュバックに対処できる方法はあるのでしょうか。
今回は「トラウマによる嫌な記憶のフラッシュバックの対処法」について説明します。
目次
フラッシュバックとは

フラッシュバックとは、過去のトラウマを受けて発現する心的外傷後ストレス障害(PTSD)や急性ストレス障害(ASD)の特徴的な症状のひとつであるといわれています。
例えば日々の生活の中で、自然災害や交通事故、あるいは暴力被害などを経験して自分が死んでしまうかもと極端に感じるような強い恐怖感を抱くイベントに遭遇したとします。その場合に適切な対処をしないままに時間が経過していくとその際に受けた大きな傷が後に悪化してフラッシュバックとして深刻な症状を引き起こすことがあります。
また、フラッシュバックという用語は過去に起こった莫大な記憶の中で、特にその記憶が自分にとって嫌なイメージを持ち、無意識的に不意に思い出されて、かつその時の光景がまるで現実世界で重複して起こっているかのような錯覚ともいうべき感覚を非常に激しく察知した際にも用いられます。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)や急性ストレス障害(ASD)だけがフラッシュバックを起こすのではありません。
発達障害の方の一部にもこのフラッシュバックを起こしてしまうこともあります。
そもそものトラウマについては以下のページで解説しています。
よくある相談の例(モデルケース)
20歳代 女性
Aさんは20歳代の女性で、大学時代に人間関係のトラブルとストーカー被害を経験しました。その出来事のあとから、突然当時の状況が鮮明によみがえるようになり、心臓が激しく鼓動し、身体が硬直して動けなくなることがありました。周囲からは「思い出すのは仕方ない」と言われましたが、Aさんの体験は単なる記憶ではなく、時間を超えてその場に引き戻されるような感覚であり、日常生活に大きな影響を及ぼしていました。夜道を歩くと急にあの時の恐怖がよみがえり、眠れない日が続き、講義やアルバイトにも出られなくなることがありました。心療内科を受診した際にはPTSDの症状と説明され、抗不安薬と睡眠薬が処方されましたが、根本的な恐怖の再体験は消えませんでした。
Aさんは生活の困難さからカウンセリングを申し込みました。初期の面接では、フラッシュバックが起きる状況を一緒に整理し、安心できる場で少しずつ言葉にしていくことから始めました。すぐに過去を詳しく語るのではなく、まずは呼吸法やグラウンディングなど、今ここに自分を取り戻す感覚を育てる練習が中心となりました。セッションを重ねるにつれて、Aさんは「思い出しても必ず現実に戻れる」という体験を積み、恐怖の渦に飲み込まれない手応えを得ていきました。さらに数年のプロセスの中で、ストーカー被害当時の無力感や怒りを丁寧に扱い、自分を守れなかったという自己否定の気持ちが少しずつ和らいでいきました。カウンセラーとの関係を通じて「安心して他者に支えられる」という新しい経験を重ねることが、孤立感を解いていく助けになりました。
現在、Aさんは社会生活に再び取り組み始め、以前のように突然フラッシュバックに支配されることは少なくなりました。不安が完全になくなったわけではありませんが、恐怖の記憶と距離をとる方法を学び、安心できる人間関係を基盤に生活を再構築できるようになっています。
フラッシュバックにはどんな症状があるのか
深刻な過去のトラウマが発生した場合における特有の反応として、過覚醒、回避、麻痺行動以外に、フラッシュバック(侵入症状)が挙げられます。
具体的には、フラッシュバックでは思い出したくなくてもそのインパクトが大きい出来事や関係するイベントを自分の意志に反して勝手に思い出したり考えたりしまう症状が代表的です。その他に、否応なしに過去の出来事に類似した感覚になる悪夢を繰り返し見るという症状もあります。
よく誤解されやすいこととして、あくまでフラッシュバックは自分のなかで過去のトラウマ体験に対して感情の整理がつかず、意思とは無関係に脳に不吉な記憶が侵入して反復されることを意味します。ですので、ただ単に日常体験に伴う嫌な感情が芽生えて思い出されることと明確に区別されるべきです。
ボキャブラリー能力が未熟な幼児期の時に経験したトラウマ体験は、言語的に十分に認識できないまま記憶してしまいます。そして、それを後になって忘却することができない場合にもフラッシュバックは起こるとされています。この場合、当時の周辺の記憶はまともに意識上に存在しないため、時間軸に比例してその内容を変造したり加工することが困難になります。
Aさんは、日常生活の中で突然ストーカー被害の場面が鮮明によみがえり、心臓が速く打ち、体が固まるような感覚に襲われました。視覚や音、匂いなども当時のものとして感じられ、現実感が失われてその場に戻ったような恐怖を体験しました。
嫌な記憶のフラッシュバックの対処法
これまで述べてきたことからも容易に想像できるように、そもそも誰しもがフラッシュバックを体験しないように衝撃的なトラウマ体験を回避することに越したことはありません。
万が一可能な範囲で環境調整を実行したにもかかわらず、トラウマの出現およびフラッシュバックの悪化を防げない場合には補足的に薬物治療を選択するケースがあります。特にフラッシュバック症状に対して抗うつ作用も有する選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の効果が過去の医学的検証で示されています。
それ以外にもトラウマ体験に対して有効と考えられている心理的アプローチを用いた治療法としてトラウマ焦点化認知行動療法(TF-CBT)があります。ただ、この治療をするうえでは専門スタッフの労力が過重になるのみならず、概ね1回あたり約1時間以上を要します。そのため、本邦では限られた施設でしか施行されておらず、実際のところはこの治療を受ける機会は非常に少ないかもしれません。
再び触れることが辛い過去のトラウマ体験を扱っていくことは誰にとっても非常に苦しいことです。嫌な記憶としてのフラッシュバックに向き合うためには、普段の生活に安心感があって余裕を持つことが重要です。まずは信頼できる相手と協力してトラウマ反応を認識することを大切にする必要があります。
フラッシュバックで長く苦悩している人たちが、臨床心理士やカウンセラーなどの専門職の方々とともに症状に向き合って治療して、つらい感情状態になっても自分である程度処理できる対策を学習して身に着けることができる日が来ることを願っております。
Aさんの場合、カウンセリングで呼吸法やグラウンディングを練習し、フラッシュバックが起きても現実に戻る方法を身につけました。また、安心できる環境で少しずつ体験を言葉にし、恐怖や怒りの感情を整理することで、次第にフラッシュバックに振り回されにくくなりました。
トラウマについてのトピック
フラッシュバックについてのよくある質問
フラッシュバックは、過去のトラウマ体験が突然鮮明に蘇る現象のことを指します。この現象は、まるでその出来事が今まさに起こっているかのように感じることがあり、感情的にも身体的にも強い反応を引き起こします。例えば、音や匂い、場所などがきっかけとなり、過去のトラウマが一瞬で再現されることがあります。フラッシュバックは、当時の痛みや恐怖を再び感じることがあり、時には周囲との現実感の違いに戸惑うこともあります。
フラッシュバックの主な原因は、過去に経験した強烈なトラウマ体験にあります。これには、事故や暴力、戦争、虐待など、感情的にも身体的にも非常に強いストレスがかかった出来事が含まれます。特に、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の一環としてフラッシュバックは現れることが多く、これらの体験は脳に深く刻まれ、日常生活の中で予期せぬ瞬間に蘇ることがあります。
フラッシュバックは、過去のトラウマ体験に関連する特定の刺激によって引き起こされることが多いです。例えば、過去に事故や戦争を経験した場合、同じような音(例えば、爆発音や車の衝突音)や匂い(例えば、煙や血の匂い)などがフラッシュバックを誘発することがあります。また、トラウマ体験を思い起こさせる場所や人、さらには状況(暗い場所や狭い空間など)がフラッシュバックを引き起こす原因になることもあります。
フラッシュバック中は、過去のトラウマ体験を再体験し、当時の感情や身体的な反応が蘇ることがあります。これには、恐怖や不安、無力感といった感情が強く現れることが一般的です。また、身体的には心拍数が上昇し、手足が震える、息が荒くなる、発汗が増えるなどの症状が現れることもあります。フラッシュバックの最中は、現実と過去の体験が混同されるため、冷静に自分を保つことが難しくなる場合もあります。
フラッシュバックを完全に防ぐことは難しいですが、予防策を講じることで発生頻度を減らすことは可能です。例えば、リラクゼーション法や深呼吸法、マインドフルネスといったストレス管理技術を学び、日々実践することが有効です。また、トラウマ体験を処理するための心理的な支援を受けることも、フラッシュバックの予防に繋がります。自分自身の感情や思考を理解し、過去のトラウマに対する適切な対処法を身につけることが重要です。
フラッシュバックが起きた際は、まず落ち着いて深呼吸をし、現在の環境に意識を集中させることが大切です。現実感を取り戻すために、五感を使って周囲の状況を確認し、目の前の物を触る、音を聞くなどして、過去の体験と現在の自分を区別できるようにします。また、安心できる場所に移動したり、信頼できる人に話を聞いてもらうことで、心を落ち着けることも助けになります。
はい、フラッシュバックが頻繁に起こる場合は、専門家の助けを受けることが非常に重要です。心理カウンセラーや精神科医などの専門家は、フラッシュバックの原因となるトラウマを適切に処理するための治療法を提供します。また、専門家はクライエントのペースに合わせて治療を進め、フラッシュバックを軽減させるための具体的な支援を行います。早期に支援を受けることで、症状の悪化を防ぐことができます。
フラッシュバックの治療法としては、認知行動療法(CBT)やEMDR(眼球運動による脱感作と再処理療法)などが効果的です。認知行動療法は、トラウマに関連する思考や感情を整理し、日常生活でのストレスや不安を減らす方法を学びます。EMDRは、目の動きを使ってトラウマ記憶を再処理し、過去の体験の感情的な負荷を軽減します。これらの治療法は、フラッシュバックの頻度や強度を減らし、回復をサポートするために非常に効果的です。
フラッシュバックは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の主要な症状の一つです。PTSDは、過去に経験した極度のトラウマが原因で、フラッシュバックを含む多くの症状を引き起こします。PTSDのクライエントは、フラッシュバックや悪夢、過剰な警戒心、感情の麻痺などが繰り返し現れ、日常生活に大きな支障をきたします。したがって、PTSDの治療にはフラッシュバックへの対処も重要な部分となります。
フラッシュバックの予防には、日常生活の中でのストレス管理が非常に重要です。規則正しい生活、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることで、心身の健康を保つことができます。また、リラクゼーション法や瞑想、マインドフルネスなどを取り入れることで、心の安定を図ることができ、フラッシュバックの発生を抑える効果が期待できます。さらに、トラウマ体験を適切に処理するために専門家のサポートを受けることも、予防に繋がります。
フラッシュバックについての相談をしたい方は
こうしたフラッシュバックはPTSDでよく起こる症状です。PTSDについて更に詳しく知りたい人は以下のページをご覧ください。
また、フラッシュバックは非常に苦痛な体験です。ですので、ただ耐えて、我慢するだけではなく、臨床心理士や医師などの専門家にまずは相談すると良いでしょう。当オフィスでもフラッシュバックについての相談を受けて受けています。相談を希望する方は以下のページからお問い合せしてください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。