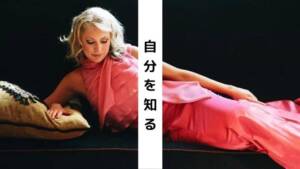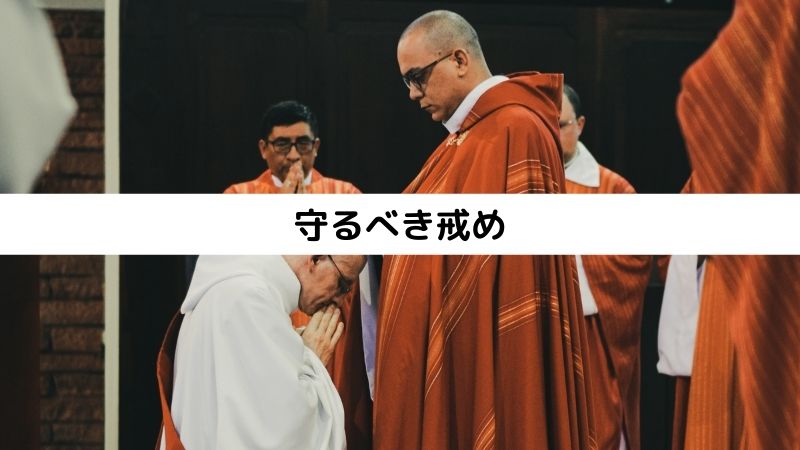カウンセラーの倫理と境界侵犯

カウンセラーによる境界侵犯や倫理違反は時折見かけられます。学会誌や学術誌などで倫理違反の処分が発表されることもありますし、事件となって報道によって知らされることもあります。
この記事ではカウンセラーによるクライエントに対する境界侵犯や倫理違反について書いていきます。
目次
境界侵犯とは

境界侵犯とは、カウンセラーとクライエントとの間にあらかじめ設定されている専門的な枠組みや距離感を逸脱する行為を指します。カウンセリングは、安心して話せる安全な空間と明確な役割分担を基盤として成立しますが、その枠が崩れると信頼関係や治療的効果に深刻な影響を及ぼします。境界侵犯の例としては、面接時間外での過剰な私的連絡、金銭や物品の授受、プライベートでの交流や依頼、性的接触、友人関係化などがあります。
一見すると親密さや支援の延長に見える場合でも、クライエントの心理的安全性を損ね、依存や混乱、再トラウマ化を引き起こす危険があります。多くの場合、援助者側の未解決な感情や承認欲求、救済願望などが無自覚に作用し、境界があいまいになることで発生します。
そのため、カウンセラーは自己理解を深め、感情や衝動を適切に管理しながら、倫理的ガイドラインや契約内容を守ることが求められます。境界を保つことは単なる規則遵守ではなく、クライエントの回復を支える安全な土台を維持するための不可欠な専門的姿勢です。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 男性
Aさんは大学院修了後から臨床心理士として医療機関や民間のカウンセリングルームで経験を積んできた。幼少期は両親の不和の中で家族の「聞き役」として振る舞い、衝突を避けて相手の気持ちを優先することが習慣化していた。愛情や安定を保つために、自分の感情や欲求を抑えてでも相手に応じる関わり方が身につき、それは成人後の人間関係にも影響を及ぼしていた。臨床経験を重ねる中で、ある女性クライエントとの関係が徐々に境界を逸脱していった。きっかけはセッション外での私的なやり取りや相談への応答で、当初は支援の延長と考えていたが、やがて面接時間外の接触や個人的感情の混入が増え、専門家としての一線を越えてしまった。クライエントの求めに過剰に応じ、自分の負担や不安を後回しにするような関係パターンが、無意識のうちに再現されていたのである。やがてクライエントからの指摘や同僚の助言を受け、自責と混乱の中で臨床の継続が困難になり、自身の内面の課題を見直す必要性を痛感した。
職場の上司の勧めもあり、専門的な自己理解と倫理的態度の再構築を目的として教育分析を受けることを決意した。初回面接では、境界侵犯に至った経緯や背景、過去の対人パターンを振り返る中で、承認を得るために過剰に相手に応じ、自己犠牲的に振る舞う傾向が改めて浮き彫りになった。分析の過程では、この関係パターンがクライエントとのやり取りで無意識に再演され、自分の未解決の感情や依存的な側面を刺激していたことを少しずつ理解していった。
分析者との安全な関係の中で、相手の期待に沿わない選択をあえてしてみる、衝動や葛藤をその場で言語化するなどの試みを重ねることで、安易な行動化を避けられるようになった。3年にわたる教育分析を経て、Aさんは以前よりも冷静にクライエントの感情と自分の感情を区別できるようになり、面接の枠組みを守ることが双方の安全を保障する行為であると実感した。教育分析での経験は、危機からの回復にとどまらず、専門家としての倫理観と自己理解を深める契機となった。
カウンセラーとクライエントとの性的接触の経験
少し古い調査研究になりますが、Pope,K,S.(1987)がカウンセラーとクライエントの性的接触の経験の有無を調べたことがあります。それによると、結果は以下の通りです。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| クライエントが服を脱ぐのを許す | 4.4% |
| クライエントとエロチックな行動を行う | 2.6% |
| かつてのクライエントと性的な接触をもつ | 11.1% |
| クライエントと性的な接触をもつ | 1.9% |
この結果は米国のものですが、おそらく日本でも同様の数値が出るのではないかと推測します。この数値が高いとみるか低いと見るかは人にもよるでしょうが、50人カウンセラーがいたら、1人はクライエントと性的接触をもっているという計算です。
Aさんは、ある女性クライエントとの関係の中で、面接枠を越えた私的接触を重ねるうちに、徐々に身体的な関係を持つに至った。当初は感情的な支え合いの延長のように感じていたが、やがて専門家としての一線を越えた重大な境界侵犯であることを自覚し、強い罪悪感と混乱を抱えるようになった。
境界侵犯するカウンセラーの4つのタイプ
そして、Gabbard,G,O.らはカウンセラーがクライエントと不適切な関係をもつことを「境界侵犯」と定義しています。その境界侵犯をするカウンセラーを以下の4タイプに類型しています。
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| 精神病性障害 | 病的万能感、躁病エピソード、妄想様症状など |
| 搾取的サイコパスと性倒錯 | 反社会的性格や自己愛パーソナリティ |
| 恋わずらい | 自己愛的な傷つきと不安定さ、満たされないプライベート、愛情に飢えている、その結果患者に恋をする |
| マゾヒスティックな服従 | 患者の無茶な要求に従ううちにエスカレートし、境界侵犯に陥る |
この4タイプのいずれも多かれ少なかれ自己愛の問題が絡んでいると指摘しています。こうした境界侵犯を犯すカウンセラーは自己愛やパーソナリティの問題があるので、何度も繰り返します。そのため、カウンセラーに対する治療が必要であるし、時には資格剥奪などの処分も必要でしょう。
ただ、こうしたケースを単に特別なものであり、特殊な人が起こす、非常に稀なことであり、自分自身とは関係ない、と想定することが一番危険であると思います。自動車事故は自分には関係ない、と考える危険と同様かと思います。
Aさんの場合、相手の求めに過剰に応じてしまう傾向が強く、自分の欲求や限界を後回しにしてしまう「マゾヒスティックな服従」に該当していた。その背景には、幼少期から身についた相手優先の対人パターンがあり、クライエントの依存や要望を断りにくい性質が影響していた。
逆転移と倫理
そうではなく、自分自身も条件やタイミングが重なれば境界侵犯に滑り落ちてしまうかもしれない、と注意しておくことが大事でしょう。なぜなら、臨床的には、クライエントに対して様々な思いをカウンセラーとして抱くことはあります。いわゆる逆転移です。
(1)モニタリングツールとしての逆転移
逆転移は個人的な問題については、自身が教育分析を受けたり、スーパービジョンを受けたりして、乗り越える必要があります。
そして、逆転移にはもう一つの側面があります。それはクライエントとの関係性をモニタリングするツールという側面です。逆転移で感知したことをアセスメントや対応に活用するということです。おそらく、そうした活用をするために我々は研鑽を積み、知識を得、訓練を繰り返すのでしょう。逆転移のなかにはもしかしたら恋愛感情的なものが含まれることもあるかもしれません。専門家であれば、それは理解のために利用します。
けっして、行動化して、カウンセラー自身の欲望成就に至ってはいけません。それをしてしまうのがギャバードの4タイプの人であると同時に、我々のような平均的なカウンセラーでもそうしてしまうリスクを常に抱えています。ですので、境界侵犯に滑り落ちたカウンセラーを非難するだけでは、この問題は解決しないでしょう。そうしたことを教訓にして、自身がどのように理解し、どのように訓練するのか、を考えることが専門家として求められます。つまり、自分自身の問題だと捉えなおすのです。
逆転移やその取扱い方についての詳細は以下に書いています。
Aさんは教育分析の中で、自身の感情や衝動がクライエントとの関係でどのように動くのかを丁寧に観察し、それを「逆転移」として理解することで、無自覚な行動化の兆しを早期に察知できるようになった。
(2)倫理の重要性と面白さ
私は以前に自主シンポではありますが、カウンセラーの心の中の非倫理的な逆転移の扱いについて発表したことがあります。非倫理的な逆転移を抑え込んで、なかったことにすることではなく、むろん行動化することでもなく、どのように治療に転換させていくのかを論じました。
倫理についてのセミナーは不人気であると聞き及んでいます。おそらく、「してはいけない」「やってはいけない」と断罪されたり、叱られたりするというイメージがあるのでしょう。また、「私には関係ない」という想定もあるのかもしれません。
しかし、倫理は非常に面白いと私は思っています。倫理を巡って、何を感じ、何を考え、どう行動するのか、に極めてリアリティある我々の心が見て取れるからです。また、倫理ほど臨床に活用できる概念は無いとも思っています。
長期にわたる分析を経て、Aさんは倫理を単なる制約としてではなく、クライエントの成長と安全を守るための創造的な枠組みとして捉えられるようになった。その学びは、臨床の質を高める上で欠かせない知的刺激と実践的価値を伴うものとなった。
まとめ
カウンセラーによる境界侵犯や倫理違反はクライエントの福祉に反するので、絶対的に行ってはいけないことです。そして、それらは特殊な人がするのではなく、平均的なカウンセラーでも時と状況によって境界侵犯や倫理違反に滑り落ちてしまうこともあります。だからこそ、自分自身には関係がない、とするのではなく、常日頃から点検し、振り返る必要があります。
カウンセラーが自らを振り返る作業はスーパービジョンや教育分析を通して行われます。(株)心理オフィスKでは臨床心理士や公認心理師といったカウンセラーだけではなく、広い意味での対人援助職の方々に対してスーパービジョンや教育分析を行っています。
スーパービジョンや教育分析についての詳細は以下のページをご参照ください。
スーパービジョンや教育分析を希望される方は以下の申し込みフォームからご連絡を頂けたらと思います。
参考文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。