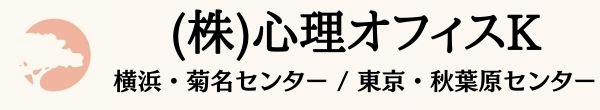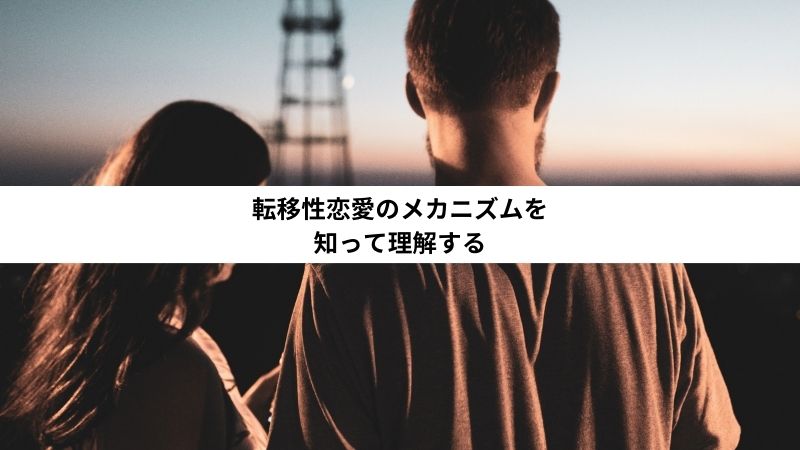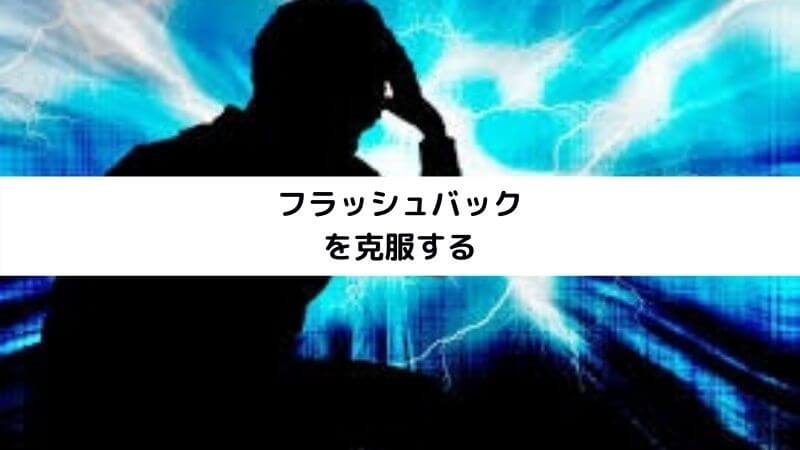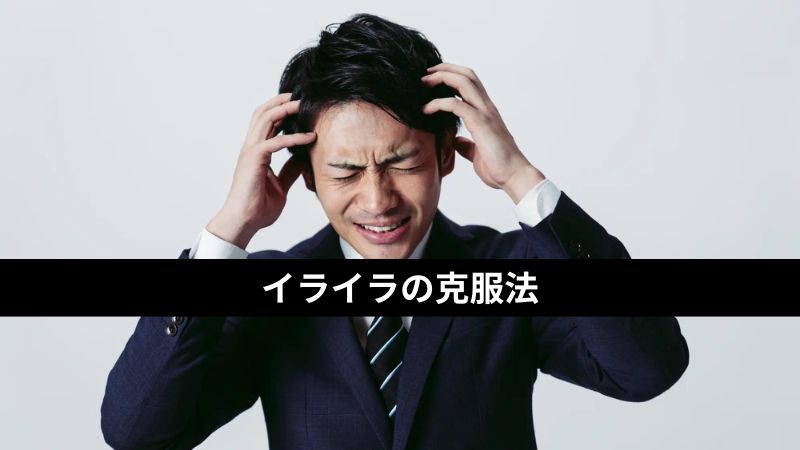対象喪失とは何か?回復するために必要な心のケア
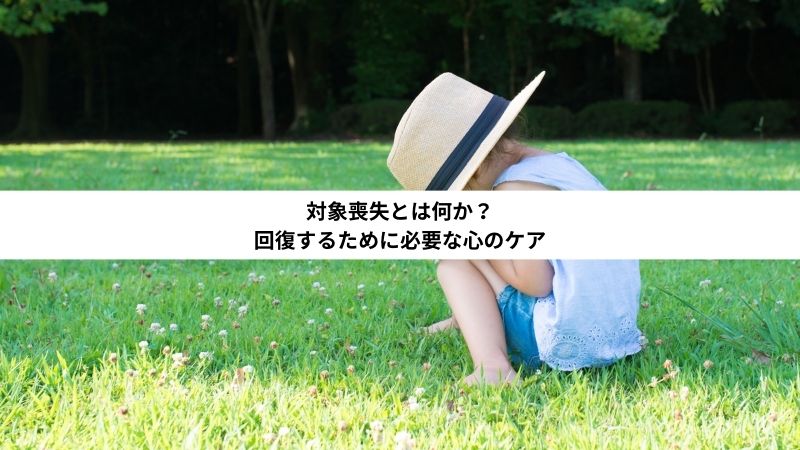
愛着や依存の対象を失う対象喪失は、ライフイベント上で最も重大なストレスといわれ、さまざまな心身の反応や症状を生じさせます。対象喪失を乗り越えるには、喪失から生じた悲嘆の感情を自由に語り、受け止められる場が重要な役割を果たします。
支援の場の一つとして、カウンセリングもご活用ください。
目次
対象喪失とは

対象喪失とは、愛着や依存の対象を失う体験を指す概念のことで、フロイトによって提起されました。
喪失の対象は、単なる物や人にとどまりません。対象喪失の中でも、物理的・外的な対象喪失は、外的対象喪失といわれます。たとえば、近親者の死や生き別れ、失恋、引っ越しや転勤、身体の器官や機能の一部などは、外的対象喪失です。
一方、心理的・内的な対象喪失は、内的対象喪失といわれます。たとえば、幻想上の自己像や恋人像を失ったり、理想化していた親に幻滅したりする体験は、脱錯覚、脱理想などと呼ばれ、内的対象喪失に含まれます。内的対象喪失は、その人の心の中で起こるものです。
また、役割や仕事、家庭、自分自身の若さや健康なども喪失の対象となります。特に、配偶者の死や別離、近親者の死は、最もストレスの度合いが高いライフイベントと位置付けられています。対象喪失は、特に重大な精神的ストレスをもたらすのです。
よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 女性
Aさんは、小さい頃から家族の中でしっかり者として期待され、幼少期には両親や兄弟との関係も比較的良好でした。しかし、思春期に父親が病気で他界し、その喪失体験はAさんの心に深く刻まれました。成人してからは結婚し、二人の子どもにも恵まれ、家庭を支える日々を送ってきましたが、夫とは価値観の違いからすれ違うことも多く、次第に孤独感を感じるようになっていきました。
そんな中、最も信頼していた母親が突然倒れ、急逝しました。母親はAさんにとって唯一無二の相談相手であり、心の支えでもあったため、喪失感は非常に大きく、その後Aさんは深い悲しみに包まれました。日常生活でも気力が湧かず、何事にも興味を持てなくなり、仕事にも集中できずミスが増え、家事や子育てもおろそかになっていきました。夜はなかなか眠れず、食事もとれない日が続き、体調も崩しがちになりました。身近な友人や家族も気づき、心療内科を受診するよう勧められました。
Aさんは心療内科を受診し、軽度のうつ病と診断され、抗うつ薬を処方されました。薬を服用しながら、医師の勧めでカウンセリングも受けることになりました。初回のカウンセリングでは、母親の死後、自分の存在価値を見失い、「自分は誰からも必要とされていないのではないか」という思いが強くなっていることが明らかになりました。カウンセラーはAさんが自分の悲しみや孤独、怒りの感情を少しずつ言葉にできるようサポートしました。数回の面接を重ねるうちに、Aさんは母親に対する思いだけでなく、自分自身がこれまで家族の中で担ってきた役割や、周囲からの期待に応えようと無理をしてきたことにも気づくようになりました。
時間をかけて悲しみを受けとめ、感情を表現することを続ける中で、Aさんの気分は徐々に安定し、少しずつ日常生活への意欲が戻ってきました。また、家族との関係にも変化が生まれ、「頼ること」や「助けを求めること」ができるようになったことで、以前よりも自分の気持ちを大切にできるようになりました。現在では、母親との思い出を悲しみだけでなく温かいものとして振り返ることもできるようになり、新たな一歩を踏み出せるようになっています。
対象喪失の症状と反応

対象喪失を経験した後には、さまざまな反応や症状が表れます。生じる反応の強さや持続期間によっては、治療の必要な症状となることもあります。
(1)対象喪失の反応
対象喪失という圧倒的な出来事に遭った直後に生じる反応はさまざまです。たとえば、悲しみ、怒り、恐怖感、無力感、罪悪感といった感情が湧き起こります。
また、突然の出来事で衝撃が大き過ぎる場合は、現実感を失ったり、事実を認められなかったりすることもあります。たとえば、突然の死別や離別を経験した場合、現実をすぐに受け入れるのは困難です。そのため、故人が「帰ってくるから待っている」などと、今でも生きているかのように振る舞うことや、「失ったことが現実になってしまう」という思いから、援助を拒否することもあります。
Aさんは、最愛の母親を亡くしたことで、強い悲しみと喪失感に襲われました。日常生活の中でも、母親の存在がどれほど自分にとって大きな支えだったかを改めて感じ、涙が止まらなくなることや、気分が落ち込み何も手につかない時間が続きました。
(2)対象喪失の症状
対象喪失を経験した後の反応が、心身の症状として表れることがあります。
たとえば、頭痛や胃腸障害、疲れやすさ、食欲低下、不眠、息切れ、不安、抑うつといった症状が挙げられます。こうしたさまざまな心身の不調には、失意や絶望、うつといった悲嘆の心理が影響しているといわれます。
悲嘆の心理状態はさまざまな病気への抵抗力を弱めてしまうため、対象喪失を経験した人は病気にかかりやすく、死亡率が高いとの報告もあります。対象喪失のもたらす心理状態は、心身の不調や病気、時には死の原因にもなってしまうのです。
Aさんの場合、抑うつ気分、不眠、食欲低下、仕事や家事への集中力の低下など、典型的な喪失反応が見られました。また、周囲とのコミュニケーションも減り、孤立感が深まっていきました。
対象喪失の悲哀の過程

喪失をどのように心におさめていくかは、臨床心理学における大きなテーマです。対象喪失の引き起こす心の営みは「喪(あるいは悲哀)の仕事」「モーニング・ワーク」と呼ばれ、その過程は「モーニング・プロセス」と呼ばれています。
ここでは、喪の作業についての理論のうち、ボウルビィとキューブラー・ロスによる理論を紹介します。いずれにおいても、対象喪失を経験した人は、喪の過程(悲哀の過程)を経ることで、徐々に愛着や依存の対象から離れられるようになり、ふたたび心の安定を得る方向に向かうと考えられています。
(1)ボウルビィの4段階
英国の精神分析学者であるボウルビィは、乳幼児の対象喪失に関する研究を通じて、対象喪失に続くモーニングは4つの段階をたどるとしました。
|
段階 |
テーマ |
説明 |
|---|---|---|
|
第一段階 |
情緒的危機 |
数時間から1週間ほど無感覚の状態が続き、だんだんと強い情緒が引き起こされます。一種の急性のストレス反応です。
突然の事故や別れにより激しい衝撃を受け、興奮や不安、心細さや挫折感、「どうしよう」とこれからを模索するといった心理状態が続きます。 |
|
第二段階 |
抗議 |
喪失の現実を認められず、失った対象を求めたり、対象がいるかのように振る舞ったりする状態が数か月、場合によっては数年続きます。
たとえば、失った親が戻ってくるのを期待して子どもが探し求める、恋人と別れた後も何度も相手の気持ちを取り戻そうと努力する、といった行動に表れます。目の前にはいない対象への思いが、心の中では続いている状態です。 |
|
第三段階 |
断念 |
喪失の現実を受け入れ、激しい絶望感や失意を体験します。失った対象がもう絶対に戻ってこない現実を認めることで、失った対象と結び付いて成立していた心の在り方は解体してしまいます。
そして、激しい絶望感や失意に襲われたり、引きこもりや抑うつ、無気力状態に陥ったりします。 |
|
第四段階 |
離脱 |
失った対象への穏やかな感情が生まれ、立ち直ろうとします。
失った対象への愛着や執着から心が離れて自由になり、場合によっては別の対象に気持ちを向けられるようになります。新たな対象との結びつきに基づいて、新たな心の在り方を見出そうとする段階です。 |
Aさんは、ボウルビィの示した「ショック・否認」「渇望・探索」「絶望・無力感」「再組織化」という4段階のうち、母親の急死直後は現実感を持てず、否認と混乱の状態に陥りました。その後、母を求めて思い出をたどり、やがて深い悲しみと無力感を感じる時期を経て、徐々に母親の死を受け入れ始めました。
(2)キューブラー・ロスの5段階
死に臨む患者に対する精神医学的研究を行ったキューブラー・ロスは、死を予期した患者がたどる心的プロセスを5段階で示しました。
|
段階 |
テーマ |
説明 |
|---|---|---|
|
第一段階 |
死の否認と隔離 |
死の宣告を受けた患者はまず、衝撃と不信の反応を示し、事実を否認します。
たとえば、自分が死に至る病気であることは、医者の誤診や機械の故障のせいだと考えるといった反応です。事実を認めないことは、衝撃を和らげる働きでもあります。 |
|
第二段階 |
怒り |
否認を続けられなくなると怒りの感情に襲われ、「なぜ私なのか」と、健康な人への羨望を感じることもあります。そうした感情は、家族や医療従事者といった周囲の人々への攻撃として表現されます。
周囲の人々がそれを理解し、受け止めることで、患者は続く「取り引き」「抑うつ」を経験できるようになります。 |
|
第三段階 |
取り引き |
よい行いをすることで神や周囲の人たちから報酬を得ようとする「取り引き」が、心の中に生じる段階です。
「何でも言うことを聞くから治してほしい」「どんなに痛くても恐ろしくても耐えるから治してほしい」といった思いを抱きます。 |
|
第四段階 |
抑うつ |
それでも死が避けられないと分かると、大きな喪失感を抱くようになり、抑うつ感情が生じます。
喪失には、身体の衰弱や経済的負担、家庭生活の崩壊などのさまざまな局面があり、こうした喪失に伴って生じる「反応性抑うつ」と、世界との訣別を覚悟しなければならないことへの「準備抑うつ」の2種類の抑うつが体験されるといわれます。 |
|
第五段階 |
死の受容 |
十分な時間が残されている場合は、死を迎える運命に怒りも抑うつも覚えなくなる「受容」の段階に至ります。
この頃にはウトウトとまどろむことが多くなり、周囲への執着もなくなり、死を迎える準備が整います。 |
ただし、これらの各段階は明確に区別されるものではなく、重なり合ったり、表れたり消えたり、逆戻りしたり、同じ段階を繰り返したどったり、しばらく同じ段階にとどまり続けたりすることもあります。
Aさんの場合、最初は「否認」から始まり、「怒り」「取引」「抑うつ」という段階を経て、最終的には「受容」へと至りました。特に抑うつの段階では自分を責める思いも強くなりましたが、時間とともに少しずつ気持ちを整理できるようになりました。
対象喪失の乗り越え方

大切な人やペットとの別れを経験するなど、対象喪失を経験したら、どのようにその悲しみを乗り越えていけばよいのでしょうか。
ここでは、対象喪失の乗り越え方として、病院を受診すること、悲しみを分かち合う場に参加すること、カウンセリングを受けることについて紹介します。
(1)病院を受診する
対象喪失の後にさまざまな心身の不調や症状がみられる場合には、病院の受診を検討しましょう。
必要に応じて投薬治療などの専門的治療や、心理教育などが行われます。中には、死別体験者を対象とした「グリーフケア外来」を設置している病院もあり、必要に応じたさまざまな援助を受けられます。
また、地域の自助グループや相談室、日常的な困り事に対応できる外部専門機関などを紹介している病院もあります。
Aさんは、心身の不調を感じたため心療内科を受診し、医師からうつ病と診断され、薬物療法と休養を勧められました。この診断をきっかけに、自分が抱えている状態について理解が深まりました。
(2)悲しみを分かち合う場に参加する
大切な人との死別を経験した場合、悲しみを分かち合う場に参加するのも一つの方法です。悲しみを分かち合う場には、子どもを失う経験をした親の集まる遺族会や、地域の自助グループなどがあります。同じ死別を経験した人の話を聞き、交流することを通じて「自分だけが特別ではない」と思えるようになるかもしれません。
また、日常ではなかなか人に打ち明けにくい話も自由に語れることで、感情を解放させることができ、苦しみが軽くなることも期待できます。そして、素直な感情を他者に受け止めてもらえる体験は、ありのままの自分を認められることにもつながっていくでしょう。
Aさんの場合、遺族の会など、同じような体験をした人々と悲しみを分かち合う場にも参加しました。他の人の体験を聞いたり、自分の思いを語ることで、孤独感が和らぎ、支えを感じることができました。
(3)カウンセリングを受ける
思いを自由に語る場として、カウンセリングも役立ちます。
対象喪失の悲しみとともに生きる在り方を見出していくためには、自分の抱える思いをそのまま受け止め、理解してくれる他者が必要です。喪失にまつわる思いを1人で抱えていると、混沌としたどうしようもない苦しみに飲み込まれた状態のままですが、その耐えがたさや切実さを他者に語り、受け止められることを通じて、内面をいったん自己から切り離すことができます。
そして、失った対象をただ忘れようとするのではなく、良い思い出や失った苦しみなどのさまざまな思いを行き来しながら語っていく中で、失った対象のいない世界の意味が再び見出されていくでしょう。対象喪失を経験した人が、失った対象のいない世界の意味をつくり出していく道のりを、支援者は傍らで支えていきます。
Aさんは、医師の勧めでカウンセリングも始めました。カウンセラーとともに、母親との関係や自分の感情を丁寧に振り返りながら、悲しみや怒り、不安などの気持ちを少しずつ表現できるようになりました。カウンセリングを通じて、Aさんは再び自分の生活に目を向け、徐々に前向きな気持ちを取り戻しています。
対象喪失についてのよくある質問
対象喪失とは、感情的に強く結びついていた人、物、または環境を失うことを指します。これには、身近な人の死、離婚、ペットの死、引っ越しによる環境の変化など、さまざまな出来事が含まれます。対象喪失は心理的に大きな影響を与えるため、喪失感や孤独感を強く感じることがあります。この感情は一時的なものから長期間にわたるものまで様々で、個人の価値観や過去の経験によっても異なります。喪失をどう捉え、どのように向き合うかが回復の速度に影響を与えます。
対象喪失に伴う症状は、心理的なものから身体的なものまで広範囲にわたります。一般的には、深い悲しみや涙が止まらない、食欲がなくなる、睡眠に問題が生じる、仕事や日常生活に集中できなくなるなどがあります。身体的には、肩こりや頭痛、胃の不調などが見られることもあります。感情面では孤独感や不安、罪悪感、無力感を抱くことが多く、日常生活に支障をきたすことがあります。これらの症状は、喪失後すぐに現れることが多いですが、時間が経っても続くことがあり、深刻な場合は専門家の支援が必要になることもあります。
対象喪失からの回復には、まず喪失による悲しみや痛みを認識し、それを受け入れることが重要です。回復のためには、感情を無理に抑え込まずに自分の感情に正直になることが大切です。信頼できる友人や家族と話をすることや、カウンセリングを受けることで心の整理がつきやすくなります。また、日々の生活に小さな楽しみを見つけることも回復を助けます。運動や趣味、外出など、自分が楽しいと感じることを積極的に取り入れることが有効です。最も大事なのは、回復には時間がかかることを理解し、無理せず自分のペースで前に進むことです。
対象喪失の影響を受けやすい人には、過去に重大な喪失経験を持っている人や、感情を抑え込みがちな人、または感情的なサポートを受ける機会が少ない人が多いです。過去のトラウマやストレスフルな状況に対する耐性が低いと、喪失後の影響が長引くことがあります。また、社会的に孤立している人や、心身ともに健康に問題がある場合も影響を受けやすいです。これらの人々は、喪失を乗り越えるために支援を求めることが重要です。心理的な支援やカウンセリングを受けることで、回復が促進されます。
対象喪失が原因でうつ病を発症することはあります。特に、喪失を深く悲しみ、感情が整理できないままでいると、うつ病に至る可能性があります。喪失後に無気力感、興味の喪失、絶望感などが長期間続く場合、うつ病の症状と重なることがあり、注意が必要です。また、喪失をきっかけに過去の未解決の感情が表面化することもあります。うつ病と診断される前に、早期に専門家の診断を受けることが重要です。回復には専門的なカウンセリングや治療が効果的です。
子どもは対象喪失に対して非常に敏感であり、その反応は年齢や発達段階に応じて異なります。小さな子どもは喪失の意味を理解するのが難しく、混乱や不安を感じやすいです。例えば、親の死や家庭内の変化が子どもに大きな影響を与えることがあります。年齢が上がるにつれて、喪失の理解度が増すものの、悲しみや怒り、孤独感を抱くこともあります。こうした場合には、子どもが自分の感情を表現できるようにサポートし、感情を共有できる環境を提供することが大切です。大人が積極的に支援し、子どもの感情を理解することが回復を助けます。
対象喪失からの回復には個人差があり、数週間から数ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。喪失の種類やその人の感情の処理の仕方、社会的支援が回復のスピードに大きく影響します。また、回復には無理をせず、時間をかけて少しずつ進んでいくことが大切です。感情が整理される過程は人それぞれ異なり、長い時間を要することもあります。そのため、焦らず自分のペースで回復を目指すことが、心身の健康を保つためには重要です。
対象喪失に関する専門的なサポートは、心理カウンセリングや精神科の医師によるサポートを通じて受けることができます。カウンセラーは、喪失に対する感情を整理する手助けをし、適切な対処法を提案してくれます。また、必要に応じて、医師が精神的なサポートを行ったり、薬物治療を行うこともあります。地域の保健所や医療機関、またはオンラインでの相談サービスも利用できます。専門家による支援は、回復を促進し、適切な対処法を学ぶために非常に役立ちます。
対象喪失後は、心理的なストレスが身体的な健康にも影響を与えることがあります。そのため、規則正しい生活習慣を保つことが大切です。例えば、バランスの取れた食事を摂取し、十分な睡眠を確保することが重要です。また、適度な運動を取り入れ、ストレスを発散することが健康を保つために役立ちます。リラックス法としては、深呼吸や瞑想、ヨガなども効果的です。生活習慣を整えることで、精神的な健康を支えることができます。
対象喪失を経験した人をサポートするためには、まず相手の気持ちを理解し、共感することが大切です。無理に励ますことなく、相手が話したい時に聞いてあげることが最も効果的なサポートです。さらに、相手が孤立しないように、適度に関わりを持ち、日常的なサポートを提供することも重要です。相手が感情を表現しやすくなるように、安心感を与えることが回復を助けます。また、必要に応じて専門家に相談できるようにサポートすることも大切です。
対象喪失のカウンセリングを受けたい

愛着や依存の対象を失う対象喪失は、ライフイベント上で最も重大なストレスといわれ、心身にさまざまな症状や反応を生じさせます。
対象喪失を乗り越えるには、喪失にまつわる悲しみや苦しみなどの感情を自由に語り、受け止められる場が重要です。
支援の場の一つとして、カウンセリングもぜひご検討ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。