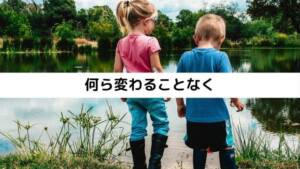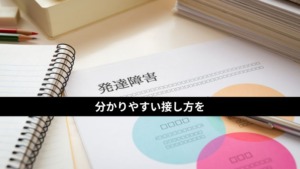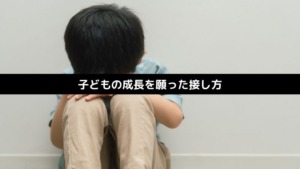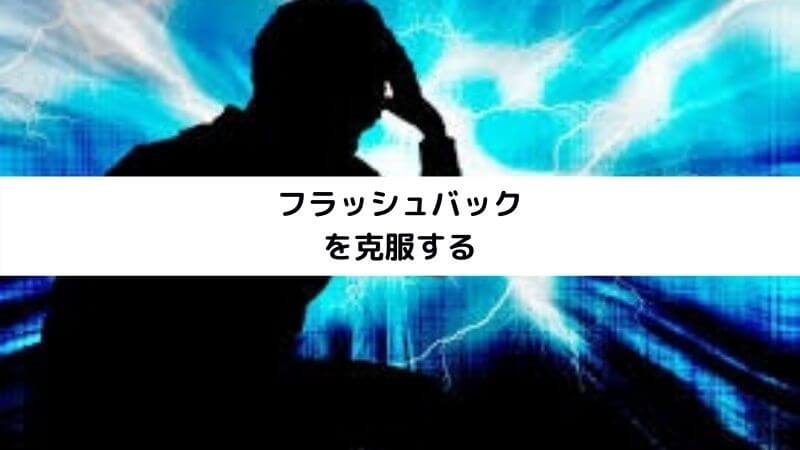自閉スペクトラム症(ASD)とは、社会性の障害、コミュニケーションの障害、想像力の障害、感覚過敏などの特徴をもつ発達障害のなかの一つです。ここでは自閉スペクトラム症の特徴、症状、種類、診断、治療、カウンセリングなどについて解説します。
目次
自閉スペクトラム症とは

自閉スペクトラム症の原因は主には生得的、遺伝的な要因が強く関係しています。特に中枢神経系の機能の障害ではないかといわれています。また、胎児期の母体の薬物や感染症も一部影響を受けているといわれることもありますが、まだまだ未解明なところが多いです。
自閉スペクトラム症は総称で、その中には自閉症やアスペルガー症候群、高機能自閉症などの分類があります。ちなみに自閉スペクトラム症のスペクトラムというのは健常と障害が地続きであり、量的な違いにすぎないということをあらわしています。ですので、健常に近いけど、自閉スペクトラム症的な要素が少しあるという場合もありますし、自閉スペクトラム症だけど、やや健常に近い、といったこともあらわれてきます。健常と障害のグレーゾーンといった言い方をされたりもします。
自閉症・アスペルガー症候群・高機能自閉症を分類すると以下のようになります。
表1 自閉スペクトラム症の分類
| 社会性の障害 | コミュニケーションの障害 | こだわり | 知能の低下 | |
|---|---|---|---|---|
| 自閉症 | ある | ある | ある | ある |
| アスペルガー症候群 | ある | なし | ある | なし |
| 高機能自閉症 | ある | ある | ある | ある |
自閉スペクトラム症は発達障害の下位カテゴリーです。上位カテゴリーの発達障害については以下のページをご参照ください。
よくある相談の例(モデルケース)
20歳代 男性
Aさんは、小学校低学年の頃から友人関係の構築に困難を感じていました。クラスメートとの遊び方が分からず、一人で過ごすことが多かったといいます。また、特定の話題に強い興味を示し、その話を延々と続ける傾向がありました。中学生になると、周囲とのコミュニケーションギャップがさらに顕著になり、いじめの対象となることもありました。高校進学後も状況は改善せず、孤立感や自己評価の低下が続きました。
大学生になったAさんは、アルバイト先やサークル活動でも人間関係の構築に苦労し、自分の特性に疑問を抱くようになりました。インターネットで情報を調べる中で、自閉スペクトラム症(ASD)の特徴が自分に当てはまるのではないかと考え、専門家の意見を求めることを決意しました。
カウンセリングを申し込んだAさんは、初回面談で幼少期から現在に至るまでの生育歴や人間関係の悩みを詳しく話しました。心理検査(WAIS-4やAQなど)や面接の結果、ASDの特性が見られることが確認されました。カウンセリングでは、Aさんの自己理解を深め、社会的スキルを向上させることを目指しました。具体的には、ソーシャルスキルトレーニング(SST)を通じて、適切なコミュニケーション方法や感情の表現方法を学びました。また、必要に応じて両親との面接も行い、Aさんの特性についてカウンセラーから説明を行いました。
カウンセリングを重ねる中で、Aさんは自分の特性を受け入れ、無理に周囲に合わせるのではなく、自分らしいコミュニケーションスタイルを築くことの重要性に気付きました。また、自分の興味や得意分野を活かせる環境を見つけることで、自己肯定感も向上しました。現在では、職場での人間関係も良好で、自分のペースで社会生活を送ることができています。
自閉スペクトラム症の症状と特徴
(1)自閉スペクトラム症の3つの症状
自閉スペクトラム症には以下の特徴・症状があります。
- 社会性の障害(社会的な常識を理解し、その場の状況は把握することが困難)
- コミュニケーションの障害(人と言葉のやりとりをすることが困難)
- 想像力の障害(柔軟性がなく、強いこだわりを示す)
コミュニケーションの障害とは言葉を用いて人と会話をしたり、考えや思いを伝達することに困難があることをさします。その他に書き言葉で話をしたり、過度に堅苦しい表現を用いた話をするなどがよく見られる特徴です。
社会性の障害は、コミュニケーションの障害とも多少は関係してきますが、人と良好な関係を築くことが苦手で、相手の気持ちや状況を推測したり把握したりすることができないことです。そのため時として一方的な人間関係になってしまい、学級や社会の中で孤立してしまいがちになります。
想像力の障害とは、柔軟性やこだわりの問題と言い換えても良いものです。例えば、些細なことに強い関心やこだわりをもったり、突発的な出来事に上手く対処できなかったり、無意味とも思える行動を何度も繰り返したりします。
この3つの特徴以外にも、ちょっとした物音や出来事に過度に反応してしまい、時にはパニック様になってしまう感覚過敏、味覚や触覚が適切に作動しない感覚異常、落ち着きのなさや立ち歩きなどの多動、などが見られることもあります。
Aさんはクラスメートとの遊び方が分からず、一人で過ごすことが多かったようで、このことから社会性の障害が疑われます。また、周囲とのコミュニケーションギャップがさらに顕著になったところがあり、これはコミュニケーションの障害と言えるでしょう。そして、特定の話題に強い興味を示し、その話を延々と続ける傾向があったことから、想像力の障害もあったと思われます。
(2)自閉スペクトラム症の3つの分類とその特徴
自閉症・アスペルガー症候群・高機能自閉症のそれぞれの症状について以下にまとめました。
- 自閉症
- 社会性の障害
- コミュニケーションの障害
- 想像力の障害
- 知的能力の低下
- アスペルガー症候群
- 社会性の障害
コミュニケーションの障害- 想像力の障害
知的能力の低下
- c.高機能自閉症
- 社会性の障害
- コミュニケーションの障害
- 想像力の障害
知的能力の低下
自閉症は3つの症状に加えて知的能力の低下があります。そして、アスペルガー症候群は自閉症の中でコミュニケーションの障害と知的能力の低下がない障害です。また、高機能自閉症は自閉症の中で知的能力の低下がない障害です。
このような特徴は多くは小児期・児童期に現れ始めますし、時には乳幼児期にも見られたりします。乳幼児のころでは、視線があわない、抱っこしにくい、変に育てやすい、痛みに鈍感、などの特徴があったりします。
また「大人の発達障害」が最近は問題になっています。子どものころはそこまで問題がなかったにも関わらず、社会人になり、就職したり、昇格した時期を境に問題が突然出現し、自閉スペクトラムがあらわになることもしばしば起こります。これは成人期に発症したということではありません。
もともとそうした特性があったが、比較的症状は軽かったので、目立たなかったし、問題としてあらわれなかっただけと言えるでしょう。それが仕事をはじめたり、昇格するなど様々なストレスや柔軟性が求められるようになることで、問題が顕在化したということです。
自閉スペクトラム症の診断

(1)生育歴から
自閉スペクトラム症の特徴や症状はほとんどの場合が幼少期からあらわれています。例えば、生まれて数ヶ月後から視線が合いますが、自閉スペクトラム症ではそうした視線が合いにくいということがよくあります。また、幼児は一つのことに熱中して、周りが見えにくくなることは一般的ですが、自閉スペクトラム症の場合にはそれが非常に強くあらわれます。2~3歳頃になるとお友達とそれとなく一緒に遊び始めますが、自閉スペクトラム症はそうした交流がなく、延々と一人で遊ぶだけのこともあります。
ですので、幼少期からの生活や行動、対人関係などを丁寧に聞き取ることが必要になります。本人に話を聞いて、聞き取ることもありますが、クライエントが幼児や児童であればうまく話をすることができないこともあります。また、成人でもあまり小さい頃のことは覚えていないこともあります。
そのため、保護者や家族からの聞き取りをすることもあります。さらには、子どもの頃の成績表や母子手帳を持ってきてもらうこともあります。
Aさんは少なくとも小学校の時期から自閉スペクトラム症の特徴や症状がみられてました。
(2)心理検査から
心理検査にはさまざまな種類がありますが、その中でも知能検査や発達検査をすることにより自閉スペクトラム症の診断をすることもあります。能力のアンバランス・能力の凸凹と俗に言われることもありますが、知能検査・発達検査では結果にそれが顕著に出てきます。平均以上の数値を出す部分もあれば、一方では平均以下の数値を出すこともあります。得意なところと苦手なところの差が大きいことがよく分かります。
自閉スペクトラム症でよく使う検査はWAIS-4(ウェクスラー成人知能検査)、WISC-4(ウェクスラー児童知能検査)などの知能検査があります。これは知能を全般的に、分析的に検討することができます。またCARS2、PARS、ADI-R、SCQなどの自閉スペクトラム症を発見、スクリーニングする検査もあります。
ただし、心理検査の数値だけで自閉スペクトラム症の診断ができるわけではありません。自閉スペクトラム症でも凸凹のない結果を心理検査で出す場合もあります。ですので、心理検査の結果は参考程度にする方が良いでしょう。
(株)心理オフィスKではWAIS-4があるので、成人の人の自閉スペクトラム症の検査は可能です。ただ、WISC-4がないので、児童に対してはできません。
自閉スペクトラム症の知能検査をご希望の方は以下からお申し込みしてください。
ちなみにAさんはカウンセリングを申し込んだ後、WAIS-4やAQの心理検査を受けています。
(3)行動観察から
自由遊びの場面や学習場面、職場での様子などで行動を観察し、そこから自閉スペクトラム症の特徴を把握します。さまざまな状況で実際に起こっている出来事を観察することで、よりよく自閉スペクトラム症の特徴を判断することができます。
例えば、自閉スペクトラム症の小学生などではクラスで授業を受けている場面を見させてもらうと、より際立ってわかります。授業に集中できず、自身の興味あること関心あることに熱心でいたりします。また、みんなが静かにしているところで、突然声を出したりすることもあるでしょう。
こうした様子は実際の場面を見ることで分かります。
自閉スペクトラム症の治療

また、現在では自閉スペクトラム症を根治する方法は残念ながらありません。しかし、それは手立てがない、ということではありません。対処療法的なことをしつつ、心理社会的なサポートを提供していくことがベストとなります。
(1)本人ができること
自閉スペクトラム症の本人ができることとしてはまずはご自身の特性をしっかりと理解することです。そのために心理検査を受けて特徴を知ることも必要でしょう。さらに、何度も繰り返されるパターンを見つけ、それがどういうことで起こるのかについて検討してみましょう。
そして、自閉スペクトラム症の方は極端にできる部分があったりします。そうしたところを伸ばし、ご自身の得意分野にしていくことです。歴代の天才や偉大な研究者のなかには自閉スペクトラム症の方が非常に多いのです。そこまでではなくても、得意な面を発見し、そこを特技にしていくことが良いかと思います。
また、そうした自身の特徴や特性を周りの人に伝えて、理解を得られるようにすることが大事です。カミングアウトすることはなかなか勇気のいることかもしれませんが、理解を得られると非常に生きやすくなるかと思います。
Aさんもカウンセリングを通して、自身の特徴について理解を深め、良いところを伸ばしていくような努力をしています。
(2)家族ができること
自閉スペクトラム症の家族の方ができることはとても大きいです。まず、自閉スペクトラム症のことを勉強し、その理解を深めることは大事です。自閉スペクトラム症の特徴であることが分かると対応も分かってきます。なによりも、それによってイライラすることはなくなるでしょう。
そして、自閉スペクトラム症ではない部分を発見してあげてください。つまり、自閉スペクトラム症とは関係のない個性を見つけることです。そうした個性に関わり、そこを伸ばしてあげると良いと思います。
自閉スペクトラム症では抽象的なことが苦手であったり、その場の雰囲気を把握することが苦手です。そのため、何かを伝える時やお願いする時、指示する時には、具体的に言う方が良いでしょう。
例えば、「綺麗にしなさい、掃除しなさい」ではどこを綺麗にすれば良いのか、掃除とはどこからどこまでするのかが分からないのです。適度にするということができません。ですので、例えば、「あなたの部屋の中の床に落ちているおもちゃを、この箱に入れなさい」というような具体的な働きかけをすると、自閉スペクトラム症の方は理解しやすくなるでしょう。
モデルケースでも親面接を必要に応じて行い、理解を促すことをしていました。
(3)家族支援
臨床心理士や児童精神科の医師など専門家による家族に対する助言やサポートを受けることができます。やはり家族なので、時には感情的になったりしてしまうこともあります。そうしたとき、冷静な第三者である専門家に相談し、助言をもらうことで的確な対応ができるようになります。
また、家族を支援する具体的な技法としてペアレントトレーニングなどがあります。これは子どもに対する対応を家族が学ぶ体系的なプログラムです。少人数のグループを作り、専門家による講義や実習、ワークなどを通して、育児方法を学ぶというものです。
このようなペアレントトレーニングを受けることで、自閉スペクトラム症の子どもへの対応が分かり、行動や態度が変容していきます。
(4)療育
療育(治療教育)とは行動分析や行動療法などをもちいたトレーニングになります。この療育のなかで対人関係のスキルを学んだり、さまざまな視点があることを発見するような課題に取り組んだりします。
こうした療育では勉強的な雰囲気だけでは自閉スペクトラム症の子どもは飽きてしまったり、苦痛を感じてしまったりします。ですので、遊び的な雰囲気を取り入れ、楽しく取り組めるような工夫をしたりします。
こうした療育は自治体などの療育センター、児童発達支援センター、放課後等デイサービスなどで行っています。
(5)薬物療法
自閉スペクトラム症は脳機能の障害ですが、薬物療法などで完治することはありません。しかし、薬物療法によっていくつかの症状をやわらげ、生活しやすくすることはできます。
自閉スペクトラム症によって様々なトラブルに見舞われて、抑うつ的になることもあります。また、パニックになってしまい、不穏な状態になることもあるでしょう。注意が散漫になり、落ち着きがなくなることもあります。
こうした時には抗うつ薬、気分安定薬、気分調整薬などが効果があります。
薬物療法を安易に使うことは戒めなければなりませんが、必要の応じて、必要な範囲で的確に使用することは大事だと思います。
当オフィスによる自閉スペクトラム症のカウンセリング

(1)本人に対するカウンセリング
自閉スペクトラム症の特徴を持っていると、社会の中では非常に生きづらい思いをしてしまいます。特に周囲から理解されなかったりすることは多いでしょう。能力のアンバランスもあるので、ちょっとしたことができなかったりするのですが、それをさぼっているとかわざと間違えているといった誤解をされてしまうこともあります。
こうした苦悩を吐き出し、気持ちを整理することはカウンセリングでできることです。そして、それだけにはとどまらず、実際にどのように振舞えば良いのか、どのように行動すれば良いのか、どのように伝えたら良いのか、などについてカウンセラーと話し合い、現実的な対処法を一緒に考えることができます。
このような相談が適宜できることで、精神的に安定して学校に行ったり、職場に行ったりすることができるようになるでしょう。
また、カウンセリングのなかで認知行動療法やソーシャルスキルトレーニングなどをすることにより、より適応的な行動や考え方にしていくことが可能です。例えば、悪い方にばかり考えてしまい、それによってますます苦痛が強くなるなどがあれば、認知行動療法などで思考や認知の妥当性をカウンセラーと一緒に検討し、より現実的で、より合理的な思考や認知に置き換えていく、などを行います。
認知行動療法についての詳細は以下をご覧ください。
(2)家族に対するカウンセリング
自閉スペクトラム症の人への家族としての対応に困られている人はとても多いでしょう。時にはイライラしてしまい、きついことを言ってしまうこともあるかもしれません。それがさらに強くなって、暴力的なことをしてしまい、あとで後悔・反省することもあるでしょう。精神的に追い詰められてしまうと、冷静な時には考えられないことをしてしまいます。
そうしたときカウンセリングのなかで、自閉スペクトラム症をもつ家族としての苦しみや悩み、怒りなどについてカウンセラーと話し合い、気持ちの整理をしていくことは非常に大切です。
そして、カウンセリングのなかで自閉スペクトラム症のことを学び、対応を検討します。カウンセラーと検討した対応を実際の家庭のなかで実践し、その結果をまたカウンセラーと話し合うことで、さらに次の対応を検討します。そうした繰り返しをしていくことで、家族として機能できるようになっていきます。
自閉スペクトラム症や発達障害についてのトピック
自閉スペクトラム症についてのよくある質問
自閉スペクトラム症(ASD)は、発達障害の一種で、社会的なコミュニケーションや対人関係の困難、特定の興味や行動への強いこだわりが特徴です。これらの特性は幼少期から現れ、日常生活に影響を及ぼします。原因は主に遺伝的要因や脳の働き方の違いによるもので、親の育て方が原因ではありません。症状や程度は個人によって異なり、知的障害を伴う場合もあれば、知的能力が高い場合もあります。早期の診断と適切な支援が本人の生活を豊かにする鍵となります。
自閉スペクトラム症(ASD)の主な症状には以下のようなものがあります:
- 社会的コミュニケーションの困難:会話や非言語的なサイン(視線、表情)の理解が難しい。
- 対人関係の構築の困難:友達作りが難しく、集団行動に馴染みにくい。
- 特定の興味や行動へのこだわり:特定の物や活動に執着し、それ以外に興味を示さない。
- 感覚の過敏さまたは鈍感さ:音や光に過敏であったり、逆に鈍感な場合がある。
これらの症状は個人差が大きく、日常生活に及ぼす影響も異なります。適切な支援が症状の緩和に役立ちます。
自閉スペクトラム症(ASD)の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因と脳の発達の違いが主に関与しているとされています。家族内でASDの発症率が高いことから、複数の遺伝子が関係していると考えられます。また、妊娠中の環境や母体の健康状態などの要因が、脳の発達に影響を与える可能性も示唆されています。ただし、親の育て方やしつけが原因ではないことが明らかになっています。
自閉スペクトラム症(ASD)の診断は、専門の医師や心理士による行動観察、発達歴の聴取、標準化された評価ツール(ADOS、ADI-Rなど)の使用を通じて行われます。また、他の発達障害や精神疾患との鑑別も行われます。診断のためには本人や家族の協力が不可欠で、ASDの特徴を総合的に評価して判断されます。早期診断が支援の開始を早め、本人の生活の質を向上させることに繋がります。
自閉スペクトラム症(ASD)を完全に治す治療法はありませんが、適切な療育や支援が症状の軽減に役立ちます。ABA(応用行動分析)や言語療法、作業療法などが広く用いられており、これらの方法はコミュニケーション能力や社会的スキルの向上を目的としています。また、特定の症状に対しては薬物療法が用いられる場合もあります。支援は個々のニーズに応じて調整されるべきで、専門家と連携して最適な方法を選ぶことが大切です。
自閉スペクトラム症(ASD)の人は、その特性に合った環境で能力を発揮することができます。例えば、データ入力やプログラミングなど集中力を活かせる仕事、製造業や品質管理など決まった手順を繰り返す作業、また特定の興味や知識を活かせる研究やデザイン分野が挙げられます。対人関係の負担が少ない職場環境が適している場合もあります。個々の強みを理解し、適切な支援を提供することで、社会での活躍が期待できます。
自閉スペクトラム症(ASD)は遺伝的な要因が大きく関与しているとされています。家族内でASDを持つ人がいる場合、他の家族メンバーにも発症する可能性が高まることが研究で示されています。ただし、遺伝子だけでなく、妊娠中の母体の環境や出生後の環境も関係しているため、単純に親から子へ遺伝するわけではありません。複数の要因が絡み合ってASDが発症すると考えられています。
自閉スペクトラム症(ASD)の子どもには、個性を尊重し、安心できる環境を提供することが重要です。言葉や指示を分かりやすく伝える、日常のルーチンを一定に保つ、小さな成功を積み重ねる、そして努力を褒めることが大切です。また、専門家のサポートを活用して、子どもの特性に応じた適切な支援を受けることが推奨されます。これにより、子どもが持つ可能性を最大限に引き出すことができます。
自閉スペクトラム症(ASD)の診断は一般的に3歳ごろまでに行われることが多いですが、1歳半から2歳ごろに症状が現れる場合もあります。早期の診断と支援が、本人の能力を引き出し、生活の質を向上させる鍵となります。親や保護者が子どもの行動や発達に気づいた際には、早めに専門家に相談することが推奨されます。
自閉スペクトラム症(ASD)の人が普通の学校に通うことは可能ですが、個々の特性や支援の必要性によります。特別支援教育が必要な場合もあれば、通常のクラスで適応できる場合もあります。学校や地域のサポート体制、教師の理解と協力が重要です。また、本人が必要な支援を受けられる環境を整えることで、学習の成果が向上し、より良い学校生活を送ることが期待できます。
自閉スペクトラム症のカウンセリングの申し込み

当オフィスで自閉スペクトラム症についての相談、カウンセリングを受けたいという方は以下の申し込みフォームからお問い合せください。