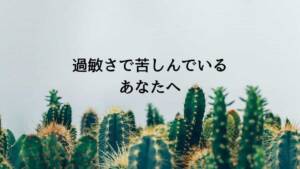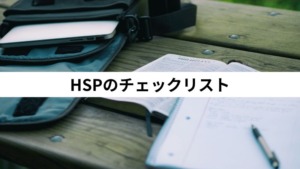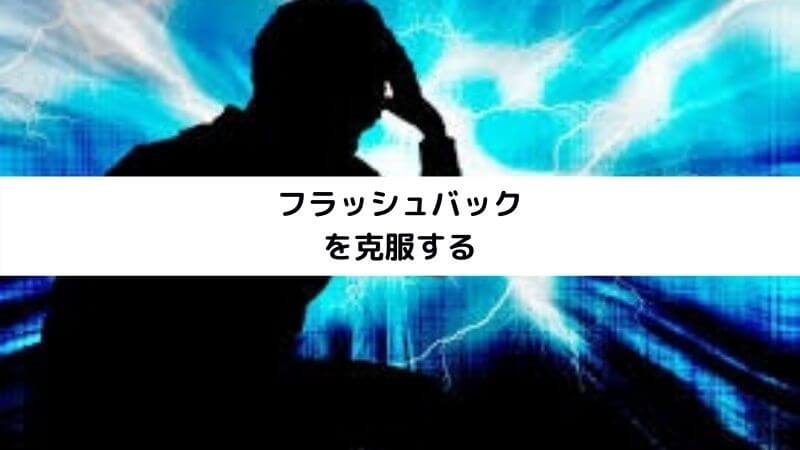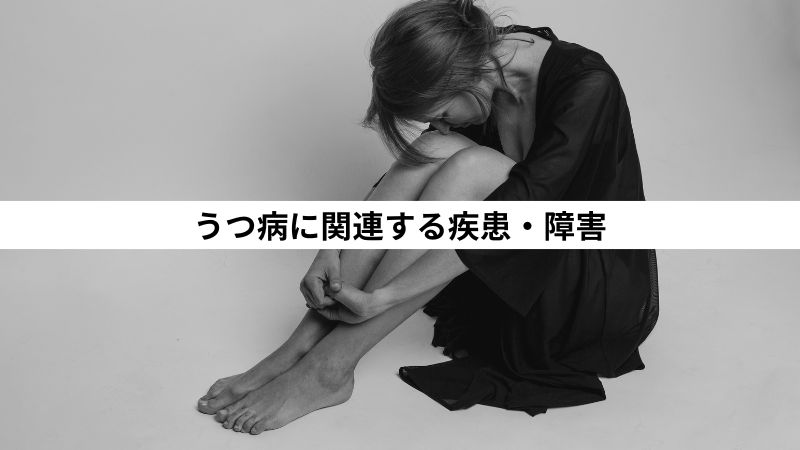感情移入しすぎる人とは

感情移入しすぎる人というのは身近に一人や二人はいるかもしれません。もしかしたら、ご自身がそうかもしれません。
感情移入しすぎる人はHSP(Highly Sensitive Person; 以下HSP)かもしれません。HSPとは、心理学者であるアーロン博士により定義された「生まれつき非常に繊細な人」で人口の約20%がその特性を有し、決して病気や障害ではないことが報告されています。HSPでは、幼少期より敏感・繊細の気質から生きづらさが続き、不安やうつになりやすい傾向があります。またその多くは出来事や人に対し、しばしば感情移入しすぎる傾向があります。
今回は「感情移入しすぎる人」の特性と対策について、HSPとの関連を中心に述べます。
目次
感情移入しすぎる人とは
感情移入しすぎる人、いわゆるHSP(Highly Sensitive Person)は、生まれつき感受性が高く、他人の感情や環境からの刺激に敏感な人を指します。病気ではなく、人口の約15~20%に見られる特性です。特徴としては、物事を深く考える追求心、騒音や光など刺激への過敏性、他者への強い共感、環境の微妙な変化に気づく感受性が挙げられます。
これらの特徴により、相手に合わせすぎて疲れやすく、情緒不安や不眠に悩むこともあります。自分の感受性を理解し、セルフケアや人との適切な距離を学ぶことで、生きづらさを和らげることができます。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは30代の女性で、子どもの頃から周囲の人の感情にとても敏感でした。幼少期には母親の気分が不安定で、機嫌が悪いと家の空気が一気に重くなるため、Aさんは常に母親の表情を伺い、先回りして行動することで安心を得ていました。学校でも友達が少しでも落ち込んでいると気づき、自分が何とかしなければと頑張りすぎて疲れてしまうことが多かったといいます。社会人になってからも、職場で同僚や上司の感情の変化を敏感に察知し、「自分のせいかもしれない」と過剰に責任を感じてしまい、帰宅後はぐったりして動けなくなる日が増えていきました。
心身の疲労から不眠や胃痛が出るようになり、内科で検査を受けても異常がなく、心療内科を受診しました。医師からは軽い自律神経の不調と診断され、睡眠導入剤を処方されましたが、根本的な改善には至らず、カウンセリングを勧められました。Aさんは「人の感情に巻き込まれてしまう自分を変えたい」と思い、当オフィスに申し込みました。
カウンセリングでは、まずAさんが他者の感情に過剰に同調してしまう背景を丁寧に整理しました。幼少期に母親の機嫌を読むことで安心を得てきた経験が、現在も人間関係で繰り返されていることが明らかになりました。セラピストは、Aさんが相手の気持ちと自分の気持ちを区別する練習を重ね、必要以上に他者の問題を引き受けない境界を意識できるよう支援しました。また、職場でのストレス場面を具体的に振り返り、実際にどの感情が自分のもので、どれが他者のものかを確認し、落ち着いて対応できるようになるまで繰り返し練習しました。
1〜3年かけて継続的に取り組む中で、Aさんは次第に自分の感情を優先して良いという感覚を取り戻し、相手の感情に引きずられずに関わることができるようになっていきました。以前は仕事終わりにぐったりしていた体も、適度に趣味を楽しめるほど回復し、対人関係の負担感も軽くなりました。現在は感情移入の力を生かしつつ、必要なときには距離をとるという柔軟な対応ができるようになり、生活全体のバランスが整っています。
感情移入しすぎる人(HSP)の4つの特徴
HSPは、以下の4つの特性が特徴的です。4つ共通することは、ある意味長所ですが、その程度によってはストレスを感じやすく疲れがたまりやすくなります。例えば、常に周囲にアンテナを張っていて、気が休まりにくい状態です。疲労しているときは余裕がなく、これ以上は無理となるとより繊細になり、悪循環に拍車がかかる傾向があります。
他人から見て「気が利く」と評価されがちな一方、疲労やストレスが溜まってしまいます。
(1)物事への深い追求心
物事を深く考えることは、物事の本質を見抜くのは長所です。しかし深く考えすぎることや、些細なことへの気づきは時にストレスになります。
Aさんは仕事でも趣味でも、一度興味を持つととことん掘り下げる傾向がありました。資料を徹底的に調べたり、相手の気持ちを理解しようと考え続けたりするため、エネルギーを使い果たしてしまうことが多く、疲れがたまりやすい状態でした。
(2)高度な共感性・協調性
他人の思考や言動に強く共感する姿勢は、コミュニケーションの基本で長所といえます。しかしそれが強すぎて自分が我慢することが多くなると、他人からは評価されても自身のストレスにつながります。
Aさんの場合、同僚や友人の小さな変化にも敏感に気づき、相手に合わせて行動することが自然にできました。しかしその分、自分の気持ちよりも相手の感情を優先しすぎてしまい、気づかないうちにストレスを溜めていました。
(3)刺激に対する過敏性
相手の言葉や行動に対し、敏感に感じ取ります。気づきという意味では長所ですが、その真意を読もうなど敏感になりすぎることはストレスにつながります。
Aさんは職場の騒音や人の怒鳴り声、強い照明などにとても敏感で、集中力が途切れたり、動悸や疲労感が強まったりすることがありました。
(4)五感で感じる環境変化への過敏性
五感で感じる環境変化(光・音・風など)に過敏になりやすい傾向です。日常の些細な刺激に対しても感性豊かになれるのは長所です。しかし敏感になりすぎることで注意力が散漫になったり、疲弊しやすい弱点があります。特に、「高度な共感性・協調性」と「刺激に対する過敏性」はアンテナの対象が自分の意思で変更しづらい他人であることから、「感情移入しすぎる人」には、深みにはまると二次的な精神不調のリスクが高いともいえます。
Aさんの場合、匂いや温度、空気の流れなどの変化にも影響を受けやすく、居心地の悪さを感じると落ち着かなくなり、心身が緊張することが多くありました。
感情移入しすぎること=受診の対象か?
感情移入しすぎることは、程度問題にもよりますが特性であり病気や障害ではありません。ですので、自主的な気づきで上手に対策ができ、生きづらさなどを回避もしくは改善できるならば受診の必要はありません。まずは自主的な対策で身体や精神的な不調を予防するように努めることが大切です。
以下は、具体的な相談前の自主的な対策と相談するタイミングの目安と相談機関の適切な選択についてです。
(1)相談前の自主的な対策
HSPの傾向がある人は潜在的な特性のゆえ、以下のことを少し極端にやってみても実際には雑にはならない傾向があります。
Aさんはストレスを感じると、静かな部屋で深呼吸をしたり、音楽を聴いたりして気持ちを落ち着ける工夫をしていましたが、根本的な疲れは取れませんでした。
a.考えすぎない工夫
一つのことを掘り下げて考えるのではなく、ジャンルを多くして浅くしか考えない状況にし、掘り下げて考える習慣を意識的に封印すると良いでしょう。
b.刺激を減らす工夫(環境調整)
環境面でもシンプルにします。例えば、部屋のものを出張のホテル空間レベルに減らすイメージです。物の断捨離が心に有効に働きます。
c.対人距離を確保する工夫
他人と意識的に相手と距離を取ります。スマートフォンなどの確認も自分のタイミングで時間を決めて行うなどの工夫をすると良いでしょう。
d.自分で自由に使える休養時間を意図的に確保する工夫
他人と一緒にするリラックスや休養時間でなく、自分の日程で調整できる手段と内容を優先します。その内容はのんびりするとか、自主トレーニングするなり人それぞれで良いでしょう。
e.思っていることを一人で口に出したり、メモに残す工夫
他人やものに繊細でも、自分でいる時には自分自身の意見を聞いてあげようというイメージです。考えがまとまりやすく、それを口に出すことで脳にインプットするメリットもあります。忘れないように、メモに残すことも効果を高めるでしょう。
f.規則正しい生活をする。
規則正しい生活は、心の健康には必須です。
(2)相談するタイミングの目安
自己で対処していても長期化すると、つらさやうつ傾向が改善しない、仕事への悪影響がある、大切な人との関わりが悪化したりします。そのことで感情移入が強くなりすぎ、社会生活で弊害が生じることがあります。そうした時には、専門家の人に相談した方が良いです。相談するタイミングの目安は、精神的なつらさの程度・つらさの初発からの経過・つらい期間・社会生活への弊害の程度をまずは相互的にご自身で判断されるのが良いです。
Aさんの場合、職場から帰宅しても疲れが取れず眠れない日が続き、気持ちが不安定になったため、専門家に相談しようと決意しました。
(3)相談機関の適切な選択
相談機関の選択も、まずはご自身の希望で考えましょう。薬物治療が必要な時や希死念慮が強い時などは医療機関の受診が良いでしょう。一方で、相談者に話を聞いてもらうことや、アドバイスを求めることによって、解決しそうな場合はカウンセリングやコーチングを受けてみるのも有用かもしれません。
Aさんは心療内科を受診したあと、紹介を受けてカウンセリング機関に通い始めました。専門家と一緒に自分の特性を整理し、対処法を学ぶことで少しずつ楽になっていきました。
HSPについてのトピック
HSPについてのいくつかのトピックです。HSPについてさらに詳細に知りたい方は以下をご覧ください。
感情移入しすぎることについてのよくある質問
感情移入しすぎるとは、他人の感情や体験に過度に共感し、その感情が自分に強く影響を与えてしまう状態を指します。たとえば、他人の悲しみや怒りに深く心を痛めすぎて、自分の感情や行動にもその影響が強く出ることがあります。このような傾向が見られる場合、自己と他者の感情の境界が曖昧になり、自分の感情が他人のものと混ざり合ってしまうことがあるため、時にストレスや疲れを感じやすくなります。特に、高い感受性を持つ人、いわゆるHSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれる人々に多く見られます。感情移入は他者への共感や思いやりから生まれるものであり、完全に悪いことではありませんが、過度に行われると自分自身の感情が消耗し、心身のバランスを崩すことがあるため注意が必要です。
感情移入しすぎることにはいくつかの影響があります。最も一般的な影響は、他人の感情に引きずられることにより、自分の感情や思考が曖昧になり、自己感覚が低下することです。他人の痛みや困難に過剰に共感してしまうことで、感情的に疲れ果てることがあります。感情移入が過度に行われると、感情的な疲労感や無力感を感じることが増え、日常生活の質が低下する恐れもあります。特に仕事や人間関係において、他人の問題や感情に引き込まれすぎると、自分の立場を見失ってしまい、ストレスや不安が蓄積しやすくなります。さらに、感情移入しすぎることが自分自身の感情やニーズを見過ごし、過剰な責任感や負担を感じることにもつながるため、長期的には健康に悪影響を与えることがあります。そのため、感情移入しすぎる自分に気づき、意識的に感情の境界線を引くことが大切です。
感情移入しすぎる自分を改善するためには、まず自分の感情と他人の感情を区別することが重要です。自分自身が感じている感情と、他者の感情をしっかりと認識し、分けて考えることで、過度な感情移入を防ぐことができます。自分の感情を意識的にチェックし、他人の感情に引きずられすぎないように努めることが大切です。また、自己肯定感を高めることも改善に繋がります。自己肯定感を高めるためには、自己理解を深め、自分の感情や思考に対する評価を大切にすることが必要です。過剰な感情移入に対して、自分の境界を意識的に設定し、他人の問題を自分の問題として引き受けないようにすることが必要です。さらに、リラックス法や瞑想などを取り入れることで、感情のコントロールがしやすくなり、自己のバランスを保つことができます。
感情移入しすぎること自体は病気ではありません。しかし、感情移入が過度に行われ、日常生活に支障をきたすような場合には、心理的な問題が潜んでいることが考えられます。例えば、自己感覚が弱く、自分と他人を明確に区別できない場合、過度に他人の感情に巻き込まれてしまうことがあります。これが続くと、精神的な疲労や不安、抑うつなどの症状が現れることがあります。特に、感情移入が自分のエネルギーを消耗しすぎると、心身にストレスを感じるようになることがあります。このような状況が長期間続く場合、専門家のカウンセリングを受けることを検討することが重要です。感情移入しすぎることが原因で心理的な問題を抱えることがあるため、適切な支援を受けることが大切です。
感情移入しすぎる自分を受け入れる方法として、まず自分の感受性や共感能力を強みとして捉えることが重要です。感情移入が強いことは、他者への思いやりや理解を深める能力が高い証拠でもあります。そのため、感情移入が過度にならないように工夫しながらも、その特性を自分の中で肯定的に受け入れることが大切です。また、自己理解を深め、自分の感情やニーズに意識的になることも受け入れの一歩です。感情移入を自分の成長の一部として捉えることで、ストレスを減らし、よりバランスの取れた方法で感情を表現できるようになるでしょう。他者の感情と自分の感情を分けて考え、感情的に疲れすぎないようにすることも大切です。
感情移入しすぎる自分を改善するためのカウンセリングは非常に有効です。専門の臨床心理士や公認心理師によるカウンセリングを受けることで、自己理解を深めるとともに、感情移入と自己の感情を適切に分ける方法を学ぶことができます。カウンセリングでは、感情移入が過剰になってしまう背景や原因を探り、無意識に他人の感情に引き込まれやすい自分の思考や行動パターンを明らかにしていきます。自分の感情を大切にしつつ、他人の感情にも配慮できるような方法を習得することができます。また、リラクゼーション技術やストレス管理方法を学ぶこともでき、感情的な負担を軽減することができます。
感情移入しすぎる自分を改善するためには、まず自分の感情と他人の感情をしっかりと区別することが大切です。他者の感情に過度に共感しないように意識することで、自己の感情を守ることができます。また、感情移入が強く出てしまう状況を理解し、無理にその状況を避けるのではなく、適切に対処する方法を学ぶことも有効です。感情移入は他人に対する思いやりの現れですが、自分自身の感情も大切にすることがバランスを取るために必要です。感情を適切に表現し、必要な時には他者との距離を取ることも重要です。
感情移入しすぎる自分を改善するためには、自己の感情に意識を向け、感情の境界を意識的に引くことが重要です。自分の感情が他者に左右されていると感じた場合、その感情が自分のものであるか、他者のものであるかを意識的に確認することが役立ちます。また、自己ケアやリラクゼーションの技術を取り入れて、感情的に疲れないようにすることも有効です。自分のニーズを大切にし、感情移入しすぎないようにするためには、他者と自分を適切に区別する力を養うことが必要です。
感情移入しすぎる自分を改善するためには、まず自分自身がどのような状況で感情移入しすぎてしまうのかを理解し、そのパターンを知ることが大切です。特に、感情移入しやすい状況や人物について認識し、その際の対処法を身につけることが有効です。また、自分の感情に対して意識的に注意を向け、他人の感情と自分の感情を切り分ける訓練をすることが改善への第一歩です。心を落ち着かせるためのリラクゼーション法を学ぶことも効果的です。
感情移入しすぎる自分を改善するためには、まず自分の感情と他人の感情をしっかりと区別し、自己の感情を大切にすることが必要です。他者に対して深く共感すること自体は素晴らしいことですが、それが過剰になると自己感覚が曖昧になり、感情的に疲れやすくなります。自分の感情やニーズを見つめ直し、他人の感情に巻き込まれすぎないようにすることが重要です。さらに、感情移入しすぎないようにするためには、自分に適切な距離を取る練習が必要です。
感情移入しすぎてしまうことについて相談する
HSPや「感情移入しすぎる」は病気ではなく特性(性格)で、時に長所にも短所にもなります。自身の持つ特性を理解し、うつや不安の程度が強くなりすぎないように調整しておくことが理想です。自己での調整が上手にできない時には医療機関やカウンセリングなどを適切に利用するなど、自分の心の出口についても普段の生活から意識しておくことはストレス社会を生き抜く上では必要なことなのかもしれません。
当オフィスでもHSPや感情移入しすぎることについて相談やカウンセリングができます。ご希望の方は以下のページからお問い合せしてください。