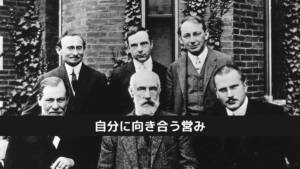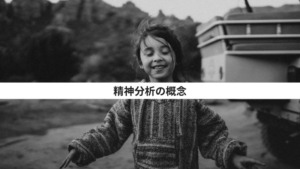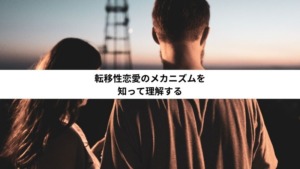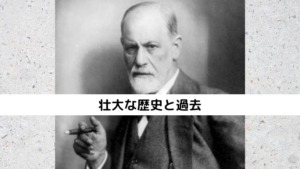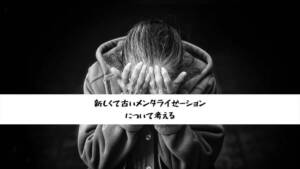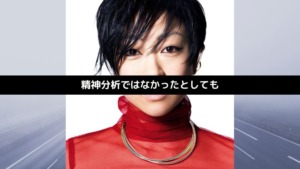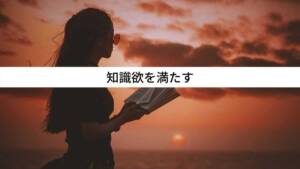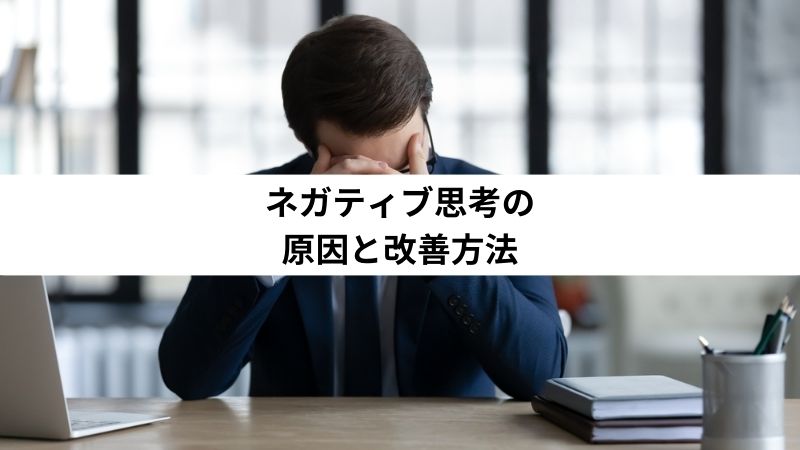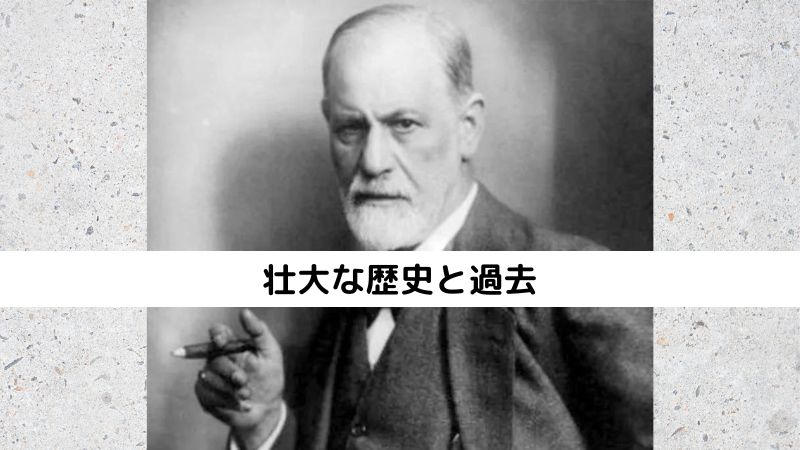メンタライゼーション(Mentalization)は、自分自身や他者の行動の背後にある心理状態・精神状態を理解することで、当初は境界性パーソナリティ障害の治療として考案されました。最近では、様々な疾患の治療に用いられるほか、自己理解を深めたり他者に共感することによって、コミュニケーション能力や自己効力感の向上が期待できるため、教育現場などにも活躍の場を広げています。
この記事では、メンタライゼーションについて定義やエビデンス、具体的な方法について解説していきます。
目次
メンタライゼーションとは

メンタライゼーションの考え方は、境界性パーソナリティ障害などの治療に用いられるほか、人間関係や社会的な相互作用において重要な役割を果たします。例えば、他人の気持ちや意図を理解し、共感することによって、より良いコミュニケーションができます。また、自分自身の感情や行動を自己観察することによって、自己理解が深まり、自己認識や自己制御力が向上するとされています。
メンタライゼーションの元となった精神分析についての概要は以下のページをご覧ください。
よくある相談の例(モデルケース)
20歳代 女性
Aさんは20代の女性で、人間関係が安定せず、恋人や友人との間で衝突や絶望的な孤独を繰り返していました。感情が急激に変化し、怒りや自己否定に圧倒されるとリストカットを行うこともあり、精神科で境界性パーソナリティ障害と診断されました。薬物治療を続けていましたが、自分の気持ちがわからないまま衝動的に行動してしまう状況を改善したいと考え、カウンセリングを希望しました。
初期段階では、Aさんは他者の言動を「見捨てられた」「嫌われた」と瞬間的に感じ取り、事実を冷静に捉えることが難しい状態でした。セラピストは、感情の高ぶりを抑えようとせず、まず「今、何が起きているか」を共に観察する姿勢をとりました。Aさんの発言を否定せず、怒りや悲しみの裏にある「相手がどう思っているか」「自分はどう感じたか」というメンタライジング(心のはたらきを想像する力)を促していきました。
中期には、Aさんがトラブルのたびに感じる「拒絶された」という思いの背景に、「自分の気持ちは誰にも理解されない」という長年の信念があることが明らかになりました。セラピストは、Aさんの感情を丁寧に言語化しながら、「他者の意図を確定せず、仮説として考えてみる」という態度を支援しました。Aさんは次第に、自分と他者の心を区別して考える力を取り戻していきました。
終盤では、Aさんは衝動的な自己破壊行為を行うことが減り、対人場面で感情が高ぶっても「自分はいま傷ついている」と認識し、相手との関係を壊さずに距離を取ることができるようになりました。セラピストとの関係を通して「相手の気持ちは変わるもの」「誤解しても修復できる」という体験を重ねることが、Aさんの安定した対人感覚を育てました。
約3年にわたる治療を経て、Aさんは「感情に飲み込まれず、自分と他者を区別できる」状態へと回復しました。メンタライゼーション・ベースド・セラピーは、Aさんにとって自己理解と他者理解の回復を通じた、深い癒しと成長のプロセスとなりました。
メンタライゼーションの定義や歴史
(1)メンタライゼーションの歴史
メンタライゼーションの歴史は比較的新しいもので、1990年代にイギリスの精神科医であるピーター・フォナギー(Dr. Peter Fonagy)らによって精神分析や愛着理論を起源として考案され、発展してきました。
フォナギーは、境界型パーソナリティ障害の患者に対する治療を行っていく中で、「自分自身(及び他者)を様々な思考や感情を持った人間であると考える機能」としてメンタライゼ-ションと言う概念を提唱し、この機能が障害されていることによって境界性パーソナリティの精神病理を説明しました。
メンタライゼーションの能力は小さい頃から養育者との関わりの中で獲得されていくもので、養育者との関係に機能不全があるとこれがうまく育まれなかったり、心理的に不安定な状態に陥ったりすると、物事を捉える際に偏った処理をしてしまいます。不完全な処理の仕方には3種類あり、「心的等価モード」、「ふりをするモード(ごっこモード)」、「目的論的モード」があります。
(2)心的等価モード
「心的等価モード」は、現実と心で思うことの境界が失われ、心で思ったことをそのまま現実であるとみなしてしまう状態で、妄想やフラッシュバックなどではその時の精神状態がそのまま現実として体験されます。
Aさんの場合、相手の表情や言葉をそのまま「現実」として受け取り、「嫌われた」「否定された」と感じてしまう傾向がありました。事実と感情の区別がつかず、思考が極端に振れることが多く見られました。
(3)ふりをするモード
「ふりをするモード」は、現実を無視して空想的、抽象的、観念的な見解に没入してしまい、「~しなければならない」「~すべきだ」といった考えにとらわれて自分の中の現実と他の現実とを柔軟に結び付けられない状態です。
Aさんは、苦痛な感情を避けるために「平気なふり」や「相手に合わせるふり」をすることがありました。内面の感情と外に見せる態度が乖離し、関係の中で自分の本当の気持ちを見失う場面が繰り返されました
(4)目的論的モード
「目的論的モード」は、願望や感情などの精神状態を推し量れずに具体的なものや行動のみで判断するような状態を指します。
このような機能不全に陥ったメンタライゼーションを修正して介入していくことで、患者やクライエントの症状の改善を期待することができます。
Aさんの場合、「相手が私を傷つけたのは、嫌いだからだ」といった単純な因果で物事を捉える傾向がありました。行動の背後にある心の動機や文脈を考えることが難しく、関係がこじれやすくなっていました。
メンタライゼーションのエビデンス
近年ではメンタライゼーションに関する研究が進んできており、その効果についてのエビデンスも蓄積されてきました。
メンタライゼーションに基づく治療は「MBT」(Mentalization Based Treatment)と呼ばれ、当初の治療ターゲットであった境界性パーソナリティ障害をはじめとして、メンタライゼーション能力の機能不全や歪みを伴うような、うつ病、摂食障害、薬物依存、自閉症スペクトラム障害など様々な精神疾患においても有効性が示されています。
また、メンタライゼーションの能力と対人関係の良好さや自己効力感の高さと関連しているといった報告もあり(菊池ら 心理臨床学研究 2012、増田ら 教育心理学第57回総会発表論文集 2015)、教育の分野でも注目されており、自己理解や人間関係の改善を促すためのアプローチとして活用されています。
メンタライゼーションに基づく治療のやり方

(1)クライエントのメンタライゼ-ション能力を評価する
セラピストは、クライエントのメンタライゼーション能力を評価するために、質問や会話を通じて彼らが自分自身や他人の感情や思考についてどのように認識しているかを観察します。
Aさんの場合、初期の段階では「感情に圧倒される」「自他の区別が曖昧になる」傾向が強く、メンタライゼーション能力は不安定でした。面接を通して、相手や自分の心の動きを観察できる場面が少しずつ増えていきました。
(2)メンタライゼーションの練習を開始する
セラピストは、クライエントが自分自身や他人の感情や思考について考える練習を始めます。このプロセスは、心の状態に関する具体的な例を示したり、フィードバックを提供したりすることで、クライエントが自分自身と他人をよりよく理解するのをサポートします。
Aさんは、衝突や不安が起きた出来事を一緒に振り返り、「そのとき相手はどう感じていたと思う?」「あなたの中では何が起きていた?」という問いかけにより、心の状態を言語化する練習を重ねました。
(3)短いセッションを続ける
MBTは、通常、週に1-2回の治療セッションで行われます。セラピストは、クライエントが治療を続けるために必要なサポートを提供し、必要に応じて他の治療者や専門家との連携を行います。
セッションでは、セラピストとクライエントが、日常生活や治療中に起こった出来事について話し合い、その出来事がどのような感情や意図をもたらしたのかを考察します。また、クライエントが他者の視点を理解するために、セラピストはクライエントに対して自分の思考や感情を説明したり、クライエントがメンタライゼーションの不全に陥ったときに話を中断したりして、クライエントの情動を適切に抑制したり喚起したりします。
Aさんの場合、感情の高まりが強く、1回のセッションを短く区切って進めることが有効でした。少しずつ繰り返すことで、安心して自分の感情を扱えるようになり、継続的な変化が定着していきました。
精神分析についてのトピック


メンタライゼーションについてのよくある質問
メンタライゼーションとは、自分や他者の感情や思考、意図などを理解し、解釈する能力を指します。これは対人関係を円滑に進めるために非常に重要な能力であり、他者の行動を予測し、反応するための基盤となります。メンタライゼーションは、他者がどのように感じているのか、その行動にどんな意図があるのかを深く考えることで、社会的な状況をうまく処理できる能力を養います。対人関係においては、この能力が高いと、誤解や対立を避け、共感的な理解を持って接することができます。
メンタライゼーションを向上させるためには、自己認識を高め、他者の立場に立って物事を考えることが大切です。まず、日常生活で他者の行動や言動に注目し、その背景にある感情や意図を推測する習慣をつけることが有効です。また、自己の感情や反応を客観的に見つめ直すことも大切です。例えば、自分がある状況でどのように感じ、なぜそのような反応を示すのかを振り返ることで、自己理解が深まり、他者への理解が促進されます。さらに、対人関係を重視する心理的アプローチやカウンセリング、グループ療法などを通じて、他者との相互作用を意識的に学ぶことも有効な方法の一つです。
メンタライゼーションは、日常生活や仕事、家庭、学校など、さまざまな場面で役立ちます。特に、他者とのコミュニケーションを深め、相互理解を促進する場面において、メンタライゼーションは重要な役割を果たします。例えば、職場で同僚の意図や感情を理解することで、協力や信頼関係を築くことができます。また、家庭内での親子間や夫婦間でも、相手の感情や思考を理解し、適切に反応することで、対立を避け、調和を保つことが可能になります。さらに、教育現場では、教師が生徒の思考や感情を理解し、適切にサポートすることが生徒の成長を促すために重要となります。
メンタライゼーションに基づく治療(MBT)は、心理療法の一種で、メンタライゼーションの能力を高めることを目的としています。この治療法は、特に境界性パーソナリティ障害や他の感情や対人関係に関する問題を抱える人々に効果的であるとされています。MBTでは、患者が自分の感情や他者の意図を適切に理解し、他者との関係をより良くするために必要なスキルを学びます。治療の進行中、患者は自己と他者を理解する方法を学び、感情を調整し、問題解決能力を向上させることができます。特に、自己と他者の違いを受け入れ、どのように適応すれば良いかを考える力を養います。
メンタライゼーションの能力が低いと、対人関係においてさまざまな問題が生じることがあります。例えば、他者の感情や意図を誤解しやすくなり、誤った反応をすることがあります。これにより、誤解や対立が生じ、コミュニケーションが不安定になります。また、自己理解が不十分である場合、自分の感情や意図を上手く伝えることができず、ストレスが増大することもあります。さらに、感情の調整が難しくなるため、衝動的な行動や対人関係での問題が発生するリスクが高まります。対人スキルや自己認識の不足が原因で、仕事や家庭での人間関係において困難を抱えることが多くなります。
メンタライゼーションは、境界性パーソナリティ障害をはじめ、うつ病や摂食障害、薬物依存、自閉症スペクトラム障害など、さまざまな精神的な疾患に効果があるとされています。これらの疾患では、他者の感情や意図を理解する能力が低下していることが多く、そのため対人関係の問題が生じやすいです。メンタライゼーションを高めることによって、他者とのコミュニケーションが改善され、感情や行動の調整が可能になります。例えば、境界性パーソナリティ障害では、情緒の不安定さや衝動的な行動を改善するために、メンタライゼーションのスキルを高めることが効果的です。
メンタライゼーションを高めるためには、自己認識を高めることが基本です。まず、自分の感情や思考を意識的に観察し、その感情がどのようにして生じたのかを振り返ることが有効です。また、他者の行動や言動を意図的に観察し、その背後にある感情や思考を推測する練習をすることも効果的です。さらに、心理療法やカウンセリングを通じて、感情や意図の理解を深めることも有益です。自分と他者の違いを理解し、他者の視点を取り入れることで、メンタライゼーションの能力が向上します。また、日常的に対人関係を改善するための意識的な努力が重要です。
メンタライゼーションの能力は、自己報告式の質問票や、臨床面接を通じて評価されます。臨床面接では、患者が他者の感情や意図をどれだけ理解しているかを、具体的なシチュエーションに基づいて評価します。また、患者が他者の視点をどれだけ取り入れているか、感情や行動に対する反応の適切さを観察することが重要です。自己報告式の質問票では、患者が自分のメンタライゼーションの能力についてどのように感じているかを調査することができます。これらの評価を通じて、個々のメンタライゼーションのレベルや、改善すべき点を明確にすることができます。
メンタライゼーションの能力には、年齢や性別による個人差があります。一般的に、メンタライゼーションの能力は年齢が進むとともに向上するとされています。幼少期には、自己中心的な考え方が強いため、他者の意図や感情を理解する能力が低いですが、年齢を重ねることで、他者の視点を取り入れる力が発達します。また、性別による顕著な差異は報告されていませんが、文化や育ち方によって、メンタライゼーションに関するスキルに差が生じることもあります。
メンタライゼーションを高めるためには、認知行動療法や対人関係療法(IPT)、マインドフルネスを取り入れたトレーニングが効果的です。これらの療法では、他者の感情や意図を理解し、それに対してどのように反応するべきかを学びます。対人関係療法では、他者との関係の中での感情の理解と調整を練習します。また、認知行動療法では、非合理的な思考パターンを修正し、より効果的な対人関係の方法を学びます。トレーニングを通じて、他者の視点を理解する力を養い、自己理解を深めることができます。
精神分析心理療法を受けたい

メンタライゼーションの能力は養育者との関わりの中で獲得されるため、養育者との関係に機能不全があると、メンタライゼーション能力の形成が不完全となり、境界性パーソナリティ障害やうつ病、発達障害など様々な疾患の症状を表出すると考えられています。
メンタライゼーションに基づく治療である「MBT」では、不完全なメンタライゼーションを修正し介入することで、自己理解や人間関係の改善を促し、人生の目的に邁進する能力を向上させることを目標とします。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。