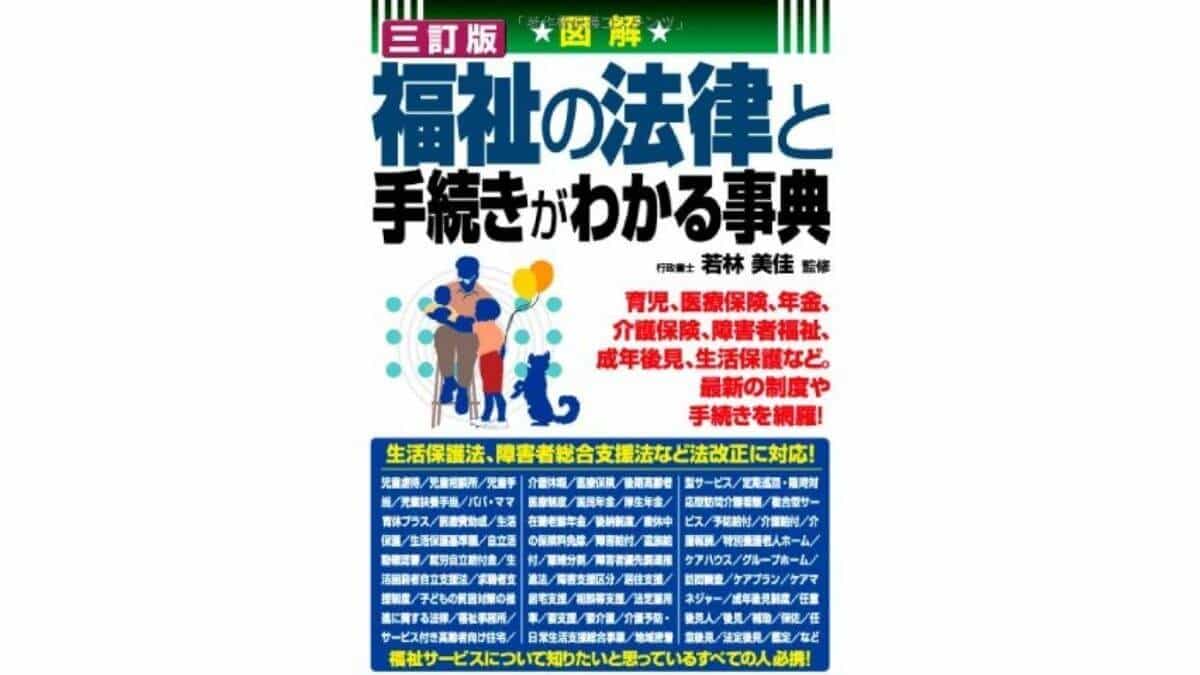欲動と欲動運命

メタサイコロジー論文の一つである「欲動と欲動運命(1915)」についての要約とそれについての講義のレジュメです。欲動論から対象関係論への橋渡しという位置づけから読み解いています。
目次
欲動と欲動運命(1915)要約レジュメ
(1)欲動と欲動運命の概要
a.欲動と刺激
生理学の立場では、外部から生体組織にもたらされた刺激は行動を通じて外部に放出される。さて「欲動」は「刺激」とどういう関係にあるのか。欲動刺激とは、刺激源泉を前にしての逃避行動によってもたらされるものであるのに対して、欲動は恒常的な力として働き身体内部から襲いかかってくるものである。そのため逃避は無意味であり、満足が得られるのはその目的にあった変化が生じることによってのみである。
刺激が外から来る場合、「それから逃れる」ために筋肉運動が行われそれが蓄積されることで、身体的遺伝的変化が促された。これに対して欲動は神経系に対して高度な要請を課すことでそれらを無限の能力を備えた段階までに高めることが可能となった。欲動そのものが生命基質に変化を及ぼしたと言って差し支えない。
また、高度に発達した心の装置の活動は快原則の支配下にあり、快-不快の感覚によって自動的に調整され、不快感覚が刺激の増大に、快感覚が刺激の低減に関係する。さらに生物学的には、欲動は心的なものと身体的なものとの境界概念として理解され、欲動は身体内部に発し心の内へと達する刺激を心的に代表するものとなった。
次に熟語の検討を行う。
- 欲動の衝迫=その欲動の運動的な契機、力の総和であり、圧迫してくる欲動の性格は一般的な姿である。
- 欲動の目標=それは満足であり欲動源泉にある刺激状態を排除することによってしか達成されない。
- 欲動の対象=それによって欲動が自らの目標を達成しうるものである。
- 欲動の源泉=身体的な過程であり、その刺激が心の生活の中で欲動によって代表されるようなものであり、心理的には満足させたいと感じることでしか理解されない。
欲動には種類や心の中での振る舞い方に違いはなく、全て質的に等しく一様であり、興奮量に差があるだけである。
b.欲動の分類と欲動運命
精神分析が、ヒステリーと強迫神経症の根本に性の欲求と自我の欲求間の葛藤を見いだしたことにより、欲動を自我欲動もしくは自己保存欲のグループと性欲動のグループに分けることが可能となった。性欲動の目標は器官快の獲得であり、それによって生殖機能を果たすことが可能となる。
性欲動が初めて姿を現すのは保存欲動であり、次第に対象を見出すに当たって自我欲動が示す道筋をたどり、終生性欲動は自我欲動と結託しリビドーを供給し続ける。欲動が生涯の経過の中でどのような運命にであうか(=欲動運命)について、性欲動に的を絞って検討する。
欲動運命には、対立物への反転、我が身への向き直り、抑圧、昇華などがあり、ここでは前の2つについて扱う。
対立物への反転には、[サディズム/マゾヒズム]の対と[視ることの快/露出]の対が特徴的な例であり、そこでは欲動の目標について反転が起こっている。苛む・視るという能動的な目標に代わり、苛まれる・視られるという受動的な目標が設定される。内容の反転は、愛することと憎むことへの転換の中に見られる。
我が身への向きなおりは、マゾヒズムが自我自身に向き直ったサディズムの中に見いだされる。また露出には自分の身体を視ることが含まれている。マゾヒストは自分の体に向けられた憤怒を共に享受し、露出狂者はむき出しにされた自分の身体を共に享受している。これらは目標は不変のままに対象だけが置き換わっているのである。さらに対立物への反転と我が身への向き直りは、合致し一緒に起こっていると考えられる。
マゾヒズムについては下記のフロイトの論文が参考になります。
c.[サディズム/マゾヒズム]と[視ること/視られること(窃視者/露出症者)]
サディズム/マゾヒズムの過程は次のようである。
- サディズムは他人の躰に向けられた暴力行為によって成り立つ。
- この対象が放棄され我が身で置き換えられる。その向き直りによって能動的な欲動目標から受動的な欲動目標への変換も遂行される。
- 新たにある人物が対象として余所から探し出され、この人物は目標の変換が遂行されたことに伴い主体としての役割を引き受けさせられる。
Cが一般的なマゾヒズムと呼ばれているものである。ここでは受動的な自我は余所からの主体によって占められているもとの自分の場所へと、空想によって自分自身を置き直し、本来的なサディズムの道を通って満足が発生している。苛め好きから生成してくるのは自己処罰であってマゾヒズムではない。サディズム理解を妨げているものは、痛みを加えるという行動だが、精神分析を行ってみると、痛みを加えることは欲動の本来的な目標行動には何らの役割を果たしていないことが分かる。
痛みや不快感覚であってもその感覚が性興奮に飛び火すれば快に満ちた状態を現出せしめ、痛みがいったんマゾヒスティックな目標になってしまうと、今度は痛みを与える目標が出現し、苦しんでいる対象と同一化することによって痛みではなく性興奮が享受される。痛みの享受が一つの目標であるなら、それは本来的にサド的な人において初めて欲動目標となり得る。視ることと視られることの対は次のように推移する。
- 視ることが能動性として余所からの対象に向けられる。
- 対象が放棄され、自分の身体の一部へと視る欲動が向き直り、それに伴い受動性への反転が起こり視られるという目標が設定される。
- 自分を視てもらうようにするために新しい主体が設定され、その主体に自分を見せる。
視る欲動は活動の始まりに当たって自体性愛的であり、対象として自分の身体が見いだされている。
欲動の図式
α自分で性器を視ている=性器が我が身によって視られている
| |
β自分が余所の対象を視ている γ自分の対象が、余所の人によって視られている
初期の発達段階では、性欲動は自体性愛的に満足させられこの段階はナルシシズムに属する。この時点での視ることの快は自分の身体を対象としていて、ここから能動的な面が発達してナルシシズムを脱していくことになる。しかし視る欲動に含まれる受動的な面はナルシス的対象を手放そうとはしない。ナルシシズムの主体は同一化によって余所からの自我と交換される。自我に向いたり能動性から受動性に向いたりする欲動運命は、自我のナルシス的な編成によるものであり、その後もその影響を免れることはない。
ナルシシズムについては下記のページに詳しく書いています。
[サディズム/マゾヒズム]、[視ることの快/視られることの快]というものは、自体性愛的に活動し、その構成要素の対象は要素の源である器官の影に隠れその器官と一体化する。
ひとつの欲望が対立物に変換されるということは、愛から憎しみへの変換のみにおいて観察される。これは1つの対象に向けて現れるものであり、この共存は感情の両価性の重要な例となる。愛することには、[愛する/憎む]、[愛する/愛される]、[愛すると憎む/無頓着と無関心]の3つの対立がある。そのうち[愛する/愛される]の対立は、能動性から受動性への向き直りに対応していて、自分自身を愛するという根本状況=ナルシシズムの特徴を持つものである。
愛することの逆を理解するためには心の生活が三種類の双極構造によって支配されることを考えると良いかもしれない。
- 主体(自我)/対象(外界)
- 快/不快
- 能動的/受動的
個体は早期に自我/非我(外部)、(主体/対象)の対立を経験する。この対立は変更されない根本状況である。快/不快は感覚系列につきもので、意志決定において最も優越される。能動的/受動的の対は、自我/外部対象の対立と混同してはならない。自我は外部からの刺激に対しては受動的であり、刺激に反応する段階では能動的に振る舞う。
自我は始まりから欲動で備給されており、その諸欲動を部分的には自分自身で満たす事が出来、これはナルシシズムの状態であり、この満足の仕方は自体性愛的な満足である。この段階では外界は関心を備給されておらず、この状態での自我-主体は快いものであり、外界は何も関心を呼び起こさない。つまり自分自身だけを愛し世界に対して無関心な状況である。
自我保存欲動の結果、外界から対象を獲得するようになると、それが快の源泉である限り自我の中に受け入れられ、不快なものは押し出してしまう(取り込み、投射)。こうして生粋の快自我への転換がおき、外界は自分が体内化した快の部分と余所のものとに二分される。快自我は自分の自我からある部分を遊離させ外界の中に投げ込んだ上で、それを敵対的と感じその組織替えを経て[主体/外界、快/不快]の2つの双極構造の重なり合いとなり、自我-主体が快、外界が不快と改めて確立されることになる。
愛/無関心の対立が自我/外界の双極性を移しているように、愛/憎しみという第二の対立対は、自我/外界という第一の双極性と結びついた快/不快の双極性を再生産している。対象が快感の源泉になると運動傾向が生じ対象を自我に近づけ体内化しようとする。そうなると快を与えてくれる対象を「魅力」的に思ったり、「愛している」等言ったりする。また対象が不快であれば自我と距離を開けようとし、反発したり憎んだり攻撃性を向けたりする。
「愛している」という語は対象に対する自我の純粋な快関係の中に深く入り込んでいき、ついには狭義の性的対象や昇華された性欲動の欲求を満たす対象に固定化されることになる。この段階で自我欲動と性欲動の区別は、我々の言葉と精神の一致する段階となる。生殖機能に奉仕するために性のすべての部分欲動が統合されるとき、はじめてこの関係に「愛している」という語が適用されるのである。
「憎む」ことの関係は性的生活に由来するのではなく、保存と固守を求める自我のもがきに由来すると主張できる。
d.欲動と欲動運命のまとめ
愛と憎しみの発生についての知見をまとめよう。
自我は自らの欲動を、器官快の獲得を通して自体愛的に満たす能力を有しており、愛はそこから芽生える。愛は元々ナルシシズム的であり、やがては諸対象へと越境してゆき、それらは拡大された自我へと体内化される。愛は、性欲動活動へと内的に結びつき、性欲動の統合が遂行されれば性的追求の全体に合致するようになる。愛することはいくつかの前駆段階を経て変化していくものであり、最初に当たるものが自分の中へと体内化すること、もしくはむさぼり食うことであり、これは両価的な愛といえる。
サディズム=肛門期編成になると、対象へと向かう追求は占有の衝迫という形で登場し、憎しみと区別することは出来ない。性器期になってやっと、愛は憎しみの対立物になっている。
憎しみは愛よりも古いと考えられる。ナルシス的な自我のそばに、刺激を与える外界を寄せ付けないようにすることから憎しみは生まれてくる。憎しみはさまざまな対象によって喚起されてしまう不快反応の表出なのであるから、自我保存の諸欲動と憎しみのあいだには、内密な関係が保持される。その結果、自我欲動と性欲動とは容易に1つの対立を形作ることになり、それによって憎しみと愛の対立が反復されるのである。
愛とない交ぜになった憎しみの一部は、十分に乗り越えられなかった、つまり愛することの前駆段階に由来している。愛の関係が断ち切られたとき憎しみが現れることはまれではなく、その様な場合には愛することがサド的な前段階へと退行して、憎むことがエロス的な性格を手に入れ愛の関係がなおも続いてゆくことが保証される。
愛することから愛されることへの変換は、能動的/受動的の作用に対応したものであり、視る欲動やサディズムの場合と同じように考えて良い。
欲動の蠢きが心の生活を支配する3つの大きな双極性の影響のもとに引き入れられていくこと、これが本質的に欲動運命である。これら3つの双極性とは、能動/受動は生物学的、自我/外界は現実的、快/不快は経済論的ということができる。
(2)考察・感想・議論したい点
非常に難しい内容でまとめるのに大変であった。自己保存欲からの「愛」をどのようにFreud,S.は考えるのか。その様な愛の領域のほうがずっと広いのではないかと思いました。
欲動と欲動運命(1915)講義レジュメ
(1)訳語の問題
ドイツ語のTriebをストレイチーはSEにおいて本能instinctと英訳した。しかし、Triebには、欲動drive、衝動impulse、衝迫urge、欲求needなど多義的な意味合いを含んでいる。本能instinctには先天的に決定された変更できない行動パターンという意味合いがある。
しかし、Triebには環境との関わりで、その目標と対象を変更する性質がある。また、衝迫性に駆り立てられた動きという性質もあり、小此木はdriveが適訳であると言っている。
(2)不安との関連
心的外傷や内的欲動から生じる葛藤を自我は抑圧する。抑圧によって、意識からその思考内容を排除しようとするが、抑圧・排除しきれない残された情動が症状を形成すると考えた。
その後、不安のメカニズムについてフロイトは大きくその仮説を修正した。1926年の「制止、症状、不安」において、不安の起源は幼少期における葛藤や危機的状況によってもたらされた記憶の痕跡であるとした。心の内部において不安が信号として働き、その結果として抑圧が生じるとした。不安と抑圧の因果関係を逆転させた。ちなみに、フロイトは幼少期の危機について、対象喪失の恐れ、去勢の恐れ、超自我の恐れを挙げている。
(3)欲動論の進化
元々、性欲動と自我欲動(自己保存欲動)の二つの欲動をフロイトは想定していた。しかし、1920年の「快感原則の彼岸」において、死の欲動の概念を導入した。この概念は思弁的であると言う批判を受けることが多く、現在の各精神分析学派でも死の欲動を理論体系に含められないことも多い。
快感原則の彼岸(1920)の論文の要約と解説が以下のページにあります。
クラインはこの死の欲動を理論体系の中心に添え、理論的な発展を遂げた。ただ、その過程で、フロイトが想定していたような有機物が無機物に変形していく静かな動きではなく、怒りや破壊性に根差した攻撃的な欲動に変化していった。
死の欲動から羨望概念が精微化され、良いものに向けられた攻撃性が人間の根本であるとクライン派は考えるようになった。
死の欲動と羨望については以下を参照してください。
また、死の欲動や攻撃性はナルシシズムと結びつき、構造的な概念の中で、心全体を覆うシステムとしての側面が強調されていった。「ナルシシズムの導入にむけて(1914)」で講義したローゼンフェルドの自己愛構造体やシュタイナーの病理的組織化が有名である。
一方で、対象関係論の祖であるフェアバーンは欲動を否定し、対象との関係を根本的な心の在り方とみなした。人間は生まれた時から対象希求的であるとした。そうであるがゆえ、愛自体が破壊的になり、対象を壊してしまう不安があることをスキゾイドの臨床から見出した。攻撃性が対象を破壊してしまうことは容易に想像できるが、愛が破壊してしまうことはそれ以上に恐ろしいことである。そのため、愛したいが、愛すると対象を壊してしまうので、愛を引っ込めるしかできないことをスキゾイド・ジレンマとした。
(4)昇華から償い
本論文で昇華についても述べられており、欲動運命の一つとされている。昇華という概念は有名であるが、現在の精神分析臨床ではそれほど多くは用いられていない印象である。おそらく、昇華は社会的価値観や道徳的要素を多く含んでしまうことが理由かもしれない。
しかし、昇華を臨床的に有用な概念にしたのがクラインであり、償いという言葉で扱うようになった。妄想分裂ポジションにおいて悪い対象を攻撃し、破壊しようとするが、実は悪い対象は良い対象の一側面であることを乳幼児は知るようになる。それが抑うつポジションである。壊してしまった対象に罪悪感を抱き、修復する過程が償いである。その償いが安易に用いられ、苦痛を否認するために用いられると躁的防衛(躁的償い)となってしまう。
さらにシーガルは妄想分裂ポジションから抑うつポジションに至る過程で、象徴形成が働き、償いによって対象を再創造するところに美を見出し、芸術活動をその点に位置付けた。
シーガルの芸術論については以下に考察を書いています。
(5)リビドー経済論
「心理学草案(1895)」を見ると、フロイトはエネルギー保存の法則を明確にではないが、念頭に置いていたと思われる。つまり、エネルギーの総量は100と想定し、どこかに向ければ、総量は減っていくというものである。
「心理学草案(1895)」の要約と解説については以下を参照してください。
しかし、後、クラインはエネルギー総量は無限大としてみていたようである。メルツァーはフロイトは知識と教養が非常に豊かで、当時の科学的枠組みに精神分析を入れ込もうとし、様々な科学的な概念を精神分析の理論に補強していた、と述べている。その点、クラインは良くも悪くも科学者ではなく、臨床家に過ぎなかった。
そのため、そうしたエネルギー保存の法則といったことは全く念頭にはなかった。閉鎖系システムに閉じ込められることなく、自由に発想することができた。そのことによって、リビドー経済論にとらわれることなく、空想という無限に広がる空間に果敢に挑むことができた。
(6)対象関係論の萌芽
欲動は、極端に単純に理解すると、良いものに近づき、不快なものから遠ざかる、とまとめることができる。フロイトは対象というものがあることは知っていたが、そこに一次的な意味は見出さなかった。欲動が向けられる対象はたまたまそこにあっただけで、たまたま別のものがあれば、そちらに向かうだけと想定していた。対象は代替可能物であった。
それでも、そこには対象に投影し、対象から取り入れるという対象関係論の視点はもっていたようである。次の「喪とメランコリー(1917)」ではそれが一層明確にされていった。
「喪とメランコリー(1917)」を知りたい方は以下のページをご参照ください。
一方で、フェアバーンやクラインらは対象が誰であるのか、対象が何であるのか、といったことを重視していった。対象が一次的であり、欲動の価値は対象関係の下にされてしまった。
(7)表象と空想
表象は欲動の派生物、附属物であるとフロイトは述べている。もしくは白昼夢のように防衛的、欲望成就的な機能に位置付けていった。表象を空想に変形させ、そこにプライマリーな価値を与えたのがクラインやシーガルらのクライン派である。クラインは無意識的空想の中に原始的な不安を見出し、それを解釈によって扱うことで不安を減じることができるという精神分析の新たな視点を導入した。
また、その空想や不安を幼児はプレイという形で表出するので、パラメータを使用せず、精神分析を無修正で適用できると主張した。また、防衛や抵抗から精神分析を始めるのではなく、最初からもっとも前面に表れている原初的で最奥の空想と不安を扱うことが必要であると述べている。これらのことが、患者の空想と不安を扱う武器となっていった。これらのことをクラインは精神分析の無修正の適用であるとしているが、やはりフロイトの技法をさらに発展させているということができる。
さらに、シーガルは象徴形成の理論を発展させた。象徴とは、そのものをあらわす他のものであり、抑うつポジションの機制が深く関わっている。象徴形成が不十分であり、そのものを表してしまうことを象徴等価物と呼んだ。
シーガルの象徴形成については以下の2つのページが詳しいです。
シーガルはバイオリンやそれを人の面前で演奏することを例として挙げている。バイオリンはペニス、演奏はマスターベーションである。象徴形成ができていると、ペニスやマスターベーションを空想の中であらわしているとしても、別物であると認識できている。
しかし、抑うつポジションが達成されておらず、象徴形成が不十分の場合、バイオリンを人前で演奏することはまさにペニスを露出し、マスターベーションを人前ですることと同義のこととして認識されてしまうのである。
(8)欲動論は流行らない?
ここ数年は対象関係論が非常に興味関心を集めている。反面、欲動論は不人気である。その理由についていくつか想像できる。
フロイトは性欲動の抑圧を症状メカニズムの中心に据えた。しかし、性欲動がそもそも抑圧されない時代背景になってきたことが挙げられる。また、抑圧機制が中心の患者ではなく、分裂機制が中心の患者が増え、その対応がテーマとなってきたことも挙げられる。そうした患者の理解として対象関係論は欠かせないということも理由としてあるだろう。それに付随して、抑圧するかどうかという一人の中で完結する病理ではなく、他者を巻き込み、他者との関係の中に病理が表出される問題が大きくなったことも挙げられるだろう。
では、欲動論は不必要なのであろうか。おそらく欲動論を単体で論じることは臨床的にも不十分になるだろう。
攻撃欲動・破壊欲動についてはよく論じられるとしても、無目標・無対象に攻撃がばらまかれるのではなく、そこに対象や目標があり、それがあるからこそ攻撃欲動が向けられるという対象関係の観点が欠かせないのである。
さらに、愛着や愛着障害の臨床はここ数年で盛り上がってきている。フォナギーのメンタライゼーションなどそれを理論背景としている。性欲動とその矛先について、または重要な他者との愛情交流とその欠如によって、今日の重篤な患者を理解できる場合が多いだろう。欲動の抑圧ではなく、愛情の剥奪の観点は臨床的に非常に重要である。また、攻撃欲動の放出はあるにしても、それによって他者に何を求めようとしているのか、という観点で患者を理解することも臨床的に有用である。
愛着や愛着障害については以下をご覧ください。
さいごに
欲動から対象関係に移っていった精神分析について興味のある方は以下のページを参照してください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。
- 小此木啓吾 監修(2002)精神分析事典 岩崎学術出版社
- シーガル(1991/1994)夢・幻想・芸術―象徴作用の精神分析理論 金剛出版
- シュタイナー(1993/1997)こころの退避 岩崎学術出版社
- フェアバーン(2017)対象関係論の源流──フェアベーン主要論文集 遠見書房
- フォナギー(2006/2011)メンタライゼーション・ハンドブック 岩崎学術出版社
- フロイト(1895)心理学草案
- フロイト(1917)喪とメランコリー
- フロイト(1920)快原理の彼岸
- フロイト(1926)制止、症状、不安
- メルツァー(1978/2015)クライン派の発展 金剛出版
- ローゼンフェルド(1952/1993)急性精神分裂病者の超自我葛藤の精神分析 メラニー・クライン トゥデイ1 岩崎学術出版社