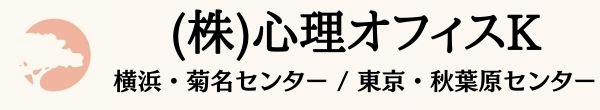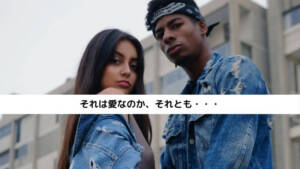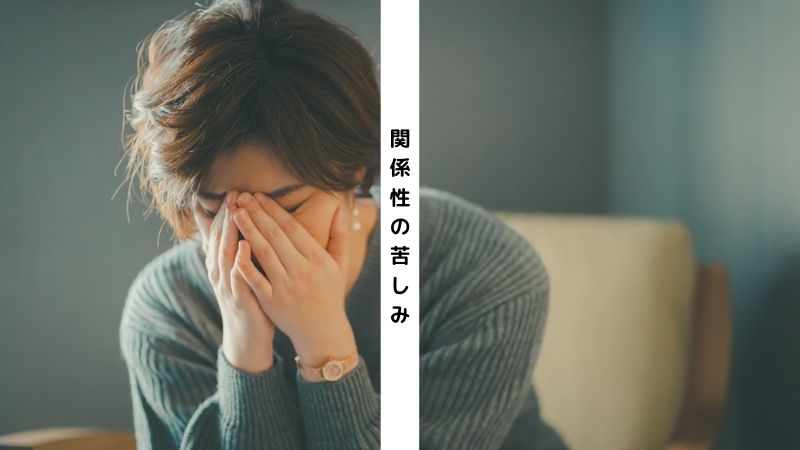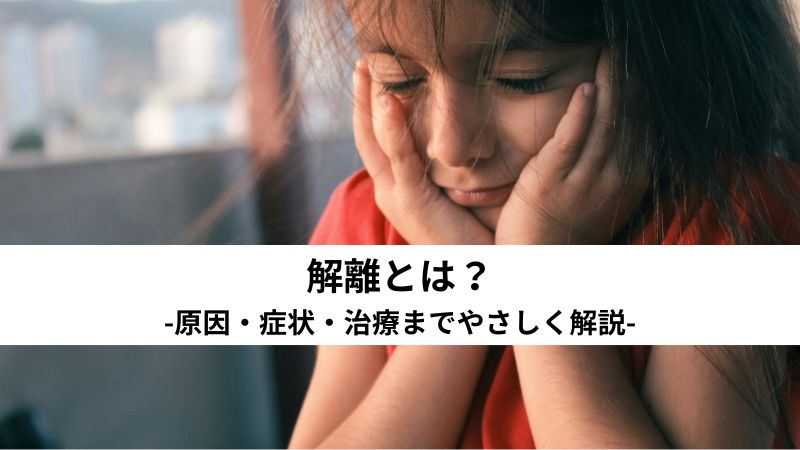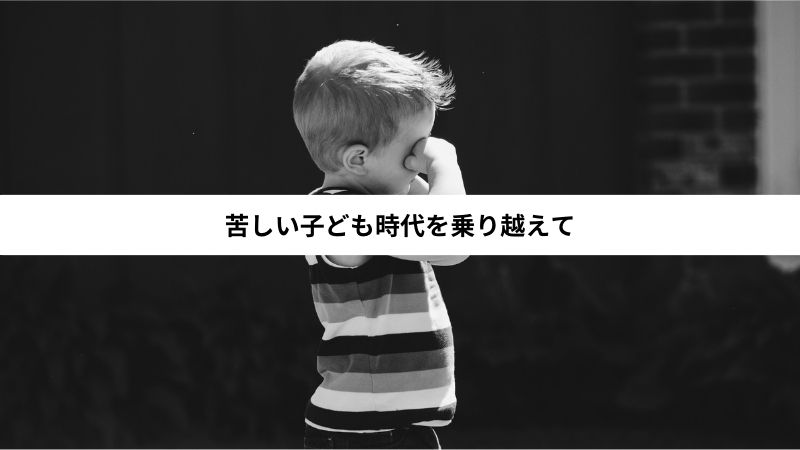インナーチャイルドとはどんなもの?共依存との関係や原因・克服方法を知ろう

こちらの記事では、インナーチャイルドとはどういうものか、原因や克服方法について紹介します。また、インナーチャイルドを説明するうえで外せないものが、共依存やアダルトチルドレンです。それぞれがどのように関係するのかについても説明します。
自分や自分の周りの人で、インナーチャイルドの症状と重なる場合、どのように治療したら良いのかも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
インナーチャイルドとは何か?
インナーチャイルドと聞いてどんなイメージが浮かびますか?まずはインナーチャイルドの定義や原因、症状について見ていきましょう。
(1)インナーチャイルドとは
インナーチャイルドとは、幼少期の経験や感情が心の奥に残り続け、大人になっても影響を及ぼす「内なる子ども」のことを指します。これは単なる比喩ではなく、子どもの頃に満たされなかった愛情や承認、または受けた傷つき体験が、無意識の中で感情や行動のパターンとして保持されている状態です。インナーチャイルドが癒されていないと、人間関係で過剰に相手に合わせたり、拒絶への恐れから自己主張できなかったり、過去の出来事と現在の状況を混同して強い不安や怒りを感じることがあります。
一方で、インナーチャイルドに向き合い癒していくことで、自分の感情を正直に受け止め、行動パターンを理解し、他者との関係を健全に保つ力が高まります。癒しの過程では、過去の体験を安全な場で振り返り、当時抑え込んだ感情を表現し、自分自身を受け入れることが重要です。
(2)よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさんは、幼少期から家庭内で感情を安心して表現できない環境で育ちました。両親は経済的には安定していましたが、厳格で失敗を許さない態度をとり、Aさんが悲しみや不安を口にすると「弱音を吐くな」「我慢しなさい」と叱責することが多くありました。そのため、Aさんは自分の本当の気持ちを押し殺し、常に「良い子」であろうと努力し続けました。思春期以降も、自分の意見より他者の期待に応えることを優先する習慣が身につき、人間関係では過剰に相手に合わせる傾向が強くなっていきました。
30代になってから職場での人間関係がうまくいかず、慢性的な疲労感や虚無感が強まりました。感情が抑えきれず涙が出ることが増え、医療機関を受診したところ軽度の抑うつ状態と診断され、抗うつ薬が処方されました。服薬で一時的に症状は和らいだものの、根本的な生きづらさは改善せず、ネット検索で「インナーチャイルド」という概念に触れたことをきっかけに、カウンセリングを申し込みました。
カウンセリング初期は、Aさんは自分の感情を言語化することに強い抵抗がありましたが、セラピストとの安全な関係の中で徐々に幼少期の記憶を語るようになりました。1年目は主に自己否定的な内的対話や、自分の感情を否認するパターンを理解する段階でした。2年目には、内面にいる幼い自分(インナーチャイルド)に意識を向け、日々の生活の中で「本当はどう感じているのか」を丁寧に確認する練習を重ねました。3年目には、自分を責める声に対抗し、安心や喜びを感じられる活動を意図的に取り入れることができるようになりました。
現在では、Aさんは職場や私生活で自分の意見を伝える勇気を持てるようになり、他者の期待だけでなく自分の価値観を大切にする生活へと変化しています。インナーチャイルドを癒す過程は今も続いていますが、Aさんは「以前よりもずっと、自分と仲良くなれた」と語っています。
(3)インナーチャイルドを引き起こす原因
インナーチャイルドを引き起こす原因は、幼少期にあります。10歳くらいまでに身体的または精神的な暴力を受けたなど家族関係になんらかの問題を抱え、それがトラウマになっていることが原因です。
自分の心を守るために、幼いながら「甘えたい」などの自分の感情を抑え込んだり欲求を表現しなくなったりします。それによって、大人になっても子どもの頃の出来事がトラウマとなり、子どもの頃と同じ考え方や習慣を繰り返してしまうのです。
例えば、「言い返しても何も変わらない」などと考え、自分の殻に閉じこもってしまうような状態が挙げられます。
Aさんの場合、幼少期に両親が厳格で感情表現を許さない家庭環境で育ったことが背景にありました。「泣くのは弱い証拠」「我慢しなさい」といった言葉を繰り返し受け、悲しみや怒りなどの感情を押し殺す習慣が形成されました。こうした環境が、心の奥に傷ついたままの幼い自己=インナーチャイルドを生み出しました。
(4)どんな症状が出るの?
インナーチャイルドには、どんな症状や特徴があるのか見ていきましょう。
- 孤独を感じやすい
- 自己否定ばかりする
- 対人関係を築きにくい
- 良い子を演じる
- コンプレックスを感じやすい
- 感情を出せない
- 人の世話をしすぎる
- 自己中心的
- 問題から逃げてばかりいる
インナーチャイルドの影響で引き起こされる症状は、このようにさまざまです。人によっても、育った環境によっても違います。また1つの症状だけが出るわけではなく、複合的にいくつもの症状が出ることもあるでしょう。
Aさんは、人間関係で過剰に相手に合わせ、自分の気持ちを優先できない状態が続きました。その結果、慢性的な疲労感や虚無感、感情の爆発や抑うつ気分が現れ、日常生活に支障をきたすようになりました。
インナーチャイルドと相互に関係するものとは?
インナーチャイルドを考える際に、忘れてはならないものが共依存とアダルトチルドレン(AC)です。共依存やアダルトチルドレンをひも解いていくなかでインナーチャイルドが関係していることがわかるなど、密接な関係にあります。
(1)インナーチャイルドと共依存
そもそも共依存は、自分の価値基準がなく、周りの人に判断を委ねてしまう状態のことです。共依存は、インナーチャイルドによって引き起こされる症状と言っても良いでしょう。共依存に陥ってしまうのは、インナーチャイルドが強く作用し、適切で、適度な関係を築くことができず、過剰に相手に合わせてしまったり、依存してしまったりすることが関係しています。そしてそれがお互いにそのようなことをしてしまうことで共依存を深めてしまいます。
インナーチャイルドを癒やすことで、共依存の症状がやわらぐ可能性があります。
共依存については以下のページに詳しく解説していますので、ご興味があればご覧ください。
Aさんは相手の期待に応えることで関係を保とうとする傾向が強く、相手の感情や状況に自分の心が大きく左右される共依存的な関わりが見られました。
(2)インナーチャイルドとアダルトチルドレン
どちらも「チャイルド」という言葉がついているため、つい同じ意味として捉えがちです。両者はたしかに密接に関係しており、インナーチャイルドを癒やすことで、共依存と同じようにアダルトチルドレンの症状が緩和する可能性があります。
インナーチャイルドは、幼少期のトラウマによって抱えてしまう負の感情のこと。アダルトチルドレンは、その負の感情にとらわれて自分らしく振る舞えなかったり生きづらさを感じたりすることです。
アダルトチルドレンについては以下のページに説明しています。よろしければご覧ください。
Aさんは幼少期に安心できる親子関係を築けなかったことで、アダルトチルドレンとしての特徴も示していました。常に「良い子」であろうとする一方で、内面では孤独感や不安感を抱えていました。
インナーチャイルドを癒やすとどうなる?
心理学では、インナーチャイルドの影響で自分らしく生きられない状態にあることを「インナーチャイルドが傷ついている」と言い、傷ついたインナーチャイルドの状態を良くするために「癒やす」という言葉を使います。
つまり「癒やす=克服」の意味です。インナーチャイルドを癒やすとどんなメリットがあるのか見ていきましょう。
(1)過去を理解し現在と切り離して考えられるようになる
インナーチャイルドが傷ついたままだと、過去にとらわれてしまいます。同じような状況に陥った際に「また前回と同じ」と感じて行動できなくなるのです。
モデルケース
例えばAさんが彼氏とケンカしたとしましょう。前の彼氏とケンカした際に自分の意見を言ったために振られました。するとAさんは、今の彼氏と別れたくないために、自分の意見を言わないようにします。
これは正解でしょうか?前の彼氏は意見を言われたことが嫌だったのかもしれませんが、今の彼氏は前の彼氏とまったく同じ考えの持ち主とは限りません。意見を言わないことがかえって別れるきっかけになるかもしれないのです。
インナーチャイルドが傷ついていると、過去と現在はずっと続いていると考えがちになります。しかし実際には、過去と現在はつながっているようでまったく別のものです。切り分けて考えることで、物事を客観的に捉えられるようになります。そうすれば、過去にとらわれていることの無意味さに気づけるようになるのです。
Aさんは、カウンセリングを通じて幼少期の体験が今の人間関係や感情反応に影響していることを理解しました。その結果、「今の相手は過去の両親とは別の存在だ」と切り離して考えられるようになり、不必要な恐れや防衛的反応が減っていきました。
(2)自分の行動パターンを理解できる
幼少期からの習慣は、なかなか取り除けません。これは考え方や行動パターンにも当てはまります。何か問題が起きた場合に、いつも同じ行動をしていませんか?それはインナーチャイルドが影響しているのかもしれません。
知らないうちに、いつも同じ行動をしているために失敗ばかりしていることもあります。これまでの自分の思考・行動パターンを理解することで、いつもとは違う行動ができ、負の感情から解放されるようになるのです。結果、負の連鎖を止められる可能性があります。
Aさんは、人と関わる際に相手を優先しすぎてしまう癖や、自分の意見を抑える傾向に気づきました。これは幼少期に身につけた「良い子」であろうとする生き方の名残であり、そのパターンを理解することで、意識的に別の選択ができるようになりました。
(3)自分の本当の感情に目を向けられる
インナーチャイルドが傷ついたままだと、自分の感情を抑え込み、人の顔色ばかり気にしているケースがあります。インナーチャイルドを癒やすことで、自分の本当の感情に目が向き、自分の気持ちに嘘をつかなくなるでしょう。
また、「自分の気持ちを表現することは悪いこと」という感情もなくなり、抑え込んだ感情を開放できるようになるはずです。
Aさんは、「怒ってはいけない」「悲しんではいけない」と抑えてきた感情を安全な場で少しずつ表現できるようになりました。すると、自分が何に傷つき、何に喜びを感じるのかが明確になり、感情を正直に受け止められるようになりました。
(4)自分を認め、自分らしく生活できる
インナーチャイルドによって引き起こされる症状で説明したように、自己否定ばかりしてしまう人がいます。それによって自分を認められなかったり、自分は幸せになれないと感じてしまったりするケースもあるでしょう。
インナーチャイルドを癒やすことで、今の自分を認めることができ、自分らしく生きていけるようになるのです。
Aさんは、欠点や弱さを含めて自分を受け入れられるようになり、他人の評価だけでなく自分の価値観を基準に行動できるようになりました。結果として、自分らしい人間関係や生活スタイルを築けるようになりました。
インナーチャイルドの克服方法と治し方
インナーチャイルドを癒やし、克服するには、どのような方法があるのでしょうか?克服方法について、順を追って説明していきます。
(1)インナーチャイルドの見つけ方
まずはインナーチャイルドを見つける必要があります。どんな感情があるのかを見つけ、自分のインナーチャイルドを把握しましょう。
方法は、昔の写真を見てその当時のことを思い出したり、家族から昔の話を聞いたりするのもおすすめ。また、当時の問題やそのときの感情をノートに書き出し、客観的に捉える方法も有効です。
Aさんは、日々の中で過剰に反応してしまう場面や感情を手がかりに、心の奥にいる幼い自分の存在に気づきました。特に、強い不安や孤独感を感じる瞬間に、その感情の源をたどる作業を行いました。
(2)どんなことがあったか把握する
幼少期にあった辛い出来事や嫌な感情は、どうしてもふたをしてしまいがちです。ただ、その出来事や感情に触れることで、過去と現在を切り離して考えることができるようになるため、実は重要な作業と言えます。
悲しくて涙が出てくるのであれば、こらえる必要はありません。ぜひ涙を流し感情と向き合ってください。
カウンセリングでは、Aさんの幼少期の出来事を時系列で整理しました。小さな失敗を責められた経験や、感情を表すことを否定された出来事を具体的に思い出し、それらが心に残した影響を確認しました。
(3)大人の行為を否認する
人は自分の心を守るために、物事を良いように考えることがあります。そのため過去を振り返った際に、「あのときの言葉は、当時の親なら仕方がない」「本心ではないのについ言ってしまったのでは…」と大人の行動を容認しているかもしれません。
どんな状況であれ、親や大人が子どもの頃の自分を傷つけたことには変わりありません。「親や大人の行為は間違っていた」と明確に否認しましょう。
ただ、過去の親の行為を責めることができたら、それですべてが解決するということでは決してありません。復讐や恨み、攻撃だけで生きていくことができないのは自明のことです。大切なことは、そうしたことを乗り越えて、自分なりの人生を送ることができるようになることが大事です。
Aさんは、当時の大人の行為を「仕方なかった」と正当化してきましたが、カウンセリングを通してそれを否認し、「あのときの自分は理不尽な扱いを受けた」と認めることができました。
(4)過去に感じた怒りの感情をすべて出す
大人の間違いを明確にすることで、怒りの感情などのこれまで行き場のなかった感情があふれ出てくるはずです。暴れることもあるかもしれませんが、これは悪いことではありません。
このことによって今までため込んでいた負の感情が開放されるでしょう。感情をすべて出す方法には、ノートに書き出す、信頼できる人に話すなどの方法があります。人に言いづらければ、ぬいぐるみなどに話す方法も良いでしょう。
Aさんは、幼少期に抱えた怒りや悲しみを、言葉や涙、時には絵や日記を通じて安全に表出しました。この作業によって心の中の圧迫感が軽減し、感情のエネルギーを健全な形で使えるようになりました。
カウンセラーに相談しよう!自分で癒やすのは大変な作業
インナーチャイルドの克服は、自分1人でできる場合もあります。ただし、過去を振り返らなければならず、自分が考えていたよりも辛い過去であることも考えられるでしょう。
1人でインナーチャイルドと向き合おうとすると、かえって辛さが増しトラウマになるなどが起こり、危険です。また、無資格の人が行う催眠療法を利用したり占い師に頼ったりする人もいますが、専門家でなければ何も解決せず費用だけかさんでしまうこともあります。
インナーチャイルドの克服を考えるのであれば、臨床心理士の資格を持ったカウンセラーに相談するようにしましょう。
Aさんは、1〜3年のカウンセリングを通じて少しずつ心の傷に向き合いました。安全な関係の中で過去を語り、感情を取り戻す作業は、自分一人では難しく、専門家の支えが不可欠でした。
インナーチャイルドについてのよくある質問
インナーチャイルドとは、私たちの心の中に存在する「内なる子ども」を指します。これは、幼少期に経験した感情や出来事が無意識のうちに私たちの心に深く刻まれ、大人になってからもその影響が続くものです。インナーチャイルドは、私たちが抱く恐れや不安、反応、行動に大きな影響を与え、過去の傷が無意識のうちに日常の中で再現されることもあります。この存在を認識し、理解することが、自己理解を深め、心の健康を保つためには重要です。インナーチャイルドは必ずしも意識的に理解できるものではなく、過去の傷や感情に対して無意識に反応していることが多いため、内面の探索を通じてその存在を知り、癒すことが大切です。
インナーチャイルドが傷つくとは、幼少期に受けた心の傷やトラウマが無意識のうちに心に残り、それが大人になってからの感情や行動に影響を与えることを指します。たとえば、虐待や無視、過度な期待、愛情不足などがインナーチャイルドに深い傷を与え、その後の人生において問題を引き起こす原因となることがあります。傷ついたインナーチャイルドは、自己肯定感が低下し、人間関係での不安や過剰な依存、自己批判、感情の不安定さなどを引き起こすことが多いです。これらの傷は無意識のうちに反応として現れることが多く、意識的に気づくのが難しい場合もありますが、心のケアを通じて癒しのプロセスを進めることができます。
インナーチャイルドを癒す方法は、まず自分自身の感情や過去の経験に向き合うことから始めます。無意識に抑圧された感情や未解決の問題に向き合い、理解することで癒しのプロセスが進みます。カウンセリングや心理療法では、専門家と共に過去の経験や傷を掘り下げ、その感情を整理し、癒していくことが可能です。また、自己受容や自己肯定感を高めるための練習も重要です。自分を大切にする気持ちを育てること、過去の自分に対して優しく接することが癒しの一環として必要です。さらに、リラクゼーションやマインドフルネスを取り入れ、心の安定を図ることも有効です。これらを通じて、インナーチャイルドが抱える深い傷が癒され、より健康的な心の状態を築くことができます。
インナーチャイルドが原因で引き起こされる症状には、自己肯定感の低下や過剰な自己批判、感情の不安定さ、過去のトラウマの再体験などが含まれます。これらは無意識のうちに反応として現れ、時に不安や恐れ、怒りといった強い感情を引き起こすことがあります。例えば、他人との関係で過剰に依存したり、自己評価が低いために人間関係で苦しむことがあります。また、過去の傷に対する無意識的な反応として、過度な防衛機制が働いたり、感情を抑圧することもあります。このような症状は、インナーチャイルドが抱える傷に気づかないまま生活していることが多いため、自己認識を深め、適切なサポートを受けることが改善に繋がります。
インナーチャイルドとアダルトチルドレンの違いは、インナーチャイルドが私たちの心の中に存在する「内なる子ども」を指し、過去の傷や感情が影響を与えている状態であるのに対し、アダルトチルドレンは、幼少期に問題のある家庭環境や過度のストレス、虐待などを経験し、その影響が大人になってからも持ち続けている状態を指します。アダルトチルドレンは、過去の経験から学び得た方法で心の中の傷を癒すことが難しく、自己肯定感の低さや人間関係の問題、感情の不安定さを抱えることがあります。アダルトチルドレンはインナーチャイルドの傷が大人になっても解決されないまま残っている状態であり、その影響を癒すことが重要です。
インナーチャイルドを癒すための具体的な方法としては、以下のような方法があります。まず、自己認識の向上が重要です。自分の感情や反応を観察し、どのような過去の経験が影響を与えているのかを理解します。次に、感情の表現を大切にします。抑圧された感情や傷ついた思いを適切な方法で表現し、それを解放することが癒しに繋がります。カウンセリングや心理療法では、専門家と共に過去のトラウマを扱い、その傷を癒していく方法を学びます。また、自己肯定感を高めることも大切です。自分を受け入れ、自己評価を高めるために、日々の練習が必要です。さらに、リラクゼーションやマインドフルネスを活用することも役立ちます。これにより、心を穏やかに保ち、内面的な安定を図ることができます。これらの方法を組み合わせることで、インナーチャイルドの癒しが進み、心の健康を取り戻すことが可能です。
インナーチャイルドの癒しにかかる時間は、個人の状況や過去の経験によって異なります。一般的には、数ヶ月から数年かかることがあります。癒しには時間がかかることもありますが、その過程で心が徐々に楽になり、自己理解が深まっていきます。焦らずに自分のペースで進めることが大切です。特に、過去に受けた傷や感情が複雑で深いものであれば、無理に急ぐことは避け、徐々にその傷を癒していくことが重要です。カウンセリングや心理療法を受けながら、無理なく進めていくことで、癒しの効果を実感できるようになります。
インナーチャイルドを癒すことで得られる効果は非常に多くあります。まず、自己肯定感の向上が挙げられます。過去の傷や感情に向き合い、それを癒すことによって、自分をより深く理解し、受け入れることができるようになります。次に、人間関係の改善が期待できます。インナーチャイルドの傷が癒されることで、他者との関係における不安や過剰な依存が減り、より健全な人間関係を築くことが可能になります。さらに、感情の安定も得られます。過去のトラウマや傷に起因する強い感情が和らぎ、日常生活における不安やストレスに対する耐性が高まります。このように、インナーチャイルドを癒すことは、心の健康を向上させ、充実した生活を送るための重要なステップとなります。
インナーチャイルドの癒しに役立つ書籍やリソースには、いくつかの素晴らしい選択肢があります。まず、『インナーチャイルドを癒す』ジョン・ブラッドショー著は、インナーチャイルドの理解と癒しについて非常に有益な内容を提供しています。次に、『あなたのインナーチャイルドを癒す』シャロン・ストーン著は、実践的な方法とともに、インナーチャイルドとの向き合い方を教えてくれます。これらの書籍は、インナーチャイルドを癒すための第一歩として非常に役立ちます。また、インターネット上でも多くのリソースがあり、オンラインコースやウェビナーを通じて、自分に合った方法を学ぶことができます。これらのリソースを活用し、自分のペースでインナーチャイルドを癒していくことができます。
インナーチャイルドの癒しにおいて、カウンセリングは非常に重要な役割を果たします。カウンセリングを受けることで、専門のカウンセラーが過去の傷や感情に向き合わせてくれ、無意識に抑圧された感情やトラウマを整理する手助けをしてくれます。カウンセリングのセッションでは、自分の感情や反応について深く掘り下げ、インナーチャイルドがどのように影響を与えているのかを理解することができます。カウンセラーは、安全で安心できる環境を提供し、過去の傷を癒すための効果的なアプローチを提案します。このように、カウンセリングを通じて、インナーチャイルドの癒しを進めることができるため、心の健康回復に大いに役立ちます。
(株)心理オフィスKでインナーチャイルドの相談をする
インナーチャイルドとは、幼少期のトラウマによる負の感情のことです。負の感情を抱えたままにしておくと、人間関係や社会生活で生きづらさを感じるかもしれません。そのことが負担となり、うつ病を発症するケースもあるため、早めに臨床心理士などの専門家に相談するようにしましょう。
当オフィスには、インナーチャイルドの克服に精通する臨床心理士の資格を持ったカウンセラーが多く在籍しています。気になることがあれば、お気軽にご相談ください。