日常臨床のための対象関係論 横浜セミナー 第二期のご案内のページです。
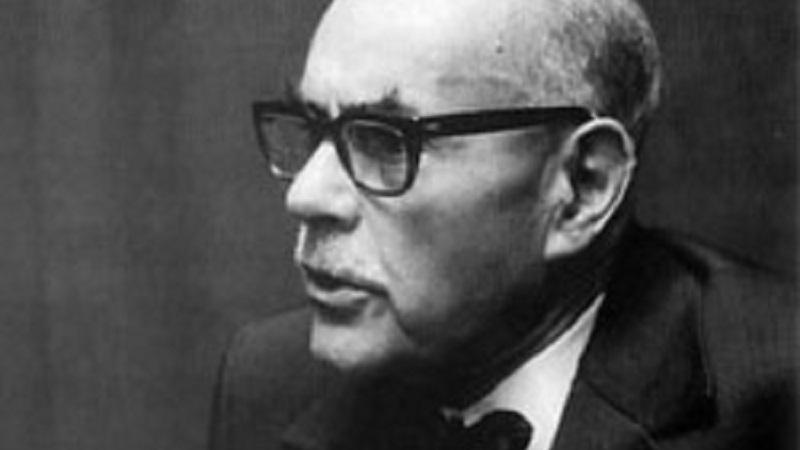
関西大学、関西大学大学院で臨床心理学やカウンセリングを学びました。平成14年に大学院を修了した後は精神病院、心療内科クリニック、小中学校スクールカウンセラー、教育センター、児童相談所、企業内保健センター、開業カウンセリング機関、就労支援施設などを中心にフリーランスで臨床活動やカウンセリングを行ってきました。
また、市民向け自殺防止講演会、専門家向け臨床心理講座、教職員向け研修会などの講師も務めました。大学や専門学校でも「心理学」「カウンセリング」「臨床心理学」「発達心理学」「心理療法」「産業心理学」「精神保健学」などの講義をしてきました。
現在、年間1100~1200セッションほどのカウンセリングを平均的にしています。