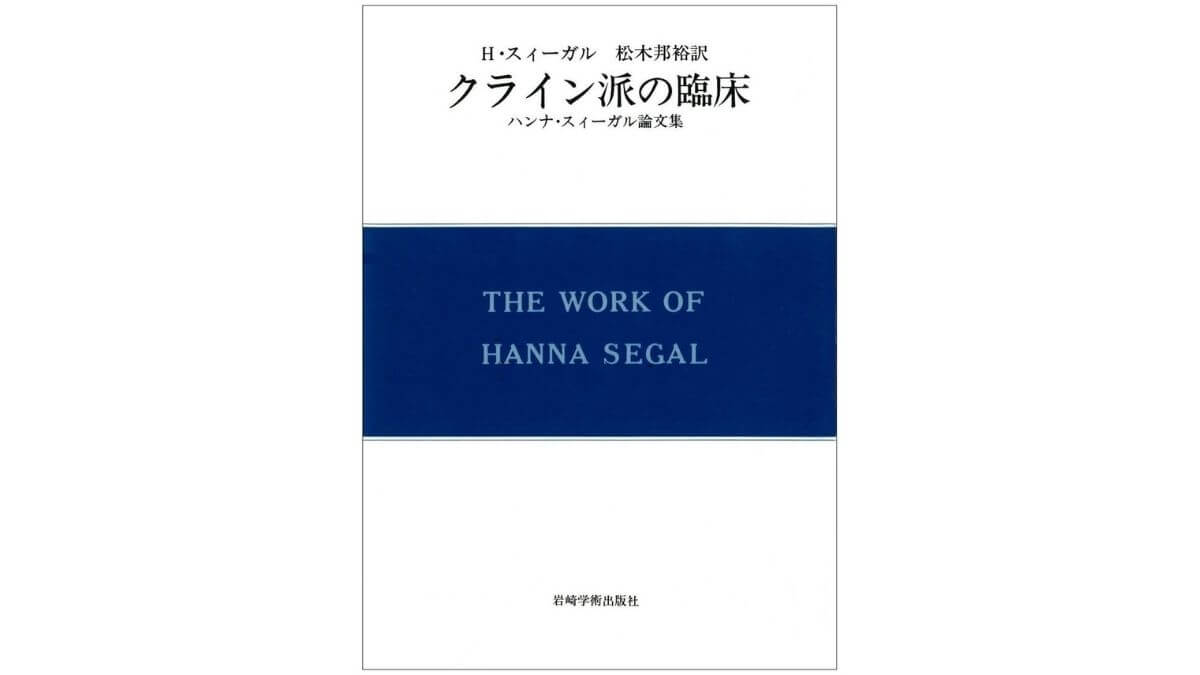快感原則の彼岸

これまでの欲動論を改訂し、死の欲動の概念を精神分析に初めて持ち込んだのがこの論文「快感原則の彼岸(1920)」である。フロイトは反復強迫、外傷夢、エルンスト坊やの遊びから死の欲動を着想した。死の欲動とは生命体が無機物に戻っていくという普遍的な営みのことである。
快感原則の彼岸(1920)の要約
(1)概要
精神分析の理論においては、心的なプロセスが快感原則によって自動的に規制されて進むことは、自明のこととして想定されている。しかし、臨床実践はしばしば快感原則を裏切るようになることを認めざるを得ない。症状の緩和に耐えられず、良くなったに違いないときに再び悪化する患者。外傷的経験を、それに付随する苦痛とともに強迫的に再現する患者。マゾヒズムとサディズム、つまり苦しむことの快と苦しませることの快。これらはどう説明されるだろうか。
本論文でフロイトは、個人の心的機能は快感原則よりも基礎的な葛藤によって統御されていると仮定している。それは生の欲動と死の欲動の根本的葛藤である。彼によれば死の欲動は、あらゆる有機体が持つ、その最初の状態すなわち無機体へと回帰する生物学的欲求に由来する。この欲動の二元論は高度に抽象的であり思弁的であるが、人間の持つ根源的な自己破壊性や攻撃性の問題が取り上げられていると理解できる。
(2)快感原則とその限界
快感原則は経済論的な概念であり、心的な活動は全体として不快を避け、快を得ることを目的とするものである(欲動論)。心的過程において支配している、安定性への性向に関して言えば、それは恒常原則からも導かれる。その目的は、心の中にある興奮量を可能な限り低く維持することである。
しかし、快感原則が心的なプロセスの推移を支配するというのは、本来は正しい言い方ではない。なぜなら、もしこのような支配関係が存在するなら、心的なプロセスのほとんどが快を伴うか、快感に導かれるものとなるはずであるが、実際の経験はこれに著しく反する。要するに、心には快感原則へと向かう強い傾向が存在するが、他の特定の力または関係がこれに逆らうため、最終的な結果は快感傾向に常に一致するとは限らないのである。
快感原則は現実原則に代わる。快感原則は、外界の重圧のもとで有機体が自己を保存するためには最初から不適切なものであり、著しく危険でもある。現実原則は、最終的に快を獲得する意図を放棄することはないが、満足を延期し、快に至るまでの長い迂回路において不快に耐えることを促し、強いるのである。
しかし、現実原則の導入だけでは不快な経験のすべてを説明できない。もう一つの不快の源泉には、抑圧されたものの存在が考えられる。自我の統一に対立して抑圧されたもの(性的欲動)は迂回路を通って直接的な満足や代用的な満足を勝ち取ることができるが、自我はこれを不快として感じる。抑圧は快の可能性を不快の源泉へと変えてしまうのであるが、すべての神経症的な不快はこの種のものであり、快として感じられない快なのである。
(3)快感原則では説明しがたい諸現象
a.外傷神経症
生命を脅かす衝撃に続き、不安や様々な症状、反復夢によって現れる。事実、患者は夢において繰り返し事故の状況に立ち戻り、その度に驚愕とともに目覚める。このことは、夢は願望充足であるという古典的理論と矛盾する。
b.子供の遊戯
フロイトの孫エルンスト(1歳半)の観察。彼は細紐の端を持って糸巻をベッド越しに投げ込み、糸巻が姿を消すと「オー(fort=いない)」と叫んだ。そして紐を引っ張って糸巻をベッドから取り出すと「ダー(da=いた)」という言葉で糸巻を迎えた。
これは姿を消すことと姿を現すことで成立する一組の遊戯であった。これは母親が「いない」と「いた」になることを自分で演出していたのである。子供は能動的な役割を演じて、不快に満ちたこの経験を繰り返し、克服しようとしたのかも知れない(支配欲動)。また、日頃は抑圧されていた母親に対する復讐衝動によるものかも知れない。
(4)反復強迫と転移
精神分析は当初、何よりも解釈の技術であった。しかし、患者が自らの回想によってこの解釈を確認する必要があるという次の目標が登場した。ここで最も重要な問題となったのが患者の抵抗であり、その抵抗を放棄するように働きかけることが精神分析家の役割となった。
しかし、患者は抑圧されているものをすべて想起することができず、現在の経験として反復するしかない。こうした再現は、幼児の性的な生活、すなわちエディプス・コンプレックスとその派生物の一場面を内容とするものであり、転移の領域、すなわち医者との関係において演じられるようになる。この反復強迫において、主体は昔の経験を反復することによって能動的に苦しい状況に身をおいているように見える。
神経症者はすべての望ましくない状況と苦痛な情緒状態を転移において反復し、いとも巧みに生き直すのである。彼らは治療を未完のまま中断させようとし、医者が自分に対して冷淡な態度を取らざるを得なくする。また、他者との関係がいつも同じ結末に終わる人もいる。転移の際の態度や人間の宿命についてのこうした観察に基づいて、心的な生には反復強迫が存在し、それは快感原則の彼岸にあると考えられる。そして反復強迫は、快感原則よりも根源的で、基本的で欲動に満ちたものである。
(5)刺激保護の役割
知覚‐意識(W‐Bw)システムを基盤とした小胞モデル。生きた小胞は外界に対する〈刺激保護〉を装備している。この〈刺激保護〉を突破するほどの強さを備えた外部からの興奮を〈外傷性の興奮〉と呼ぶ。外部からの外傷のような出来事が発生すると、有機体のエネルギー活動に非常に大きな攪乱が生じ、あらゆる防衛手段が行使される。しかしその際に快感原則は無力化されている。心的な装置が大きな刺激量によって満たされることは、もはやとどめようがない。そのため刺激を制御し、外部から入ってくる刺激量を心理的な意味で拘束して、処分できるようにすることが新たな課題となる。
ここで、「夢は願望の充足である」という命題の例外を、初めて認めねばならない。災害神経症の夢において、患者が規則的に災害の場面に連れ戻される場合、これは願望の充足に役立つのではない。こうした夢は、不安を形成しながら刺激を克服することを目指しているのであり、不安が形成されないことが外傷神経症の原因となっていたのである。この機能は快感原則に矛盾するものではないが、それとは独立しており、快感を獲得し、不快を避けるという目的よりも根源的なものである。そしてそれは、反復強迫に従うものである。
(6)あらゆる生命の目標は死である
これまで、子供の心的な生の早期の活動と精神分析の治療の経験に触れながら、反復強迫の表現について記述してきたが、これは強度に欲動的な性格を示している。子供の遊戯の実例では、子供があえて不快に満ちた経験を反復するのは、受動的に経験しているだけの場合と比較すると、反復によって強い印象をしっかりと克服できるからであると理解することができる。
新たに反復が行われる度に、こうした印象を支配するという目標の達成が進むと考えられるのである。子供は、大人が読み聞かせた話や演じた遊戯を、大人がうんざりするまで繰り返すことを求め続ける。反復、すなわち同一性の再確認そのものが、快感の源泉となっているのは明らかである。
欲動とは、生命のある有機体に内在する強迫であり、早期の状態を反復しようとするものである。すべての欲動が初期状態への回帰を目指しているものと想定しよう。これまでの経験から、すべての生命体が〈内的な〉理由から死ぬ、すなわち無機的な状態に還帰するということが例外のない法則として認められると仮定すると、すべての生命体の目標は死であると述べることができる。
(7)欲動二元論
これまでのリビドー理論の発展段階を概観してみよう。
a.性欲動と自我欲動(自己保存欲動)の対立
初期のフロイトの理論である。
b.自我の概念
自我は抑圧し、検閲し、防衛機制や反動形成を営むことのできる審級として知られていただけであった。しかし、精神分析はさらに慎重に観察を進めながら、リビドーが規則的に対象から引き離され、自我に向けられることに注目した。
そしてリビドーの発展を研究した結果、自我がリビドーに固有の根源的な〈器〉であり、リビドーはこの〈器〉から出て対象に向けられるという洞察が得られた。自我は性的な対象として認められ、しかも性的対象の中で最も重要な位置を占めるようになった。
このようにリビドーが自我の中にとどまる間は、これはナルシシズム的なリビドーと呼ばれた。これは性欲動の力が表現されたものであり、最初から存在が確認されていた自己保存欲動と同一のものと見る必要があった。このため、自我欲動と性欲動の根源的な対立という考え方は不十分なものになった。
c.生の本能と死の本能の対立
反復強迫という現象から、自我の内には自己保存欲動とは異なる欲動が働いていることが推測された。こうして死の本能の概念を導入し、生の本能と死の本能の対立を仮定した。
対象愛にも、これと同種の両極性が見られる。愛(情愛)と憎しみ(攻撃性)の対立である。我々は以前から、性欲動にサディズム的な要素を認めていた。この要素は独立して働き、倒錯として人格の全体の性の営みを支配することがある。しかし、対象を傷つけようとするサディズム的な欲動を、生命を保存するエロスからどのようにして導き出すことができるのだろうか。
このサディズムは死の欲動であり、これが自我のナルシシズム的なリビドーの影響によって自我から追い出され、まず対象に現れると考える方が分かりやすい。その場合、サディズムは性的な機能に奉仕するものとなる。リビドーの口唇愛体制の段階では、愛の対象を独占することは対象を破壊することと一致するが、その後でサディズム的な欲動が分離する。
そしてサディズムは、性器優先的な段階に至って、生殖の目的を満たすために、性的な行為の遂行に必要な範囲で、性的な対象をできるだけ征服するという機能を果たすようになる。あるいは、自我から押し出されたサディズムは、性欲動のリビドー的な要素に進むべき道を指し示すのであり、サディズムに続いてリビドー的な要素が対象に迫るとも言える。原初的なサディズムが緩和されず、他のものと混淆されない場合は、愛情生活においてよく知られている愛と憎しみのアンビヴァレンツが支配的なものとなる。
(8)補遺
快感原則は、心的装置に全く興奮が起こらないようにするか、興奮の量を一定に維持する機能を担っている。この機能は、無機的な世界の静止状態に復帰するという、すべての生命体の最も普遍的な営みに関与するものである。性的な行為のもたらす快楽は、最高度に高まった興奮が瞬時的に消滅することに結びついている。すると欲動興奮の拘束は準備的な機能であり、興奮を調整して、放出の快感において最終的に解除するものである。
死の欲動は目立たぬ形で作業を続けるが、生の欲動は障害として現れ、絶えず緊張を伴い、その解除が我々に快として感受される。快感原則は実際には、死の欲動に奉仕するものと思われる。
(9)感想と疑問点
苦痛なことばかり体験する患者。それが不安を克服するための機能というのは納得がいった。しかし、それはむしろ“生きる”ための心の働きであるように思った。フロイトはなぜ「死」という言葉を使ったのか。
(10)議論したい点
自分の対人関係のパターンを理解している人は結構多い。その上で解釈として取り上げるにはどのようなやり方があるか。
快感原則の彼岸(1920)の解説
(1)ポイント
「無機的な世界の静止状態に復帰するという、すべての生命体のもっとも普遍的な営みに関与するものと思われる」
(2)論文の背景
フロイトは1919年3月に本論文の執筆に取り掛かった。同時期に「不気味なもの」も執筆しており、その中で本論文の要旨について数多く言及されている。特に反復強迫について、もっとも深い欲動であることを示唆している。ただ、死の欲動についてはまだ言葉にはなっていなかった。
1919年秋には「不気味なもの」が出版されたが、本論文は据え置かれた。1920年初頭に再び本論文に取り掛かり、その2月20日のアイティンゴンへの手紙ではじめて死の欲動について記載された。1920年7月に本論文が完成し、9月9日の国際精神分析学会学術大会の講演の際に、本論文が出版予定であると予告した(ストレイチー)。
「不気味なもの」については以下をご覧ください。
本論文を執筆する原動力になったこととして、娘ゾフィーの死や第一次世界大戦、上顎ガンが挙げられる。特にゾフィーの死の前に草稿は完成していた、としてくれるようにフロイトは口裏合わせの要望をアイティンゴンにしていたようで(1月18日)、そうしたことも逆説的にゾフィーの死は意識的にも無意識的にも影響していたと推測できる。
フロイトは本論文の中で、最愛の者を亡くさざるをえない時、避け得たと考えるよりも、自然の法則、崇高な必然の運命であったと考えることを望むだろう、と書いている。これは死の哀しみに対するある種の防衛であり、誤魔化しであるとフロイトは言っている。そうしたことをフロイト自身もしてしまうことは認めがたいことだったのかもしれない。
フロイトの根本的な価値意識は、生物学的自然観、唯物論的生命観、進化論などに影響を受けている。その見地からすると、精神よりも身体、意識よりも無意識の欲動、生よりも死の方が恒常的で自然な状態であるとみる。それからすると、生の欲動よりも死の欲動を一次的な存在とし、その力の方が強力に人間に作用を及ぼすとするのはある意味では自然である。「生は死への迂路である」と小此木(2002)は述べている。
(3)本論文の影響とその後の展開
この1920年の欲動論の転回は非常に大きな影響をもたらした。これまでのフロイト理論のほとんど全てが生の欲動と死の欲動といった観点から書き直されていった。
しかし、この死の欲動については広く浸透せず、アンナ・フロイトのような近い立場の人でさえ否定的だった。その理由としてキノドス(2004)は、攻撃的・破壊的な欲動が心的生活の中で果たす役割に対して拒否感情があり、そうした防衛的な態度が死の欲動に対する否定的態度となっていることを挙げた。
また、フロイトも思弁的と言っているように、臨床的応用についてはほとんど語っていなかった。また、死の欲動を例証する臨床事例・臨床的事実についてはほとんど記していなかった。そうしたことは死の欲動をどのように取り扱い、解釈するのかが分からないことに起因して、死の欲動に対する否定的態度となっていったことも理由として挙げている。
しかし、メラニー・クラインはこの死の欲動を継承し、臨床と理論の中軸に据えた。メルツァー(1978)やヒンシェルウッド(1989)が述べているように、思弁的と言いつつも、転移の中の反復、戦争体験者の外傷的な反復夢、子どもの糸巻き遊びなど臨床的な素材が用いられており、十分に理論化に耐えられるものであるとしていた。
確かに死の欲動はフロイトの言うように沈黙のうちに働くのかもしれないが、投影を介し、現実に姿を現す死の欲動は非常に攻撃的で、破壊的であり、それは動的なものであると言える。一部には、そうした破壊性は実際には生の欲動であり、性的リビドーであるという批判もある。しかし、それに対してローゼンフェルド(1971)は陰性ナルシシズムの臨床論文から反論している。
(4)陰性治療反応
フロイト(1918)は狼男の無意識が明らかになるたびに改善していたものが悪化するという事態に遭遇した。そうしたことを一時的な陰性反応と名付けていた。その後、「自我とエス(1923)」で陰性治療反応に対して本格的に理論化を行い、自己洞察や自己理解が深まり、ワークスルーが進んでいるにも関わらず、症状や問題が増悪、悪化することを陰性治療反応とした。このことは死の欲動と結びついた超自我からの押し付けられた過酷な罪悪感に起因するものとした。これらは死の欲動の一つの表れである。
また、リビエールは陰性治療反応を抑うつポジションの生む罪悪感という苦痛に耐えられずに、躁的防衛で緩和させようとする動きとして定式化した。
その後、陰性治療反応は単なる一時的な反応ではなく、羨望とナルシシズムと結びつけられ、組織化されたパーソナリティ構造として理解されていくようになった。
さらに独立学派のケースメントは陰性治療反応を幼児期の外傷体験に基づいている、先立つ安心感とそれに引き続く惨事という無意識の連結がもたらす改善への反応とした。
(5)羨望
羨望の詳細については以下のページをご参考にしてください。
羨望とは、良いものを持っている他者に対する強烈な怒りと憎しみのことである。最早期にはミルクを与えてくれる乳房に向けられている。悪いものを破壊するのではなく、良いものを破壊するというこの衝動によって、良いものを取り入れ、同一化し、成長していくということを根本から阻害してしまうことに病理の深さが読み取れるであろう。
こうしたことが臨床的にあらわれると、良い解釈を与えてくれる精神分析家に、良いものを持っている精神分析家に向けられる。そして、良い体験をした途端に羨望が強く働き、解釈を破壊し、精神分析家を破壊し、分析関係をも破壊してしまい、結果的に増悪や悪化といった陰性治療反応が引き起こされることになってしまう。
これらの良いものを破壊する衝動は死の欲動の臨床的な表れといえる。そして、クライン派精神分析ではこの羨望のワークスルーが最深部にある課題であるとしている。
(6)破壊的ナルシシズム
ローゼンフェルトらが、羨望の影響下において、ナルシシズムを中心として、様々な苦痛から防衛するために、高度に構造化された自己愛的な構造体を構成し、その中に逃避する様を論じた。破壊的ナルシシズムという。これは破壊性や攻撃性が理想化され、健康な自我の部分を脅迫し、コントロールし、支配する。普段は目立たないが、人格そのものをのっとり、裏から支配している。現状維持が目論まれ、変化することや成長することが危険なことであると認識し、そのような事態になりかけると陰性治療反応が発動し、もとの状態に戻してしまうのである。
このような自己愛構造体が維持されている限り、抑うつ的な苦痛を乗り越え、抑うつポジションを達成することを妨げられてしまう。同時に、妄想分裂ポジションからの不安からも防衛することができ、一種、嗜癖的にその状態に沈殿し、倒錯的な満足を得ようとする。
シュタイナー(1993)は自己愛構造体の概念を整理し、妄想分裂ポジションと抑うつポジションに対する防衛的側面を強調した。そして両ポジションの間に第3のポジションとして、病理的組織化を置いた。これら3つのポジションの変化を好まない平衡状態を維持することが目的となっている。
(上記は「ナルシシズムの導入にむけて(1914)」講義の再掲)
(7)クライン派の死の欲動理論に対する批判
図1 オットー・カーンバーグの写真
カーンバーグ(1969)は死の欲動は「臨床的に沈黙である」と率直で簡潔な批判を行った。その他に、死の欲動のように見えているのは、リビドーの欲求不満が現れ、それが破壊的に見えているだけである、というものもある。
特にウィニコットは外界からの侵襲に対する反発として、反応としての攻撃性として理解しており、そうした意味で攻撃は死の欲動に起因する一次的なものではなく、反応性つまり二次的なものであるとした。そして、多くは活動性といった概念にまとめられていき、成長発達因子として理解されていった。また、攻撃はコミュニケーションの原始的な形式でもあり、対象が主体の攻撃に生き残る時、初めて対象恒常性が獲得され、自と他の分化につながっていくとした、それは死といった絶望的なものではなく、対象と関係を持つ希望といえる。
藤山(2008)は「反復強迫というのは、実は非常に破壊的だったり非常に絶望的な状況を、もう一度自分がマネージしようとする絶望的な努力だというんです」と述べ、こうした建設的な努力からすると、反復強迫が死の欲動であることに対して疑義を投げかけている。
(8)死の欲動の有無
上記の項目からすると、死の欲動が本当にあるのか、もしくはないのかは現在でも議論が続いているトピックであると言える。おそらく、死の欲動が実際にあるのか、それとも架空のものなのかといった正しさの議論は意味がないとは言わないが、不毛であるのかもしれない。
小川(2008)は本論文について、「フロイトがなにか無意識の真理を捉えて、混乱した文章で伝えているものを、知性と論理という意識の次元だけを用いても理解することはできない。我々は、この書物の全体をメタファーとして、夢として、体験しなくてはならないだろう」と述べている。
おそらく、この論文に個々の臨床家が何を見て、何を体験するのか、そして何を見出すのかといった個別の課題とする方が良いのかもしれない。本論文に死を見出すのか、それとも希望を見出すのかは個々の臨床家の人間観や治療観に強く根差し、個々によって変わってくるのだろう。本論文を素材にして、我々個々の臨床家は自分のスタンスを今一度見つめなおす機会になれば良いのかもしれない。
終わりに
精神分析についてさらに知りたい方は以下のページを参照してください。
参考文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。
- D.W.ウィニコット(1968)攻撃性の根源
- D.W.ウィニコット(1968)対象の使用と同一化を通して関わること
- 小此木啓吾 監修(2002)精神分析事典 岩崎学術出版社
- 小川豊昭(2008)快原理の彼岸-死の欲動と反復
- J.M.キノドス(2004/2013)フロイトを読む. 岩崎学術出版社
- P.ケースメント(1985)患者から学ぶ. 岩崎学術出版社
- J.シュタイナー(1993)こころの退避. 岩崎学術出版社
- J.ストレイチー(2005)フロイト全著作解説. 人文書院
- R.D.ヒンシェルウッド(1989/2014)クライン派用語事典. 誠信書房
- 藤山直樹(2008)集中講義・精神分析 上. 岩崎学術出版社
- S.フロイト(1918)ある幼児期神経症の病歴より
- S.フロイト(1923)自我とエス
- D.メルツァー(1978)クライン派の発展. 金剛出版
- J.リビエール(1936)陰性治療反応の分析への寄与
- H.ローゼンフェルド(1971)生と死の本能についての精神分析理論への臨床からの接近