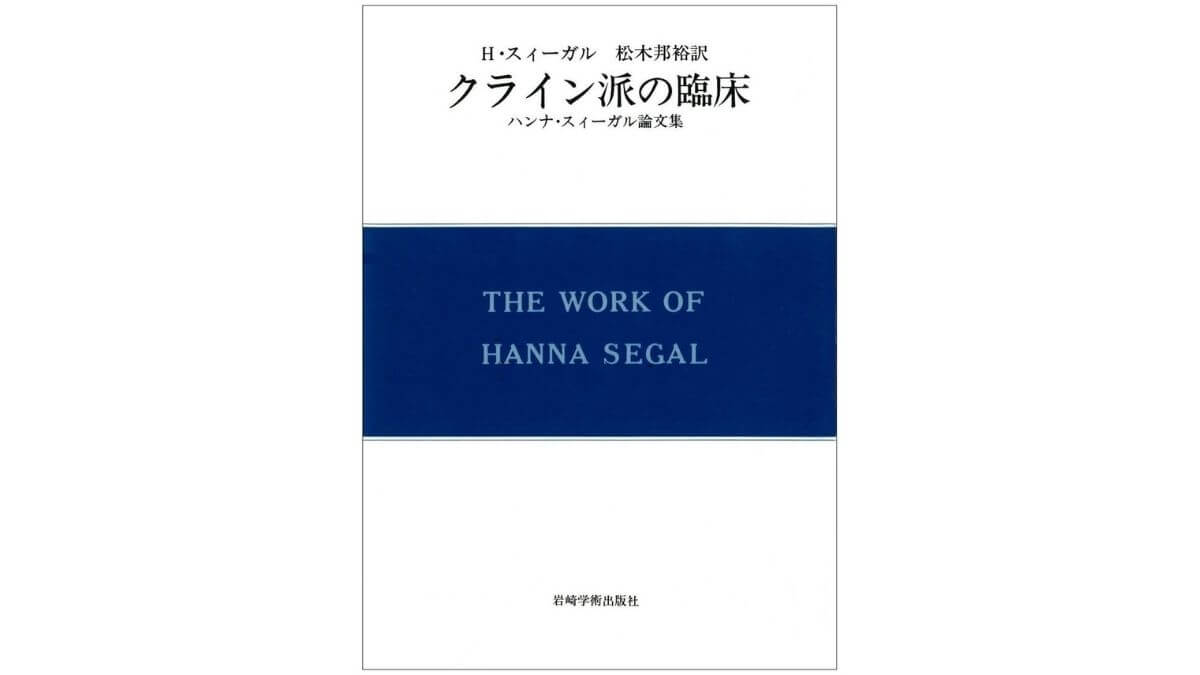出生外傷

オットー・ランクが1924年に書いた「出生外傷」という本の要約と解説である。これまでフロイトがエディプスコンプレックスを発達の中心に添えていたのを、ランクは出生外傷に置き換え、定式化しなおした。またそれによって精神分析技法も大幅に変え、短期精神療法への草分け的存在へとなっていった。
図1 オットー・ランクの写真
目次
出生外傷(1924)要約
Das Trauma Der Geburt by Otto Rank(独)
The Trauma of Birth by Otto Rank(英)
(1)ランクとフロイトの関係
本書の冒頭には、「無意識の探究者、精神分析の創始者、ジクムント・フロイトに捧げる」という一文が添えられ、当時の時代状況及び革新的な本書の内容から強くフロイトを意識したものになっている。しかし、ランクのそのようなフロイトへの配慮にもかかわらず、本書をきっかけとし当時の精神分析サークル内の政治的な事柄や人間関係も影響し、フロイトの最側近という立場は奪われ、精神分析界からランクは「離反」することになっていった。
精神分析界にも大きな衝撃を与え、ランクにとっても外傷になった。本書は第1章から第11章からなり、当時語られていなかったプレエディパルな視点から、母体回帰及び出生の外傷が精神分析、神経症、宗教、哲学、芸術などの人間の本質にかかわる事柄にいかに影響を与えているかを論じている。以下、第1章分析的状況、第2章幼児的不安、第3章性的充足、第4章神経症的再現の順に概要を述べ、若干の考察と疑問を記述する。
(2)精神分析的状況
本章では、精神分析状況は患者が精神分析家を通した母体回帰であり、精神分析治療においては患者が出生の外傷を再演しないようゆるやかに出生させることが精神分析家に求められ、母親への原固着の解消のために“期限設定”の技法についても提案する。
ランクは、精神分析の最終段階において無意識の治療の過程が”出生象徴”の中で表現されるという現象に注意を引かれ、その特徴を『治療過程におけるリビドー発達の理解に向けて』の中で以下のよう記述する。患者は回復期になると『生まれ変わったかのように』感じると述べ、母親もしくは父親との間にできた子を彼らに贈りたいと願う空想は放棄され、自分自身を新たに生まれた(心的な)子どもとみなし、エディプス・コンプレックスの中で見出される幼児期的なリビドー固着を断念できるようになる。
このような『再出生空想』は幼児期的な特徴であり、もう一方では『神秘的な』特徴を有していると考えられるが、ランクはユングが無視した『再出生空想』のリビドー傾向を主張する。母親への固着は、精神分析的な固着の基礎をなし、母親の身体への最早期の純粋に生理学的な結びつきが含まれる。
精神分析の中では、『再出生空想』は患者の出生の反復であり、精神分析家に向けられたリビドーを解消することは、母親の身体へのリビドーの切り離しであり、すなわち母親から新たに生まれることに相当する。また、それらは患者の性別に関わらず、精神分析家が知識の有無に関係なく存在し、患者は精神分析状況の中で妊娠期間を、精神分析家との別離である精神分析の終結には出生行為を経験する。
すなわち、精神分析とは十分に克服されなかった出生外傷の事後的な処理だということが明らかになったのである
とランクは述べている。一方このような精神分析の中で生じる状況は、精神分析の期間があまりにも長いために生じたものであるという批判が聞こえてくるが、そのような批判に対し、ランク自身が行う精神分析の期間は、4ヶ月から長くとも8ヶ月であり、長くはないと反論をする。出生外傷はもっとも苦痛に満ちた「記憶」であるため、通常思い返すことはないが、「自由な思いつき」という技法の中で、転移が生じ、現状況が再現される。
さらに、ランクは出生外傷の解消のため、期限設定の技法を提案する。精神分析家の課題は、母親への原固着を解消することであり、まずまずの満足をもたらす精神分析状況を無期限に求める患者に対し、精神分析に期限を設定することで、出生外傷をゆるやかな解消に置き換える。
(3)幼児的不安
本章では、通常の発達ラインを遂げる子どもの不安を出生外傷との関わりの中で解き明かす。出生の外傷の克服にはおおむね長い年月が必要であり、子ども時代のすべてが求められ、子どもはみな不安を抱え、それは神経症と称しても、差し支えないほどである。
子どもの不安の典型事例である、“薄暗い部屋の中に”置かれる時に生起する不安は、子宮内状況を想起されることから生じる。このように、閉所恐怖、鉄道不安、トンネル不安、旅行不安などは、無意識的な出生外傷の再現であることが分かる。
次に、第二の典型的な不安状況、“動物に対する不安”については、子どもに不安を喚起させる動物が大きい事、あるいは太っていることは妊娠と関連し、そのことが苦痛に満ちた原不安を子どもたちに喚起させる。また、小さな動物、ネズミ、ヘビ、カエル、甲虫についても恐怖と混じり不安情動が喚起される。
小さな動物は地面の小さな穴などの中に消え去ることが出来、それは母の隠れ家の中に戻ろうとする願望が刺激されるのと同時に小さな動物が与えるおののきによって、出生外傷が反復され、恐怖が生じる。以上のように、あらゆる不安が出生不安に基づくものであるが、それと同時に、“あらゆる快は結局のところ子宮内の原型を繰り返し再建しようとするものである”と述べる。
快を得るための動作である、指しゃぶりは母親との一体感、特に足の指が好まれるのは子宮内の姿勢を再建しようという傾向を示している。
一方、去勢不安の観点からはどのように考えていくことができるだろうか。女性器は出生外傷の場として根源的な不安情動の中心的な対象となるため、「去勢コンプレックス」は出生行為という否定のしようもない普遍性に由来するものと見なすことができる。
さらに、出生や離乳のような現実の外傷は本当に苦痛に満ちたものとして経験されるが、去勢の威嚇は空想であるため、むしろ分離は起こりえないものなのだという慰めとして作用する。同時に、出生の外傷の否認を可能にするために、「去勢」(女性器)を認めようとしないのである。
子どもの遊びについて考えてみると、「かくれんぼ」は分離と再発見を表現し、「ブランコ」などのリズミカルな遊びは、子宮内で感じていたリズムを単純に反復するものである。ある種の稚魚やカンガルーといった動物は母親の身体を母胎回帰の場として利用するが、一方、人間は以上のように遊びや不安場面において象徴的に母体回帰をする
(4)性的充足
本章は、性的充足と出生外傷の関連を幼児の性の問いやフェティシズム、男性主義的傾向、女性器の否認、そして、性的結合という視点から論じる。神経症患者の中に抑圧抵抗によって受け入れられない“真実の答え”があるように、幼児の性への問いの中には、自らが以前に滞在した場所での失われてしまった記憶の再現の希求が込められている。
女性器は出生の際の外傷を想起させる恐れがあるため、女性器は否認され、フェティシズム、すなわちリビドー対象は身体部位を覆うもの(衣服、靴、コルセットなど)に置き換わる。また、マゾヒズムは出生の苦痛を快に満ちた感覚への変換、幼児虐殺や切り裂き魔といったサディズムは、幼児期的な好奇心や胎内から追放されたという憎しみの体現である。
さらに、ランクは、社会的、科学的な思考といったものの見方や世界の捉え方が、全体としてあまりにも男性的見解を全面に押し出し過ぎていること、すなわち女性を社会的にも知性の面からも卑下している傾向を原抑圧との関係で考える。
性交については、ペニスは幼な子の象徴であり、女性の開口部に入り込むことは、母体回帰を意味し、女性においては、胎児との同一化の中にこうした願望の充足が母性愛として表現される。そして、性的結合において頂点に達する性愛とは、母親と子どもとの間の原状況の部分的再建に向けた際立った試みである。
一方、エディプス・コンプレックスは、子宮内の快、すなわち抑圧によって埋没していた古い快の源泉を再び開く、初めから失敗に終わるよう運命づけられた試みであり、それは分離という原外傷の再演である。
(5)神経症的再現
本章は、神経症から精神病、器質的疾患といった様々な病理現象を母体回帰及び出生の外傷の再現として読み直す。個々の症状やあらゆる神経症状は、実際にそこで問題となっているのが出生の際の、あるいは快に満ちた母体内の再現であることを示している。たとえば、神経症的呼吸困難(喘息)は出生の際の窒息状態の直接的な身体的再現であり、神経症性の頭痛(片頭痛)は、出生行為の際の身体の痛みの逆行である。
また、神経学的なあるいは器質的なものと認定された事例においても、無意識においてはリビドー充足の源泉と庇護のもとへと退行するように自我は強いられているため、「心的」なものと認められた事例と同様に捉えることが出来る(ナルコレプシー、呼吸困難、チックなど)。
さらに、強迫症患者の強迫的思考は、出生外傷を知的に克服しようとする幼児の最初の試みを引き継ぐものであり、躁と鬱の急速な交代を伴う病態は、最初のリビドー対象の喪失の際の快―不快という原メカニズムの再体験であり、出生の外傷前と後の感情状態の再現にほかならない。
精神病的な妄想はリビドー適合しない外的世界を、世界のあらゆるものの中でもっとも素晴らしい子宮内の存在へと置き換えてしまう現象である。幻覚やカタレプシーといった精神病的症候群は、精神分析という意味では、神経症以上の広範な退行であり、世界全体が子宮にし、母への帰還を目指す傾向がある。
(6)感想、考察、疑問、議論点
人は出生という行為によって生まれながらに心に深い傷を負い、生が始まるという主張にはいささかペスミスティックなところも感じられ、神経症から精神病、器質的なものまで一貫して出生外傷との関連の中で論じるランクに驚きを感じもするが、出生が人に根源的な影響を与え、不安の際に母体回帰を希求するという考えには素直に頷ける。
一方で、精神分析において精神分析空間に患者が抱えられる環境は、患者にとって子宮の中のように外界の刺激から守られた空間であり、ランクは精神分析状況≒子宮と主張する。
精神分析はニードが完全に満たされた状況、すなわち母体という空間ならば、そのような理想的な空間において、精神分析にとって大切な“考える”という作業は生じるのだろうか。また、現在の臨床的感覚では、母体回帰という着想からは愛着という用語を連想することが出来、母親を安全基地として利用する愛着行動や内的作業モデルという概念との異同についても議論をしたい。
出生外傷(1924)の解説
(1)オットー・ランクの生い立ち
- 1884年4月22日にウイーンで出生。宝石商だった父親は暴力的で、後に両親は離婚し、父親とは絶縁。幼少期、病気がちで、また男性からの性的被害があったらしい。思春期には対人恐怖、不潔恐怖を発症。
- 1898年、家が裕福ではなく、技術学校を卒業後は、14歳で機械店の見習いになる。
- 1903年、19歳の時にオットー・ランクと改名。おそらく戯曲「人形の家」の登場人物に由来している。
- 1905年、多数の書物を読んでいたランクは精神分析を知り、アドラーの紹介で21歳頃にフロイトに出会う。フロイトによる援助でギムナジウムに入学でき、また秘書や書記としての仕事を与えられる。神話、文化、芸術の理解に精神分析理論を応用していった。
- 1916年、従軍中の32歳の時に、現地の女性と知り合い、結婚。
- 1922年、38歳の時、フェレンツィとの共著「精神分析の発展目標」を執筆。
- 1924年、40歳の時、出生外傷を執筆。
- 1926年、42歳の時、パリに移住。以降、精神分析から中断療法に移行。フロイトからの離反は理論的相違よりも弟子同士の感情的諍いによる要因が大きい。
- 1934年、50歳の時、アメリカに移住。
- 1939年10月31日にニューヨークで死去。享年55歳。
(2)訳語
出産外傷ではなく出生外傷。出産だと母体の外傷を想起させるため。実際には乳児の外傷。
(3)母子関係の重視
- 原型としての母親からの分離。出生が外傷となりうる。
- 象徴的には分離不安、具象的には出生外傷。
- 不安の根っこは出生外傷であり、それの置き換え。
- 原点を治療することで短期に精神分析治療が終わることができる可能性を示唆。
- 3つの外傷(出生、離乳、去勢)
- 母体回帰空想について。死に対する憧れと恐怖。
- 人間は死が怖いのは、出生時に一度は死を経験しているから。死は出生における外傷の反復を惹起させる。
(4)文化、宗教、神話
文化的営み、宗教的儀式、神話等は母体回帰空想と出生外傷を象徴的に表している。
(5)中断療法
- 精神分析の長期化に対する不満。
- 出生外傷がすべての不安の根源である。つまり、出生外傷だけを扱うだけで充分である。
- 1ヶ月~18ヶ月の間で精神分析期間を設定する。
- 精神分析家からの分離を利用し、分離不安を克服させる。
- 母子関係とhere and nowの重視
(6)短期精神療法
- そもそも、フロイトの精神分析はほとんどが数ヶ月から1年以内に終結していた。ウルフマンの数年にわたる精神分析は例外。
- それがライヒの性格の鎧の理論やクラインによるプレエディパルの精神分析により一気に長期化していった。
- ランクの中断療法を出発点に、様々な短期精神療法が編み出されていった。
a.シフニオスの不安挑発的精神療法
- エディプス葛藤を治療のターゲット
- 厳格な患者選択(高い動機付け、平均以上の知能、自我の強さ、限局性の葛藤)
- 精神分析家は非常に能動的
- 回数はあらかじめ設定はしないが、多くは20~30回程度。
b.マンの時間制限精神療法
- 限りのない回数は、母子関係は永劫であるという幻想とイコール。
- 暦を導入することにより、現実の直面化。
- 分離不安の究極的な体現。
- 治療回数は12回。
c.その他
- バリントの焦点化精神療法
- フェレンツィの積極技法と弛緩技法
精神分析の無時間性、自由連想法、禁欲原則、精神分析家の中立性と受動性などに対するチャレンジ。
おわりに
こうした精神分析についてさらに学びたいという方は以下をご覧ください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。