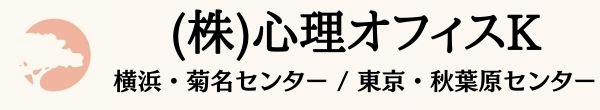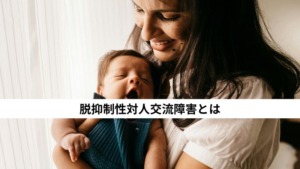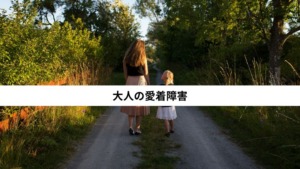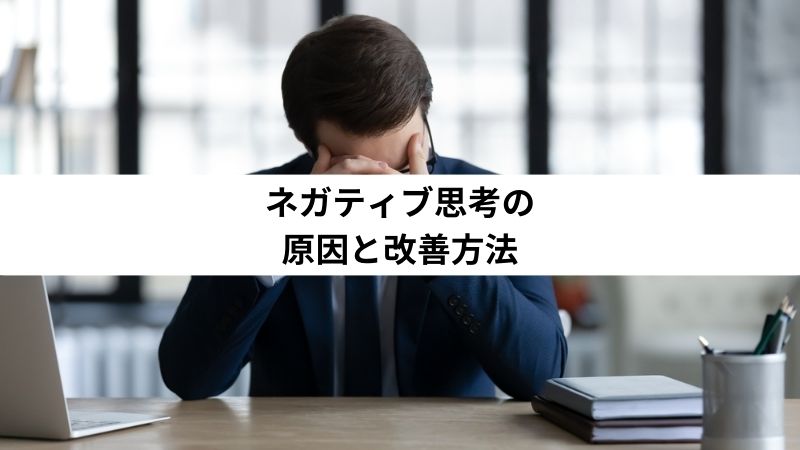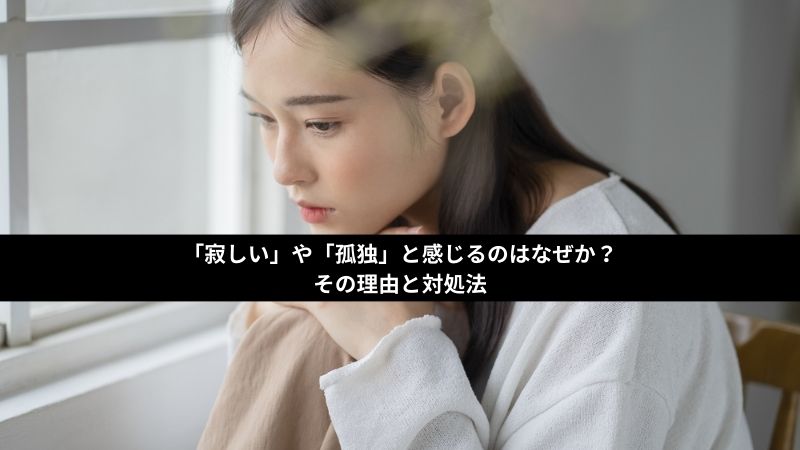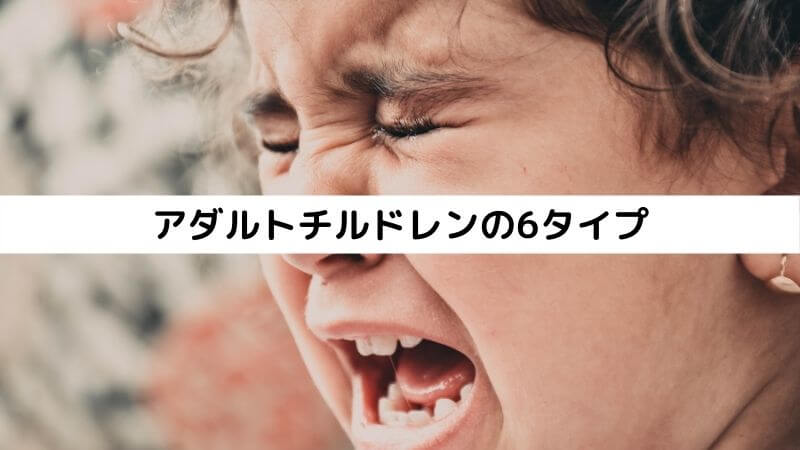寂しがり屋の心理や特徴、その克服方法とは?【愛着障害かも】

「寂しい」とは、対人関係の中で誰もが経験しうる感情の1つですが、過度な寂しさは自分自身や他者を不安にさせてしまいます。過度な寂しさは親しい友人関係や恋愛関係で生じやすく、人間関係を依存的にして自立を阻害する場合もあるでしょう。
今回は、寂しがり屋の特徴や心理、寂しがり屋と関連のある愛着障害(アタッチメント障害)とその克服について解説します。自分の過度な寂しがりを克服して自立したい人や、恋人の過度な寂しがりからくる試し行動に困っている人は、本記事を参考にご覧ください。
目次
寂しがり屋の特徴
寂しさは、彼氏・彼女と別れたときや楽しい時間が終わったときなど、ふとした瞬間に感じる気持ちであり、誰もが経験する感情です。
寂しさは誰にでも見られる性質ですが、その程度が過度になると生活や人間関係に大きな影響を及ぼすことがあります。過度な寂しさは、一人でいることに強い不安を覚え、常に誰かと一緒にいなければ安心できません。その背景には、幼少期に安定した愛着関係を得られなかった体験や、人とのつながりに対する過剰な不安が関係している場合が多くあります。
このため、相手に依存的になったり、無理に関係をつなぎとめようとしたりすることで、かえって人間関係が不安定になることも少なくありません。さらに、自尊感情が低下し「一人では価値がない」と感じやすいため、承認欲求を満たすために過剰な行動に出てしまうこともあります。こうした特徴から、過度な寂しがり屋は愛着障害や依存傾向とも関連しやすいと考えられています。
よくある相談の例(モデルケース)
20歳代 女性
Aさんは幼少期から強い寂しさを抱えて生きてきました。両親は共働きで家にいる時間が少なく、特に母親は感情的に不安定で、Aさんが甘えたり不安を訴えたりしても冷たく突き放すことが多かったといいます。父親も家庭より仕事を優先し、家族と深く関わることは少なかったため、Aさんは安心して寄りかかれる存在を持たないまま成長しました。友人関係も不安定で、「自分は大切にされない」という感覚を常に抱き、強い孤独感と承認欲求を抱えていました。
思春期以降、Aさんはその寂しさを埋めるように不特定多数の男性と関係を持つようになりました。最初は「好きだと言ってもらえれば安心できる」という気持ちでしたが、行為の後には虚しさや自己嫌悪が募り、さらに次の相手を求めるという悪循環に陥っていきました。やがて自分でも「これは依存に近い」と感じるようになり、体調を崩すことも増えてきたため、心療内科を受診しました。そこでは軽い抑うつ状態と診断され、抗不安薬と抗うつ薬を処方されましたが、根本的な不安や寂しさは消えず、衝動的な行動も変わりませんでした。
その後、インターネットで依存や愛着に関する情報を調べる中で、心理的な支援の必要性を感じ、当オフィスにカウンセリングを申し込みました。カウンセリングでは、まず彼女が抱える「寂しさに耐えられない気持ち」や「見捨てられる不安」を丁寧に言葉にすることから始まりました。当初は過去の出来事を語るだけで涙が止まらなくなり、信頼関係を築くにも時間を要しましたが、数ヶ月を経て少しずつ安心して気持ちを表現できるようになっていきました。
継続的なカウンセリングの中では、幼少期からの体験を振り返りながら、自分が求めてきた愛情や承認の形を理解する作業が進められました。同時に、衝動的な行動に走りそうになったときに自分を支える方法を一緒に模索し、日常生活において安心感を持てる人間関係や趣味を育てていく練習も行われました。数年にわたるプロセスを通じて、Aさんは「寂しいからといって誰かと関係を持たなくても、自分を大切にできる」という感覚を少しずつ身につけることができました。現在では恋愛関係も落ち着き、自分を粗末に扱わない相手を選べるようになり、以前よりも安定した生活を送れるようになっています。
寂しがり屋の心理
寂しさは恋人等の親しい相手に強く感じ、愛情の確認や自分の気持ちを満たすために試し行動として彼氏・彼女を巻き込んでしまう場合があります。
寂しがり屋には、以下のような心理が考えられます。
(1)自己肯定感が低い
寂しがり屋の人は自己肯定感が低い場合が多く、自分に自信をもてない傾向があります。
自己肯定感が低いと、恋愛関係では「こんな自分は愛されないかもしれない」、「自分には魅力がないかもしれない」等と自己否定をし、恋人の思いを素直に受け取れず心に穴が開いたような虚しさを抱きやすいです。
自己肯定感の詳細については以下のページが参考になります。
Aさんは幼少期から十分に受け入れられた経験が乏しく、自分には価値がないという感覚を抱きやすくなっていました。そのため、他者から承認を得ようと不安定な行動に走ることが多くありました。
(2)見捨てられ不安がある
恋人関係で特に寂しがり屋な人は、「恋人に見捨てられるのではないか?」と見捨てられ不安を常に感じている可能性があります。恋人の何気ない言葉や返事の遅れに対してネガティブに考え込んでしまい、恋人に依存した関わりや自分を傷つけることで関心を引く等の試し行動が生じやすいです。
また、寂しがり屋の背景には孤独の感じやすさがあり、常に恋人と一緒にいたり連絡を求めたがったりして、彼氏・彼女を困らせてしまう場合もあります。
見捨てられ不安についての詳細は以下のページをご覧ください。
Aさんの場合、相手が少しでも距離を取ろうとすると「嫌われたのではないか」「もう必要とされないのではないか」と強く不安を感じ、必死に相手をつなぎとめようとする傾向がありました。
(3)他者評価を気にしやすい
寂しがり屋の中には、周りから自分がどう見られているのかを気にして、他人から良い評価を得るために自分の気持ちを抑制する人もいます。
人の顔色を窺いすぎてしまうため、恋人から良く思われたいあまりに本音を話せず、「付き合っているのに心がつながれない」という寂しさを抱えやすいです。
Aさんは常に周囲の反応を過敏に気にしており、相手にどう思われているかを意識しすぎて、自分の本心よりも相手の期待に合わせることを優先してしまうことが多くありました。
寂しがり屋と愛着障害
恋愛等の親密な人間関係において過度に寂しがり屋な人の背景には、愛着障害が潜んでいる可能性があります。愛着障害の人は、幼少期より親等の養育者との関係の悪さから大切にされた感覚が乏しく、大人になっても人との適切な距離感が分からず対人関係に悩むことが少なくありません。
恋人やパートナーとどう接すればいいか、どのように愛せばいいかが分からず、しばしば高圧的な態度で接したり、へらへらと恋人の言いなりになったりしてしまう特徴があります。
子どもの頃に他者を信頼できず、愛着形成が不十分な人は、過度な寂しさに対処するために試し行動をせざるを得ないのかもしれません。
愛着障害についての詳細は以下のページをご覧ください。
Aさんは幼少期の愛着関係の不足から強い寂しさを抱え、不安定な対人関係に依存していました。カウンセリングを通じて寂しさを受け止め、自分を落ち着ける方法を学ぶことで、安定した人間関係を築けるようになっていきました。
愛着障害の寂しがりの克服方法
まず、寂しがり屋の克服とは、「寂しくならないこと」ではありません。寂しいという感情は1人になったとき、心細くなったとき等の自然な感情です。
過剰なまでの寂しがりから恋人に試し行動をとって困らせたり、ネガティブな行動や認知に偏ったりして日常的に困る場合は寂しさと向き合ってみましょう。愛着障害の寂しがりの克服には、安心・安全な感覚を得ることが手掛かりになります。
(1)今の自分を認める
愛着障害の人は自尊心や自己評価が低く、「こんな自分は愛されない」と自己否定をしやすいですが、まずは今のありのままの自分を認めてみましょう。
周囲の人は、否定をせずに本人の気持ちを聴く姿勢が大切になります。否定ではなく寂しくなる自分を認めることで、寂しすぎる感情の支配から抜け出しやすくなります。
Aさんはカウンセリングを通じて、自分の寂しさや弱さを否定せず「これが今の自分だ」と受け入れることが少しずつできるようになりました。
(2)認知を変える
寂しがり屋な人は、1人でいることや周りに合わせないことをネガティブに捉えすぎる傾向がありますが、それらは決して悪いことではありません。趣味等で1人の時間を楽しんだり、周りの意見も聞きつつ自分の気持ちも言って良いのだと思ったりして認知を変えてみましょう。
恋人がネガティブな考えで偏っている場合は、新しい考え方を共有してネガティブ思考を緩める促しも大切です。寂しいことについての認知を変えることで、試し行動を減らし、安心感を得ていくことも可能です。
そして、これを専門的に行うことを認知行動療法を言います。認知行動療法はセルフでできる面もありますが、やはり臨床心理士などの専門家と一緒に取り組むことが望ましいです。認知行動療法の詳細については以下のページをご覧ください。
Aさんの場合、「相手に愛されなければ自分には価値がない」という極端な考えを修正し、自分の存在そのものに意味があるという認知を育てていきました。
(3)線引きをする
愛着障害の寂しがり屋な人の場合、自己否定をしたり、他人と比較して自分や他人の悪いところにばかり目がいきやすくなります。悪い部分への注目は自分の心を不安定にするため、良い面も見出すことで人の良い面と悪い面に柔軟に折り合いをつけてみましょう。
また、親等の過去の愛着関係を現在の恋人との間で繰り返してしまうことも多いため、過去と現在の相手や関係性は別物であると線引きすることも重要です。過去の愛着関係について恋人同士で話し合う場合は、過去の関係に拘り過ぎず、客観視する意識を持ちましょう。
現在の自分の良い面を認め、目の前の恋人との関係に向き合うことで、人間関係の中で新たに安心・安全である感覚を形成しやすくなります。
Aさんは人間関係において境界が曖昧になりがちでしたが、徐々に「相手の問題と自分の問題を分けて考える」ことを学び、依存的になりすぎない関係を築けるようになっていきました。
(4)落ち着ける時間をつくる
愛着障害の寂しがり屋な人は、恋人の愛情を確かめるために様々な試し行動を起こしてしまいます。しかし、試し行動で満たされるのは一瞬であるため、すぐに寂しさに襲われてしまいます。
どうしても寂しさから自分や恋人が困ってしまう場合は、自分が落ち着ける場所や趣味等を探してみましょう。寂しさは人以外でも満たすことができます。自然の多い場所や好きなカフェ、癒されるペット、気分が良くなれる音楽等、自分が安心を感じられることと向き合い気持ちを安定させることも効果的です。
Aさんの場合、寂しさに駆られて行動する前に、自分を落ち着ける時間を意識的に持つ工夫を取り入れました。その結果、衝動的な行動が減り、安定感を得られるようになりました。
(5)カウンセリングを受ける
寂しがり屋の人に対するカウンセリングでは、まずその「寂しさ」がどのような背景から生じているのかを丁寧に理解することが重要になります。幼少期に十分な愛情や安心感を得られなかった体験や、対人関係で繰り返された拒絶や孤立の経験が、強い寂しさの根底にある場合が少なくありません。そのため、単に「寂しがりを克服する」といった表面的な目標を立てるのではなく、寂しさという感情をその人の歴史の中で位置づけ直すことが、支援の第一歩となります。
カウンセリングの場では、安心して自分を表現できる関係を築くこと自体が、寂しさの癒しにつながります。セラピストとの安定した関わりを通じて、「自分は受け止められる存在だ」という体験を積み重ねていくことで、自己肯定感が回復していきます。また、衝動的に他者へしがみついてしまう行動パターンについても、なぜそうせざるを得なかったのかを一緒に振り返り、自分を守るための別の方法を考えていく作業が行われます。
さらに、認知行動的なアプローチを用いて「見捨てられたら終わり」という極端な考えを修正し、より柔軟な思考を育むことも有効です。同時に、日常生活で安心できる時間や空間をつくり、自分一人でも心を落ち着けられる工夫を身につけることも支援の一環です。これにより、他者に依存しなくても寂しさに耐えられる力が育ち、対人関係におけるバランスが整っていきます。
このように寂しがり屋に対するカウンセリングは、寂しさを排除するのではなく、その感情を受け入れながら適切に扱う方法を学ぶプロセスです。時間をかけて取り組むことで、自分自身とのつながりを深め、人との関係もより安定したものへと変化していくことが期待されます。
Aさんは薬だけでは寂しさが改善せず、当オフィスでカウンセリングを受けました。安心できる場で寂しさや不安を語るうちに自己理解が深まり、衝動的な行動を抑え、より安定した人間関係を築けるようになっていきました。
愛着障害のトピックについて
愛着障害についてのいくつかのトピックです。さらに詳細に知りたい方は以下をご覧ください。
寂しがり屋についてのよくある質問
寂しがり屋とは、他者とのつながりを非常に強く求め、孤独を極端に恐れる傾向にある人を指します。このような人々は常に他人との接触を求め、周囲に自分の存在を認めてもらいたいという欲求が強いです。孤独感を感じやすく、他人からの拒絶や無視に非常に敏感であるため、過度に依存的になることもあります。寂しがり屋の人々は、他者からの愛情や関心を常に求め、しばしば自分の感情を他人に依存する形で解決しようとします。これは、過去の人間関係や家庭環境、育成環境が大きな影響を与えている可能性もあります。
寂しがり屋の心理的特徴には、他人からの承認を強く求める傾向が見られます。自己評価が低く、孤独を感じると極度に不安を抱くことが多いです。このような人々は、他者からの愛情や支援を得ることで自分の価値を確認したり、安心感を得たりします。そのため、寂しさを感じるとすぐに人と接したり、関わりを持つことが必要だと感じるのです。感情面では、他人に対して過度に依存してしまうことが多く、その結果として人間関係が一方的になりがちです。また、他人の反応に敏感で、他人の無関心や冷淡な態度に非常に傷つきやすい傾向があります。
寂しがり屋の原因は複数の要因に起因することが多いです。例えば、幼少期に十分な愛情や関心を受けられなかった場合、自己肯定感が低くなることがあります。家庭環境が不安定であったり、親の関心を引くために過剰に自分をアピールする必要があった場合、寂しがり屋の傾向が強くなることがあります。また、過去の人間関係で深く傷ついた経験があると、他人との接触を求める気持ちが強くなり、孤独を感じることを恐れるようになります。こうした経験が、他者とのつながりに過度に依存する心理的傾向を生むことがあります。
寂しがり屋を克服するためには、まず自己肯定感を高めることが重要です。自己肯定感が高まることで、他者に依存する必要がなくなり、独立した自己を確立することができます。そのためには、自分自身を大切にし、自分の感情やニーズを認識することが重要です。また、孤独感を感じたときに過度に他者に依存するのではなく、孤独と向き合うことを学ぶことも大切です。カウンセリングや心理療法を受けることで、自分の心の中にある不安や恐れを理解し、適切な方法で対処することができるようになります。また、趣味や興味を持つこと、自己表現の場を持つことも効果的です。
寂しがり屋の人が注意すべき点は、他者に過度に依存しないよう心掛けることです。過度に依存すると、相手に対して無理な期待をかけることになり、人間関係が不安定になりやすいです。また、孤独感を感じたときにすぐに他者に頼るのではなく、自分自身でその感情に向き合うことが重要です。自分を大切にし、自己肯定感を持つことによって、他者とのバランスの取れた関係を築くことができます。感情を適切に表現し、他者に自分のニーズを過度に押し付けないようにすることが、人間関係を良好に保つためには必要です。
寂しがり屋の人が人間関係で困ることとしては、他者からの反応に過敏になりすぎることがあります。自分が求めている反応が得られないと、極端に不安を感じたり、傷ついたりします。また、他者に依存しすぎてしまうことで、関係が一方的になりやすく、相手に負担をかけることもあります。依存的な態度を取ることが、時には相手との関係にひびを入れ、疎遠になってしまう原因にもなり得ます。さらに、自己評価が低いため、相手からの無視や冷たい態度に対して過剰に反応してしまい、人間関係に問題が生じることがあるのです。
自分を改善する方法として、まずは自己認識を深めることが大切です。自分の感情やニーズを素直に認め、過度に他者に依存しないよう意識することが第一歩です。また、他者と深い関係を築くためには、自分の感情や考えを適切に表現し、相手の立場を尊重することが重要です。信頼できるカウンセラーや心理療法士に相談し、心の中にある不安や恐れを解消する手段を学ぶことも効果的です。自立的な心を育てることによって、他者との関係においてもより健康的な距離を保つことができます。
他者との関係を築く際には、まず相手を尊重することが最も大切です。自己開示を適切に行い、過剰に依存することなく、自分の感情や思いを自然に伝えることが求められます。また、相手のニーズや感情を理解し、共感する姿勢を持つことも人間関係を円滑にします。相手に過度な期待をしないことが、良好な関係を築くためには欠かせません。信頼関係を築くためには、時間がかかることを理解し、一歩一歩着実に関係を深めることが重要です。
自分を大切にするためには、まず自分の感情やニーズを認識し、他者に過度に依存しないよう意識することが重要です。自分自身を愛し、他人の期待に応えようとするあまり、自分の心を犠牲にしないことが大切です。また、趣味や興味を持ち、自分を楽しませる時間を積極的に作ることも効果的です。日々、自分が心地よいと感じる活動を行い、自己満足を追求することが、自分を大切にする方法の一つです。自分のペースで生活し、自己肯定感を高めることが、心の健康を保つために役立ちます。
心の健康を保つためには、まず自己認識を深めることが重要です。孤独感や不安を感じたときに、過度に他者に頼らず、自分自身と向き合う時間を持つことが有効です。また、ストレス管理を行い、リラクゼーション法を取り入れることで心身のバランスを整えることができます。信頼できる友人や家族と定期的に交流することも心の支えになります。孤独感を感じたときには、専門家の助けを求めることを恐れず、心のケアをしっかりと行いましょう。
寂しがり屋を克服するカウンセリングを受ける
過度な寂しがり屋は愛着障害の傾向や可能性があることを解説しました。また、その克服方法としていくつか提示しました。自分自身の努力で克服できればそれに越したことはありません。しかし、人によっては専門家の力や助言を借りるため、カウンセリングを受ける方が良い場合もあります。
(株)心理オフィスKでは寂しがり屋や愛着障害のカウンセリングを行っています。自分自身の寂しがり屋や愛着障害について相談したり、カウンセリングをうけたりすることを希望される方は以下のボタンからお申し込みください。