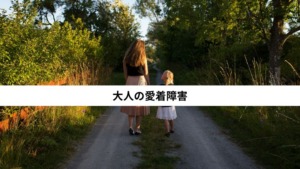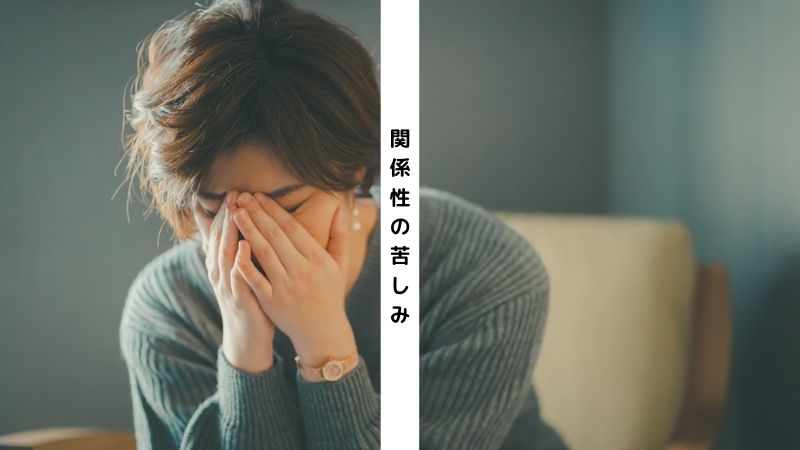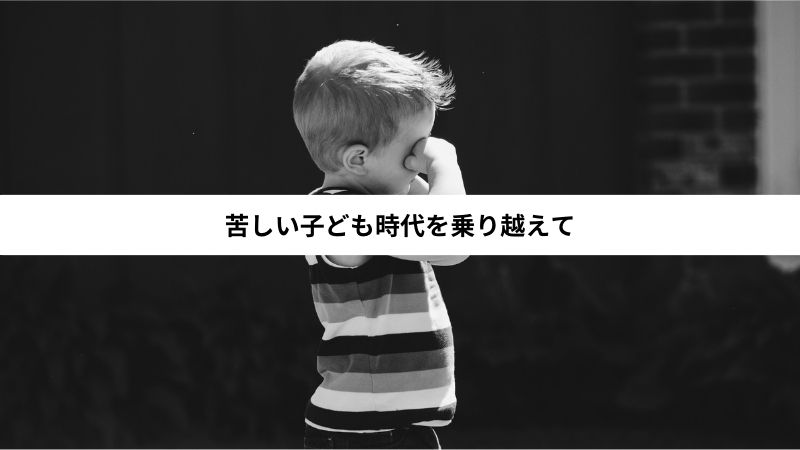脱抑制性対人交流障害とは

愛着障害(アタッチメント障害)の一つである脱抑制性対人交流障害の特徴、原因、治療などについて解説します。
目次
脱抑制性対人交流障害とは

脱抑制性対人交流障害(Disinhibited Social Engagement Disorder: DSED)は反応性愛着障害と全く反対に、過剰に人に接触し、べたべたし、馴れ馴れしく接します。それも全く見知らぬ人や普段は会わない人に対してもこのような行動をとります。
無差別に愛着行動(アタッチメント)を示し、他者の注意を引くために、大袈裟な行動や振る舞いをします。しかし、一方で他者と協調的に、協同的に行動することができず、コミュニケーションや対人交流はむしろチグハグです。そして、時には暴力的で、衝動的な行動を突発的にしてしまうこともあります。
よくある相談の例(モデルケース)
男性 小学5年生
Aさんは小学5年生の男の子です。母親の相談によれば、幼少期から人懐っこく、誰にでも気軽に声をかけたり、初対面の大人にもすぐに甘えたりする傾向がありました。家族構成は両親と妹の4人ですが、Aさんが2歳の頃、両親は仕事の都合で長期間別居し、Aさんは祖父母の家で預けられることが多くなりました。祖父母は優しいものの高齢で、日々の関わりはやや希薄だったといいます。その後、両親が戻り、家族4人での生活に戻りましたが、Aさんは小学校に入ると、友達や先生だけでなく、公園で出会う見知らぬ大人にも積極的に話しかけ、物をもらったり、一緒に遊びに行こうとしたりすることが増えていきました。母親は、危険性や他者との適切な距離感について何度も注意しましたが、Aさん自身は「相手が誰でも大丈夫」と考えている様子でした。
学校でも、人との距離が極端に近く、先生の膝に座ったり、友達の親にもすぐに抱きついたりするため、周囲からは「人懐っこい子」「無邪気」と受け取られる反面、他の保護者や先生から「少し心配だ」「不安になる」と指摘されることが増えました。家庭では家族のルールを守ることもでき、落ち着きもありましたが、外では誰とでも親密になろうとするため、母親は次第に不安を感じるようになり、小児科やスクールカウンセラーに相談しました。医師による診察や、カウンセラーによる発達検査・心理検査の結果、知的な遅れや発達障害の特徴は見られませんでしたが、「脱抑制性対人交流障害」の可能性が指摘されました。
その後、専門機関でカウンセリングを受けることになりました。カウンセリングでは、Aさんの日常生活の様子を丁寧に聴取し、家族や学校とも連携をとりながら、Aさんが安心できる人間関係を築く力を育てること、他者との適切な距離感や自分を守る意識を高めることを目標に支援が行われました。また、母親自身もAさんへの接し方や声かけの方法を学び、家庭で実践しました。時間をかけて少しずつ、Aさんも「知らない人とは距離をとる」「困った時は大人に相談する」などのスキルを身につけ、母親の不安も和らいでいきました。今では、以前ほど無防備に他人に接することが減り、徐々に年齢相応の社会性が育ちつつあります。
脱抑制性対人交流障害と間違われやすい障害
こうした症状や特徴は注意欠陥多動性障害と似ています。一見すると落ち着きがなく、慌ただしく、ちょっとしたことで癇癪を起し、パニックになります。
しかし、よくみると、そのほとんどの症状は対人関係上のことをきっかけに起こっているのが脱抑制性対人交流障害です。注意欠陥多動性障害では対人関係のこと以外でもこうしたことが起こるので、そこが鑑別のポイントとなるでしょう。
注意欠陥多動性障害については以下のページに詳しく書いていますので、ご覧ください。
Aさんの場合、発達障害(ASDやADHD)や愛着障害などと間違われやすい特徴が見られました。特に、「誰とでもすぐ親しくなる」「人との距離感が近すぎる」といった行動が、発達障害による社会性の困難や、他の愛着関連の障害と混同されやすかったです。
脱抑制性対人交流障害の原因
反応性愛着障害と同じく、養育者との関係や養育環境が主な原因となります。
- 養育者からのさまざまな虐待
- 厳しい躾けや養育
- 過度に刺激が多い家庭環境
- 干渉的な育児
- 養育者が非常に感情的
上記のようなことが脱抑制性対人交流障害の原因となります。反応性愛着障害の原因と比較すると、刺激が強く、過度に干渉的であることが特徴です。
Aさんは幼少期に両親と離れて祖父母の家で過ごす期間が長く、安定した養育者との関わりが希薄だったことが背景にありました。このような初期の養育環境の不安定さが、脱抑制性対人交流障害の発症につながったと考えられます。
脱抑制性対人交流障害の相談と治療
(1)子どもに対して
脱抑制性対人交流障害の子どもは過度に引っ付いてきたり、感情的になって、時には物を壊したりします。そうしたとき、まずこちらが感情的にならず、冷静に対応することが必要になります。また、試し行動にようにイタズラや悪さをすることもあるかもしれません。その時にも不要に責めたり、叱責するのではなく、子どもをなだめて、諭すようにすると良いでしょう。
そのように、子どもは怒られない、責められないということが徐々に理解していくとかなりの程度、落ち着いていきます。それが子どもにとっては、この人は大丈夫だ、という安心感を持つようになります。いわゆる安全基地として機能しはじめます。
Aさんの場合、専門のカウンセリングを受ける中で、他者との適切な距離感を学ぶトレーニングが行われました。また、日常生活の中で「知らない人とは距離をとる」「困った時は信頼できる大人に相談する」など、具体的な行動スキルを身につける支援がなされました。
(2)親に対して
脱抑制性対人交流障害の子どもの親はどちらかというと感情的で、養育も干渉的だったりします。時には暴力を用いて子どもに接することもあります。そうした状況を見ると、どうしても親を責めてしまいたくなってしまいます。しかし、責めても事態は変わりませんし、むしろ孤立させ、悪化させてしまうだけでしょう。
ですので、親の振る舞いを責めるのではなく、親自身が苦しんでいることや困っていること、悩んでいることに焦点を当てると良いでしょう。もしかしたら、親自身も何とかしたいと思っているけど、それが思うようにいかず、イライラしてしまい、つい手が出てしまっているだけかもしれません。
子どもがどういう状態なのか、なぜ子どもがそうした行動を取るのか、などについて説明し、別のもっと効果的な関わり方を教え、それを実践してもらうように援助すると良いでしょう。
こうした関りが親との信頼関係を育て、ひいては親が子どもとの関係の再構築をしていけるようになるでしょう。
Aさんの母親は、子どもへの関わり方や声かけの工夫、家庭での安心感を高める方法について、カウンセラーからアドバイスを受けました。親自身も不安や戸惑いを相談しながら、Aさんが安全に成長できるよう家庭内での支援を続けていきました。
愛着障害についてのトピック
愛着障害についてのいくつかのトピックです。さらに詳細に知りたい方は以下をご覧ください。
脱抑制性対人交流障害についてのよくある質問
脱抑制性対人交流障害は、子どもが見知らぬ人に対して過度に親しげな行動を示す状態を指します。具体的には、初対面の人に対しても警戒心を持たず、過度に接近したり、知らない大人に平気でついて行ったりする行動が見られます。この障害は、幼少期の愛着形成に問題があった場合に発生しやすく、特に養育環境が不安定であったり、ネグレクトや虐待を受けた経験がある子どもに多く見られます。適切な治療や介入が行われないと、将来的に社会的な問題や対人関係の困難を引き起こす可能性があります。
脱抑制性対人交流障害の主な原因は、幼少期の不適切な養育環境や愛着形成の問題にあります。具体的には、以下のような状況が原因となることがあります:
- 養育者の不在や頻繁な交代:主要な養育者が不在であったり、頻繁に交代することで、子どもが安定した愛着を形成できない場合。
- ネグレクトや虐待:身体的・精神的な虐待や、基本的な世話が十分に行われないネグレクトの経験。
- 施設での養育:孤児院や児童養護施設などでの集団養育により、個別の愛着形成が難しい場合。
これらの環境要因により、子どもは特定の養育者との安定した関係を築くことができず、結果として見知らぬ人に対しても過度に親しげな行動を取るようになると考えられています。
脱抑制性対人交流障害の主な症状は、見知らぬ人に対して過度に親しげな行動を示すことです。具体的には、以下のような行動が見られます:
- 見知らぬ大人に対する過度の親しみ:初対面の大人に対しても警戒心を持たず、すぐに近づいて話しかけたり、身体的な接触を求めたりする。
- 養育者からの離脱への抵抗の欠如:主要な養育者から離れることに対して不安や抵抗を示さず、他の大人と容易に行動を共にしようとする。
- 社会的境界の欠如:社会的な適切さを欠いた行動を取り、他者との距離感を適切に保てない。
これらの行動は、子どもの安全を脅かす可能性があり、早期の対応が求められます。
脱抑制性対人交流障害の診断は、専門家による詳細な評価が必要です。一般的な診断基準として、以下の点が考慮されます:
- 見知らぬ人に対する過度の親しみ:初対面の大人に対しても警戒心を持たず、過度に親しげな行動を示す。
- 養育者からの離脱への抵抗の欠如:主要な養育者から離れることに対して不安や抵抗を示さない。
- 社会的境界の欠如:社会的な適切さを欠いた行動を取り、他者との距離感を適切に保てない。
- 不適切な養育歴:幼少期にネグレクトや虐待、養育者の頻繁な交代などの不適切な養育環境が存在した。
これらの症状が持続的に見られ、他の発達障害や精神疾患によるものではないと判断された場合、脱抑制性対人交流障害と診断されることがあります。
脱抑制性対人交流障害の治療には、以下のようなアプローチが有効とされています:
- 安定した養育環境の提供:子どもが安心して過ごせる安定した家庭環境を整えることが重要です。継続的で一貫性のある養育者との関係が、子どもの愛着形成を助けます。
- 心理療法:専門のカウンセラーやセラピストによる個別の心理療法を通じて、子どもの感情や行動の理解と調整を図ります。プレイセラピーや家族療法が効果的とされています。
- 養育者へのサポートと教育:養育者が子どもの特性やニーズを理解し、適切な対応ができるよう支援します。これには、子どもの行動に対する一貫した対応や、適切な対応の仕方を学ぶプログラムが含まれます。
- 学校や地域との連携:学校や地域の支援機関と連携し、子どもの適応を助ける環境づくりを進めます。
治療は継続的なプロセスであり、専門家の助けを借りながら進めることが重要です。
脱抑制性対人交流障害は、子どもの対人関係や社会生活に多くの影響を及ぼします。具体的には、以下のような影響が考えられます:
- 他者との境界感覚の欠如:見知らぬ人にも過度に親しげに接するため、子どもの安全が脅かされるリスクが高まります。
- 愛着形成の困難:特定の養育者と深い信頼関係を築くのが難しく、将来的な人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
- 社会的スキルの欠如:適切な社会的行動を学ぶ機会が少なく、友人関係や集団生活で問題が生じることがあります。
- 感情のコントロールの困難:安定した愛着が形成されないことで、感情を適切にコントロールする能力が十分に発達しない場合があります。
早期の介入と支援が、これらの影響を最小限に抑えるために重要です。
脱抑制性対人交流障害を予防するには、子どもが健全な愛着を形成できる環境を提供することが重要です。以下のポイントが予防に役立ちます:
- 安定した養育環境の提供:子どもが安心して成長できる、一貫性のある環境を整える。
- 養育者の教育と支援:親や養育者が子どものニーズを理解し、適切な対応ができるように支援する。
- 早期介入:ネグレクトや虐待の兆候が見られる場合は、早期に専門家に相談し、適切な対応を行う。
- 地域や社会の支援:家庭だけでなく、地域や学校などの社会的支援を活用し、子どもの健全な成長を促進する。
これらの取り組みにより、子どもの愛着形成の問題を防ぎ、将来的なリスクを軽減することができます。
脱抑制性対人交流障害と他の愛着障害(例:反応性愛着障害)には、症状や行動に違いがあります。具体的には以下の点が挙げられます:
- 脱抑制性対人交流障害:見知らぬ人に対して過度に親しげな行動を示し、社会的な境界感覚が欠如しています。
- 反応性愛着障害:他者に対して過度に警戒心を抱き、親しさを避ける行動が特徴です。また、感情表現が乏しい場合があります。
どちらの障害も不適切な養育環境が原因とされますが、表れる行動の方向性が異なります。診断と治療には専門家の評価が必要です。
脱抑制性対人交流障害は、成長とともに改善する場合もありますが、早期の介入と適切な支援が重要です。安定した養育環境が提供されることで、子どもの愛着形成が進み、症状が軽減される可能性があります。しかし、適切な支援が行われない場合、症状が持続し、思春期や成人期においても対人関係の問題が続くことがあります。専門家の助けを借りながら、継続的な支援を行うことが求められます。
脱抑制性対人交流障害を持つ子どもをサポートするには、以下の取り組みが重要です:
- 一貫性のある対応:養育者が一貫した愛情とサポートを提供し、子どもが安心感を持てる環境を整える。
- 専門家との連携:心理療法やカウンセリングを通じて、子どもの行動や感情の理解を深める。
- ポジティブな行動の強化:子どもが適切な社会的行動を取った際には、積極的に褒める。
- 安全な環境の提供:見知らぬ人に対する過度の親しみを避けるため、適切な境界を設定する。
- 家族療法:家族の温かい支えと専門的な支援が、子どもの健全な成長に大きく寄与します。
これらの取り組みを通じて、子どもの適切な愛着形成を助け、症状の改善を促すことができます。
脱抑制性対人交流障害について相談する
脱抑制性対人交流障害についての解説をしました。こうした問題があると、人間関係が非常に難しくなったり、生活を送ることが困難になってしまったりします。また、時には犯罪に巻き込まれてしまったりすることもあります。
愛着障害について相談したり、カウンセリングを受けたりすることで、生活や人間関係が少し楽になります。カウンセリングや相談をご希望の方は以下からお申し込みください。