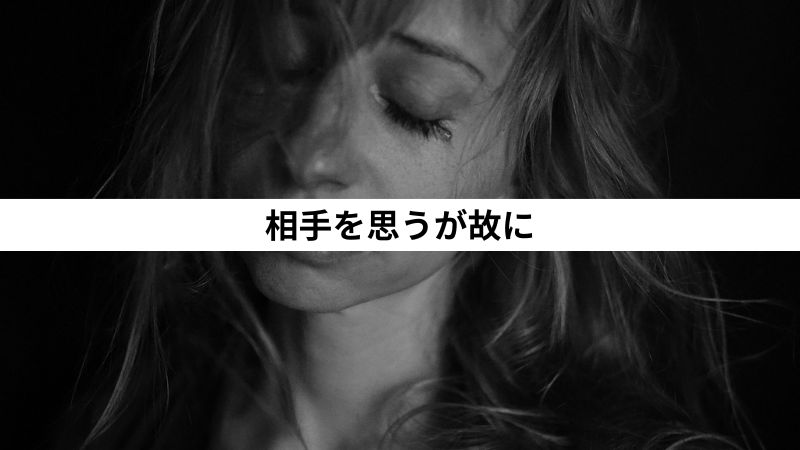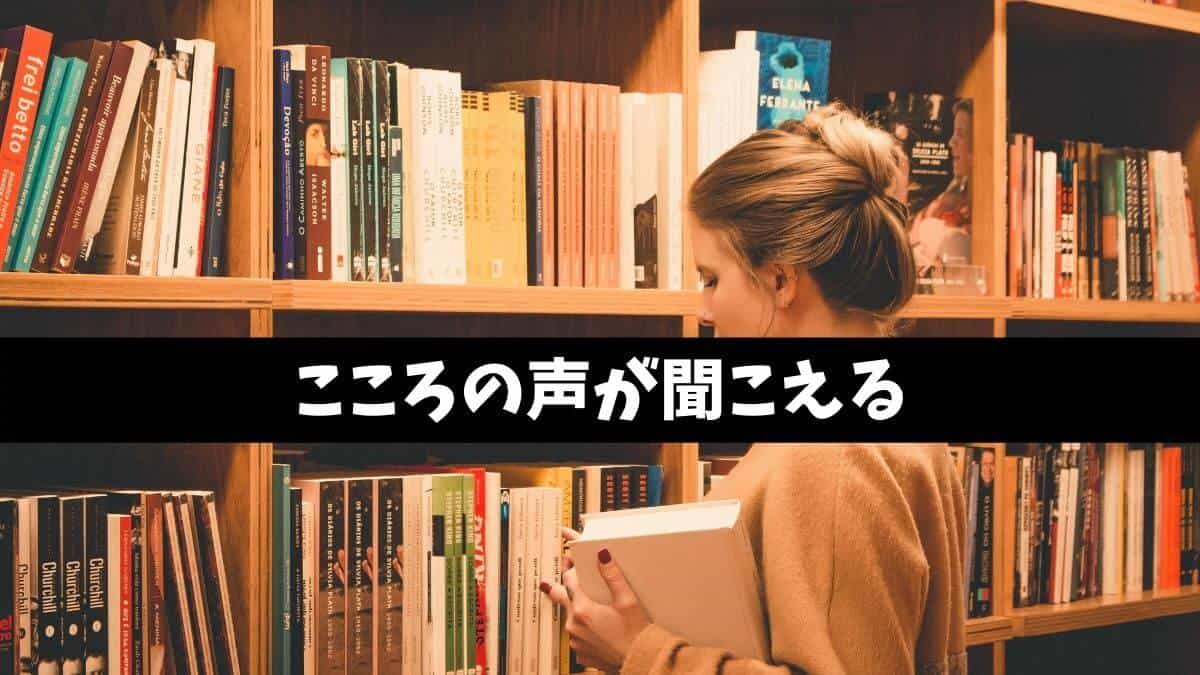「カール・ロジャーズ」と言う人の名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。それは、心理療法家で有名な偉人の名前をたずねると必ずといっても良いくらいカール・ロジャーズの名前が出てきます。
現在もなお、語り継がれているカール・ロジャーズのカウンセリングである来談者中心療法についてご紹介いたします。
目次
来談者中心療法とは

ロジャーズは「援助する人が誠実な態度で傾聴し、クライエントと対話ができる関係性のなかでは、どのようなクライエントも成長していく可能性がある」と定義しています。また、来談者中心療法のなかでクライエントが話す体験のなかにこそ多くのことが隠されており、そのことを知っているのはクライエントのみであると考え、援助者の態度が重要視されています。日本では、1940年代後半に知られるようになってからカウンセリングの主流となりました。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 女性
Aさん(30代・女性)は、職場での人間関係のストレスから不眠や食欲不振が続き、心療内科を受診したことをきっかけにカウンセリングを紹介された。薬の服用で一時的に体調は落ち着いたが、「自分がどうしたいのか分からない」「人に合わせてばかりで疲れる」という感覚が強く、心理的な支援を求めて来談した。幼少期から「良い子」として振る舞うことを期待され、感情を抑えて過ごしてきたことが、現在の生きづらさの背景にあった。
カウンセリングでは、来談者中心療法の立場から、Aさんの話を評価や助言を交えずに丁寧に聴き、共感的理解を重ねた。セラピストは、Aさんが抱える葛藤や迷いをすぐに解決しようとせず、そのまま受け止める姿勢を大切にした。Aさんは当初、「こんなことを話しても意味がないのでは」と戸惑っていたが、次第に「誰にも否定されずに話せる」安心感を得ていった。面接を重ねる中で、Aさんは職場での不安や怒り、家族への複雑な思いなど、これまで抑えてきた感情を少しずつ表現できるようになった。
セラピストは、Aさんの言葉を繰り返したり、気持ちを言語化して返すことで、Aさん自身が自分の感情を理解し、受け止めていく過程を支えた。たとえば、「我慢していると苦しくなる」というAさんの発言に対して、「我慢し続けてきた自分に気づき始めているのですね」といったフィードバックを行い、自己理解の深化を促した。その結果、Aさんは「怒ってもいい」「悲しんでもいい」という自己受容の感覚を得ていった。
半年ほど経つ頃には、Aさんは職場で過剰に周囲に合わせることが減り、自分の考えを伝えられるようになった。さらに時間を重ねる中で、Aさんは自分の気持ちや欲求を他者との関係の中で自然に表現できるようになり、以前よりも自信をもって行動できるようになった。来談者中心療法を通じて、Aさんは「正解を探す」生き方から、「自分で感じ、自分で選ぶ」生き方へと変化していった。
来談者中心療法の3つの条件

(1)自己一致・純粋性
カウンセラーがカウンセリングで出会う人々は、不一致の状態にあると考えられています。不一致とは、自分自身とその他の人々との間で起こる体験のズレであるため、心理的に混乱が起こりやすい状態になっているということです。また、人間が抱きやすい不安とはロジャーズによると理想の自己と現実の自己との間に生まれる不一致が意識的に象徴化されつつある状態のこととされています。
不一致の状態では、自己実現が難しく自分らしさを獲得しにくくなってしまいます。その不一致のなかで苦しむクライエントは、象徴化されたものを正確に自覚できることによって理想の自己と現実の体験が一致の状態になることが目標とされます。
カウンセリングのなかで、カウンセラーはクライエントに対して現実の自己を受け入れられるように接していく必要があります。そのためには、カウンセラー自身も自己一致をしていることが重要で、クライエントに対してカウンセラーの言葉や態度が一致していることを目指す必要があります。カウンセラーは、カウンセリング場面で自然と湧き上がるさまざまな感情に気づき、それらを否定せず十分に受け入れることが自己一致されている状態であり続ける必要があります。
Aさんは、これまで他者に合わせることで人間関係を保ってきましたが、カウンセリングを通して「本当はどう感じているのか」を少しずつ表現できるようになりました。セラピストが率直で飾らない態度を保ち、自分の感情を正直に共有する姿を示すことで、Aさんも安心して本音を語れるようになっていきました。
(2)共感的理解
クライエントが体験してきたことを感情移入的に理解する姿勢を大切にし、さらにこの感覚を正確に理解することが重要で、カウンセリング内でカウンセラーは自分があたかもその人であるような感覚を得るように努めることを努力する必要があるという考え方です。また、その際に浮かび上がった感情や体験の意味を共有することが大切ですが、同情や心配という感覚とは本質が違ってきます。
カウンセラーはクライエントと違う人間であるという前提を忘れず、カウンセラーの価値観を押し付けずにクライエントを理解する立場です。このように相手の立場から感じることが必要で、共感的に接してもらうことでクライエントの安心感につながりセラピーは進められていくことが重要です。
Aさんの場合、セラピストが評価や助言を避け、Aさんの気持ちをそのまま受け止めて理解しようとする姿勢が信頼の基盤となりました。Aさんは「どんな感情でも受け止めてもらえる」と感じ、自分の中の複雑な思いを整理する力が育っていきました。
(3)無条件の肯定的な関心
カウンセリング内で話されたクライエントの体験や体験に対する感情に対して、カウンセラー自身の価値観やそれによる評価することはせず、肯定的に受け入れて受容していく姿勢が重要です。
その姿勢を続けることによって、クライエントはカウンセリング内で安心して怒りや恐怖など、普段は見せることができない感情を吐き出すことがあります。このような、ネガティブな感情が表出されても巻き込まれることはなく。カウンセラーは治療上に必要な感情として受け入れる姿勢が必要になります。
Aさんは、失敗や弱さを見せることに強い恐れを持っていましたが、セラピストが批判や否定をせず、存在そのものを受け入れて関わり続けることで、自分を少しずつ肯定できるようになりました。その結果、「完璧でなくても価値がある」と感じられるようになりました。
来談者中心療法のやり方

(1)感情の受容
クライエントの話を聞いている際に、「なるほど」「そうですか」などの応答をおこなうことでクライエントへ安心感を与え、クライエントが語りやすい雰囲気をつくることができます。
Aさんは、これまで「怒ってはいけない」「弱音を吐いてはいけない」と自分を抑えてきました。カウンセリングで安心して話せる場ができると、悲しみや怒りを率直に受け止められるようになりました。
(2)感情の反映
クライエントが体験を語る上で表出された感情をカウンセラーが受け止め、言葉にして伝え返してあげることです。伝え返すことで、クライエントは自身の抱く感情を理解してくれたと感じ安心感を抱いて更に語ることができます。
セラピストがAさんの感情を丁寧に言葉にして返すことで、Aさんは自分の内面を理解しやすくなりました。「そう感じていたんだ」と気づく体験が自己理解の深化につながりました。
(3)繰り返し
クライエントが語った内容を、そのままの言葉で伝え返すことです。クライエントとカウンセラー間で理解のズレがないかを確認することができ、クライエントの語る内容を正確に理解することができていると示すことができます。
セラピストがAさんの言葉を繰り返し確認することで、Aさんは自分の気持ちが確かに聴き取られていると感じ、信頼感を強めていきました。
(4)フィードバック
語られた内容やクライエントの言動を、カウンセラーは客観的な視点からどう見えているかを伝えることです。クライエントは自分の言動について自覚しやすく必要な場合は修正することができます。フィードバックでは、カウンセラーの考えや推測を話すのではなく、目の前にある事実に向けて伝えていく必要があります。
Aさんが変化に気づけない時、セラピストが小さな成長や気づきを言語化して伝えることで、自己理解と自己効力感が高まりました。
(5)自己開示
カウンセラー自身の考えや感じたことを、クライエントへ伝えることです。カウンセリング内では信頼関係が重要で、クライエントもカウンセラーがどんな人間なのか知りたい気持ちが自然とわいてきます。そのため、カウンセラーの考えを伝えるとクライエントも安心して話しやすくなり、さらに自分自身の話をしやすくなります。
しかし、安易に自己開示をするのではなくクライエントから語られた内容についての考えを適切に、タイミングを考えておこなう必要があり、その効果についてもカウンセラーは知っておく必要があります。
セラピストがAさんに共感した時の感情を率直に伝えることで、Aさんは「人と気持ちを分かち合う」体験を学びました。
(6)感情の明瞭化
クライエントが語った漠然とした感情や遠回しの表現について、カウンセラーは感情について明確にして伝え返すことです。それをすることによって、クライエントの語りをさらに促進する効果、クライエント自身の内省を深められる効果、重要なことはクライエントが語っている内容についてカウンセラーの理解が正確にできているのかを確認するためです。
感情が混乱している場面では、セラピストが丁寧に整理を助けることで、Aさんは自分の本当の気持ちをより明確に把握できるようになりました。
来談者中心療法のメリットと欠点

(1)メリットや効果
来談者中心療法では、カウンセラーとクライエントが会話を通してカウンセリングを進めていきます。
カウンセラーが傾聴を続けていくと互いに信頼関係が徐々に構築されるようになり、会話を続けていくことで自分自身の感情について気づきやすくなります。安心できるカウンセラーとは、自分の感情に気づいたときに否定することなく受容することができるようになってきます。そのため、不一致状態から一致状態へと移行していきクライエントの主訴が解決していけます。
Aさんは、来談者中心療法によって自己受容が深まり、人との関わりでも自分の意見を率直に表現できるようになりました。心身の緊張が和らぎ、対人関係における安心感が増しました。
(2)デメリットや欠点
その反面、言葉で話さなければならないことが負担と感じる人には向いていないかもしれません。また、カウンセリングに対して抵抗が強いクライエントには、話すことを強制的に求められていると感じて苦痛を覚える可能性があります。
さらに、内省して話すことが元来難しい発達障害のクライエントや年齢の低いクライエントには難しいため来談者中心療法は向いていません。また、クライエントが求める答えを具体的に提示することができないこともデメリットの一つです。そのため、自分の考えについてアドバイスを求められることには不向きであるといえます。
一方で、Aさんは「具体的なアドバイスが少ない」と感じる場面もありました。すぐに問題解決を求める人には、変化が見えにくい時期がある点が課題といえます。
来談者中心療法についてのよくある質問
来談者中心療法は、アメリカの心理学者カール・ロジャーズによって提唱された心理療法で、クライエント中心療法とも呼ばれます。この療法は、カウンセラーがクライエントの話を無条件に受け入れ、共感的に理解する姿勢を取ることを特徴としています。来談者中心療法の根底には、人間は自己成長を遂げる能力を持っており、その成長を助けるためには安心して自己表現できる環境が必要だという考え方があります。カウンセラーは指示的なアプローチではなく、クライエント自身が自分のペースで問題解決に向かうようサポートします。これにより、クライエントは自己理解を深め、自分の感情や思考に対する洞察を得ることができ、心理的な回復が促進されます。
来談者中心療法の最大の特徴は、カウンセラーがクライエントに対して無条件の受け入れを示し、共感的理解を提供する点です。このアプローチでは、カウンセラーはクライエントの感情や体験に対して評価や判断を行わず、ただ傾聴することに徹します。クライエントが話す内容に対して反応を返すのではなく、クライエント自身が自分の思いや感情を言葉にすることで、心理的な問題を解決する力を引き出すことが狙いです。また、来談者中心療法では「自己一致」が重視され、カウンセラーが自分の本当の感情を隠さず、クライエントに対して誠実であることが求められます。このアプローチは、クライエントが自己の問題に対して主体的に向き合い、最適な解決策を見つけるためのサポートを提供します。
来談者中心療法は、自己理解を深めたい、感情をもっと表現できるようになりたい、または自分自身の問題に対するアプローチを見つけたいと考えている人に非常に適しています。特に、自己肯定感が低く、他人とのコミュニケーションに不安を感じている人や、過去のトラウマや人間関係の問題に悩んでいる人に有効です。この療法では、カウンセラーが無条件に受け入れてくれることから、クライエントが自分を表現しやすくなり、深層の感情や思考にアクセスできるようになります。また、指示を受けたくない、または自分のペースで進みたいという人にも向いています。自己成長や自己理解を深めたいと考える人々に特に効果的です。
来談者中心療法は、クライエントが自己理解を深め、感情や思考をより適切に認識できるように導きます。これにより、自己受容が進み、自己肯定感が高まることが期待されます。結果として、クライエントは自分自身の感情に対してオープンになり、他者との関係にも良い影響を与えることが多く見られます。特に、自己表現が苦手な人にとっては、感情を自由に表現する力を育むことができ、精神的な健康が向上します。また、この療法を通じて、クライエントは自分自身の目標に向かって積極的に行動する力を得ることができ、生活全体の質が向上することが期待されます。
来談者中心療法のセッションでは、まずカウンセラーがクライエントを無条件に受け入れ、リラックスした環境を提供します。クライエントは、自分の思いや感情を自由に表現することが奨励され、カウンセラーはその言葉に対して評価や判断を行わず、共感的に反応します。カウンセラーは、クライエントが自分の感情や考えを深めていく手助けをするために、時にはリフレクション(感情を反映する)や質問を行いますが、基本的にはクライエントが自己のペースで進むことを尊重します。この過程で、クライエントは自己理解を深め、問題に対する新たな視点を得ることができます。
来談者中心療法と他の心理療法との大きな違いは、そのアプローチにあります。例えば、認知行動療法(CBT)では、クライエントの思考や行動に焦点を当て、具体的な変化を促すことを重視しますが、来談者中心療法では、感情や自己表現の自由を促し、クライエントが自らのペースで自己成長を実現することに重点を置きます。また、精神分析療法は無意識に焦点を当て、過去の経験を掘り下げて行動の動機を探ることが特徴ですが、来談者中心療法では、今現在の感情や自己表現を重要視します。このように、来談者中心療法はクライエントが自己のペースで問題を解決できるようにサポートする点が他の療法と異なります。
来談者中心療法のセッションの頻度は、クライエントの状況やニーズによって異なりますが、通常は週に1回のペースで行われることが一般的です。ただし、クライエントがより集中したサポートを必要としている場合は、セッションの頻度が増えることもあります。セッションの頻度は、個別のニーズや治療目標に基づいて調整されるため、カウンセラーと相談しながら最適なペースを決定することが重要です。また、セッションの期間はクライエントの進捗や心理的なニーズに応じて、短期間で終わる場合もあれば、長期間続ける場合もあります。
来談者中心療法のセッションの期間は、クライエントの治療目標や心理的なニーズによって異なります。一般的に、初めは数回のセッションから始め、その後クライエントの進捗に応じて継続するかどうかを判断します。短期間で問題解決に至る場合もあれば、より深い自己探索が必要な場合には長期間続けることもあります。セッションの期間や回数は、クライエントとカウンセラーが共に話し合いながら決定することが重要です。重要なのは、クライエントが自己理解を深め、感情を表現できるようになり、成長を実感できることです。
来談者中心療法では、特に決まった話題や内容を話す必要はありません。クライエントは自分の感情や思考を自由に表現することが奨励されます。最も大切なのは、クライエントが自分自身に正直であり、感情や経験をありのままに話すことです。もし話すべきことが見つからない場合でも、その感情や考えを表現すること自体が重要です。カウンセラーは、クライエントが感じることや考えることを否定せず、どんなことでも受け入れる姿勢を持っています。
はい、来談者中心療法のセッション中に感情が高ぶることは完全に正常です。クライエントが自分の内面を深く探る過程で、感情が強く表れることはよくあります。感情が高ぶることは、自己理解の一環として自然な過程であり、その感情を表現することが心理的な解放や成長に繋がります。カウンセラーはそのプロセスを支え、クライエントが感情に圧倒されることなく、自分自身を受け入れられるようサポートします。
カウンセリングを受けたい

当オフィスではこのようなカウンセリングを行っておりますので、ご希望の方は以下の申し込みフォームからお申し込みください。
文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。