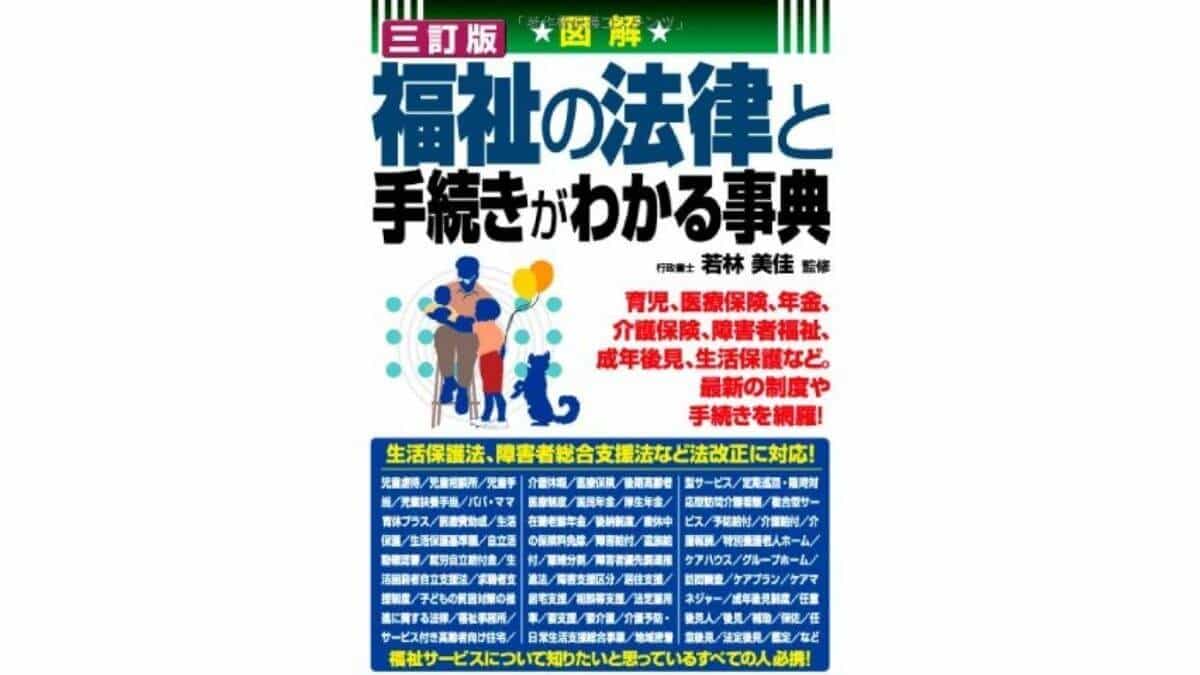乳児の対人世界

- D,N,スターン(著) 小此木啓吾、丸田俊彦(監訳) 神庭靖子、神庭重信(訳)「乳児の対人世界 理論編」 岩崎学術出版社 1989年
- D,N,スターン(著) 小此木啓吾、丸田俊彦(監訳) 神庭靖子、神庭重信(訳)「乳児の対人世界 臨床編」 岩崎学術出版社 1991年
上記の2冊を読んだ感想を書きました。
目次
精神分析における発達論の意義
精神分析療法、もしくは精神分析的心理療法をしていく上で、発達論的視点から患者を理解していくことはとても重要です。単純な言い方をすると、発達の後の方での失敗や固着は、病理が軽いと言えるし、発達早期の障害はより病理が重いと言えます。
そして、その発達論はフロイトの精神分析の頃より色々と論じられてきましたが、その論じられ方はクライエントの回想をもとに発達論ができあがってきたという経緯があります。それは、今ここで幼児期の頃をどのようなものとして体験し、経験してきたのかというクライエントの主観的理解が現在の病理を理解していくうえでとても重要であるからです。
このように主観的ゆえに臨床的に価値がありますが、やはり客観的立場にたつ発達論者からは恣意的であるというふうに批判をされていることも事実です。そのため、回想から形成された発達論と、直接観察から形成された発達論はお互いを受け入れることなく平行線をたどっていたようです。
被観察乳児と臨床乳児
しかし、精神分析の中にも乳児を直接観察して、そこから色々な知見を見出していく研究も徐々にされ始めていました。ボウルヴィ、スピッツなどがその先駆的な仕事をしてきたようです。
そういう歴史的背景の中から精神分析家のスターンは本書で総合的な発達論を論じています。
まずスターンは、乳児を「被観察乳児」と「臨床乳児」に分けました。被観察乳児は直接観察の中から乳児の発達や行動を理解していく際の対象です。臨床乳児は成人患者の回想から導き出される体験としての乳児です。スターンはそれら二つの乳児を両方ともつかい、統合していく作業を進めました。これらがスターンの発達論の出発点となっています。
自己感の観点からの発達論
そして、スターンはそれらのデータから発達論を形成していきましたが、その中心は自己感においています。自己感は自分自身を全体として機能させていくオーガナイザーとして表現されています。その自己感がどのような働きをし、どのように発達していくのかが着目点です。
(1)新生自己感
まず初めの自己感は、新生自己感と呼び、出生直後からだいたい2ヶ月間のことをさします。乳児は生まれた直後から環境からの様々な情報を取り入れ、かなり積極的に環境に作用していこうとしているようです。
(2)中核自己感
2つ目は、中核自己感と呼び、2ヶ月~6ヶ月ぐらいの時期を指します。この頃にはすでに自分と他の人との区別をつけれるようになっているようです。
(3)主観自己感
3つ目は、主観自己感と呼び、7ヶ月~9ヶ月ぐらいの時期です。前の段階で自分とは違う他の人を理解しており、さらにその上で、他の人の心についての理解まで進めていきます。この頃には他者との心の触れ合いも近くし、いわゆる情動調律も体験できるようになっています。
(4)言語自己感
4つ目は、言語自己感であり、24ヶ月ぐらいをメドに発現します。言語を獲得した乳児がそれを使って他の人とコミュニケートしていきます。言語がお互いを理解していくのに役に立つと同時に、言語であるからこそその限界として理解のズレが生じます。言語が他者との相互理解を促進する道具でもあり、逆に阻害する要因にもなり、二律背反的な世界に住むこととなります。
このようにスターンは発達の中心を自己感に置き、4つの段階を経るとしました。スターンの発達論の今までとは違うところは、これまでの発達論では、発達の段階が上がると、前の段階の発達は捨て去られるものとなっていました。しかし、スターンは、前の段階は捨て去られるものではなく、一度獲得したら半永久的に機能し続けるものだとしました。
能動的な乳児像
また、これまでの発達論では乳児は環境に対して受身的で、無力である、とされてきました。しかし、スターンが考えた乳児はそうではなく、かなり積極的で、環境に対して能動的で、進んで様々な情報を摂取し、思った以上に色々なことを理解し、体験しているようです。
精神分析における発達論は、発達がどのように進むのかだけで話は終わりません。各発達段階での失敗や固着などが現在の病理とどのように関連しているのか、というところに着眼点があります。スターンの4つの自己感の発達も同じように、各段階の自己感の病理がどのように現在の病理に関連してくるのかがとても重要になってくると思います。
発達と病理
「乳児の対人世界 臨床編」では、理論編を土台にして、実際の病理の表れや関係性の持ち方などを具体例を持ち出しながら論じられています。
それぞれの発達に固着(スターンはこの言葉をつかってなかったようですが)した場合に、どのような病理現象になるのかが分かりやすく書かれていました。精神分析の中での発達論はただの発達心理学に留まらず、精神病理との関連で論じられるところにその特徴があります。事例提供の際の分析的フォーミュレーションにおいても、発達的観点が必ずと言っていいほど論点となってきます。
これまでの発達論で有名なところというと、フロイトの口唇期・肛門期・男根期といったリビドー発達、エリクソンの信頼感などの8段階発達、ボウルビィのアタッチメント、マーラーの自閉期・共生期・分離個体化期、などが挙げられます。
最早期の発達について
スターンはその中でもかなり早期の発達に目を向けています。また、その理論確立には、想起だけではなく、観察や実験によるデータも採用し、非常に高い科学性も持っています。
私の臨床感覚においても、これらの早期発達と現在の病理との関連は非常に重要であるような手ごたえはあります。しかし、カウンセリングの中で具体的なストーリーとして語られるのは、2歳児以降のことが多いように思います。スターンでいうところの言語自己感が確立された段階以降であると思います。
人間の記憶は言語を媒介としてなりたっているというのはどこかで聞いたことがあるのですが、それが顕著にあらわれているのだと思います。そして、2歳以前のことについてはストーリーとして語られることはあまりありません(統合失調症や精神病レベルの重度になるとたまにあると言えばあるのかもしれませんが)。中核自己感・主観自己感の感覚というのはストーリーとして語られることは少なく、関係性のとり方や、対人認知のあり方や、情緒的体験のあり方といった、前言語的な部分で臨床場面では見られることが多いでしょう。
解釈することと体験すること
このあたりについてカウンセラーの逆転移や連想を通して、理解していくことが必要となってきます。そのためには教育分析や個人分析、スーパービジョンを受けることが必須です。そして、時には逆転移を利用しながら、解釈という形でクライエントに伝えていくこともあると思います。これらの体験を無意識に属するものとするのかしないのかは分かりませんが、体験の言語化という作業が非常に重要になってくると思います。
といっても、それらの体験をすべて言語化していくことが可能であるとは思えませんし、現実的ではないかもしれません。それらの過去を今ここでカウンセラーとの間で再体験し、焼き直していくことも必要であるかもしれません。
精神分析的心理療法やカウンセリングにおいて、個人の歴史を振り返り、今ここで体験しなおしながら、理解していく作業が重要であり、その道しるべとなるのがこのような発達理論であると思います。