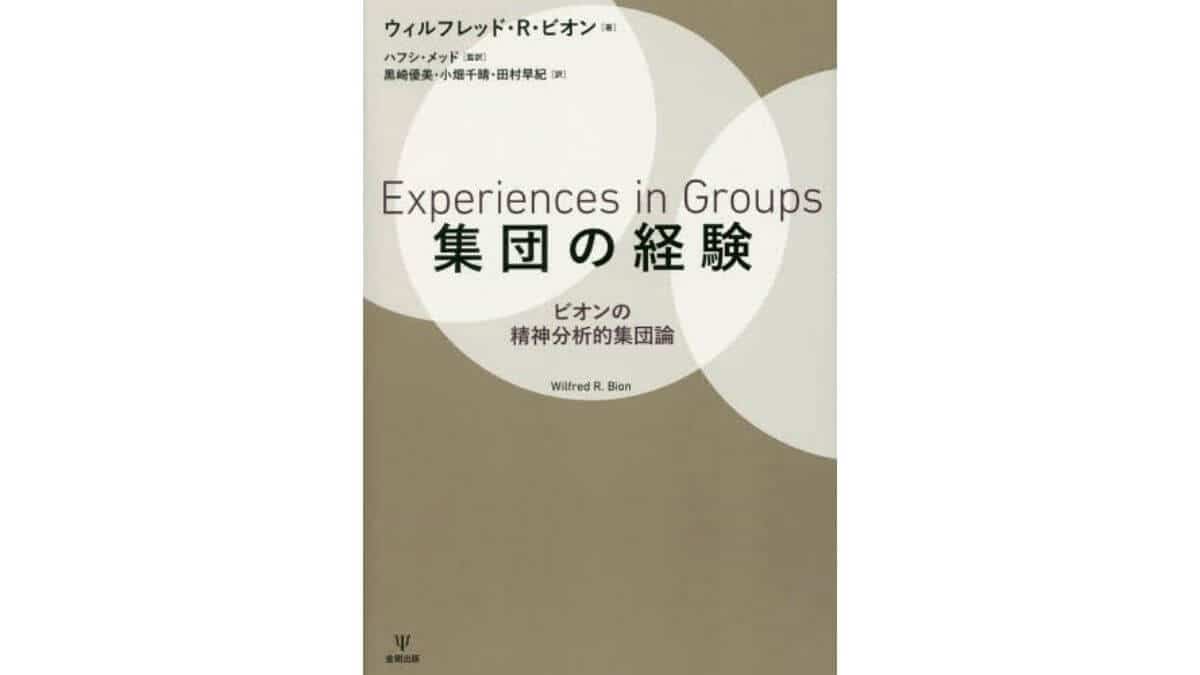ラカンから見た精神分析とは

新宮一成(著)「ラカンの精神分析」講談社現代新書 1995年を読んだ感想です。ラカンの理論は非常に独自的で、精神分析のみならず哲学や思想、文化論に多大な影響を及ぼしました。ラカンの理論は難解で、理解しがたいところが多いですが、知的創造を刺激されてしまいます。
はじめに
本書はラカンの人生とラカン理論について簡潔に書かれた入門書です。入門書ですが、やはり基本的な精神分析についての知識や経験がないと理解しにくい本でもあります。また、言語学や記号論についての知識があればなお良いでしょうが、なくても丁寧に読めば、理解はできるでしょう。。
フロイト回帰
ラカン理論は基本的にフロイト回帰から出発しており、フロイト理論の読み直しが最重要課題となっています。特に死の欲動の概念はフロイト以後は思弁的なものとしてクライン派などの一部の精神分析家以外はあまり重要視していません。しかし、ラカンはこの死の欲動こそが他者と自己とをつなぐ概念として再注目しています。
短時間セッション
ラカンの技法としてもっとも目を引くのが短時間セッションです。これは精神分析の一回のセッションの時間を短くするというものです。この技法によってラカンは主体を尊重できるという主張をしており、IPA(国際精神分析学会)からの要請にも関わらず、この技法を捨てることはありませんでした。このためにラカンは訓練分析家になることができなかったようです。
短時間セッションについては、ラカン理論の背景から読み解けば、確かにそこに大変意味のあるものと思われます。特に時間を区切るということが解釈としての機能を果たすということはうなづけるところもあります。しかし、反面では、解釈というのはそれをすること自体も重要ですが、解釈後のクライエントのレスポンスを見ることも重要となってきます。
カウンセラーの解釈を肯定するのか、否定するのか、無視するのか、連想が変わるのか、連想が変わらないのか、そういうところからさらに分析を進めていく素材が浮き上がってくるのです。時間を区切るということはその区切った後のクライエントのレスポンスを扱うことが難しくなってしまうというデメリットは無視できないものでしょう。ちなみに、短時間セッションはラカン以外のラカン派精神分析家は使用していなかったようです。
黄金数
また、本書では黄金数という言葉が多数出てきます。これらは「他者を見る中に自分の存在をみる」という観点から重要な考え方で、いわゆる存在論的な視点です。P93で「”どう見えるか”ということを割合で、つまり理性で表すことにしよう」としています。
すなわち、「他人y/私x」となり、そこからさまざまな数式で黄金数に導いています。しかし、なぜこれらの前提が成り立つのか正直理解できていません。また、見ることがどういうところから割合で示すということになるのかも理解に苦しみました。
ラカンの思想的側面
ラカン理論の他者の欲望や対象aという概念はフロイトのテクストから抽出したラカン独自のものです。これらの概念から転移や精神分析における精神分析家とクライエントの間における関係性の変化を理解していくことができます。
また、それに留まらず、精神分析を超えて、人間存在を規定するもの、人間のありようを証明するものとして、哲学的・思想的な価値を有するものであると考えられます。その傾向が強いがゆえに、臨床的にこれがどのように活用されるのか、クライエント理解にどうつなげられるのか、といったことが削り取られてしまっており、臨床的有用性の観点から少し物足りなく感じてしまうところもあります。
精神分析は臨床の中から生まれ、臨床の中で活用されるものです。しかし、ラカン理論は臨床の中で活用されるというよりも、思索的に活用されることが多いようです。ラカン理論を研究している人は、臨床家よりも哲学者や思想家、文化人に多いようです。精神分析臨床をしている人は自我心理学-クライン派-独立学派-コフート派-対人関係論学派を基盤にしている人が多いのではないでしょうか。こういう風になっているのも色々な歴史的経緯が関係していることが考えられます。
ラカンの独特な考えや思想、技法はIPAの考えとはかなり異なっており、IPAからは破門に近い形でラカンは追放されています。IPAに属さないということは、精神分析家や訓練分析家となることができず、臨床指導ができないということになります。ラカンはその代わり、教育機関において臨床家対象ではなく、哲学者や思想家、文化人を対象としたセミナールを開講しています。
対象がそうした文化人であったために、臨床というよりは思想的な観点が強調されていったのではないかと思われます。ラカンは臨床実践を軽視するなと言ったり、パリ・フロイト派を立ち上げたり、といった活動はしていたようですが。こういうところから、ラカンが臨床家ではなく、非臨床家を中心に思想が展開して行ったのではないかと想像します。
ラカンの人生
ラカンの人生はかなり紆余曲折があり、対立と同盟が繰り返されていたようでした。また、その難解な語りが災いしてか、誤解や偏見によって迫害されていたところもあるようです。ラカンは教育分析や個人分析、スーパービジョンを通して多くの弟子を育て、自分の理論の実践の場としていくつかの団体を結成しました。しかし、その弟子にさえ、その理論の根本を理解されることなく、言われなき分裂や決別、失望、失敗を体験しました。パリ・フロイト派の解散はラカンにとってはかなり大きな痛手であったようです。
フロイトが「分析技法における構成の仕事(1937)」で弟子たちがフロイト理論を正しく継承していなかったことを嘆いていたのと同様に、ラカンもラカン理論が正しく伝えられなかったことを嘆いていたのかもしれません。特にパスという資格制度についてはラカンの理想や理念が織り込められたものであったのでしょうが、最終的には「失敗だった」と言わざるを得なくなり、自らパリ・フロイト派を解散させねばならなくなってしまいました。
ここにラカンがラカンであったがゆえの悲しみが付されているように思います。