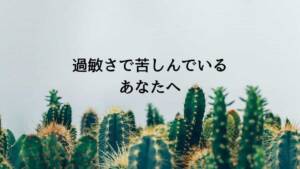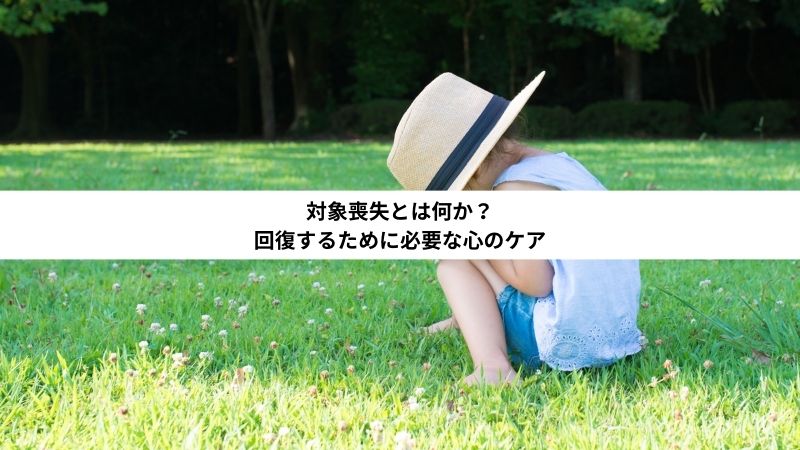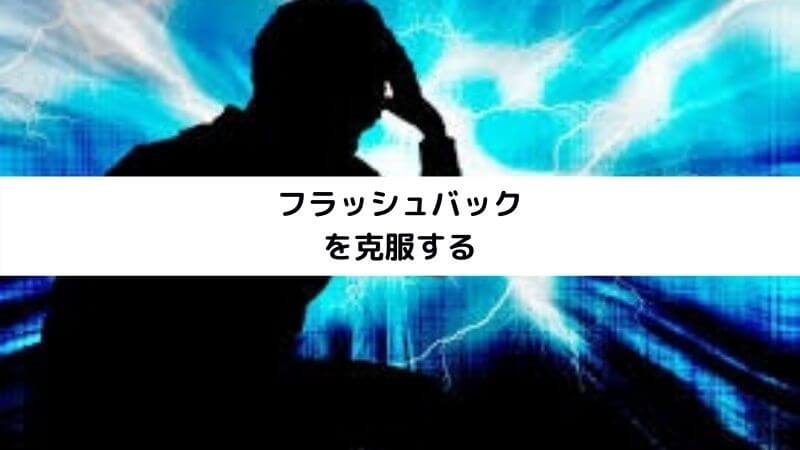生きづらさの原因とその解決法とは

現代は多様性の時代と社会といわれています。さまざまなタイプ、性格、生き方などを承認されています。しかし、一方では勝ち組・負け組などと区別されたり、目に見えにくいマウントの取り合いが横行していたり、社会的ステータスが幅をきかせていたりします。
こうした中で、一部の人たちは、社会で生きづらい思いをしながら生きています。このコラムではこうした生きづらいことについて書いてみたいと思います。
目次
生きづらい性格
現代社会は大量の情報に覆われています。そして、人間の脳の処理能力では、そのすべての情報を把握することは不可能です。
そのため、要領の良い人は情報を選択し、必要なものだけを取り入れ、不要なものを排除します。
しかし、要領の良くない人はすべての情報を取り入れねばならないと強迫的になってしまいます。その結果として、反対に情報の取り入れだけに必死になり、それを活用するところまでいかないのです。
これはおそらくは脳の処理能力の問題ではなく、性格的な原因が大きいようです。良くいえば真面目で、きっちりとしないといけない思いが強いといえるでしょう。悪くいうと、強迫的、完璧主義といった性格であるといえます。
よくある相談の例(モデルケース)
30歳代 男性
Aさんは30歳代の男性で、子どものころから「人に迷惑をかけてはいけない」と強く思い込んで育ちました。両親は真面目で厳しく、失敗すると「もっと努力しなさい」と言われることが多く、安心して弱音を吐くことができませんでした。学校生活では勉強や部活動に励み、表面上は順調に見えましたが、心の中では常に不安や緊張を抱えていました。大学卒業後は希望する会社に就職しましたが、完璧に仕事をこなそうと無理を重ね、残業続きで心身の疲れが蓄積していきました。30歳を過ぎた頃から朝起きられなくなり、仕事への意欲が湧かず、休日も何も楽しめない状態が続きました。職場でも人間関係に悩み、自分が役に立っていないのではという思いが強まり、孤立感が深まっていきました。心療内科を受診すると抑うつ状態と診断され、抗うつ薬と睡眠薬が処方されましたが、生きていること自体の重さが消えることはありませんでした。
限界を感じたAさんは、インターネットで情報を探し、カウンセリングを申し込みました。初期には、自分の「生きづらさ」が具体的にどのような場面で強くなるのかを一緒に整理し、安心できる場で感情を言葉にすることから始めました。徐々に、幼少期から「弱さを見せてはいけない」と思い込んでいたことが、自分を追い詰めている大きな要因であると気づきました。数年のカウンセリングを通じて、Aさんは自分の気持ちを抑え込むのではなく、疲れたときに休むこと、困ったときに人に助けを求めることを練習しました。小さな成功体験を重ねることで、自己否定感が少しずつ和らいでいきました。また、職場では「完璧にやる」よりも「できる範囲を伝える」工夫を実践し、人間関係でも無理なく自分を出せるようになりました。現在では、完全に不安がなくなったわけではありませんが、「生きていてもよい」と感じられる時間が増え、趣味や友人との交流を通して日常に充実感を取り戻しつつあります。
生きづらい人間関係
競争社会は経済的な発展にとってはとても必要なことです。しかし、それが行き過ぎると人を出し抜いてでも勝たねばならないという殺伐とした社会になってしまいます。
また、限りあるパイを奪い合うことによって、勝ち組と負け組に分類が生まれてしまいます。
こうしたことが身近な人間関係のなかでしばしば起こります。例えば、成績によって良いところに行ける人と、そうではない人が分けられます。また、人よりも上に居ようとするマウントの取り合いなど起こることもよく見かけることです。
こうした人間関係では、他者の意図を推測し、雰囲気をつかみ、人の弱点をうまくついて、自身を優位な立場にすることが得意な人ほど勝ち残ります。時には人を傷つけることも躊躇しない非人間的なことを平気でできることが強さの秘訣になったりすることもあります。
こうした中で、人に配慮し、人を優先させ、自分を二の次にするような優しい人はこうした競争社会で脱落してしまいます。
こうしたことは生きづらさに直結するでしょう。
Aさんは、職場や友人関係で相手の期待に応えようと無理をしてしまい、疲れ切ってしまうことが多くありました。相手の顔色をうかがう癖が強く、断ることができずにストレスを抱えていました。
生きづらいことと差別
ひと昔前に比べると、人権意識は急激に向上し、差別というのがだんだんと無くなっています。また、法律的にもさまざまな差別を禁止、解消するようになっています。しかし、それでも、まだまだ差別が残っている部分もあります。
差別には、性差別、人種差別、地域差別、職業差別、障害者差別、コロナ差別などがあります。多くはマイノリティが差別される側にされてしまいます。
差別はしている人はほとんど意識していない反面、差別されている人は強烈に生きづらさを押し付けられます。
人は自分とは違うもの、自分には理解できないものを排除しようとします。おそらく、進化的に、同族で結集し、他種族や他生物からの攻撃から身を守り、生き残るために必須のことだったのでしょう。異質なものを排除するのは人類の進化には不可欠だったのですが、それが現代にも残っており、自分とは違うものを排除するという行動になってしまいます。
こうした差別により生きづらい思いをしている人は現代でも非常に多いでしょう。
Aさんの場合、周囲に理解されないことで孤立感が深まり、「自分はおかしいのでは」と感じることがありました。
生きづらいことと障害
(1)障害と生きづらいこと
社会はいわゆるマジョリティや健常人が生きやすいように設計されています。例えば、右利きの人が多いため、文字や設備の多くは右利きの人に操作しやすいように作られています。そうすると、必然的に左利きの人は操作がしにくいことになります。
障害者はさまざまな病気や疾患により、健常人には容易にできることが、容易にはできないのです。身体障害の場合であれば、目に見えて分かるので、人が手助けしてくれることがそれなりにあります。
しかし、いわゆる精神障害の場合、目に見えて分かることが少なく、そうした人の手助けを得られにくいのです。
Aさんは、精神的な不調を打ち明けると偏見を持たれるのではと恐れ、苦しみを抱え込んでいました。
(2)アダルトチルドレンと生きづらいこと
アダルトチルドレンとは幼少期に養育者から不適切な養育を受け、それによってその後の人間関係や社会生活に支障をきたしてしまっている人を指します。
アダルトチルドレンは人間関係において、人のことを常に気にしてしまい、過度に緊張してしまい、自分を出すことができず、過剰に合わせてしまう生き方をしてしまいます。それによって、部分的に社会適応をすることはできますが、無理をしているため、精神的に非常に疲弊してしまいます。
こうしたことはアダルトチルドレンの生きづらさに直結しています。
アダルトチルドレンについての詳細は以下のページに詳しく書いています。
Aさんは、親の機嫌を気にする家庭環境で育ち、大人になっても人間関係で過剰に気を遣うパターンが続いていました。
(3)HSPと生きづらいこと
HSPとは感覚が過敏で、ちょっとした刺激を強く感じてしまう特性をもつ人のことです。音、触感、人の感情などに反応してしまい、非常に翻弄されてしまいます。
また、人から言われたことを過度に否定的に捉えてしまったりすることもあり、傷つきやすい側面もあります。
この世の中は刺激に満ちています。適度のその刺激にフィルターをかけ、感じなくすることで生きていくことができます。しかし、HSPはそうした器用なことができず、全ての刺激にそのまま曝されてしまいます。
このようなHSPの方にとっては生きづらい社会や時代であるといえるでしょう。
HSPについての詳細は以下のページをご覧ください。
Aさんの場合、他人の感情や職場の雰囲気に敏感で、刺激の多い場面では強い疲労感を覚えていました。
(4)発達障害と生きづらいこと
発達障害には主に自閉スペクトラム症とADHD(注意欠陥多動性障害)などがあります。いずれも発達特性、認知特性の標準からの偏りがあり、そのため、人間関係や社会生活が思うようにこなせない障害です。
発達障害は些細な事柄にこだわりを持ってしまい、広い視野で物事を見ることが苦手です。また、落ち着きがなく、つねにソワソワとし、身体を動かし続けてしまう特徴もあります。さらには感覚過敏のところもあり、ちょっとした刺激に左右されてしまう面もあります。
こうした発達障害の特性のために、この社会の中で生きづらい思いを抱えてしまうことは必然です。
発達障害についての詳しいことは以下のページに解説していますので、ご興味があればご覧ください。
Aさんは、仕事の優先順位をつけるのが苦手でミスが続き、自己肯定感が下がってさらに生きづらさを感じていました。
(5)愛着障害と生きづらいこと
愛着障害とは幼少期に養育者との間で健全な愛着、アタッチメントが形成されず、さまざまな問題行動を起こしてしまう障害です。
愛着障害には反応性愛着障害と脱抑制性対人交流障害の2つのタイプがあります。前者は接触することを求めず、人と距離を取ろうとするタイプです。後者は反対にベタベタと過度に接触し、馴れ馴れしい態度を誰に対しても取ってしまうタイプです。いずれも距離の取り方が極端な人間関係なので、社会生活上、著しい困難が生じてしまいます。
愛着障害は、人との愛情関係や恋愛関係においても影を落とします。過度に恋人やパートナーの顔色をうかがってしまい、恋愛を楽しむことができません。いつも振られるのではないか、捨てられるのではないかといった疑心暗鬼をもってしまい、心が休まりません。
こうした愛着障害においても、生きづらいことと強く影響しています。
愛着障害については下記のページに詳細に書いています。
Aさんの場合、親密な関係になると不安が強まり、相手に依存したり逆に距離を取りすぎたりするなど、人との関係が安定しませんでした。
生きづらさについてのよくある質問
生きづらさとは、日常生活や人間関係において、他者と比べて困難や不便を感じる状態を指します。具体的には、社会的な適応が難しい、感情のコントロールが難しい、自分の価値観や感覚が周囲と合わないなどの状況が含まれます。これらの感覚は、幼少期の経験やトラウマ、発達障害、性格的な要因など、さまざまな背景から生じることがあります。
生きづらさの原因は多岐にわたります。主な要因として、幼少期の虐待やネグレクト、親との関係性の問題、トラウマ的な経験、発達障害やパーソナリティ障害などの精神的な要因が挙げられます。また、社会的なプレッシャーや人間関係のストレスも生きづらさを感じる一因となります。
生きづらさを感じる人の特徴として、自己評価が低い、他者とのコミュニケーションが苦手、感情の起伏が激しい、過度な完璧主義、他者からの評価を過度に気にするなどが挙げられます。これらの特徴は、幼少期の環境や経験、個人の性格特性などが影響しています。
生きづらさを解消するためには、専門的なカウンセリングや心理療法を受けることが効果的です。自分の感情や思考のパターンを理解し、適切な対処法を学ぶことで、日常生活の困難さを軽減することができます。また、信頼できる人とのコミュニケーションを増やし、サポートを受けることも重要です。
発達障害を持つ人は、社会的なコミュニケーションや行動の面で特性があり、その結果として生きづらさを感じることがあります。例えば、自閉スペクトラム症の人は、他者との意思疎通が難しく、社会的な場面での適応が困難な場合があります。適切な支援や理解が得られないと、生きづらさが増す可能性があります。
生きづらさを感じたときは、専門のカウンセリング機関や精神科・心療内科の医療機関に相談することが推奨されます。専門家との対話を通じて、自分の感じている困難の原因や対処法を見つけることができます。また、地域の相談窓口や支援団体も活用することで、適切なサポートを受けることができます。
HSP(Highly Sensitive Person)は、日本語で「非常に敏感な人」を意味し、外部からの刺激や他者の感情に対して非常に敏感に反応する特性を持つ人を指します。HSPの人は、音や光、匂いなどの感覚刺激や、他者の感情の変化に敏感であるため、日常生活で過度なストレスを感じやすく、生きづらさを感じることがあります。
生きづらさを感じる子どもへの対応として、まずは子どもの気持ちや考えを尊重し、じっくりと話を聞くことが重要です。無理に問題を解決しようとせず、子どものペースに合わせてサポートすることが大切です。また、必要に応じて学校のカウンセラーや専門の心理士に相談し、適切な支援を受けることも検討してください。
自己肯定感が低いと、自分の価値を感じにくく、生きづらさを感じる原因となることがあります。自己肯定感を高めるためには、自分の良い点や成功体験を振り返り、自己評価を見直すことが効果的です。また、他者と比較せず、自分らしさを大切にすることも、自己肯定感の向上につながります。
生きづらさを抱える人を支援するためには、まずその人の話をじっくり聞き、感情を受け止めることが大切です。アドバイスを押し付けるのではなく、共感を示し、安心できる環境を提供してください。また、専門的な支援が必要な場合には、心理カウンセラーや医療機関を紹介するなど、適切な支援につなげるサポートを行うことも重要です。
生きづらいことを相談する
現代は生きづらいと感じる人が増えている印象です。人によってその生きづらい理由は違うでしょうが、上記に書いたような性格、人間関係、障害が関わっていることが多いでしょう。
こうした生きづらいことについて何が理由なのか、原因なのか、どうすれば良いのか、などについてお困りの場合には相談、カウンセリングをすることができます。
相談、カウンセリングをご希望の方は以下のページからお申し込みください。