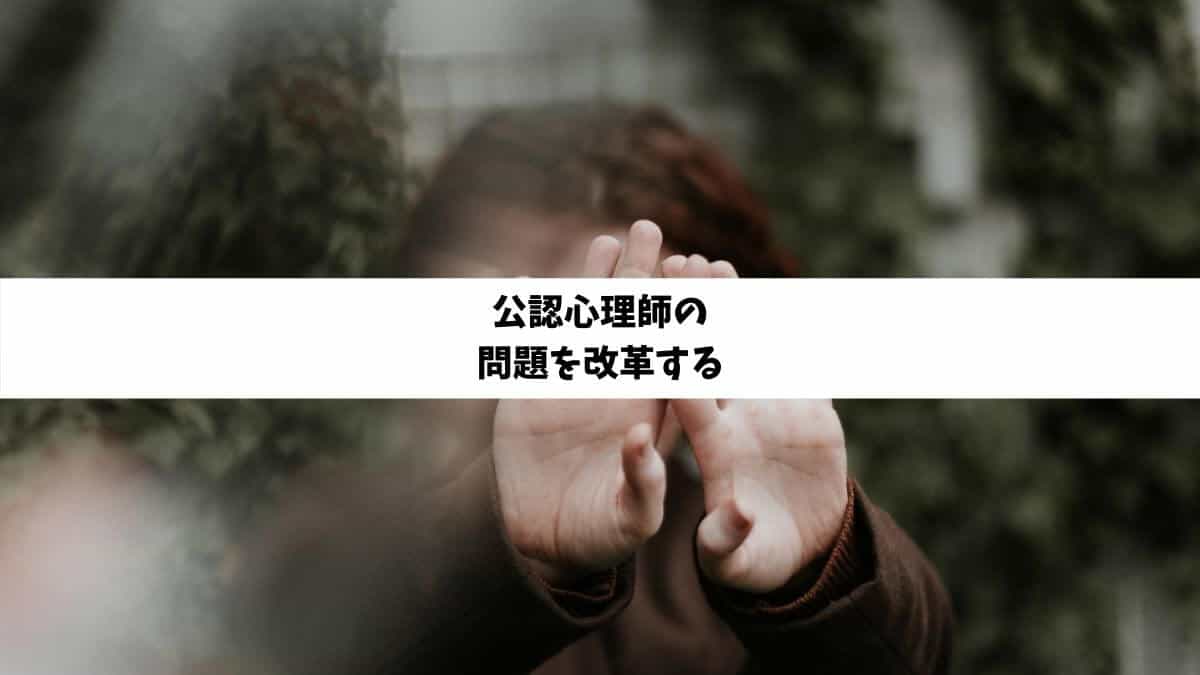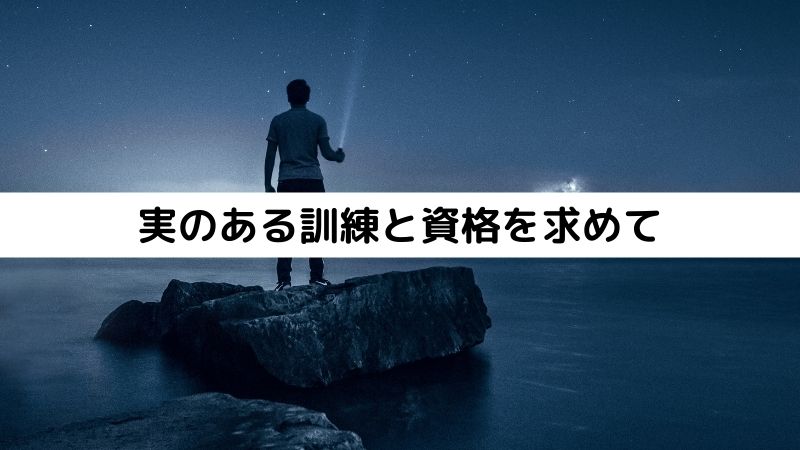カウンセリングの倫理

カウンセリングにはカウンセラーが守らなければならない倫理があります。倫理には非常に道徳的なニュアンスが含まれますが、非倫理的なことをすることによってクライエントに害を与え、福利に反することになってしまいます。以下に主だった倫理について書きます。
各々のカウンセラーは「自分はこうしたことをしない」と無関係なものと考えるのではなく、何かのタイミングときっかけによって、倫理に反することをしてしまう可能性があると頭の片隅にでも置いておくことの方が大事になってきます。
目次
二重関係の禁止

カウンセラーは家族、親族、恋人、友人、クラスメイト、職場の人、生徒など、もともと私的な関係のある方にカウンセリングをしてはいけません。もし仮に、そうした私的な関係のある人とのカウンセリングをおこなった場合、私的関係とカウンセリング関係が重複してしまいます。これをカウンセリングにおける二重関係の禁止と言います。クライエントとカウンセラーは、カウンセリングの場のみの付き合い・関係でなければいけません。
二重関係については以下のブログに詳しく書いています。
私的利用の禁止
カウンセラーがクライエントにカウンセリングを実施する目的はクライエントの福祉や福利に貢献するためです。そして、それの対価として料金を頂きますが、それはサービスの質と量に即した適正なものでなければいけません。それ以上のものを要求することやクライエントをカウンセラー自身の欲望のために利用することは私的利用にあたり、禁止されています。
例えば、カウンセラー自身の宗教を押し付けること、カウンセリングとは関係のない売買を持ち掛けること、個人的な頼みごとをすること、セミナーや研究会に参加することを強要すること、などが挙げられます。
性的行為の禁止
カウンセラーとクライエントが性的な関係を持つことは厳しく戒められています。例え、それがクライエントから求められたことであったとしても性的行為をしてはいけません。なぜなら、どういう形であったとしても性的行為によりクライエントは傷つくことになってしまうからです。
守秘義務
カウンセラーやカウンセリングの中でクライエントから見聞きしたことを、みだりに第三者に話したり、公開したりしてはいけません。クライエントはカウンセリングの中ではプライバシーが守られるからこそ自由に話をしたりすることができます。秘密がばらされることほど傷つく体験はないでしょう。
しかし、これには例外があり、例えば、自傷他害の危険性があり、関連機関との連携が必要になるときには守秘義務が解除され、適正な範囲内で情報共有を行うことのほうが寧ろ望ましいこともあります。虐待やDV(ドメスティックバイオレンス)などがあるときには、こうした事態になることが多いかもしれません。
これに関しては下の「カウンセリングにおけるカウンセラーの守秘義務」で詳しく書いています。
インフォームドコンセントの順守
日本語では「説明と同意」と訳されることがあります。カウンセラーはこれから実施しようとするカウンセリングの方法や心理査定の方法などについて、クライエントの理解できる言葉で十分に説明する義務があります。そして、そのことについてクライエントから同意を得られない限り、実施してはいけません。
適正な技術の実施
カウンセラーはこれまでに積み重なってきた心理学的な知見、臨床心理学的な知見を参照し、適正で、妥当性のある、効果がある程度保証されている技術を用いらねばなりません。研究が積み重なっておらず、効果が不明、もしくは効果のない技術をクライエントに対して実施してはいけません。
時折、カウンセラーの中でも、効果が立証されていない代替医療や疑似科学、霊的治療の実施を標榜しているホームページも見かけますが、厳に戒められねばなりません。
自己研鑽の義務
カウンセラーは日々、勉強、学習、訓練、研究を行い、自身の技術を向上する努力を続けねばなりません。カウンセリングの技術は日々発展しています。そうしたこと全てを身に着けることは不可能ですが、それでもできる範囲で研鑽する義務があります。
当オフィスではカウンセラーの自己研鑽の場を用意しています。詳細は以下をご覧ください。
カウンセリングにおける倫理についてのよくある質問
カウンセリングにおける倫理とは、カウンセラーがクライエントの権利と福祉を守るために遵守すべき行動規範を指します。これには、守秘義務や自律性の尊重、公平性、誠実さなどの倫理的原則が含まれます。また、カウンセリングの過程において、クライエントに対して常に安全で信頼できる環境を提供することが求められます。倫理を守ることは、クライエントとの信頼関係を築く基盤となり、効果的な支援を可能にするために非常に重要です。
守秘義務とは、カウンセラーがクライエントから聞いた相談内容や個人情報を第三者に漏らさない義務を指します。これはクライエントのプライバシーを守り、安心して話せる環境を作るために欠かせない原則です。ただし、例外的に守秘義務が解除される場合もあります。例えば、クライエントや他者の生命や安全に重大な危険があると判断される場合や、法的な義務がある場合などです。守秘義務を遵守することは、カウンセラーとしての信頼を保つ鍵となります。
守秘義務はクライエントとの信頼関係を守る上で非常に重要ですが、特定の状況では例外が認められます。例えば、クライエントが自傷行為や他者への暴力を示唆している場合、生命や安全を守るために必要最低限の情報を関係機関に伝えることが許されます。また、法律で情報提供が義務付けられる場合や、クライエントが情報開示に同意した場合も守秘義務が適用されません。こうした例外は、倫理と法律を踏まえた上で慎重に判断されます。
カウンセラーとクライエントの関係では、専門的な境界を守ることが非常に重要です。二重関係(例えば、カウンセラーがクライエントと私的な関係を持つこと)や金銭的利益の衝突は避けなければなりません。また、クライエントに対して過度な依存を促すような言動や、カウンセラー自身の価値観を押し付けることも不適切です。これらを避けることで、公正で効果的なカウンセリングが可能になります。
カウンセラーは常に専門性を高める努力を続けることが求められます。具体的には、最新の研究や技術を学ぶための研修への参加、定期的なスーパービジョンの受講、自身の実践を振り返るための自己評価などがあります。また、学術的な知識だけでなく、クライエントとのコミュニケーションや文化的な理解を深めることも重要です。これにより、クライエントに質の高い支援を提供できます。
文化的多様性を尊重するためには、カウンセラーが偏見を持たずにクライエントの価値観や背景を理解する努力をすることが必要です。例えば、クライエントの文化や宗教的信念、社会的状況を尊重し、それに基づいた対応を行うことが求められます。また、多様な背景を持つクライエントとの関わりを通じて、自身の文化的感受性を高めることが重要です。これにより、より効果的で信頼性の高いカウンセリングが可能となります。
インフォームド・コンセントとは、カウンセリングを始める前にクライエントに十分な情報を提供し、その内容に同意してもらうプロセスを指します。この情報には、カウンセリングの目的、方法、予想される効果やリスク、料金などが含まれます。インフォームド・コンセントは、クライエントの権利を守り、自分で選択する力を尊重するための重要な手段です。
利益相反を避けるためには、カウンセラーが自分自身の利益や感情がクライエントとの関係に影響を及ぼさないよう努める必要があります。例えば、業務外での私的な関わりを避ける、第三者の利益を優先しないなどの行動が重要です。また、定期的にスーパービジョンを受けることで、利益相反の可能性を客観的に見直すことが求められます。
クライエントの自律性を尊重するために、カウンセラーはクライエント自身が問題解決の方法を選び、意思決定を行う権利を認める必要があります。また、クライエントの価値観や信念を尊重し、強制や過度な誘導を避けることが大切です。自律性を尊重する姿勢は、クライエントの自己成長を支える基盤となります。
信頼関係を築くためには、カウンセラーがクライエントに対して誠実で共感的な姿勢を持ち、真摯に対応することが重要です。また、守秘義務を守り、クライエントが安心して話せる環境を提供することが求められます。信頼関係は、カウンセリングの成功に直結する要素です。
カウンセリングを受けたい方へ
カウンセラーはこうした倫理に縛られています。これはクライエントを守るためのものです。こうした倫理がないカウンセラーはクライエントにとっては恐ろしいことでしょう。そして、倫理から逸脱した場合には一定の制裁が課せられます。こうした仕組みがクライエントを守るのです。
ですので、クライエントは倫理で縛られている資格を持ち、団体に所属しているカウンセラーにカウンセリングを受けると良いでしょう。
当オフィスのカウンセラーは全員、臨床心理士や公認心理師の資格を持ち、心理系の学会や職能団体に所属しています。そして、それらの倫理に縛られています。そうした当オフィスのカウンセラーのカウンセリングを受けたいと希望される方は以下からお申し込みください。
カウンセリング関連団体の倫理綱領
以下に心理学、臨床心理学、カウンセリングに関係する諸団体が公表している倫理綱領を挙げておきます。その団体に所属するカウンセラーはこうした倫理綱領に従って業務を行っています。反対にいうと、こうした団体に所属していない無資格カウンセラーは倫理に縛られておらず、野放しになっているため、時として危険になることもあります。
- 日本心理臨床学会 倫理綱領
- 日本臨床心理士会 倫理綱領
- 日本臨床心理士資格認定協会 倫理綱領
- 東京臨床心理士会 倫理綱領
- 日本産業カウンセラー協会 倫理綱領
- 日本カウンセリング学会認定カウンセラー 倫理綱領
その他にカウンセリングと倫理については以下のような書籍もでているので参考になるでしょう。