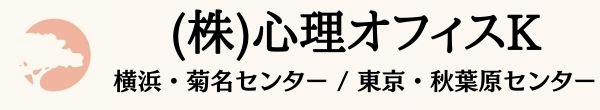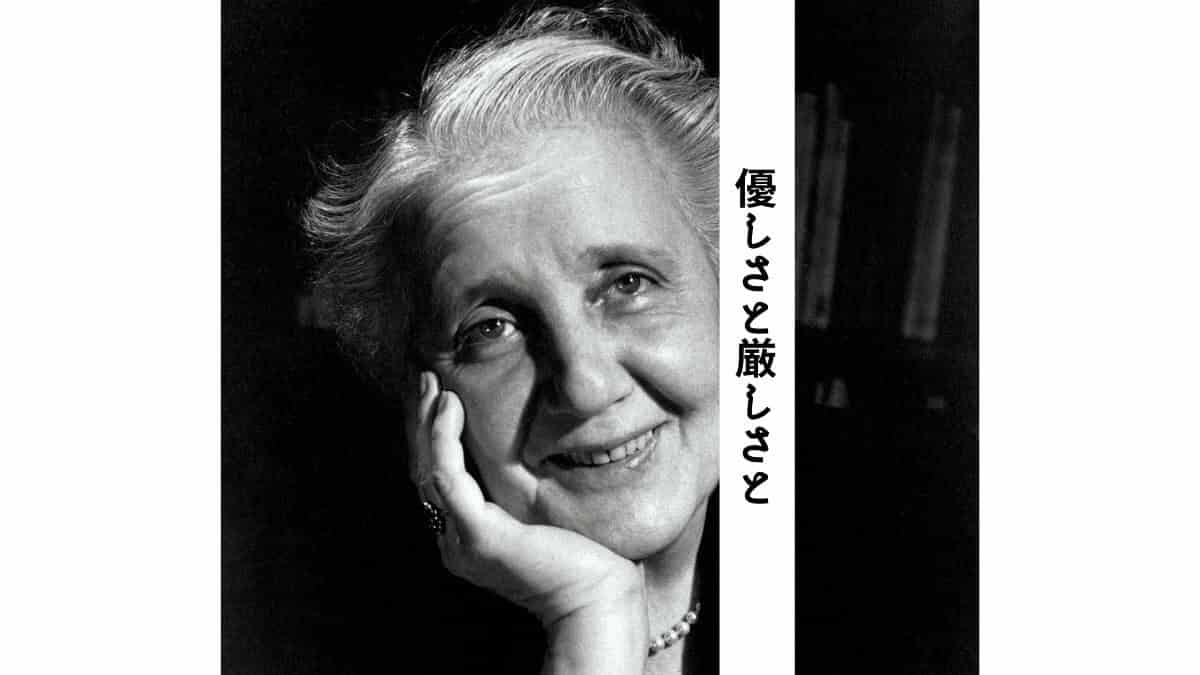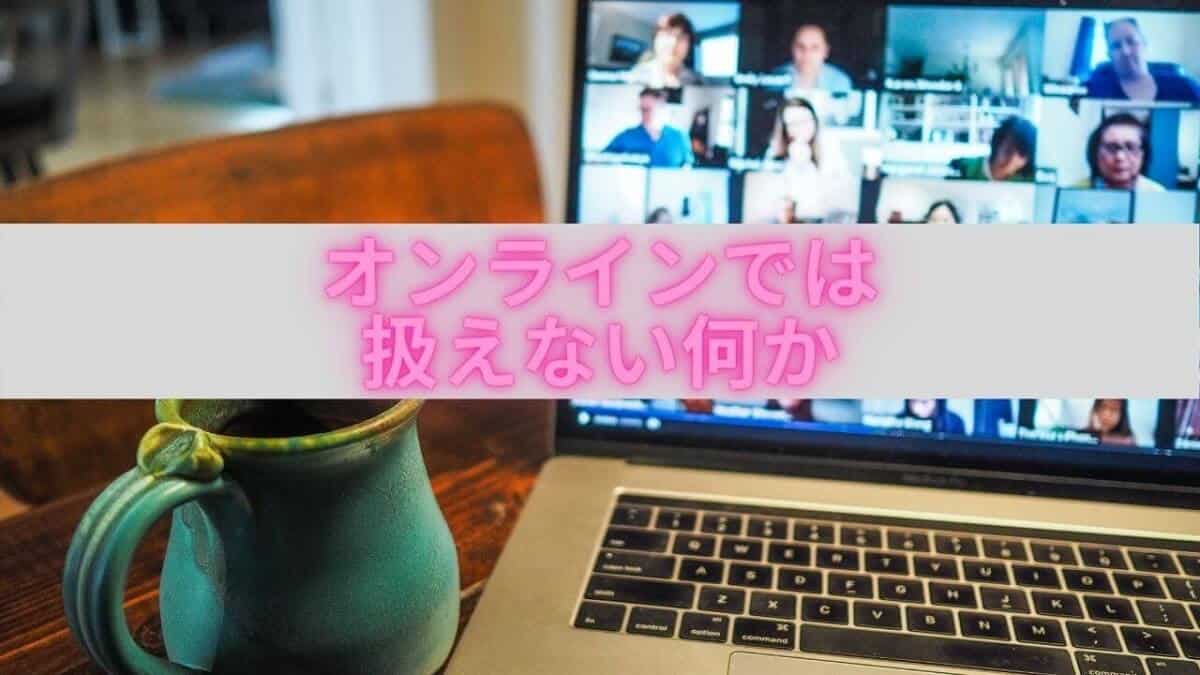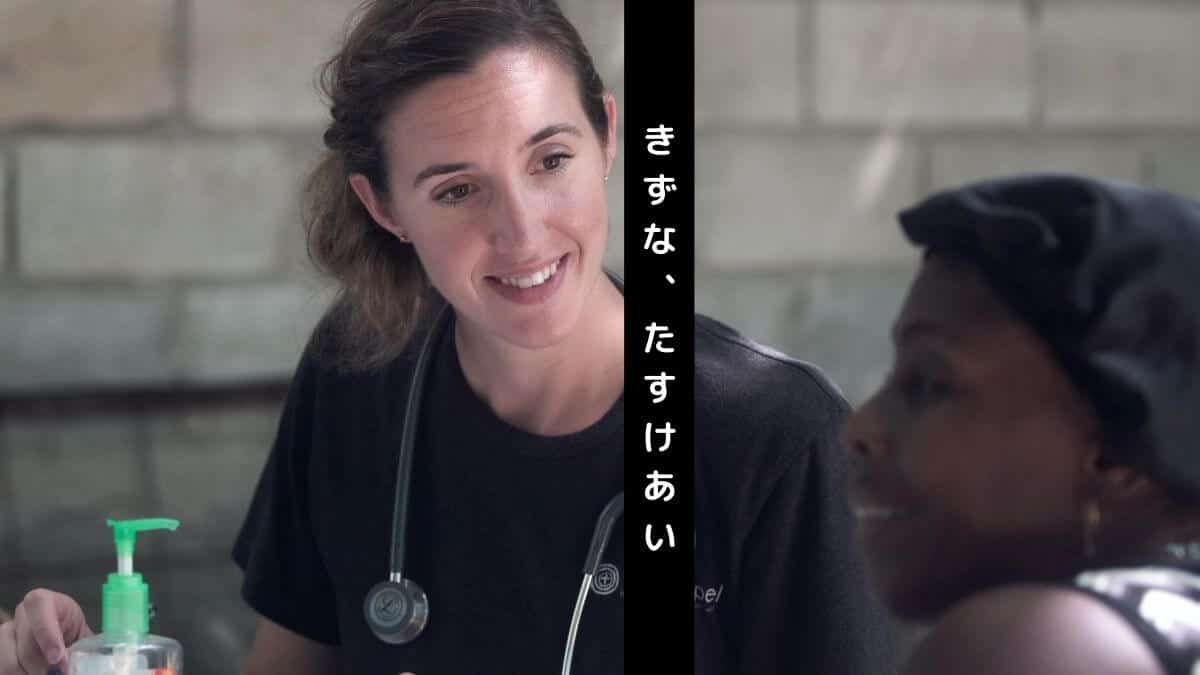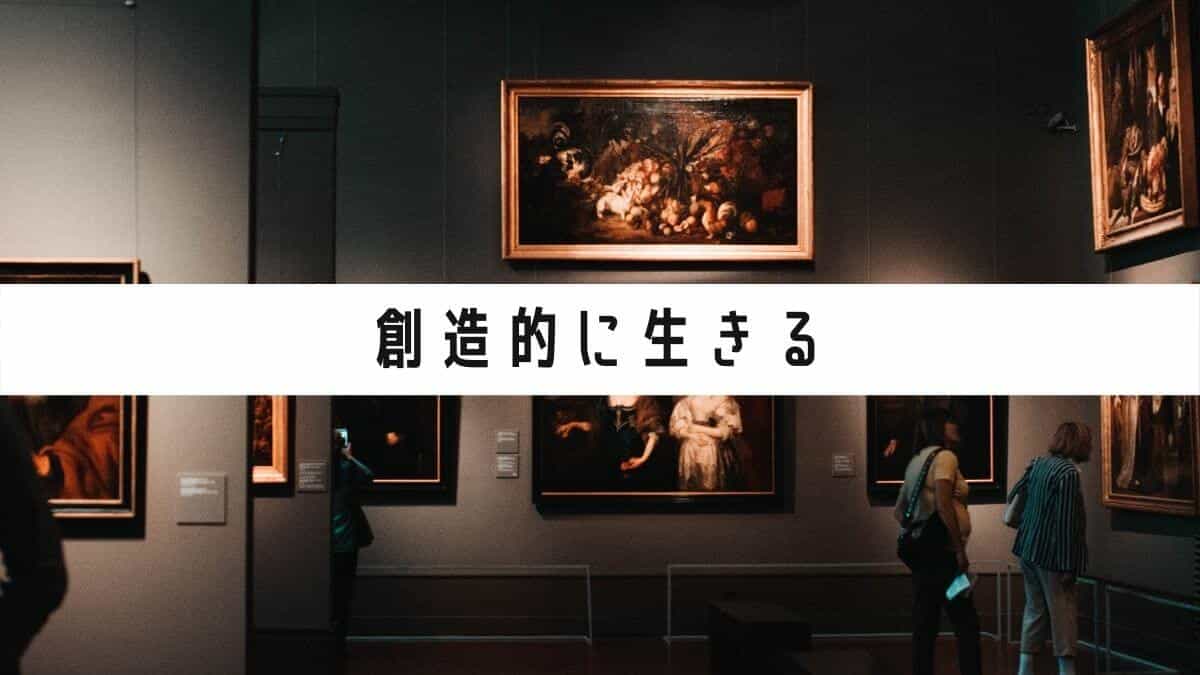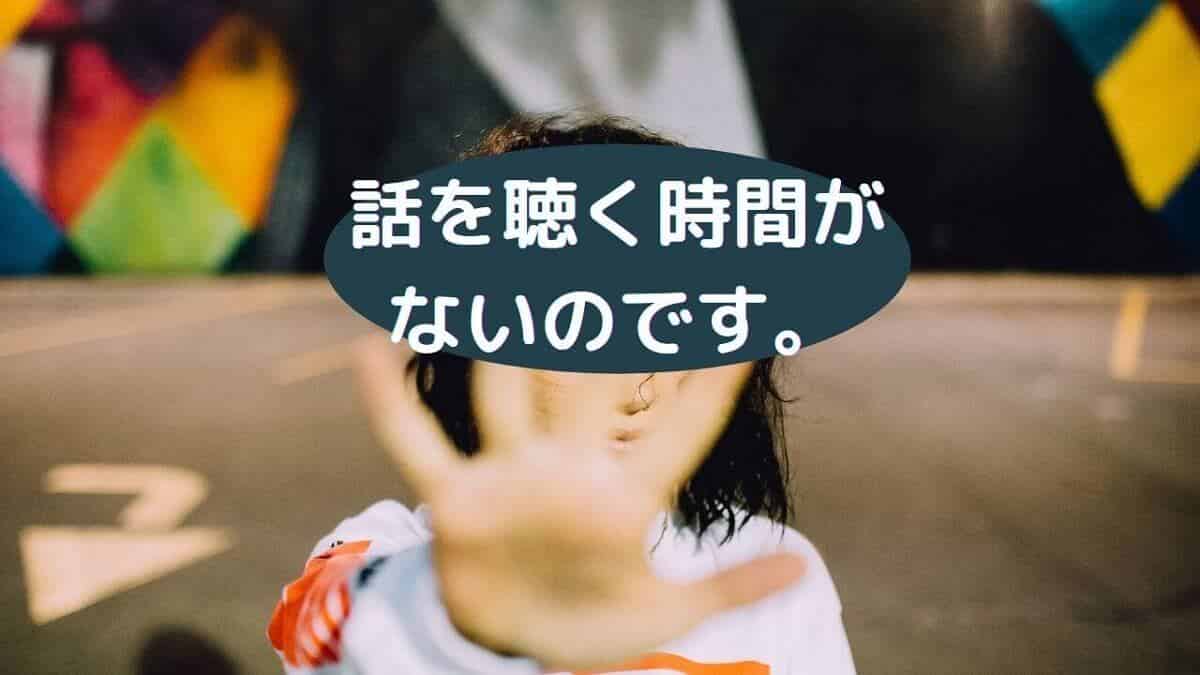優しさを苦痛に感じるクライエントについて

人の優しさや人との交流といった一見は肯定的なことを苦痛に感じてしまう一群のクライエントがいます。そうしたクライエントに対する対応やカウンセリングについて書いています。
目次
優しさを苦痛に感じるクライエントとは

人の優しさや肯定的な関係が、一般には癒しや安心をもたらすものと考えられますが、あるクライエントにとってはそれがむしろ苦痛になることがあります。肯定や親身な共感が「侵襲」として感じられ、関係や感情の距離が急に近づくことで不安や恐怖を引き起こすケースが存在します。これは、幼少期に発達にそぐわない環境で育ち、親密さを受け入れることが傷つきの再現に感じられたり、信頼を持てずに自我を守るための防衛が働くことから来ています。表面的には社会適応できていても、内面には空虚さや虚無感、不安定な感情が広がっており、生きる手応えが乏しく、「世界が色あせて見える」という感覚を抱えることも少なくありません。
このようなクライエントに対しては、まずアセスメントを丁寧に行い、意識的な「ニード(要望)」だけでなく無意識の要望も見立てて、カウンセリングの目的や方法についてクライアントとの合意を得ることが重要です。無暗に距離を詰めたり共感を押し付けたりせず、クライアント側のペースや安全感を尊重するスタンスが回復への鍵となります。
よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 女性
Aさん(40代女性)は、誰かに親切にされると胸が締め付けられ、涙が出そうになる一方で、その場から逃げたくなる苦痛を感じてきました。幼少期、体調の弱い母は「あなたが良い子でいてくれたら助かる」と繰り返し、Aさんは気遣いのできる子として家族を支えましたが、感謝の言葉は恩義と義務に変換され、優しさは「返さねばならない負債」と学習されていきました。成人後も、職場で手を差し伸べられるほど自己価値の低さと罪悪感が刺激され、過剰に頑張って消耗する悪循環が続きました。数年前、動悸と不眠が強まり心療内科で軽度のうつ病と不安症の併存が指摘され、睡眠導入薬とSSRIを短期的に使用しつつ、紹介で当室にカウンセリングを申し込むことになりました。
面接では、セラピストの気遣いさえ刃物のように痛むことがあり、まずは「優しさに触れると体のどこがどう反応するか」を言語化し、同意と選択を明確にしながら関わりの速度を調整しました。Aさんは、褒め言葉を受け取ると肩がすくみ呼吸が浅くなる一方、断ると見捨てられる恐怖が立ち上がることに気づき、優しさ=支配、断る=関係破綻という家族由来の連想を丁寧にほどいていきました。並行して、境界の練習、マイクロ・エクスポージャー(小さな援助を受け取り、その後に感覚を確かめる)、自責の自動思考を書き換える作業を継続しました。さらに、面接内でセラピストが意図せず与える温かさが苦痛を招いた場面をその都度検討し、関係の中で起こる安全な再体験として扱いました。
数年のプロセスを経て、Aさんは「優しさは私を縛る合図」から「選べる資源」へと意味づけが変化し、援助を受けても反動で過剰奉仕せずにいられる時間が増えていきました。仕事では頼まれごとを一拍置いて検討できるようになり、睡眠も安定してきました。完全ではないにせよ、優しさの痛みは鋭利さを失い、必要なときに必要な援助を自ら選ぶ力が育ってきました。再発予防として、心身のしんどさが増す合図(肩こり、過呼吸気味、義務感の高まり)を早期に察知し、受け取る量とペースを調整する計画を作成しました。医師とは薬物療法を終了し経過観察に移行しつつ、必要時に連携を続けています。家族や同僚との関係でも「ありがとう」「いまは難しい」を両立させる言い方を身につけ、寄り添いを痛みではなく温度として感じられる瞬間が増えてきました。
苦痛となる肯定的な関係
カウンセリングというと、話を聴き、気持ちを共感し、思いを理解して、肯定的な関係を作っていく、という一般的なイメージがあるかもしれません。比較的健康なクライエントであれば、そうしたことによって整理され、前向きな気持ちになって前進することができるでしょう。しかし、一方で、そうした思いを聴く行為を侵襲と感じ、肯定的な関係や交流を苦痛と感じるクライエントもいます。
そうしたクライエントに親身さこそ正義とばかりに共感性や肯定的な関心を向けることによって、クライエントにとっては傷付きとなってしまうこともある、ということを知っていることは特に重篤なクライエントとのカウンセリングでは必要なことです。
Aさんは、人から優しくされたり褒められたりすると、心が温かくなるどころか強い緊張や居心地の悪さを感じました。特に職場での労いの言葉や配慮は「見返さなくてはならない」という圧力に変わり、過剰に頑張って疲弊してしまいました。
アセスメントの重要性
こうした重篤なクライエントのカウンセリングするためには、まずはアセスメントが必要です。そして、その上でのカウンセリングで何を目的にし、何を行うのかといった同意(契約)が必須となります。そして、意識的なニードだけではなく、無意識的なニードを把握することがカウンセリングの初期の作業になるでしょう。
こうした作業をいきなりすっ飛ばして、いきなりカウンセリングに入るのはリスクを孕んでしまいます。これまでのケース発表などを聞いていると、アセスメントと同意(契約)を有耶無耶にしたままカウンセリングをしているカウンセラーは結構多いように思います。
Aさんの場合、カウンセリング初期に「優しさが苦痛になる場面」「体の反応」「考え方のクセ」を丁寧に把握するアセスメントが行われました。これにより、無理のないペースで関係を築き、援助を安全に感じられるよう調整できました。
幼少期の傷つき
親密さを侵襲と体験する人は、全てではありませんが、多くは幼少期に発達にそぐわない環境からの侵襲を被っているように考えます。そのため、環境や周りの人間関係に対して信頼感よりも不信を持っています。そして、スキゾイド的な在り方や解離を用いて身を守らざるを得なくなります。もしくはピエロ的な振る舞いを通して、一見は社交的で明るいが、本質的なところでは人との関係を拒絶している人もおられます。
彼ら彼女らにとっては心を開くことは、すなわち外傷の反復という危機的状況に陥ってしまうため、不安と恐怖に駆られます。そのため、易々と人との関係を作るなんてことはできなくなってしまいます。せいぜい、仮面を作って、表面的な適応をし、本当の自分は隠して付き合う程度でしょう。
Aさんは、幼少期から母の期待に応える「良い子」として過ごし、助けられるよりも助ける役割を担ってきました。そのため、人からの親切を「借り」と感じ、甘えることに強い罪悪感を抱くようになりました。
心に占める空虚感
そうした防衛によって、社会生活はそこそこ送れたとしても、常に不安と空虚感が付きまとい、人生を生き生きと楽しめず、心があたかも死んでいるようになってしまいます。もしくは、死んでいるかのようにしか生きることができなくなってしまいます。世界は色あせ、虚しさが心を占めます。
いわゆるアダルトチルドレンと言われる方々にはこうしたことに当てはまる方が多いかもしれません。
アダルトチルドレンについての詳細は以下をご覧ください。
こうしたクライエントに親切心であっても無闇に近くことはただ単に不安を煽り、傷付きを深めてしまう結果となるだけでしょう。こうした意味で、精神症状は軽くても、非常に重篤な問題を抱えた対応困難なクライエントである、と言えます。そして、神経症レベルの健康度の高いクライエントとは違う対応や方法を弄することが求められます。そして、そうであると分かるためのアセスメント能力が必要となるのでしょう。
Aさんの場合、誰かに優しくされても心が満たされず、むしろ空虚感が広がる感覚がありました。カウンセリングを通して、この空虚感が幼少期に十分に受け取れなかった安心感や承認欲求と関係していると理解し、少しずつ人とのつながりを安心して感じられるようになりました。
優しさを苦痛に感じることを相談する
こうした優しさを苦痛に感じることは人生を生きていく上で非常に困難が伴います。もし、「優しさを苦痛に感じる」ことがつらいと感じているなら、その苦しさには必ず「理由」があります。私たちのカウンセリングでは、まずあなたの幼少期の体験、無意識のニーズ、自分を守ろうとしてきた防衛の仕方などを丁寧に見立て、その上で「優しさ」を安全に、あなた自身が選べる資源として取り入れていく道を一緒に探していきます。今感じている違和感や痛みも、「あなたがこれまで耐えてきたもの」の証です。それらを一人で抱え込まず、一歩踏み出してみませんか?対話の中で、自分を取り戻す感覚がきっと見えてくるはずです。
専門家の方へ
「優しさが苦痛になるクライエント」への関わりは、支援者にとっても迷いや戸惑いを伴いやすいテーマです。共感が逆に負担となったり、関係調整が難航する場面では、専門的な視点からのスーパービジョンが有効です。ケースの背景理解や介入のタイミング、セラピスト自身の感情への気づきを一緒に整理し、安全で創造的な支援へつなげてみませんか。