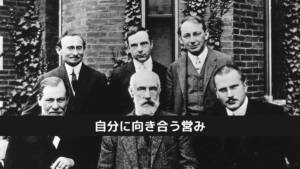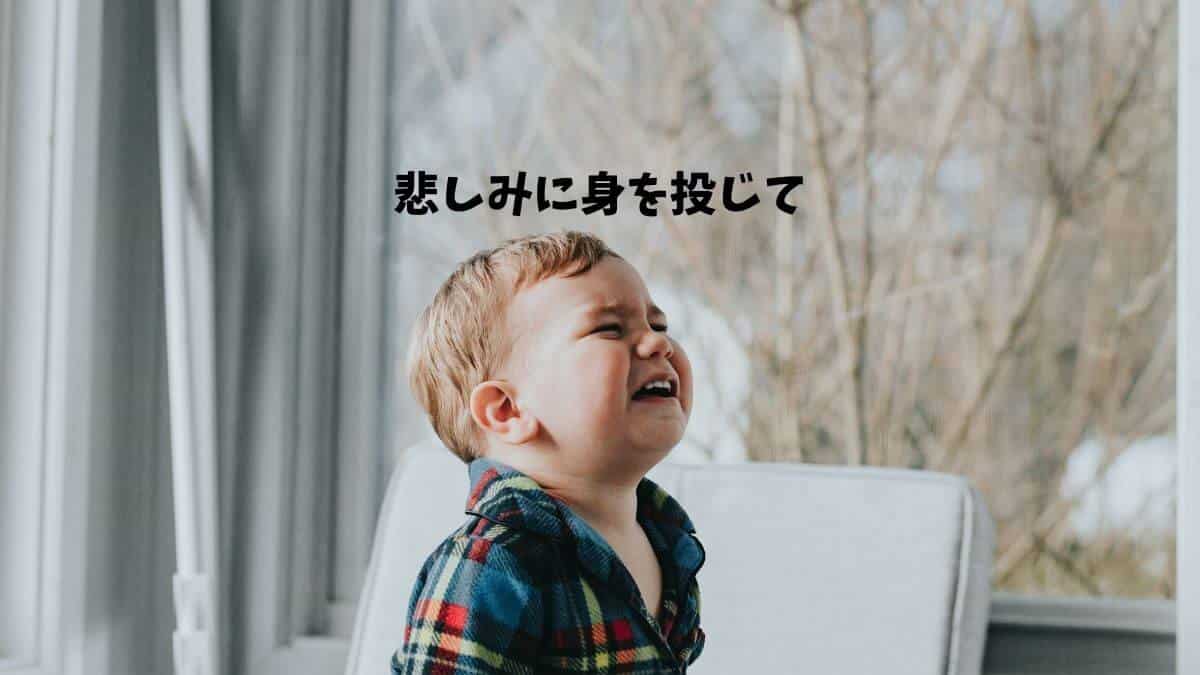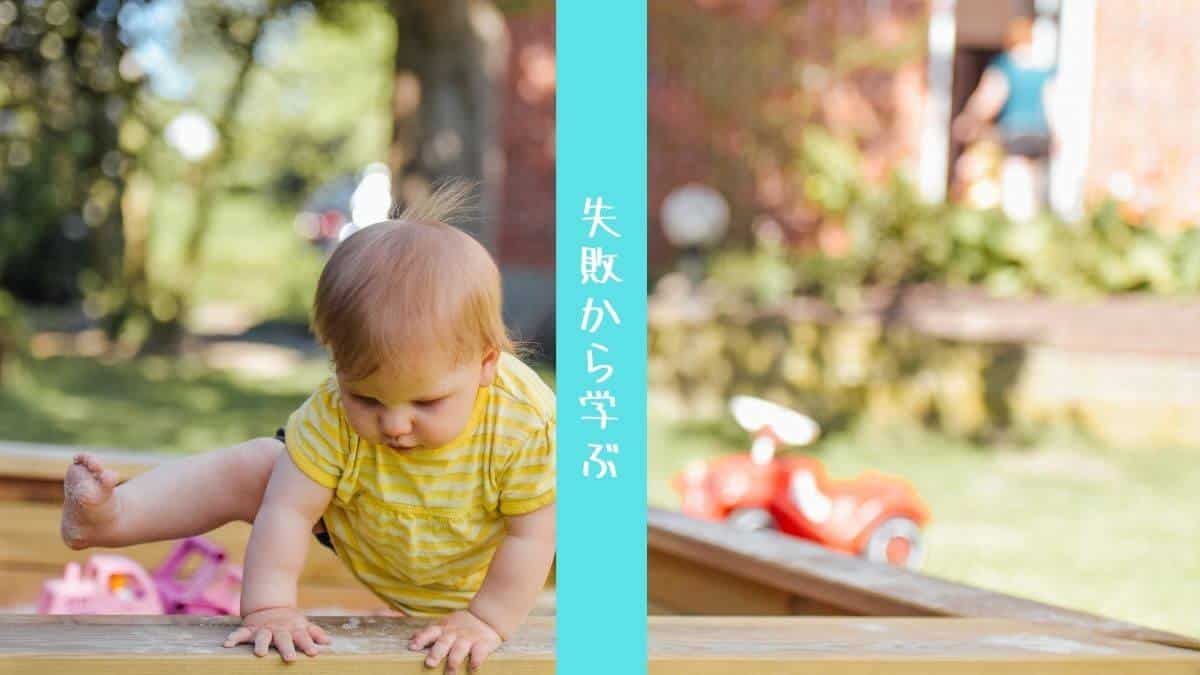ナルシシズムの導入にむけて

S,フロイトの1914年の論文「ナルシシズムの導入にむけて」についての要約と解説です。フロイトはナルシシズムの概念を作ることにより、その後の重篤な病理の解明に重要な手がかりを残しました。
目次
ナルシシズムの導入にむけて(1914)の要約
(1)一次ナルシシズムから二次ナルシシズム
Kraepelinの早発性痴呆(Dementia praecox)やBleulerの精神分裂症(Schizophrenie)、パラフレニア患者(Paraphreniker) をリビドー理論で理解しようとした。
a.パラフレニアの特徴
- 誇大妄想
- 外界の人物や事物からの関心の離反
2つ目の特徴が精神分析の影響を届きにくくする。
ヒステリー患者や強迫神経症者は外界の人物や事物へエロティックな関係は失っていない。パラフレニアは現実の対象を自己の空想によって補充するか、両者(現実と空想)を混同している。
b.二次的ナルシシズム
精神分裂病においては、対象から撤収されたリビドー(対象リビドー)が自我へと供給され、自我リビドーとなることで誇大妄想が生じ、これがナルシシズムの特徴として現れる。つまり、対象へのリビドーの割り当てを内に取り込むことによって二次的なナルシシズムが形成されるのである。フロイトは「自我リビドーと対象リビドーの間には対立があり、一方が増えれば他方は減少する」と述べ、対象リビドーの最高の発展段階を恋着とし、これに対立するものとして偏執病者が抱く世界没落の空想を挙げている。
c.この仮説に伴う論点
ナルシシズムと自体愛の関係については、自体愛が原初的なものであり、ナルシシズムが成立するためにはその自体愛に新たな心的作用が付け加わることが必要とされる。リビドーの一次的な割り当てが自我であるとすれば、性的リビドーと性的でない自我欲動とを区別する必要があるのかという問いが生じるが、フロイトは純粋な感情転移神経症(ヒステリーや強迫観念)の分析を通じて、自我リビドーと対象リビドーがそれぞれ自我欲動と性欲動に基づくものであることを見いだした。
フロイト自身は「まずなんらかの仮説を立てて、それが役に立たなくなるか、あるいはその正しいことが証明されるまで徹底的に吟味する」と述べ、まだ十分に説明しきれない段階にあっても、自らの理論を前提に議論を進めようとした。また、この姿勢に対してユングは、リビドー理論を否定するのは誤りであるとの趣旨で批判を加えている。
(2)ナルシシズムの具体例
ナルシシズムの理解のために、器質性疾患、ヒポコンデリー、両性間の愛情生活を観察することが必要。
a.器質性疾患
病気で苦しむ人、痛苦に耐えている人。このような人はリビドーを愛の対象から引き上げて、自我に引き戻している(二次的ナルシシズムの達成)。
睡眠中の状態もリビドーが自己自身に向かっており、ナルシシズム的に引っ込められている。
b.ヒポコンデリー
関心とリビドーを外界の対象から引っ込めて、両者を自分が気を取られている器官に集中させる。
c.器質性疾患とヒポコンデリー の違い
両者の違いは、実際に器官の変化があるか否かにあるとされるが、ヒポコンデリーにおいても器官の変化が認められるのではないかという疑問が生じる。病的な状態ではないにもかかわらず、特定の器官に過敏で苦痛を伴う状態として、たとえば興奮状態にある性器が挙げられる。ヒポコンデリーは自我リビドーに大きく左右され、そこで生じるヒポコンデリー不安は自我リビドーに由来する神経症的な不安である。苦痛として扱いきれない大きな感情が生じ、これを直接外部へ放出できない、あるいは放出することが望ましくない場合には、興奮は内部で転向される(内的加工)。この転向は実在の対象に対して行われることもあれば、想像上の対象に向けられることもある。そして、この反応のあり方の違いこそが、強迫神経症とヒポコンデリーとを分けるものとなる。
d.パラフレニア
パラフレニアにおける誇大妄想は、自我に回帰したリビドーが積み重なり病原となることで、周囲から病気として認識される。ここではリビドーの所在が自我と対象のどこに位置するかによって、病系を三つのグループに分けることができる。
第一は正常性を保持しているか、あるいは神経症を示すグループで、いわば残存現象として理解される。第二は疾患の進行過程を示すグループであり、リビドーが対象から離脱した状態に対応し、誇大妄想、ヒポコンデリー、感動障害、あるいは広範な退行といった症状が含まれる。第三は回復を示すグループで、ヒステリー(早発性痴呆や真性パラフレニアの場合)や強迫神経症(パラノイアの場合)において見られるように、リビドーが再び対象に付着する過程が含まれる。
この新たなリビドーの割り当ては、一次的な割り当てとは異なる水準から開始され、正常な自我形成との差異は、心的装置の構造をより深く理解するための重要な手がかりとなる。
e.人間の愛情生活
人間は自己自身と世話をしてくれる女性という二つの根源的な性対象を持ち、それによってすべての人間が一次的ナルシシズムを備えていることになる。男性においては、依存的な対象愛は本来的に男性的特徴とされ、小児期のナルシシズムに由来し、性対象へのナルシシズムの転移として現れる。恋着は神経症的強迫を思わせる独特の状態であり、その原因は対象のために自我のリビドーが乏しくなることにある。
一方で、女性は思春期に性器の発達に伴って対象愛を構成しにくくなり、とりわけ美しくなる女性は自己満足を抱くようになる。その結果、男性が女性を愛するのと同じ強さで自分自身を愛することになり、女性の対象愛は出産後に子どもに対して初めて形成される。さらに親となることで、人は子どもを通してナルシシズムを満たし、両親の愛情とは過去に抱きながら満たされなかったナルシシズムが再生したものであるといえる。
(3)男女間・親子間の愛情について
ナルシシズムは幼児の自我と同様に、あらゆる完全性を備えて存在している。しかし成長に伴い、その完全性を維持することは困難となり、人は自我理想(Ichideal)の中に再び完全性を獲得しようとする。自我理想は欲動を昇華したものではなく、自我の要求を高め抑圧を引き起こす機能を持つ。これに対して昇華は抑圧を生じさせない点で異なる。また、現実の自我を絶えず観察し、理想に合致させようとする特殊な心的法廷の働きが想定される。
このような働きは注意妄想や観察妄想として発現し、患者は自らの考えがすべて他者に知られていると感じ、観察されていると受け取る。さらに、それはしばしば人の声によって知らされ、常に三人称で語られる。「今、彼女はまたあのことを考えている」といった形でである。
自我感情とナルシシズム的リビドーは緊密に関連しており、その強弱は精神病理において異なる様相を示す。たとえば、パラフレニアでは自我感情が高いが、感情転移神経症ではむしろ低い。愛情生活においても、愛されることは自我感情を高め、愛されないことは逆にそれを低下させる。
さらに、愛する対象への依存は自我感情を低下させる側面を持つ。恋着においては自己のナルシシズムの一部が喪失されており、それは愛されることで補償される。恋慕の本質は、自我リビドーが対象へと溢れ出すことであり、性的理想はしばしば代償的満足として機能する。人は自分がかつてそうであったもの、あるいは喪失してしまったもの、さらには一般に所有されていないものを愛するようになる。
しかし、対象にリビドーを割り当てることで自我が貧困となると、自我理想を実現できなくなった神経症者は、自分では達成できないような長所を備えた性的理想を選び取ることになる。こうした恋愛体験は、しばしば「恋愛による治癒」として作用するのである。
(4)感想
リビドーを自我に引き戻して、二次的ナルシシズムが成立した状態がパラフレニア患者であるという考え方は、とても興味を引くものであった。
一方、自我にリビドーを引き戻さざるをえない現実的な背景が患者側にもあるだろうと思うが、その点の説明が曖昧なので、もっと例を挙げて欲しかったなとは思う。対象にリビドーを割り当てた状態(恋愛しても)でも適応的に行動している人はたくさんいる。対象にリビドーを割り当てて自我が乏しくなっていく人は、どこが違うのか。
ナルシシズムの導入にむけて(1914)の解説
(1)ナルキッソスの物語
ナルキッソスはアフロディーテからの贈り物を侮蔑したことで、愛してくるものを拒絶してしまう罰を受けた。ナルキッソスに恋をしたエコーはナルキッソスから拒絶され、悲しみのあまり死んでしまい、声だけが残り木霊となった。
そのことでナルキッソスはネメシスからの怒りをかい、自身しか愛することができないようにさせられた。ナルキッソスは水面に映った自らの姿に恋をし、水に落ちて死んでしまった(離れられなくなり餓死をしたというエピソードも)。ナルキッソスが死んだ後には水仙(Narcissus)が咲いていた。
(2)ナルシシズム概念の成り立ち
H,エリスが自体愛の男性例を報告する際にギリシア神話のナルキッソスを引用したのが最初と言われる。その後、P,ネッケが性倒錯の一種として定義した。
S,フロイトは1910年の「性欲論三篇」の補注と「レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期のある思い出(1910)」でナルシシズムに言及した。シュレーバー症例において、リビドーが対象から撤収され、自己に向かう状態について論じた。「自我とエス(1923)」では乳児の初期状態としての一次ナルシシズムを詳しく論じた。
ナルシシズムは自己愛self-loveではなく、もっと広い概念である。リビドーの撤収や他者との関係を隔絶し、自己の中にひきこもることを含めている。
(3)一次ナルシシズムと二次ナルシシズム
一次ナルシシズムとは、乳児が子宮内で体験するありようを原型にし、外界との関係がまだ成立しておらず、自我やエスが未だに未分化な状態のことである。対象関係が生じる以前の時期、もしくは、他者や外界に未だリビドーが備給されていない時期ともいえる。睡眠はこの一次ナルシシズムの再現であるといえる。
二次ナルシシズムは、一度は対象との関係が成立し、リビドーが対象や他者、外界に備給されていたが、何らかの理由で、リビドーを撤収し、自己に向けかえた状態のことである。対象関係からの退行であるともいえる。パラフレニーが、リビドーをさらに外界に向けなおそうとする修復企図のプロセスの中で、それが病的な形となり、妄想や幻覚といった陽性症状として惹起される。
(4)自己愛神経症に対するフロイトの見解
S,フロイトは精神分析が可能なヒステリー、強迫神経症を転移神経症とした。それに対比させ、リビドーが自己に向き、転移をおこさないか、非常に困難であるため精神分析ができない疾患として、自己愛神経症を定義した。この中にはパラフレニー、心気症、メランコリーなどが含まれる。
転移神経症では対象リビドーが抑圧されているが、その性質は保たれているため、退行を通して緩むことによって転移が十分に展開するとした。一方で、自己愛神経症では、リビドーが自我に供給されており、そうしたリビドーが再度対象に向かうことは困難であるとした。そうなると分析家との間で転移が展開することは非常に難しいとS,フロイトは考えた。
(5)ナルシシズムの転移と、その障害に対する分析技法1
この一次ナルシシズムを認めるのか認めないのかで技法面が大きく左右される。
一次ナルシシズムの存在を認め、その上で技法形成を行っているのが、A,フロイト、M,マーラー、D,W,ウィニコットなどである。
M,マーラーは正常な自閉期という概念で一次ナルシシズムを論じた。発達段階として、自閉期の後に、共生期、分離個体化期(分化、練習、再接近、個体化)、対象恒常性確立期が続く。
D,W,ウィニコットは一次ナルシシズムを絶対的依存の時期としている。対象は無く、望めばそれがすぐに実現される魔術的な世界である。母親は対象ではなく、環境として機能している(ホールディング)。そうしたありかたは、母子ユニットと言われる。母親は原初的没頭により乳児の世話をする。しかし、成長するにつれ、母親の世話が失敗し、乳児の万能的な世界は侵襲される。
その侵襲が適度なものであれば、世界は魔術的でも万能でもないことを知り、脱錯覚へと導かれる。侵襲が過度で、外傷的であるならば精神病的不安が刺激され、存在そのものが危機にさらされ、絶命の苦痛となってしまう。技法的には、患者がナルシシズムの状態に陥ると、解釈といった関係や交流の中で成長を促進させるのではなく、ホールディングによる世話をすることが優先される。
ちなみに、D,スターンの臨床乳児研究や、神経生物的な発達研究から、乳児は出生直後から活発に環境からの情報を摂取し、環境に働きかけ、心的交流を持とうとしているという知見が提起されている。つまり、一次ナルシシズムを否定する見解である。
(6)ナルシシズムの転移と、その障害に対する分析技法2
一次ナルシシズムを否定・批判している分析家はW,R,DフェアバーンやM,クライン、その後のクライン派グループなどである。
W,R,Dフェアバーンは死の本能ではなく、対象希求性を根本に置いた。
M,クラインは「分裂的機制についての覚書(1946)」において、投影同一化や妄想分裂ポジションを定式化し、「羨望と感謝(1957)」においては、死の本能のあらわれである羨望を定式化した。これらは一次ナルシシズムを否定し、原初からの対象関係を明確に打ち出したものと言える。
クライン派グループによると、乳児は出生時より対象関係は成立しており、活発な交流が存在しているとしている。また、転移とは内的対象の外在化であるため、接触直後から活発に活動しているとされている。そのため、分析開始当初から、内的空想についての解釈を積極的に行うことが多い。そこには、転移が生じないということではなく、ナルシスティックな転移、もしくは精神病的な転移が生じていると理解している。W,R,ビオン、H,シーガル、H,ローゼンフェルトなどの統合失調症の精神分析の貢献により、精微化されていった。
(7)自己愛構造体・病理的組織化
S,フロイトは「自我とエス(1923)」の中で死の本能との関連で、陰性治療反応について論じた。これは症状が軽快しようとすると無意識的罪悪感が刺激され、反対に悪化してしまう事態を説明するために導入された。S,フロイトは超自我との関連で論じ、クラインは羨望との関連で論じた(1957)。J,リビエールは「陰性治療反応への寄与(1936)」において、パーソナリティの中にある構造化された躁的防衛システムとの関連で論じた。
これらを踏まえ、H,ローゼンフェルトらが、羨望の影響下において、ナルシシズムを中心として、様々な苦痛から防衛するために、高度に構造化された自己愛的な構造体を構成し、その中に逃避する様を論じた。破壊的ナルシシズムという。これは破壊性や攻撃性が理想化され、健康な自我の部分を脅迫し、コントロールし、支配する。
普段は目立たないが、人格そのものをのっとり、裏から支配している。現状維持が目論まれ、変化することや成長することが危険なことであると認識し、そのような事態になりかけると陰性治療反応が発動し、もとの状態に戻してしまうのである。このような自己愛構造体が維持されている限り、抑うつ的な苦痛を乗り越え、抑うつポジションを達成することを妨げられてしまう。同時に、妄想分裂ポジションからの不安からも防衛することができ、一種、嗜癖的にその状態に沈殿し、倒錯的な満足を得ようとする。
J,シュタイナーは自己愛構造体の概念を整理し、妄想分裂ポジションと抑うつポジションに対する防衛的側面を強調した。そして両ポジションの間に第3のポジションとして、病理的組織化を置いた。これら3つのポジションの変化を好まない平衡状態を維持することが目的となっている。
さいごに
さらに精神分析について興味のある方は以下のページを参照してください。
参考文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。