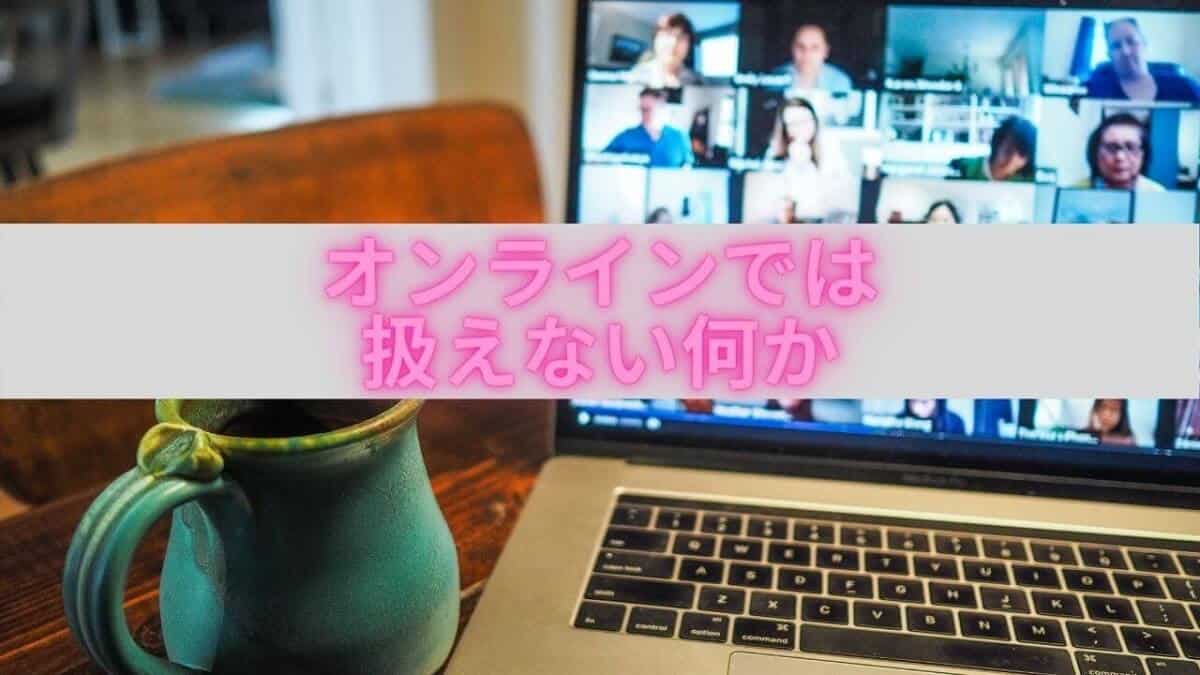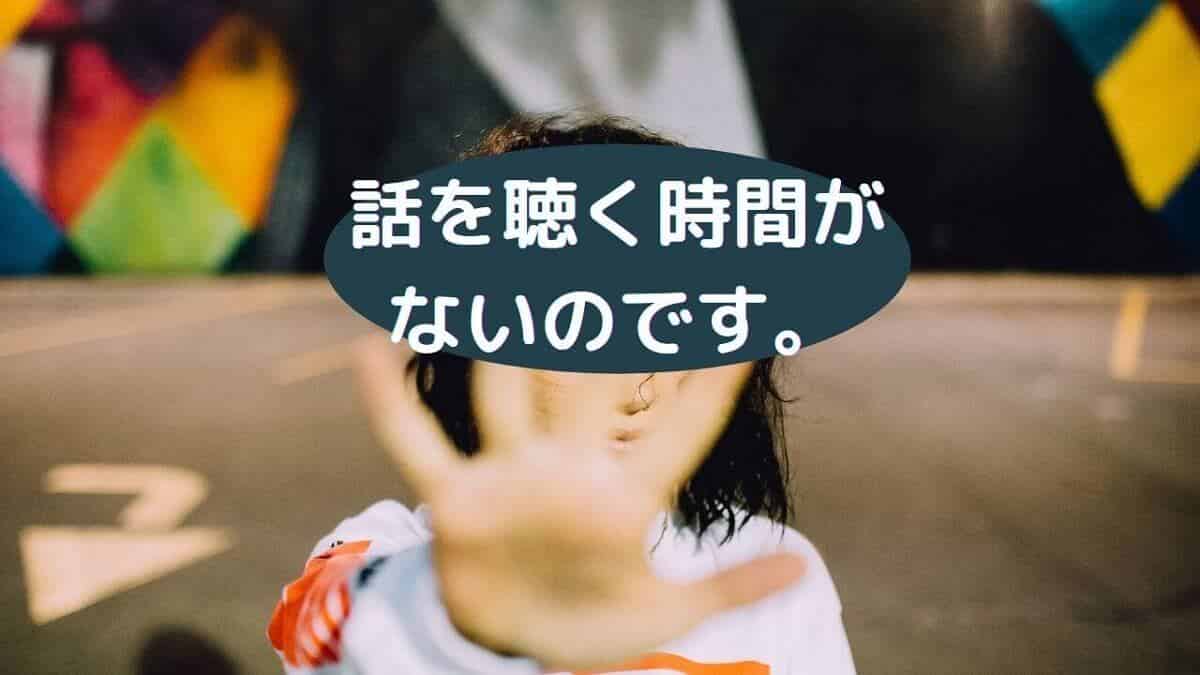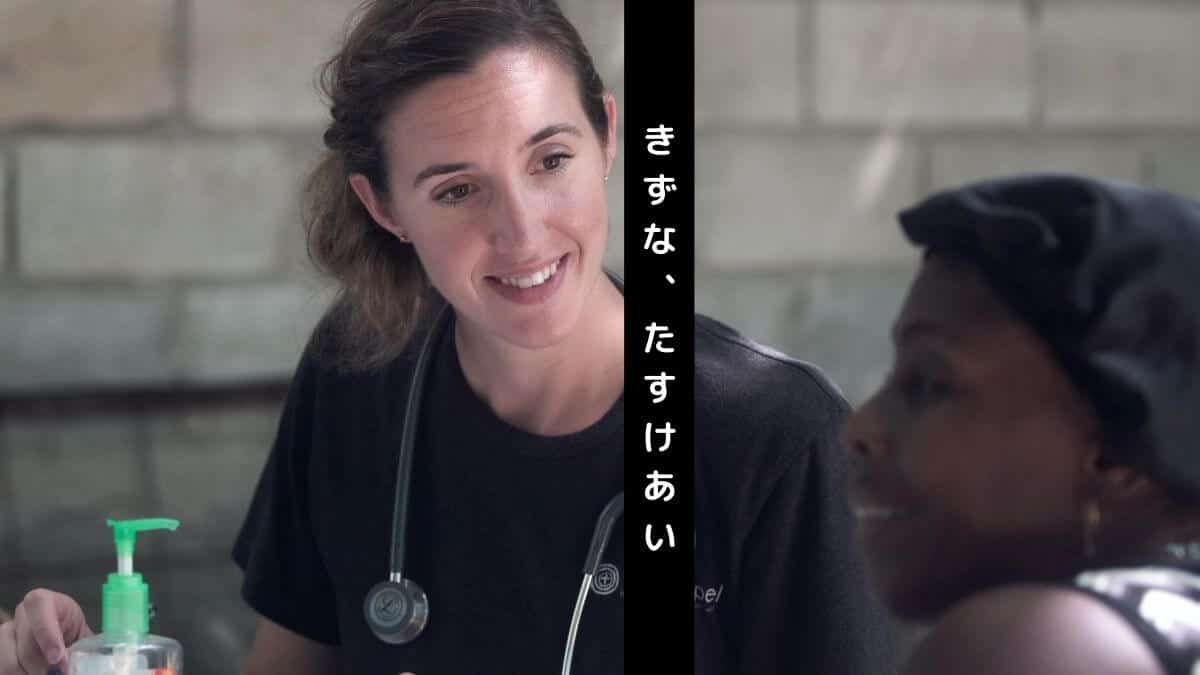自閉症という物語り

自閉スペクトラム症の病理について、単に診断基準や行動特徴から語るのではなく、心理臨床において重要とされる「物語」と「逆転移」という二つの視点から改めて捉え直してみました。それにより、症状の理解だけでは見えてこない心のあり方に光を当ててみようと試みました。
目次
自閉症・自閉スペクトラム症とは

自閉症・自閉スペクトラム症(ASD)は、生まれつきの脳の特性によって、社会的なコミュニケーションの難しさや、行動や興味の偏り、感覚の過敏さや鈍さなどが見られる発達特性です。人との距離感をつかむことが苦手であったり、暗黙のルールを理解しにくいことから誤解を受けやすく、学校や職場で孤立することも少なくありません。また、予定の変更や予測できない出来事に強い不安や混乱を抱えやすい特徴もあります。
一方で、特定の分野に強い集中力や優れた能力を発揮する人も多く、適切な理解と環境調整があれば、その人らしい力を伸ばすことができます。カウンセリングの場では、単なる問題解決にとどまらず、精神分析的な視点を用いながら「物語」としてその人の体験を受け止め直すことも大切です。言葉にならない苦悩や孤独を物語化して照らし返すことにより、自分の歩んできた人生に意味を見出し、安心して生活できる基盤を整えていく支えとなります。
自閉スペクトラム症については下記に詳しく書いています。
よくある相談の例(モデルケース)
20歳代 男性
Aさんは20歳代の男性で、幼少期から人との関わりにぎこちなさが見られました。幼稚園では友だちの輪に入ることが難しく、一人で積み木や絵本に集中して過ごす時間が多くありました。小学校に入ると、先生の指示を理解するまでに時間がかかったり、曖昧な言葉に混乱することがありました。また、強いこだわりがあり、予定の変更や急な出来事に対応できず、パニックを起こすことも少なくありませんでした。周囲の子どもたちからは「わがまま」と誤解され、孤立することが増えていきました。
中学・高校に進むにつれて学習面では得意不得意が極端に分かれ、興味のある理系分野には深く没頭する一方で、国語や社会では曖昧な記述を理解できずに成績が振るわないこともありました。友人関係も長続きせず、「人とうまく関われないのは自分のせいだ」と自己否定感を強めていきました。大学に進学したものの、グループワークやゼミでの対人関係が大きな負担となり、体調を崩して休学に至りました。その過程で精神科を受診し、自閉スペクトラム症と診断されました。
服薬によって不安はある程度落ち着いたものの、根本的な対人関係の難しさや自己理解の不足は残っており、Aさんはカウンセリングを申し込みました。初期の面接では、沈黙が多く、カウンセラーにどう話せばよいか分からず戸惑う姿が目立ちました。カウンセリングを進める中で、Aさんは少しずつ自分の特性について理解を深め、失敗や混乱は性格の弱さではなく、発達の特性から生じていることを受け止められるようになっていきました。
数年にわたるカウンセリングの中で、Aさんはまず安心できる関係を築き、「自分のまま話しても受け入れられる」という体験を重ねました。その後、日常生活で起こる困りごとを具体的に検討し、スケジュール管理や人とのやり取りで役立つ工夫を取り入れていきました。さらに、自分の特性をオープンにすることで周囲の理解を得る経験を積み、職場での小さな成功体験につなげることができました。
現在では、Aさんは以前ほど対人場面を恐れることなく、無理のない範囲で人間関係を築けるようになっています。困難さが完全に消えたわけではありませんが、自分を責めることが減り、特性を前提に工夫して生きる姿勢を持てるようになりました。
自閉スペクトラム症理解の科学的進歩
自閉スペクトラム症の神経生物学的な解明は、近年めざましい進展を遂げています。脳の構造や機能に関する研究が進み、社会的認知や感覚処理、注意の特性に関わる神経回路の違いが少しずつ明らかになってきました。たとえば脳画像研究では、扁桃体や前頭前野の働き方が独特であること、感覚刺激に対する過敏さや鈍さが神経レベルの情報処理の違いに関連していることが報告されています。また、遺伝的要因や神経発達のメカニズムに関する研究も進み、発達早期からの特性理解に役立てられつつあります。
こうした知見の積み重ねは、社会での「合理的配慮」をどう行うかという実践に直結しています。学校や職場では、曖昧な指示ではなく明確で具体的な言葉を使うこと、環境の刺激を減らすこと、予定変更の際には事前に予告することなど、脳の特性に基づいた支援方法が検討されるようになりました。従来は「努力不足」とされがちだった困難が、神経生物学的な理解を背景に「特性として当然のこと」と見なされ、制度として支援される方向に変わってきています。
さらに、支援技術の面でも大きな進歩があります。IT技術を用いたスケジュール管理アプリや視覚的支援ツール、ソーシャルスキルトレーニングのデジタル教材などが開発され、日常生活に取り入れやすくなっています。コミュニケーションを補助するためのAAC(補助代替コミュニケーション)機器や、感覚過敏に対応したノイズキャンセリング機器なども実用化が進んでいます。これらの技術はまだすべての人に十分行き渡っているわけではありませんが、十数年前と比べれば格段に進化しており、生活の質を高める可能性を広げています。
Aさんは、自閉スペクトラム症の理解が神経生物学的に進歩してきたことで、周囲から「合理的配慮」を受けやすくなり、以前より学校や職場での困難が少し軽減されるようになりました。
自閉スペクトラム症に特異的な逆転移
一方で、自閉スペクトラム症のクライエントと関わる際には、特有の心的世界に触れることになります。それはしばしば、豊かな感情や物語性が乏しく、無機質で平面的な印象を与える心のあり方として表れます。まるで心が二次元的に切り取られているかのように感じられ、背景にある文脈や物語が織り込まれていないように見えるのです。そのため、カウンセラーは手の届かない感覚に直面し、温かさや深みを感じにくい逆転移を抱くことがあります。これは臨床家にとって、無力感や距離感を強く感じさせる体験となりがちです。
神経生物学の進展は、自閉スペクトラム症の脳機能や神経回路の特徴を明らかにし、社会的認知や感覚処理の違いを理解する上で大きな助けとなっています。しかし、そうした科学的知見が、面接の場でカウンセラーが体験する「無機質さ」に直接的な彩りを与えてくれるわけではありません。むしろ時に、カウンセラーが感じる空虚さや孤立感を説明で覆い隠す「否認」の手段となってしまうこともあります。知識が豊かであるほど、体験を生きることを避けてしまう危険性があるのです。
精神分析的視点から見ると、こうした逆転移には重要な意味があります。Bionは「コンテイン」という概念で、クライエントが処理できない生の感情をカウンセラーが一時的に引き受け、消化して返すことの大切さを説きました。しかし、自閉スペクトラム症のクライエントと関わるとき、カウンセラー自身が「何も受け取れていない」「中身が空っぽである」と感じることがあります。これは実際には、クライエントが伝えようとしているものが言葉にならず、未加工のまま漂っているために生じる体験とも考えられます。Meltzerは、このような無機質さや空虚さを、クライエントの世界の一部として理解し、そこに意味を見出す努力が必要だと指摘しました。
このような逆転移を理解するためには、教育分析や個人分析を通じて自分自身の反応を見つめ直し、スーパービジョンを通して他者の視点を取り入れることが欠かせません。カウンセラーが無機質さや拒絶感をただの「壁」として体験するのではなく、それをクライエントの心の表現の一部として受け止めることができるとき、初めてその関係性に奥行きが生まれます。
こうしたプロセスは簡単ではなく、時に耐え難いものです。しかし、逆転移に耳を傾け、そこから学ぶ姿勢を持ち続けることで、無機質に見える心の奥に潜む豊かさや意味を少しずつ理解できるようになります。そしてそれこそが、自閉スペクトラム症のクライエントと関わるカウンセリングを深め、臨床の可能性を広げていく営みなのです。
Aさんの場合、感情表現の少なさや独特の対人スタイルが、カウンセラーに「無機質で距離がある」という逆転移を引き起こしました。カウンセラーはその体験を通じて、Aさんの内面世界の特異性を理解する契機を得ました。
物語の生成
自閉スペクトラム症の方にとって、自分の体験や感情を物語として言葉にすることは容易ではありません。出来事が断片的に記憶され、心の中でつながらないまま残ってしまうことも多くあります。そのため、出来事の意味づけや因果関係が曖昧で、人生の流れを物語として捉える感覚が希薄になりがちです。こうした「物語れない物語」を、カウンセラーが面接の中で受け取り、自らの心の中でつなぎ合わせ、仮の物語として形にしていくことがあります。この作業は、単に理解を示すためではなく、クライエントの断片的な体験に光を当て、その背後に潜む感情や関係性を見える形にして返す営みです。カウンセラーのこうした「照らし返し」が、クライエントの心の中に小さな物語の萌芽を芽生えさせるきっかけになります。
やがて、その物語はクライエントにとって、自分と世界との関わりを理解するための枠組みとなり、ばらばらだった出来事の中に辻褄や意味を見出す助けとなります。自分がなぜ苦しいのか、なぜ人とうまくいかないのか、あるいはなぜ特定の状況で不安が強まるのか、といった問いに対し、一貫した筋道を与えることができるのです。物語が持つ力は、混沌とした体験に秩序を与え、理解可能なものとして心に位置づけ直すことにあります。
しかし、ここで生まれる物語が必ずしも心地よく、肯定的なものであるとは限りません。世界は必ずしも優しくはなく、理不尽で残酷な現実が常に存在します。人の悪意に傷つけられることもあれば、努力が報われずに終わることもあります。挫折や失敗は避けられず、時に生きることそのものが重荷に感じられる場面もあるでしょう。そのような現実を無理に美化したり、希望的な物語にすり替えるのではなく、苦しさや理不尽さを含めて物語の中に取り込むことが大切です。物語は慰めであると同時に、世界の厳しさを受け止める容器でもあるからです。
カウンセラーがクライエントと共に紡ぐ物語は、そのような残酷さや不条理も抱え込みながら、なお「生きる意味」を見出す営みへとつながっていきます。物語化の過程は、光と影の両面を持ち、決して一方向的な癒しではありません。それでも、断片のまま放置されていた経験を言葉と物語に変えることは、クライエントが世界と自分を結び直し、少しずつ自分自身を理解し直すための大切な一歩となるのです。
Aさんは、カウンセリングで自身の体験を少しずつ言葉にすることで、断片的で平面的だった出来事に物語性が芽生え始めました。その過程で、自分の過去を新たに意味づける感覚が生まれました。
自閉スペクトラム症の哀しみ
その哀しみは、表面的な悲しみではなく、心の奥底に沈殿し、時に言葉を超えて感じ取られるほど深いものです。その哀しみを抱えながら生きていくことは、絶えず苦悩を伴い、未来に希望を描こうとするときにも過去の痛みに引き戻されるような体験を繰り返します。苦悩に満ちた歩みは、常に「後戻りしたい」という甘美な欲望と隣り合わせであり、その誘惑は安全で馴染みある場所に戻るような感覚を与えるため、とても強力です。しかし、その誘惑に身を委ねれば、一時的な安らぎは得られるものの、前に進む機会を失ってしまいます。したがって、その哀しみを引き受けながら進んでいくことは容易ではなく、大きな勇気と支えを必要とする営みなのです。
これは決して自閉スペクトラム症に限った体験ではなく、人が深い傷や喪失を抱えたときに共通して生じる苦しみでもあります。しかし、自閉スペクトラム症をもつ人の場合、その体験はさらに強烈で切実なものになりやすいと想像されます。対人関係の理解や感情の処理の難しさがあるために、哀しみが心の中でうまく言葉や物語に変換されず、むしろ断片のまま強く残ってしまうことが多いのです。そのため、哀しみの重さを逃れられず、時に世界全体が理不尽で冷たいものとして映ることもあるでしょう。
それらを含み込んだ物語化は、確かに苦しく、簡単には成し遂げられない作業です。しかし同時に、それは人生の成熟そのものであり、人が根源的に求める営みであるとも言えます。物語化によって、断片化された体験や意味を持たない苦痛に秩序を与え、自分の人生を自分なりに理解し直すことが可能になります。哀しみを無理に消そうとするのではなく、それを抱えたまま語り直すことによって、自らの存在の厚みを実感できるのです。そうした作業は一見苦難に満ちていますが、その先にはより深い自己理解と人生の豊かさが広がっていると私は考えます。
Aさんは、周囲との誤解や孤立の経験を通して深い哀しみを抱えていました。その哀しみをカウンセリングで語ることは大きな苦痛を伴いましたが、同時に「苦しみを共に抱えてもらえる」という体験が、新しい一歩を支える力となりました。
カウンセリングを受けたい
自閉症や自閉スペクトラム症について、私たちは「物語」や「逆転移」といった視点からも理解を深めることができます。物語とは、自分の体験や感情に意味を与え、人生を一つの流れとして語り直す営みです。しかし自閉スペクトラム症の方は、その物語化が難しく、断片的な体験のまま残ってしまうことがあります。そのため、カウンセリングの中でカウンセラーが心の中に浮かぶ感情やイメージを受け止め、時に逆転移と呼ばれる複雑な感情を手がかりにしながら、クライエントの世界を丁寧に理解し直していくことが大切になります。
日常生活の中で直面するコミュニケーションや人間関係の困難さ、感覚の敏感さやこだわりへの対応など、具体的な課題に取り組む支援はもちろん重要です。しかし、それと同じくらい、表現されにくい苦悩や孤独感に寄り添い、一緒に向き合っていくようなカウンセリングも必要になる場合があります。その過程は時に苦しく、容易なものではありませんが、少しずつ自分の感情や経験に意味を見出すことで、生きやすさや安心感が育まれていきます。
(株)心理オフィスKでは、自閉症や自閉スペクトラム症をもつ方に対して、その人に合った方法でのカウンセリングを行っています。日常的な困りごとの相談から、深い心の問題への取り組みまで幅広く対応しています。希望される方は、以下の申し込みフォームからお気軽にご連絡ください。
スーパービジョンを受けたい
自閉症・自閉スペクトラム症のクライエントとのカウンセリングでは、日常的な支援の工夫に加え、関係の中で生じる逆転移や理解の困難さに直面することも少なくありません。そのような時に、一人で抱え込むのではなく、経験豊富なスーパーバイザーと共に振り返り、省察を深めることが専門家としての成長に大きく役立ちます。スーパービジョンは、臨床の安全性を高めるだけでなく、クライエント理解の幅を広げ、持続的な実践を支えるための大切な場です。
(株)心理オフィスKでは、自閉症・自閉スペクトラム症を含む幅広い臨床領域に対応したスーパービジョンを提供しています。ケースの具体的な検討から感情面への理解まで丁寧にサポートいたします。安心と自信を積み重ねたい方は、ぜひお申し込みください。