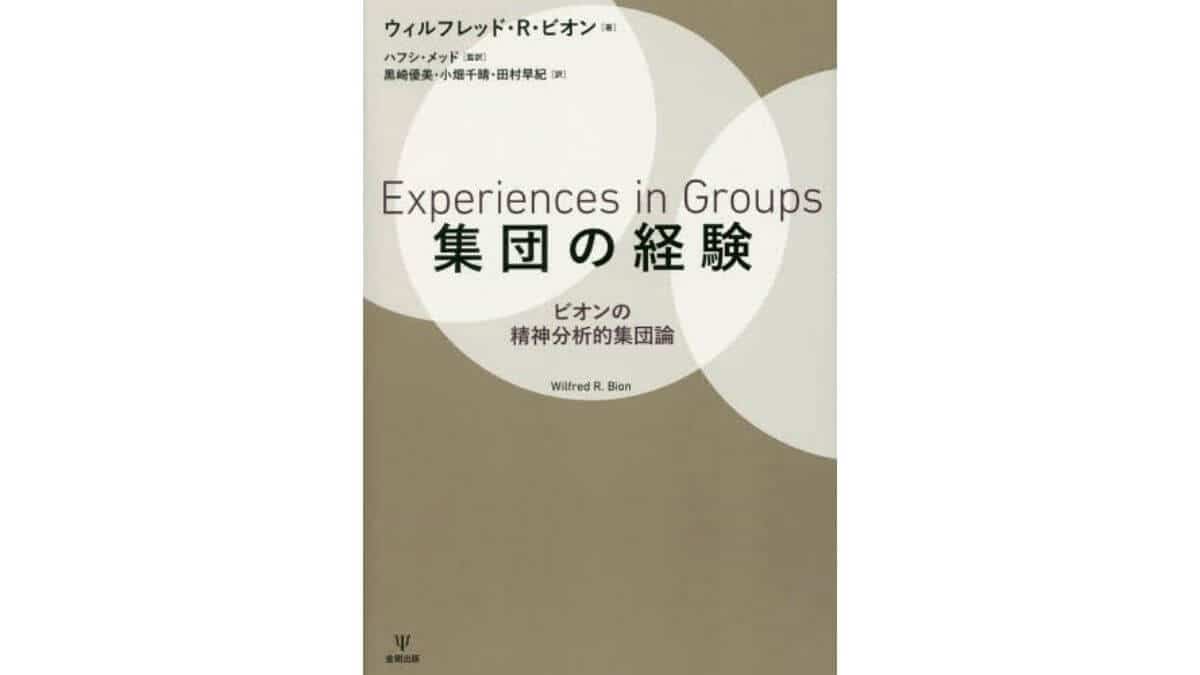子どもの心的発達

メラニー・クラインの1921年の論文「子どもの心的発達」についての要約と解説です。後年のように理論が整理されていないだけ、粗削りだが、非常にエネルギッシュで、独創性にあふれた論文です。

図1 メラニー・クラインの写真
目次
メラニー・クラインの生涯
1882年3月30日にウイーンで出生。父親であるモリツ・ライチェスは医師であり、文学にも詳しく、数ヵ国語を話す博識な人物であった。ただ、医師としては成功していなかった。父親の最初の結婚はうまく行かず、離婚となり、その後、クラインの母親となるリブサ・ドイチェと再婚した。結婚時、父親は47歳、母親は24歳であった。家計は母親がペットショップなどを営業し、その収入で暮らしていた。
兄弟は6歳上の姉エミリー、5歳上の兄エマニュエル、4歳上の姉シドニーである。上3人は年子で、クラインはそこから4歳も離れているが、もともとは計画にない、「予想外」にできた子どもであったという。また、母親の事業の関係で、上3人は母乳だったが、クラインだけは乳母に育てられた。母は愛情関係に疎く、しかし、過干渉的で、支配的な女性であった。
クラインが4歳の時、優しくて、算数などを教えてくれていた姉シドニーが肺結核のために死去した。シドニーは長い闘病生活であり、自身の死期が近いことをしっていたのか、知っていることをすべてクラインに託そうとしていたようであった。兄エマニュエルもクラインに対して優しく、またクラインの才能を認めていた。
エマニュエルは心臓病を患っており、非常に病弱であった。彼は医師を志すと同時に、芸術に深い関心があった。彼はクラインを色々なサークルに連れていき、見聞を広めさせた。そのサークルの中で、後にクラインと結婚することとなるアーサー・クラインと知り合った。
この時期、父親は既に認知症となっており、クラインが18歳の時に死去した。クラインは父や兄のように医師になることを希望していたが、経済的な問題のため、家庭の問題のため(姉エミリーの夫の暴力とギャンブル癖)、母や姉の勧めでアーサーと婚約した。しかし、その後すぐに兄も死去している。その兄の死の悼みが癒えないまま数ヶ月後に結婚し、家庭に入ることとなった。
結婚後のクラインは夫の仕事のため欧州各地を転々としていた。そして、22歳の時に長女メリッタを出産。メリッタは後に精神分析家となった。25歳の時に長男ハンスを妊娠中に酷いうつとなり、2年半の療養生活を送っている。1910年(28歳)の時にブタペストに移住。
クラインは結婚後、日に日に悪化するうつ病のため、ほとんど機能することができなくなり、家事や育児は他の家族やお手伝いに任せている状況であった。その折、夫が当時ブタペストで開業していたフェレンツィと個人的な知り合いだったことをきっかけにクラインはフェレンツィにうつ病治療のための精神分析を受けることとなった(1913年 31歳)。
そして、32歳の時に次男を出産し、その4ヶ月後に母親が亡くなっている。フェレンツィとの精神分析の中でフェレンツィはクラインの才能を見出し、精神分析家になることを勧め、クラインもインスティテュートで学ぶようになった。
そして、1919年に「誕生の状態における家族幻想」という論文を提出し、精神分析家となった。1921年に夫が仕事の都合でスウェーデンに行くこととなったが、それにはついていかず、別居となった。クラインはフェレンツィとの精神分析に物足りなさや不満を抱えており、その折、学会で知り合っていたアブラハムを頼ってベルリンに移住することとなった。
アブラハムはクラインに子どもの精神分析を勧めた。アブラハムは躁うつ病の研究から早期幼児期の攻撃性の探求に関心を向けており、クラインはそうしたことを実践してくれるのにちょうど良い人物であった。ベルリンに移住したクラインはアブラハムという良き指導者に恵まれ、また9歳下のジャーナリストであるクロツェルとの恋愛があり、しばらくは充実した生活であった。
またクラインは42歳からアブラハムの精神分析を受けるようになったが、18ヶ月という短い期間で、アブラハムの死をもって中断してしまった。アブラハムという後ろ盾がなくなり、ベルリンにいることが困難になっていた時期に、ジョーンズによってイギリスに招聘されて連続講義を行った。その講義に勇気づけられ、またジョーンズの子どもを精神分析するということでイギリスに移住することとなった(1926年 44歳)。
イギリスでのクラインはジョーンズに守られつつ、賛同者や弟子が徐々に増えていき、精力的に臨床実践と研究を行っていた。しかし、1933年頃から既に精神分析家となっていたメリッタ・シュミデバーグとエドワード・グラバーがインスティテュート内で公然とクラインを批判するようになり、また翌年の1934年には長男ハンスが登山中の事故で死亡するということもあった。この時の哀しみは非常に強く、クラインは酷い抑うつ状態に陥っていた。
1936年にはフロイトとその娘であるアンナ・フロイトがイギリスに亡命してきており、その前後からイギリス精神分析学会の中では論争が繰り広げられるようになった。その論争は時として感情的なものが含まれており、また娘であるメリッタもアンナ・フロイトの側に立っていたこともクラインにとっては非常な苦しみであった。その後、論争自体は収まっていったが、1951年にはウィニコットが、1955年にはハイマンがクライングループから離脱していったことはクラインにとっては喪失であった。
1960年の夏にクラインはスイスで休暇を取っていたが、突然吐血し、エスター・ビックがロンドンの病院に連れていった。そこで結腸癌が見つかった。9月に手術をし、それ自体は成功したが、その数日後にベッドから転落し、骨折をしたことで合併症を引き起こし、9月22日に78歳で死去した。
クラインからスーパービジョンや訓練分析をうけた精神分析家は多数おり、その一部を挙げると、スーパービジョンではウィニコット、ミルナー、ボウルビィが、訓練分析ではビオン、ローゼンフェルド、スィーガル、メルツァーなどがいる。ちなみにクラインが使っていたカウチはメルツァーが譲り受けたようである。
メラニー・クラインの生涯については以下の「子どもにおける良心の早期発達」からの抜粋です
クラインの理論
(1)早期幼児期の理論
フロイトは大人の中に幼児の心を見出した。→エディプス・コンプレックス
クラインは幼児の中に乳児の心を見出した。→早期エディプス・コンプレックス
フロイトは3~5歳ごろになりエディプスが完成し、その時点で心ができるとした。その為、それ以降ではないと精神分析は不可能であると結論した。
クラインは早期エディプスを見出し、フロイトが提示した3~5歳以前にも心はあり、それを精神分析していくことは可能であるとした。
(2)妄想分裂(PS)ポジション・抑うつ(D)ポジション
フロイトのような発達段階のモデルではない。常に移り変わる可能性のある心の中の二つの側面。
部分対象関係:破壊的な本能衝動。迫害的で被害的な心性。スプリッティングや投影同一化、否認といった原始的な防衛機制が優勢なPSポジション。
全体対象関係:喪や悲哀。思慕の情。罪悪感。神経症的な防衛機制の優勢なDポジション。
(3)プレイ・アナリシス
たくさんのおもちゃがあり、その中で楽しく遊ぶプレイセラピーとは全く別物である。
面接室にあるものは“洗える床、水道、テーブル、2~3の椅子、小さなソファとクッション、玩具収納のためのカギ付きの戸棚”だけ。その他に、その子ども専用のおもちゃ(ミニチュアや絵画セット)
「自由連想はプレイに匹敵する」→子どもと一緒に遊ばず、ただ子どものプレイを観察し、解釈する。
(4)転移/逆転移
クラインの転移の理解→「最早期段階において対象関係を決定づけていた過程と同じ過程の中で生まれる。そして、情緒、防衛、対象関係と同様に全体状況すなわち現在の状況と最早期の体験の間にある全て」。
患者の語られる空想は最初からすべて転移である。自我心理学のように徐々に発展するものではない。
逆転移は対象関係論学派やポストクライン学派のように利用するものではない。フロイトのいうようにすべてが精神分析家の病理なので、訓練分析で処理するもの。
子どもの心的発達(1921)の要約
第一部は1919年に「誕生の状態におけるファミリーロマンス(Der Familienroman in statu nascendi)」としてハンガリー精神分析協会にて発表されたものであり、クラインがその会員となる資格を得た論文である。第二部は1921年”Analysis of young children”あるいは”The Child’s Resistance to Enlightenment”としてベルリン精神分析協会にて発表されたものである。いずれも症例のフリッツはクライン自身の3番目の子どもエリック(1914年生まれ)である。
(1)性教育と権威の弱まりの子どもの知的発達に及ぼす影響
導入
精神分析によって得られた知見は、子どもがとても幼いころから「子どもの知識への欲望の成長が求めるに応じて、性的な知識を子どもに得させるべきである」ということ。そうすることで、子どもを強すぎる抑圧から守ることができれば、健康、精神的バランス、好ましい性格発達だけでなく、知的能力の発達にも良い影響が生じる。
症例フリッツ(5歳)
精神発達は遅れていて、2歳で喋り始めたが、3歳半まで思ったことを続けて喋ることがなかった。4歳半頃に急速な精神発達があり、同時に万能感が目立ってきて、話に出てきたこと(料理をするとかフランス語を自由に操るとか)はどんなことでも自分は完全にやってのけると確信していた。4歳9ヶ月頃に質問の数が著しく増え、出産に関する「人はどのようにして生まれるの?」というような質問が繰り返された。
これらの質問にはいつも全く誠実に、また必要なときには子どもの理解力に合わせて科学的に、しかもできるだけ簡潔に答えられた。フリッツは、言い伝えや様々なおとぎ話による超自然的な説明について、他の家族や保母や家庭教師や友達の家の人にも尋ねたりしながら、結局はそういったお話が本当でないことを確かめた。
神の存在についても同様に、無神論者である母親(クライン自身)とその他の人との答えの違いを吟味していき、特に神の存在を許容する父親と否定する母親との違いに直面し、そのことが、「両親の過度の権威を引き下げ、万能感と全知の考えを弱める」ことに繋がった。
第3期はフリッツの質問は減り、「その知識をより確かなものにしようと」する方向へ向かった。「こうしたあらゆる好奇心の中には、興味を持ったものを根底まで検索し、その深さまでつき進んでゆきたいという欲求があるように」みえ、それは、「子どもの出産に際しての父親の役割についての無意識的な好奇心」からきていたと思われた。
この頃から性差についての質問が増え、性器や尿や大便に関する興味が高まった。フリッツの現実的な感覚は大きく改善され、全てのものを吟味しようという欲求が前面に出てきて、「長く馴染んでいたものや、長年知っていたもの、何度も観察したり、やってみたことがある活動になどついて、その現実性と根拠を調べよう」とし続けた。
「この方法で、彼は自分の自主的な判断に達し、そこから再び自分自身の推理を引き出すことができるようになる」。そうして「現実の(real)」、「現実でない(not real)」という言葉の使い方が洗練され、「これらの‘現実の’物によって、全ての目に見える実際のものと、願望と空想の中でのみ生じるものとを区別するための基本的な意味を理解し」、現実原則が確立した。
現実感の発達とともに万能感は衰退し始めていたが、「発達しつつある現実感」と「深く根ざした万能感」との間で葛藤しつつあり、後者は「教えてもらえばなんでもできるはず」という形で表現された。万能な父親に同一化したい気持ちと、自我を縛る力でもある両親の万能感を取り除きたいという気持ちとの間で、アンビバレントになっていた。
この現実感と万能感との間の葛藤に関して、「現実原則がこの戦いにおいて上位に立ってその個人の万能感の持つ無限性に枠をはめる必要がある時には、それに平行した両親の万能感から咎められることによる苦痛な衝動の緩和を発見しようとする欲求が生じてくる。しかしながら、もし快楽原則が優位に立てば、両親の完全さの中にそれが防衛しようとしていることの支持を求めることになる」。
「現実原則に動かされて、彼が自分の無限の万能感をしぶしぶ放棄しようとする際、これに伴って、一般の子どもによく見られるように、自分自身と両親の限界を知ろうとする欲求が生じている」。権威の没落と万能感が弱まることには相互作用がある。
フリッツは友達に邪険にされた時に、現実を否認する楽天性と、それを認めざるを得なくなった時の攻撃的傾向を揺れ動いた。攻撃的傾向は対象の死を連想させ、フリッツは死という現実に取り組み始めた。
子どもの全ての質問に誠実に答えることが生み出す自由さが、子どもの心的発達に大きく有益に影響する。思考は抑圧の傾向から保護される。すなわち、昇華を進める本能的エネルギーをひっこめてしまうことから、また、抑圧されたコンプレックスにつながる観念構成的連想を抑圧してしまうことで思考の筋道が破壊されることから、思考を保護する。
知性や現実感覚を妨げる重要な要因である、性的で原始的なものへの拒否や否認は、解離によって抑圧を機能させる。もう一つの妨げる要因は、既成の考えを押し付けられるという問題である。押し付けられれば反発を生むが、反発はまた依存していることに他ならない。知性や現実感覚は、ただそれに反対することで発達するのではない。現実的な知的独立性は、対立と服従の両極端の狭間から発達してくるものなのである。
権威に由来する理性的なものに対する依存と独立の葛藤は、子どもと両親との関係に根ざしている。大人から権威的に倫理的道徳的な観念が与えられることで、子どもの思考の自由は妨げられる。しかし、そのような観念は現実的根拠を感じさせないから、子どもはそれに疑問をぶつけるという形で攻撃し始める。それに対して、大人の側で「目に見えず万能的で全知の神の概念」が導入されると新しい危機が生まれる。
そこには2つの要素が含まれる。1つは、幼い子どもは弱さ・孤独・寂しさを体験し、神様という大きく強い権威を求めるという、「生得的な権威への欲求」の存在である。もう1つは神の概念が自分自身の万能感と結びつくという、「生得的な万能感や‘思考の万能における信仰’」の要因である。
科学的思考としての現実原則の完全な発達は、現実原則と快感原則との間で子どもが自分で行う調整と密接に関係している。これが確立すれば、現実原則が思考と確立された事実の領域を支配するように、願望や空想が万能感に属するものとしてみなされるようになる。
神の観念を教育に導入し、その取り扱いを個人の発達に任せることは、この点に関して、決して子どもに自由を与えるやり方ではない。
(2)早期の分析
大人の神経症の要因は6歳以前の体験にさかのぼることができるという精神分析の知見から導かれるのは、子どもにとってひどく有害だと考えられている要因、特に強制的な道徳的要求を少なくするような工夫をし、子どもの「無邪気さに直接的に文化的風潮を対抗させることなく、いろいろな本能衝動やそれに伴った快感を意識することができるようにさせる」ことが大事だということ。
「私たちは、本能が部分的に意識化され、それに伴って昇華が可能となるための余地を残すような、ゆっくりとした心的発達を目標にするべき」であり、目覚めつつある性的好奇心を表現するのを拒否することなく、段階を追ってそれを満たしてやることが求められる。
こうしたことがうまく行けば神経症や偏った性格の発達を完全に予防できるかというと、その効果は部分的なものに留まる。神経症の形成には素質と環境因が影響する量的な要素を伴っているから。また、子どもの側にも知ることへの抵抗が生じるものであり、子どもが意識的に尋ねることができる質問の水準に合わせて、漸進的に性的な知識を伝えていくことが大事である。
フリッツの場合も、探求衝動にもとづく質問は減り、質問は思弁的になっていったが、同時に紋切り型の質問もまた増えていった。物語を聞かされることも嫌がるようにもなった。子どもの探求への強い衝動は、同じように強い抑圧傾向と葛藤を生じるに至っていること、そして無意識に説明を拒む後者の抑圧力が支配的となっていることが、想定された。
抑圧は知性に対して、幅広さと深さの次元で悪い影響を生じる。性的好奇心の抑圧の結果として、子どもがいろいろ表層的に尋ね始める段階で固定化していたならば深さの次元で知性への害が生じる。反対に、尋ねたり、聞こうとしない段階で固定化するならば、興味の表層と幅が避けられ深さの方向だけへと導かれることになる。
フリッツは知ることへの抵抗を示しつつも、夢のような空想の話に熱中することもあった。そこにはエディパルな空想が含まれ始めていて、父親への激しい攻撃性が表現されていた。フリッツは性器や尿や大便に関心を高め、(母親の)お腹の中にも執着を示していた。子どもができるプロセスを説明されると、「彼の性理論はある程度解決したが、彼は初めて、たった今受け入れた説明の拒否された部分(父親の役割)に興味を抱いた」。
すなわち、「性理論の明確化により、現実の性的過程の知識を受け入れることの抵抗は克服され」ると、今度は「エディプス・コンプレックスが前景へ現れてきた」。フリッツはそれまでの遊びには関心を失い、クローゼットの中の出来事への空想を表現し続けた。その中での作業は生パンでいろいろなものを生み出すことであり、サディスティックな要素が含まれていた。
2ヶ月の精神分析の空白を経て、フリッツは入眠困難や夜驚を呈し、読んで一気に学ぼうという熱中をみせ、いたずらで機嫌はよいことは少なかった。フリッツは再び抵抗が強まっていて、その物語は恐怖症的なものだった。そこにはわずかに同性愛的要因が現れていた。精神分析が再開され、物語が続き抵抗が減ってくると、フリッツは性的行為そのものについて質問し、その答えを得るとさらに抵抗は弱まった。
そしてフリッツは、愛する母親を失わないために母親の面影を分割し、空想には魔女が登場した。それは同性愛へと導く、ペニスを持った女性の象徴でもあった。そして、フリッツは父親の役割を取ることに失敗すると、父親に対する自分の攻撃性を父親に投影した。その後、再度数ヶ月間の精神分析の空白があったが、精神分析の影響は持続したように感じられた。
精神分析的な形での養育は、これまでの教育原理と対立するものではなく、むしろそれを補うものである。それも、より小さい子どもの方が抵抗は少なくてすむ。「あまりに深く及ぶ影響」は怖れる必要がない。
精神分析が目指すことは、子どもをひどいショックから保護し、制止を克服することであり、それは子どもがもっている良い性質に対して悪く働くことはなく、むしろ昇華の可能性を高めるものである。無意識であるよりは意識に上りつつあるものの方が、コントロールしやすいものである。
いくつかの問題が提起されうるが、まず、子どもの周囲の考え方が精神分析的なものとは全く異なる場合でも、子どもの方がそれが通じる相手を区別する。一日中、精神分析的なやり取りを求めたり、何か別の目的で(例えば夜に起きていたいために)精神分析的なやり取りを求めたりしかねないという問題については、特定の時間を精神分析のためのものとして区別しておくことで操作可能である。
また、「すべての子どもに精神分析的養育は必要なのか?」という疑問に対しては、後に性格の歪みをもたらすような、抑圧されたコンプレックスという形の種を持ち続けなくて済むので、ある程度の予防的役割を担っているといえる。病気は素因と経験の総和であり、誰でもがそこに至り得ると考えるならば、予防の効果もまた大事なものとなる。
逆に子どもの性的好奇心を満たし、その表現を阻止することなく、子どもが本能衝動やエディプス・コンプレックスを生き抜くことができるならば、精神分析的養育の必要性は低くなる。
精神分析的原理にのっとった早期教育を実践するには、子どもに関わる大人たちが精神分析を受けることが求められるが、当面は精神分析家を中心とした幼稚園を作るという方法が実現可能かもしれない。
終わりに
このようなメラニー・クラインを代表とするような精神分析について詳しく学びたい方は以下の精神分析のページをご覧ください。
リーディング・ガイド
- 松木邦裕(著)「対象関係論を学ぶ―クライン派精神分析入門」岩崎学術出版社 1996年
- ローバート・ヒンシェルウッド(著)「クリニカル・クライン―クライン派の源泉から現代的展開まで」誠信書房 1999年
- ハンナ・スィーガル(著)「メラニー・クライン入門」岩崎学術出版社 2000年
- 松木邦裕(編集)「現代のエスプリ別冊 オールアバウト メラニー・クライン」至文堂 2004年
- ロイ・シェーファー(編集)「現代クライン派の展開」誠信書房 2004年
- カタリーナ・ブロンスタイン(著)「現代クライン派入門―基本概念の臨床的理解」岩崎学術出版社 2005年
- ザルツバーガー・ウィッテンバーグ(著)「臨床現場に生かすクライン派精神分析―精神分析における洞察と関係性」岩崎学術出版社 2007年
- ジュリア・スィーガル(著)「メラニー・クライン-その生涯と精神分析臨床」誠信書房 2007年
- ジュリア・クリステヴァ(著)「メラニー・クライン-苦痛と創造性の母親殺し-」作品社 2013年